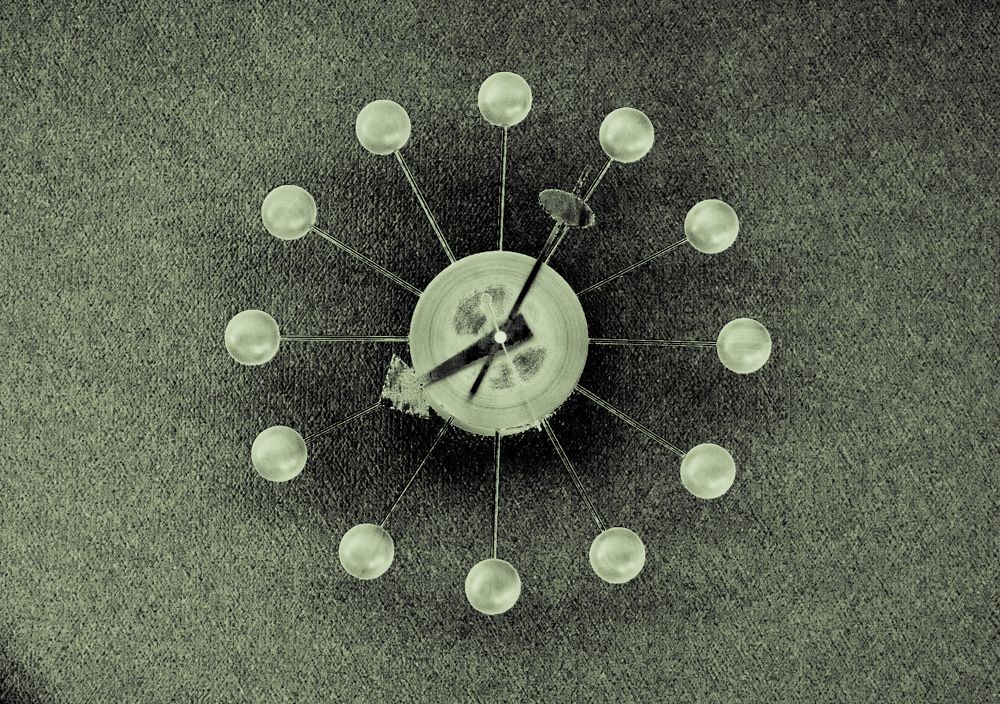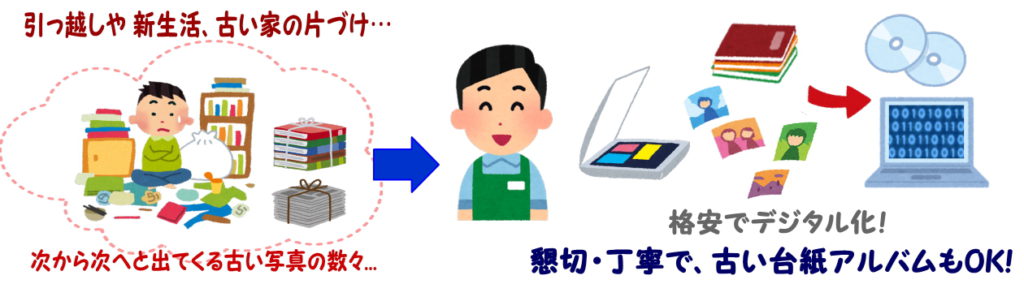ディズニー映画「アナと雪の女王」が世界的に大ヒットしていて、日本でもゴールデンウィークを終えた5月6日までで、動員1265万人、興行収入159億円を突破したそうです。
ディズニー映画「アナと雪の女王」が世界的に大ヒットしていて、日本でもゴールデンウィークを終えた5月6日までで、動員1265万人、興行収入159億円を突破したそうです。
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンの歴代の映画の興行収入においても断トツの1位となり、日本歴代の興行収入でも「アバター」の156億円を超え、8位となったとかで、日本でもっともヒットした3D映画、ということになるようです。
興行収入200億円超えも射程圏内で、過去に200億円を超えたのは、「千と千尋の神隠し」(2001年)、「タイタニック」(1998年)、「ハリー・ポッターと賢者の石』」2001年)の3作品しかないそうですが、どうやら「アナ雪」もこれに並びそうです。
実は、我々も先月の末、これを見に行きました。骨折して長いリハビリを送っていた母が退院してきていたのですが、まだまだ自由には歩けないことから、何か室内娯楽を、ということで、かねてより評判の高かったこの映画を見に行ったわけです。
私の感想としては、ストーリー的には、まぁお子ちゃま向けの内容だな、と物足りなくは思ったものの、ところどころに大人のための寓話的な内容も盛り込まれていて、見終わったあとにそうしたことがジワジワ利いてきました。ちょっと考えさせられてしまう、といった部分もあって、なかなか良かったと思います。
しかし驚くべきは、この映画のCGの素晴らしさで、その映像の美しさには本当に感動しました。主演の松たか子さんやエンディングでMay.Jさんが歌う「ありのままに」の響きもこのCGとよくマッチングしていて、この映画を見た人の多くが、「あリの~♪ ままのぉ~♫」とついつい口ずさんでしまう、というのも分かる気がします。
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオズが製作したこの映画の原案は無論、アンデルセンの童話「雪の女王」ですが、ストーリーは全く異なり、雪と氷の魔力を持つ女王エルサと、その妹の姉妹を主人公として、彼等自らが住まう王国を救うという話です。
ディズニー映画で、主人公が女性の場合、これを「ディズニープリンセス」というそうですが、過去13人のプリンセスがいる中で、今回は史上初の2人のプリンセスが登場し、このことも話題になりました。
本家英語版のほうでは、「ありのままに」の英語バージョン「Let it go」も歌ったイディナ・メンゼルが姉のエルサ役をやりました。どちらかというと舞台女優として有名な人で、映画作品ではあまりヒット作への出演がなく、2007年のディズニー映画、「魔法にかけられて」でもちょい役でしか出演していませんでした。
2003年にミュージカル「オズの魔法使い」で西の悪い魔女役をやってトニー賞のミュージカル主演女優賞を受賞しており、こうしたミュージカルのキャストレコーディングCD以外にも歌手として2枚アルバムを出しているなど、歌手としても定評のある人のようです。
日本でも、松たか子さんやMay.Jさんの日本語版のほうが有名になってしまったので、あまり流れていないかと思いきや、この英語版のほうも大人気のようで、日本以外の国でも大ヒットしており、You Tubeでの再生回数も1000万回を軽く超えているそうです。
この歌は、第86回アカデミー賞では、歌曲賞に輝いており、また、映画本編としては長編アニメ映画賞も受賞してダブル受賞を果たしました。ほかにもゴールデングローブ賞のアニメ映画賞を受賞したほか、アニメのアカデミー賞といわれるアニー賞では、作品賞、監督賞、声優賞、美術賞、そして音楽賞と、数々の賞を総なめにしました。
本作と「風立ちぬ」でアカデミー長編アニメ映画賞を争ったスタジオジブリのプロデューサー、鈴木敏夫さんも、「原作に引っ張られずに、今の時代を表している作品になっている」と高い評価をしているそうです。
アンデルセンによる原作のストーリーは、カイとゲルダという仲良しの男女の子供が主役です。ある日、悪魔の作った鏡の欠片がカイの眼と心臓に刺さり、彼の性格は一変してしまい、そこへどこからともなく雪の女王が現れて、彼を連れ去ってしまう、という話です。
春になって少女のゲルダは、カイを探しに出かけ、太陽や花、動物の声に耳を傾けながら雪の女王の行方を探しあてていきますが、途中で山賊に襲われあわや殺されようになるなど苦難に満ちた旅を続けます。しかし、逆にこの山賊の娘にも助けられ、とうとう雪の女王の宮殿にたどり着いたゲルだは、カイを見つけて涙を流して喜びます。
そしてその涙がカイの心に突き刺さった鏡の欠片を溶かし、カイは元の優しさを取り戻し、二人は手を取り合って故郷に帰る、というストーリーです。
このとき、雪の女王は何もせず、二人が帰るのを黙って許したようで、もう少し派手に暴れて話を面白くせんかーい、と私的には突っ込みたくなるエンディングなのですが、このように原作では雪の女王はむしろ脇役です。
本作では、雪の女王たるエルサと妹のアナが主役であり、アナの恋物語もまたこの話の中に盛り込まれています。ところが、エルサのほうは、数ある男性からの求婚をも拒否する、といった設定になっており、この話のエンディングにおいて扱われる「愛」もまた、男女の愛ではなく、姉妹愛になっています。
ここのところは、なんのことやら映画を見た人ではないとわかりにくいでしょうが、ここでネタバレするのもなんなのであまり触れません。が、この姉妹愛に代表されるように、愛にも色々な形があり、同性愛もそのひとつです。
このため、アメリカではこの映画の主テーマでもある、「ありのままの自分」を歌い上げる「Let it go」は、実は同性愛者たちのカミングアウトの歌ではないか、と解釈する向きもあるそうです。
このため、キリスト教関係者などの中には、この映画は子供を同性愛に導くのではと批判する向きもある一方で、逆にキリスト教的自己犠牲を尊ぶものである、といった評価もあり、あちらでもかなりのヒットをしただけに、多彩な解釈を生む問題作とみなされているようです。
もっとも日本では、こうした風潮はなく、むしろ「ありのままに」を人生の応援歌として位置づけ、これによって大いに勇気づけられるといった声も高く、一般のサラリーマンのおっさんが、ありの~ままの~姿ァ見せる・の・よ~(上司に)と口ずさみながら出勤する様子が各地で見られるようになるなど、社会現象になっているそうです。
確かに耳に心地良い歌であることは確かで、ビートルズの「let it be」にもつながるものがあるよな、と思っていたら、昨日のお昼のワイドショーでも、これに着想を得た歌ではないか、といったことを音楽関係の専門家さんがおっしゃっていました。
このLet it goとlet it beの意味はだいたい同じようなものなのですが、let it beは「現在形」とでもいうのでしょうか、今のままでいいよ、無理に変えようとしないで今のままをありのままを受け入れましょうという意味です。
一方、Let it goのほうは、こうした現状維持ではなく、goですから、ありのままの自分「it」を解き放て「let go」という意味になり、より能動的な意味があります。従って、現状のままに満足せずに頑張ろう!という意味になり、これが人生の応援歌、といわれるゆえんでしょう。
実はこの「雪の女王」というストーリーの企画はかなり昔からあったようで、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオズは長年にわたってアンデルセン童話を翻案したものを作品化しようと考えていたようです。
しかし、企画が持ち上がるたびに、廃案となり、2010年時点ではかなり具体的なプロジェクトとして形を成したものの結局は棚上げされました。その理由は、2000年以降ディズニーアニメが長きに渡って低迷していたためであり、1998年にアニー賞を受賞した「ムーラン」以降、ディズニーのアニメ映画はめだったヒット作がありませんでした。
ところが、2011年に公開された「塔の上のラプンツェル」において久々のヒットを放ち、この成功を受けてディズニーは「Frozen」と題された新作を2013年末に公開すると発表しました。
こうして2012年から本格的に制作され始めたこの映画においては、舞台となる王国のある場所のモデルとしてノルウェーが選ばれました。同国のフィヨルドの地形や建築物、とくにスターヴ教会と呼ばれる教会などは、製作者たちにインスピレーションを与え、城のデザインなどに生かされたといいます。
このスターヴ教会というのは、ウルネスの木造教会とも呼ばれ、英語表記では”Urnes stavkirke”と書かれるようです。ノルウェー東部の山岳地帯にあり、ノルウェー語でスターヴ(stav)は、「垂直に立った支柱」のこと、stavkirkeのkirkeは「キルケ」と発音し、教会のことです。
1979年に、ユネスコの世界遺産に登録されたこの教会は、ルストラフィヨルドを望むことができ、高さ120メートルの崖の上にあり、現在は、ノルウェー考古物保存教会が所有していますが、時々、ミサが催されるなど、現役の教会です。
建築されたのは、1130年前後と推測されていて、この近辺にはこれだけでなく、ほかにも教会が多いそうで、こうしたウルネスの教会建築は、キリスト教建築とヴァイキング建築が結びついた「ウルネス様式」と呼ばれ、これらはスカンディナヴィアに生息する数々の動物をモチーフにしたスタイルだそうです。
この教会の写真をネットで探してみましたが、背後にある際立ったフィヨルドとその足元に広がる深い青い海をバックに立つこの教会は本当に美しく、製作者たちのインスピレーションを掻きたてたというのもわかります。
このほか、映画のドローウィングには、ローズマリングと呼ばれるノルウェーの伝統的な花柄模様がインテリアなどさまざまな場所に利用されたそうで、キャラクターの服装としてもノルウェーの民族衣装を採用したり、ローズマリングを入れるなど、ノルウェーを意識したデザインが生かされたといいます。
ただ、エルサが「雪の女王」となってからの衣装などにあしらわれている雪の結晶などは、CGスタッフによる一からのオリジナルだそうで、氷の城もこの衣装と統一感を持たせたデザインにしたそうです。
これもまた映画を見た人ではないとわからないのですが、こうした細かい模様の描写の素晴らしさだけでなく、複雑にデザインされた雪や氷がキラキラと光りながら流れ動くアニメーションは本当に見るものを圧倒します。
これらコスチュームデザインや背景画のCGは薄い生地を何十枚も重ねるようにデザインされたそうで、膨大なレイヤーが費やされたといい、これもまた映画を見た人はお気づきでしょうが、この映画のエンディングに流れるCG関係者の数はハンパなものではありません。
私もかつてこんなに長いエンディングロールをみたのは初めてで、しかもそのほとんどすべてがCG関係者という映画はこれまでもあまりないのではないでしょうか。
こうしたコンピュータ・グラフィックスがディズニー映画で本格的に採用されたのは1982年の「TRON」からだそうで、この映画では世界で初めて全面的にコンピューターグラフィックスが導入され、話題を集めました。
当初、こうしたCGの造画には、高性能ワークステーションや専用のレンダリングサーバ、時としてスーパーコンピュータなども用いてレンダリング処理を行っており、莫大な大変コストがかかるものでした。
しかし、最近ではパソコンの高性能化に伴い、安価で高性能なパソコンを使って分散レンダリングを行う方法が主流となり、安価なパソコンをレンダリング専用にクラスター化したものを使います。
ちなみに、レンダリングとは、コンピュータプログラムを用いて画像・映像・音声などを生成することをいいます。またクラスターというのは、複数のコンピュータを結合し、クラスター、つまり「葡萄の房」のようにひとまとまりとしたシステムのことです。
こうしたクラスターを使ってレンダリングを行い、CGを作成するチームのことを「レンダーファーム」呼びますが、ディズニー映画を作るような大手プロダクションでは数百台規模のパソコンをクラスター化してレンダーファームを構成する例が多くなっているそうです。
映像のレンダリングでは、あらかじめ一枚一枚の画像を作り、それらを繋げて映像化していきますが、一枚ずつセルに絵具(アニメカラー)で彩色する工程を踏んでいた昔のアニメーションのほうが臨場感が出しやすいことから用いられることもあり、その制作にも最近はコンピュータ彩色導入することで効率化が図られているそうです。
こうしたCG映画が主流となる以前より、ウォルト・ディズニー社は創業以来、多くの傑作アニメ映画を生み出してきました。
世界初のトーキーアニメ、長編アニメ、カラーアニメなど歴史に残る業績を残してきましたが、創業者であるウォルト・ディズニーが亡くなった1966年以降低迷し、1990年代に再び黄金期を迎えました。
復活の立役者は当時映画部門の責任者だったジェフリー・カッツェンバーグという人です。彼は伝統的なディズニー・アニメを再建する一方で、CGアニメ時代の到来を受けて、CG技術の草分けともいわれる「ピクサー社」との提携を実現しました。
しかし1994年にカッツェンバーグはディズニーを辞職しドリームワークスの設立に関わることになり、ピクサーとも製作方針の食い違いなどから不仲になっていきました。
ピクサーもディズニーとは「カーズ」を最後に契約を終了する予定でしたが、2005年にピクサーと相性の悪かったディズニーのCEOが退任したことから、関係を再び修復。そして2006年、ディズニーはピクサーをM&Aにより買収し完全子会社としました。
その後、アップルコンピュータとピクサーのCEOだったスティーブ・ジョブズは、株式交換によってディズニーの筆頭株主になると共に役員に就任しました。そのジョブズも今や亡くなってしまいましたが、ウォルト・ディズニー・カンパニーの筆頭株主は、今も彼の意思を継いで設立されたスティーブン・P・ジョブズ・トラストとなっています。
現在のウォルト・ディズニー・カンパニーは、本業の映画の製作やテーマパークの経営を中心に、三大ネットワークのひとつである放送局のABCやスポーツ専門放送局ESPN、インターネット・ポータル「go.com(Walt Disney Internet Group・旧infoseek)」などを傘下に納める世界有数のメディア・エンターテインメント系総合企業体です。
無論、浦安のディズニーランドを運営する、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社もこのウォルト・ディズニー・カンパニーの日本における現地法人です。
その創業者のウォルト・ディズニーを知らない人はいないでしょうが、これはアメリカ・イリノイ州シカゴに生まれた実業家です。
もともとはアニメーターでしたが、その後プロデューサー、映画監督、脚本家、声優、など数々をこなすンターテイナーとして活躍しましたが、世界的に有名なアニメーションキャラクター「ミッキー・マウス」の生みの親であります。
兄のロイ・O・ディズニーと共同で設立したウォルト・ディズニー・カンパニーは1923年の設立であり、ハリウッドを拠点とし、当初は「ディズニー・ブラザーズ社」と言っていました。
当初は、兄のロイ・ディズニーと共にミズーリ州のカンザスシティーに住んでいた時代に一本だけ制作した「アリスの不思議の国」シリーズの続編商品を販売する会社としてのスタートでした。
このアリスは、実写作品だったようですが、会社を運営していく過程で、これをアニメとして制作する機会を得たウォルトはアニメーター仲間を集めることとし、こうして会社はアニメ製作の専門会社へと転進しました。
これが実質的な「ディズニー社」の設立であると考えられ、ロスアンジェルス市ダウンタウンの北側、シルバーレーク地区ハイペリオン通りに開設された制作スタジオは、その後ロス西北部にあるバーバンクへの1939年の移転による閉鎖までディズニーアニメを世に送り出し続けました。
やがて少女子役の実写にアニメーションを織り交ぜた「アリスコメディシリーズ」は人気を博し、ディズニー社の経営は軌道に乗っていきました。1925年には、自社キャラクターとして「しあわせウサギのオズワルド」を考案、オズワルドを主人公にしたアニメをユニバーサル社の配給で制作しました。
「オズワルドシリーズ」はスタートと同時に子供の間で大ヒットを飛ばし、一躍ディズニー社躍進のきっかけを作りました。ウォルトはカンザスフィルム時代の旧友達を次々に会社へと誘って会社を大きくし、こうしてディズニー社はアメリカでも屈指のアニメ製作会社に急成長していきました。
ところが1928年のこと、彼等の映画を配給していたユニバーサル社が法外な配給手数料を支払う様に要求し、ウォルトがこれを拒否するとユニバーサル社は露骨な社員への引き抜き工作を仕掛けてきました。
ディズニー社は、配給会社であるユニバーサル社の管理下に置かれていた事も不利に働き、こうしてディズニー社は配給元と自社キャラクター、そしてスタッフの大半を失って倒産寸前に追い込まれました。
このとき最後までウォルトに付き従ったアニメーターがおり、彼の名は、アブ・アイワークスといいました。
アイワークスはウォルトと同い年。1901年のミズーリ州カンザスシテ生まれで、ディズニー・カンパニーではアニメーター兼特殊効果技師を努めていました。のちに、ミッキーマウスの生みの親としても知られる人物であり、ウォルトは諦めず、このアイワークスとの二人三脚でディズニー再建に取り掛かる事を決めます。
再建するにあたって、オズワルドに代わる新たな自社キャラクターを必要と感じたウォルトは、それまでにもうさぎのオズワルドやアリスコメディの中でライバルとして度々登場させていた敵役のねずみを主役に抜擢し、これを映画化することにしました。
アブ・アイワークスがスケッチをしたこのねずみは、実はユニバーサルに持っていかれたキャラクター、オズワルドそっくりでした。ただ、オズワルドはウサギであっために耳が長く描かれていましたが、このキャラクターではねずみであるため、耳が丸く描かれていました。
このねずみ、すなわちミッキーマウスは、かつてウォルトがミズーリのカンザスシティでアニメーターとして働いていた当時に飼っていたマウスにヒントを得て、ウォルト自身がスケッチしたと一般には言われています。が、これは権利処理の問題をクリアするためであって、実際にはアイワークスの作品というのが定説のようです。
このころ、アメリカでは「フィリックス・ザ・キャット」というクロネコキャラクターの漫画が流行っていましたが、二人はこれに似せた「ジュリアス・ザ・キャット」というものもディズニー社の作品として登場させており、フェリックスを製作していた会社のプロデューサーからは、模倣であると、何度も警告されていました。
ウォルトはこの当時既に監督や演出に専念し始めていたため、作画監督を委ねられたアイワークスが、これらのキャラクターの作画を担当していたのでしたが、こうした批判や中傷をかわしながらデザインを修正し、世に知られる「ミッキーマウス」の完成に至るまでには、かなりの紆余曲折があったようです。
が、出来上がったものは現在に至っても大変優れたデザインであり、後にディズニー社の従業員は「ミッキーの動きはアイワークスが、魂はウォルトが生み出した」と語っています。
ミッキーマウス・シリーズの初期作品において、秀逸な動きの描写をアイワークスが書き出す一方で、ウォルトは主として演出面で高い才能を発揮していきました。
因みに当初このキャラクターは、ミッキーではなく、「モーティマー」とされる予定でした。が、ウォルトの妻のリリアン・ディズニーのアイディアで「ミッキー・マウス」と変更されました。ただ、モーティマーの名は、後の作品でミッキーのライバルキャラクターに用いられました。
ミッキーマウスシリーズの第一作「プレーン・クレイジー」はサイレント映画として作られましたが、第二作「蒸気船ウィリー」で効果音や声を吹き込んで世界初のトーキー映画の短編アニメとしての制作が行われました。
場面の転換や物語のテンポに合わせて効果的に音や音楽が盛り込まれるといった手法はこのとき確立され、ウォルト自らがミッキーマウスの声を演じていました。
こうした演出技法は、その後長らくディズニー映画の象徴とも言うべき手法となり、その優れた合成技法はディズニー時代を築き、ミッキーマウス・シリーズのヒットに貢献しました。
これとは対照的にウォルトの演出とアイワークスの作画技術を失ったユニバーサル社のキャラクター、オズワルドは次第に人気を失っていき、、1930年代には完全にミッキーに取って代わられる事になりました。
こうして、ミッキーマウスはオズワルドを凌ぐ人気キャラクターとなり、世界的な知名度を得てディズニー社はますます発展していきました。ウォルトはこうした成功によって得た資金によって、1955年にはカリフォルニア州アナハイムにて、150エーカーの土地を購入。自らの名を冠したテーマパークであるディズニーランドを開設しました。
このときディズニーが参考にしたのは、カリフォルニア州オークランドに1950年に作られた、最初の子供用遊園地「チルドレンズ・フェアリーランド」と、デンマークに1843年に作られた遊園地チボリ公園だったそうです。
1965年、ウォルトは後にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとなる土地をフロリダ州の中心に求めました。マンハッタン島の2倍程にもなる広大な土地に造成する予定のテーマパークは彼により「エプコット」と名付けられました。
が、そのウォルトも1966年12月、肺癌のためウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの完成を見ないまま死去。翌年、最後に手がけた遺作「ジャングル・ブック」が公開されました。
彼は晩年は酒に溺れ、朝食はドーナッツをスコッチ・ウィスキーに浸けて食べるのが一番のお気に入りだったといいます。その反面ウォルトはディズニーランド開設前に「いつでも掃除が行き届いていて、おいしいものが食べられる。そんな夢の世界を作りたい」と語っていたそうです。
この思想は、現在浦安や、香港やパリ近郊にも建設されているディズニーランドの土台となっている大事な思想です。
ディズニーランドは日常から切り離された架空の世界を冒険するというコンセプトにのっとり、パーク内では徹底した雰囲気作りが行われており、パークにはいわゆる「従業員」がおらず、従業員を「キャスト」来客を「ゲスト」と呼んで、キャストは全員がディズニー作品にのっとったコスチュームをまとって役を演じながら作業をしています。
パークの周囲を木枝で覆って隠し、逆に中からは周囲の住宅や電車の駅が見えないようにしたり、食料やゴミの運搬は地下の通路を通じて搬送することで、現実感をゲストに与えないようにしてあります。
これは東京ディズニーランドでも同じで、他のテーマパークでは何の変哲も無く行われている地面の掃除がまるで1つのショーであるかの如く行われているのをご存知の方も多いことでしょう。
ウォルトは生前のディズニーランドのオープン時のスピーチの中で、「私はディズニーランドが人々に幸福を与える場所、大人も子供も、共に生命の驚異や冒険を体験し、楽しい思い出を作ってもらえる様な場所であって欲しいと願っています」と語ったそうです。
その「誰もが楽しめる」というファミリーエンターテイメントの理念は、今も各ディズニーのパークで受け継がれているとともに、数多く制作されたディズニー映画の中にも生かされています。
その最新作である、アナと雪の女王は、その興行が終わらないうちから、早くもディズニー作品の中でも最高傑作との呼び声も高いようです。まだご覧になっていない方は、連休疲れの残る今週末を終えたら、「口直し」のつもりで劇場に足を運ばれてはいかがでしょうか。