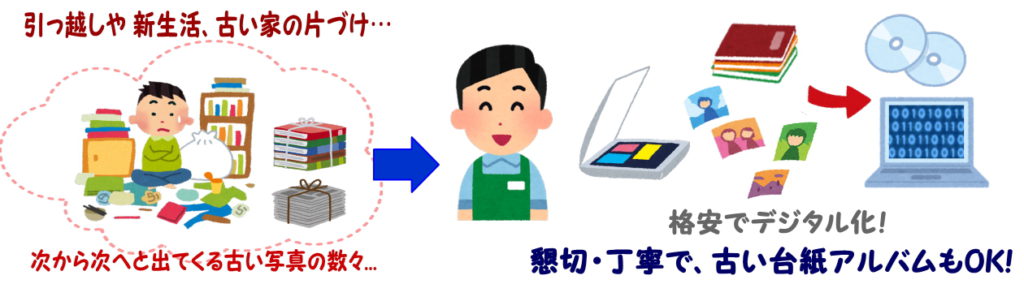クリスマスも終わりました。今年ももうあと一週間にも満たないという現実が何やら妙に不思議な気がしています。それだけ今年は良い年だった……というのではなく、前半を中心に激しい動きのあった一年だっただけに、それに対する揺り返しというか、今頃になってどっと疲れが出てきたような感があります。
昨日の修善寺は、その今年の前半を思わせるような強い風が吹いていて、まるで台風並みでした。外に干していた洗濯物数枚が吹きとばされました。我が家は山の上に位置するのでさらに風のふきっさらしは強く、家が揺れるほどでした。
気温も低く、コタツから離れられない気分でしたが、所要があって麓の大仁まで出かけるとそこはすっかりクリスマスムードでした。しかし、それにしてもみなさん寒そうです。温かいといわれる伊豆ですらこれですから、ここより北の地方のみなさんの寒さはいかほどであろうかと思います。
こうした寒い日には、温かいものを食べたあと、お風呂に入るというのが一番です。幸い温泉が出るので、こうした寒い日にはじっくり時間をかけてお湯につかれます。温泉というのは不思議なもので、出たあとの体のぬくもりが本当に長続きします。昨夜もそのおかげでそのあと入った冷たい布団も気にならず、ぐっすり眠れました。
風呂の歴史
さて、毎月26日は、ごろ合わせで「風呂の日」と決められているようで、今日がその日です。別に12月だけではないようで、毎月この日がそうなっています。おそらく銭湯がまだたくさんあったその昔のお風呂屋さんの組合か何かが、お客さんをたくさん呼び込もうとしてこういう日を設定したのでしょう。
この「風呂」という用語を調べてみたところ、もともとは人が温まるための、温浴施設だけをさすのではなく、漆器に塗った漆を乾燥させるための専用の部屋なども風呂と呼ぶようです。またサウナなどの室(むろ)を蒸気などで満たした設備も含めた総称が風呂と呼ばれるみたいです。
しかし一般的に風呂といえば、やはり温泉や水を沸かした湯を満たして浸かる入浴施設のことでしょう。ただ、大昔にはお湯につかるという風習ではなかったようで、古くは衛生上の必要性や、宗教的観念から水のある場所で行う「水浴」が普通だったようです。
ただ、日本などの火山地帯に属する国では温泉が湧き出すところも多く、こうした地域ではお湯につかるという風習も古来からあったようです。しかし、そうした場所は限られており、なんとか温泉のような温かい環境を人工的に造りだせないかということが考えられるようになりました。
温泉の効用は、単に寒体を温めるということだけではなく、新陳代謝や老廃物の除去や排出、はたまた傷や痛みにも役立ちます。そういうことが長い間に確認されるようになり、やがて人が自由に火を操れるようになってからは、水からお湯を温めてできた温水や蒸気を造りだす技術が発達し、温泉のない場所でも温浴が行われるようになりました。
「風呂」の起源として現在確認されるものは、紀元前4000年のころメソポタミアのものだそうで、これは温浴ではなく、やはり水を使った清めの沐浴だったようです。それからさらに年月を経た紀元前2000年頃になって、ようやく薪を使用した温水の浴室が神殿に作られるようになり、こうした温浴はとくにギリシア文明において発達していったようです。
ギリシア文明では、現在のオリンピック精神の元となった「健全な精神は健全な肉体に宿られかし」との考えから、スポーツ施設に付帯して沐浴のための大規模な公衆浴場としての水風呂が作られていたそうで、この発展形として紀元前四世紀ころまでには温浴の施設が完成したようです。
ただ、温水を作るための技術はまだまだ未発達であり、燃料となる木材などを大量に消費したため、こうした施設は一般には広まらず、神殿などのごく限定的な場所だけで造られていました。
中央アジアにおいても紀元前1世紀ごろには既に風呂があったようですが、これはその後の温浴施設ではなく、蒸し風呂だったようで、高温に加熱した石に水をかけることで蒸気を発生させるものでした。とくに寒い地方では冷水に入るのは酷ということで、燃料などが少なくて済み手軽に使用できるこの蒸し風呂が急速に発達したようです。
中東では、この蒸し風呂が「ハンマーム」と呼ばれる公衆浴場として広まり、この形態は北方のロシアや北欧にまで伝わり、こちらではこれが「サウナ」の原型になりました。
また、北アフリカの地中海沿岸地方やシリア地方はイスラム教徒が支配するようになり、イスラム圏となったため、ここでも広まるようになり、ハンマームは、モスク・市場と並んでイスラム都市の基本構成要素とまでいわれるようになりました。
こうしたサウナ風呂の原型は、ヨーロッパでは古代ローマ帝国に受け継がれ広まっていきました。もともと限られた人だけが使っていた温浴施設も、「造湯技術」の発達によりようやく一般に普及するようになり、紀元前100年ころには豪華な公衆浴場が登場するようになります。
湯を沸かす際の熱を利用した「ハイポコースト」という床暖房設備も発達するようになり、ローマ帝国が地中海世界にまで及ぶころには、社交場としての男女混浴の公衆浴場が楽しまれるようになりました。
しかし、その後キリスト教がヨーロッパ全土に浸透するようになると、その教義から男女が裸で同一の場所に集うことが忌避されるようになり、混浴の公衆浴場といった施設だけでなく、大勢で風呂に入るという習慣そのものがタブー視されるようになっていきました。
このため、13世紀頃まではヨーロッパの各地での入浴習慣は大きく衰退し、教会に行くための清めとして、大きめの木桶に温水を入れて身を簡単にすすぐ行水程度のようなものになりました。ただ、街中に公衆浴場が設けられるところもあり、こうした場所では週に1・2度程度、温水浴や蒸し風呂を楽しむことができました。
しかし、依然公衆浴場というと男女混浴という風習は消えておらず、このため、みだらな行為や売春が横行するようになっていくと、これにキリスト教の観念が加わり、さらに公衆浴場は廃れていきました。
14世紀にはペストが頻繁に流行するようになり、このことが拍車をかけ、公衆浴場はもちろんのこと入浴自体も「ペスト菌を積極的に体に取り込んでしまう」といった間違った解釈がなされるようになります。風呂に入るという習慣自体が人々に忌避されるようになり、地中海やヨーロッパからは急速に入浴文化が縮小していきました。
ところが、かつてのローマ帝国の東部に位置する中近東では、蒸し風呂を中心とした入浴文化があいかわらず受け継がれており、ハンマームも健在で、依然住民の重要な社交場としての役割を担っていました。
このため、風呂を沸かすための技術はこの中近東で温存され、のちにヨーロッパで入浴文化が復活するときにはこれが「逆輸入」されることになります。
やがて、18世紀になり、ヨーロッパでは医学の進歩に伴い、「入浴によって病原菌が体に取り込まれる」といった間違った解釈が科学的根拠によって否定されるようになると、入浴はむしろ健康の上で好ましいと見なされるようになっていきました。
長い間に封印されていた造湯技術も中東からの逆輸入で復活されるようになり、これに伴って、長い間行われてこなかった入浴の習慣が一般家庭でも積極的に取り入れられるようになりました。
しかし、ヨーロッパの各国は、日本のように豊富な水源をもたない国が多く、またあまりにも長い間入浴を忌避する習慣が続いてきたため、豊富にお湯を造って温水に浸かるという風呂はなかなか広まらず、できるだけ温水を節約できる「シャワー」のほうがより普及していきました。
中東やアジア諸国と違い、長い間入浴をタブー視する時代が続いたため、現在の欧米の多くの国で家庭で浴槽を造るという習慣はあまり浸透しておらず、このため浴槽のないシャワー室だけの家庭も多いといいます。
さらに、温水の風呂に浸かるのは月に1・2度程度が一般的という国もあり、365日ほぼ毎日入浴を行う我々日本人からみると、なんて不潔なんだろう、ということになってしまいます。
が、この辺は、文化の違いというか、歴史的な出来事の積み重ねの結果であり、また日本のように豊富な水量や温泉量を誇る国はヨーロッパからみればむしろ特殊な国であり、そう考えると入浴習慣の違いを一概に非難するわけにもいきません。むしろ、こうした「水」を育む豊かな自然の地に生まれた自分たちをラッキーだったと思うことにしましょう。
日本の風呂の歴史
さて、そんな日本の風呂についての歴史もみていきましょう。
日本語の「風呂」の語源は、2つあるといわれています。もともと「窟」(いわや)や「岩室」(いわむろ)の意味を持つ室(むろ)が転じたという説と、抹茶を点てる際に使う釜の「風炉」から来たという説です。
一方、英語でいう “bath” は、イギリスにある温泉場の街の名前、バース(Bath)が語源ではないかという俗説があります。温泉の発祥がギリシャともローマともいわれる中、ちょっと意外なのですが、考えてみればローマ帝国時代にはイギリスもその属国です。
紀元前55年にはローマのユリウス・カエサルがグレートブリテン島に侵入し、西暦43年ローマ皇帝クラウディウスがブリテン島の大部分を征服しており、ローマ帝国時代に「ブリタニア」と呼ばれたイギリスの大部分は、ここに住むケルト系住民の上にローマ人が支配層として君臨していました。
このため、バースの温泉街もローマ人たちによって開発されたと考えられ、これが風呂の語源になったという説もそれならばうなずけます。もともとは地名であった “Bath” はやがて温泉施設の代名詞として使われるようになり、これがローマ帝国全体に広まっていったようです。
ちなみに、英語のbathに相当する「温浴」または「温めること」を意味する名詞がゲルマン古語にもあるそうで、紀元前にこの地を席巻していたゲルマン民族がもしローマ帝国に負けていれば、このゲルマン古語が今のbathに変わる風呂の代名詞になっていたかもしれません。
さて、日本の風呂の話をするつもりが、道をはずれてしまいました。元に戻りましょう。
風呂という言葉の語源は、「窟」や「岩室」であったと書きましたが、もともと日本では神道の風習のもと、こうした場所の多い川や滝で「沐浴」の一種と思われる禊(みそぎ)を行う習慣を古くから持っていました。
このため、仏教が伝来した際にも建立された寺院には「湯堂」とか「浴堂」とよばれる沐浴のための施設が作られました。「湯」という字が既に使われていますが、無論このころの「湯堂」は水風呂です。
「湯」という言葉は、現在は温かいお湯のことを指しますが、その語源は「湧(ゆう)」ではなかったという説もあり、その後温かい湯に入ると体がリラックスできるので「ゆるむ(緩)」という字に代わり、それが現代の「湯」に変わったというのが有力な説だということです。
なので、このころの「湯堂」「浴堂も」もともとは僧尼のための水風呂で、仏教においては病を退けて福を招来するものとしてこれが奨励されました。
8世紀半ばの奈良時代に書かれた経典に「仏説温室洗浴衆僧経」と呼ばれるものがありますが、このお経ではもともとは僧侶だけが使っていた風呂を一般の人に奨励し、僧侶が一般人のために入浴を施す「施浴」を勧めており、このころから風呂の一般民衆への開放が進むようになっていったようです。
奈良の法華寺にあったといわれる「浴堂」は、光明皇后(701~760)が建設を指示したものだそうで、これは入浴治療を目的として造られたものだといわれています。この浴堂では薬草などを入れた湯を沸かし、その蒸気を堂内に取り込んだ蒸し風呂形式だったそうで、これを使って貧困層へ施し、病気を癒す「施浴」が行われました。
このころ既に温かいお湯につかる形式の風呂はあったようですが、この時代の「風呂」といえばまだこのような蒸し風呂さしており、現在の浴槽に身体を浸からせるような構造物はあるにはあったもののまだ一般化していませんでした。また「風呂」とは呼ばずに「湯屋」「湯殿」などと称して「風呂」とは区別されていたということです。
その後平安時代になると、こうした寺院にあった蒸し風呂様式の浴堂の施設は、上級の公家の屋敷内に取り込まれるようになっていきます。
「枕草子」などにも、蒸し風呂の様子が記述されているそうで、このころには次第に宗教的意味が薄れ、「衛生」のための利用が進み、またお公家さんの「遊興」のための施設としての色彩が強くなっていったと考えられています。
現在のように、浴槽にお湯を張り、そこに体を浸かるという風呂がこうした蒸し風呂を駆逐するようになったのがいつ頃なのかはよくわかっていないようです。しかし、もともと古くから桶に水を入れて体を洗う「行水」というスタイルはあり、その後蒸し風呂が発達するにつれ、蒸し風呂に入った仕上げに行水が行われるようになったと考えるのが自然でしょう。
冬場の行水は寒すぎますから、やがて行水を温めるようになり、やがて行水と蒸し風呂を別々に行うよりも、一度に入浴で済ませるほうが合理的、というふうに両者が融合していったのではないでしょうか。
このブログでも前に取り上げたように、源頼朝の子で鎌倉幕府第二代将軍の頼家は北条氏の陰謀によって修禅寺に幽閉されましたが、その最後は風呂に入っているところを北条氏の刺客によって殺害されており、この風呂は修善寺が豊富な温泉場であったこともあり、浴槽にお湯を張るタイプだったようです。
このことから、少なくとも平安時代から鎌倉時代には風呂に浸かるという風習は定着していたようで、少なくとも江戸時代には既に蒸し風呂は一般的なものではなく、入浴といえばお湯を張った桶などに浸かることを指すようになっていました。
江戸初期には「戸棚風呂」と呼ばれる下半身のみを浴槽に浸からせ、上半身だけ蒸気にあたるという「ハイブリッドタイプ」の風呂が登場しているそうで、また二代将軍の秀忠の治世の終わりごろには、「すえ風呂」と呼ばれる全身を浴槽に浸からせる風呂が登場していました。
すえ風呂の「すえ」は「水風呂」の「水」であるという説がある一方で、「据え」とも書くという説も根強く、これは桶の下部が釜になった、水から沸かす形式の風呂であったといわれています。
後年の木桶風呂の元祖ともいえるものであり、湯を別途沸かして桶に汲み入れる形式の風呂に比べれば格段に効率的な風呂であり、この風呂の普及に伴い、戸棚風呂や蒸し風呂は急速に姿を消していきました。
このすえ風呂の発展形が、木桶風呂や五右衛門風呂で、江戸時代を通してとその後の明治時代以降も使われ続けました。
五右衛門風呂は、鋳鉄製の風呂桶に直火で暖めた湯に入浴する形式です。風呂桶の底部に薪をくべる釜があり、ここで火をおこして底部を熱することで釜の中のお湯をわかします。風呂に入るときには、釜の底は高温になっており、直接触れると火傷するため、木製の底板の踏み板や下駄を湯桶に沈めて湯浴みします。
厳密には、全部鉄でできているものは「長州風呂」と呼び、五右衛門風呂はふちが木桶で底のみ鉄のものを指すそうなのですが、私が小学生のころに自宅にあったお風呂はこの原始的な「長州風呂」のほうでした。母方の実家は山口だったので「長州風呂」の発祥地である山口に近い広島でもより普及していたのかもしれません。
原始的ではあるのですが、風呂釜自体が厚い鋳鉄製のため、比較的高い保温力が期待でき、またすぐにお湯が温まるのでなかなか便利なものでした。学校から帰ってきて宿題を終えると、このお風呂にくべる薪を斧で割って小口にし、火をおこして風呂を沸かすのが私の日課でしたが、今はもうなかなかこういう光景は見ることができなくなりました。
五右衛門風呂のほうの名前の由来は、安土桃山時代の盗賊、「石川五右衛門」によることは多くの人に知られています。豊臣秀吉の配下によって捕えられ、京都の三条河原で釜茹での刑に処せられたときに使われたのと同じ形式だと言われています。従って、江戸時代に入る前からもう庶民の間では使われていたのではないかと考えられています。
一方の木桶風呂木桶風呂は、ヒノキで造った大型の小判型木桶の横に、火を焚く為鋳物製の釜が付いており、窯にはさらに煙突がとりつけられています。煙突の付いた釜の形状が鉄砲に似ている為、「鉄砲風呂」と呼ばれる事もあります。
おそらくは江戸時代の後期あたりには既にあったものと考えられますが、一般に普及したのは明治時代から大正時代にかけてと言われています。現在ではこの鋳物製の釜がガス湯沸し器に代わり、また湯船そのものも木桶ではなくホーローやFRP製が普及した為、五右衛門風呂と同様にあまり見られなくなってきています。
しかし、私が大学時代に借りていた下宿の風呂はまぎれもなくこの木桶風呂でした。もっともさすがに釜そのものはガス湯沸かし器でしたが、木桶の風呂はなかなかさめにくいため、冬などにこの風呂に熱燗を持ち込んで長風呂しながら風流を決め込んだことなどが思い出されます。
銭湯の歴史
現代でも木桶風呂や五右衛門風呂を依然使っているところは、農村部などではあるようです。木桶風呂もなかなか断熱性能が高く冷めにくいのですが、さらに薪で沸かしたお湯は冷めにくいとよく言われます。
その根拠は定かではありませんが、今も残る銭湯の中には、いまだもって薪でお湯を沸かすところがあって、こういう銭湯の常用者に聞くと、口を揃えたようにやはり薪で沸かしたお風呂は湯冷めがしにくい、とおっしゃるようです。なので何か科学的な根拠があるに違いありません。
今はもう、街中でほとんど見ることの少なくなったこの銭湯ですが、日本の法律では「公衆浴場法」に定められている「公衆浴場」のことで、その定義は「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」だそうです。
この公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は各都道府県の条例ではさらに、「普通公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類されるそうで、「普通公衆浴場」のほうが、いわゆる「銭湯」です。一方の「その他の公衆浴場」とは、自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ばれ、サウナ風呂や健康ランド、スーパー銭湯等がこれにあたります。
なぜこういう違いを設けたのかはよくわかりませんが、健康ランドやスーパー銭湯は大規模な企業が経営するなど、個人または小規模の企業が経営する銭湯とは規模が違います。大規模な施設ほどレジオネラ菌などのばい菌が万一発生したときの影響が大きいので、衛生面でのより厳しい規制が課されているのだと思われます。
江戸時代の銭湯は「風呂屋」あるいは「湯屋」と呼ばれており、銭湯が経営されるようになった初期のころは、水蒸気に満ちた部屋に入って蒸気を浴びて汗を流す、いわゆる「蒸し風呂タイプ」の入浴法で営業している業者が多くあり、これを「風呂屋」と呼んでいました。
一方、沸かした湯を浴槽に入れ湯を身体に掛けたり、浸かったりするタイプの入浴法で営業している業者もありましたが、江戸初期にはまだ少なく、このためこれは風呂屋ではなく、「湯屋」と呼んで風呂屋と区別していたようです。
しかし、江戸時代中頃にはこの区別はなくなっていき、むしろ入浴タイプのほうの風呂のほうが蒸し風呂を席巻するようになり、京都や大阪などの畿内ではこの風呂のほうを「風呂屋」と呼ぶようになりました。
一方の江戸ではこのタイプの風呂はもともと「湯屋」と言っていたため、同じものであっても関西では「風呂屋」、関東では「湯屋」が定着し、このほかの地域でも、風呂屋と呼んだり湯屋と呼んだりする地域が混在するようになりました。
お金を徴収して風呂に入らせる現在の銭湯の形式は、これに先立つ鎌倉時代には既にあったようであり、日蓮商人が書き記した「日蓮御書録(1266年(文永3年))」にも入浴料を支払う形の銭湯が存在していたことが書かれています。
このころの銭湯もまた蒸し風呂タイプの入浴法が主流であり、その後の室町時代、安土桃山、戦国時代にもこの形式の銭湯が継続されていました。
とはいえ、銭湯はまだまだ庶民のものではなく、このころの銭湯は庶民には高嶺の花でしたが、やがて時代が下って江戸時代になり、国勢が安定してくると、庶民の間で銭湯は急速に普及するようになっていきました。
その最初のものといわれるのは、1591年(天正19年)に江戸城内の銭瓶橋(現在の大手町付近に存在した橋)の近くで「伊勢与一」と呼ばれる商人が開業した蒸気浴風呂でした。
その後、江戸時代初期には銭湯でも前述の戸棚風呂が流行るようになり、これは浴室のなかに小さめの湯船があって、膝より下を湯船に浸し、上半身は蒸気を浴びるために戸で閉め切るという形式のものでした。
このころの銭湯は、小規模なものだったため、一度客が使ったお湯は捨てていましたが、その後は客が一度使った湯を、温め直して再び浴槽に入れるということも行われるようになり、薬草などを炊いて蒸気を浴びる蒸し風呂から、次第に湯に浸かる湯浴みスタイルへと本格的に変化していきました。
しかし、燃料となる木材はまだ高価であり、お湯を沸かすということ自体に莫大な金がかかる時代であったため、男女別に浴槽を設定することは経営的に困難であり、老若男女の混浴は普通でした。ただし、田舎はともかく、江戸などの都会では、公序良俗のため湯浴み着を着て入浴するという最低限のモラルはあったようです。
1791年(寛政3年)になると、天保の改革によって「男女入込禁止令」が発せられ、混浴が禁止されましたが、全国的にみればこの禁令は必ずしも守られませんでした。ただ、江戸においては隔日もしくは時間を区切って男女を分ける試みは行われたといいます。
このころになると、銭湯は「石榴口(ざくろぐち)風呂」という形式に変化し、せっかく沸かした貴重なお湯の温度を下げないための工夫として、蒸気を逃がさないようにするために柘榴口と呼ばれる狭い入り口を持つようになっていました。
このため浴槽内には湯気がもうもうと立ちこめて暗く、湯の清濁さえ分かりませんでした。窓も設けられなかったために場内は暗く、そのために盗難や風紀を乱すような状況も頻繁に発生したそうです。
とはいえ、このころは内風呂を持てるのは大身の武家屋敷に限られ、また火事の多かった江戸では防災の点から内風呂は基本的に禁止されていたため、庶民はこうした劣悪な環境の銭湯でも利用せざるを得ませんでした。
その後、明治の時代になり、1877年(明治10年)頃に東京神田区連雀町の「鶴沢紋左衛門」という人が考案した「改良風呂」と呼ばれる風呂が発明されると、これが大人気になります。この風呂は天井が高く、湯気抜きの窓を設けた、広く開放的な風呂であり、これが現代的な銭湯の元祖といわれるものです。
政府は1879年(明治12年)に石榴口風呂形式の浴場を禁止したため、こうした旧来型の銭湯は姿を消していき、また外国人への配慮もあって混浴は禁止となりました。
そして、銭湯そのものは都市化の進展や近代の衛生観念の向上とともに隆盛を極めるようになり、大正時代を経て昭和時代になると、板張りの洗い場や木造の浴槽は姿を消し、陶器のタイル敷きの浴室が好まれるようになり、さらに近代的な水道式の蛇口も取り付けられるようになっていきました。
戦後、本格的に都市人口が増大すると、至るところで銭湯が建築され、1965年(昭和40年)頃には銭湯は全国で約2万2000軒を数えるようになりました。
ところが、その後の高度成長時代の中にあって住宅事情の改善やユニットバスなどの普及により内湯を設ける家庭が急増。銭湯は徐々に姿を消していきます。1964年(昭和39年)の調査では、銭湯を利用している世帯は全世帯の39.6%でしたが、1967年(昭和42年)には30.3%にまで減少。
大阪府での統計では1969年(昭和44年)に2531軒あったものが、2008年(平成20年)3月末には半分以下の1103軒まで激減しました。
平成期に入って「スーパー銭湯」と呼ばれる前述の「その他の公衆浴場」が続々と開業するようになり、こうして正規の「普通公衆浴場」である銭湯は急速に利用客、軒数ともに減らしていきました。
2005年(平成17年)3月末日における全国浴場組合(全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会)加盟の銭湯の数は最盛期の四分の一以下の5267軒となっています。
文化財化する銭湯
銭湯と聞くと富士山の壁絵のある大浴場を思い浮かべる人も少なくないと思われますが、これは大正元年(1912年)に東京神田猿楽町にあった「キカイ湯」の主人が、画家の川越広四郎に壁画を依頼したのが始まりで、これが評判となり全国に広まったものです。
しかし、相次ぐ銭湯の閉鎖により、こうした銭湯のペンキ絵を描く職人も激減、というよりも「絶滅」状態といい、2012年10月の時点でペンキ絵の絵師は関東でわずか2名ほどといい、後継者の存続が危ぶまれています。
銭湯の建築様式もまた、その存続が危ぶまれています。特に関東では寺社建築のような外観の共同浴場が多く、これは関東大震災後に東京で流行った「宮型造り銭湯」の様式の名残です。この建築様式の名残は関東近郊に集中しており、地方の銭湯では見られずきわめて数が少ないといいます。
その発祥は東京墨田区東向島の「カブキ湯」だといわれ、建物入口に「唐破風」もしくは「破風」が正面につく建築様式が「宮型」といわれています。
当時の主な銭湯の利用客である市井の人々には「お伊勢参り」や「金毘羅山参り」、「日光東照宮参り」 など日本各地の神社仏閣への「お参り」旅行は参詣本来の目的に加えて非日常を感じることのできる娯楽でもありました。
このため、人々の平凡な日常にとって宮型造りの銭湯に足を運ぶことは、こうした「お参り」にも似た魅力的な「装置」として機能したものと思われます。
こうした宮型造りの銭湯は昭和40年代頃まで関東近郊で盛んに建てられましたが、ビルなどに改築する際に取り壊されることも多くなり、現在その数は非常に少ないといわれます。
そのうちのひとつで、大阪市生野区にある源ヶ橋温泉は外観・内装とも昭和モダニズムの面影を残す貴重な建物のため、風呂屋の建造物では数少ない国の登録有形文化財に登録されているということです。
我が家にも近い、伊豆の伊東にもこのように文化財として保存が決まった銭湯があります。
「東海館」といい、伊東市指定文化財に指定されている建物で、伊東温泉を流れる松川河畔に大正末期に建築されました。大正・昭和の情緒をいまだに残す木造三階建ての風情のある建物であり、昭和の代に三回にわたって望楼の増築などが行われましたが、ほぼ原形をとどめているといいます。
しかし、経営難から1997年(平成9年)に閉館。その後、伊東温泉情緒を残す街並みとしての保存要望もあり、所有者から建物が伊東市に寄贈されることになりました。
1999年(平成11年)には、昭和初期の旅館建築の代表的な建造物として文化財的価値をもち、戦前からの温泉情緒を残す景観として保存し、後世に残す必要があるという理由から市の文化財に指定されました。
平成11年から3年ほどかけて保存改修工事が行われ、2001年(平成13年)の7月から、伊東温泉の文化・観光施設「東海館」として一般公開されています。現在、伊東市の運営による「日帰り温泉」として運営されているほか(入湯料500円)、入館料200円を払えば艦内を自由に見学できます。
我々もその前まで行ったことがあるのですが、このときは時間に余裕がなく、館内見学までできませんでした。古きよき銭湯が味わえるということで、もし伊東に行く機会のある方は立ち寄ってみてください。
さて、今日も長くなりました。明日からはそろそろ大掃除を始めようかと思います。みなさんのお宅はもう大掃除を終えましたか?