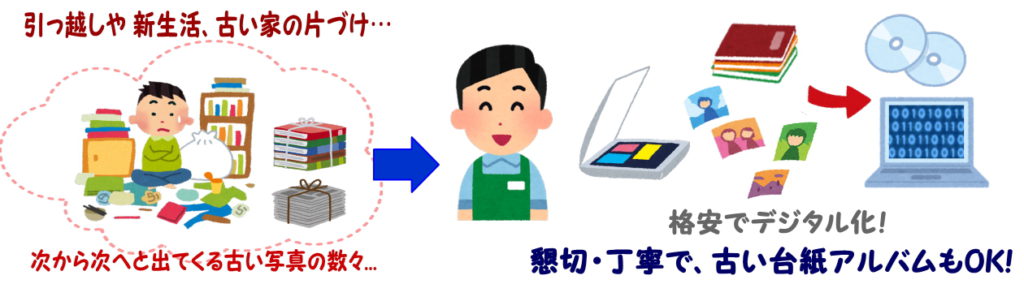先週末、富岡製糸場がユネスコの境遺産に登録される見通しである、との報道がなされ、関係者の間では喜びの声があがっているようです。
ご存知の方も多いと思いますが、群馬県富岡に設立された日本初の本格的な器械製糸の工場で、1872年(明治5年)に開業しました。
現在も当時の繰糸所、繭倉庫などがきれいなまま現存しているとのことで、これは、最後にこれを所有していた片倉工業という会社が、この施設を売らず、貸さず、壊さないをモットーに大事に保全してきたためだからそうで、その維持費だけでも年間1億円かかっていた、といいますから、その功績は大いに称えられるべきものでしょう。
この工場は、日本の近代化だけでなく、絹産業の技術革新・交流などにも大きく貢献した工場であり、ユネスコ登録の前からもうすでに敷地全体が国指定の史跡や重要文化財に指定されており、製糸工場本体だけでなく、これに関連する「絹産業遺産群」も合わせて今年ドーハで行われる世界遺産委員会で正式登録される見通しということです。
この富岡製糸場がある群馬県一帯は古くから養蚕業がさかんであり、この界隈にはほかにも養蚕に関連した文化遺産も多く、県北の沼田市には樹齢1500年ともいわれる「薄根の大クワ」が残っており、これは天然記念物に指定されているヤマグワの木としては、日本最大で、地元の人々からは神木として崇められているそうです。
ほかにも、1792年ごろに建てられた冨沢家住宅という重要文化財に指定されている養蚕農家があり、この冨沢家がある中之条町にはほかにも同様の古い養蚕農家があって、これらは「赤岩地区養蚕農家群」として、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
この養蚕の技術は、日本には紀元前200年くらいに、稲作と同時期にもたらされたと考えられています。文書に残っている記録としては、195年に百済から蚕種技術が伝えられたという記録があるほか、283年にも絹織物の技術が伝えられたとする記録があり、養蚕技術の発展とともに日本の歴史は作られてきました。
この養蚕に使われるカイコですが、チョウ目・カイコガ科に属する昆虫の一種で、正式和名は「カイコガ」という蛾です。「カイコ」という名称は本来この幼虫の名称ですが、一般的にはこの種全般をも指します。
ご存知のとおり、クワ(桑)の木の葉っぱを食べ、絹を産生して蛹(さなぎ)の繭(まゆ)を作ります。この繭をたくさん集めて紡いだものがすなわち絹糸になるわけですが、この養蚕業は日本という国の農業の進展に大きく寄与し、日本人は有史以来カイコとともに生きてきたといっても過言ではないでしょう。
しかし、最近はレーヨンのような安価な人絹に押されてカイコはほとんど日本では作られなくなり、自前でカイコを飼って絹を産出している会社はもう2~3社しか残っていないようです。
当然、カイコそのものを見たことのある人もほとんどいないのではないかと思われますが、
実は私はみたことがあります。
息子が通っていた東京多摩地区の小学校の周辺にはその昔たくさんの養蚕農家があったそうで、その関係からこの小学校では児童たちにカイコの幼虫を持ち帰らせ、クワの葉っぱを与えて繭になるまで大きくなる様子を観察させる、という情操教育を行っています。
我々が住んでいた家のすぐ前にも大きな桑の木があったため、彼は学校から帰ってくるたびにこの桑の木の緑を取ってきてはカイコに与えていましたが、わずか一週間ほどの間に丸々と太って大きくなり、やがて10日目ごろから口から糸を吐いて、繭を作り始めました。
次第に丸い繭になっていく様子は実に幻想的で、息子とともにその様子を食い入るように見ていたことを思い出します。
このカイコですが、家蚕(かさん)とも呼ばれ、実は家畜化された昆虫で、野生には生息しません。またカイコは、野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物として知られ、餌がなくなっても逃げ出さないなど、人間による管理なしでは生育することができません。
カイコを野外の桑にとまらせて自然に返そうとしても、ほぼ一昼夜のうちに鳥や他の昆虫などに捕食されてしまうそうです。また、カイコの幼虫はお腹についている脚でモノを掴む力が非常に弱いので、自力で木の幹などに付着し続けることができず、風が吹いたりするとすぐに落下して死んでしまうそうです。
成虫になると一応、羽も生えてくるのですが、体が大きいことや飛翔に必要な筋肉が退化していることなどにより、飛ぶことはできません。
養蚕は少なくとも5000年の歴史を持つといわれ、こうしたカイコの家畜化は長い間に人間によってなされたものです。伝説によれば中国の黄帝の后・西陵氏が、庭で繭を作る昆虫を見つけ、黄帝にねだって飼い始めたと言われており、絹(silk)の語源は、西陵氏の中国読みを、英語に直したもの“Si Ling-chu”からきているそうです。
カイコの祖先は東アジアに現在も生息するクワコという種だそうですが、これを飼育して絹糸を取る事は、現代の技術であっても不可能に近く、5000年以上前の人間が、どのようにしてクワコを飼いならして、現在のようにカイコを家畜にしたのかは、まったくもって不明だということです。
このため、カイコの祖先は、クワコとは近縁ではあるものの別種の、現代人にとっては未知の昆虫ではないかという説もあるようで、もしかしたら、太古に宇宙人がどこかの星からもたらしたものなのかもしれません]。
カイコは、ミツバチなどと並び、愛玩用以外の目的で飼育される世界的にも重要な昆虫です。これを飼うのは無論、天然繊維の絹の採取にありますが、とくに日本では戦前には絹は主要な輸出品であり、合成繊維が開発されるまで日本の近代化を支えました。
農家にとって貴重な現金収入源であり、地方によっては「おカイコ様」といった半ば神聖視した呼び方で呼ばれていました。山口のウチの実家でもその昔カイコを飼っていて、母もまた、「お蚕様」と呼んでいた、と述懐していました。
このためか、その昔は他の昆虫のように数を数えるのにも「一匹、二匹」ではなく「一頭、二頭」と数えていたそうです。
このカイコが吐き出す繭ですが、驚くなかれ、すべて一本の糸からできており、切れ切れではないということです。絹を取るには、繭を丸ごと茹で、ほぐれてきた糸をより合わせて紡いでいきます。
繊維用以外では、繭に着色などを施して工芸品にしたものを「繭玉」と呼んだりしますが、このほか絹の成分を化粧品に加えることもあり、繭の利用は多彩です。
ただ、茹でて絹を取った後のカイコの蛹はかわいそうに熱で死んでしまいます。しかし、日本の養蚕農家の多くは、このカイコの死骸もまた有効利用し、鯉、鶏、豚などの飼料として使ったほか、さなぎ粉と呼ばれる粉末にして、魚の餌や釣り餌にすることもありました。
また、貴重なタンパク源としてこれを食するという風習があり、長野県や群馬県の一部では佃煮にしたものを「どきょ」などと呼んで保存食にしていました。このどきょは、現在でも長野県などではスーパー等で売られおり、伊那地方では産卵後のメス成虫を「まゆこ」と呼んで、これも佃煮にして食べるそうです。
このように、その昔は日本人の生活に密着していた昆虫であるだけに、日本の各地にカイコにまつわる民話や神話が残っています。
古くは「古事記」にも登場し、高天原を追放されたスサノオノミコト(須佐之男命)が、食物神であるオオゲツヒメ(大気都比売神)に食物を求めたところ、オオゲツヒメは、鼻や口、尻から様々な食材を取り出して調理して差し出した、という話があります。
しかし、スサノオはたまたまその様子を覗き見してしまい、穢れた食物を差し出したな、と怒って、オオゲツヒメを殺してしまいました。すると、オオゲツヒメの屍体から様々な食物の種などが生じたといい、目に稲、耳に粟、鼻に小豆、陰部からは麦、尻には大豆が生まれ、そしてカイコは頭から生まれたといいます。
養蚕自体は、奈良時代にはもうすでに全国的に行われるようになり、絹は租庸調の税制における税として集められました。しかし、この当時の日本の技術は劣っており、国内生産で全ての需要を満たすには至らず、また品質的にも劣っていたため、中国からの輸入が広く行われていました。
この輸入は江戸時代に至るまで続き、その代金としての金銀銅の流出を懸念した江戸幕府は国内の養蚕農家の奮起を促し、このため諸藩もが殖産事業としての養蚕技術の発展に努めました。
その結果、幕末期までには技術改良がかなり進み、画期的な技術も発明され、中国からの輸入品に劣らぬ、良質な生糸が生産されるようになりました。これはちょうど日本が鎖国から開国に転じようとしていた時期でもあり、このため生糸は重要な輸出品となっていきました。
明治時代には欧米の優れた技術も輸入されるようになったころから、養蚕は隆盛期を迎え、良質の生糸を生み出す養蚕業は重要な「外貨獲得産業」とみなされました。
我が国の富国強兵の礎を築いたといっても過言ではなく、日露戦争における軍艦をはじめとする近代兵器は絹糸の輸出による外貨によって購入されたものです。
ただ、日本の絹がもてはやされたもうひとつの背景としては、同時期においてヨーロッパでカイコの伝染病の流行により、養蚕業が壊滅したという事情もあったようで、アジアではライバルは中国しかおらず、その中国にも1900年頃には抜き勝ち、日本は世界一の生糸の輸出国になりました。
しかし、1929年の世界大恐慌、1939年にはヨーロッパで第二次世界大戦がはじまり、これに続いて日本もアメリカを相手に太平洋戦争を始めたため、生糸の輸出は途絶しました。ほぼ同時期に絹の代替品としてナイロンが発明されたこともあり、日本の養蚕業は、ほぼ壊滅状況に至ります。
敗戦後の復興を経て、ようやく養蚕業も復活し、1970年代ころまでには再び生産量も増えていきましたが、それでもかつて1935年ころのピーク時の半分以下の生産量しかありませんでした。その後も、農業人口の減少や化学繊維の普及で衰退が進み、2014年現在での日本産生糸の生産量は、最盛期の1%ほどにすぎない、といわれています。
こうしてかつての日本の栄光を支えた絹産業は、現在ではさびしいものになってしまいましたが、往時には世界最先端といわれたその技術の証しとしては、各地にその名残がとどめられており、富岡製糸場はそれらの中でも最大級のものです。
群馬県にこの器械製糸の官営模範工場を建てることが決まったのは1870年のことでした。富岡の地が選ばれたのは、周辺での養蚕業がさかんで原料の繭の調達がしやすいことなどが理由であり、建設に当たっては、元和年間に富岡を拓いた中野七蔵という代官の屋敷が工場用地の一部として活用されました。
明治政府は、フランス人のポール・ブリューナという人物を呼んでその指導を仰ぐこととし、彼の指導のもとにフランスの製糸器械が導入された富岡製糸場は1872年におおよそが完成し、その年の内には部分操業が始まりました。
この製糸場は一般向けにも公開されており、これは見物人たちに近代工業とはどのようなものかを具体的に知らしめることが目的でした。また、ここに全国から集められた工女たちは、一連の技術を習得した後、出身地に戻って、さらに後輩の指導に当たり、そのために建設された日本各地の器械製糸場からさらにその技術が地域に伝えられました。
富岡製糸場自体も最初は公営の施設としてスタートしましたが、その後は民間への払い下げを経て、利潤追求のために労働が強化されていくとともに、さらなる技術開発を行っていくように変化していきました。
ここ伊豆でも、西伊豆の松崎は古くから早場繭の産地として知られており、大正3年発行の「南豆風土誌」によると、この地方における養蚕の起源は、少なくとも200余年も前から行なわれていた、と記録されています。
特に幕末から明治のはじめにかけては、横浜の生糸商人が大量買いつけに訪れ、その初繭取り引きで決められる「伊豆松崎相場」は欧米にまで知られるほどだったといい、ここに富岡製糸場の新技術を取り入れたのは、松崎・大沢村の名主、依田佐二平という人物でした。
このことについては、以前にも以下のブログで書いていますので、ご興味のある方はのぞいてみてください。
依田佐二平は、明治5年、わが国初の官営製糸工場として開設された富岡製糸場へ、自分の一族から若い女性6名を派遣、製糸技術を進んで習わせました。
実は、富岡製糸場は、まったく当初女工のなり手がなく、初代所長である尾高淳忠は非常に困っていました。工場の建設を進めることと並行し、明治5年2月には、政府から工女]募集の布達が出されたのでしが、「工女になると西洋人に生き血を飲まれる」などの根拠のない噂話が広まっていたこともあり、思うように女工が集まらなかったのです。
政府は生き血を取られるという話を打ち消すとともに、富岡製糸場の意義やそこで技術を習得した工女の重要性などを説く布告をたびたび出し、尾高は、噂を払拭する狙いで娘の勇を最初の工女として入場させました。
また、とくに全国各地の士族の娘を優先して募集しており、これは女工が卑しい職業ではないことを示す目的でした。こうした風潮の中、伊豆の依田佐二平が自分の村の娘たちを派遣したというのは、かなり思い切った行為だったと思われ、このことからも、また時代の先見性に富んだ人物であったことがうかがわれます。
明治8年、技術を習得した女工たちが帰郷すると、佐二平は、当時はまだ松崎村と呼ばれていたこの地の清水という場所に水車を動力とする25人繰り富岡式木製製糸機械を設置、し生糸の試作を開始しました。
さらにその翌年、この工場を大沢村の自邸内に移転し、松崎製糸場の名で40人繰り、のちに60人繰りに拡張して、本格的製糸業を始めています。これは静岡県下の民営製糸工場としては第1号であり、これを契機に明治後半までには、松崎周辺と県内各地に続々と製糸場が設立されるようになりました。
明治44年当時の賀茂郡では、この依田の松崎製糸場をはじめとして、隣接する岩科村の岩科、三浜村の勝田、南中村の山本、稲生沢村の河内、稲梓村の鈴木、下河津村の正木、河津の全部で8つの製糸場が操業していました。
このほか生成した糸を巻くだけの「座繰り」と呼ばれる工場5ヵ所を合わせ、西伊豆から南伊豆にかけての総釜数は433個にもおよび、女工総数は442人、絹糸の総生産量は4,787貫、総生産額はおよそ20万円に達しました(現在の価値では8億円ほど)
養蚕を通じて農家の経済を豊かにし、地域の産業振興をと目指した佐二平は、優良桑苗を無償で配ったり、良質の繭生産者を表彰したり、繭と生糸の品質向上のために全力を注ぎ、明治40年のアメリカ・セントルイス博覧会では銀牌を、アラスカユーコン太平洋万国博覧会では金牌、イタリア博覧会の際には名誉賞状を受けるなど、数々の栄誉に輝きました。
ただ、戦前の大恐慌に端を発した不況時代を反映して伊豆の製糸産業も次第に衰退の道を辿り始め、大正8年に佐二平が病に倒れたあげく、同じ年に発生した関東大震災によって、横浜港の倉庫に保管中の生糸が被災するにおよんで、依田の松崎製糸場はついに倒産のやむなきに至りました。
西伊豆や南伊豆のほかの製糸工場もまた次々と閉鎖されていきましたが、これは伊豆だけのこどではなく、全国的な衰退でした。
この依田邸にあった松崎製糸場は、当初は富岡の官営工場と並び称せられほど規模が大きかったといいますが、現在この依田邸だけは残っており、その大部分は「大沢温泉ホテル」というホテルに改築され、その土蔵脇に、今もわずかながら製糸場の跡が残っています。
このように、富岡製糸場の役割は単に技術面の貢献にとどまらず、近代的な工場制度を日本各地にもたらしました。
ところが、この当時の富岡の工女たちの待遇は、「あゝ野麦峠」という映画がヒットしたことや、労働問題などに鋭く切り込んだ細井和喜蔵著のルポルタージュ。「女工哀史」などが出版されたことから、その労働環境はひどいものであった、といわれています。
しかし、富岡製糸場が開城した当初はそれほど過酷なものではなく、特に当初はおおむね勤務時間も休日も整っていたといいます。ただ、その後富岡製糸場もまた民間に払い下げられ、企業としての厳しい生き残り競争の中で、労働の監視や管理が強化されていったようです、
それらについては、今日ここで書くとまた長くなりそうなので、やめておくとして、この富岡製糸場の今回の世界遺産登録が、なぜ単体ではなく、「絹産業遺産群」なのかについて最後に触れておきましょう。
明治以降、製糸業の発展に伴い、繭の増産も求められるようになったわけですが、考えてみればカイコのような昆虫というものは、夏や秋夏などの暖かい時期には活発ですが、冬になると活動力が低下し、このため繭を作ってくれません。
この繭を増産し、年間を通じて安定した繭玉の供給を行うためには、蚕種が孵る時期を遅らせ、夏や秋に養蚕する数を増やす必要が出てきます。
そこで、活用されたのが「風穴」と呼ばれる洞窟でした。夏でも冷暗な風穴の存在は、気温の上昇が孵化の目安となる蚕を蚕種のまま留めおくのに適しており、こうした蚕種保存への風穴はとくに長野県に多く、幕末の1865年(慶応元年)ころにこれを利用した繭玉の冷暗が始まりました。
長野ではその後、蚕種貯蔵風穴の数を増やし、明治30年代にはその数30以上にもなって他県を凌駕していましたが、富岡製糸場のある群馬ではごく例外的な単発の利用を除けば、あまり本格的な風穴の利用はありませんでした。
その群馬での風穴利用の初期に作られ、日本最大級の蚕種貯蔵風穴に成長したのが「荒船風穴」でした。荒船風穴では1905年から1913年までに3つの風穴が繭の冷暗用として整備されており、これを作り上げたのが庭屋千壽(にわやせんじゅ)とその父の静太郎という人物でした。
千壽は高山社蚕業学校の卒業生であり、在学中に長野の風穴などについての知見を得ていたことがここでの風穴の整備に役立ちましたが、この関連で群馬ではこのほか県内第2位の規模だったとも言われる栃窪風穴も作られ、これらが遺産群の候補となりました。
また、生産した絹を外国に輸出するためには、交通が必要です。群馬には海はなく、このため東京や横浜まで生糸を運ぶためには鉄道が必要でした。このため、荒船風穴の近くに作られたのが上野鉄道(こうづけてつどう)であり、これは現存する「上信電鉄」です。
1897年に県北の高崎から県南西部の下仁田を結んで開通したこの鉄道は、生糸、繭、蚕種の運搬などを目的に開かれた鉄道で、筆頭株主は三井銀行でした。富岡製糸場はこの鉄道が開通した当時、三井家に属しており、その、株主の半分以上が養蚕農家でした。
ただ、この鉄道だけでは、群馬やさらに内陸の長野の生糸を運搬することができず、これより更に西へ鉄道を結ぶ必要があり、こうして開通したのが、長野と群馬を結ぶ「碓氷線(1893年開通)でした。
この碓氷線には、「碓氷峠」という勾配の急な難所があり、ここの鉄道施設のひとつ、碓氷第三橋梁(めがね橋)は、明治中期の面影を残したレトロな有様で、現在も鉄道ファンならず、一般にも人気の観光スポットです。
碓氷越えを果たした碓氷線は絹産業との関わりだけでなく、日本の鉄道史にとっても重要なものであり、近代化遺産の中で最初の重要文化財に指定される、これもまた世界遺産登録がなされる施設のひとつとなりました。
このほか申請がなされるのは、伊勢崎市に残る養蚕業を行っていた古民家である田島弥平旧宅(や、高山社跡と呼ばれる施設などです。高山社は高山長五郎という人によって高山村(現藤岡市高山)に設立されたもので、外気の条件に合わせて、風通しと暖気を使い分けてカイコを育成する「清温育」という技術が導入された施設です。
最終的な推薦物件は、「富岡製糸場」(富岡市)のほか、この「高山社跡」(藤岡市)、「田島弥平旧宅」(伊勢崎市)、「荒船風穴」(下仁田町)の4件で、これらの選定にあたり、当初は日本の近代化に対する貢献に力点が置かれていました。
が、むしろ国際的な絹産業史の中での意義を強調する方向のほうがアピールするという意見が出て、この方向で推薦されることになったといいます。
日本国内では、2012年8月に世界遺産センターに正式推薦されることが決定し、翌年2013年1月に正式な推薦書が世界遺産センターに受理されました。
その後、同年9月に世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議 (ICOMOS) から調査委員が派遣されてきて現地調査を行い、この現地調査を踏まえて、ICOMOSは先n4月26日に正式に「登録」を勧告しました。
この勧告に基づいて、二か月後の6月にも正式に登録が発表される見通しで、登録されれば、日本の世界遺産の中で産業遺産としては石見銀山遺跡とその文化的景観(2007年登録)に次いで2例目であり、いわゆる近代化遺産としては初めてのことになります。
無論メインは富岡製糸場ですが、この施設を現在に至るまで保存し続けてきた片倉製糸紡績株式会社(現片倉工業)がその操業を終えたのは1987年のことでした。
それまでの間、新たな機械が導入されることもあったといいますが、もともと工場自体が巨大に作られていたためは、改築などを必要とせずにそうした機械を受け入れることができたことが、オリジナル性を保ってきた理由だといいます。
私としても前々から登録されてもされていなくても、ぜひ見に行きたいと考えていただけに、ぜひ訪れてみたいと考えています。みなさんもいかがでしょうか。