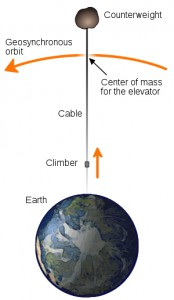先日より、かつての名女優、岡田嘉子さんのことを書いていたら、奇しくも昨夜、森光子さんの訃報が入ってきました。岡田さんともども昭和を代表する名女優であり、哀悼の意を表したいと思います。
逮捕
1938年(昭和13年)1月3日、樺太から国境を越え、ソビエトに不法入国した嘉子と杉本の二人でしたが、歓待されると思いきや、予想外にソ連側の対応は厳しいものでした。
入国後わずか3日目で嘉子は杉本と離されGPU(ゲーペーウー:内務人民委員部附属国家政治局、ソ連の秘密警察で、のちのKGB)から厳しい取り調べを受けたあと、別々の独房に入れられました。二人はこののち、二度と会うことはありませんでした。
ソ連に亡命するにあたり、実は杉本にはある目算がありました。その当時ソ連在住だった同じ演劇仲間の「佐野碩(さのせき)」や「土方与志(ひじかたよし)」を頼るつもりだったのです。
佐野は第二次日本共産党の指導者になった佐野学の甥で、母方の祖父は後藤新平。1929年(昭和4年)に結成された日本プロレタリア劇場同盟の中心的存在であり、筋金入りの共産党員でした。
演出家の土方与志夫妻ともに1933年(昭和8年)に入国し、ソ連では世界的演出家のメイエルホリドが主催する国立劇場の演出研究員となり、メイエルホリドの指導を受けました。
土方の祖父は土佐藩出身で、維新後は宮内大臣などを務めて伯爵を授けられたため、祖父没後に襲爵。新築地劇団を結成し、「プロレタリア・リアリズム」に基づく演劇を志向し、プロレタリア文学の代表作である小林多喜二の「蟹工船」を「北緯五十度以北」という題ではじめて帝国劇場で上演したことで知られています。
彼もまた筋金入りの共産党員であったため、官憲の弾圧を受け、1932年に土方は検挙を受けています。その翌年の1933年(昭和8年)に、小林多喜二は治安維持法違反容疑で逮捕、特別高等警察による拷問で死亡。
その数か月後に吉井は、佐野碩や妻の梅子とともにソ連を訪問。日本プロレタリア演劇同盟の代表として、「ソヴィエト作家同盟」で日本代表として小林多喜二虐殺や日本の革命運動について報告を行っています。この内容はまもなく日本に伝わったため、1934年に爵位を剥奪されたため、土方は帰国せず、そのままソ連に亡命。
嘉子と杉本がソ連に亡命したとき、この佐野と土方がソ連入りした時から5年が経っていましたが、日本国内で二人はソ連にそのまま居残り、亡命していたと考えられていました。
しかし、実際には、佐野と土方の二人はその前年の1937年の8月に大粛清に巻き込まれて国外追放処分になっていおり、嘉子と杉本はそれを知りませんでした。
この点について、土方与志らとともに新築地劇場の創立に参加し、小林多喜二とも親交の深かった、演出家の千田是也は「自分たちの新築地劇団のグループは前年9月にその事実を知っていたが、当時新築地劇団と演劇理論などで対立していた新協劇団の杉本はこの事実を知らなかった」と後に述懐しています。
嘉子と杉本はそうした事実を知らず、佐野と土方を頼ってソ連に亡命したわけですが、このときソ連国内はまさに大粛清の只中であり、杉本と嘉子もスパイ容疑をかけられて逮捕されてしまいます。
大粛清
大粛清とは、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンが1930年代に国内でおこなった大規模な政治弾圧のことで、この弾圧では、党指導者を目指してスターリンに対抗していた者の多くが見せしめ裁判(モスクワ裁判)にかけられ、死刑の宣告を下されました。
死刑宣告を受けたのは、5人の元帥の内の3人、国防担当の人民委員代理11人全員、最高軍事会議のメンバー80人の内75人、軍管区司令官全員、陸軍司令官15人の内13人、軍団司令官85人の内57人、師団司令官195人の内110人でした。
准将クラスの将校の半数、全将校の四分の一ないし二分の一が「粛清」され、大佐クラス以上の将校に対する「粛清」は十中八、九が銃殺というすさまじいものでした。
ソビエト国内にいた外国人の共産党員も被害者となり、600人のドイツ共産党員がゲシュタポに引き渡されたほか、ハンガリー革命主導者達12人も捕され処刑。このほか、イタリア人共産党員200人、ユーゴスラヴィア人100人あまり、ポーランド共産党の指導者全員、そしてソビエトに逃亡していた5万人ほどのポーランド人の内わずかな例外を除く全員が銃殺されました。
このほかにもイギリス、フランス、アメリカからの共産党員が殺害され、日本人もスパイもしくは反政府主義者、あるいは破壊活動家という理由で、さらし者にされた上で多数が殺害されました。
この当時にソ連に渡っていた日本人がどの程度いたのかについては正確な数字はわかっていないようですが、一説によると80人を超える日本人がおり、このほとんどが粛清の対象になったのではないかともいわれています。
処刑そして幽閉
1月3日にソ連入国後、杉本と引き離された嘉子は、その後厳しい取り調べの中拷問と脅迫を受けその一週間後の10日には、スパイ目的で越境したと自白してしまいました。このため、杉本への尋問も拷問を伴った過酷な取り調べとなり、杉本自身や佐野碩、土方与志、メイエルホリドをスパイであると認めるように強要されます。
そしてついにそれに抗しきれず「自分はメイエルホリドに会いに来たスパイで、メイエルホリドの助手の佐野もスパイであった」という虚偽の供述をしてしまいます。
その後開かれたソ連軍事法廷で杉本は、この供述は虚偽であると証言を翻し「そのような嘘をついたことを恥ずかしく思う」と述べたといいますが、時は既に遅すぎました。
1939年(昭和14年)9月27日、嘉子と杉本の二人に対する裁判がモスクワで行われ、嘉子は起訴事実を全面的に認め、自由剥奪10年の刑が言い渡されました。杉本は容疑を全面的に否認、無罪を主張しましたが、銃殺刑の判決が下され、10月20日、杉本は処刑されました。
杉本がスパイである自分の仲間だったと虚偽の証言をしたメイエルホリドも、この年の第一回全ソ演出家会議で、ソ連当局の圧力によって自己批判を余儀なくされたうえに投獄されました。
その後いったん釈放されますが、その後再度逮捕・投獄され、残忍な拷問を受けた末にフランス、日本とイギリスの諜報部に協力したと無理やり供述させられました。そして、1940年2月に死刑判決を受け、翌日に銃殺刑に処せられています。
その後、ソ連は崩壊してロシア連邦になりますが、ソ連崩壊後に明らかにされたこの当時のメイエルホリドの供述調書の中には、佐野の名前は頻繁に出てきますが、杉本(本名である吉田)の名前はほとんど出てこないといい、起訴状でもスパイ容疑を裏付ける「供述者4人の1人」になっていただけだそうです。
日本のメイエルホリド研究者のひとりは、「杉本の強制自白がメイエルホリド粛清の口実になった」のではなく、メイエルホリドが粛清の対象であることは何年も前からスターリンの方針であり、たまたま日ソ関係が最悪の時期に密入国してきた杉本がメイエルホリドや佐野の名前を口にしたため、その「最後の仕上げ」に利用されたのであろうと語っています。
スターリンの没後、こうした事実が明らかになってきたことから、杉本は冤罪であったことが確認され、1959年になってソ連内でその名誉は回復されます。しかしこうした名誉回復の事実や銃殺されて死亡していたことなどは、その後も長い間日本には伝えられず、病死したとされてきました。
しかし、1980年代になり、ゴルバチョフが登場すると彼のグラスノスチ政策の進行の結果、彼の冤罪死の事実などがようやく日本にも知られるようになりました。
モスクワで行われた裁判で起訴事実を全面的に認め、自由剥奪10年の刑が言い渡された嘉子でしたが、1939年(昭和14年)の12月、モスクワ北東800キロのキーロフ州カイスク地区にある秘密警察NKVD(エヌカーヴェーデー、GPUの改組組織)のビャトカ第一収容所に送られます。
嘉子はこの収容所でようやく自己を取り戻し、虚偽の証言をして自分や杉本を窮地に陥れたことを後悔したようですが、時既におそしでした。ソ連当局に再審を要求する嘆願書を何度も書き続けたといいますが、ソ連当局からはことごとく無視されたといいます。
このビャトカ第一収容所に約3年間収容された後、1943年(昭和17年)1月からは、モスクワにあるNKVDの内務監獄に収容され、約5年後の1947(昭和年12月になり、嘉子はようやく釈放されます。嘉子42才。杉本とソ連に亡命してから5年の年月が経っていました。
ソ連当局は釈放前にこの5年間の嘉子の幽閉の間の虚構の経歴を作り上げ、外でこれまでの経歴を聞かれたときにこれが事実である話すように嘉子に強要し、これを釈放の条件としたといいます。
ビャトカとモスクワにおけるNKVD監獄での彼女の実際の活動や任務は、その後本人も明らかにしていませんが、何等かの極秘の任務に属したとみられています。
嘉子は後年の自伝や帰国後のテレビ番組で、「釈放は1940年(昭和15年)であり、労役三年後にモスクワに近いチカロフの町に送られて最低限の生活を保証され、第二次世界大戦中、1941年(昭和16年)の独ソ開戦後は看護婦をしていた」と語っていますが、実際は1947年に釈放されるまで劣悪な環境の刑務所に幽閉されていたようです。
「労役三年」や「看護婦をしていた」というのは、釈放の時に幽閉されていた事実を隠蔽するよう指示されたための作り話だったことが、嘉子の死後のNHKによる現地取材の結果から明らかになっています。
結婚そして帰国
ロシア政府から釈放され自由な身になった嘉子ですが、釈放後すぐには日本へもあえて帰国をしませんでした。そして第二次世界大戦終了後、モスクワ放送局に入局し、後の「ロシアの声」といわれる日本語放送のアナウンサーを務めるようになります。
そして、日本人の同僚で、このころハヴァロフスク放送局の日本語アナウンサーをしていた、元日活の人気俳優、「滝口新太郎」と結婚し、穏やかに暮らしはじめます。
滝口新太郎は、1913年(大正2年)生まれで嘉子よりも11才年下でした。子役として舞台で活躍した後、松竹蒲田に入社。20才のころに「忠臣蔵」で嘉子と共演したことがありました。その後日活に入社し、二枚目スターとして活躍するようになり、1936年(昭和11年)にも舞台で嘉子の子供役として出演し、共演を務めています。
その後東宝、大映などにも出演する人気俳優でしたが、1943年(昭和18年)、徴兵され満州に駐留。1945年(昭和20年)、敗戦により軍の上層部や財界人や官僚が日本にいち早く逃げ帰る中、置き去りにされた滝口ら多くの日本人は、ソ連の捕虜となり、シベリアに抑留されました。この点、私の父と同じです。
抑留が終了し、収容所から釈放後は日本に帰ることもできましたが、社会主義の理念に共感したためソ連に残り、ハヴァロフスク放送局の日本語アナウンサーとなります。その後、嘉子がモスクワ放送の日本語課に勤務していることを知り、手紙を送るようになり、1950年(昭和25年)、上司の計らいでモスクワへ転勤させてもらい、岡田と結婚することになりました。
嘉子はこの滝口と結婚前から、再び演劇の道に戻ることを決意し、現地のロシア人演劇学校に通った結果、演劇者としてロシアの舞台にも立つようになっていました。
嘉子と岡田が結婚して、ようやく穏やかな日々を迎えたころの1952年(昭和27年)、この年、ソ連を訪問した参議院議員の「高良とみ」が嘉子の存在を知り、現地でその生存を確認後、日本でこれをアナウンスしたため、日本中が驚きに包まれました。嘉子は同じくソビエトへ渡った杉本とともに、大粛清や大戦の戦乱の中でとうに死んでいたと皆が思っていたからです。
そしてさらに10以上の年月を経たあとの1968年(昭和43年)、日本のあるテレビ番組の中でモスクワの赤の広場からのカラー中継があり、そこに往年のスターであったときと変わらない若々しい口調で話しかける嘉子の姿にまたしても日本中が驚きました。
この中継が話題を呼び、このころの東京都知事であった美濃部亮吉のほか、かつての演劇仲間らが嘉子を帰国させようという運動を盛り上げたため、嘉子もこれに応じ、1972年(昭和47年)、ついに嘉子の帰国が実現することになりました。嘉子はもう70才になっていました。
そして、11月13日、羽田空港に34年ぶりに降り立った嘉子は、かつての大勢のファンや劇団関係者に取り囲まれ、この中にはかつての親しい劇団仲間だった宇野重吉さんも含まれていたということです。
しかし、そこには愛する夫の滝口の姿はありませんでした。この帰国の前年、肝硬変でこの世を去っていたためです。嘉子は、亡くなった夫・滝口の遺骨を胸に抱きながらタラップを降り、激動の人生を歩んできた気丈な彼女もさすがに涙々にあけくれた帰国となりました。
晩年
嘉子は、その後14年間もの間日本で暮らしました。この間、日本の芸能界にも復帰し、「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」などのほかの3本の映画に出演したほか、舞台演出にも関わり、数本のテレビドラマのほか、「クイズ面白ゼミナール」「徹子の部屋」などのトーク・バラエティ番組にも出演しました。
しかし、嘉子が80才を超えるころから、ソ連では国内改革が始まり、1985年(昭和60年)からはゴルバチョフ主導でペレストロイカがはじまると、嘉子は「やはり今では自分はソ連人だから、落ち着いて向こうで暮らしたい」と考えるようになります。
翌年の1986年(昭和61年)、正式にソ連国籍を取得した嘉子は、この年再びソ連へ戻ります。以後、亡くなるまで日本へは2度と帰国しませんでした。しかし、この間何度か日本のテレビ番組の取材には応じており、モスクワのアパートの自宅内も公開していたといいます。日本からの取材クルーが来るととても喜んでいたという逸話も残っています。
晩年は軽度の認知症など老衰症状が出ていたことで、モスクワの日本人会の人々がヘルパーとして常時入れ替わり立ち替わりで彼女の面倒をみていたそうですが、1992年、モスクワの病院で死去。90年の波乱に満ちた生涯に幕を閉じました。
嘉子が日本に帰国していた間、服部義治との間に設けた一児、といってもこのころには、もう50才を超えていたと思いますが、この方と嘉子はとうとう再会することはなかったようです。
岡田嘉子の息子さんということで、芸能界にも関わったこともあったようですが、その娘さん(嘉子のお孫さん)のブログによれば、彼女が22才のとき、放浪の旅に出たあと、2005年に亡くなったそうです。
岡田嘉子はこの一児のことを死ぬ間際に思い出したでしょうか。なぜ日本に帰国したときに探し出して会おうとしなかったのかは、ご本人に聞くしかありません。しかし、再会することにはいたたまれない思いがあったでしょう。
しかし、そんな二人もこの世の人ではなくなりました。きっとあの世再開し、生きていたころのことは邂逅されていることでしょう。そう願いつつ、この項を終わりにしたいと思います。