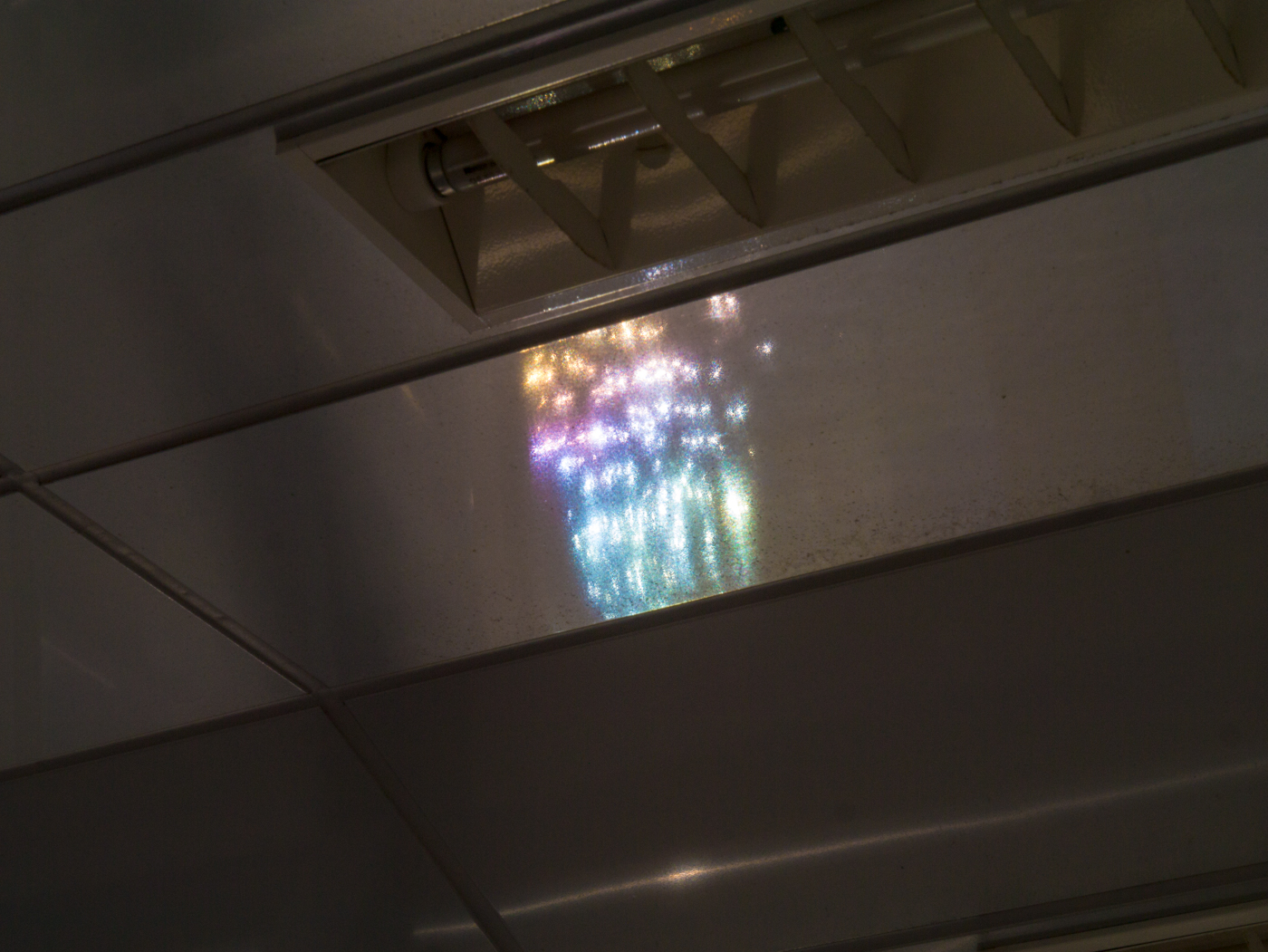……ついつい思い出してしまうのが、その昔流行った「フランシーヌの場合」という歌です。
フランシーヌの場合は あまりにもおばかさん
フランシーヌの場合は あまりにもさびしい
三月三十日の日曜日
パリの朝に燃えたいのちひとつ フランシーヌ
覚えているのは、私より上の世代の方々だと思いますが、このフランシーヌとは誰ぞや、と改めて調べてみると、これは、当時30歳だったフランス人女性のフランシーヌ・ルコントという人のことのようです。
1969年3月30日にパリで起こした政治的抗議のために焼身自殺したとのことで、これを歌ったのは、「新谷のり子」という人です。幼い頃から歌が好きで、歌手になろうと高校中退して北海道より上京、銀座のクラブで歌うようになりましたが、同時に学生運動の闘士でもあったそうです。
成田空港建設に反対する三里塚闘争に参加するようになり、ここで出会った市民運動家の紹介で、そのころCMソング作家として活躍していた作曲家と懇意になり、「フランシーヌの場合」を渡され、同曲でメジャーデビューすることになりました。
このフランシーヌが亡くなった年より9年前の1960年の6月15日には、全学連7000人が国会議事堂に突入を図り警官隊と衝突し、このとき、東大生だった闘争家、樺美智子が亡くなりました。これにちなんで、この日は運動家の間では「安保の日」とされており、このレコードは1969年の同日に発売され、約80万枚を売る大ヒットを記録しました。
新谷氏は、その後も闘争に参加しながら芸能活動を続けましたが、2枚目のシングルは、「さよならの総括」といい、左翼団体が暗躍していたこの時代の世相を表したものであり、「総括」という単語への嫌悪感からかあまり売れなかったようです。
このため、次第に歌うことの意味を見失い、メディアからは遠のいていき、また銀座のクラブ歌手に戻りましたが、徐々に政治意識をとりもどし、その後は朝鮮問題や部落問題にも取り組んだといいます。現在69歳になっておられるようですが、5~6年前に久々にテレビに出演し、往年の「フランシーヌの場合」を披露されたとのことです。
それにしても、明日で3月も終わりです。
もう4月か、といつものように時の流れの速さを思ってしまうわけです。なんとか時間を止めたいところですが、止まりそうもありません。この分だと、あっという間にジジイになりそうなので、なんとか歳をとらない方法はないでしょうか。もっとも既にジジイであるわけであり、ジジイがと更に齢を重ねてもやはりジジイであるわけですが……。
……新年度となり、新しいピリオドが始まる時期でもあります。それにしても、なぜ日本では4月が新年度のスタートなのでしょうか。
調べてみると、明治維新当初の明治7年、日本は旧暦から新暦への改暦に合わせて、年度を「1月~12月制」に変更するとし、明治6年(1873年)1月から実施していました。しかし2年後の明治8年(1875年)地租、すなわち土地への課税金の納期に合わせて、「7月~6月制」が導入されました。
従ってそのままいけば、現在でも7月が年度初めのはずなわけです。ところが、その後日本は軍備増強の中で無謀にも帝国海軍の大規模な拡充計画を推し進め、これが原因で著しい財政赤字に陥りました。
明治17年度(1884年度)は従来どおり、7月から始まりましたが、どうにもこうにも金がなくなり、いよいよ国庫の金が底をつきそうになったことから、税金のひとつである「酒造税」については、翌年の明治18年度に入る分を無理やり前年度に繰り入れしてしまいました。
例年だと酒造税の納期の第一期は4月です。その帳尻を合わせるための唯一の方法は、その翌年の4月から新しい年度が始まる、ということにして、この繰り入れてしまった税収を補うことでした。こうして、明治19年度(1886年度)より酒造税の納期に合わせて4月を年度初めとすることになり、その年だけは、酒税の4月の納税が二度行われました。
国民にしてみればいい迷惑だったわけですが、これが慣習となり、以後、4月が年度初めとなったわけです。そして、この会計年度に合わせ学校や企業なども4月を年度はじめとするようになりました。
現在では何から何まで4月が新しい年度のスタートとされます。学校・官公庁・会社などでは一斉に入社式・入学式が行われますが、このうち入学式の時期はちょうど桜の咲く季節であり、これはまるで、学校に入学することを許可されたことをお祝いをするようで、うってつけの時期ではあります。
このように、日本では一般に春の行事であるわけですが、しかし、欧米では、一般に学校の入学は9月ごろであることが多く、秋の行事です。最近東大をはじめとして、秋に入学時期をずらそうという動きがあるようですが、これも海外からの留学生を増やしたいがための措置のようです。
では、入社式はどうかといえば、こちらはあいも変わらず4月入社というところが多いようです。しかし、欧米やその他の国では4月一斉入社などを行うところはなく、そもそも入社式なるものを行うのは、日本くらいのものです。これはなぜでしょうか。
まず考えられるのは、欧米などの他の国では、卒業時期がそれぞれの学生によって異なるということ。また、企業のほうもそれゆえに、新卒の学生を定期的に採用する事がない、ということがあげられます。
さらに欧米では企業においては「即戦力」である事が重視されます。従って実務経験が全く無い新卒者を手厚く迎える事はありません。もちろん、新卒者が卒業後、すぐに正社員として迎えられる場合もありますが、多くの場合は在学中に「インターンシップ」や「パート・タイム・ジョブ」を経験してから会社に入ります。
あるいは、「契約社員」という形で入ることも多く、このように社会経験を積む事によって、正社員のポジションを獲得していきます。
しかも、彼の国々では比較的頻繁に転職をしますし、退職時期も人によって様々です。なので、いつどのポジションに欠員が出るかを予測する事が出来ないため、必要な人材を必要な人数だけ必要な時に採用するのが一般的、というわけです。
ですから、日本のように、ある時期に一斉に新卒の学生が就職をする、という事はほとんどなく、おのずから入社式も無い訳です
従って、外国人にすれば日本の入社式というものが不思議でしょうがないようです。また、この儀式も独特なものであり、その年に入社する新入社員を一堂に集めて、経営首脳による訓示等を行う、という光景は欧米ではまず見られません。
事業体によっては、入行式、入庫式、入組式、入庁式、辞令交付式、入職式などとその名称まで変わるわけで、ますますわけがわからなくなります。
それでは、なぜ新卒一括採用方式をとり、入社式をするのか。これは、日本では、実務経験の無い新卒者を採用してから「育てていく」という考え方が浸透しているためのようです。そして、入社式で社会人としての「けじめ」をつけさせ、社会の一員として自覚をつけさせる、という目的もあります。
こうした入学式や入社式以外にも、何かと日本人はけじめをつけるのが好きです。では、そもそもけじめとなにか。これは、連続する物事などの境目、区切れです。何等かの一定の形式にのっとった一定の規律をもつ行為でもあり、「儀礼」ともいいます。
人生にはいろんな境目があります。日本では入学や入社だけでなく、出生、成人、結婚、死などの人間が成長していく過程で、次なる段階の期間に新しい意味を付与することが求められることが多いものです。このとき、何等かのかたちで「儀礼」を行うわけで、これらは一括して、「通過儀礼」といいます。
人生儀礼ともいいます。英語ではイニシエーションといいます。大昔に行われていたものは、だいたいが割礼や抜歯、刺青など身体的苦痛を伴うものでした。割礼とは、男子の性器の包皮の一部を切除する風習であり、主に欧米で行われていた風習です。
いかにも痛そうですが、なんでこんなことをしたかといえば、これは包皮切除をしていれば性病のような症状が発生しにくいからです。包皮が取り除かれ、亀頭粘膜が角質化するため、性器が乾きやすくなります。また、ウイルスが粘膜上で生存する可能性が低減されるなど、ある程度の医学的根拠はあるようです。
このため、欧米では、1990年代までは生まれた男児の多くが出生直後に包皮切除手術を受けていたといい、アメリカの病院で出産した日本人の男児が包皮切除をすすめられることも多かったようです。
しかし、包皮の有無に関わらず多くの性病に関しては陰茎の洗浄を行っているかが重要であり、ウイルスが表面上に滞在することによる感染を防ぎたいのなら、性行為後に念入りな洗浄を行えば包皮の有無は関係しなくなります。このため、こうした知識が普及した現在では欧米でもこれをやる国はかなり減っているようです。
一方の日本では、こうした割礼という通過儀礼は定着しませんでした。と、いうか考えつきもしなかったでしょう。これはキリスト教ほか割礼を推奨する宗教があまり根付かなかったためです。もっとも、キリスト教に帰依していた一部のクリスチャンはやっていたのでしょう。詳しくは調べていませんが。
しかし、多くの日本人は仏教徒であり、そうした庶民の場合は、男子の場合、米俵1俵(60~80キログラム)を持ち上げることができたら一人前とか、地域の祭礼で行われる力試しや度胸試しを克服して一人前、1日1反の田植えができたら一人前などという、年齢とは別の成人として認められる基準が存在しました。
また、女子の場合には子供、さらに言うならば家の跡継ぎとなる男子を出産して、ようやく初めて一人前の女性として周囲に認めてもらえる、ということも多かったようです。
一方、武家階級では、ご存知のとおり元服というものがありました。服装、髪型や名前を変える、男子は腹掛けに代えてふんどしを締めるといったことであり、女子では成人仕様の着物を着て厚化粧などをする、といったことが行われました。
しかし、武家社会が崩壊した明治以降は、この風習は無くなりました。それと同時に欧米から「会社」という概念が導入され、多くの企業が誕生するようになりました。社員は、会社員ともいい、すなわち給料をもらって働く従業員です。給料は英語でサラリーということからサラリーマンともいいますが、この“salaryman”は元々和製英語です。
大正時代頃から、大学卒で民間企業に勤める背広にネクタイ姿の知識労働者を指す用語として、このサラリーマンはよく使われるようになりました。
この日本のサラリーマンこと、会社員は、「年功序列」で出世していきます。官公庁、企業などにおいて勤続年数、年齢などに応じて役職や賃金を上昇させる人事制度・慣習のことを指し、日本型雇用の典型的なシステムです。
日本においてこのような制度が成立した理由のひとつとしては、組織単位の作業を好むという国民性があり、このため成果主義を採用しにくかったことがあるようです。日本では何かと「和」が重んじられます。集団で助け合って仕事をすることも多く、この場合は、個々人の成果を明確にすることが難しくなります。
しかしそれでは給料に差異をつけられないため、そこで、組織を円滑に動かすためには従業員が納得しやすい上下関係をつくればいい、ということになりました。日本には、年少者は年長者に従うべきという儒教的な考え方が古代から強く、この考え方は浸透しやすかったようです。
つまり、長く働いた人ほどエライ、ということであり、年功序列制度は、集団組織というものを重視しつつ給料格差をつけるといったニーズを満たす合理的な方法でした。
和を重んじ、争いを嫌う国民性にとっては、こうした年功序列は最も波のたたない、リスクの低い確実な労働制度だったわけです。しかし、年功序列を制度として保つためには、同じ社員を永続的に雇用していく必要があります。
人は誰でも齢をとりますから、死ぬまで雇うというわけにはいきません。が、ある程度の年齢まで行ったらやめて貰うものの、この間の雇用は保証するし、長年働いてくれたご褒美に退職金もあげよう、とすれば皆が納得しやすくなります。そしてこれが「終身雇用制度」です。
現在は事情が変わってきているとはいえ、大企業の場合は、だいたいが終身雇用制であり、ほとんどの社員が大学卒業後に入社した会社で定年を迎えています。
この年功序列と終身雇用制度を組み合わせは、会社人事を検討する上でも好都合です。なぜならば合わせてうまく運用すれば、どの職務にどのような人材がどの程度必要なのかをある程度予測できるからです。
1年も前から人数と職種を決めて新卒者を採用する事が可能になるわけであり、永続して「年功序列」と「終身雇用制度」が保たれていれば、毎年3月にはそれぞれの企業で定年に達した社員が一斉に退職していきます。これにより人員を補充する必要がありますが、そこに新入社員が毎年入って来てくれる、というわけです。
この年功序列に近いものは江戸時代にもありましたが、商家や職人などごく一部の社会だけでした。武士の多くは藩主から雇われている身であり、身分毎に異なる扶持をもらって生活していましたが、年齢には関係なく定額制です。
農民に至っては、米や作物を自ら生産するだけで、たくさん働いてたくさん作ったから、長く働いたからといっても上に行けるというわけではありません。
一方の終身雇用のほうは、起源は丁稚奉公制度ではないかといわれることもあるようで、商売人では近いかたちがあったようです。が、武家社会ではそれぞれの「家」が主体であり、その職務は世襲制でした。このため、一生同じ職業に就くことは普通でしたが、これは社会全体の仕組みにのっとったものであり、現在の会社組織の終身雇用とは少々違います。
そもそも士農工商それぞれの身分で違う生産システムが決められていて、皆で頑張って利益をあげるという、会社組織というようなものもなかったわけです。
従って社会全体の通念としての終身雇用、というものはありませんでした。現在のような長期雇用慣行の原型がつくられたのはやはり明治になってたくさんの会社ができるようになってからです。また、定着したのは大正末期から昭和初期にかけてだとされているようです。
明治末期から大正にかけては、いわゆる殖産興業がとくに盛んな時期であり、多くの職人がいた時代でしたが、とくに1900~1910年代ころは熟練工の転職率が極めて高かったそうです。より良い待遇を求めて職場を転々としており、当時の熟練工の5年以上の勤続者は1割程度でした。
企業側としては、熟練工の短期転職は大変なコストであり、このため、大企業や官営工場では、その足止め策として定期昇給制度や退職金制度を導入しました。これが現在の終身雇用の原型です。
しかしこの時期の終身雇用制は、あくまで雇用者の善意にもとづく解雇権の留保であり、明文化された制度としてあったわけではありませんでした。このため、その後、終身雇用の慣行は、第二次世界大戦による労働力不足による短期工の賃金の上昇と、敗戦後の占領行政による社会制度の改革により、一旦は衰退しました。
ところが、その後日本は高度経済成長時代を迎え、50年代から60年代にかけては、神武景気、岩戸景気と呼ばれる好況のまっただなかにあり、多くの企業の関心は労働力不足にありました。このため、この時期に特に大企業における長期雇用の慣習が復活し、一般化しました。
1970年代に入ると、種々の裁判で労働者の不当解雇が会社の責任である、とされたことや、多くの企業で労働組合が結成されたことから、実質的に会社側の解雇権の行使も制限されるようになり、戦前まではあくまで慣行であった終身雇用が制度として認められ、人々の間に定着するようになっていきました。
ところが、最近は、長引く不況によって終身雇用を見直したり、中途採用を行ったりする企業が増えてきており、新たな時代に突入しようとしています。
雇用制度を見直す過程で、入社式を行なわない、といった会社も増えているようであり、学校なども秋季入学などが増えていく中、学生の卒業時期もランダムになっていくと思われます。このため通過儀礼としての入社式というものは、そのうちなくなっていくか、激減していくに違いありません。
さすれば、4月の桜の咲く時期の入学式や入社式といった風情もなくなっていくのか、と少々寂しい気もしますが、冒頭でも述べたとおり、そもそもは4月が年度初めなどというのは政府の気まぐれから決まったようなものであり、こだわる必要はないわけです。
通過儀礼としての入学式や入社式も新しい時代に合わせて撤廃するか、形を変えていくかすればいい、と個人的には思う次第です。最近選挙権の行使も20歳から18歳へ引き下げられましたが、これも通過儀礼と言えなくはなく、時代の変化に応じてその内容が変わった良い例です。
もっとも、現代の日本においては、幼少時の七五三や、老年期の還暦や喜寿の祝いなど、一定の年齢に到達することで行われる通過儀礼はまだ根強く残っており、これらは古きよき伝統ともいえ、あえて撤廃する必要もありません。
ただ、これらの儀礼は、昔ほど明確には意識されていないようで通過儀礼とみなされるほどのものではなくなってきています。それを行ったからといって必ずしも人生の節目や個々の成長の証しと認められるような性質のものではなくなってきているようです。こうした儀式をやらない人は増えているようであり、さらに形骸化していくのでしょう。
一方、まったくなくなってしまった通過儀礼の中には、「徴兵検査」というものもあります。男子の場合、明治の徴兵令施行から太平洋戦争が終結した1945年までは、「国民皆兵」の体制が取られ、徴兵検査がその通過儀礼となりました。
徴兵検査で一級である甲種合格となることは「一人前の男」の公な証左であり憧れの対象でもありました。徴兵検査により健康状態や徴兵上の立場が明らかにされることは、当事者の社会的・精神的立場にも影響を与えました。
現役兵役に適さないとされる丙種合格であった、作家の山田風太郎は、自らを「列外の者」と生涯意識する要因になったと述べています。また、1938年にはこの丙種合格判定をめぐって、日本犯罪史に残る大量殺人事件も起きています。
これは、「津山事件」といい、1938年(昭和13年)5月21日未明に岡山県苫田郡西加茂村大字行重(現・津山市加茂町行重)の貝尾・坂元両集落で発生した大量殺人事件です。犯人の姓名を取って「都井睦雄事件」とも、30名が死亡したことから、「津山三十人殺し」とも言われます。
2時間足らずで30名(自殺した犯人を含めると31名)が死亡し、3名が重軽傷を負うという、犠牲者数がオウム真理教事件(27名)をも上回る日本の犯罪史上前代未聞の殺戮事件でした。
犯人の都井睦雄(といむつお)は1917年(大正6年)、岡山県苫田郡加茂村大字倉見(現・津山市)に生まれました。幼い時に両親が病死したため、祖母が後見人となり、その後一家は祖母の生まれ故郷の貝尾集落に引っ越しました。
都井家にはある程度の資産があり、畑作と併せて比較的楽に生活を送ることができたようで、都井も尋常高等小学校に通わせて貰い、成績は優秀だったようです。しかし小学校を卒業直後に肋膜炎を患って医師から農作業を禁止され、無為な生活を送るようになります。
病状はすぐに快方に向かい、実業補習学校に入学しましたが、姉が結婚した頃から徐々に学業を嫌い、家に引きこもるようになっていきました。このため、同年代の人間と関わることはなかったものの、この地域での風習でもあった「夜這い」などの形で近隣の女性達と関係を持つようになっていったといいます。
事件の前年の1937年(昭和12年)に20歳になり、徴兵検査を受けました。この際、結核を理由に丙種合格となり、入営不適、民兵としてのみ徴用可能とされ、実質上の不合格となりました。そしてこの頃から、それまで関係を持った女性たちに、丙種合格や結核を理由に関係を拒絶されるようになっていきました。
翌年、狩猟免許を取得して津山で猛獣用の12番口径5連発ブローニング猟銃を購入。毎日山にこもって射撃練習に励むようになり、毎夜猟銃を手に村を徘徊して近隣の人間に不安を与えるに至ります。
この頃から犯行準備のため、自宅や土地を担保に借金をしていたといいます。しかし、祖母の病気治療目的で味噌汁に薬を入れているところを祖母本人に目撃され、そのことで「孫に毒殺される」と大騒ぎして警察に訴えられました。このために家宅捜索を受け、猟銃一式の他、日本刀・短刀・匕首などを押収され、猟銃免許も取り消されました。
都井はこの一件により凶器類を一度はすべて失いましたが、知人を通じて猟銃や弾薬を購入したり、刀剣愛好家から日本刀を譲り受けるなどの方法により、再び凶器類を揃え、犯行準備を進めていきました。
ちょうどそのころ、以前懇意にしてい女性が、嫁ぎ先から村に里帰りしてきましたが、それがちょうど運命の1938年(昭和13年)5月21日の前日でした。
5月20日午後5時頃、都井は電柱によじ登り送電線を切断、貝尾集落のみを全面的に停電させました。しかし村人たちは停電を特に不審に思わず、電気会社への通報をしたり、原因を調べたりはしませんでした。
午前0時を過ぎ、翌5月21日になった1時40分頃、彼は行動を開始します。詰襟の学生服に軍用のゲートルと地下足袋を身に着け、頭には鉢巻を締め、小型懐中電灯を両側に1本ずつ結わえ付け、首からは自転車用のナショナルランプを提げるといういでたちでした。
さらに、腰には日本刀一振りと匕首を二振り、手には改造した9連発ブローニング猟銃を持った都井は、まず自宅で就寝中の祖母の首を斧ではねて即死させました。その後、近隣の住人を約1時間半のうちに、次々と改造猟銃と日本刀で殺害していきました。
被害者たちの証言によると、この一連の凶行は極めて計画的かつ冷静に行われたとされていますが、「頼むけん、こらえてつかあさい」と足元にひざまづいて命乞いをする老婆や、返り血を浴びた都井に猟銃を突きつけられたものの、逃げることもできず茫然と座っていた老人などは見逃したといいます。
しかし、都井の凶行はさらに続き、最終的に事件の被害者は死者30名となりました。このうち即死は28名とされ、重傷のち死亡2名であり、このほか重軽傷者が3名出ました。計11軒の家が押し入られ、そのうち3軒が一家全員が殺害され、4軒の家が生存者1名でした。死者のうち5名が16歳未満の少年少女だったといいます。
一方で、激しい銃声と都井の怒鳴り声を聞き、すぐに身を隠すなどして助かった生存者もおり、また上述の老人以外にも「決して動かんから助けてくれ」と必死に哀願したところ都井は「それほどまでに命が惜しいんか。よし、助けてやるけん」と言い、助けられた人もいました。また、2名は襲撃の夜に村に不在だったため難を逃れています。
こうした約一時間半に及ぶ犯行後、都井は遺書用の鉛筆と紙を借りるため、隣の集落の一軒家を訪れました。家人は返り血を浴びた都井を見て驚き動けない状態でしたが、その家の子供は以前から都井の顔見知りでした。彼はその子供から鉛筆と紙を譲り受け、立ち去り際に「うんと勉強して偉くなれよ」と声をかけています。
その後彼は、3.5km離れた峠の山頂で遺書を書いた後、猟銃で自殺しました。都井の遺体は翌朝になって山狩りで発見されましたが、猟銃で自らの心臓を撃ち抜いており、即死状態でした。
その後の警察の調べでは、都井はこのとき書いた遺書以外にも実姉を始め、数名に宛てた長文の遺書を書いていました。さらに自ら自転車で隣町の駐在所まで走り、難を逃れた住民が救援を求めるのに必要な時間をあらかじめ把握するなど、犯行に向け周到な準備を進めていたことなどが判明しました。
自姉に対して遺した手紙には、「姉さん、早く病気を治して下さい。この世で強く生きて下さい」と書いてあったといいます。また、犯行の理由として、以前から関係があったにもかかわらず、他家へ嫁いだ女性への恨みだけでなく他の村人への悪意についても書かれていたようです。
この女性はその前夜実家に里帰りしており、ここに都井は当然のように踏み込んで来ましたが、彼女は運よく逃げ出すことができ、生き延びました。しかし、彼女を追いかけた都井は、逃げ込んだ先の家の家人を射殺しています。
この他にもかねてから殺すつもりの相手が他所へ引っ越していたり、他者の妨害にあったりして殺害することができなかったようで、最後に峠で記した遺書には「うつべきをうたず、うたいでもよいものをうった」という反省の言葉が記されていました。また、真っ先祖母を手に掛けことを、「後に残る不びんを考えてつい」と書かれていました。
この前代未聞の惨劇は、ラジオや新聞などのマスコミがセンセーショナルに報道され、少年誌である「少年倶楽部」までもこの事件を特集したといいます。
この事件が貝尾集落に与えた影響は計り知れず、集落の大部分が農業で生計を立てているため、一家全滅や家人の多くを失った家では生活苦に陥りました。さらに、都井から襲撃を受けなかった親族は、企みを前々から知っていて隠していたのではないかと疑われ、村八分にされたといいます。
現在も津山市の奥にあるこの集落は存在し、そこには昔ながらの墓所が点在していますが、その墓石の多くには“昭和十三年五月二十一日”と刻まれているそうです。
あまりにも身勝手で理不尽な殺人事件ですが、その原因となったのが徴兵検査という通過儀礼であったことを考えると、その意味を改めて考えさせられてしまいます。
出生、成人、結婚、死など通過儀礼は誰しもが否応なく経験することの多いものですが、ことしもまた、例年のように繰り返される入社式や入学式の意味ももう少し真剣に議論されてもいいように思います。
その日のためにわざわざ大枚をはたいて晴れ着やスーツを買って出席しても、その時の社長や学長の御言葉を、卒業まで、あるいは何十年後の退職の日まで覚えているという人はどれくらいいるでしょうか。
なかにはその指導者の言葉に感銘を受けて、仕事や学業に励むようになった、という人もいるかもしれませんが、わざわざ大勢の人をお金をかけて集めて訓示しなくても、ほかに方法はあるように思います。その銭をもっと会社の益になるよう使ったほうがよいかもしれません。
形式にこだわるより、その組織に入った日から必死に働き、勉強しろ、と教えるのが本物の指導者のような気がします。「けじめ」の意味が薄れている現在、そのために行う通過儀礼の意味も問われている時代になっているのではないでしょうか。