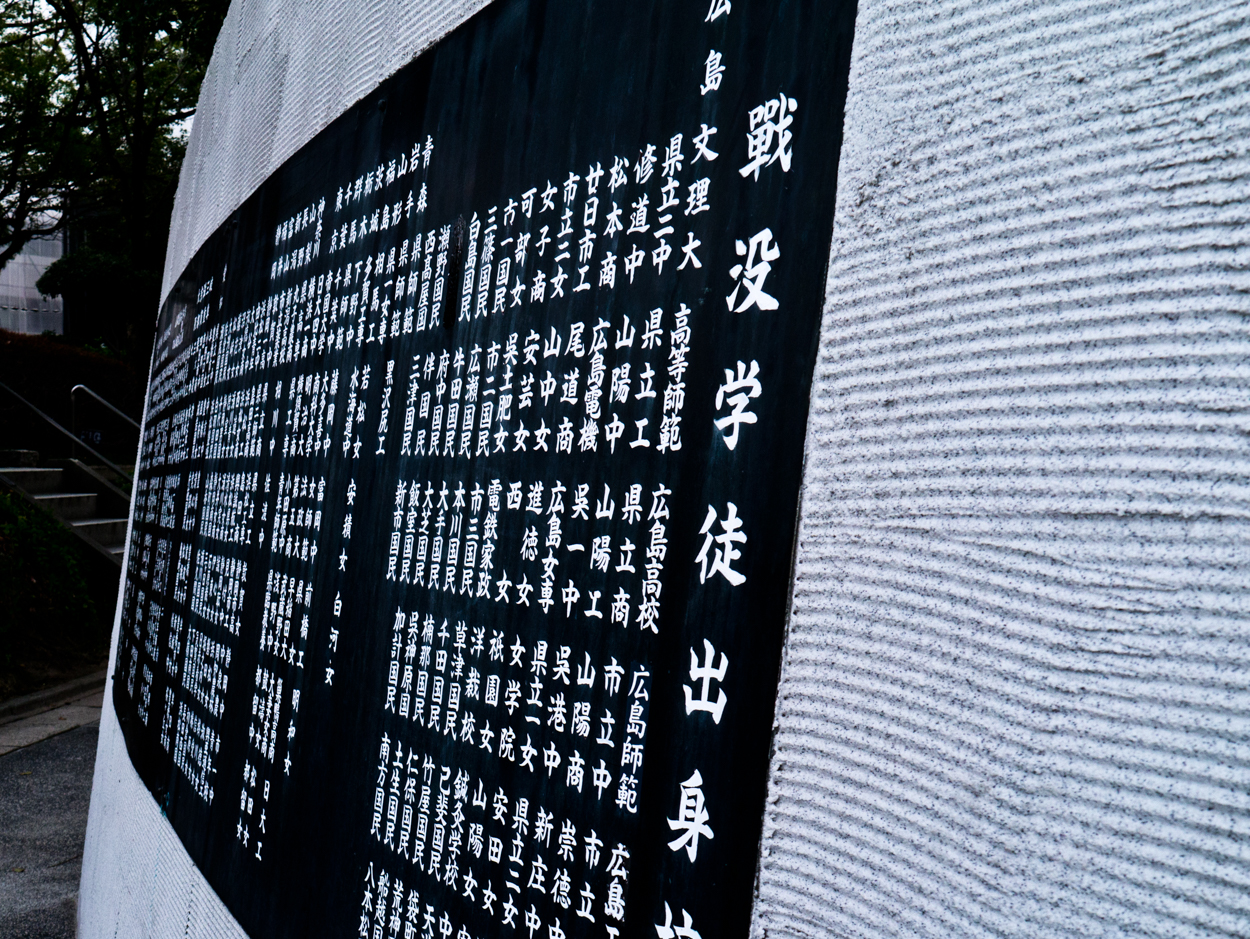先日、中国で大きな爆発事故がありました。
もう既に「2015年天津浜海新区倉庫爆発事故」という事故名もつけられているようで、その被害の甚大さから、歴史的な爆発事故として記録に残っていくことになりそうです。
爆発の中心は天津市浜海新区の港湾地区にある国際物流センター内にある危険物専用の倉庫らしく、発生したのは現地時間8月12日午後11時ごろ。当初、一帯に火災が発生したのを受け、消防員が駆け付けて消火活動にあたっていたところ、11時半ごろに2回にわたる大爆発が発生し、鎮火作業を行っていた消防隊員等17人が即死したといいます。
この際、周辺住民も爆発に巻き込まれ、現時点で170人以上の死者・行方不明者を出しているようです。爆発現場から半径2キロ圏内にある建物の窓ガラスが割れ、近くの「津浜軽軌」という鉄道の駅舎やコントロールセンターは爆発で大きく損傷したため、全線は運営停止になりました。
同地区は、天津港の中心となる巨大なコンテナターミナルがあるほか、精油所、石油化学コンビナート、製塩工場、造船基地などが集積する工業地帯です。1980年代の改革開放後、天津経済技術開発区(TEDA)など経済特区や工業団地が設けられ、外資系の工場やオフィスが進出する新たな都市となっており、日本企業も多数がここに進出していました。
それら複数の日本企業にもこの爆発が及んだようで、死傷者は出なかったようですが、今後の営業にも影響が出そうです。
2010年代にはこうした大爆発事故があいついでいます。2年前の4月17日にも、「テキサス州肥料工場爆発事故」というのがあり、アメリカ合衆国テキサス州マクレナン郡ウエストで大規模な爆発事故がありました。
化学肥料工場を操業していたウエスト・ファーティライザー社が起こした事故で、約270tの硝酸アンモニウムにインカしたと考えられ、工場には爆発防護壁を設けていなかったため、周辺の民家60-80棟が被害を受けたほか、死亡者15人、負傷者200人以上の被害を出しました。
また、記憶に新しいところでは、昨年2014年の8月1日に「高雄ガス爆発事故」というのがあり、これは台湾の高雄市で発生した大規模爆発事故です。現場道路の地下にはプラスチック原料となる可燃性のプロピレンガスのパイプラインが通っており、これが漏出したことにより発生し、死者32名、負傷者321名の損害を出しました。
中国では、今回の事故を起こす前にも大規模な事故が起こっており、これは「長征3Bロケット」の爆発によってもたらされたものです。1996年2月14日のことであり、中国の四川省涼山(リャンシャン)イ族自治州にある西昌衛星発射センターから打ち上げられた長征3Bロケットが、西昌市街に墜落・爆発しました。
この爆発では、ロケットに搭載されていた、強い腐食性を持つ非対称ジメチルヒドラジンが一帯に飛散し、西昌市街は壊滅。中国当局は、御多分に漏れず、現場を封鎖して証拠隠滅を図りましたが、すぐに世界の知るところとなりました。死者は公式発表によれば約500名とされていますが、実態はそれ以上だろうとされています。
こうしたロケットがらみの大爆発事故は、ロシアでも起こっており、これは「ニェジェーリンの大惨事」といい、1960年10月24日に発生しました。ロシア西部のバイコヌール宇宙基地でR-16大陸間弾道ミサイルの発射試験中にミサイルが爆発したもので、100名以上の死者を出したといい、一説には約200名が死亡したといいます。
この事故では、初代戦略ロケット軍司令官のミトロファン・ニェジェーリン砲兵元帥が死亡しており、爆発の炎は50km離れた地点からも観測できたと伝えられます。この当時はまだ共産党支配下のソ連邦時代だったため、この事故は政府によって秘匿され、1990年代になってようやく事故事実が公表されました。
ロシアではその9年後の、1969年7月4日にも「N-1ロケット爆発事故」が起こしており、こちらも同じバイコヌール宇宙基地で発生しました。打上げ試験が行われたN-1ロケット(総重量約2,750t)の2号機が発射台を離れた直後に爆発したものです。
死傷者数は明らかにされていません。事故の詳細が明らかにされていないのは、この時期にちょうどソ連とアメリカは熾烈な宇宙開発競争を行っており、ソ連側としては、この事故を表に出すことによって、自国の宇宙開発がお粗末なもの、という印象を世界に与えたくなかったからでしょう。
その競争相手のアメリカもまた宇宙開発においては数々の爆発事故を起こしています。その最たるものは、1986年1月28日におきた、チャレンジャー号爆発事故でしょう。スペース・シャトルチャレンジャー号が射ち上げから73秒後に分解し、7名の乗組員が犠牲になった事故です。
爆発によるものではありませんが、スペースシャトルは2003年2月1日にもコロンビア号空中分解事故を起こしており、同機は大気圏に再突入する際、テキサス州とルイジアナ州の上空で空中分解し、7名の宇宙飛行士が犠牲になっています。
ロケットの爆発事故としてはこのほか、2003年8月22日に発生した、ブラジルロケット爆発事故というのもあります。ブラジル宇宙機関のVLS-1ロケットがマラニョン州のアルカンタラ郡北部にあるアルカンタラ射場で爆発した事故です。
打ち上げ時ではなく、打ち上げを数日に控えての直前の整備中の出来事で、1段目が突然点火し、21人が死亡しました。轟音は付近の密林一帯に轟き、遠方からも煙が目撃されたといい、ブラジル独自設計したロケットの打ち上げとしては、3度目の大事故となりました。
こうしたロケットがらみの大爆発事故というのは、さらに過去に遡るとさらにたくさんあるのですが、それはさておき、それでは日本で過去に起こった大爆発事故としてはどんなものがあるかといえば、戦前では、「禁野火薬庫爆発事件」という大きな事故がありました。
1939年3月1日のことで、大阪府枚方市禁野の陸軍禁野火薬庫で起こった爆発事故です。砲弾の解体作業中に発火、倉庫内の弾薬に引火し爆発したもので、近隣集落も飛散した砲弾等によって延焼し94名が死亡、602名が負傷しました。
また、戦中では、1943年6月8日に発生した、「戦艦陸奥爆沈事件」というのがあります。広島湾沖柱島泊地で、戦艦陸奥の錨地変更のための作業を行おうとしていたところ、突然に煙を噴きあげて爆発を起こし、一瞬にして沈没しました。この事故では、乗員1,121名が亡くなりました。
原因はわかっていませんが、自然発火とは考えにくく、直前に「陸奥」で窃盗事件が頻発しており、その容疑者に対する査問が行われる寸前であったことから、人為的な爆発である可能性が高いとされます。
戦後の1970年(昭和45年)になって朝日新聞が四番砲塔内より犯人と推定される遺骨が発見されたと報じ、この説は一般にも知られるようになりました。この時、窃盗の容疑を掛けられていた人物と同じ姓名が刻まれた印鑑が事故現場で発見されていたといいますが、何の目的で爆破を図ったかまではわかっていません。
スパイの破壊工作ではないか、いや砲弾の自然発火による暴発では、はたたま、乗員のいじめによる自殺や一下士官による放火ではなどの説がいろいろ持ち上げられ、フィクション作品の題材としても数多くとりあげられました。
戦艦「大和」もその沈没時に大爆発を起こしています。1945年4月7日のことであり、鹿児島県坊ノ岬沖合で空襲により大火災を起こし横転、弾薬庫内にあった多数の主砲弾が誘爆して轟沈しました。火柱が高さ6,000mまで立ち上り、鹿児島からも見ることができたといい、また近くを飛んでいた米軍機が爆風に巻き込まれて墜落したと言われています。
軍艦がらみではこのほか、「横浜港ドイツ軍艦爆発事件」というのが1942年11月30日に発生しています。ドイツのタンカー・ウッカーマルクが、船倉清掃作業中に火災を起こし、近くの停泊していたドイツの仮装巡洋艦トール他2隻を巻き込んで爆発したもので、ドイツ兵を中心に102名の犠牲者を出し、横浜港内の設備が甚大な被害を受けました。
さらに終戦直前の1945年4月23日には、「玉栄丸爆発事故」というのがありました。鳥取県西伯郡境町(現・境港市大正町)の岸壁で火薬を陸揚げ中だった旧日本軍の徴用船「玉栄丸・937トンが爆発したもので、その後の誘爆によって周辺の家屋431戸が倒壊焼失し、115人が死亡、309人が負傷しました。
陸揚げの途中での休憩中に上等兵が投げ捨てたタバコが、同船に積んでいた火薬に引火したのが原因とされます。
こうした戦争時に使用された砲弾・火薬がらみの爆発は、戦後すぐにも相次いでおり、1945年11月12日には、「二又トンネル爆発事故」という過去において最大級の事故が起きています。これは、福岡県添田町にあった日田彦山線未開通区間の二又トンネルに旧日本軍が保管していた約530tの弾薬が爆発したというものです。
進駐軍の監督下でこれを警察官と作業人夫が処分しようとしたところ火薬が大爆発を起こして山全体が吹き飛んでしまい、彼らは落ちてきた土砂の下に埋もれてしまいました。また、これによりトンネルの上の山が吹き飛ばされ、周辺住民147名が死亡、149名が負傷しました。
二又トンネルはこの爆発で丸山ごと吹き飛んだために消滅し、1956年に開通した鉄道は、切り通し(オープンカット)のようになった場所に線路が通されています。また二又トンネル跡から筑前岩屋駅側に下った箇所にある第4種踏切の正式名称は「爆発踏切」であり、遠目ながらこの踏切から切り通しになっている様子を見ることが出来ます。
1948年8月6日には、「伊江島米軍弾薬輸送船爆発事故」というのも起きています。沖縄本島の本部半島から北西9kmの場所に位置する伊江島で起きた事故で、この当時同島はまだ米軍統括下にありました。5インチロケット砲弾約5,000発(125t)を積載した米軍の弾薬輸送船が接岸時に爆発したものです。
その日は夏休み中だったこと、たまたま地元の連絡船が入港していて多くの人が出迎えに来ていたことなどで、米軍事故調査委員会報告書によると死者には、地域住民を多数含む107人、負傷者70人であり、米軍統治下の沖縄で最大の犠牲者を出す事故となりました。
以後、長らくこうした戦時中に保持していた爆弾による爆発事故は生じていませんでしたが、1959年12月11日には、「第二京浜トラック爆発事故」というのが起こっており、これは、米軍の砲弾を解体して取り出したTNT火薬を積載していたトラックの1台が、砂利運搬トラックと正面衝突して、その衝撃で火薬が爆発した、というものです。
横浜市神奈川区子安台46の第二京浜国道上で、対向車線を走行中の砂利運搬トラックと正面衝突し、TNT火薬4トン(30kg積×134箱)が爆発し、双方の乗員4名が即死しました。砂利運搬トラックの運転手は、運転免許を取得したばかりの初心者で、この運転手が居眠りして対向車線にはみ出した所へ、火薬積載トラックが衝突したと推定されています。
戦後に起こった、旧日米両軍の保有火薬等による大規模な爆発は以上ですが、戦後日本が高度成長していく過程においては、このほかにも大きな爆発事故が起こっており、1955年2月4日には、「秋葉ダム・ダイナマイト爆発事故」というのが起こっています。
静岡県浜松市天竜区・天竜川本川中流部の秋葉ダム建設現場で、不発のまま放置されていた大量のダイナマイトが誘爆した事故です。ダム現場の爆破作業を行なったところ、それ以前の発破作業で不発のまま残っていた1.9トンのダイナマイトが誘爆し、約3,000立方メートルもの土砂が崩れて現場にいた19名の技術者と作業員が生き埋めとなり死亡しました。
こうした建設作業現場での事故はこのほかにも多数起っていますが、この事故はその中でも最大規模のものです。このほか、花火による爆発事故も多数生じており、そのうち最大規模のものは、1955年8月1日の「墨田区花火問屋爆発事故」です。東京都墨田区にある花火工場の倉庫で爆発事故。死者18名、重軽傷者80名以上を出しました。
実はこの翌日にも大規模な爆発が起こっており、この年は大爆発の当たり年でした。これは、「日本カーリット工場爆発事故」といい、1955年8月2日におきました。神奈川県横浜市保土ケ谷区にある火薬工場において発生した爆発事故です。
日本カーリットというのは、電気系化学品のほか、自動車等に搭載される発炎筒や産業用の爆破材料を生産している会社であり、同社横浜工場の填薬室において、火薬の充填作業中に火薬の中に異物が混入していたことが原因で発生した摩擦により爆発が発生したものです。
この最初の爆発が引き金となり、同じ作業場にあった別の約600キロの火薬が誘爆して爆発、さらに作業所内を手押し車で搬送中だった400キロの火薬にも引火し爆発したと推察されており、この事故により3名が死亡(1名は即死、2名は病院搬送後に死亡)、重軽傷者19名を出しました。
前日に墨田区花火問屋爆発事故が発生したばかりのことでもあり、この当時、この二つの連続爆発事故は世間の注目を大いに集めました。
その後、前述の「第二京浜トラック爆発事故」が1959年に発生して以後、それほど大きな事故は起っていませんでしたが、大阪万博が開催された1970年には、同じ大阪で「天六ガス爆発事故」というのが発生しています。
万博が3月に開催された直後の4月8日のことであり、大阪市北区菅栄町(現・天神橋六丁目、通称天六)で、都市ガス爆発事故が発生しました。地下鉄谷町線天神橋筋六丁目駅の工事現場で発生したもので、この事故では、直前に地下に露出した都市ガス用中圧管と低圧管の水取器の継手部分が抜け、都市ガスが噴出していました。
たまたま通りかかった大阪ガスのパトロールカーが通報し、事故処理車が出動しましたが、現場付近でエンストを起こし、エンジン再始動のためにセルモーターを回したところ、その火花に漏れたガスが引火して炎上。この時、その事故現場の上にあった道路上の覆工板上に、騒ぎを聞きつけた野次馬と大阪ガスの職員、消防士、警察官など多数がいました。
この爆発とともに、その被覆工板もろとも上に乗っていた人間が吹き飛ばされ、死者79名、重軽傷者420名の大惨事となりました。この事故により、大阪万博で大阪ガスが開いていた「ガスパビリオン」は一時公開中止となり、また、当事故現場を含む大阪市営地下鉄谷町線の工事区間の開通はこの事故によって大幅に遅れ、1974年5月となりました。
この10年後の、1980年8月16日、今度は静岡でガス爆発事故が発生しました。「静岡駅前地下街爆発事故」といい、静岡駅北口の地下街で発生したメタンガスと都市ガスの2度におよぶガス爆発事故です。15人が死亡、223人が負傷しました。
実はこのとき、私は学生で隣町の清水市にいました。さすがに爆発音までは聞こえてきませんでしたが、このとき清水側からもたくさんの消防車が静岡ヘ向かったようで、町中がなにやら騒がしいので、なんだろう、と思いつつ、下宿へ帰ってからテレビをつけて、はじめて事件を知りました。
この爆発は、地下の湧水処理漕に溜まっていたメタンガスに何らかの火が引火したことが原因と考えられており、最初の爆発は小規模なものであり、火災の発生には至らなかったものの爆発により都市ガスのガス管が破損しました。
すぐに消防隊が駆けつけ、現場処理を行っていましたが、このとき消防士たちはガス濃度が高いことに気づき、すぐに地下街からの脱出を指示するとともに排気作業を開始しました。が間に合わず、午前9時56分に2回目の爆発が起こりました。
この2回目の爆発は大規模なもので、火元となった飲食店の直上にあった雑居ビルは爆発炎上し、このビルの向かいにあった西武百貨店(現・パルコ)や周囲に隣接する商店及び雑居ビルなど163店舗にガラスや壁面の破損などの大きな被害をもたらしました。
事故発生の当日はお盆や夏休み中の土曜日で買い物客も多かったことから数多くの通行人が現場に駆けつけ、写真撮影をする者、応急的な救助活動をする者などで現場はパニックとなりました。爆発がデパートの開店直前だったことも、負傷者が増えた要因になりました。
この事故以降、地下街に関する保安基準(都市ガスの遮断装置、消防設備など)が厳しくなり、地下街の新設も1986年の神奈川県川崎市の川崎アゼリアの開業までしばらく認められませんでした。宮城県仙台市でも一時地下街の開発が計画されていましたが、地下街に関する保安基準の厳格化により、計画は中止となっています。
事故後しばらく閉鎖されていた地下街は防災センターや消防設備を整備のうえ復旧しましたが、私は卒業前にこの真っ黒に焼け落ちた一角を訪れており、その惨状を目にしています。その後、この地下街は復旧して新しく「紺屋町地下街」と改称となり、事故現場の地上のビル群も建て変えられたりして、現在ではかなり事故当時の面影は薄らいでいます。
その後、日本では上述の保安基準以外にも安全基準がかなり見直されて、こうした大規模な爆発事故は起りにくくなりました。が、今回の中国、天津でおきた爆発事故などを見ると、彼の国の安全対策は現在の日本のレベルにはまだまだ達していないんだろうな、と思ったりします。
中国以外にもあまり先進国のメディアが報じないような大爆発が起こっているに違いなく、とくにインドやアフリカあたりでは、あちこちで何やらやらかしていそうです。
それでも、現在のように戦争が比較的少ない時代には、兵器がらみの大爆発といったものは少なくなっているといえ、その昔に比べればずいぶんと世界も安全になったほうだ、ということはいえるでしょう。
戦争がらみの大爆発というのは、過去にはかなり凄惨なものが多く、無論、我が国が受けた広島・長崎の原爆被害はその中でも最大のものですが、近代において、こうした核爆発によらない、戦争がらみで一番大きかった爆発は何か、というと、これは1856年に発生した、ロドス島騎士の宮殿爆発事故のようです。
ギリシャのロドス島において騎士団長の居城とされた宮殿に落雷、地下火薬庫が爆発したともので、詳しい記録はありませんが、4,000人が死亡したといわれます。
落雷による爆発事故はこれ以前にもあり、1578年10月12日に、「ペンテコステの大爆発」と呼ばれるものがあり、これは、ハンガリーの首都ブダペシュトにあったブダ城の倉庫に落雷したというもので、保管していた粉類が粉塵爆発し、おおよそ2,000人が死亡しました。
こうした1000人以上もの被害者を出した事故というのは、17~19世紀にかけては結構多発しており、1654年5月18日には、オランダのデルフト市で、「デルフト大爆発」というのがあり、火薬庫に蓄えられていた40tの火薬が爆発して、市街の大部分が破壊された上、約1,200人が死亡し、1,000人以上の負傷者が出ました。
また、1769年8月18日には「ブレシア・聖ナザロ教会爆発事故」というのがあり、これはイタリアのヴェネツィア近郊の都市ブレシアにある聖ナザロ教会に落雷、通廊に保管されていた80トンの火薬に引火して爆発したもので、都市の1/6が破壊され、3,000人の死者を出す大事故となりました。
20世紀に入ってからは、1917年12月6日に「ハリファックス大爆発」というのがあり、ます。これはカナダのハリファックス港での船同士が起因で、そのうち1隻はピクリン酸を主とする2,600tの爆発物を積んでおり、衝突の際に火災が起き、爆薬を積んだまま火のついた船が埠頭へと流れ着いて爆発しました。
1,600名が死亡、約9,000人が負傷し、ハリファックス中心街の大部分が壊滅しましたが、この事故を調査する過程において、その威力の大きさが「反射波」によるものであることがわかりました。
爆薬が空中で爆発した場合には、爆風の入射波が地面に当たって地上反射波と跳ね返りますが、この入射波と地上反射波が合わさることで、爆発の威力が倍加します。その後開発された、原子爆弾はこの効果を利用しており、上空で爆発させることによって威力を高める、という原理はこのハリファックスの爆発の調査結果から分かったとされています。
20世紀に入ってからはこのほか、過去における最大の犠牲者を出した「メシヌの戦い」における爆発というのがあります。1917年、第一次世界大戦中のことで、このときイギリス軍は、ベルギーのメシヌの尾根にあるドイツ軍根拠地への攻撃を計画していました。
当日6月7日、ドイツ軍根拠地の地下にトンネルを掘って埋設された19個の巨大な地雷、総計600tが爆破され、これによりドイツ兵約10,000名が死亡。爆発の音は遠くダブリンにまで響き、チューリッヒでも振動を感じたとされます。
しかも、このとき使用された火薬は全て爆発せず、その後1950年代に落雷により残った火薬の一部が爆発する事故が発生しました。現在でも不発の爆薬が現地の尾根に眠っていると思われています
このメシヌの戦いというのは、「パッシェンデール作戦」といわれる一連の作戦の序盤戦で実施されたものです。イギリスほか連合国とドイツとの間で行われ戦いであり、三ヶ月に渡る激戦の末、カナダ軍団が1917年11月6日にパッシェンデールという町を奪取して戦闘は終わりました。
「パッシェンデール作戦」といわれるのはこのためですが、この戦いを通じて膨大な人的損害が出たことから、「第一次世界大戦のパッシェンデール」と言えば、「初期の近代的戦争が見せた極端な残虐性」を象徴する言葉でもあります。
この戦いで、ドイツ軍は約270,000人を失い、イギリス帝国の各軍は計約300,000人を失いました。この中にはニュージーランド兵約3,596人、オーストラリア兵36,500人、カナダ兵16,000人が含まれます。
また、イギリス・ニュージーランド・オーストラリアで合わせて90,000人の遺体は身元を特定できず、また42,000人の遺体は遂に発見できませんでした。空撮写真の分析では1平方マイル(2.56 km²)当りの砲弾孔は約1,000,000個を数えたといわれ、その後の第二次世界大戦以前では最も凄惨な戦いでした。
このメシヌの戦いの爆発があったのと同じ年の12月に起こったのが、上述の「ハリファックス大爆発」であり、事故を起こしたフランス船籍の貨物船モンブランは、ハリファックス港でヨーロッパ戦線のための軍用火薬を積んで出航する直前でした。
第一次大戦はこの事故の3年前の1914年に勃発しており、ハリファックスは北アメリカからヨーロッパへの軍需品の積み出しが盛んに行われている港でした。自然の良港で冬も凍らず、しかもフランス、イギリスへ最短距離の位置にありました。
北アメリカ大陸からの軍需物資輸送船は、ここに集結し、ドイツ潜水艦対策のため船団を組んで大西洋を渡っていましたが、この時期のハリファックス港は常に混雑しており、外洋船、フェリー、艀、漁船が入り乱れ、港の管理が不十分であり、船舶の小さな衝突は頻繁に発生していました。
実は、この前年の1916年にも、同じ北米大陸、アメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティで大爆発が起こっています。ただし、こちらは事故ではなく、「爆破事件」であり、軍需物資が第一次世界大戦の連合国側諸国に輸送されるのを阻止するための、ドイツの諜報員によるアメリカ合衆国の弾薬供給に関する破壊活動でした。
ブラック・トム大爆発(Black Tom explosion)と呼ばれ、1916年7月30日に発生しました。「ブラック・トム」は当初リバティー島に隣接した、ニューヨーク港の島の名前です。島の名前は、かつてトムという名の浅黒い漁師が長年住んでいたという伝承に基づきます。
ここに1905~1916年に連邦政府のドックと倉庫、発着場を配置した1マイル(約1.61km)の桟橋ができましたが、ブラック・トムはアメリカ北東部で製造される軍需物資の主要な発着所でした。
桟橋や倉庫棟がほぼ完成した7月30日の夜の時点で、ここには200万ポンド(約900,000kg)の弾薬が発着所の貨車の中に保管され、ジョンソン17号はしけの上に10万ポンド(約45,000kg)のTNT火薬などが、イギリスとフランスへの出荷品として用意されていました。そして、それはテロリストにとっても魅力的な目標でした。
真夜中過ぎに、突如、複数の火の手が桟橋の上で上がりました。一部の守衛は爆発を恐れて逃げ出しましたが、残った者達は火災を食い止めようと踏み留まりました。そして、午前2時8分、最初の、そして最大の爆発が発生します。爆発による金属片は長距離まではじけ飛び、一部は自由の女神に達しました。
そして1マイル以上離れているジャージーシティの商業地区にも達し、地元紙ジャージージャーナルの時計台の時計を2時12分で止めました。地震波の規模はマグニチュード5.0~5.5を計測し。地震波は遠くフィラデルフィアまで達し、40km(25マイル)離れた地点の窓が割れたり、近隣のマンハッタン南西部では数千枚のガラスが割れました。
ジャージーシティの市役所の壁にはひびが入り、ブルックリン橋は衝撃で揺れ、その後も、小さな爆発が何時間にもわたり起こり続けました。この爆発により、負傷者は数百人を数え、7名が犠牲となったとされますが、正確な死者数は分かっていないようです。
その後の調査の結果、桟橋の守衛の内2人はドイツの諜報員であることが明らかなりましたが、この二人は既にアメリカを出国していました。また、この二人を操っていたのは、1915年までアメリカ大使館付き武官だった、フランツ・フォン・パーペンであることなどもわかりました。
パーペンは、武官としてアメリカに赴任すると、国内でさまざまな諜報活動に従事し、また兼轄国であるメキシコをドイツ寄りにすることに努めました。また、フランクリン・ルーズベルトやダグラス・マッカーサーといった、後年のアメリカ合衆国指導者の知遇を得ており、これがアメリカ国内での破壊活動をよりやりやすくしました。
結局、この事件との関わりは証明されないまま、1916年にサボタージュ活動や破壊工作活動に関与しているとされてアメリカ政府から国外追放処分を受けましたが、このとき帰国の際不用意に別送した荷物がイギリス海軍の臨検を受け、パーペンがアメリカ国内に構築したドイツの諜報網が暴露されました。
パーペンは、その後ドイツ帰国後に皇帝から鉄十字章を授与され、参謀本部に戻りオスマン帝国に派遣され、オスマン帝国軍大佐となりましたが、第一次世界大戦の敗北後は、政治家に転身しました。
その後、国家社会主義ドイツ労働者党、いわゆる「ナチ党」の党首アドルフ・ヒトラーと接近し、彼が首相になれるよう尽力するなどナチ党の権力掌握に大きな役割を果たしました。
1933年のヒトラー内閣成立では、ヒトラーに次ぐ副首相の座に就きましたが、「長いナイフの夜」事件で失脚し、その後はオーストリアやトルコでドイツ大使を務めました。大戦後、ニュルンベルク裁判で主要戦争犯罪人として起訴されましたが、無罪とされ、1969年満89歳で没しました。
パーペンが仕組んだとされるこのブラック・トム大爆爆発による被害総額は、2,000万ドル(現在価値で3億9,000万ドル相当)と推定されており、自由の女神の損害は100,000ドル(同約200万ドル相当)とされ、それにはスカートとトーチの損害も含みます。自由の女神の腕の部分はそれ以来ずっと開かずの間となっているそうです。
この百年間で米国本土へ仕掛けられた攻撃で、成功したとされるのは、このブラック・トム大爆発と、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件、そして9.11アメリカ同時多発テロ事件の3つだけといわれています。
しかし、ブラック・トムと他の2件が異なるのは、テロリズムによるものではなく、主権国家の諜報員による破壊活動による仕業だったことです。だからといって許されるわけではありませんが、この爆破事件への関与も状況証拠しか集められなかったため、ニュルンベルク裁判でも立件対象にはならなかったようです。
日本においては、今も安保法案を巡って与野党の対立が続いていますが、仮にこうした悪法が通った場合、いずれまた日本も戦争への参加を余儀なくされ、その結果としてこうした事件に巻き込まれる、といったこともあるかもしれません。
そうならないことを祈るばかりです。