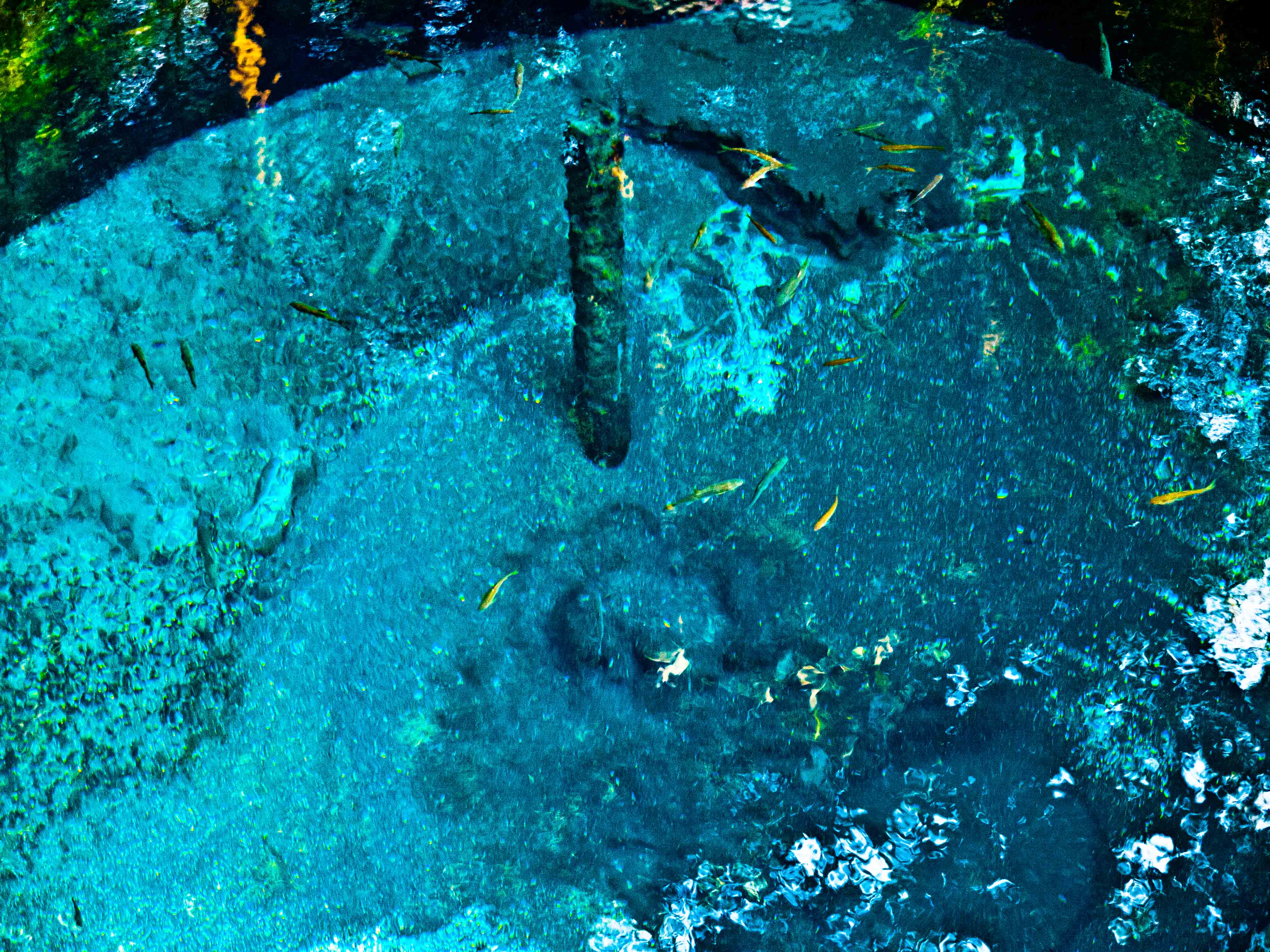ラジウムとポロニウム
1898年、マリーは、ピッチブレンドから新元素を取り出すため、ピエールが入手してくれた貴重な試料を乳棒と乳鉢ですり潰すという地味な作業を始めました。
当初は、マリーが始めたこの分析作業を傍観しているだけのピエールでしたが、やがては彼女の考察の正しさを確信するようになり、そのころ自分が取り組んでいた結晶に関する研究を中断してまで、彼女の仕事に加わるようになりました。
しかし、ピッチブレンドは複雑な化学組成を持つ混合鉱物であり、分離精製は非常に難しいものでした。しかもこの当時、かなり高価な鉱石であり、マリーとピエールが分析できたのはほんの少量の試料でしかありませんでした。
それでもと、二人がこの少ない試料で測定を続けたところ、ピッチブレンドに含まれるウランから、計算した放射線より少なくとも4倍もの線量を検出されました。このため、マリーはウランだけではなく、これとは異なる未知の放射性元素が含まれているのではないかと推論し、これを祖国ポーランドのラテン語形「Polonia」にちなんで、「ポロニウム」と名付けました。
さらに12月26日には、ポロニウムとは別の激しい放射線を検出する元素も含まれていることが判明し、こちらのほうは「ラジウム」と命名しました。ラジウムのほうは、放射線を出している元素であることから、ラテン語で放射を意味するradiusにちなんだといいます。
そして、早速二人は、このポロニウムとラジウムの発見を論文としてとりまとめ、発表します。しかし、夫妻の期待に反し、学会の反応は極めて冷淡でした。物理学者たちは、新元素といわれるこの元素の放射線が、どのような現象から生じているのか不明な状態では、元素とはいえないと言い、化学者たちは、新元素ならばその原子量が明らかでなければならないと主張したのです。
物理学者と化学者、その双方の賛同を得る唯一の方法。それは、不純物の含まれない、純粋な新元素の塊を抽出することでした。
マリーはそれに挑む決意をします。しかし、家計の苦しい中、高価なピッチブレンドをどうやって入手するかは大きな問題でした。
なぜ、ピッチブレドがそれほど高価だったのか。この当時の、ピッチブレンドの最たる使用方法、それはこの鉱物からウランを抽出し、このウランの酸化物や塩化物を化合することで、陶器、磁器の釉薬を作ることでした。
ウランから作った釉薬は、ほかの材料からは作りだせない鮮やかな色を出せるということで、とくに緑の蛍光を発する黄色のガラスや陶器、磁器の上薬として使われ、珍重されました。また、写真術で写真ネガやプリントにセピア色を出すためにも使用されました。
19世紀なかばには、黄色及びオレンジの化合物の大量生産工場が建設されるようになり、ガラス及び磁器への色付けの商業利用が活発化するなか、銀よりもピッチブランドのほうが入手しずらい、といわれるような時代でした。
それというのも、ピッチブランドが生産されるのは、イギリスのコーンウェル地方や、ポルトガル、米国コロラドなどのほんのわずかな地域だったためです。しかし、オーストリアのボヘミア地方では、これを上回る算出量があり、ピッチブランドはオーストリアの重要な輸出物でした。
マリーらは、当初、ウランを精製する前のピッチブランド原石を入手することばかり考えていましたが、やがて、ウラン塩を抽出した後の廃棄物ならば安価に入手できるかもしれないと気が付きました。そして主生産地であるボヘミアのザンクト・ヨアヒムスタール鉱山へ問い合わせたところ、なんと廃棄物となる鉱滓ならば無償で提供を受けられるという答えが返ってきたのです。
この朗報に二人は大喜びしました。ウランを取り出したあとの鉱滓の中には、ポロニウムやラジウムなどの元素がまだ残っている可能性があったからです。タダ同然で手に入る鉱滓なら、時間と手間さえかかれば、新元素を抽出できる可能性があります。
ところが、いくらタダで鉱滓が入手できるといっても、その運送費は自らが負担しなければならないことに二人は気がつきます。しかも鉱滓にわずかに含まれるポロニウムやラジウムを取り出すためには、おそらく膨大な量の鉱滓を入手しなければなりません。
仕方なく、運送費を負担し、鉱滓を山のように取り寄せますが、この費用負担はますます家計を圧迫する要因となりました。
比較的安価にピッチブランドを入手できるめどはついたものの、次に必要なものは、精製に必要な広い場所でした。ピエールがEPCIに掛け合った末、二人は建物を借りることができました。しかしそれは以前、医学部の解剖室に使われていた場所で、精製工場とは名ばかりの床板も無いただのだだっ広い小屋でした。それでもこの場所は、やがてキュリー夫妻が様々な輝かしい業績を生む舞台となっていったのです。
精製
こうして鉱滓を手に入れ、分析を始めた二人でしたが、ピッチブレンドは複雑な化学組成を持つ混合鉱物であり、分離精製は非常に難しいものでした。
しかし、試行錯誤の結果、やがて夫妻はラジウム塩を特殊な方法で結晶化させて取り出すという方法を思いつきました。しかし、その方法には過酷な肉体労働が伴いました。数キロ単位の鉱石くずを砕いてつぶし、これを大鍋や壷で煮沸したあと、攪拌することで溶解させます。そして沈殿・ろ過を繰り返すことでラジウム塩を含む溶液を分離し、それを凝縮することで結晶化させていくのです。
一度の行程で凝縮できる溶液は限られていたため、この行程は何度も何度も繰り返す必要があります。しかも、小屋には煙突も無く、大なべで鉱滓くずを煮るとき作業は屋外で行なわなければならず、雨の降る日は仕事も中断せざるをえません。
二人はこの作業とは平行して放射能の効果や定義に関する研究も行っており、そのための時間も割かなければなりません。やがて仕事を効率的にこなすため、夫婦それぞれの分担をするようになり、細かな研究をピエールが、精製作業をマリーが行うようになっていきました。
精製の作業は少しずつ進んでいましたが、しかし最初に手に入れた1トンを処理しても、試料として使えるような十分な結晶は得られませんでした。夫妻はピッチブランド鉱滓に含まれる新元素の含有率を1/100程度と考えていましたが、実際には約万分の1程度の含有量しかなく、有意な量を得るために、いったいあと何トン必要になるのかさえも予想できていませんでした。
実験にかかる経費の負担は容赦なく家計を圧迫したため、生活費を稼ぐためふたりとも講師のアルバイトなどを続けなければなりませんでしたが、このことにより十分に研究時間がとれないという悪循環を生み出していました。スイスのジュネーヴ大学から夫妻を好条件で教授に迎えたいという申し出も来ましたが、実験を中断しなくてはならないため、泣く泣く辞退しました。
こうした二人の窮状を知った、知人の数学者の骨折りで、ピエールはソルボンヌ大学の医学部の物理・化学・博物学課程教授に就任することができ、またマリーもセーブルの女子高等師範学校の嘱託教師となることができました。こうして家計は少し救われましたが、増え続ける鉱滓の購入費用やその他の実験費用を工面するためには焼け石に水でした。
青白き妖精
しかし、こうした苦闘の中、二人はポロニウムの純粋元素をようやく取り出すことに成功します。ポロニウムは医薬品として使われる元素のビスマス(元素番号83)に科学的性質が比較的近く、鉱滓の中でビスマスと似た性質の元素の抽出をしているうちに、比較的簡単にポロニウムにたどり着くことができました。
しかしラジウムの発見はポロニウムと違い、一筋縄ではいきませんでした。ポロニウムの場合のビスマスと同様に、化学的性質が近い元素にバリウムがありますが、鉱石中にはバリウムとラジウムの両方が含まれており、これを純粋分離することが困難だったのです。1898年の段階で二人は、もう少しでラジウムを取り出すことができる段階まで進みましたが、どうしても純粋な状態の抽出を行うことができませんでした。
劣悪な環境と過酷な作業、逼迫した家計を賄うための教職、そして研究と、二人にとって休息と呼べる時間はまったくなく、健康状態は最悪でした。ピエールは精製を一時中断すべきであると考え初めていましたが、マリーはあきらめませんでした。
1トンのピッチブレンドから分離精製できたラジウム塩化物はわずか、1/10グラムほどでしたが、次の1トンそして次の1トンと精製を重ねるうちに、放射性元素は着々と濃縮されていきます。
そしてある夜のこと、精製を続け、凝縮したラジウム塩化物をマリーが試験管から蒸発皿へ移したときのことです。蒸発皿が何やら、青白く光っているように見えたのです。最初は連日の疲れから、天上のランプの光に蒸発皿が反射しているのかと思いましたが、そのランプを消してみたところ、確かに蒸発皿全体が青白く光っているではありませんか!
後年、マリーはこのときの光を「青白い妖精のようだった」と語っています。こうして、1902年3月、マリーとピエールは世界で初めて、純粋なラジウムに限りなく近い濃縮試薬の抽出に成功しました。出来上がった試料のスペクトルを計ってみたところ、ラジウム固有のものであることも確認でき、暗い実験室の中で青白く光る純粋ラジウム塩の青い光を、二人は手をつないでいつまでも眺めていました。
二人がこの純粋ラジウム塩を得るまでに費やしたピッチブレンド鉱滓の量は11トンにも達しました。しかし、ラジウム抽出に至るまでの過酷な労働は、二人の体をむしばんでおり、ピエールはリウマチを悪化させ発作に苦しむようになり、マリーは神経を病んでしまい、睡眠時遊行症(夢遊病)で夜中に徘徊を繰り返すようになりました。
翌1903年には第二子を流産してしまうなど、ラジウム塩抽出成功の喜びとは裏腹に、マリーは悲しみにくれました。
しかし、こうした苦境の中でも二人は、1899年から1904年にかけて32もの研究発表を出し、それを読んだ研究者たちは、放射能や放射性元素に対するそれまでの認識を改めざるを得ないことを知ります。
他の多くの学者たちも放射能研究に取り組むようになり、放射性元素としては、同じ元素番号を持つ放射性元素であっても、原子の質量数が異なる「同位体元素(アイソトープ)があることなどが発見されました。また、ラジウムは元素でありながら、崩壊することによってヘリウムが発生することも確認されたことなどから、当時の概念であった「元素は不変」という考え方は変革に迫られ、このころから原子物理学は大きく飛躍していくようになります。
さらに、1900年にドイツの医学者ヴァルクホッフとギーゼルが、放射線が生物組織に影響を与えるという報告がなされました。早速ピエールがラジウムを自らの腕に貼り付けたところ、火傷のような損傷を確認できたため、友人の医学教授らと協同研究した結果、ラジウムには変質した細胞を破壊する効果があることが確認されました。
このことは、ラジウムを使って皮膚疾患や悪性腫瘍などが治療できる可能性を示唆したものでもあり、これは後にキュリー療法と呼ばれるようになります。こうしてラジウムは「妙薬」としても知られるようになります。
こうした事実が明らかになったことで、マリーはそのころ自分たちの研究を手伝ってくれるようになっていた他の研究所員らに対して、ラジウムなどの放射性物質を扱うときには、手袋での防護をするよう厳しく指導していました。しかし、当の本人は放射性物質を素手で扱う事が多く、防護対策はほとんど行いませんでした。このため、マリーの手はラジウム火傷の痕だらけで干しスモモのような皺が残っていたといいます。
新元素であるラジウムの利用は、医療現場だけにとどまらず、他の産業分野での有用性も次々取沙汰されるようになっていきました。産業技術への応用の際、ラジウムの精製法は特許に値するほど重要な発見でしたが、二人はこれを一般に公開し、特許の申請を出しませんでした。
ラジウムを広く社会一般で使ってもらうことが、科学の進歩につながると二人が確信していたためであり、窮乏生活を送りながらも無私の精神を貫いた二人の高い志は後世の人々によっても高く評価されました。
二人が特許を申請しなかったことで、他の科学者たちは何の妨げもなくラジウムを精製して使用することができたるようになり、また、フランスの実業家アルメ・ド・リールのように、民間人もラジウムの工業的生産に乗り出すことができるようになりました。
リールは高邁な精神を持つ夫妻を尊敬していたといい、その生産にあたって二人に協力を要請。そして共同で医療分野への応用研究も始めました。ラジウムは世界で最も高価な物質となりつつあり、マリーとピエールの二人にもようやく経済的に救われる時が訪れつつありました。
栄光の影に
ラジウムやポロニウムなどの放射性物質の研究は、そもそもマリーの博士号取得を目的に始められたものでした。しかし、ラジウム塩素の抽出に成功後、ふたりとも多忙のためなかその準備にとりかかることができませんでした。しかしそれでもようやく審査論文の提出を終え、論文審査を受けることができ、1903年6月、マリーは正式にパリ大学から理学博士の称号を受けることができました。
このころ、イギリスは他国にも増して二人の業績を最も高く評価しており、1903年6月、王立研究所は夫妻を正式にロンドンへ招待し、講演を依頼しました。ピエールの実験を交えた講演は喝采を浴び、に11月にはイギリスの王立協会からデービーメダル(化学の諸分野での重要な発見に贈られる賞)が授与されます。
そして1903年12月、スウェーデン王立科学アカデミーはピエールとマリーそしてアンリ・ベクレルの3人にノーベル物理学賞を授与すると発表しました。マリーは、女性初のノーベル賞を授与された人物となり、賞の授与ともに7万フランの賞金を得ることができ、この賞金は一家の深刻的な経済状態を救いました。
このノーベル賞の受賞は、一躍二人を有名人にしましたが、その結果として、数多くのメディアから取材や面会の依頼が殺到し、寄せられる大量の手紙の処理に追われるようになりました。自宅や研究所にまで踏み入ろうとするマスコミに辟易しながら毎日を送るようになり、このため二人の研究時間は奪われていきました。
1904年、パリ大学はピエールを物理学教授職に迎える打診を行います。実験室を用意する、しないで大学ともめましたが、結局議会がこの金を捻出するということで事態は落着。ピエールは晴れて大学教授となり、しかも自由に使える、きちんとした実験室を得ることになったのです。
この年、マリーは次女エーヴを産み、翌年の1905年には教職に復帰し、実験室に入ることもできるようになるなど、ようやく生活は落ち着いてきました。心に余裕ができると演劇鑑賞などにも出かけるようになり、パリに住む舞踏家のロイ・フラーや彫刻家のロダンなどの芸術家とも付き合うようになるなど、科学者以外の分野の文化人とも交流を持つ機会が増えました。
1906年に入り、ピエールは正式にパリ大学の教授となり、これと同時に得た新しい実験室で動き始めました。手狭で交通に不便な郊外にある実験室でしたが、助手と手伝いが大学から提供される上に、大学は実験主任として、マリーを指名し、給与も支払ってくれました。
マリーは、貧乏だった時代の職であるセーブル女子学校の教師をまだ続けており、ピエールも科学者そして大学教授としての様々な雑務に追われ、二人とも相変わらず多忙な日々を送っていました。
それは4月19日木曜日のことでした。雨模様の一日でしたが、ピエールはその日の様々な予定をこなし、郊外の実験室から自宅へ戻る途中でした。パリ郊外のデ・プレ地区は、その当時も美しい田舎町でしたが、そこにあるドフィーヌ通りは、馬車が頻繁に行き交う繁華街にありました。
ピエールが、この狭い道を横断しようとしていたときのことです。坂道であったこともあり、左手から急にスピードを上げて走ってきた荷馬車が急速に近づいてきました。連日の仕事で疲れていたのでしょうか、これに気が付かずに足を踏み出したとたん、荷馬車がピエールにぶつかってきました。
あっと思ったときには、荷馬車の車輪の下敷きになっており、御者があわてて馬の手綱を引いたときにはもう既にピエールの体はぴくりとも動きませんでした。
すぐに、たくさんの人が周りに集まってきましたが、その中の一人が、彼を有名な科学者であると気がつきます。すぐに医者が呼ばれましたが、そのときはもう既にピエールはこと切れていました。この男性から大学に電話連絡がなされ、パリ大学の学部長のジャン・ペランがキュリー家に向かいました。
ぺランがキュリー家でピエールの遺体にまみえたとき、マリーは自宅には不在でした。そして、夕方の午後6時ころ、長女のイレーヌを連れて帰宅し、玄関を入ったところでその事実を知らされ、蒼白になりました。冷たくなったピエールに面会したとき、マリーは暫くは誰の問いかけにも何の反応を示さなかったといいます。
ピエール47才。道半ばでの若き死でした。
この不慮の事故は世界中に報道されました。しかし、21日にピエールの生家で行われた葬儀は質素なものでした。マリーが大がかりな葬儀や弔辞、行列さえも断ったためです。マリーは感情を失った人形のように見えたそうで、この当時のマリーの日記には、ただ一言「同じ運命をくれる馬車はいないのだろうか」と書かれていました。