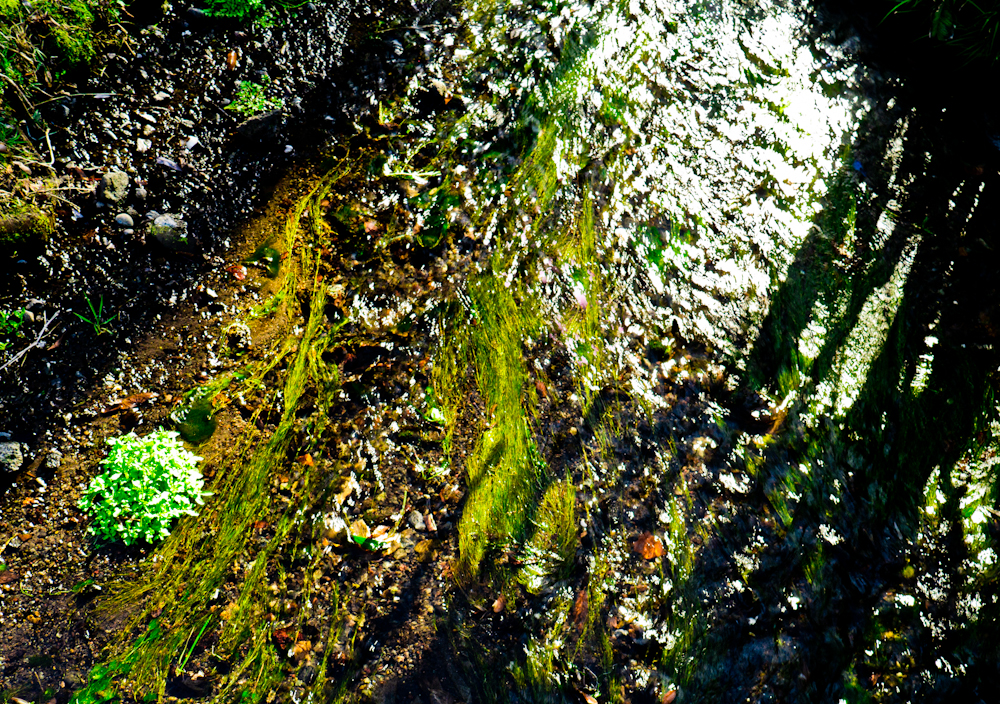さて、昨日の続きです。
芥川龍之介が「歯車」や「河童」といった破滅的な内容の作品を書いた晩年は、病に苦しんだ日々ではありましたが、そんな中、龍之介は文との間に三人の子供を設けています。
長男の比呂志を筆頭に、多加志、也寸志の三人がそれであり、ご存知のとおり、この兄弟のうちの比呂志は後年著名な演出家になり、三男の也寸志もまた有名な作曲家になりました。
次男の多加志は、三人のうち最も文学志向が強く、このため龍之介にもよく似ていると言われていたようで、長じてから京外国語学校(現東京外大)仏語部文科に進みましたが、残念ながら二次大戦の戦役にとられ、ビルマで戦死しました。
長男の比呂志は、俳優としても活躍した人で、舞台の他、ラジオドラマ・ナレーション・映画・テレビなどにも数多く出演。1963年、仲谷昇、小池朝雄、岸田今日子、神山繁らと共に文学座を脱退し、「現代演劇協会」を設立。協会附属の「劇団雲」でリーダーとして活動しました。
1966年にはNHK大河ドラマ「源義経」で源頼朝役も演じており、俳優業の傍ら、演出家としての才能も発揮し、1974年には「スカパンの悪だくみ」の演出で芸術選奨・文部大臣賞、泉鏡花の戯曲「海神別荘」の演出で文化庁芸術祭・優秀賞を受賞しています。
しかし、晩年には若い頃からの持病である肺結核が悪化していて入退院を繰り返し、1981年、療養中だった目黒区内の自宅にて死去。享年61歳という若さでした。
一方、三男の也寸志は、1947年に東京音楽学校本科を首席で卒業すると、すでに在学中に作曲していた「交響三章」などが着目され、すぐに作曲家として引っ張りだこになっていきました。快活で力強い作風と言われ、「交響三章」は特に人気のある代表作であり、このほかにも「交響管絃楽のための音楽」「絃楽のための三楽章」などの名作があります。
また映画音楽・放送音楽の分野でも「八甲田山」「八つ墓村」「赤穂浪士のテーマ」などの作曲をした人としてよく知られているとともに、童謡の分野でも「小鳥の歌」「こおろぎ」などの抒情あふれる曲をつくりました。そのほか、多くの学校の校歌や日産自動車の「世界の恋人」など、団体(企業等)のCMソングや社歌も手がけています。
也寸志はその生涯で3回結婚していますが、2度目の妻は女優の草笛光子です。最初の妻との間に生まれた長女・芥川麻実子はタレントとして活躍した後にメディアコーディネイターになりました。また、3度目の妻はエレクトーン演奏の名手といわれた江川真澄でしたが、彼女との間に生まれた息子・芥川貴之志は現在もグラフィックデザイナーとして活躍しています。
このように、龍之介の死後もそのDNAはその息子たちに受け継がれ、現在に至るまで脈々と生き続けています。
ちなみに、也寸志は、その生前、父・龍之介に対しては強い尊敬の念を抱いていたといいますが、しかし同時に有名人の息子であるがゆえに、ことあるごとにそのことを知人に引き合いに出され、苦しんだそうです。
「学校を卒業して社会に出た時には、ことある毎に「文豪の三男」などと紹介され、いい年をして、親父に手を引っぱられて歩いているような気恥ずかしさに、やり切れなかった」と語っています。
また、「父が死んだ年齢である三十六歳を越えていく時は、もっとやり切れなかった。毎日のように、畜生! 畜生! と心の中で叫んでいた。無論、自分が確立されていないおのれ自身への怒りであった」とも告白しており、父の死はその生涯に大きな影を落としていたようです。
その後も長く名作曲家として活躍しましたが、1989年、東京都中央区の国立がんセンターに入院中、肺癌のため逝去。享年63才。最後の言葉は「ブラームスの一番を聴かせてくれないか…あの曲の最後の音はどうなったかなあ」だったといいます。
これより2歳若くして逝った長男の比呂志よりもわずかばかり長く生きましたが、父の龍之介といいその息子といい、どうもあまり長生きはできない性質(たち)の人々のようです。
彼らの父の龍之介は、その後その名を文学界の「芥川賞」に残しましたが、その息子の也寸志もの音楽界での功績を記念して、1990年にはサントリー音楽財団により「芥川作曲賞」が創設されており、親子でこうした賞によりその名を歴史に刻んでいくことになりました。
また、也寸志の死の半年後、埼玉県松伏町には、彼が作曲した「エローラ交響曲」から名を取った「田園ホール・エローラ」も完成しています。
さて、龍之介のその後の話に戻りましょう。この三兄弟の末っ子の也寸志が生まれた1925年(大正14年)、龍之介は専修学校の文化学院文学部講師に就任していますが、その翌年には、胃潰瘍・神経衰弱・不眠症が高じ再び湯河原で療養しています。
一方、妻の文は自身の弟・塚本八洲が病を得たことから、その療養のために実家が鵠沼に持っていた別荘に移ることになり、彼を看病するためにここへ息子たちを連れ、弟とともに移住しました。
このため、一時は龍之介と別居状態となりましたが、その後龍之介も鵠沼にある旅館「東屋」という宿に滞在するようになり、その後、この東屋の北方にあり、同じ東屋の経営だった貸別荘を借りてここへ妻子を呼び寄せ、一緒に住まうようになります。
そしてこの鵠沼で開業医、富士山(ふじたかし)という医者の治療を受けつつ療養を続け、この間、晩年の作品群の多くを執筆しています。
ちなみに、この東屋という旅館は、数々の文士が逗留した宿として有名であり、明治期には、志賀直哉と武者小路実篤がここに滞在して「白樺」の発刊を相談し、これがやがて白樺派を生みだすことにつながっていきました。
龍之介が滞在したのちの1936年(昭和11年)にも、川端康成が滞在して少女小説「花のワルツ」を執筆していますが、その後日本が戦争に突入していく中で、旅館業も振るわず、1939年(昭和14年)に廃業。その建物も戦後まで残っていましたが、1957年以降解体され、今は記念碑しか残っていません。
この龍之介が滞在していた時代はまだ文士の溜り場といった雰囲気だったようで、堀辰雄、宇野浩二、小沢碧童、斎藤茂吉、土屋文明、恒藤恭、川端康成、菊池寛といった当時の蒼々たる文壇の名士たちがここを訪問しています。彼らとの交流のためにこの鵠沼で借りていた東屋の別荘もさながら龍之介サロンのようだったといいます。
しかし、ここには結局一年弱いただけで、元号が昭和に替わってからは、妻子をまず田端に返し、そのあと龍之介はしばらくここにとどまっていたようです。が、結局はその翌年の1927年(昭和2年)の正月には自身も田端に帰っています。
ただ、この鵠沼の家は4月ころまで借りていたといい、その後も時折訪れていたといいますから、龍之介はこの東屋という旅館をよほど気に入っていたのでしょう。
そんな折、1927年(昭和2年)の正月の余韻も冷めやらぬ頃、義兄の西川豊(次姉の夫)が突然、放火と保険金詐欺の嫌疑をかけられ、西川はこれを苦にして鉄道自殺します。
また、ちょうどこのころ、実家の田端では芥川家の当主であった異母弟も亡くなっており、このため龍之介は、西川の遺した借金やその家族、また養父母の面倒も見なければならなくなり、自身の持病に加えてまた心労を得ることとなります。
このころ知人に宛てた手紙には「又荷が一つ殖えたわけだ。神経衰弱治るの時なし。毎日いろいろな俗事に忙殺されている」とこぼしています。
さらに龍之介を悩ませたのは、このお膝元の田端で同居する芥川家の老人たちだったといいます。
龍之介の伝記には、死の直前、彼が自家の老人達のヒステリーに悩んでいたことが記されており、主治医の下島勲が龍之介の健康を心配していろいろ助言しているのに対し、彼は「こちらのことは御心配なく。それよりもどうか老人たちのヒステリーをお鎮め下さい」と手紙で頼んでいるそうです。
彼はまた別のところで、「老人のヒステリーに対抗するには、こちらもヒステリーになるがいいと教えられたので、今それを実践中です」というような内容の手紙も書いているといい、この老人たちの言動がかなり晩年の龍之介を苦しめていたことがわかります。
芥川は結婚後、養父母と伯母という三人の老人と同居していました。最初はそのことを取り立てて苦にはしていなかったようで、彼は一日中、二階に腰を据えて原稿を書くか、訪ねてくる編集者や友人と会うかしており、同じ家にいても老人達と言葉を交わすことがほとんどなかったようです。
ところが、義兄や異母弟が亡くなって、龍之介が芥川家一族の中心になると、彼は老人達と腹を割って話さなければならなくなり、このことは彼の持病をさらに悪化させる原因となっていきました。
このころから二階の書斎にこもりきりになり、あまり人とも合わなくなっていったといい、その理由は扶養する老人達の前に姿を現わせば、彼らとの接触は避けられないためだったようです。
さらにこの頃、龍之介はその秘書を勤めていた平松麻素子という女性と帝国ホテルで心中未遂事件を起こした、といわれています。
これは私としても初耳だったので、詳しく調べてみたのですが、どうも真相は明らかになっていないようです。ただ、推理作家の松本清張が「昭和史発掘」という著書の中で、この龍之介の自殺未遂について触れており、ここにはかなり核心に近い「らしい」ことが書いてあります。
実はこの「昭和史発掘」は私も大学時代に通読しており、国鉄総裁が轢死した下山事件の真相などのいろんな昭和の事件に触れており、なかなか面白い読みものでした。
その内容はほとんど忘れていましたが、この龍之介の項を書き始めたときにネットで色々調べていたら、この清張さんの著述に触れている方がいたので、それで私も松本さんがこのことを書いていたことをおぼろげに思い出しました。
このころ、妻の文は、持病に苦しむ夫が、老人たちとの軋轢からしばしば過激な言動も繰り返すようになっているのをたびたび耳にしています。そしてそれらの言動や、もめごとがあるたびの嘆息から、夫がもしかしたら自殺を計画しているのではないかと疑うようになっていたようです。
このため不安に襲われ、ときおり二階に駆け上がって夫の無事を確かめるようにもなっていたといいます。そして彼女は彼女なりに善後策を考え、もしかしたら、龍之介に文学のことが分かる女友達をあてがえば、彼の孤独感が解消するのではないかと考え、幼友達の「平松麻素子」に救いを求めました。
平松麻素子は文より2~3才年上で独身でした。父親は弁護士で裕福な暮らしをしていましたが、生まれつき病弱だったため、結婚もせずに弟妹の面倒を見ていたようであり、こういうか細い印象により、後年、実際に龍之介と心中を図ったと、書かれるようになったのかもしれません。
彼女は短歌を作るなどの文才もあり、芥川の作品もほとんど読んでいたといい、文から事情を聞いて、龍之介の話し相手になることを承知しました。文は、彼女が訪ねてくると二階の芥川の書斎に案内するようになり、その後麻素子は龍之介の書斎で彼と文学談義までするほど親しくなっていったといいます。
こうなるとはやり、男女の中のことでもあり、やがて龍之介と平松麻素子は、文に隠れて二人だけで外で会うようになります。恋愛関係にあったのではないかとも言われていますが、おそらく事実でしょう。
こうして龍之介は麻素子との逢う瀬を重ねてはいましたが、その関係はプラトニックのままだったとする説が強いようです。その理由は言うまでもなく、龍之介と彼女との交際を勧めたのはほかならぬ妻の文であり、その監視の目がいつもあったから、ということでしょう。
が無論、実際に龍之介が外出したあとの二人がどういう行動をしていたのかについては、想像でしか語ることはできません。
ところが、この二人の関係はこれだけでは終わらず、このころ既に精神を相当病んでいた龍之介は、あろうことか彼女を踏み台にして自殺を決行しようと考えるようになっていきました。つまり心中です。そしてある日彼女を連れだって散歩しているとき、一緒に死んでくれないかと切り出します。
もっとも、プライドの高い龍之介はその後に書いた、「或阿呆の一生」の中で、話を持ちかけたのは女の方からだと書いています。
しかし、麻素子が龍之介と心中する約束を交わした、というところまではどうやら事実のようです。そして、その場所を帝国ホテルとし、実行する日時も二人で決めました。
そして昭和2年の春、二人で決めた日に龍之介は家を出ました。文が、「お父さん、どこに行くんですか」と尋ねても何も答えないで出ていったそうで、胸騒ぎを感じた文は、近所に住む龍之介の有人で画家の小穴隆一の下宿に駆けつけ、このことを相談しました。
ところが、そうやって文が小穴と二人で話し合っているところに、なぜか意外にも平松麻素子がそこを訪れます。実は、彼女は龍之介との約束を破って帝国ホテルに行かなかったのですが、彼のことを見捨てることもできず、かといって龍之介との間が深くなっていたために文にも告げられず、龍之介の親友である小穴に相談にやってきたのでした。
夫の行方を知らないかと文に問い詰められた麻素子は、その面前では本当のことを言えません。文は「とにかく、芥川の行方を捜さなければならない」と言って二人を置いて出て行ってしまいますが、二人きりになると、麻素子はそれまで隠していた秘密を小穴に打ち明けます。
こうして、心中事件は発覚するところとなり、小穴は自宅に帰っていた文にこのことを告げ、さすがに麻素子は同伴しませんでしたが、小穴と文の二人は連れ立って龍之介の泊まっていた帝国ホテルにかけつけ、彼が借りていた一室を訪れました。
泊っている部屋のドアを叩くと、「お入り」と、大きな声で芥川が怒鳴り、中へ入ると龍之介はベッドの上にひとりで不貞腐れたような顔をして坐っていたそうです。
そして、「麻素子さんは死ぬのが怖くなったのだ。約束を破ったのは死ぬのが恐しくなったのだ」と、龍之介ベッドに仰向けになって、怒鳴るような、訴えるような調子で叫んだといいます。
平松麻素子が結局龍之介との心中に踏み切らなかったのは何故か、という疑問に対する答えとして、松本清張は龍之介が平松麻素子に逃げられたのは芥川の側に過信があったからだ、と書いています。
「芥川が平松麻素子と体の関係を持っていなかったことは、事実だと思われるが、肉体的交渉もない女が、自分と一緒に死んでくれると思いこんだところに芥川の甘さがあり、その甘さは自己の名声に対する過信から来ている」とも書いています。
つまり、大作家である自分が頼めば、女一人ぐらいは道連れにできるだろう、と龍之介が高をくくっていたということであり、確かに現代でも人気のあるミュージシャンに甘い声をかけられようものなら、心中までしてしまいそうな若い女性はゴロゴロいそうです。
が、結局のところ、平松麻素子はそれほど軽い女ではなかったということなのでしょう。むしろ心中してくれるだろうと信じ切っていた龍之介のほうがミーハーだったといえます。
この事件があってからは、当然のこと平松麻素子は芥川家に寄りつかないようになりました。一方の龍之介はこの一件を境にさらに自殺に対して一歩踏み込んだ姿勢を示すようになり、単独で自死を決行する決意を固めはじめたようです。
そして7月24日未明、「続西方の人」を書き上げた後、龍之介は斎藤茂吉からもらっていた致死量の睡眠薬を飲んで自殺した、とされています。が、松本清張によれば、これは睡眠薬ではなく青酸カリであり、これは誰あろう、心中事件を引き起こしたときにその相手であった平松麻素子が彼に与えたものだった、というのです……
この青酸カリ説を支持する人は多いようで、例えば後年の作家、山崎光夫は、芥川の主治医だった下島勲の日記などからもこの青酸カリによる服毒自殺説の可能性が高いと主張しています。
睡眠薬説のほうは、死の数日前に龍之介を訪ねた、同じ漱石門下で親友の内田百閒の証言によるもののようです。それによれば、龍之介はこの日にも大量の睡眠薬でべろべろになっていたそうで、起きたと思ったらまた眠っているという状態だったといいます。
既に自殺を決意し、体を睡眠薬に徐々に慣らしていたのだろう、というのが睡眠薬説を推する人達の言い分です。
また、龍之介は自殺の直前に身辺の者に自殺を仄めかす言動を多く残していたといい、実際には早期に発見されることを望んだ狂言自殺で、たまたま発見が遅れたために死亡したとする説もあります。青酸カリならば、死ぬのは確実ですが、睡眠薬であれば本当に死んでしまう前に人に発見してもらいやすくなるわけです。
また、死後に見つかり、旧友の久米正雄に宛てたとされる遺書「或旧友へ送る手記」の中では自殺の手段や場所について多少具体的に書かれています。
それには「僕はこの二年ばかりの間は死ぬことばかり考へつづけた。(中略)…僕は内心自殺することに定め、あらゆる機会を利用してこの薬品(カルモチン・睡眠薬の一種)を手に入れようとした」と書いてあります。
この記述を信頼すれば、やはり睡眠薬によって計画的に自殺を企てていたとも考えられるわけですが、睡眠薬を使おうと思ったけれども直前に気が変わったかもしれません。実在の平松麻素子という人物との関係も確かであり、このため、彼女が手渡したという青酸カリによる死亡説はいまだに消し去れない有力な説となっています。
平松麻素子がその後どういう人生を送ったかについては、ネットで調べた限りではよくわかりませんでした。が、青酸カリを手渡したなどと公表すれば、お縄になるのはみえていますから、その後そうしたことを自らが口にするはずはありません。
警察も青酸カリだったとすれば、当然その入手先を調べたでしょうが、仮にそうだったとしてもそうした調査情報を新聞などのメディアに公表するメリットは何もありません。
こうして睡眠薬説か青酸カリ説のどちらが本当かはいまだに不明のままであり、前述の息子二人もその後何も語っていません。おそらくは母の文からもその生前には何も知らされなかったのでしょう。
その後文は、1968年9月11日、調布市入間町の三男・也寸志邸にて心筋梗塞のため68歳で死去。
死後の1975年、筑摩書房から「追想芥川龍之介」が刊行されていますが、これは本人が書いたものではなく、中野妙子(ジャーナリスト?)という人が文にインタビューを行い、この時文の口から出たことばを取りまとめたもののようで、こうした見ず知らずの人に夫の死の真相を話すわけはなく、当然、その死についても何ら触れられていません。
龍之介はこうして36歳の若さで亡くなり、その人生の終焉がどんな形であったのかは今も闇の中です。が、その遺書としては、妻・文に宛てた手紙、菊池寛、小穴隆一に宛てた手紙があり、その中で龍之介が自殺の動機として記した「僕の将来に対する唯“ぼんやりした不安”」という言葉は、今も非常に有名です。
自殺直前の龍之介ののこうした厭世的な心境は「河童」を初めとする晩年の作品群のあちこちに表現されているようですが、この「ぼんやりした不安」というものが、果たして彼を死に追い込むほどの激しい不安であったのかどうかは、これらの作品を読み込むことでしか理解できないのかもしれません。
死の前日、芥川は近所に住む室生犀星を訪ねたそうですが、犀星は雑誌の取材のため上野に出かけており、留守でした。犀星は後年まで「もし私が外出しなかったら、芥川君の話を聞き、自殺を思いとどまらせたかった」と、悔やんでいたといいます。
龍之介は死の直前に
「橋の上ゆ胡瓜なくれは水ひびきすなはち見ゆる禿の頭」
と河童に関する作を残しています。これが、彼の命日を「河童忌」とするゆえんです。
死の8年後、親友で文藝春秋社主の菊池寛が、芥川の名を冠した新人文学賞「芥川龍之介賞」を設け、龍之介はこの世からいなくはなりましたが、その名を冠した芥川賞は現在に至るまでも最も有名な文学賞として受け継がれ続けています。
龍之介が亡くなったのは7月24日の未明だったそうですが、この日の朝、文夫人が亡くなった夫に対して「お父さん、良かったですね」と語りかけたという話が先述の「追想芥川龍之介」の中に書かれています。
この「良かったですね」は意味深なことばですが、素直に受け取れば、龍之介の生前の苦しみが、その死によってようやく払拭されたことに対する祝意でしょう。しかし、と同時に夫とともに苦しみ抜いた、自分自身へのねぎらいの言葉であったようにも思えます。
また、このとき文夫人は、夫の龍之介の「安らぎさえある顔」をみて、こういったといい、だとすれば、龍之介の死因は苦しみの伴う青酸カリではなく、やはり睡眠薬だったのかもしれません。
実際にはどんな表情だったのかは、ご本人が亡くなられていることでもあり、もうわかりませんが、この言葉が表すように、彼の苦しみを一番よく知り、また最も愛していたのは、親友までも愛人としてその夫に差し出した彼女であったことは間違いありません。
戒名は懿文院龍之介日崇居士。墓所は、東京都豊島区巣鴨の慈眼寺だそうです。河童忌の昨日はおそらくは多くのファンがこの墓前を訪れたことでしょう。
煙草が大好きで、1日に180本も吸っていたといいますから、きっと空の上から好きなタバコをくゆらせながら、彼らの姿を見ていたに違いありません……