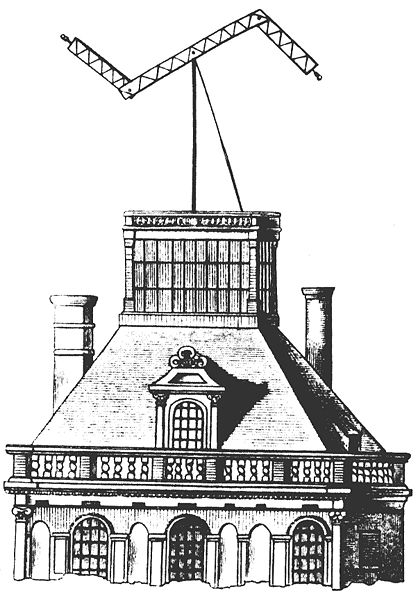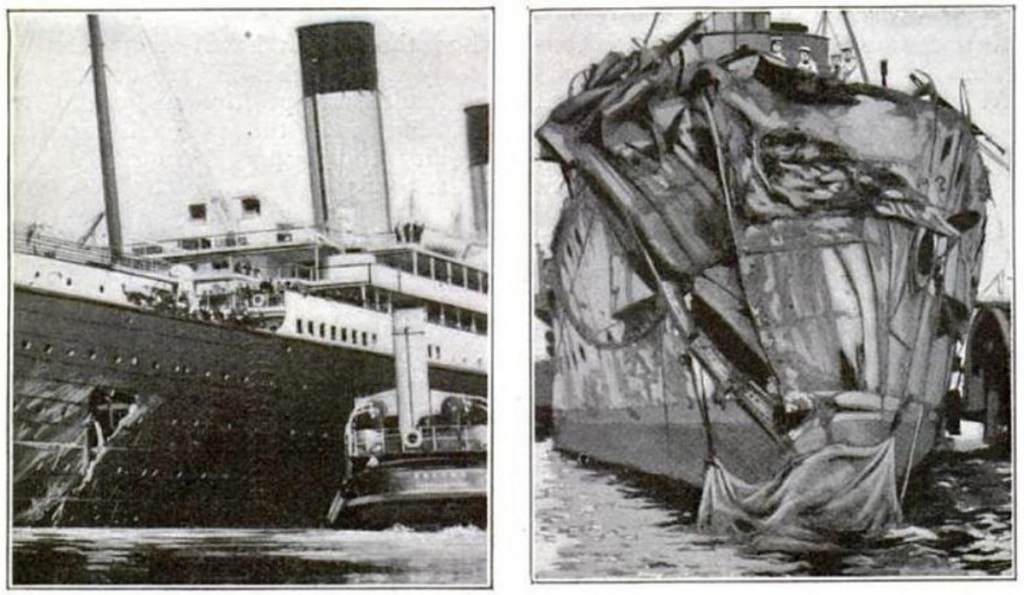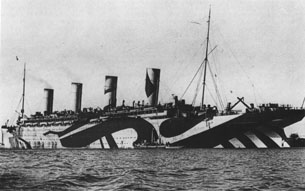一昨日、伊勢神宮の内宮で20年に一度の式年遷宮が行われ、テレビや新聞等でも大きくとりあげられました。
さらに先の5月には、島根の出雲大社でも60年に一度の遷宮(正確には修造遷宮)が行われており、今年は日本中が「遷宮フィーバー」で盛り上がった年でもあります。
伊勢神宮の遷宮は、明日5日に外宮の遷御(せんぎょ)も行われ終了しますが、巷ではさらに引き続きこのニュースで盛り上がるに違いありません。
ところで、この伊勢神宮というのを、「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」の2つのお宮の総称、と思っている人も多いようですが、「伊勢神宮」というのは、この二つを含め、紀州を中心に125も存在する関連神社の総称です。
内宮、外宮のほかに、14所の「別宮」、43所の「摂社」、24所の「末社」、42所の「所管社」があって、合計125社であり、これらは伊勢神宮のある伊勢市を中心とした周囲の4市2郡に位置しています。
これらの神社をすべて合わせた総敷地面積は、約5,500万平方メートルもあるそうで、これは東京の世田谷区の大きさにも匹敵します。
ただ、これらすべての遷宮をするとさすがに大変なので、引越しをするのは、この内宮と外宮のほかに、14の別宮と、宝殿、外幣殿、鳥居、御垣、御饌殿など計65棟の殿舎だけです。「だけ」、といってもかなりの規模なのですが、このほかにも、神官の装束や神宝も新調し、宇治橋等も造り替えられているそうです。
神宝(かむだから)というのは、元々は、剣、玉、鏡といった神器のことをさします。ただ、こうしたものを造りかえるのはさすがに大変なので、神様が使う日用品、すなわち手箱、碗、化粧用具、衣服といったより身近なものを新しくするようです。
「内宮」の正式名称は「皇大神宮(こうたいじんぐう)」、「外宮」の正式名称は「豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」で、それぞれに違う神様が祀られています。
内宮には、日本の総氏神である「天照大御神」が、外宮には五穀豊穣の神「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」がお祀りされていて、これは日本中の神社の中の神社、つまり、
“Mr.&Mrs 神社”ともいえる存在です。
式年遷宮が行われる理由は、ニュースなのでさんざん流されているのでご存知だと思いますが、これはこうした古式ゆかしい神殿や神宝の「造り」の技術を正しく伝承していくためだと言われています。
しかし、古くなった神殿を新しくしてお祭りすることで、祀られている神様も永遠に若々しく光り輝く存在であり続けてほしい、という思想も受け継がれてきており、これは「常若(とこわか)」という言葉で説明されています。20年ごとに生まれ変わることで、日本という国が新しい命を得て永遠に発展することを祈るわけです。
ちなみに今回の遷宮にかかる総工費は約570億円だそうで、これはこの付近だと小田原市や富士市などの中堅都市の年度予算に匹敵します。莫大な金額ではありますが、1300年も続く伝統を途絶えさせないためには必要な金額なのかもしれません。
そのお金をどう工面するかですが、当然税金などはあてにできません。なので、資金獲得のためには、神宮の信者を増やし、この信者さんたちからの寄付によってまかなうことになります。
仏教の場合はこの寄付のことをお布施といいますが、神道ではこれを「奉幣」といいます。
奉幣の対象となるのは、現在のようにお金ばかりではなく、古くは布や衣服、武具、神酒、神饌(供物)などでした。
そもそも伊勢神宮は、もともとは皇室の氏神として造られたものであるということはご存知だと思いますが、このため伊勢神宮では、当初は天皇以外の奉幣は禁止されていました。これを「私幣禁断」といいます。
中世になり、朝廷への、そして皇室とその氏神への崇拝から、伊勢神宮は日本全体の鎮守として全国の武士から崇敬されるようになり、神道においては最高神とされるようになりました。
こうして全国的にも知名度が高まったのは、外宮で度々行われていた一種の勉強会である「講」で奉じられた「伊勢神道(度会神道)」という教えのためでもあり、これは度重なる戦乱によって荒廃した古代の日本人にとっては心の拠り所となっていきました。
お陰参り
こうした戦乱は、やがて神宮側にも及ぶようになり、その神宮領が侵略され、経済的基盤を失ったため、式年遷宮が行えない時代もありました。このため、伊勢神宮としてはその存続の資金獲得のため、私幣禁断を捨て、神宮の信者を増やして彼らから奉幣を募るようになりました。
そのためには各地の講を組織する指導者が必要であり、このために「御師(おし)」という人達が台頭し始めます。
こうした御師たちの努力もあり、伊勢神宮の人気は高まる一方となり、近世になると、いわゆる「お伊勢参り」も流行するようになります。このお伊勢参りは、「おかげ様」を文字って「お蔭参り」ともいいます。
また、伊勢神宮そのものも、庶民らは親しみを込めて「お伊勢さん」と呼ぶようになり、江戸時代には、弥次さん、喜多さんの「東海道中膝栗毛」でも語られるように、多くの民衆が全国から参拝するようになりました。
このお蔭参りは、無論毎年のように行われていましたが、年によっては、その規模が数百万人にも及ぶこともあり、これはほぼ60年周期毎に発生し、こうした年は「おかげ年」と呼ばれていました。江戸時代には都合、5回ほど発生しています。
その5回とは、元和3年(1617年)、慶安年間(1648年~1652年)、宝永2年(1705年)、明和8年(1771年)、文政13年・天保元年(1830年)であり、これらの間隔はほぼ等間隔で60年周年です。
このうちの1705年(宝永2年)のお蔭参りはとくに大きく、これが本格的なお蔭参りの発端となったといわれており、「宝永のおかげ参り」とも呼ばれています。
主な発生地域は京都といわれ、たった2ヶ月間に330万~370万人もの人が伊勢神宮に参詣しています。このことを本居宣長が書き残しており、それによると、4月上旬から1日に平均で2~3千人が松阪を通ったといい、最高はなんと1日23万人もの人がここを通過したとか。
当時の日本総人口が2770万人ほどだったといいますから、全人口の一割以上の人がお伊勢参りをしたことになります。
明和8年(1771年)のお陰参りの参拝者数も比較的多く、このときの主な発生地域は山城の宇治でしたが、およそ200万人もの参詣者が伊勢に殺到しました。このときには、宇治から女・子供ばかりの集団の参加も多かったといい、彼女たちは仕事場であった宇治の茶山から無断で仕事を離れ、着の身着のままやってきたといいます。
このときのピーク時には、地元松坂では自分の家から道路を横切って向かいの家に行くことすら困難なほど大量の参詣者が町中を通ったといい、参詣者らは口々に「おかげでさ、ぬけたとさ」と囃しながら歩いていったそうです。
集団ごとに幟を立てる者も多く、最初はこの幟に出身地や参加者を書いていただけでしたが、段々とこれがエスカレートして滑稽なものや卑猥なものを描いたものすら増えてきました。
「おかげでさ、ぬけたとさ」というお囃子も、これにつれて卑猥なものに変わっていったそうで、これを若い人達だけでなく、老人や女性たちも口にするようになり、文字通り老若男女がこれを声高に叫ぶようにして通っていくさまは、滑稽を通り越してちょっと不気味にさえ見えたことでしょう。
このとき、この人出による経済効果もまた大きく、人々が通る街道沿いの物価はかなり高騰したそうで、白米1升が50文が相場のこの時代に、これが4月18日には58文に上昇し、5月19日には66文、6月19日には70文まではね上がったそうです。
お伊勢参りの必需品でもあった、わらじの値段も高騰し、5月3日で8文だったものが、5月7日には13~15文になり、5月9日には18~24文に急上昇しました。
このときは、街道沿いの富豪による「施行」も盛んに行なわれたといい、これが市中への大量の金の流通を促し物価が上昇したわけですが、そのおかげで無一文で出かけた子供が、逆に銀を貰って帰ってきたといった事もあったそうです。
初めは与える方も宗教的な思いもあって寄付をしていたようですが、さらには徐々にもらう方ももらって当然と考えるようになり、感謝もしなくなって中にはただ金をもらう目的で参詣に加わる者も出てきたといいます。
そして、三度目のピークの1830年(文政13年/天保元年)の「文政のお蔭参りでは」この過去の2回を上回る最大のフィーバーが起き、このときはたった3箇月の間で、約430万人もの人が伊勢に押し掛けました。
このときには既に過去の経験から、人々は60年周期の「おかげ年」を意識していたといい、それがこの騒動を後押しした形となりました。それにしてもこの当時の日本総人口は約3200万人ほどだったといいますから、全人口の13%もの人が殺到したことになります。
現在の日本ならば1600万人以上に匹敵しますから、これは東京と名古屋を合わせた人口にほぼ等しいことになります。すごいことです。
この文政のお蔭参りの特徴としては、大商人がこの参詣に賛助したことで、彼らは参詣者に対して店舗や屋敷を解放し、弁当・草鞋の配布を行ったそうです。
発生地は、四国の阿波が中心だったようで、その伝播地域は、明和のときよりも狭かったようですが、参加人数は逆に大幅に増えました。
前回の明和8年のときのフィーバーでも幟を立てたり、卑猥なことばを口にしながら行進するというヘンなことが流行りましたが、今回の参拝者たちは、なぜか参詣するときに、手に手にひしゃくを持って行き、しかも伊勢神宮の外宮の北門にこれを置いていくということが流行ったそうです。
これは、巡礼の際に柄杓を持って出かけるという風習がこの当時の阿波にはあり、阿波の人達が始めたことを、ほかの地域の人達も真似るようになったためのようです。
このときのお蔭参りによる経済効果も大きく、その額はおよそ86万両以上だったといわれています。これは現在の貨幣価値に換算すると200億円近い数字になります。このときも著しい物価上昇が起こっており、大坂で13文のわらじが200文に、京都で16文のひしゃくが300文に値上がりしたと記録されています。
以後、幕末に至るまでこれほど大きなお蔭参りは発生していませんが、1867年(慶応3年)には、有名な「ええじゃないか」が起こっています。
これは、近畿、四国、東海地方などで発生した騒動で、「天から御札(神符)が降ってくる、これは慶事の前触れだ」という話が広まるとともに、民衆たちが仮装するなどして囃子言葉の「ええじゃないか」等を連呼しながら集団で町々を巡って熱狂的に踊るというものでした。
人々が向かう先はとくにお伊勢さんとは限らなかったため、歴史的にはお蔭参りとは考えられていませんが、それまでのお蔭参りの影響を受けていることは確かのようです。
なお、近畿や四国などの西日本圏では、ええじゃないか、という掛け声が見られたものの、東海地方ではそうした掛け声はなく、「御札降り」を巡って民衆が踊り狂っただけでした。
こうした、江戸時代に流行したお蔭参りの最大の特徴としては、奉公人などが主人に無断で参詣する、といった一種の「掟破り」が横行したことであり、このほか子供であっても親に無断で参詣したというケースも多かったようです。
このため、お蔭参りは「抜け参り」とも呼ばれ、子供であっても旅ができたのは、大金を持たなくても信心の旅ということで沿道の施しをうけることができたためでした。
伊勢神宮へは、江戸からは片道15日間、大阪からでも5日間、名古屋からでも3日間かかり、しかも東北や九州からも参宮者があり、無論彼らは歩いて参拝しました。
岩手の釜石からは徒歩で100日もかかったと言われており、そこまでして全国的にお蔭参りが流行ったのは、伊勢神宮が、天照大神の神社として全国に公家・寺家・武家が加持祈祷を行っていたためです。
前述したとおり、中世の伊勢神宮では、戦乱の影響で領地を荒らされ、式年遷宮が行えないほど荒廃しましたが、その伊勢神宮を建て直すため、もともとは神宮で祭司を執り行っていた御師が活躍しました。
御師たちは、外宮に祀られていた「豊受大御神」を全国にアピールし、伊勢へ足を運んでもらえるようにするため、神宮の「伊勢暦」を各地の農民にタダで配ったといいます。
度重なる戦乱によって現世に失望していた人達は、はじめのころは来世の幸福を願って近所の寺院へばかり巡礼していましたが、やがてこれらの御師たちの活躍によって「神社」が強烈にアピールされるようになり、とくにその総本山である伊勢神宮への注目度がアップしました。
また、秀吉によって天下が統一されると街道の関所なども撤廃されたことから、参詣への障害が取り除かれ、他国の神社仏閣への巡礼も可能となり、中でも農民たちに配られていた伊勢暦の出所である伊勢神宮まで足を延ばす人も増えました。
さらに江戸時代になると、五街道を初めとする交通網が発達し、この参詣はさらに以前より容易となります。
そして世の中が落ち着いてきたため、巡礼の目的も来世の救済から現世利益が中心となり、伊勢への参拝の目的には観光も含まれるようになります。
加えて、米の品種改良や農業技術の進歩に伴い農作物の収穫量が増え、農民でも現金収入を得ることが容易になり、商品経済の発達により現代の旅行ガイドブックや旅行記に相当する本も発売されるようになりました。
当時、幕府は庶民の移動、特に農民の移動には厳しい制限を課していましたが、伊勢神宮参詣に関してはほとんどが許される風潮がありました。特に商家の間では、伊勢神宮に祭られている天照大神は商売繁盛の守り神でもあったため、子供や奉公人が伊勢神宮参詣の旅をしたいと言い出した場合には、親や主人はこれを止めてはならないとされていました。
また、たとえ親や主人に無断でこっそり旅に出ても、伊勢神宮参詣をしてきた証拠の品物であるお守りやお札などを持ち帰れば、おとがめは受けないことになっていました。
庶民の移動には厳しい制限があったといっても、伊勢神宮参詣の名目で通行手形さえ発行してもらえば、実質的にはどの道を通ってどこへ旅をしてもあまり問題はなく、参詣をすませた後には京や大坂などの見物を楽しむ者も多かったといいます。
ただ、このお伊勢参りは本州、四国、九州などのおおむね全域に広がりましたが、北陸などでは広まりにくかった傾向があります。これはこの地では真宗がさかんであり、仏教徒が神宗の風習であるお伊勢参りに出かけることがはばかられたためです。
このため、巡礼を拒んだ真宗教徒が神罰を受けたといった話がこの地には多く残っており、それらの中で一番多いのは、「おふだふり」です。村の家々に神宮大麻と呼ばれるお札が天から降ってきたといい、これは伊勢信仰を民衆に布教した御師たちが、真宗門徒をけん制する目的でばら撒いたものだと考えられています。
しかし、全国的にみれば北陸のようなケースはむしろ稀であり、他国の庶民にとってはたとえ仏教徒であっても伊勢神宮参詣は一生に一度とも言える大きな夢でした。
お伊勢講
それにしても、遠路はるばる伊勢まで出かけるのには、徒歩とはいえその旅費は相当な負担であったはずです。無論、沿道からの施しもあったでしょうが、お伊勢参りする人の全部が全部をまかなうことはできなかったはずであり、一般人の日常生活ではそれだけの大金を用意するのはかなりの困難だったと思われます。
いったいどうやってそのお金を工面したのでしょうか。
ここで考え出されたのが「お伊勢講」という仕組みであり、この講には次のようなしくみがありました。
まず、「講」の所属者は定期的に集まってお金を出し合います。そして長い間には、それらのお金の合計は、伊勢に一人分を派遣することができるほどの旅費として貯まります。
こうして一人もしくは複数の人が旅行できるほどの金額が貯まったら、その「講」の中で誰が代表者となって伊勢に行くかを「くじ引き」で決めます。
ただ、何度もこのくじ引きに参加すると、複数回伊勢に行くことができる人ができてしまうため、一度このくじに当たった人は、次回からはくじを引けなくなるようにしました。こうして、「講」の所属者は順番にこのくじに当たることとなり、全員がいつかはお伊勢参りが当たるように工夫がなされていたわけです。
くじ引きの結果、選ばれた者は「講」の代表者として伊勢へ旅立つことになります。その旅の時期は、農閑期が多かったようです。また、「講」の代表者は道中の安全のために2~3人程度のグループで行くのが通常でした。
出発にあたっては盛大な見送りの儀式が行われました。また地元においても道中の安全が祈願されます。参拝者は道中観光しつつ、伊勢では代参者として皆の事を祈り、土産として御祓いや新品種の農作物の種、松阪や京都の織物などの伊勢近隣や道中の名産品や最新の物産を購入して帰ります。
この物産品としては、長い道中に邪魔にならないよう、軽くてかさばらず、壊れないものがよく買われたといいます。
無事に帰ると、講をあげて帰還の祝いが行われ、その席でお土産を渡してみんなで盛り上がります。規模にもよりますが講に集まる人の数には限りがあり、貯まるお金にも限度があったでしょうから、そうそう度々あるお祝いではなかったでしょう。しかし、それだけに、さぞかし賑やかなお祝いだったに違いありません。
このように、江戸時代の人々が貧しくとも一生に一度は旅行できたのは、こうした「講」の仕組みによるところが大きかったわけです。
またこの「お伊勢講」は平時においては、神社の氏子の協同体としても役立っていました。お伊勢様に近い、畿内では室町中期ごろから普通に見られた集いだったようですが、全国的になったのは、街道が整備され、日本中が安全になった江戸以降からのことのようです。
一方では、「お伊勢講」が無かった地域でも、周囲からの餞別(せんべつ)を集める、という形で旅費を集めるということが流行っていたようです。
無論、タダで餞別を貰うのは心苦しいことですから、手ぶらで帰ってくる事がはばかられ、この場合には、それ相応のお土産を持って帰ることが必須でした。しかし、これにより、講だけでなく、講に入っていない一般人もお伊勢様に行くことができ、これがときにブームとなると、60周年に一度という大規模な「お蔭年」が発生したのでした。
また、お蔭参りの実施は、この当時、最新情報の発信地であったお伊勢さんで知識や技術、流行などを知りことにもつながり、これを持ち帰ることは地域にとって大きなメリットとなり、また本人にとっても見聞を広げるために大いに役立ちました。
お蔭参りから帰ってきた者によって、最新のファッション、といってもこの時代のことですから、最新の織物の柄などが伝えられ、ほかにも最新の農具や、新しい品種の農作物のタネや苗がもたらされました。とくに、伊勢神宮の神田には全国から稲穂の種が集まり、参宮した農民は品種改良された新種の種を持ち帰ることができました。
箕(みの)は、脱穀などで不要な小片を吹き飛ばす平坦なバスケット状の選別用農具ですが、これに代わって、手動式風車でおこした風で籾を選別する「唐箕」という器械が全国的に広まったのもこのお伊勢参りのお陰だといわれています。このほかにも、音楽や芸能情報も伝えられ、「伊勢音頭」に起源を持つ歌舞も各地に広まりました。
御師の活躍
こうしたお伊勢講を広めるのにとくに活躍したのは、前述の御師たちです。御師は当初、数名ずつのグループに分かれて各地に散らばり、農村部で伊勢暦を配ったり、豊作祈願を行ったりして、その年に収穫された米を初穂料として受け取る事だけで生計を立てていました。
江戸時代も中頃になると、農業技術の進歩により、農家の中に現金収入を得られる者が増え、単にお伊勢参りに出かけるだけでなく、これを機会として新たな知識や見聞、物品を求めて旅をしようと思い立つ者が現れるようになりました。
しかし、農民の移動に規制があった江戸時代に旅をするにはそれなりの理由が必要であり、その口実としては、「伊勢神宮参詣」というのは非常にもっともらしい名目でした。
当時、他藩の領地を通るために必要不可欠な通行手形の発行には厳しい制限がありましたが、伊勢神宮参詣を目的とする旅についてはほぼ無条件で通行手形を発行してもらえたのです。
ちなみにこの当時、伊勢神宮参拝だけでなく、善光寺参詣や日光東照宮参詣など、寺社参詣目的の旅についてはおおむね通行手形の発行が認められていました。
通行手形の発行は、在住地の町役人・村役人など集落の代表者または菩提寺に申請していましたが、これらの中でも伊勢神宮参拝を口実にした人がとくに多かったのは、伊勢講の御師たちが各地の農民に対して熱心な伊勢神宮参詣の勧誘活動を行っていたことと無関係ではありません。
このため、伊勢に向かい、伊勢神宮でお参りした人達の多くは、この伊勢滞在時にはたいてい、自分達の集落を担当している御師のお世話になっていました。御師の中には伊勢参拝に来る人をもてなすため、自分の家で宿屋を経営している人も多かったといいます。
これは、今年世界遺産になった富士山を信仰する「富士講」の御師たちの家が宿屋も兼ねていたことと同じです。この富士講の御師たちも自宅を講の人達に提供しており、現在まで残されたそれらの住宅のうちの「旧外川家」や「小佐野家住宅」が、今回の世界遺産登録ではその対象となりました。
こうした御師の宿屋では、盛装した御師によって豪華な食器に載った伊勢や松坂の山海の珍味などの豪勢な料理や歌舞でもてなし、農民が住んでいる所では使ったことがないような絹の布団に寝かせる、など、参拝者を飽きさせないもてなしを行ったといいます。
また、伊勢神宮や伊勢観光のガイドも勤め、参拝の作法を教えたり、伊勢の名所や歓楽街を案内して回りました。この時には、豊受大御神が祀られている外宮を先に参拝し天照大御神が祀られている本殿の内宮へ向かうしきたりだったといい、こうした作法をとくに「外宮先祭」と呼んでいたそうです。
こうして、最初は豊作祈願に対する対価や初穂料だけで生計を立てていた御師たちは、宿屋の主あるいは観光ガイドとしての収入を増やし、かなり裕福な暮らしをするものも増えていきました。
無尽講から現代へ
こうした御師たちによって支えられていたお伊勢講は、江戸時代が過ぎてもその仕組みが残り、これは「無尽講」という名称に変わりました。
しかし戦後は講を賭博行為とみなしたGHQにより、その多くは解散させられました。とはいえ、地域によってはそれまでと同様の活動を続けていた伊勢講もあり、伊勢神宮参拝は数年に一度行うのみとして、簡素な宴席のみを毎年行う習慣が残存しながら、その組織を維持している講も多かったようです。
一方のお伊勢参りに関しては、民衆の神宮への参拝熱は冷めてしまっており、今ではもうお伊勢参りに行くことが一生一代の大事というような風潮はありません。
これは明治に入り、明治天皇が伊勢神宮へ行幸したのをきっかけに伊勢神宮の性質が変容し、大昔の「私幣禁断」の時代にさえ遡るような風潮が出てきたためであり、さらには明治政府が御師の活動を禁じたためでもあります。
このようにお伊勢参りが衰退する一方で無尽講だけは根強く生き残るかたちとなり、明治時代のおわりごろにはまだ、大規模で営業を目的とする無尽業者がまだたくさんありました。
中には会社組織として営業無尽をするものも現われ、これらの事業者には脆弱な経営、詐欺的経営や利用者に不利な契約をさせる者も出てきました。
が、当時は、これを規制する法令がなかったため、大正になってから1915年(大正4年)にはこれを取り締まる旧「無尽業法」が制定され、こうした業者は免許制となり、悪質業者は排除されていきました(現在の「無尽業法」は1931年に改めて制定)。
ただ、この法律は住民や職場などで、業者を関与させずに無尽をする行為を禁止するものではなかったので、その後も裏社会では無尽は続けられ、現在に至っています。このことは後述します。
こうして一応法律ができ、取締りは厳しくなったものの、戦前には、世界恐慌が起こったことなどから、こうした無尽会社の勢いが復活してかなり発展した時代もありました。銀行に相当するほどの規模を持つものまで現れ、やがてこの当時の日本の経済を担う金融機関の一つとなっていきました。
しかし、太平洋戦争終結後、GHQは、無尽を賭博的でギャンブル性の強いものであると見ており、これを廃絶しようとしました。ところが、戦災復興のために各方面から無尽会社を残したいとの声が政治家の間からあがるようになり、GHQと対立し始めました。
このため、政府は当時の銀行並の業務を可能としつつも、無尽の取扱が可能とし、そのかわりこれを制度・監督上で厳しく制御できる金融機関制度を企画し、その規模も比較的小さいものに限定したものだけを設立可能としました。
こうして1951年(昭和26年)に誕生したのが、「相互銀行法」です。そしてこの法律を受け、現在も残る「日本住宅無尽株式会社」の一社を除く、無尽会社の全社が「相互銀行」へと転換しました。
ちなみに、日本住宅無尽株式会社というのは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県を対象に土地や建物の給付を行っている会社です。現在は三菱東京UFJ銀行系列の会社として知られていますが、「無尽」の名前を残しているのは全国広しといえども、ここだけです。
このように、かつて我々が「下町の金融機関」として親しんでいた「相互銀行」とは、実はその歴史を遡れば伊勢神宮にお参りする人々が作った「お伊勢講」の名残だったというわけです。
無論、相互銀行と呼ばれていたものがすべてお伊勢講の名残である無尽会社の流れを汲むものであったかといえばそうではありません。
相互銀行法の成立に伴い、新たに相互銀行として設立された株式会社も含まれており、例えば現在の神奈川銀行がそうであり、かつて長野相互銀行と呼ばれていた現長野銀行、そして、りそな銀行もまたその当時は三栄相互銀行と言っていました。
こうした相互銀行は、主に中小企業などを対象にしていて、無尽から発展した「相互掛金」を主な商品として取り扱うことができました。また、長い間一社当たりの営業範囲が、ほぼ一都道府県内に限定されていました。
しかし、その後、「金融機関の合併及び転換に関する法律」が成立し、その後ほとんど全ての相互銀行が普通銀行に転換し、現在では「第二地方銀行」と呼ばれるようになりました。
ただ、一部の相互銀行は既存普通銀行へ吸収合併されており、例えばかつて日本本相互銀行と呼ばれていた銀行は、このとき太陽銀行へと名前を変えており、これはその後太陽神戸銀行~太陽神戸三井銀行~さくら銀行を経て、現在の三井住友銀行となっています。
そして、最後の1行であった東邦相互銀行が1992年4月1日に伊予銀行へと吸収合併されたことで消滅し、その直後に相互銀行法も廃止され、相互銀行は法的にも消滅した企業形態となりました。
こうして、かつての無尽講の名残であった相互銀行は完全に消滅し、現在も昔のような賭博性の強い商品を扱っている銀行は皆無となりました。その業務はこれより大規模な普通銀行と変わりはありません。その多くはまっとうな商売をしており、世間の批判を浴びるような銀行はそう多くはないでしょう。
一方では、こうしたまっとうな組織に形を変えた銀行を横目でみつつ、21世紀となった現在でも、日本各地に、「無尽」の名をそのままとし、あるいはその名を「頼母子」とか「模合」に変えた非合法の小さな会や組織が存在しています。
これらはとくに農村・漁村地域に多いそうで、これらの組織では、メンバーが毎月金を出し合い、積み立てられた金で宴会や旅行を催す場合もあれば、くじに当たった者が金額を総取りする形態のものもあるといいます。
多くは実質的な目的よりも職場や友人、地縁的な付き合いの延長としての色彩が強く、中には一人で複数の無尽に入っている人もいるそうで、とくに沖縄県では県民の過半数が参加していると言われるほか、九州各地や山梨県、福島県会津地方などでもよく行われているといいます。
民間においては、現在でも親しい仲などが集まり小規模で行われていて、近所付き合いや職場での無尽、同窓会内で行われる無尽などもあります。
毎月飲み会を主催する「飲み無尽」や定期的な親睦旅行を目的とした無尽など、本来の金融以外の目的で行われているものも多いそうで、そうしたものは一見、ご近所のご老人の寄合いとあまり変わりがありません。
甲府市にはいまだに「無尽会承ります」などの看板が掲げられ、まるで老人介護サービスのような無尽向けサービスまで行っているところもあるそうです。
これらについては、ご近所づきあいの域を出ないと思われ、多少の賭博性があるからといって、そうそう目くじらを立てる必要もないかもしれません。
しかし、同じ山梨県では「地縁血縁選挙」が今もさかんであり、昨年の衆議院議員総選挙で当選した、同県選出のある女性代議士さんの最大支持基盤は無尽であると言われています(現在は、自民党山梨県第1選挙区支部長)。
会費の扱いなど政治資金規正法上グレーな部分が多く、政治と無尽の関係が近年は問題視されているそうで、本当だとするとあまり好ましいことではありません。
とはいえ、「無尽」の行為自体に関する法律は現在までいまだに存在しません。このため、例えば石川県加賀市の特に山中温泉地区、山代温泉地区では預金講(「よきんこ」と呼ばれる)という無尽が今も盛んだそうで、これは見方を変えれば一種の消費者金融です。
この預金講がそうだとはいいませんが、その他の無尽の中には金融機関から融資を受けられなかった社会的マイノリティー層に今も利用されている民間金融もあり、ときにこれらは暴力団などの犯罪組織とリンクする可能性もあります。
時々街中の看板で「ローンが借りれなかった人」向けの融資を語る看板をみかけることがありますが、こうした融資金の出所はこのような民間無尽にプールされたお金であることも多いようです。
一方では、こうした金が町内会や商店会などで運用される場合もあるそうで、これは平時には宴会、旅行目的の会と称してお金を集めており、メンバー本人あるいはその身内に不幸があった場合は葬儀を業者に頼らず、預金講仲間が取り仕切ります。
こうした風習は、1990年代までは地域の「常識」であったようですが、現在では地区の高齢化率の高さと地区住民の多くが従事する地場産業の疲弊ゆえにこうした葬儀の際の互助組織という役割は廃れつつあります。
とはいえ、地域の人々のためとはいえ、現在においてもこうしたグレーな金が巷で流通しているという現実をみると、いかにも日本ではまだまだ昔ながらのムラ社会続いているのだなと思ってしまいます。
ちなみに、無尽講の無尽は、「無尽蔵」に由来します。もともとは、中国唐代に長安にあった「無尽蔵院」という名前の寺院の名称であり、ここでは民衆から集められた財貨が、広く中国全土の寺院の修築に供されたそうです。
その後この無尽蔵院は、唐の時代の玄宗皇帝の勅命によって破壊されましたが、この「無尽」という考え方はその他の仏教宗派に広まって、お布施等で集められた財産を広く民間に貸し出して利潤を得るシステムとなりました。
これが、日本でも大勢で小額の金銭を出し合い、必要な時やくじ引き順で一定量の金銭を構成員各員が受け取る無尽、無尽講の用語として使われることになったわけですが、それ以前の歴史としては、これまで述べてきたようにその背景にお伊勢講があったわけです。
このように、仏の世界では無尽蔵であったはずの功徳を施すはずのシステムは、いまや神式のしきたりであった伊勢講をいわば乗っ取るような形で取って代わり、現代社会に至るまでにグレーな金融システムに変化し、今の日本社会にも大きな影響を与えています。
戦前の日本で発達した悪しき金融システムの名残ではありますが、だからといって、その前身であったお伊勢講もまた古き時代の悪しき風習だったかといえばそうではなく、ましてやこ今行われようとしている伊勢神宮の式年遷宮の価値を卑しめるものでもありません。
これはこれ、日本の伝統を守るよき習慣としてこれからも続けていってほしいものです。
次の20年後には私ももう、70ウン才です。多分まだ生きているとは思うので、次回の遷宮はぜひ見物に行きたいものです。
皆さんもご一緒にいかがでしょうか。