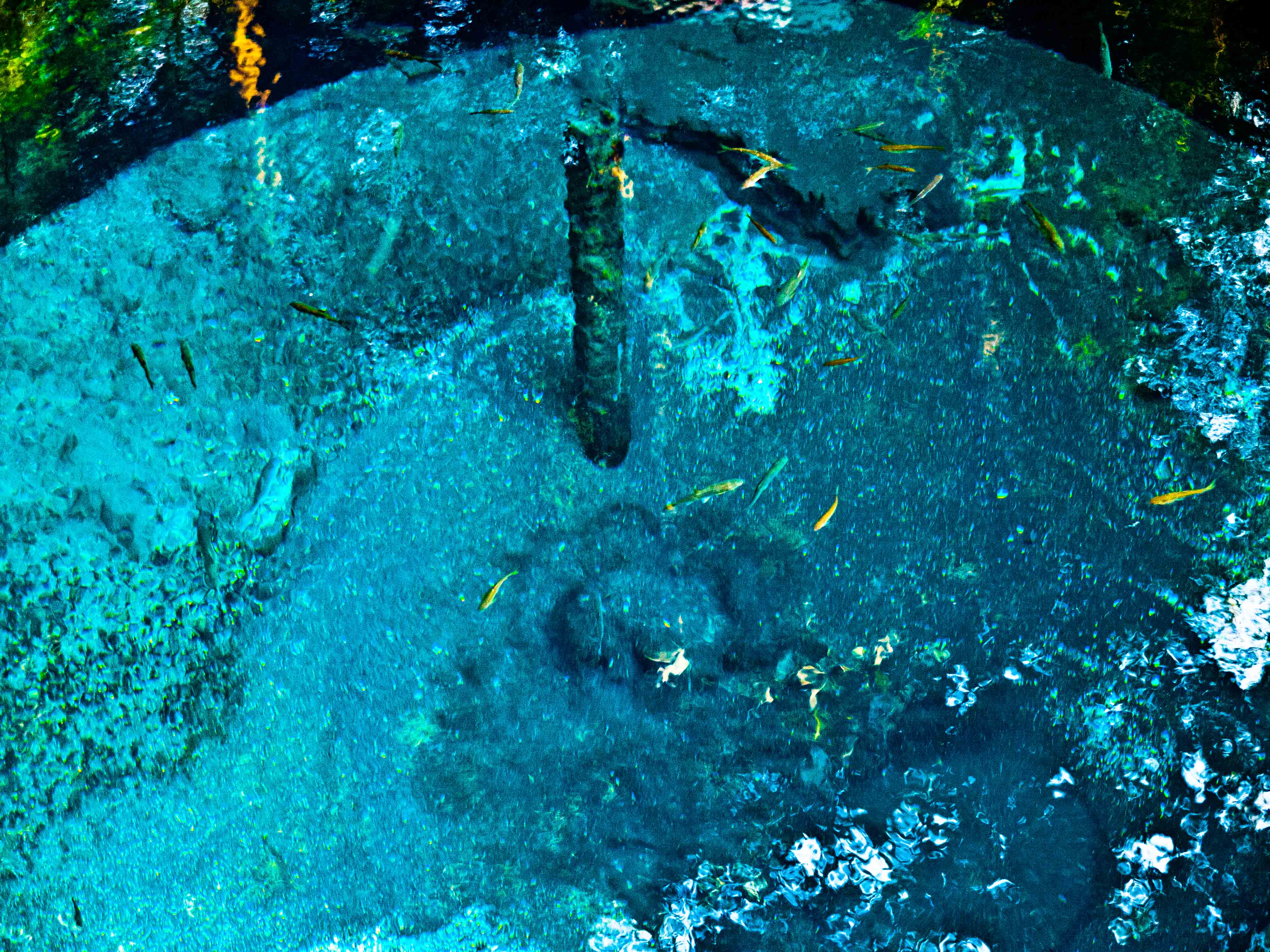今朝、庭木の水やりを終え、なにげなく富士山を見たら、何か様子がヘンです。なんだろうなーと思ってよく見ると、どうやら山頂のあたりが白くなっています。えっ!?これってもしかして初冠雪? と家の中に戻ってテレビをつけてみましたが、特段ニュースでは触れていません。もしかしたら気象庁が定めるところの「初冠雪」の定義に至らないほどの少量の積雪だったのかもしれませんが、雪は雪です。
巷ではまだまだ猛暑が続いているようですが、富士山の上にはもう冬が迫っているんだなと、季節の移ろいの速さを思います。
ちなみに、昨日11日で、我々が伊豆へ引越ししてきてちょうど、半年が過ぎました。季節の移ろいもさることながら、時の経つことの速さも、齢を重ねるごとにより一層感じるようになってきました。
京浜急行
さて、お話は変わり、先日、テレビで横浜や横須賀のグルメ特集をやっているのをみていました。その中で、横須賀在住の方が、「横須賀って、都内から遠いように思うけど、意外に近いんだよね。一時間もかかんないはずだよ。確か45分くらい。」とのたまわっていました。
へえー、ほんとかなーと思って調べてみると、確かに、京浜急行で横須賀中央から品川までは、だいたい45分ぐらいで着くみたいです。これに対して、JRの横須賀線経由で、品川へ行くとすると、1時間10分ほどもかかるようです。
ただ、横須賀線の場合、横須賀を出るとやや西北に進路を変え、鎌倉経由で東京方面に向かうので、距離の面ではやや分が悪いのは確か。
とはいえ、神奈川の片田舎(横須賀在住の方、すいません)から、都内までは50km以上あるはずですから、その距離をわずか45分でも都内へ出れるというのは、やはり早い!と思わざるを得ません。
ほかに何かからくりがあるのかな?と思ってちょっと調べてみました。
すると、京浜急行が速い理由のひとつとしては、横須賀から品川までの停車駅が少ない、いわゆる特急列車が多いためのようです。JR横須賀線の場合、成田エクスプレスや湘南ライナーがこの路線を走っていますが、特急・快速電車のため、横須賀には停車しません。
普通列車の場合、やはり鎌倉を経由するのがネックとなり、品川まで一時間以上かかるみたいで、こうなると、地元の人はやはり京浜急行しか使わないですよね。JRは運賃も高いみたいですし。
と、にわか横須賀市民になって、そんなことを調べてみていたところ、あるサイトで、JRなどのほとんどの列車が「狭軌」のレールを使っているのに対し、京浜急行が走っている線路は「広軌」を使っている、というお話が掲載されていました。
どうやら京浜急行の線路の幅は、JRの線路幅よりも広い、「広軌」と呼ばれるもののようで実際の線路幅は、広軌軌道のほうが1435mm、JRの狭軌軌道のほうが1067mmと、結構差があり、なんと35.8cmも違うではないですか。
だから、何ナノ?という話ですが、一般に、鉄道路線というのは、線路の幅が広ければ広いほど、スピードの出る電車を走らせやすいのだそうです。いまや九州、鹿児島まで伸びた、新幹線の線路もこの広軌軌道だそうで、なるほど京浜急行が速いのもそれが理由かな?と思ったりもします。
じゃあなんで、JRの在来線ももっとスピードの出る広軌軌道にしないんだろう、そもそも、レールの幅ってJRと他の私鉄ではなぜ違うんだろう、ということなのですが、これには話せば長いお話があるようなのです。
鉄道ことはじめ
そもそもの話は、明治時代のはじめ、日本に初めて鉄道が敷かれたときにさかのぼります。
江戸時代の末には既に、薩摩藩や佐賀藩、江戸幕府などがそれぞれのテリトリーで鉄道を走らせることを計画していたようですが、いずれの計画も幕末の動乱でとん挫し、実際に具体的な計画がまとまったのは明治維新が始まってからになります。
この当時、日本を含むアジアでは、欧米列強諸国がこれら東洋の国を植民地化しようと虎視眈々と狙っていましたが、明治政府の方針としては、敵に弱みを見せないためには、自分を強く見せることが一番、というわけで、いわゆる「富国強兵」政策を推し進め、できるだけ早く列強のような工業力をつけることを国家目標としていました。
しかし、明治の初めのころの日本人というのは、そのまえの250年以上に及ぶ江戸時代の鎖国政策のために、外国人を見たことがあるなどという人は、人口比率からすると、皆無に近い状態でした。ましてや、海外の文物といえば、ゾウやトラが見世物になるくらいで、一般庶民が見ることができたものといえば、せいぜい西洋ガラスの器ぐらい、という時代です。
浦賀に黒船が入ってきたのを見ただけで、国中をあげての大騒ぎになったくらいですから、そんなところに、西洋でも最新式の鉄道なんかを持ってきたら、みんな驚きでぶっ飛んでしまうのではなかろうか、と凡人の私などは思うのです。
ところが、時の権力者、大隈重信・伊藤博文らの偉人が私と違うのは、逆に、こういう最新式の西洋の道具を日本に持ち込めば、みんなその先進性にびっくりし、こういうもんか~へへーと恐れ入るに違いない、と踏んだのです。
逆に国民に西洋というものがはっきりと目に見えるようにするほうが、文明開化が進めやすいだろう、という逆転の発想?で鉄道の建設を行うことにしたらしいのです。
とまあそれは表向きの理由で、実際のところは、それまでの日本では海運が物流の中心でしたが、今後国を栄えさせていくためには、陸上での貨物や人員の輸送量を効率的に増やす必要があると考えたようです。
で、鉄道の導入を決めたものの、まず最初にどこにしようかと考えたところ、最初は、東京と京都・大阪・神戸などの関西の間を結ぶ路線と、その途中の米原から日本海側の貿易都市である敦賀へ至る路線が候補にあがりました。
ところが、これだけの距離に鉄道を敷設しようとすると莫大な金がかかります。明治新政権は、このころ実施した、版籍奉還と廃藩置県に伴って必要になるお金、約2400万両(現在の価値でおよそ5600億円)を、各藩に代わって肩代わりしており、多額な負債をかかえていました。
そんなところへ、長距離の鉄道の建設に回すお金なんてあるわけがない、ということで、大蔵省からは建設予算が下りませんでした。一方、「富国強兵」を実現するためには軍隊の整備も進める必要があり、鉄道なんてちゃらちゃらしたもんより、先にそちらの強化をおこなうべきだ、と西郷隆盛などを中心に反対の声も上がっていました。
民間からの資本を入れてでも建設をおこなうべきだという声もあるにはありましたが、とりあえず、庶民に実際に鉄道を見せれば、その素晴らしさが理解され、お金を出そうという人も増えてくるに違いない、ということで、とりあえずのモデルケースになる区間を決めようということになりました。
そして、首都東京と港がある横浜の間、29kmの敷設を行うことが1869年(明治2年)に決定されます。
で、この日本初の鉄度の敷設にあたっては、その線路の規格を決めなくてはなりません。当然、すべての基本となる、線路幅を決めるのが先、ということになります。ところが、その線路の幅を、なぜ欧米で主流だった1435mm(標準軌=広軌)にせず、これよりかなり狭い1067mm(狭軌)にしたのかについては、はっきりした理由を示した公的文書は残っていないんだそうです。
ただ、当時新政府の財政担当だった大隈重信が、「軌間」というものの重要性を理解しておらず、そのころの新政府の技術顧問だったお雇い外国人が、「予算や輸送需要を考えれば、狭軌を採用して鉄道を早期に建設すべきだ」と主張したという事実があるようです。
大隈重信といえばご存知のとおり、早稲田大学を創設した人物ですが、もともとは国学が専門で、憲法論などには詳しかったものの、技術とか科学とかは専門外です。所詮は「教育者」にすぎず、バリバリの文系人間ですから、そんな人間に、鉄道の幅の広い、狭いがその後の国是にどう影響してくるか、といった想像力あるわけがありません。
結局、大隈重信は、これらの外国人のもっともらしい説得に押されてしまいますが、後年、日清戦争や日露戦争が勃発したとき(このときもうすでに大隈は下野していましたが)、大陸で広軌の鉄道が大量の物資を運搬する実情を見聞きし、国内では狭軌を採用した当時のことを述懐して、「一生の不覚であった」と述べているそうです。
もっとも、当時の日本政府の財政事情を考えれば、ヨーロッパやアメリカの本線用の車両を購入して輸送することはかなりの無理があり、必ずしも日本政府の判断が誤りだったとはいえません。しかし、このときのあやまりが、まさか150年以上も経った現代の日本まで持ち越されようとは大隈も考え及ばなかったでしょう。
あいかわらず狭軌鉄道
それにしても、こうして最初の決断で決められてしまったレール幅1067mmの狭軌鉄道は、スピードや輸送力では、欧州など多くの国の鉄道で採用されていた広軌1435mm鉄道に劣るものとなってしまいました。
その後もこの1067mm軌間を1435mmという世界標準に改めようという運動が何回か起こりましたが、度重なる戦争や、戦後も政争や予算の問題でなかなか実現せず、結局、日本において標準軌を採用した国鉄路線が生まれるのには、1964年の東海道新幹線開業まで待たねばなりませんでした。
東海道新幹線が最初に計画されたとき、この新線についても当初、単純に東海道本線を複々線化すればよいとか、狭軌新線にすべきだという案が出ていましたが、戦前に広軌化計画に携わったことのある官僚で「十河信二」という人が総裁に就任していたこと、また、鉄道技術研究所のメンバーが標準軌新線ならば東京~大阪間の3時間運転が可能であると公表したことなどが影響し、標準軌高規格新線での敷設が決定しました。
その後はご存知のとおり、いまや九州は鹿児島まで新幹線軌道が造られ、北海道まで伸びるのは時間の問題という時代になっています。
しかし、新幹線以外の日本の大多数の路線は、今日に至るまで、あいかわらず1067mmの狭軌のままです。1067mmは、3フィート6インチなので、一般に「三六軌間」とも呼ばれています。
明治初頭の大隈重信の決断後、今の国鉄の前身の「鉄道院」の時代には、その総裁になった後藤新平の指示で、標準軌への改軌の技術的な検討もされたようですが、狭い軌道のままのほうが、列車が通っていない地方へ鉄道を延伸しやすく、これを指示する地方代議士が多かったため、こうした政治的な理由から、一ランク低い規格のまま、全国的な鉄道網の建設が続行され続けました。
しかも、「地方鉄道法」という法律が1919年(大正8年)にでき、使用できる最大の線路幅が狭軌に制限されてしまったため、私鉄にも狭軌が広がりました。この地方鉄道法は、民間の会社が敷設した鉄道を、あとで政府が買い上げ、国有鉄道に一体化することを前提にして作られた法律でした。
国有鉄道が狭軌であったことから、戦争などが勃発した場合などに大量の貨物輸送を行う必要が生じた場合、国有鉄道から私鉄への貨車の直接乗り入れが可能になるように、ということでこの法律が定められたのです。
関西では広軌軌道が主流
ところが、地方鉄道法が定められたあとの、1921年(大正10年)には、「軌道法」という新しい法律が制定されました。この法律は、「道路に敷設される鉄道」についてのきまりごとを示したもので、元来は主として路面電車を対象としたものでした。この法律は現在も生きており、近年ではモノレールや新交通システム等にも適用されています。
この、軌道法を、拡大解釈して、地方鉄道法によらず、広軌(標準軌)を数多く敷設したのが関西の鉄道会社です。当時の私設鉄道法では標準軌の路線敷設は認められておらず、地方軌道法により狭軌の鉄道しか建設できませんでしたが、この軌道法ができたことで、路面電車に本来適用される軌道法を拡大解釈して路線を建設したのです。
一説によると軌道法の監督省庁である内務省が、関西の電鉄事業に好意的であったということです。道路に作るんなら、幅が広い鉄道でもいいよ、と逃げ場を作ってやったのです。
広軌路線であっても、車両の大きさの限界は国鉄と同じか、それ以下に制限されていましたので、逆にこのことで、トンネル断面積や駅の設備などは、狭軌のものと同じにすることたでき、あまり建設コストに差がでないという結果になりました。
この結果として、関西では軌道法による1435mmのレールを高速で走る「路面電車」が続々と開業しました。また、関西だけでなく、全国の地下鉄路線も「路面電車」として1435mmの広軌で敷設されるようになりました。
関西で広軌を採用した私鉄の中でもとくに高速化の技術を発展させたのは、京阪電気鉄道(現阪急鉄道)で、とくに新京阪線(現:阪急京都本線)は、鉄道が完成した当初、その当時の国鉄最高の特急列車「燕」を山崎付近で追い抜いたという逸話が存在するほどでした。
近畿日本鉄道も当初は、狭軌を採用していましたが、伊勢湾台風により名古屋線が壊滅的打撃を受けたのを機会に、当時の社長が周囲の猛反対を押し切って、路線を復旧させるときに、標準軌化を断行しました。
関東での広軌鉄道
一方、関東圏では、この二つの法律ができる前から、広軌鉄道による鉄道を敷設していた会社がありました。それが、1899年(明治32年)、六郷橋~大師間に路面電車を開業させた大師電気鉄道で、これが現在のの京浜急行電鉄の「大師線」です。
京浜急行は、国鉄の標準軌への改軌を見越して、広軌鉄道を敷設したといわれています。法律改正によって、地方鉄道は狭軌にしなければなりませんでしたが、京浜急行は「路面電車」であったため、「軌道法」の適用になり、国鉄の改軌が行われなかったことを尻目に、その後も、電気鉄道・路面電車・地下鉄の分野それぞれで1435mm軌間を急速に普及させました。
このほか、かつては東京のあちこちで見られた路面電車を保有していた、東京都電(現在はほとんどが廃止され、路面電車は荒川線だけ。一部は地下鉄として現存)は、1372mmという、狭軌以上広軌以下、という中途半端なサイズの路線を採用。このため、広軌を採用していた地下鉄と昭和中期に相互直通運転を行う際の対応で苦慮しました。
また、東京都電に乗り入れていて、同じく1372mmゲージを採用した京王帝都電鉄(現:京王電鉄)も、都営新宿線との相互乗り入れを行う際に広軌への改軌を東京都から打診されたものの、当時の急激な沿線の発展による乗客の急増に対応するのに手一杯で結局実現できず、今もあいかわらず、1372mmという特異な軌間を使い続けています。
このほか、以下に示す、関東地方の私鉄は、今もJRと同じ1067mmの狭軌を採用しています。
東京地下鉄(銀座線、丸ノ内線を除く)
関東鉄道(全線)
京王電鉄(井の頭線)
東京急行電鉄(世田谷線を除く)
小田急電鉄
江ノ島電鉄
箱根登山鉄道(小田原駅~箱根湯本駅間のみ)
西武鉄道
東武鉄道
秩父鉄道
相模鉄道
東京都交通局(都営三田線)
東京臨海高速鉄道(りんかい線)
首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス線)
富士急行
わが伊豆を南北に走る、伊豆急行、伊豆箱根鉄道も狭軌路線です。富士山や海を臨みながらのんびりとゴトゴトと走るその景色は、田舎の風景にはぴったりですが、東京都内を走る電車のほとんどが、今もこうした古い時代に決められた幅のレールの上を走っているのは、なにやら時代遅れのようなかんじもします。
京浜急行のようにスパッ、と広軌に切り替えられないものなのでしょうか。お金はかかるでしょうが、広軌化による時間の短縮は、この国の活性化にもつながるのでは。
新しい総理大臣が誰になるのかわかりませんが、そのへんのこと、ちょっと考えてみてもらいたいものです。