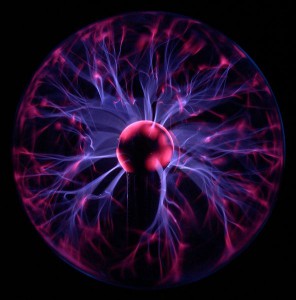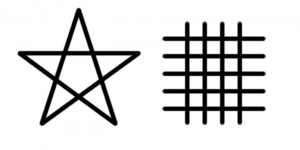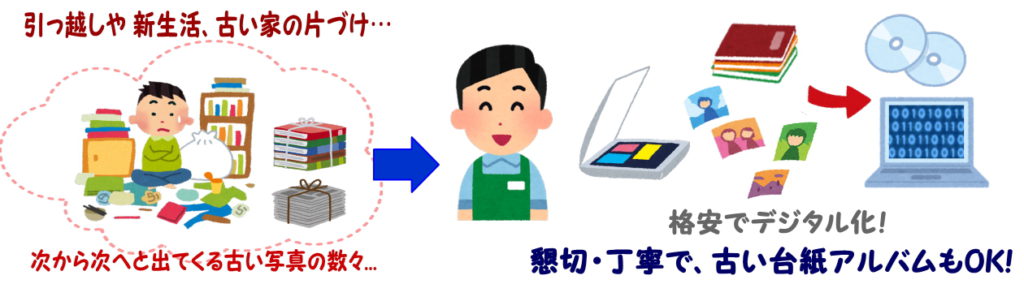佐原は、霞ヶ浦の東端から南へ10kmほど行ったところにあります。すぐ北側2kmほどのところに利根川が流れており、その支流の小野川は運河として機能するよう、底ざらいや岸壁が整備されており、これを通じてかつては、あたり一帯で獲れた豊富な穀物を江戸へ、あるいは外港の鹿島へ運び出していました。
この小野川沿いは、古き時代を思い出す懐かしい町並みが江戸時代そのままに保存されています。文化財でもある銀行や書店、呉服屋、乾物屋などなどの古めかしいお店が立ち並んでおり、東京からもほど近い人気の観光スポット。6月のあやめの時期には、小野川を中心とした周辺の運河を通って舟にゆられながら水郷を見物できるほか、7月と10月の大祭には豪華な山車(だし)も引き出されて、より一層観光客で賑わいます。
私も利根川の環境調査をしていた時期があり、この佐原には何回か行ったことがあります。佐原市民の方には大変失礼ですが、佐原の駅前はひなびたというか、ごく平凡な街並みなのに、この小野川沿いの街並み保存地区に入るいなや、いきなり時代を遡ったような感覚におそわれるほど、風景が一変。
両側に柳の木が並ぶ石造りの運河の中には、昔ながらの手漕ぎの和船などもあって、もし観光客がいなければ、本当にタイムスリップしてしまったのではないかと思えるほど、江戸時代そのままの町並みが残っていて大変風情のある風景でした。
伊能忠敬の旧宅は、この街並みからややはずれた場所にあり、忠敬自身が設計したという母屋と店がその当時のまま保存され、公開されています。忠敬は江戸の八丁堀亀島町(現日本橋茅場町)の自宅で晩年を過ごし、ここで亡くなったため、この佐原の自宅には戻ってきませんでしたが、この佐原の観福寺にも遺髪をおさめた参り墓があるそうです。ちなみに、遺骨は上野の源空寺に埋葬されました。
その忠敬は、50才で隠居して、この旧宅を離れ、その年齢で新たに暦学を学ぶという希望に燃えて、江戸にやってきました。
そして、そのころちょうど、幕府の暦局に招へいされていた天文学者の高橋至時に弟子入りします。また、高橋と同じく大阪の麻田剛立の高弟であり、高橋とともに暦局に入った間重富という知己も得ながら研鑽を重ね、やがて忠敬は、天体の観測や測量の技術にかけては、師匠の至時以上の技術を持っているとまで評されるようになっていました。
緯度1度の距離
その当時、高橋至時らの暦学者の間では、緯度1度の長さが実際にはどれくらいあるかが学問上の大きな話題になっていました。緯度1度の南北の距離については、30里とも32里ともいろんな説が入り乱れていましたが、いずれも実測に基づいた結果はなく、検証することはできません。
緯度1度の長さが確定しなければ、地球の大きさも測れないわけで、これは暦学上の大きな問題でありました。忠敬もこれに強い関心を持ち、浅草の暦局と黒江町の自宅が3キロメートルほど離れていたところから、この両地点の距離を計測し、その緯度の差と比較して緯度1度の長さを算出しようと試みました。
暦局と黒江町の緯度差は約1分半であり、この測定値に忠敬は自信を持っていましたが、問題はどうやってその距離を測定するかです。これを正確に測るには、間縄などの道具が必要になります。間縄は、現在の巻尺に相当するもので、1間ごとに目盛を付けた全長60間(約11m)の縄で、使い勝手のよさを考え、軽くて丈夫な麻縄が用いられたようです。
この間縄を使って、暦局と黒江町の長さを計測しようというのですが、しかしいざ、これを使って地上の長さを計ろうとすると、建屋が込み入った江戸の町では、思うように縄がはれず、直線距離を測ることは至難のわざでした。直線で縄を張ろうとすると、家々の屋根の上に上がらねばならず、そんなことを幕府が簡単に許すわけがありません。
しかたなく、忠敬は暦局と黒江町の間を何回も歩いて歩測を繰り返し、さらには磁石を使って南北の距離を出してみましたが、どうしても正確な測定ができません。そこで至時に相談したところ、至時は「たとえ距離を精密に測定することができたとしても、そんなに小さい緯度の差や距離から、緯度1度の長さを計算したのでは、信用のおける数値を得ることは無理だろう。」と答えました。
実は至時は、忠敬から相談を受けた時、既に緊迫する政治情勢をにらみながら、その後忠敬によって実現する蝦夷地測量の計画を自らも考えていました。
18世紀の後半には、鎖国日本の近海にしばしば外国の艦船があらわれ、水や食料の補給の要請ばかりでなく、通商まで求めるようになっており、鎖国をポリシーとしていた幕府の悩みの種になりつつありました。
1792年(寛政4年)には、帝政ロシアのラクスマンが根室港に入港し、日本人漂流民を送り届けるのを口実に、あからさまに通商を要求してきました。
このとき、幕府は通商は拒否しましたが、長崎への入港許可証ををラクスマンに与えました。その後、ロシアは、1804年(文化元年)にその許可証を持って長崎に来航し、再度交易を求めていますが、この1800年前後のころというのは、ロシアだけでなく、アメリカやフランスの艦船が蝦夷地や紀伊大島などの住民と接触するという事件が相次いだ時期であり、幕府としても迫りくる諸外国の圧力をひしひしと感じ始めていた時期でもありました。
このため、幕府は、蝦夷地探検や調査団の派遣を実施し、幕府の直轄領とするために番屋を置くなどの対策も講じ始めました。沿海測量も実施し、蝦夷地の広さを確認しようとしましたが、測量技術が稚拙であったため、絵地図程度のものしか出来上がってきません。
幕府の天文方であり、国内の測量部門を統括する責任者でもあった高橋至時のもとには、こうした情報が集められており、早晩、自分が計画して蝦夷地の測量を行ない、幕府が欲しがっている精密な地図を作る必要性を感じていました。
そして、まずその皮切りとして、忠敬が確認したがっていた、「緯度1度の長さ」の実測を実現しようとし始めます。
至時は、その実務担当者として忠敬が適任と考えていたようです。自分が教えたその測量技術の技量は今や自分の技量をはるかに超えており、佐原の造り酒屋の頭領として、人を見る目や人を率いる手腕も優れています。
さらに優れた筆記能力があり、測地測量という膨大なデータを処理するための記録能力も申し分なく、しかも自分のように天文方という職務に縛られない隠居の身でもありました。
しかし、高橋至時が最も忠敬に期待したのは、その財力でした。幕府は蝦夷地などの精密な測量が必要としながらも、その測量をするための十分な資金を用意するにあたっては幕閣があまりいい顔をしませんでした。幕府は、江戸時代半ばから物価の高騰や、安定しない米中心財政の行き詰まりに悩まされていたためです。
従って、測量のための蝦夷遠征を実現するにあたっては、当面、幕府からの財政援助はあてにできず、自費を前提にしてでなければ、その許可を得ることが難しかったのです。
その費用は莫大なものであったと考えられますが、忠敬は、至時からこの計画について相談を受けた時、これを喜んで引き受けました。
しかし、忠敬には忠敬の考えがありました。資金難から、至時が当面はこの計画を主として緯度1度の長さを測定するだけにとどめようと考えたのに対し、忠敬は蝦夷地の実測地図作成までを目標としたいと考えたのです。
当然、忠敬が長年佐原で蓄えた銭の大半がそれによって失われることになりますが、忠敬自身の心はもうすでに老境に入っていたのでしょう。老い先短いのに金を大量に残しておく必要はない、と考えたに違いありません。
幕府当局へ提出された蝦夷測量嘆願の書状には、「後世に残るような」地図を作成したい旨の決意が述べられていたといいます。
蝦夷測量
至時は、1799年(寛政11年)の末から、幕府に蝦夷地測量の許可が早くおりるように精力的に働きかけ、それが効して翌年2月には幕府から内定の裁可を得ることができます。
しかし、本裁可にあたっては問題一つありました。それは幕府の許可が、人員も器城も船で運ぶこと、となっていたことです。至時や忠敬の蝦夷行の目的のひとつは、できるだけ正確な緯度1度の長さを確定することであり、そのためにはできるだけ長い距離を陸路で測定することが必要です。船で蝦夷地へ行ったのでは、せっかくの陸地測量ができなくなってしまいます。
このため、至時は、陸路で奥州から蝦夷地へ向かうという行程に変更してもらうよう、幕府と交渉しました。しかし、幕府としては、陸路を通れば、忠敬らの奥州の諸藩との接触は避けられず、欧米の知識の豊富な忠敬らが彼らに無用の影響を与えることは避けたい考えでした。
またこの当時は測量術は最新技術のひとつであり、いわばトップシークレットであったため、その技術の内容を幕府に先んじて奥州諸藩に知られたくなかったのです。
至時の粘り強い説得により、ようやく幕府は陸路は承認します。しかし、自らが言い出したとはいえ、陸路の移動であるがために、船のように大量の荷物を運搬することはできず、携行する器械の数は絞らなければならないというジレンマを抱えることになりました。その機器の選定や、危機不足を補うための工夫のために、忠敬たちはかなりの苦労を余儀なくされました。
やがて幕府の本裁可下り、「浪人 伊能勘解由 その方、かねがね心願の通り、測量試みのため、蝦夷地へ差し遺わされる。入念に努力せよ」との書状が忠敬の元へ送られてきました。「測量試みのため」という表現からもうかがえるように、幕府は忠敬の測量成果に大した期待を持っていなかったことがわかります。
そして、1800年4月、忠敬を筆頭として、門倉隼人・平山宗平・伊能秀蔵らを従えた一行6名が江戸の町を出発しました。忠敬の測量日記「蝦夷于役志」によれば、奥州街道を北上していたときには、一日に9里から10里、時には13里以上も歩いたといいます。一里は約4kmですから、13里といえば50km以上の道のりです。かなりの強行軍といえます。
しかも、夜には寝る間を惜しんで天体観測を行っていたといいますから、彼らのタフネスぶりがうかがわれます。
こうした「快進撃」の結果、一行は江戸出発から早くも30日目には津軽海峡を船で渡り、5月22に蝦夷地に足を踏み入れています。箱館(現函館)の蝦夷会所に顔を出し蝦夷測量の手続きを取ったあと、測量隊は室蘭、襟裳(えりも)岬、釧路と蝦夷地の東南岸を測量し続けます。
そして、根室の少し手前にある別海(現野付郡別海町)に8月7日に到着。別海の仮宿で天体観測を行い、2日間滞在したと記録に残っています。
ちなみに、忠敬の歩測の歩幅は江戸の町で訓練し、69センチと決まっていたそうで、自分の歩幅まで測量器具にしていたというところが、すごいなあと思います。この当時の蝦夷は、本州ほど道が整備されているわけではなく、当然難路ばかりであり、1日に歩ける距離もせいぜい4~5里程度でした。
道路の曲がり角では小方位盤で方位を測り、夜の天体観測は、北極星だけではなく、大熊座、小熊座など多い時には一晩に20個くらいの恒星を観測したといいます。
実は、今回の蝦夷測量には、幕府が決めた期限がありました。往路も考えると十分な時間もなくなってきたため、忠敬らは、蝦夷全土の測量を断念し、やむなく蝦夷東側だけの測量を終え、帰路につきました。
ちなみに、忠敬らが測量できなかった西蝦夷地の測量は、その後、忠敬の弟子の間宮林蔵によって行われ、この師弟の実測によって、蝦夷地全体の輪郭が初めて科学的で正確なものとなりました。
忠敬らが行った奥州・蝦夷を中心とするこの第一次測量では、宿泊日数は180日、天体観測日数は81日に及んでいます。帰路は、福島城下と二本松城下、白河城下などを通過し、10月21日に無事、江戸に帰ってきました。
測量の途中で下僕1人が暇を取った以外、他の5人は1日も病気もせず、元気であったといいます。
幕府は、この忠敬らの奥州蝦夷地測量の結果を見て、初めて忠敬の測量技術の高さに驚嘆します。この測量結果により、忠敬は、緯度1度の距離を、二十八・二里と算出し、天文方であり、師匠の高橋至時に提出しました。1里=3.9273Kmとして、110.75Kmが、忠敬らが算出した緯度一度の長さです。
現在の測量技術をもって算出されている長さとの誤差は、わずか約0.2パーセントでした……