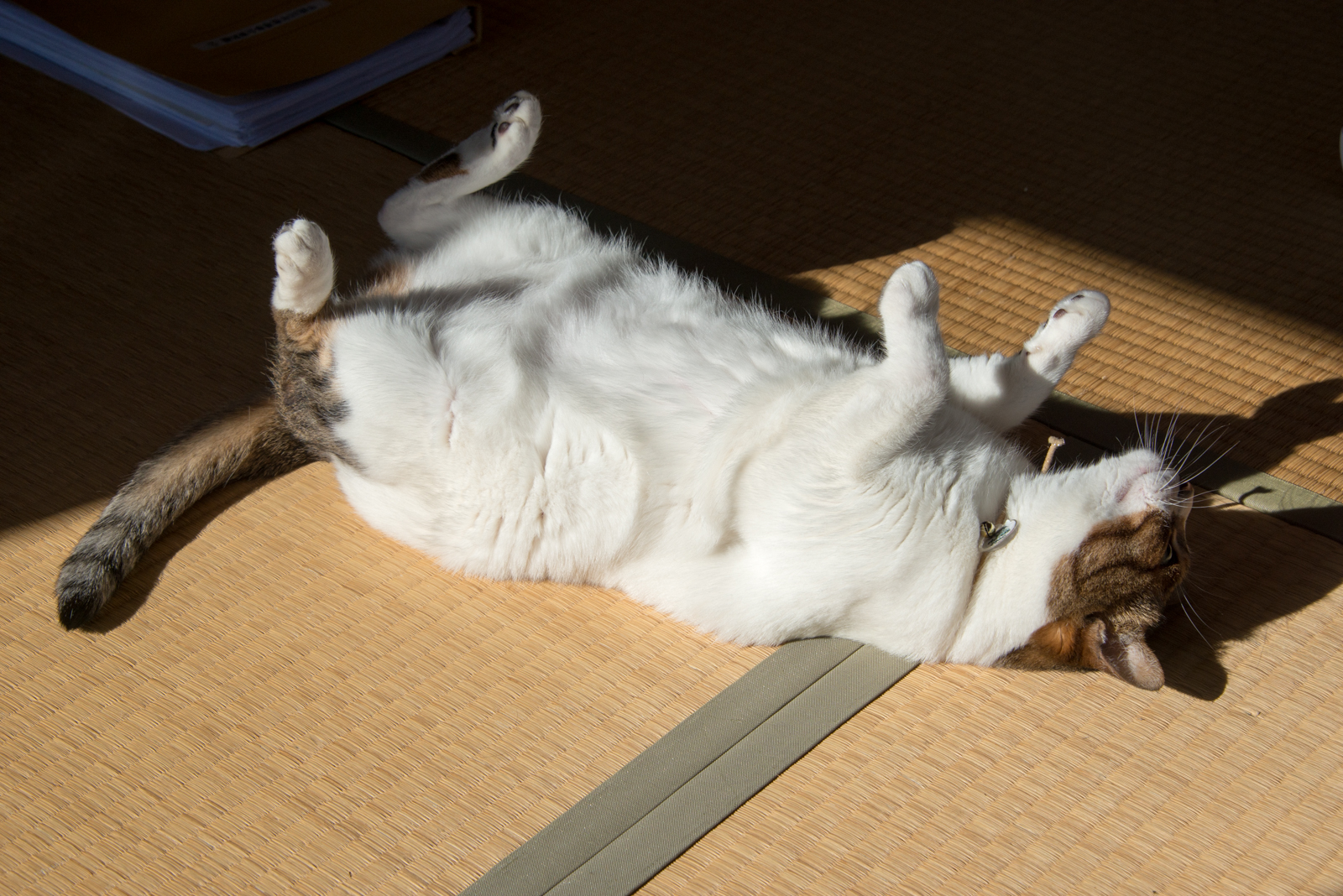先日来、各種メディアではつんくさんが声帯を摘出して声を失ったという話でもちきりです。
先日来、各種メディアではつんくさんが声帯を摘出して声を失ったという話でもちきりです。
ファンだけでなく、その名を知らなかった人たちも驚きとともに、切ない思いに駆られたと思いますが、私も同じです。
しかし、自分が一番大事にしてきたものを犠牲にしても、ともかく生きる、という選択をとられたことについては、誰もがエールを送っているかと思います。
それにしても声を失う、ということはいったいどういうことなのか。改めてこの「声帯」というものについて調べてみました。
すると、声というものは、まず、肺から押し出される空気が声道を通過することによって生み出される、ということがわかりました。声道というのは、人間を含めた哺乳類の場合、喉頭と咽頭、つまり我々が「のど」と認識している部分に加え、口の中の空洞と鼻の穴を合わせたものの総称です
このうちの咽頭、これは食べ物が通る食道とつながっている部分ですが、この咽頭の前にある部分が喉頭で、肺とつながっている管です。この喉頭の部分には、粘膜で覆われ内部に筋組織を持つ両側に存在する1対のひだがあります。これが、声帯です。
この声帯は、普段は開いていますが、肺から空気を押し出して空気を出す時、無意識に閉まったり、開いたりします。これにより、通過する空気が振動し、音になります。ただ、この時点では声と認識できるものではなく、このあと、口腔と鼻腔がこの震動をさらに変化させ、共鳴音を作り出します。
そして、口や鼻の外から外へ放射されるのが、「声」です。
今回のつんくさんの病気は、この声帯の部分に癌ができたことにより、その切除手術を行い、他への転移を防ぐ、というものだったようです。過度の物理的刺激、例えば大声を張り上げ続ける、歌い続ける、といったことにより、声帯にポリープができることはよくあるようで、通常は声帯への負荷を避けることにより自然治癒するようです。
が、何等かの要因である一線を超えると癌になるようで、その要因もいろいろあるようですが、飲酒や喫煙、精神的なストレスといったものがあげられているようです。つんくさんの場合が何だったのかは明らかにされていないようで、よくわかりませんが。
とまれ、なかなか治りにくい病気です。「声帯癌」という呼称は一般的ではなく、もっぱら「喉頭がん」と呼ばれるようです。これまでも芸能人や有名人で亡くなった人はたくさんおり、例えば同じくミュージシャンの忌野清志郎さんもこの病気でした。このほか立川談志さん、池田勇人元首相なども喉頭がんで亡くなられました。
それにしても、声帯を切除するということは普通にしゃべれなくなるということであり、その決断にはさぞかし勇気がいったことでしょう。が、声帯を取らなければ他への転移も考えられるわけであり、苦渋の選択としても本当に辛いことだったでしょう。
私自身も仮に声をなくすとしたら、やはりそれは人生の一大事に違いありません。そこで、改めて、この声を失う、ということの意味を考えてみました。
まず考えられる物理的な意味は、文字通り、「言葉を失う」ということです。言葉というものは、話す・書くことによって、心、気持ち・思い・考え等を表すための手段です。
人は言葉によって認識を共有する事が容易となります。太古の時代より、人間はそれぞれの民族毎に意味を持った言葉を作り出してきましたが、言語の形成は、さらに人間に「思考」というものを与えました。
考える、ということを言葉を使って行うようになったわけです。これにより意志・感情を言葉で表現することによって複雑な心理を明確にすることができるようになり、そして、このことによって自己理解もまた深まり、知能を発達させたと考えられています。
この、言葉というものがまだ無い時代の原始時代の人は、その意思伝達を行うために、ただ、あーとかうーとか、動物と同じように唸るだけで相手の注意を喚起していたようです。しかし、それだけでは伝えられないことも増え、次第にこれに加えてボディーランゲージや絵文字等を指し示す、といった行為も行われるようになりました。
こうした行為は、日常の生活の中では、だいたい同じパターンになります。社会生活の中で、同じボディランゲージや絵文字を指し示す、といったことが何度も繰り返されるうちには、一定の規則性が生じます。そしてあるとき、これを発声行為に置き換えればいいんだ、と気づきます。
やがてはただのあー、うーだったのが、がぁ~とか、うぅーも加わって、そのバリエーションも増えて規則性のある言葉が増えます。それと絵文字等が合致し、絵文字を指し示すと、それに関する音を口から出す、といったことで言語が生まれたと考えられており、これがやがて時代を経てさらに高度な言葉の文化になっていきました。
従って、声帯を失い、その言葉を口から出す、という行為ができなくなる、ということは、いわばその文化を生み出すための原動力、能力の一つを失った、ということになります。しかし、声は失われたかもしれませんが、まだ書くことで意思を伝えることがでるわけで、意思伝達方法のすべてを失ったわけではありません。
相手に何らかの方法で意思を伝えることができ、それを言語と呼ぶのなら、口がきけなくなっても言語を失ったとはいえないわけです。目は口ほどに物を言う、とも言うように、目による意志疎通もでき、ボディランゲージで自分の考えていることも伝えられます。無論、手話も言語のひとつといえるでしょう。
また、現在では、言語に代わり、科学的な方法で自分の意思を伝える方法はたくさんあります。音声合成などがそれで、これについては後述しますが、従って自分の声を失ったからといって意思伝達の方法がまったく失われたわけではありません。
しかし、声を失うということでもうひとつ大きな喪失があります。それは、歌うことです。歌、唄とは、声によって音楽的な音を生み出す行為のことであり、リズムや節をつけて歌詞などを連続発声するという行為は、娯楽とも考えられますが、より洗練されたものは「芸術」といわれるものになります。
「歌う」ことは、「感情を表現とすること」を最大の目的としており、その点で、事件や事象を聴く人にわかりやすく伝達することだけを目的とした言葉を「語る」こととは大きく異なります。極論すれば、歌詞などもまったくめちゃくちゃの意味不明でもよいわけで、この点が単に「言語を話す」ということと違います。
鳥もまた、「うたう」というぐらいで、彼等は言語なんか知りません。歌詞などなくても、歌えるわけです。そういう意味では、そうした自分らしさを表現をする重要な手段を失ったということの喪失感は大きいでしょう。
とくにつんくさんのように人気歌手だった方が自分のアイデンティティを示す最大の手段を失うということは、相当に大きなダメージだったに違いありません。
しかし、ハミングなど、歌詞をともなわない歌唱方法もないわけではありません。つんくさんもハミングができるのではないでしょうか。
結論からいうとこれは難しそうです。ハミングというのは、鼻音唱法とも母音唱法ともいい、いわゆる鼻歌です。言葉の明瞭さはないものの、実はこれも声帯の振動によって音を出しています。
普通の人はハミングしている状態で甲状軟骨を優しく触診すれば声帯振動を指に感じることができます。つまり、ハミングは声帯を使って音を出していることがわかります。
声帯をなくした人が訓練を積み、食道などの部分を使ってこれを共鳴させ、共振による音造りをする、ということは聞いたことがあり、ある程度は可能なようです。しかし、これはかなりの厳しい鍛錬が必要になるといい、また、仮にハミングができるようになったとしても、普通とはかなり違う音になるようです。
従って、つんくさんも普通のやり方で健常者と同じ程度に歌うことができるようになるかというと、それ相応の努力が必要になる、といえるでしょう。
とまれ、もう少し、この「歌う」ということの意味を考えてみましょう。
「うた・歌う」の語源は、「うった(訴)ふ」だそうです。これからもわかるように、歌うという行為には相手に訴えたい内容、すなわち何等かの「歌詞」の存在を前提としています。また、この歌詞は「うた」が語源です。
このうたとは、古代では「言霊」と考えられており、言葉そのものが何等かの霊力を持っていると考えられていました。これを発することによって相手の魂に対し激しく強い揺さぶりを与えることができます。つまり、相手を「打つ」わけで、この打つが、「打た」、に変わり、「うた」になっていったという説があります。
この言霊は、ことだま、とよみますが、清音では「ことたま」とも発音します。仮名文字(平仮名、片仮名)を母音に基づき縦に五字、子音に基づき横に十字ずつ並べたものを「五十音」といいますが、古代の日本では、この言葉ひとつひとつによって森羅万象が成り立っているという考え方があり、これを「コトタマの法則」といいます。
古代では、声に出した言葉が、現実の事象に対して何らかの影響を与えると信じられており、この五十音を使って良い言葉を発すると良い事が起こり、不吉な言葉を発すると凶事が起こるとされました。このため、何等かの行事で祝詞を奏上する時には絶対に誤読がないように注意されたといいます。
今日にも残る結婚式などでの行事でもこのコトタマの法則の名残はあり、例えば「忌み言葉」というのがあります。サル、キル、カエルなどがそれであり、これは「去る」「切る」「帰る」などであり、こうしたおめでたい席では使ってはいけないことばです。これも言霊の思想に基づくものです。
また、その昔の日本人は、この日本という国は言魂の力によって幸せがもたらされると信じ、そうした国を「言霊の幸ふ国(さきわうくに)」としました。言霊があふれて幸せな国、という意味になります。また、この「幸ふ」は「万葉集」などでは、「佑ふ」と表現されており、大和の国(日本)は、「事靈の佑(さき)はふ國」などの表現がなされています。
この「佑」という漢字は「助ける」という意味があり、つまり、言霊によって助けられている国、ということになります。ちなみに、この例からもわかるように、この時代には「言」と「事」が同一の概念でした。漢字が導入された当初も言と事は区別せずに用いられており、例えば古事記では「事代主神」が「言代主神」と書かれている箇所があります。
なので、これは正しいのかどうかはわかりませんが、「事件」という現代用語は「言件」とも書けるわけであり、これは言霊によって起こされた出来事、ということになります。言い争いなどによって起きた結果、というほどの意味になり、事件の本質を表しています。
さらには、自分の意志をはっきりと声に出して言うことを「言挙げ」と言い、それが自分の「慢心」に基づいて発せられたものであった場合には悪い結果がもたらされると信じられていました。
例えば「古事記」において倭建命(ヤマトタケルノミコト)が伊吹山に登ったとき山の神の化身に出会った際、「これは神の使いだから帰りに退治しよう」と「言挙げ」しました。しかし、この言霊は彼が、自分は強いんだぞ、という慢心によるものであったため、命は神の祟りに遭い亡くなってしまった、とされます。
このように、言霊思想というのは、それを発する人間の心の持ちようによっては良いものにもなり、悪いものにもなるという、心のありようを指し示す物差しと考えられたわけで、さらには、万物にもその言霊によって神が宿る、と考えられていました。
日本だけでなく、他の文化圏でも、こうした言霊と共通する思想は見られます。旧約聖書や新約聖書でも、「言霊」に相当すると考えられることばがあるそうで、これを「プネウマ」と呼んでいました。これは「吹く」という意味の動詞を語源とし、息、大いなるものの息、といった意味です。
聖書には、「風はいずこより来たりいずこに行くかを知らず。風の吹くところいのちが生まれる」といった表現があり、この「風」と表記されているものが「プネウマ=言霊」です。「風の吹くところ」を言い換えると、「言霊があるところに命が生まれる」というふうに訳すことができます。日本と同じです。
このように、洋の東西を問わず、一般に、言霊は、禍々しき魂や霊を追い払い、場を清める働きがあるとされます。また、言霊は言葉だけでなく、「音」にも宿るとされます。
祭礼や祝い、悪霊払いで、神事での太鼓、カーニバルでの笛や鐘、太鼓などはこうした音を立てて場を清めたわけであり、日本の神社で柏手を叩いたり、中華圏での春節の時の爆竹を使うのもそのためです。
そして、こうした祭事に出された音が次第に高度化していったものが、「音楽」であり、また音と言葉が合体したものが、「歌」であるわけです。呪文や詔(みことのり)には、時に抑揚をつけて現代のような音楽のようにして唱えられていましたが、その霊的な力を利用して神事を執り行おうとしたわけです。
無論、さまざまな文化により、時代により、また個人によりそうした行事の内容は大きく異なっているわけですが、いずれにせよ、歌もまた言霊であり、言い換えれば真理や魂の叫びを伝えるものだということになります。
単なる言葉よりもさらに高度な、心から神に伝えたい気持ちを表出するための手段でもあり、それを失うというのは、人間にとってはかなりつらいことかもしれません。なんにせよ、それを自分の体から発することができなくなるわけですから。
しかし、ここでちょっと考えてみてください。歌が歌えても音痴な人はいます。音痴な人はどうするかというと、他の人が歌っている中に混じって自分の歌の下手さをごまかすか、あるいは楽器を奏でてこれを補ったりします。
またメガネをかけている人はメガネが無くなったら何もできません。このメガネは視力が弱いことを補助する道具に過ぎませんが、その道具を使うことによって、目がみえるようになります。
ごく普通に正当化されていることであり、それならば、声が出せない人は同様に何等かの道具を使って音を出しても何ら人に不思議がられることはなく、ましてや非難されるようなことは何もありません。
メガネ同様、自分自身の力で矯正できないからと言って恥じることは何もなく、言霊を自らの体から発せないならば、何等かの手段でもってそれを出せばいいだけ、ということになりませんか。
ご存知のように、最近は音性合成技術がかなり進んでいます。
イギリスの理論物理学者であるスティーヴン・ホーキング博士の例で有名になりましたが、博士は意思伝達のために「重度障害者用意思伝達装置」を使って生活しています。スピーチや会話ではコンピュータプログラムによる合成音声を利用しており、その音声を聞いたことがある人も多いでしょう。
こうした音声合成技術を使って、現在ではメガネのように気軽に自分の声を合成して出す、という技術が確立されつつあります。
まだまだ、完成度は低いようですが、いずれはもっと進化し、つんくさんが生きておられる間には、声を失う前とほとんど寸分変わらないような声を出したり、歌ったりすることができるようになるかもしれません。
実はこうした音声合成技術の歴史は古く、現代的な電子信号処理が発明されるずっと以前から、音声を模倣する試みはなされてきました。西アフリカには、「トーキングドラム」とうものが昔からあり、これは日本の鼓(つづみ)のような形をしていますが、これを叩いて人の声を真似た合図が遅れるそうです。
ただ、もっと科学的な意味での音声合成の試みとしては、1779年にドイツ人クリスティアン・クラッツェンシュタインという人が、母音(a, e, i, o, u)を発声できる機械を製作したものが嚆矢とされているようです。
1791年には、オーストリア(ハンガリー)のヴォルフガング・フォン・ケンペレンがこれを改良して、ふいごを使った機械式音声合成器を作っており、この機械は舌と唇をモデル化しており、母音だけでなく子音も発音できたそうです。
同様の試みは、1837年のイギリスの物理学者、チャールズ・ホイートストンも行っており、彼はケンペレンの合成装置をさらに改良し、「しゃべる装置」のレベルまで引き上げたとされています。
さらには、1930年代、アメリカのベル研究所のホーマー・ダドリーが、通信用の電子式音声分析・音声合成マシンとして、ヴォコーダー(Vocoder、Voice Coderの略)を開発しており、その後この器械の音声合成部にキーボードを付加した、世界初の「鍵盤演奏型スピーチ・シンセサイザー」、ヴォーダー(voder)を製作しました。
この器械は、ニューヨーク万国博覧会 (1939年)に出展されましたが、その発声は十分理解可能だったと言われます。その後も、多くの科学者が同様の機械の開発に取り組みましたが、最初のコンピュータを使った音声合成システムは1950年代終盤に開発され、最初のテキスト読み上げシステムは1968年に開発されています。
1961年、ベル研究所の物理学者ジョン・ラリー・ケリーとルイス・ゲルストナーは、IBM 704というコンピュータを使って音声合成を行い、「デイジー・ベル」という歌を歌わせることに成功しました。これは、現在でいうところの、「ボーカル・シンセサイザ」ーの走りです。
この器械の噂を聞いてベル研究所に来ていたアーサー・C・クラークは、このデモを聴いて感銘を受け、これにより「2001年宇宙の旅」でHAL 9000が歌うクライマックスシーンが生まれたといいます。この器械は現在までにさらに進化しています。これは後述します。
一方、ただ単に言葉をしゃべるだけの音声合成装置はこれ以上に進化してきています。初期の電子式スピーチ・シンセサイザーの発声は、ロボット的であまり明瞭ではないものが多かったようです。が、その後の発達により、単にテキストを読み上げるだけならば、人間の声と区別が付かないほどになっています。
最近では、文字を読むことが困難な障害者や、文字が読めない人(幼児、外国人など)のために、画面を読み上げてくれるコンピュータソフトは既に普及しており、これは「スクリーンリーダー」といいます。
また、家電製品の音声ガイダンスや、公共交通機関や防災関係のアナウンス用途として音声合成されたものが広く使用されるようになっており、カーナビでもこうした音声装置は普通に使われています。
ただ、これらの電子式の機械式音声合成装置は、スピーカーから音が出ているため、どうしてもどこか機械が出している音のように聞こえてしまいます。そこで、ロボットで人間の体の構造を模倣した機械式音声合成しようとする試みも最近は進んでおり、これなら、もっと人間に近い発声になると考えられています。
とはいえ、これはつまり人間の声帯を真似たロボットということになり、そこまで優れたものはまだ完成されていないようです。いわんやロボットに歌を歌わせるというのは、かなり難しい技術らしく、人と寸分変わらず歌が歌えるというものはまだないようです、
しかし、上述の「ボーカルシンセサイザー」のようなコンピュータとスピーカーの組み合わせだけで音声合成するものは、かなり開発が進んでいて、メロディと歌詞を入力することで歌声の合成ができるものができているそうです。
特に有名なボーカルシンセサイザーはヤマハのVOCALOIDで、動画共有サイト利用者の間で爆発的に普及したそうです。2003年に発表され、編集ソフトの最新版は昨年暮れに最新版が出ています。
2010年にはこの装置とソフトを用いた「EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク」という曲が、VOCALOIDをボーカルに用いた楽曲を集めたアルバムで初のオリコン週間チャート1位を獲得したそうです。
メロディーと歌詞を入力することでサンプリングされた人の声を元にした歌声を合成することができるそうで、対応する音源については、主にヤマハとライセンス契約を締結した各社から販売されています。
これらの各社と契約した歌手から音声サンプリングを収録してライブラリを製作し、ヤマハ製のソフトウェア部分と組み合わせて製品として販売されているそうで、このサンプリングを過去のつんくさんの歌った歌で行えば、つんく版の音声合成はできそうです。
このほか、AquesTalk(アクエストーク)といった音声合成ソフトも出回っており、これは「アクエスト」という会社が開発・販売しているものです。
この技術を応用しているボーカルシンセサイザーもあり、2013年1月現在は試作品という形で無料にて配布されているといいます。
このように、声を失ったとはいえ、つんくのようにたくさんの声を録音しているような人はその過去の遺産を生かして、これをさらに別の曲に作り替えることもできるはずであり、音楽業界にお詳しい方であろうことから、当然こうしたこともご存知でしょう。
とはいえ、口で言うのは簡単で、それを実際に行うのは、ご当人も大変でしょうが、これを支える人達もまた大きな労苦が必要になってくるでしょう。
が、自分で発する言霊は失ったかもしれませんが、自分の意思で現在の技術を使って新たに生み出せる言霊もあるはずであり、従来作品以上に素晴らしい言霊をぜひ再び提供していってほしいと思います。御健闘をお祈りします。