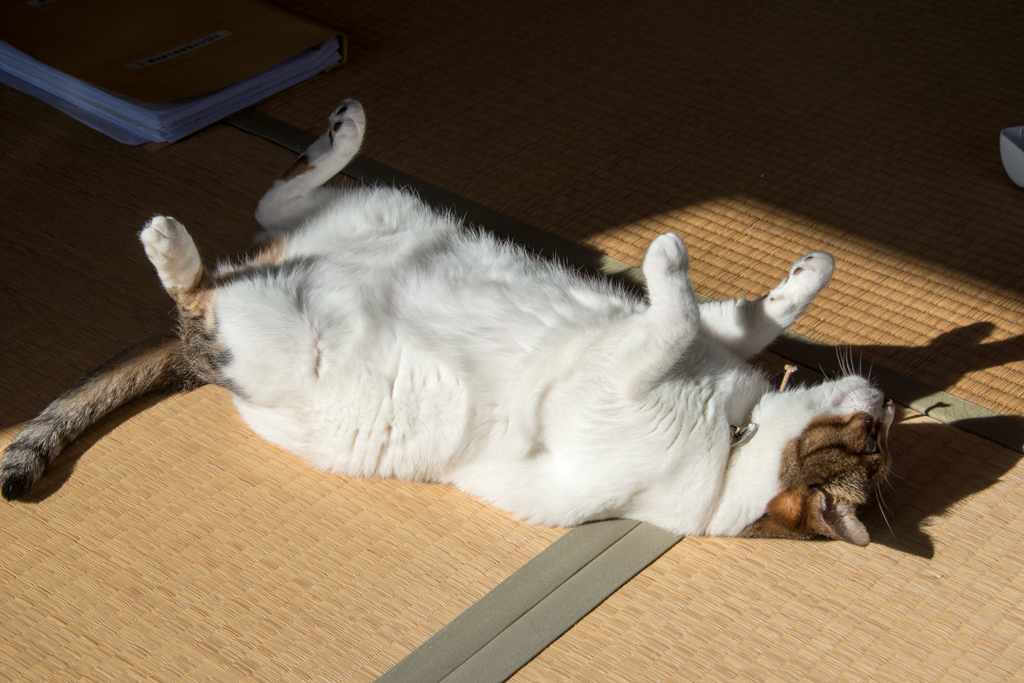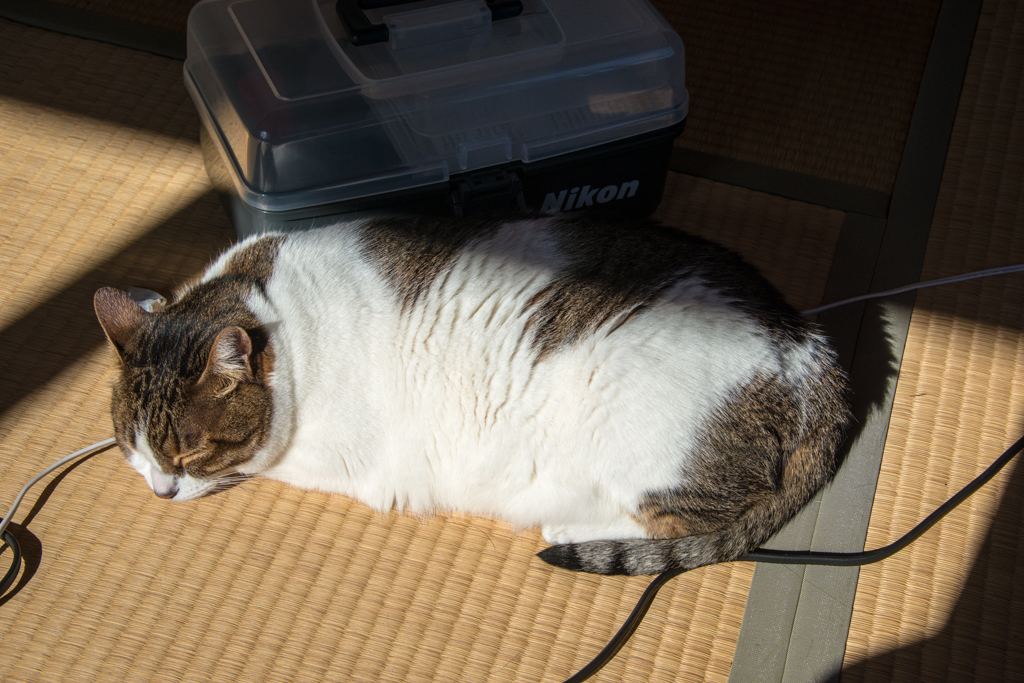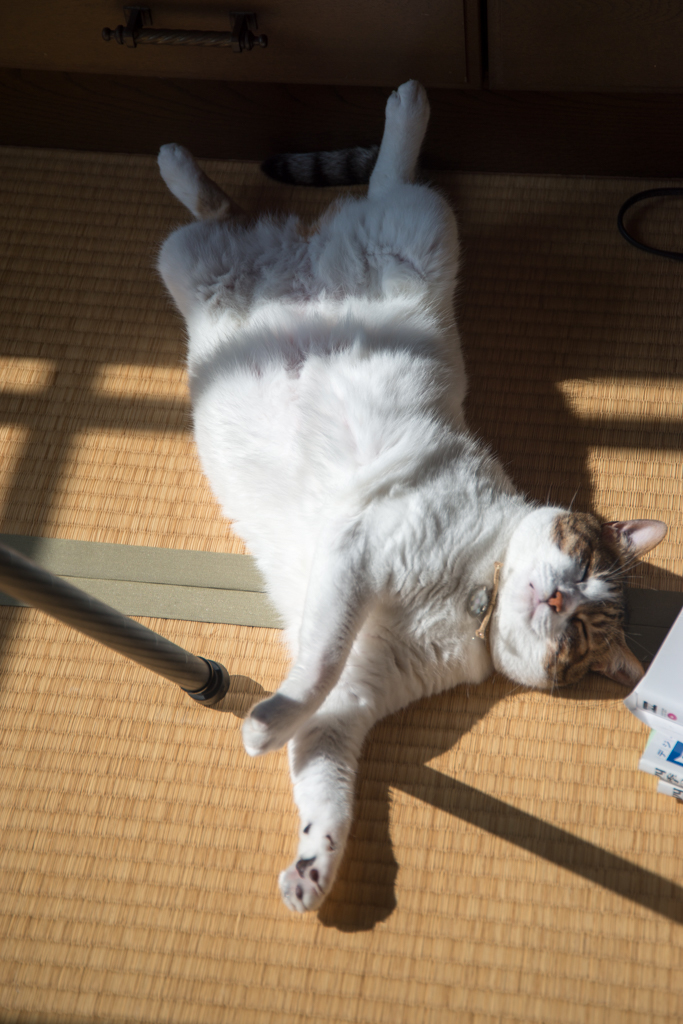最近、2005年に製造が中止になった、犬型ペットロボット「AIBO」に対する修理依頼が増えているといいます。
生産が中止になったあとも、ソニーは修理対応をしていましたが、それも2014年3月末で打ち切られたため、故障したAIBOの修理は困難となり、「死なないペットロボット」であったはずのAIBOに実質的な「死」が訪れることとなりました。
ところが、千葉県習志野市の電子機器修理会社がこのAIBOの修理を行ってくれるという口コミが広がり、修理依頼が殺到。
1999年に発売され、家庭向けロボットの先駆けとなったこのアイボの修理は、ソニーを退社したOBたちが立ち上げたこの会社にとっても初めてだったそうですが、社長は「やってみよう、道は必ずある」と引き受けたのが始まりだといいます。
ソニー時代のつてをたどって情報を集め、数カ月かかって何とか修理に成功。それが口コミなどで広がり、同社には全国からアイボの修理依頼が舞い込むようになり、これまで200体近くを修理しましたが、まだ260体余りが修理待ちの状況だそうです。
しかし、いずれ修理部品の枯渇は見えており、やがてこの会社での対応も行き詰ると考えられます。今年の2月には、飼い主によってAIBOの「合同葬儀」が執り行われたとい、これらのAIBOは、今後、故障した他のAIBOの「ドナー」となるといいます。
このアイボを創ったソニーは、トランジスタラジオ、トリニトロンカラーテレビ、ウォークマン…と数々のヒット家電を生み出してきた日本を代表する家電メーカーですが、ちょうどアイボの販売をやめた2005年ごろから元気がなくなりはじめました。
10年ほど前に退社した社員によれば、「社内が、売り上げなどお金の話ばかりになってきた」といい、昔は「お客さんにどういうサプライズを与えるか」を絶えず考えている会社だったのに」とかつての勤めた会社の凋落ぶりを嘆いています。
このソニーと入れ替わるように飛躍したのが米アップル社であり、2007年にスマートフォン時代の幕開けとなる初代「iPhone(アイフォーン)」を発売し、現在も日本国内のスマホの約6割を占めるまで業績を伸ばしました。
ソニーは、革新的な企業というお株をアップルに奪われた格好であり、ここでようやく、一つの技術が一つのヒット商品を生み出せる時代ではないと気づいたようです。
また、優れたハード、ソフト、デバイスを結集させ、さらにそこに「魅力」を醸し出すなんらかの「スパイス」を添加することができた企業だけが生き残れると考えるようになったようです。
このため、約1年前に、新規事業の開発につなげる“オーディション制”を取り入れました。100人程度の参加を見込んだこのプロジェクトの説明会には1200人もの応募があったといいます。
現在では、3ヶ月月ごとに新たなアイデアを募集し、合格した案件も3ヵ月枚に進捗状況をチェックしているそうです。このプロジェクトとは別に、30代の社員が着想した「電子ブロック」も市販の準備に入っています。
「MESH」というLEDや加速度センサーなどを備えたブロックを組み立てるDIYキットだそうで、タブレット画面上でアイコンをリンクさせるだけで連携して動かすことができるといい、これを使えば、レゴのように簡単に電子機器を自作できるようです。
かつてプレイステーションやネット銀行を世に送り出した「革新力」が胎動し始めているのでは、と業界からは期待を込めたエールがソニーに送られています。日本を代表するメーカーとして、ソニーは好業績だけでなく、常に革新につながる何かを期待される宿命を負っているといえるでしょう。「攻め」に転じるのはこれからなのかもしれません。
それにしても、アイボという製品を世に出し、「ペットロボット」というジャンルを確立した功績は大きいといえます。それまでにも類似の商品がなかったわけではありませんが、受け身ではなく自律稼働する装置が家庭に持ち込まれ、これを「ペット」と称した点は革命的でした。
「電気製品の日本」「ロボット大国日本」のイメージを世界に向けて強く発信したという面も功績の一つだといえ、おそらくはエンターテイメント装置としては歴史に残る金字塔を打ち建てた、といっても過言ではないでしょう。
近年では、このAIBOに代わるロボットが次々に登場しており、一般家庭に愛玩品や娯楽品、果ては「家族」という位置付けで、家庭の構成員すべてに愛されるべき様々な家庭用ロボットが発売される時代に入ってきました。
これらは人間とコミュニケーションを取ったり、自由に動き回って目を和ませたり、更には「ロボットの居る生活」という「近未来的な暮らしをしたい」という欲求に応えているといえます。人間型も増えてはいますが、動物型の方が多く、これらは主に、「ペット」という性格付けが強いことから、人間型よりも多く市場投入される傾向にあるようです。
この「家庭用ロボット」というヤツですが、本来はその動作を持って人の役に立つ事を求められる機械装置です。1960年代以降、SF小説や漫画・テレビアニメ・映画等でロボットが活躍する作品が増えるにつれ、こうしたロボットの動作している所を見たい・自宅に置きたいと考える人が増えました。
その潜在需要は次第に巨大な市場基盤を形成していき、1980年代から1990年代にかけては、潜在的な市場はさらに奥行を深め、人々をロボット展示のあるイベント会場や博物館に駆り立てました。しかし、制御するコンピュータの製造・運用コスト的な問題から、一般家庭に普及するにはあまりにも高価過ぎました。
また家庭進出を目指した先駆的製品では、高価な上に機能的には非常に限定された物で、使用するにはかなりの技術知識を要する物でもあることから、ほとんど普及する事はありませんでした。
その一方、「ロボットが欲しい」という欲求は衰える事は無く、ロボットと称した単なるラジコンやマイコン制御で簡単な動作を繰り返すおもちゃは数多く発売され、消費者の購買意欲を度々煽ってきました。
しかし、操作が複雑なわりには自動的に何かをやってくれる訳でもないこれら製品は、飽きられるのも早く、次々と新種の製品が出ては消えていきました。しかし新しいものがでるたびに、多くの購入希望者を出していたことは事実であり、「ロボット」という分野の市場を広めるという意味ではある程度の成功を収めたといえるでしょう。
そして、1990年代からは急速に、コンピュータの低価格化と高度・小型化が進みました。この中で1997年にAIBOが発表されるやいなや、なんだ、今はもう「本物のロボット」を“飼える”時代になっていたんだ、と人々は気づきました。
誰もがロボットを家に置く、ということは夢ではなく現実的な話だ、と誰もが思いはじめました。そして、個人的な玩具としてのロボットに寄せる期待は高まりに高まり、その期待の高さはAIBOの初売りの時に表出しました。
日本時間で1999年6月1日の午前9時にインターネット上でのみの販売で、一台25万円(動作を編集できる別売キットは5万円)もするこの製品は、計5,000台(日本国内3,000台・米国2,000台)が受付開始後たった20分で完売しました。
AIBOは、自分で判断して行動する他、持ち主が一緒に遊んだり、叩くなどの動作・声や音・光に反応する機能を持っており、これによって動作状況が変化するといった「動物的な反応」を主な機能にしていました。しかも各家庭のそれぞれ違う環境に応じてです。
言い換えればこれを「性格」とも考えることができ、そこが単なる機械ではなく、「ペット」として広く受け入れられた理由でしょう。それ以外にはちょっとしたゲーム的機能があるだけで、何等かの家事を分担させられるような、実用を目指した物ではなかったにもかかわらず、販売を開始した1999年以来、あわせて15万台以上を販売したといいます。
この成功を受け、その後ソニー以外の会社もこうしたロボットの開発に取り組むようになりました。その多くはAIBOのように犬や猫など、ペットとして親しまれている動物の形状をしたもの、あるいは、何らかのキャラクターを模したものなどが多く、「顔(頭部)」・「2つの目」・「手や足といった棒状の機能部分」を持っているのが特徴です。
コミュニケーションを取る際に何らかの意思表示を音声以外で行うものも想定されており、最近は目が光ったり、口を開いたりと言った動作によって「表情」に相当する動作をさせるものも多いようです。
円滑なコミュニケーションを図る機能が想定されており、コンピューターと人間の間での情報をやりとりするためのインタフェースである、「ユーザーインターフェイス」は最近のロボットにとってなくてはならない機能です。
これにより、こうした愛玩ロボットの中にはメールをチェックしたり、扱い状況を計測することがきるようになったものもあります。例えば自分にタッチされた回数を記録し、これを独居老人の安否情報として看護施設に送信したりする、といった機能がそれです。
また、動物アレルギーの人でも、」いわゆる「癒し」とされるアニマルセラピー的な好作用をこうしたロボに求めることができます。さらには、これらの愛玩ロボに住宅内の防犯・防災機能を持たせようという製品の開発や研究が行わつつあり、センサーと連動した「防犯ロボット」などが一部では実用化されているようです。
しかし、防犯ロボットなどになると、これはもう動物ロボットの範疇を出るところとなり、相手を威嚇するという意味では少々迫力に欠けます。このため、犬猫よりもむしろヒト型の方が良いということで、人の姿をしたもの、ヒューマノイド型、アンドロイド型の家庭用防犯ロボットの開発も急ピッチで進められています。
そうした人型ロボットの最前線にあるのが、テレビコマーシャルへの出演でも有名な、ASIMO(本田技研工業)のほか、HRP-2/HRP-3(川田工業・産業技術総合研究所・川崎重工業)、SDR-4X/QRIO(ソニー)・PALRO(富士ソフト)といった、二足歩行可能な人型ロボットです。
オーケストラを指揮したり、TPR(トヨタ)等のトランペットを吹いたり、ドラムを叩いたりする物も登場しており、こうした企業が製作した人型ロボット以外にも、ROBO-ONEのように、個人が趣味で製作したロボットを募集して競技大会を開催する、といったことも行われるようになってきています。
二足歩行ロボットによる格闘競技を中心としたロボット競技大会であり、2002年の初開催依頼、年々参加者が増え、昨年9月に開催された第25回ではエントリー数113 台、予選参加101体の盛況を博しました。
2000年代に入り、ロボットブームが盛り上がった中で本大会は生まれたこともあり、第1回大会から広く注目を浴びることとなり、そして早くより広く一般に知られたことから、2足ロボット関連の製品などが数多く発売され、安価なロボットキットの普及にも貢献しました。
現在では長年にわたって高い知名度を持つ高専ロボコンに勝るとも劣らない知名度を持つ大会となっています。今後は、ロボット競技としては異例とも言える宇宙を舞台にした宇宙大会も計画されており、ここから新たな分野のロボット産業が生まれていく可能性もあります。
これら人の形を目指したロボット開発は、古くからのSF作品で描かれた「人間社会に溶け込んで、人間と共同作業や共に生活するロボット」というイメージに沿ったものです。日本においては「鉄腕アトム」に触発されて二足歩行ロボット開発の道に進んだ、とする技術者も少なくありません。
前述のASIMOの開発陣のメンバーの多くはこの「鉄腕アトム」世代だそうで、その一方で、もう少し若い世代では「機動戦士ガンダム」に代表されるような巨大ロボットに触発されたという人も多いようです。このほか川崎重工のHRP-2/HRP-3は、「機動警察パトレイバー」で有名な出渕裕がデザインを担当したことでも有名です。
ちなみに、この「機動警察パトレイバー」は近未来の東京を中心とした地域を舞台としたアニメに登場する警察ロボットで、その姿を模したHRPは、映画の「ロボコップ」を彷彿とさせます。
これらの人型ロボットは、近年のコンピュータの高度化に伴い、施設案内業務等の仕事を実質的に任せることもできるほど高度なものも増えてきています。ASIMOは、イベント会場の客寄せにレンタルされるなど既に実用化されているといってよく、2002年にはニューヨーク証券取引所で、史上初めて「人間以外では初めて」取引開始の鐘を鳴らしました。
最近では日本科学未来館・ツインリンクもてぎ・鈴鹿サーキットホールメープル・Hondaウエルカムプラザ青山に常設され、訪れた人々の間を歩き回ったりもしています。
このほか、最近ソフトバンクの宣伝でよく見るようになった、pepper(ペッパー)もほぼ実用化を達成した人型ロボットです。「感情認識ヒューマノイドロボット」とされ、これはフランスのアルデバランロボティクスと同社に出資するソフトバンク傘下のソフトバンクモバイルにより共同開発されました。
「感情エンジン」と「クラウドAI」を搭載した世界初の感情認識パーソナルロボットだということですが、ヒト型ロボットといいながら足がありません。これは、二足歩行機能とすると連続稼働12時間以上の実現が難しくなるためと、コストを削減するためであり、このため、販売価格は19万8000円(税抜)とかなり健闘しました。
これは1999年に発売されたAIBOが、動作編集キット込みで30万円もしたのと比べれば格安といえるでしょう。開発者向け初回生産300台が今年の2月27日に開始されましたが、ものの1分で売り切れになったといい、また先の6月20日に開始された一般向け販売1000台に関しても、受付開始1分で完売となりました。
現在、Pepperの生産体制では、月間で最大でも1000台が生産台数の限界とされているため、次回以降の販売についても1月当たり1000台程度になるとみられているようです。
既に2014年末からはネスレ日本のネスカフェにおいて、接客を開始しており、このほかカラオケ店JOYSOUND八丁堀店で夜間の接客が始まっていますが、こうして購入されたペッパーが町のあちこちで見られるようになる日もそう遠くないでしょう。
従来、家庭向けといわれるロボットは、自律的な動作しない「玩具」に分類される物多く、大半が動物型でしたが、人工知能の研究が深まるとともに、このペッパーのような人型タイプが増えていく傾向にあるようです。人類が四足で歩くサルから進化してきたように、ロボットも進化しているというわけです。
動物型と違って、「友達」感覚で対話が楽しめるのもこうした人型ロボットの特徴です。各種イベントで登場し、歩き回りながら、人間と「コミュニケーション」をとるものも多くなり、家庭用ロボというよりは「エンターテインメント・ロボット」と呼ばれることも多くなってきました。
従来の家電製品・玩具・家具・インテリア・情報機器(パソコン・テレビゲーム等)のいずれにも属さない、かなり新しいジャンルの工業製品であるといえます。Pepperに代表されるようにそれなりに価格も手ごろとなり、高価なわりには機能が低く、しかもただのペットにすぎなかったAIBOとはまた一味違う魅力があります。
しかし、こうした家庭で用いられるロボットでは、安全性が最優先となります。もし誤動作して家庭内の器物を損壊させたり、人だけでなく、それこそ本物のペットに怪我を負わせるなどした場合は、メーカー側の責任を問われる事にもなりかねません。
ただ、現在のエンターテインメント・ロボットでは、自意識が存在せず、動力もさほど強力ではないため、過度の気遣いは必要ないかもしれません。が、いずれはさらに高度化するに伴って、さらに高知能を持ち、かつ大型化、強力化される可能性もあります。
こうなると、古くからSFで問題視される「フランケンシュタイン・コンプレックス」の発端に成りかねないという意見もあります。これは、自律性を持つ人間の創造物に、人間が迫害されるかもしれないという懸念です。

ただ、そこに至るまでにはまだまだ相当時間がかかるでしょう。現在開発が進められているエンターテインメント・ロボットでは、むしろそうした懸念よりも人間といかに自然なコミュニケーションを取れるようになるか、といった機能が重要視されており、ロボットを人間に近づけるためには、このことが最重要課題といわれています。
人間は感情の生き物であるわけですが、それら感情をロボットが感じ取り、適切な応答を返す事が求められているわけです。ということは楽しい愉快だといったことばかりではなく、悲しい寂しいといった感情のほか、「怒り」もその対象に含まれます。このため、その一端として「口喧嘩する事の出来るバーチャル・キャラクター」の研究も行われています。
が、現段階では予測された範囲内でしか対応できない事もあり、対話しているとわけのわからないことで怒りだすので、「別の意味で苛立つ」といった問題もあるようです。
ただ、将来的には声の抑揚だけではなく、表情や仕草でも感情を読み取り、予め適切であるとしてプログラムされた物であるにせよ、それに対して自身の感情を身振りでも表現する事の出来るような対話型ロボットが登場するのではないでしょうか。
この他にも、連続して動作させるために「空腹」を感じて自分で充電する機能や、学習した情報を適切に処理して行動に反映させていく機能、少々乱暴に扱われても自分で対処する機能も必要です。
さらには、屋内のどんな環境にも対応できる必要があります。そのロボットを置くためにわざわざ部屋の大改装が必要になる、といったものは困りものであり、引越ししたら使えなくなったというのも問題です。家屋内の何処のどんな環境でも対応できる、自在に環境に対応し得るだけの判断力も求められています。
そうした中においても人間との対話は不可欠であることから、上述のユーザーインターフェイスの開発はとくに重要です。言語によるコミュニケーションが想定される一方で、仕草や表情と言った、人間間で重視される非言語的なコミュニケーション手段も必要とされており、場合によっては「手話」ができるロボットも必要かもしれません。
しかし、その一部ではなまじ人間に似た外観を目指したために、いわゆる「不気味の谷現象」を起こすものもあり、この辺りの改良も視野に入れて研究が進んでいます。
不気味の谷現象というのは、はロボットや他の非人間的なものに対する人間の感情的反応です。一般に、外見と動作が「人間にきわめて近い」ロボットと「人間と全く同じ」ロボットは、見ればすぐにわかります。
その見る者の感情的な反応をポリグラフのようなもので測定してグラフ化した場合、著しく「感情が低下する」ケースがあり、これが「不気味の谷」です。
いわゆる「嫌悪感」というヤツで、人間とロボットが生産的に共同作業を行うためには、人間がロボットに対して親近感を持ちうることが不可欠ですが、この不気味の谷に陥った「人間に近い」ロボットは、人間にとってひどく「奇妙」に感じられ、親近感を持てません。
この現象は、対象がある程度「人間に近く」なってくると、非人間的特徴の方が目立ってしまい、観察者に「奇妙」な感覚をいだかせるために起こります。一方、対象が実際の人間とかけ離れている場合、人間的特徴の方が目立ち認識しやすいため、親近感を得やすくなります。これはつまりは、マネキン、あるいは死体とゆるキャラの違いに似ています。
ヒューマノイドが多くの不自然な外観を見せるのは、病人や死体と共通するためであり、こうした場合にはロボットに対して同じような警戒感や嫌悪感を抱きます。しかも死体の場合、その気持ち悪さはわかりやすいものですが、ロボットの場合は、それがいったいなぜ気持ち悪いのか、明確な理由がわかりません。
ゆえに、実際の死体よりも不気味に感じることさえあり、動作の不自然さもまた、病気や神経症、精神障害などを思い起こさせ、時に不快な印象を与えます。ロボット開発における不気味の谷の最大の問題は、この不快だ、不気味だ、と思う感情をどうやったらV字回復できるかという点です。
というのも、本当に完全な人間に近づけば好感度が増すのか、それとも「人間と全く同じ」にすれば好感を持ってくれるのかがわからないのです。なぜかといえば、まず、これまではまだ「人間と全く同じ」ロボットが作られていないため、それがどの程度不快なものなのかが誰にも分かりません。
たとえ「人間と全く同じ」だとしても、ロボットだと聞いたとたんに、なーんだ、ロボットじゃん、と不快感を持つ可能性もあり、ロボットが完璧すぎることがその答えとはいえないわけです。また「限りなくロボットに近い」ものができたとしても、それはどこかやはり人間と違うものであり、いつかどこかで親近感を失う可能性があります。
こうした研究は進みつつあるようですが、いまだ確固たる結論が出ているわけではありません。ただ、最近はCGにより「人間臭さ」を表現する手法の研究が進んでおり、不気味の谷に落ちないように人に良い感情を抱かせるため、登場人物の人間的な特徴のどこを少なくすれば良いのか、といった知見がかなり蓄積されてきています。
3D技術を使ったバーチャルなキャラクター開発も進んでおり、近いうちにはこの不気味の谷問題にも解決の糸口が見つかるかもしれません。
ところで、こうした人型ロボットではありませんが、最近、極めて「動物に近い」ロボットがアメリカで開発されて話題になっています。ビッグドッグ(BigDog)という愛称が付けられており、2005年にアメリカのボストン・ダイナミクス社とジェット推進研究所、ハーバード大学が開発した四足歩行ロボットです。
ビッグドッグは起伏の多い地形で歩兵に随伴出来る輸送用ロボットとして用いるため、米軍の国防高等研究計画局による資金提供で開発されたため、カテゴリーとしては「軍事ロボット」ということになります。
テレビのニュースでご覧になった方も多いかもしれませんが、その歩行の様子は幾つかの動画共有サイトに掲載されています。まるで向かい合った二人の人間が足踏みしているかの様な、機械とは思えぬ特徴的なロボットでそのユーモラスな動きが話題を呼んでいます。
荒い砂利道、雪上、砂浜、及び海の浅瀬などでも問題無く歩行でき、また、歩幅が非常に小さくはなるものの、急な勾配も登る事ができます。35度の傾斜を登る事も可能であり、かつて軍馬が担っていた勾配のある不整地での物資輸送を担うことが期待されています。
横から胴体部分を蹴られても倒れる事無く即座に姿勢を復元でき、氷上で足を滑らせても素早く体制を立て直す事で転倒にはいたらず、その姿勢制御技術の高さは見事です。転倒対策に半円のボディを採用し、転倒時は反動を利用して自力で起き上がることができるためです。
また、通常は左右の脚を互い違いに進ませて歩行しますが、馬のギャロップの様に疾走させ、ジャンプして障害物を飛び越えさせる実験も行われており、現時点では脚を素早く動かし時速8km(5マイル)の速さで走ることもできるようになりました。
荷物を積んだままの歩行もできます。車輪では走行不能な地形において、154kgの荷物を搭載したまま時速5.3kmでき、最近では180kgの荷物搭載で30km踏破する事が可能になったそうです。30kmというのは一回の燃料補給で走る事が出来る距離であり、燃料を足せばさらに長距離を歩く事ができます。
取り付けられた一本のアームでコンクリートブロックを掴み、それを放り投げることもでき、ブロックを投げる際、人間の運動選手が行う様に脚や胴体を総合的に使う事もできるようです。
さらには、GPS機能を使用し自動で目的地へ移動する事もでき、兵士を認識して追尾する機能も備えるといい、足には姿勢制御用の接地センサーを持ち、レーザージャイロとステレオビジョンで地面の傾きなどを把握できるともいいます。ここまでくるとまさにハイテク技術を駆使した大型ロボット犬です。
既に2012年からアメリカ海兵隊で運用試験が始まっており、音声指示が可能となっているほか、既に今年あたりから実運用開始が開始されたという情報も入ってきています。
15馬力の2ストローク単気筒ガソリンエンジンを搭載し、毎分9000回転で油圧ポンプを駆動することで作動します。これにより作られた油圧で各脚4本、合計16本の油圧アクチュエータを作動させ、スムーズな歩行を実現しているそうです。
「大きな犬」という名称ですが、サイズは子牛ほどもあり、全長約1m、高さ約70cm、重量約110kgもあります。Calf(子牛)のほうがより適切なネーミングのような気もしますが、これをビッグ・ドッグとあえて呼ぶのはアメリカ人なりのユーモアでしょう。
アメリカではこのロボットのような特殊用途のロボットも数々研究されているといい、二足歩行のPet-Proto、PETMANなどが存在します。Pet-Protoのほうは、上述のHRPに似ていますが、PETMANのほうは、まさに「ロボット兵士」と言った趣です。
このほかビッグドッグを小型化した、その名も「リトルドッグ」というものもあり、こちらも同様に不整地踏破性が強く、学習機能により的確な接地点を判断したり、姿勢制御や踏み外した時での復帰制御、踏む力の自動調整などに優れ、動作も高速です。
さらに小型化された高速移動を重視したタイプに「ワイルドキャット」と言うモデルも開発されているようですが、これこそネコというよりも、「ドッグ」と言った感じです。
ちかいうちに、さらに小型のネコ型高速ロボを開発して欲しもの。うちのテンちゃんを模した、「マイルドてんてん」というネーミングはどうでしょう。一緒に走れる日が来ることを夢見ましょう。