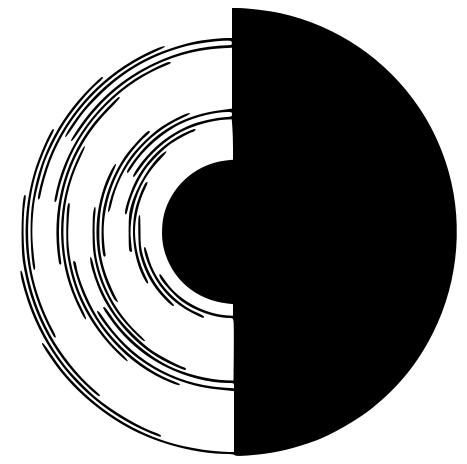9月になりました。
まだまだ秋本番にはほど遠いようですが、朝晩かなり冷え込むようになり、日が短くなってきました。私の大嫌いな夏も遠からず終わりを告げるのは確かであり、いずれ、そこここを赤とんぼが飛び回るようになるのでしょう。
トンボは漢字で「蜻蛉」と書くようですが、この赤とんぼは、「赤卒」とも書くようです。
中国語でもこれで通じるようですが、なぜ「卒」の字をあてるのか調べてみたところ、この文字には「にわかに」、「急に死ぬ」、「終える」、という意味があるようです。なので、秋の終焉を迎える虫ということで使うのかもしれません。赤とんぼが終わるころには、秋が終わり、冬がやってきます。
赤卒は「せきそつ」と読む一方で、「あかえんば」とも読むようです。こちらも由来を調べてみたのですがよくわかりません。飛騨地方の方言で「えんば」とは、もうじき、もうすぐ、という意味のようなので、こちらもやがてやってくる冬を意味するのかもしれません。
昆虫の分類上、赤とんぼといえば、普通「アキアカネ」を指すようです。こちらは「秋茜」と書き、秋にふさわしく、哀愁を感じさせるネーミングです。トンボ科アカネ属に分類される日本特産種で、日本では小笠原諸島、沖縄県を除き各地で普通に見られる種です。
平地から山地にかけて、水田、池、沼、湿地などにヤゴとして生育します。孵化した未熟な成虫は夏に涼しい山地へ移動し、成熟し秋になると平地に戻る、という習性があります。他の多くのトンボも未成熟成虫が水辺を離れて生活しますが、アキアカネの場合この移動が極端に長距離なのが特徴です。
5月末から6月下旬にかけての日中の気温が20-25℃程度のとき夜間に羽化します。まれに標高2000m代の高所からの羽化記録もあります。成虫となったアキアカネは朝になると飛び立って水辺を離れ、1週間ほどを摂餌に費やします。
様々な小昆虫を空中で捕食し、長距離飛翔に必要なエネルギーの蓄積を行います。十分に体力がついた段階で3000mぐらいまでの高標高の高原や山岳地帯へ移動して、7~8月の盛夏を過ごします。そして、夏が終わるころ、通常は秋雨前線の通過を契機に大群を成して山を降り、ふたたび平地や丘陵地、低山地へと戻ってきます。
なぜ移動するか、ですが最も大きな理由は暑さが苦手なためです。アキアカネが活動中の体温は外気温より10~15℃も上昇するそうです。にもかかわらず排熱能力が低いため、気温が高い場合は簡単にバテてしまいます。30℃を超えると生存が難しくなるといい、このあたり、25℃を超えると生息が危うくなる私とよく似ています。前世は赤とんぼだったか?
逆に低温時におけるアキアカネの生理的な熱保持能力は高く、秋の終わりごろになり、大半の虫が死に絶えるころになっても平気です。ただ、ちょっと残暑が厳しくなると涼しい環境をみつけて移動します。酷暑の年には移動先はより高い標高の地域となり、冷夏の年にはそれほど高いところまでは移動しないこともわかっています。
普通にじっとしているときも何気に暑さ対策をしています。夏の昼間の日差しが強い時間帯に、止まっているアキアカネが逆立ちをしているのをよくみかけますが、これは、日光が当たる面積を減らし体温の上昇を抑えるためと考えられています。
赤い色をしているためか、危害を加えると罰が当たるとする言い伝えもあるようです。東北地方では、捕まえると雷に打たれるとして「かみなりとんぼ」と呼びます。また、東海地方では目が赤くなったり腹が痛くなったり、瘧(おこり・マラリア)などの発熱発作を起こすとする伝承があります。
アキアカネに限らず多くのトンボは害虫を食べてくれるので、むやみに殺生することを戒めため、こうした伝承がうまれたのでしょう。あるいは、秋に真っ赤になるほどの大群で出現するため、その姿に何らかの霊性を認めたためかもしれません。同じく秋の赤い色の風物詩といえばヒガンバナがあり、こちらは“あの世”である「彼岸」にちなんでいます。
赤い色をしたトンボにはこのほか、「ナツアカネ」と呼ばれる種があり、アキアカネは夏に一旦低地から姿を消し、秋に出現するのに対して、こちらは一夏中低地から姿を消しません。「ナツ」の和名が与えられたのはこのためのようです。ただ、アキアカネに比べ、相対的に数は少なく、夏の間でもほとんどみかけない地方も多いようです。
いずれも同じアカネ属に分類される近縁種ですが、高地と平地でそれぞれ棲み分けがなされているのは、おそらくその生活史の中での食餌環境をシェアするためでしょう。ナツアカネのほうが少ないのは、同じ平地においては競争相手として他のトンボもいるためと考えられます。
なぜ赤い色をしているのか、ですが、これは彼らの生殖行動に関係があるようです。通常アキアカネもナツアカネもオスはメスに比べて赤色が濃いようで、これは交尾のためによりメスにアピールするため、といわれています。メスが性的に成熟したオスを識別しやすくするためでもあります。
また、赤く見えるということはその色をはね返しているということでもあり、青や紫、さらに紫外線などの波長の短い光を吸収しやすいということです。紫外線などの波長の短い光は、高いエネルギーを持っています。それを吸収しやすいということは、晩秋のよう寒い時期になっても体温を暖かく保てる、ということになります。
暑さに弱いという特徴があるのに矛盾しますが、寒い季節になっても保温能力が高いということは、摂餌においてはそれだけ他の昆虫に比べて有利になります。また、とくにオスが日なたにとどまって縄張りを守る際には役立つ、といったこともあるようです。
この「赤」という色名ですが、あらゆる文化には、それぞれ化特有の特徴を持った色があり、呼び方はさまざまです。文化の背骨となっている言語の中で生まれてきたものであり、日本語では「赤」ですが、中国語で赤という場合は「紅」になります。こうしたある文化で生まれた固有の色名を「基本色名」と呼びます。
日本のJIS規格での基本色は、無彩色としては白・灰色・黒の3種類であり、有彩色では赤を含めて10種類が採用されています。アメリカでは13種あります。
ところが、色というのは、そんな単純なものではなく、特別な名前が付けられた色や、また名前の付けられていないような色が、それぞれの国でゴマンとあります。ただ、それらは全て基本色名で言い換える事ができます。
例えば、日本では黒みがかったシブい赤色で「蘇芳色(すおういろ)」というのがありますが、これも基本色名である「赤」と言い代ることができますし、空の色や海の色などをまとめて「青」と呼んでいます。
同様に、基本色である赤にはほかにも、朱(シュ)、丹(タン)、緋(ヒ)、紅(コウ)などがあり、それぞれが日本の長い歴史のなかで文化的な意味を保ってきました。
基本色名である「赤」の語源は「明(アカ)るい」に通じるとされます。「赤恥」、「赤裸(赤裸裸)」などの用例のように、「明らかな」、「全くの」という意味を持つとともに、暗黒の世界の象徴である悪霊や病気に対する効果がある色とされてきました。
古来日本では、疱瘡(天然痘)をもたらす疫病神(疱瘡神)が赤色を嫌うと信じられており、患者の周囲を赤で満たす風習がありました。また沖縄では病人に赤を着せ、痘瘡神を喜ばせるために歌、三味線で、痘瘡神をほめたたえ、夜伽をしたといわれます。
そのほかにも、赤系の色はさまざまな文化的意味を持って使われてきました。中でも特筆すべきなのは、朱色です。
朱は、硫化水銀(HgS)からなる鉱物から採れる「辰砂」から作られます。平安時代には既に人造朱の製造法が知られており、16世紀中期以後、天然・人工の朱が中国から輸入されるようになり、中国の辰州(現在の湖南省近辺)で多く産出したことから、「辰砂」と呼ばれるようになりました。中国では古くから錬丹術などでの水銀の精製の他に、顔料や漢方薬の原料として珍重されていました。
日本では弥生時代から産出が知られ、古墳の内壁や石棺の彩色や壁画に使用されていました。漢方薬や漆器に施す朱漆や赤色の墨である朱墨の原料としても用いられ、古くは伊勢国丹生(現在の三重県多気町)、大和水銀鉱山(奈良県宇陀市菟田野町)、吉野川上流などが特産地として知られていました。
色料としての朱の範囲は比較的幅があり、例えば「黄口」や「青口」といったものがあります。赭土(三酸化二鉄)、鉛丹(四酸化三鉛)、鶏冠石(硫化砒素)を加えるか、それ以外の顔料や染料、或いは他の朱色の発光物の混合に基づいて、いろいろなバリエーションがあり、これらの混合の度合いで朱の色合いが定まります。
この朱を作る材料のひとつ、赭土(しゃど)は、別の赤色である「丹(タン)」を生み出します。発色成分の三酸化二鉄は、いわゆる赤土に多数含まれているものです。要は鉄が錆びたものであり、古来から日本国中どこでも容易に入手できる顔料のひとつです。鶴の一種タンチョウの和名は、頭頂部(頂)が赤い(丹)ことに由来し、“丹鳥”の意です。
朱や丹が鉱物から生み出される赤色であるのに対し、緋(ヒ)は、植物性由来の色で、「アカネ」の根を原料とします。「茜染」といわれる染物に古来から使われてきており、濃く暗い赤色を「茜色」というのに対して、最も明るい茜色を「緋色」といいます。
日本では大和朝廷時代より緋色が官人の服装の色として用いられ、紫に次ぐ高貴な色と位置づけられました。また江戸時代には庶民の衣装にも広く用いられていました。ちなみに、緋色は英語圏の色、scarlet(スカーレット)とほぼ同じ色と言われています。
紅(コウ)は、くれない、べに、とも呼ばれ、こちらも植物性です。キク科の紅花の汁で染めた赤色で、鮮やかですが、やや紫を帯びており、中国に由来するとされることからで「唐紅(からくれない)」とも言います。ほかに古来から染料として利用してきた色に「藍」があり、“くれない”は「呉の藍」(くれのあい)から来ている、という説もあります。
現在の中国や旧ソビエト連邦をはじめ、共産主義のシンボルとしても使われています。紅花の原産地はエジプトとアナトリア半島といわれており、このためか、どちらかというと他の赤い色よりもエキゾチックなイメージがあります。
このように、日本における赤色は、他の基本色と比較すると、かなりバラエティーに富んでいます。以上は代表的なものにすぎず、いわゆる赤系の「和色」と呼ばれるものは、分類法にもよりますが、だいたい90種類ほどもあるようです。日本の国旗の色でもあることを考えると、日本人というのは赤という色に相当のこだわりがある国民のようです。
ちなみに、日章の色に定められているのは、輸入色ともいえる「紅色」で、マンセル色体系(色を定量的に表す国際的体系)で 3R 4/14 です。ただ、より明色に見える朱色系の「金赤(同 9R 5.5/14)」が使われることも実際には多いようです。いずれにせよ、より日本的な色である朱や丹が使われていない、というのは不思議なことではあります。
この赤色に限らず、一般に色は、生活や文化、産業や商業、デザインや視覚芸術の重要な要素であるため、多種多様なものが生み出されてきました。「様式」「作風」「文化」の特徴の一つとして、特定の色の使用、特定の色の組み合わせ、色と結び付いた意味などが含まれている場合も多く、色に関していえば、広辞苑や国語辞典のような一般的な辞書というものは存在しません。
また、色は様々な感情を表現したり、事物を連想させることがあり、時代や文化による影響も大きいといえます。たとえば今日では喪服は黒が一般的ですが、江戸時代までは白が一般的でした。
ただ、「赤」 ついていえば、太古の昔からおおむねその意味は変わっていないと思われます。日の丸の赤は太陽を表しており、すなわち日本そのものですし、このほか血や生命、火に関するものも赤、女性も赤です。現代的なものとしては、左翼、革命、力、愛、情熱、危険、熱暑、勇気、攻撃、敵、といったものも赤で示されることが多く、電気や信号も赤で表現されることがあります。
交通信号などでは、赤色が停止や危険を示す表示として使われるほか、日本の消防車の車体色は運輸省令「道路運送車両の保安基準(昭和26年号)」で朱色と規定されています。フランス、イギリス、スイス、オーストリア、アメリカの一部の州等でも消防車の色に赤を用いています(ドイツでは赤または紫)。
このような場合に赤が使われる理由としては、人間には感知し易い色と知覚し難い色があるためです。色が人の注意を引きやすく目立つ度合いを、色の「誘目性」と呼び、無彩色よりも有彩色、寒色系よりも暖色系のほうが誘目性が高く、赤は暖色系です。
また、赤や黄などの暖色系の色および白色は実寸より物が大きく近くに見える膨張色で、他の色より知覚し易くなります。日本の児童の帽子やランドセルカバーが黄色なのは、知覚し易く、大きく見える色を採用する事で自動車事故を減らす狙いがあるからです。
ちなみに、青や黒等の寒色系の色は実寸より物が小さく遠くに見える収縮色です。誘目性も低く小さく見えるため、実際に黒色の自動車は他の色に比べて事故が多く、バスやタクシーが黒色を避けているものが多いのはこのためです。また、囲碁の碁石も黒石と白石が同じ大きさだと黒石の方が小さく見えてしまうので、黒石を一回り大きく作っています。
また、赤を多用するのは人間の生理にも基づいているためともいわれます。乳幼児は赤色を強く認識するので、乳幼児の玩具は赤色を基調に作られています。また、子供部屋を黄色や赤の暖色を基調に作ると、知能指数が高い子供が育つという説があります。
さらに、年齢を重ねると波長の短い青色緑色系統の色は黒っぽく見えるようになりますが、波長の長い赤色は比較的年長の方でもよく見えます。ちなみに、老人性白内障に罹ると水晶体が黄色く濁り、より青色緑色系統の色が見えにくくなります。このため、老人はガスコンロの青い炎が見えにくく、火傷や火事を起こし易いといわれます。
生理学的に言うと、人間の目は、赤、緑、青の光を感知する「錐体」によって様々な色の視覚情報を知覚していますが、このうちL錐体は「赤錐体」と呼ばれ、赤色を感知する錐体です。その分布密度はM錐体(緑)の2倍、S錐体(青)の40倍もあり、他の色に比べて赤色光に対する感度が高いということがいえます。
これをもう少し詳しく説明すると、ヒトの目の網膜内には、L錐体・M錐体・S錐体と呼ばれる3種類の「錐体細胞」があり、これらが吸収する可視光線の割合が色の感覚を生んでいます。
これらの錐体細胞は、それぞれ長波長・中波長・短波長に最も反応するタンパク質(オプシンタンパク質)を含んでいます。錐体が3種類あることはそのまま3種の波長特性を構成する元となるので、L , M , S の各錐体を赤・緑・青でなぞらえることもあります。
ところが、人や猿などの霊長類における錐体はかつて2種類だったそうです。色刺激の受容器である目の進化の過程で、2種から3種に分岐したとされており、ヒトを含む旧世界の霊長類の祖先は、約3000万年前、3色型色覚を有するようになったといわれています。
これに対して、ヒトと同じ哺乳類の多くは2色型色覚か、色覚を持ちません(実は色覚を持っているがその感度が低い)。目の進化の過程で取り残されたかたちです。
ところが、さらに、です。この哺乳類のさらに祖先である古代の爬虫類は、もともと4色型(4色型色覚)だったそうです。上のL、M、Sに加えて4つ目の色覚がありました。
この4番目の色覚とは、波長300~330ナノメートルの紫外線光を感知できる錐体網膜細胞のことで、これによってこれらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までの色を認識できるものと考えられています。
哺乳類の祖先ももともとこの4つ目の色覚を加えて4錐体細胞を持っていましたが、これがある過程で2種類になりました。
その理由としては、哺乳類だけは他の種類からの捕食を恐れて、夜や暗い所で活動することが主となったためです。わずかな光でも見えるよう桿体細胞(光の刺激を受容する細胞)が発達し、その代わりに2色型色覚になり、色覚そのものを失ったとされます。
夜行性となったため、色覚は生存に必須ではなく、結果、M錐体(緑)と紫外線感知錐体の2タイプの錐体細胞を失い、青を感知するSと赤を感知するLの2錐体のみを保有するに至りました。これは赤と緑を十分に区別できないいわゆる「赤緑色盲」の状態です。
変わらず昼夜ともに活動が活発だった魚類、両生類、爬虫類、鳥類はそのまま4色型色覚にとどまり、この名残で現在でもこれらの種のほとんどは4タイプの錐体細胞を持っています。
一方、2錐体のみを保有するに至った哺乳類のうち、ヒトを含む旧世界の霊長類の祖先は、上述のとおり、約3000万年前、突然3色型色覚を有するようになりました。3000万年前といえば、氷河期が終わり、ようやく地球全体が緑に包まれるようになった時代であり、このころ2色型色覚(赤緑色盲)に退化した哺乳類から、人や猿の先祖である霊長類が分科しました。
その理由としては、ビタミンCを豊富に含む色鮮やかな果実等の獲得と生存に有利だったためと考えられ、霊長類が暮らすようになった「森の環境」がその原因です。
森の中というのは、うっそうと木々が生え、緑と緑陰に囲まれた場所です。こうした環境では、果実が熟した時などに、葉の緑の中から赤を識別できるかというと、2色型色覚ではそれができません。
明度(明暗)が違えば識別できますが、常時ほぼ同じ明度の森の中では、色度だけをたよりに果実を区別しようとしても周囲の緑に完全に埋もれてしまいます。ところが、3色型の色覚なら、緑の背景から黄色やオレンジや赤っぽい果実がポップアップして見えます。
これが、ヒトや猿が現在のように3つの錐体を持つに至った理由と考えられています。ただ、ヒトに関して言えば、その他の猿とは違って、その後狩猟生活をするようになりました。このため、果物などの植物に依存して生活する必要がなくなり、若干この3色型色覚の優位性が低くなったといわれており、それは他の霊長類に比べて色盲が多いことからもわかります。
色盲の出現頻度は狭鼻下目のカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%です。これに対し、日本人では男性の4.5%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされます。またニホンザルもヒトよりも色盲の数が非常に少ないことがわかっており、3色型色覚という点では人はやや退化した状態ということになります。
イギリスのロマン主義の画家、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775~1851)は、黄色を好んで使用したといわれています。彼の絵具箱では色の大半が黄色系統の色で占められていたといい、逆に嫌いな色は緑色で、緑を極力使わないよう苦心したそうです。このことから色覚異常ではなかったかと言われており、同様にやゴッホ、ピカソやシャガールなど著名な画家達も色覚異常であったのでは、との説があります。
ターナーは知人の1人に対して「木を描かずに済めばありがたい」と語っており、また別の知人からヤシの木を黄色く描いているところを注意された時には、激しく動揺していたといいます。近代社会においても、とくにアニメなどのように、生理的な識別が容易で単純な色を多用する分野・領域では、色覚異常者はとかく肩身が狭い思いをしています。
しかし、色覚異常といわれているのは、あくまで標準的な色覚を持っている人に対しての評価であり、一般に普通と言われている人であっても、色覚に関しては大小の差異があります。人が色として感じる感覚には非常に多くのものがあるといわれており、赤色の和色が90種あるように、他の国の基準を入れればもっと多くの赤色の分類ができるでしょう。
こうした色覚の違いが表面化するのは、同じように見えるもののその見え方の違いが微妙であるため、お互いの意見に疑義が生じるなどの場合です。大多数の人がはっきりと同じものだ、あるいは異なる、といった判断をしているのにそれは違う、という人はその生理については色覚異常、機能については色覚障害というレッテルを張られてしまいます。
ところが、色覚が正常といわれている普通の人々の生活の上においても、印刷や塗装の過程において、いつもとは異なり、明るく鮮やかな色を多用するとか、色素の濃度を高くしたり塗料を厚く塗ったりすることはママあります。色の飽和度を高くしたり、色素の存在比を大きくして生理的な弁別の容易さを高めるなどした結果、結局はオリジナルとはかなり変わった色になってしまった、というのはよくあることです。
上で色覚異常が疑われている画家たちに関しても、彼らが生きていた時代には用いる絵具などの画材の消費量は少なく、また使用法も厳密ではありませんでした。一般に原料の品質も低く、このため発色が良くないものも少なくなく、より古い時代はなおさらです。従って、上の有名画家たちが本当に色覚異常だったかどうかはわかりません。
さらに、同じ組成の光を受けた場合でも、それをどのように知覚するかは人それぞれの目と脳の相関関係によって異なるので、複数の人間が全く同一の色覚を共有しているわけではありません。同様に、ある人が同じ物を見ても右目と左目では角度や距離が異なり、見えた色も一致しないことがわかっています。他者の色知覚を経験する手段は存在せず、同一の色知覚を共有することも不可能です。
また、知覚した色をどのような色名で呼ぶかは学習によって決定される事柄であり、例えば赤色を見て二人の人間が異なる知覚を得たとしても、二人ともそれを「赤」と呼ぶので、色覚の違いは表面化しませんが、実際にはイチゴ色とサンゴ色ほどに違っていたりします。
近年、人間以外の様々な生物の色覚を知ろうとする試みがあり、色覚の有無や性質が研究されていますが、こうした研究もはたして人間が感じるのと同様な色を感じているのかどうかを確認することでその生活史を探るためです。違った色の見え方をする人を比較してみた場合、その世界は青と赤ほども違っている可能性もあるわけです。
もっとも、文明が発達した人間社会ではそれでも共同生活は可能です。複数の個体間で知覚される色がどのような色であるかを直接すり合わせることは出来ませんが、人間同士であれば言語やカラーチャートを用いて情報交換することが可能だからです。色の違いで混乱がおきないのは、人間がこうした高度な科学力を持っているからです。
なので、この項で強く言いたいのは色覚に「異常」というものはなく、それは個性だということです。
ヒトも生物である以上、色覚の個体差があるのはあたりまえであり、このように色の認識の上において違いがあるのは、色覚を感知する目の機能がひとりひとり微妙に違うためです。目は色刺激に由来する知覚である「色知覚」を司りますが、色知覚は、質量や体積のような機械的な物理量ではなく、音の大きさのような「心理物理量」であるといわれています。
同一の色刺激であっても同一の色知覚が成立するとは限らず、直前に起こった事象による知覚や体調・心理状態によって、それをその人がどう感じるか結果はかなり異なります。たとえば、対象物が白や灰色・黒といった無彩色なのに、色を知覚する場合があり、その例えとして良く使われるものに「ベンハムの独楽(こま)」というのがあります。
イギリスのおもちゃ製造業者である「チャールス・ベンハム」の名に由来する独楽です。視覚に関する錯覚、「錯視」の実験として良く知られており、ベンハムは、1895年に下図に示したように上面を塗り分けた独楽を発売しました。
回転していないオリジナルは白と黒の図形にすぎない
見るとわかると思いますが、ベンハムの独楽を回すと、何等かの色のついた弧があちこちに見えるはずです。この弧の色は、刺激に関する感覚の定式を“ヴェーバー‐フェヒナーの法則”として定式化したドイツの物理学者、グスタフ・フェヒナーによって、「フェフナーの色」と呼ばれています。
誰が見るかによって異なる色となりますが、なぜこのような現象が起こるのか完全には理解されていません。ただ、赤(正確には黄色からオレンジ)、緑、青に感受性が高い網膜内の光受容体(錐体)が応答する光の変化率がそれぞれ異なっているからではないかとも考えられています。
このベンハムの独楽は、単色光の下で回してもやはり色感覚が生まれます。さらに左目と右目別々に、独楽の模様の一部分ずつを見せるように工夫しても色感覚が生まれます。日本では、あるテレビ局がこの錯視を応用してモノクロテレビ放送で擬似的な色を発生させる試みが行われ、テレビCMでの映像効果に使用した事もあったそうです。
このベンハムの独楽の現代版ともいえるようなおもちゃが最近流行しているようです。
ベンハムの独楽と違って色の変化をみるためのものではなく、ストレス解消等が目的で、「ハンドスピナー」といい、アメリカ生まれの手慰み玩具です。英語ではフィジェットスピナー(fidget spinner)とも呼ばれており、あちらではこのほうが一般的な呼び名です。
考案者はアメリカフロリダ州のキャサリン・ヘティンガー(Catherine Hettinger)という女性で、重症の筋無力症を負った彼女が、娘と遊べる玩具として考案しました。特許も保有していたそうですが、特許更新料の支払いができずに2005年に特許が切れています。
本来はただ単に、「回すだけの玩具」でしたが、回転速度や回転時間を向上させるなどの改造を加えた遊び方が受け、全米で広まりました。実際は一方方向に回っているにすぎませんが、ストロボ効果で逆回転しているようにみえるものもあり、このほか5枚羽のハンドスピナーやLED付きハンドスピナー、いろいろなものがあります。
一般には手のひらに乗るサイズであり、ボールベアリングと、その外輪から放射状に伸びるように付くプラスチックや金属等で出来たプレート部分、内輪を軸方向から挟むホールド用の部分とで出来ています。手や指でプレート部分を回転させることで一定時間プレート部分が回り続けます。
製品によっては5分以上回転し続けることを謳った商品もあるそうで、 基本的には指の間や机の上などで回転する様子を眺めたり、ジャイロ効果を感じたりして遊びます。動画サイトYoutubeなどでは「トリック(技)」を組み合わせてパフォーマンスを行う動画も個人などによって公開されています。
ただ、アメリカでは流行の拡大とともに遊んでいた子供が眼を怪我する事故や、幼児の誤嚥、子供たちが熱中するあまり学業の妨げになる問題も起きたため、一部の学校で使用を禁止するなどの混乱も起きたようです。しかし、その後改良は進み、日本にも輸入されるとともに、日本独自のオリジナル商品も出始めました。
アメリカでは昨年暮れぐらいから流行し始め、今年の4月あたりから「fidget spinner」の検索数が急激に伸びたといいますが、日本でも先日NHKのニュースなどで取り上げられたことから、これから話題になりそうです。
米CNNはADHD(注意欠陥・多動性障害)のカウンセリングにも有用であると報道したといい、もともとは筋無力症という重度の病を負った女性が生み出したものであることから、精神医学的にも着目されそうです。
暑かった夏がそろそろ終わり放心状態のあなた、夏バテで最近集中力が途切れがちな貴兄。飛び回り始めた赤とんぼを指先をクルクル回して捕まえてみるのも一興ですが、ここはひとつ、長い秋の手慰み。こちらをスピンさせてみてはいかがでしょうか。