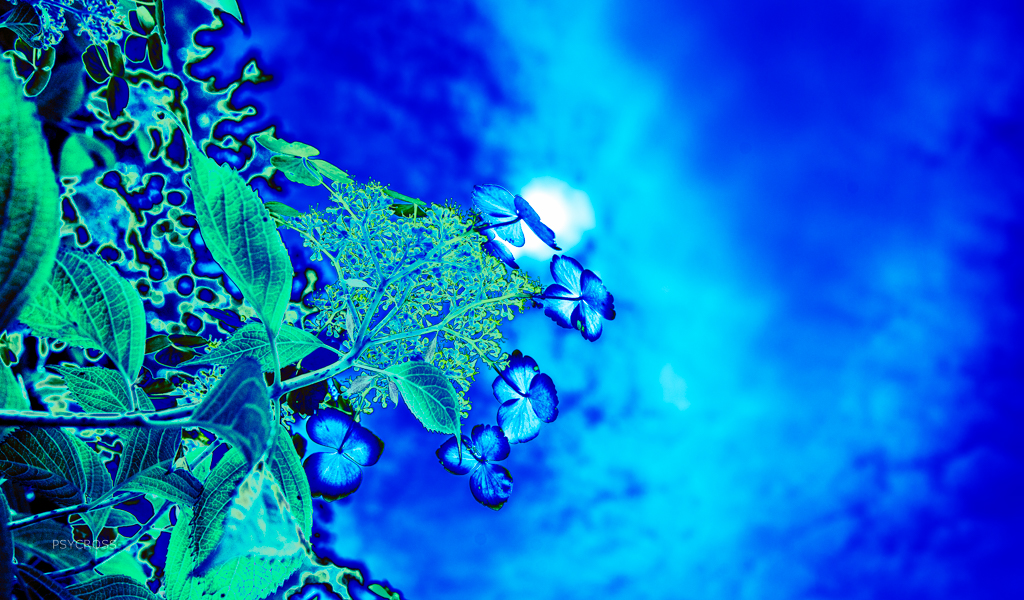入学が決まった国泰寺高校は、かなりの街中にある。というか、その場所には隣接して南には市役所、西側には中央郵便局がある、という立地で、ほぼ広島の町の中心部に位置する。
北へ歩いて5分ほども行けば広島一の繁華街八丁堀があり、さらにその隣には流川(ながれかわ)という全国的にも有名な夜の街がある。直線距離で1キロほど離れた場所は、8月6日に投下された原爆が炸裂した中心であり、現在そこは世界の人々が集まる巡礼地、平和記念公園だ。
北には広島城、その周りには県庁のほかありとあらゆる官公庁も軒を並べていて、いわば広島文化の中心に位置する学校なのであった。広島の東端の僻地で育った我が身としては何か急に華やかな舞台に飛び出た感じがした。
ちなみに、国泰寺高校は通称、鯉城高といい、鯉城とは広島城のことを指す。語り継がれる伝統的応援歌の「鯉城の夕べ」は、この城の下で育つ若者にエールを贈る内容だ。
鯉城と呼ばれる所以は諸説があり、その昔鯉の産地だったから、といったことや、城のお堀に鯉がたくさん泳いでいたから、といったことが言われている。しかし、城の一帯はその昔、海に近く、そこが己斐浦(こいのうら)と呼ばれていたから、とする説が有力のようだ。それにちなんでか、市の西部には「己斐」という町と駅がある。
それにしてもなぜ、学校の名前は己斐ではなく、国泰寺なのか。その近くには同名の寺はない。なぜなのだろう、という疑問は入学してすぐのころのガイダンスで説明された。
戦前、そういう名前の大きな寺があって、この地域一帯がその名をとってそう呼ばれていたそうだ。原爆投下によってそうした歴史的な建物はすべて破壊されたから、せめて新しく建てる学校施設にそうした名残を残そう、ということだったらしい。
それにしても、もっと別のネーミングでもよかったのではないか、と思ったりもする。国泰寺の名を拝する前は「広島一中」の名で親しまれ、この地を代表する学舎だったようだから、せめて広島一高とか、己斐のような地域を代表するような名称を与えてほしかった。そう思うのは私だけだろうか。
住んでいる東雲からこの国泰寺高校までは約4キロあった。バスで行けば15分ほどで着く距離であり、自転車通学も許されていたから30分もあれば登校できる。しかし小学校、中学校と学校へは歩いて通っていた私は、ここでも歩いて行くことを決め、毎朝やや早めに家を出ることにした。徒歩だと、約45分ほどもかかる。
歩いて登校することについては、実はこだわりがあった。ただ単に小中学校からの名残り、あるいは惰性といった面もあったが、そのころ読んだ新田次郎の小説に影響されてのことだ。
「孤高の人」という小説で、主人公は加藤文太郎という。昭和の初め頃に現れ、不世出といわれた登山家で、「地下足袋の文太郎」と呼ばれていた。なんでも登山靴を買うこともできないほど貧乏だったので地下足袋で山登りをしていたが、その姿が他の登山者の間で評判となり、そのうちにその呼び名が定着したらしい。
歩くのが早い人で、平坦地もさることながら、山登りのスピードは驚異的だったといわれている。新田さんの小説のストーリーは、当時の登山界に彗星のごとく現れて消えていったこの偉人の生涯を追ったものだった。
実在する人物で、現在の三菱重工の技師である。当時は三菱内燃機製作所と言っていた。仕事の合間に行う登山活動がやがて本業のようになり、最後は北アルプスで遭難死するのだが、登山にあたっては徒党を組まず、必ず「単独行」で臨んだ。
すべての責任は自分ひとりで背負い人に迷惑はけっしてかけない、あらゆることを自分の中だけで完結させる、という人だった。その生きざまは強烈であり、そのキャラクターに魅せられた。何よりも「孤高」ということばが気に入り、その後の私の人生のある時期までにおいては、ひとつの座右の銘のようになっていった。
もとより一人で過ごすほうが好きであり、歩くことを好んだ自分をこのヒーローに重ね合わせ、かくありたい、と願ったものである。
かくして、この高校時代にも4キロ先の学校までせっせと歩く毎日が始まった。雨の日も風の日にもである。小中高とこれほどまでに歩いて学校に通った学生は、広島中探してもほかにいなかったのではなかろうか。
私が入学したころの国泰寺高校には、入ってすぐのところに二棟の木造校舎とこれに付随する木造家屋があった。校門から入ってすぐにあるこれらの家屋群は古き時代の風情を残すものであり、この学校の歴史の長さを思わせた。
といっても、広島の町は原子爆弾によって破壊されており、戦前の建物はほとんど残っていない。この校舎も戦後すぐの創建だろうから築30年ほどのはずだった。細部をみると確かにそれほど古くない。ただ、デザイン自体が明治大正を想わせるものであり、造りもがっしりとしていた。
入学してすぐの1年生の時は、このレトロな校舎で学んだ。もっとも、学内にはもうひとつ近年建てられた鉄筋コンクリートの校舎もあり、高学年になるとこちらに移った。新参者にはお古を、経験を積んだら新しい校舎を与えてやる、という見え透いた学校の指導方針のように思えた。
一年生の担任は江上先生といった。やせ形でひょろりとしており、つかみどころのない感じの先生だったが、穏やかな性格でこの学校のルールについては、ひととおりの行き届いた説明をしてくれた。右も左もわからない新入生にとってはありがたい配役だったかもしれない。
クラスには50人ほどいた。そのうち、何人かは卒業まで一緒に過ごすことになったが、その中の二人とは今でも親しい付き合いがある。一人は藤井君といい、こちらはなんと、小中学と同じで、この高校までもが一緒だった。
幼馴染といっていいが、それほど仲が良かった、というほどでもない。それが現在までもつきあいが続いているというのは、腐れ縁というかんじがしないでもない。もしかしたら前世でも何かご縁のあった人物なのかもしれない。
出来のいい子で、その後、難関の大阪大学工学部に入学、卒業後は同じく大阪に本社があり、世界的な企業として知られる大手の電機メーカーに入った。同級生の中ではエリート中のエリートといえる。
もう一人は高橋君といった。中学時代は柔道をやっていたそうだ。この学校では体操部に入り、器械体操をやりはじめたが、そのずんぐりとした体形からは体操をやっている、というのは想像できない。後年、大学に入ったあとは、弓道をやるようになったというから、体型とそれに合ったスポーツというのは必ずしも合致しないものらしい。
こちらは、妙にウマがあい、同じクラスだったのは一年のときだけだったが、三年間を通じよく行動を共にした。親友と言ってよく、その後の大学時代も、就職したあとも、何かと機会があれば会い、近況を報告しあっていた。広島に帰ることがあれば、時間を作って飲みにも行ったりもした。
ちなみに、彼は大学では鉱山科に入り、卒業後は通産官僚となった。現在も経済産業省となった同じ省庁で、あちこちの鉱山の管理をする仕事をしているようだ。
普通、高校の同級生というのは、卒業後は縁が遠くなる。ところがこのふたりは、その後の人生においても節目節目に出会うという、不思議な人たちである。
もっとも、現在の私の妻も同その一人であるのだが、そのことはいずれこのあと書いていこう。ちなみに、家内との人生二度目の結婚式のときにはこの友人二人を、高校時代の代表ということで招待している。
ほかの高校時代の友達にも後年かなりの時間を経て再会し、また新たな親交を深めていくことになるのだが、紙面と時間のこともあるので、とりあえずは自分のことをさらに書いていこう。
高校に入学したそのころ、私はもうすでに次の目標を見失っていた。難関校に入学したことで安心してしまった、というところはあるだろう。さらにその3年後に迎えることになる大学受験についてはまるで視野になかった。
ただ、それ以前の問題として、将来いったい何をやりたいか、何になりたいか、といったことについてもほとんど何も考えていなかった。高校を卒業したあとのビジョンについてはまるで白紙に近い状態だ。
ただ、頭の片隅になんとなく、ひっかかっていたことがある。小学校の卒業文集に、自分は何になりたいか、を書くコーナーがあり、そこには「エンジニア」と書いていた。その当時エンジニア、などという言葉はまだまだ新しい響きがあり、それをあえて使っていた、というあたり、大人びている。
しかし、その意味を果たしてはっきりわかっていたのかどうか。父親が電気技師であったことから、漠然とそういう仕事をする人たちだろう、というくらいの知識しかなかった。自分も手先が器用だし、大人になったら父と同じような仕事をやるのもいいな、程度に思っていた。
それを思い出し、将来、エンジニアとやらになるももいいな、と考え始めた。ただエンジニアといってもその幅は広い。いったい何の分野の技術者なのかについては、あいかわらず明確なイメージは持てないままにいた。
配電工などの職人から博士級の研究者まで数多くの種類のエンジニアは存在する。その中から、自分がなりたいものを選ぶというのは、高校に入ったばかりの小僧には少々難題だ。
とはいえ難しく考える必要もない。なりゆきに任せる、ということもできたはずだが、私はことあるごとに何か目標を作らないと走れないタイプだ。目の前に人参をぶらさげた馬よろしく、何かご褒美、何か目的がないと、次の行動に移れないのである。
そこで、自分はいったい何が好きか、と自問してみた。すると、あえていえば子供のころからなぜか海が好きだったということを思い出した。
幼少時代を過ごした堀越や青崎が海に近かったこともあり、いつも潮の香を感じつつ育った。また小学校のころはいつも夏休みになると山口を訪れ、そこにある海で遊んだ。子供のころから海がいつもそばにあり、傷つきやすい幼ない心を癒してくれた。
が、海が好きだということは、そうした育った環境のせいばかりではなく、そもそもは何か生まれつきの性質とも関係があるようにも思える。
のちに二度目の結婚をした後、相方の知り合いの紹介で、いわゆる霊能者と言われる人に自身を霊視してもらったことがある。彼女の母親はいわゆるスピリチュアルの分野に傾倒していた人で、知り合いにはそうした霊能者がたくさんいた。
娘の彼女も霊視してみてもらっており、私と結婚してからは私のこともみてもらいたくなったようだ。あるとき連絡し、二人してその人に会いに行った。
その霊視の結果、私の背後にはでっぷりと太った船問屋の主人がいるという。そしてその人こそが守護霊の代表格だということだった。さらに私自身も前世では海関係の商売をやっていたらしく、船の積み荷の前で算盤をはじいていたその当時の姿も見えるという。
この世に生まれ変わる前の人生で何か海の関係の仕事をしていた、という記憶はまるでないのだが、そういわれてみればそんな気もする。思い当たる節はいくつかあった。
そのひとつとして、私はほとんど船酔いというものをしたことがない。普通、船に強い、と自称する人であっても、小舟であればあるほど揺れはひどくなり、ときに気分が悪くなることがある。しかし、私の場合それをむしろ快感のように感じる。
子供のころ、山口に帰るたびに母方の従弟とあちこち遊びに行ったが、遊覧船などに乗る機会があるとき、決まって船酔いするのはこの従弟で、私はケロッとしていた。
後年、大学や仕事でいろいろな船にのったものだが、ほとんど船酔いをした、という記憶がない。留学していたころ、研究所の調査船で時化気味の海に出ることがあったが、同僚のインド人はゲーゲーやっていたにも関わらず私は平気だった。
さらに私は車酔いをしない。バスなどで長距離を移動すると気分が悪くなるという人も多いようだが、これまでの人生でただ一度ですら陸上の乗り物で酔ったことはない。
船や車に酔わないというのは自慢ですらあり、「揺れ」というものに対する耐性のようなものがあるようだ。これは明らかに今生で経験的に得られた能力ではない。
それに加えて、海に出るとやけに高揚とした気分になる。普段の生活のほとんどは陸上で過ごしているわけだが、時々妙に海のあるところに行きたくなるし、船にも乗りたくなる。
船の上で過ごすことを職業にしているわけではないので、その機会はそれほど多くはないが、たまにそうしたチャンスがあると、うれしくてうれしくてしょうがない。
こうしたことは、前世で何等かの海の仕事をしていたという傍証になるかもしれない。何か船に乗る職業についていた、あるいは何等かの形で海とか関わっていた、ということは確かなことのように思えてくる。
そのくせ水泳は苦手で、水の中に入る、というのはどうも子供のころから嫌いだった。まったくの金槌ではないが、どうも水の中に浸かっているというのが好きではないのだ。小学校時代に体育で水泳の時間があると、たいてい仮病を使って休んでいた、ということは先にも書いた。
さらに想像をふくらませてみると、もしかしたら、船乗りだった最後、乗っていた船が難破したか何かで、死んだのかもしれない。前世でそうした苦しかったことなどの記憶は現在までも持ち越されるという。今生でも何等かの障害を引き起こしたり、そうでなくても苦手とすることとして現れたりするらしい。
と、こうしたことを書いても、輪廻転生を信じていない人にはピンとこないだろう。論議があることは承知しているから、それが自分の進路を決めるためにまで影響していた、と断定するのはやめておこう。ただ、将来の進路を考えるにあたり、漠然としたイメージとして「海」を思い浮かべたのは、そうした過去生の経験と無関係ではないのかもしれない。
一方で、このころ海という分野で何かをやっていきたい、という気持ちが高まっていったのは、時代変化とも関係がある。
高校に入学してしばらしくてからのこのころ、ちょうど日本は高度成長期をそろそろ終え、次の開拓期に入ろうとしていた。その中で「海洋開発」という言葉がさかんに使われるようになっていく。
海洋開発といっても、いろいろあり、一般的には海底に眠る石炭石油などの化石燃料を開発することを指す。しかし、それ以外にも波や潮流を利用した発電、魚介類の増養殖、海洋水そのものの利用などがある。利用方法としては塩の抽出だけでなく、その他のミネラルや鉱物などの取り出しもあり、数多くの利用の可能性が取り沙汰されていた。
加えて深海の開発、という分野があり、水深が1000mをも超えるような海底には数々の未発掘の豊富な資源ある可能性が示唆されている。現在、深海底のシェールガスの開発などが話題になっているが、私の高校時代にも既にマンガン団塊や熱水鉱床、ガス田といった言葉が日々のニュースにも取り上げられるようになっていた。
アメリカはそうした分野のパイオニアで、アポロ計画における月面探査の成功のあと、海という新たな分野への取り組みに熱心であった。そうした情報がさかんに日本にも入って来るようになっていた。
日本は周囲を海に囲まれており、そこにある大陸棚の開発は大きな国益にもなる、ということで毎年、政府が積み上げる予算の中で、科学技術分野のその部分にもかなりのウェイトが置かれるようになっていた。
しかしこのとき私はまだ16~7歳だ。そんな国家的なプロジェクトに関われるとは思ってもいなかったし、何の能力があるわけでもない。ただ単に海に関わる仕事がしたい、と感覚的に思っていただけである。
もっとも、海を意識し、より具体的な進路─進学先を探り始めたのは、高校生活も2年を終えようとするころのことである。高校に入ってすぐのころはまだ遊びたい気分も強く、そこである部活動をやることにした。
写真である。
もともと興味があった。幼かったころ、「日光写真」というキャラメルのおまけに熱中したことは前にも書いた。それ以後、小学生時代には子供向け雑誌の付録についている「幻灯機」などにも興味を示した。
原理は簡単だ。いろいろな映像が刷り込んであるセロファン製の「ネガ」に後ろから豆電球で光を当てる。そのままだと大きく映らないので、フィルムの前にはプラスチック製のレンズが取付られるようになっていて、そのレンズで拡大された映像を壁に映して楽しむ。
ふすまなどの白い壁に映写するのだが、連続した映像を見るためにセロファンのネガは帯状になっていた。違う映像が何枚も印刷されており、帯を引っ張れば次々と映像が変わる、という仕組みだ。
日光写真をもう少し複雑にしただけのものだが、そのわくわく感は数段違った。小さな感光紙に白黒の映像が出てくるだけの玩具とは違い、より大きな画像が楽しめ、しかもカラーときた。その映像を見るために夜になるのが楽しみにしていたが、そのうち昼間でも押入れの中なら使えることを悟り、さらに熱中していった。
ちょうどこのころ、高度成長期にあった日本はそんなおもちゃではなく、本格的なカメラの開発に取り組むようになっていた。そうした中、のちに世界に冠たる有名カメラメーカーや電子機器メーカーになる会社が次々と生み出されていく。
オリンパスもその一つである。もともとは内視鏡などの医療器具を作っていた会社だったが、そうしたトレンドに乗ろうということで、カメラ開発にも力を注ぐようになっていた。
この時代、フィルムカメラの主流は、ブローニー判と呼ばれる大判フィルムカメラの時代から、35ミリ判と呼ばれる現在まで引き継がれる小型サイズのフィルムカメラへと移り、その全盛時代を迎えようとしていた。
そうした小型のフィルムカメラが普及した理由は、フィルムの製造コストが安くなったことと、小さなサイズでも高精度の映像が撮影できるようになったことである。
35ミリカメラで撮影した映像は、障子半分ほどの大きさの印画紙に印刷しても十分に鑑賞できるほど解像度が高い。またコンパクトサイズであることから、それまで大きいものではバケツほどのサイズであったカメラの大きさを弁当箱程度のサイズにまで小さくすることに貢献した。これは200年近くある写真の歴史を塗り替えるほどの画期的な技術であった。
一方、一般家庭で見る写真はそれほど大きくなくてもいい。せいぜい手札程度の大きさで十分であり、35ミリ版フィルムほどの解像度はむしろ過剰すぎる。
そうしたことから生まれたのが、ハーフサイズのカメラである。35ミリのフィルム一枚に、その半分の大きさの映像が2枚撮影できるというもので、24枚撮りのフィルムなら48枚、36枚撮りなら72枚も撮影できる。
カメラ自体がまだ比較的高価だったこの時代、このアイデアは庶民の多くに受け入れられ、ハーフサイズカメラは爆発的に普及した。
そのひとつが、「ペン」の名前で親しまれたオリンパスのカメラである。私が小学生の高学年になったころ、我が家でも父親が早速この「オリンパスペン」を購入した。
このころ、父の役職は主任クラスになっており、給料もそこそこよかったようだ。近くの雑貨屋で借金をしていた堀越時代に比べれば、裕福とはいえないまでもそうした贅沢品を購入できるほどになっていた。
ところが、このカメラ、所有者は父親なので自由には使わせてもらえない。ただ、購入当時は父が独占していたが、そのうち家族全員のもの、ということで、それぞれが必要なときに使う、ということになった。
しかし、それでも自分の好きなものを撮影することはできない。べつに共有カメラでも写真は撮影できなくはない。しかし、自分だけのマシンで世界を創造したい、というそこだけは妙なへ理屈を自分で作り、家是を捻じ曲げて、贅沢にもマイカメラが欲しい、と願った。
このころ、小学校高学年だった私の小遣いは月千円程度であり、それで買えるわけがない。そこで、息子にはいつも甘い父にねだったところ、思いがけなくOKが出た。
こうして生まれて初めて買ってもらったカメラはコニカ製だったと思う。プラスチックでできたボディーに、カートリッジ式のフィルムが付いている。カートリッジには12枚、24枚、36枚撮りの3種があったが、価格設定が高かったため、私の少ない小遣いでは12枚撮りぐらいしか買えなかった。
このため、一枚一枚を大切に撮ったが、もともとはフィルムカートリッジを売りたい商品であったため、カメラ本体の機能は大したことはない。レンズも単焦点で品質もよくなく、映りもたいしたことはなかった。それでも初めて自分だけのカメラを持ったうれしさで、肌身離さず毎日そのカメラを持ち歩いたものである。
最初は庭の花とかが多かったが、そのうち風景写真も撮るようになっていった。家族で出かけるときなどはフィルム代を親が出してくれるので、家族写真をサービスで撮ることも多かった。無論、余ったフィルムで自分の好きなものを撮影するのである。
このカメラにはキュービック状のストロボが付いていたため、雨の日や夜にも実験的に撮影を行うようになり、徐々に自分の写真のレパートリーを広げていった。
その後、家族用と位置付けられていたオリンパスペンも飽きたのか誰も使わなくなり、中学生のころ、ついには私が自由に使うカメラとなった。映りのイマイチなコニカ製カメラは次第に日の目をみなくなり、いつのまにか引き出しにしまいっぱなしになっていった。
もっとも中学時代の私は趣味が勉強のようなものだったので、あまり写真には熱中しなかった。ところが、高校に入学し、多少心に余裕ができたこともあり、もともと興味のあった写真に本格的に取り組むようになっていく。
中学校ではあまり本腰を入れなかったものの元美術部の私は、作画をする、ということに対しては依然強い興味を持っていた。絵を描くということに関しては挫折したが、写真という新たな分野ならもしかしたらモノになるかもしれない、などという恐れ多い野望を抱いた。
そこでまずはどんなカメラがあるのかを写真雑誌で調べはじめた。次にはそうしたカメラのスペックばかりを特集した番外編を購入して、徹底的に研究した。難しい用語はそうした雑誌についている用語集で勉強し、わからないことは本屋で立ち読みして理解に努める、という念の入れようだ。
もともと学習意欲がたかまると集中的にそれを勉強する、という性癖を持っていた私は、たちまちのうちに「カメラ博士」となっていく。
ところが手元にあるのは、ハーフサイズのカメラにすぎない。本格的なフルサイズの35ミリカメラ、しかもレンズ交換が可能な一眼レフカメラが欲しい。
この時代、日本のカメラメーカーが製造するカメラは世界的にみても最高水準のものになりつつあり、外貨を稼ぐ重要な輸出品となっていた。
それまでのカメラは、ライツに代表されるドイツメーカーのものが主流であったが、一般には被写体をとらえるファインダーと、実際の映像を取り込む光学系が二つある、いわゆる二眼レフやレンジファインダーといわれるカメラだった。
被写体を目で見て確認する光学系と、被写体からの光を取り込み、フィルムに落とす光学系のふたつがあるため、二眼などと呼ばれる。この方式のカメラの欠点はファインダーで見ているものと実際に撮影されたもの間に細かな差異が出てくるという点である。
「二つの眼」で被写体の方向を見ているわけであるから、眼で見てシャッターを押すまでには非常に短い時間であってもタイムラグが生じる。また、「眼と眼」の間にも僅かな距離差があるわけであり、ファインダー画像と撮影画像の間には小さなズレが生じることになる。
つまりはリアルタイムで撮影した画像が撮れないという点が最大の欠点であったが、これを解決したのが日本のメーカーが開発した一眼レフである。
今でこそ普通の技術になってしまったが、この当時は画期的なものであった。原理としては、ひとつのレンズで取り込んだ映像を、カメラ内部にある「鏡」で反射させてファインダーに取り込む。このことで実際の被写体を目で確認しながらシャッターを押すことが可能になる。
シャッターを押すと同時に、その鏡が跳ね上がり、その後ろにあるフィルムに映像が焼き付けられる、というものなのだが、書けば簡単に聞こえる。しかし、その鏡を瞬時に跳ね上げるためには高度な技術が必要であり、また鏡で反射させてファインダーで確認するためには「ペンタプリズム」という特殊なレンズが必要になる。
このレンズを世界に先駆けて開発し、それまでの主流だった二眼レフから一眼レフの時代を作るきっかけを作ったのが、旭光学工業という会社である。
のちにペンタックスと名前を変え、現在はコピー機などを製造するリコーグループに取り込まれているが、この当時は一眼レフといえばペンタックスといわれるほどに、その名をとどろかせていた。
ペンタックスのペンタは、言うまでもなくペンタプリズムからとったものである。五角形のことをペンタゴンといい、その形のプリズムだからペンタプリズムである。
のちにその特殊プリズムや跳ね上げ式ミラーの特許期間が切れ、国内メーカー各社がこぞってこの技術を使って一眼レフカメラを作るようになっていった。その中には戦前から軍需用の光学機器を製造していた日本光学工業(現ニコン)があり、ほかにはキャノン、ミノルタ、オリンパスといった現在までも続くほぼすべてのカメラメーカーが含まれている。
ちなみに、今はもうなくなってしまったヤシカやトプコン(東京光学)といったメーカーも一眼レフを作っていた。
とまあ、こうしたうんちくがスラスラ書けるほどに高校一年生のころにはもうすでに、どっぷりとカメラお宅になっていた私だが、いかんせん、現物がない。
そこで、それとなく父親にモーションをかけると、いつものように息子に甘い父が、それなら志望校に受かったお祝いに、と言ってくれた。もっともいますぐに、とういわけではなく、クリスマスあたり、と言われた。年末にはボーナスが出るのでそれを当て込んでの約束であり、とはいえ、それを聞いて飛び上がるほどうれしかったのを覚えている。
一方では、カメラを買ってやるという父の確約を取ったものの、ではどのカメラを買うかについては、かなり悩んだ。どこのメーカーのものも優れた製品ばかりだったが、最終的にはミノルタSRT101とアサヒペンタックスSPFという二機種に絞り込んだ。
両者の大きな違いはフィルムに露出を与えるための測光方式だったが、そのころ主流になりつつあった中央部重点測光方式のペンタックスを最終的には選んだ。これはファインダーの中央部に位置する被写体を重視し、ここの明るさを計測することに重きを置く、という方式だ。片やミノルタのほうは全フィルム面を平均的に測光するというものだった。
前者はとくに動きの速いものには有効であり、後者はどちらかといえば風景や人などの動きの少ないものの露出に向いているといわれていた。一眼カメラをまだ一度も使ったことがない人間がそんな聞きかじりの知識だけで機種をえらぶなど笑止だったが、スペックを見比べ、ああでもないこうでもないと悩んでいる時間は実に幸せだった。
こうして念願の一眼レフを手に入れるときがきた。白黒のデザインに赤字でPENTAXと書かれた化粧箱を手にしたときは天にも昇るような気持ちになった。
前述のとおり、一眼レフカメラの最大の特徴はファイダーとレンズという二つの光学系を一つにまとめることが可能になったという点であるが、これによりもう一つ大きな利点が生まれた。
それはレンズ交換が容易にできる、という点である。それまでの二眼レフなどでも交換レンズ式のものはあったが、レンズだけでなく、ファインダーもまたレンズに合わせて交換するか、何等かの方法でファインダー倍率を変える必要がある。
一眼レフの場合は、ファインダーで覗いている画像はレンズを通して直接入って来ているものであるから、レンズを交換すれば自動的にファインダーで見ている映像も変わる。使っているレンズを通してありのままの被写体を見ることが可能なのである。
レンズは撮影したい被写体に応じて自由に焦点距離が違うものを使うことができる。遠くのものを写したければ望遠レンズを、狭い場所で広い範囲を撮影したければ広角レンズを用意すればいい。つまり、交換レンズがあれば、飛躍的に被写体の対象が広がるのであり、一方、交換レンズがなければその最大の特徴を生かせないということになる。
私が買ってもらったペンタックスには「標準レンズ」というものが付いていたが、これは被写体が普通の大きさ、等倍に見えるだけのものである。対象とする被写体の幅を広げ、より作品のレパートリーを増やしたいならば、さらに視野を広げる広角レンズや、逆に部分を拡大して見ることのできる望遠レンズがあったほうがいいに決まっている。
現在ならば広角から望遠までの広い範囲をカバーするズーム式の交換レンズがかなり安価に入手できるが、この当時はまだ高価で、単体レンズを買うほうが安上がりであった。このため少ない小遣いを貯めて、最初に比較的安価な望遠レンズを買ったが、光学系が複雑になるため高価な広角レンズのほうまで手が出ず、こちらは少し父に援助してもらって買った。
こうしてカメラ本体に加え、望遠レンズ、広角レンズの三種の神器を手に入れた私は、意気揚々と写真部に入部した。二年生の初め頃だったと記憶している。
その部室というのが変わった場所にあった。一年生のときに入っていた木造の古い校舎の階段裏にあり、入り口は極端に狭くしかもドアの高さも背丈ほどしかない。階段下の空きスペースを使って無理やり作った部屋であるためと思われるが、そのために室内も狭く、4~5人も入るといっぱいになる。
それに加えて一人がやっと入れるほどの暗室がしつらえられており、それがまた部室を狭くしている要因だった。
北向きで薄暗く、窓も小さい。そうした環境の悪さもあったためか、部員数は少なく、同じ二年生が私を含めて3人、先輩が2~3人ほどしかおらず、一年生はいなかった。
私以外の二年生の名は今井君と小林君といい、のちに三年生が卒業した後は今井が部長に、小林が副部長になった。おまえが部長をやれ、という話も出たが断った。私自身はリーダーになりたいという気分はなく、むしろ自由に一人で好きな写真を撮りたい、というふうに思っていたのでその人事には何の不満もなかった。
一応、顧問の先生がいたと思うが、名前や顔も全く覚えていない。ほとんど部室に顔を出したことはなく、部員のやりたいようにやればいい、という考えだったようだ。
写真部に入って以降というもの、私の写真熱は日増しに高まっていった。そのころ撮影に最もよく使ったのは、フジフィルム製のネオパンSSSという感度400のフィルムで、駅前の写真材料専門店でまとめて買うと、かなり安くなる。
ほかにコダックのTRY-Xという同感度のフィルムがあり、はっきりとした輪郭の出るフィルムだったことから気に入り、その後常用フィルムとなった。
フィルムや印画紙などの購入費の一部は学校側から出るし、また現像液や定着液といったものの値段はそれほど高くはなかった。従って、少ない小遣いを圧迫するといったこともない。
かくして今考えると「愚作」といえるような作品の量産化が始まった。部長だった今井君がありとあらゆる分野にチャレンジしていたのに対し、私はどちらかといえば風景写真専門で、いかに景色をきれいに撮るか、に重きを置いていた。
この点、絵と同じであり、その作風には性格が出る。他の人が動きのあるものや人物を対象として選ぶ一方で、私はというと一人で対象とじっくり向き合える形を好んだのはそうした性格としかいいようがない。
もっとも風景写真だけでなく、学校の行事についてもよく撮影した。バレーボール大会や体育祭といったスポーツ系の行事だけでなく、文化祭や修学旅行といった行事でも必ずといっていいほどカメラをぶら下げていた。また日常的にカメラを教室に持ち込むことが許されていたことから、ことあるごとにクラスメートを撮影するようになった。
その中には今の奥様も含まれている。のちに結婚をすることになるわけだが、ただ、このころはまるでその人には関心はなかった。従って彼女だけを選んで写真を撮るといったことは全くなく、この当時の彼女が写っている写真は数枚残っているにすぎない。
興味はなかったが、ただ面白い子だな、という印象だけは持っていた。この高校では「班」を編成し、そのグループ毎に課外活動をする、ということを奨励していた。それが何の意味があるのかは考えたこともなかったが、今思うに、おそらくその後社会に出たあとのコミュニケーション能力を養わせるという意図があったのだろう。
それはともかく、いわば「合法的」に異性と話ができる、というわけでこの班活動はわりと人気があった。何をやるかについては特に決められているわけではなく、グループディスカッションをしたり、共有日誌を書く、といったことをみんなやっていた。
班は二年間ずっと同じというわけではなく、一学期が終わる毎に総入れ替えする、というきまりだった。あるときこの未来の奥様と同じ班になることがあり、それをきっかけに会話をする機会が増えた。
といっても、何を話すでもなく、共通の話題といえば、お互い本が好きだったので、今何を読んでいるか、どんな小説がおもしろいか、といった話だったと思う。先方もそうだったようだが、こちらも異性としての魅力はとくに感ぜず、ただ背の高い子だなと思った程度だ。話の内容もまるで覚えていないことから、相手に合わせるほどのものだっただろう。
二年生の最後の学期前のことだったと記憶しているが、一度だけ彼女が年賀状をくれたことがある。そこには、次の学期になって班が変わっても、お互い無視などはしないようにしましょう、といった優等生的なことが書いてあった。
わざわざ年賀状にそんなことを書いてこなくても、と思ったが、年賀状をくれたこと自体がうれしく、またその親しげな文面に好感を持った。ただ、それ以上何も期待しなかったし、ましてや恋愛感情などはこれっぽっちも持たなかった。彼女と浅からぬ縁ができるようになるのは、その後高校を卒業してからのことになる。
二年生になってからの担任は岸本先生といった。名前を千紘といい、これは「ちひろ」と読むらしかったが、われわれは陰でセンコー、と呼び捨てにしていた。口の悪い友達は、それを「先公」と同じ意味で使っている風でもあった。
ちょっと変わった先生で、授業の合間に自分が学生のころにいかにバンカラだったか、という話をよくしてくれた。
そのひとつに、喫茶店に入って、誰が一番大きなものを持ち出してくるか、という遊びをやった、というものがある。友達とみんなで入り、お茶を飲んで店を出るとき、たいていはスプーンだのカップだの小さなものを持って出るのに対し、彼はトイレに入って便器を取り外しマントにくるんで持ち出してきた、という。
嘘かまことかわからないような話だったが、繰り返し聞かされるその話は皆の笑いを誘った。別のときには、映画館に入るときの話もあった。学生でお金がなかった彼は、入り口の発券売り場のおばさんの前に立ち、いきなり、うしろ!と叫ぶ。
驚いたおばさんが、後ろを振り向いている間に、さっと中に駆け込み、タダで映画をみることができた、という。しかし、同じことを何回も繰り返しているうちに、そのおばさんも呆れ、もう「うしろ」はいいからさっさと入りなさい、とタダで映画を見せてくれるようになったそうだ。
そういった過去の自分の蛮勇を、いかにも楽しそうに話す。同じ話を何度も何度も聞かされたが、聞かされるほうもあーまた始まったよ、と思いつつも、それを話しているときのセンコーの楽しそうな様子に釣り込まれて、ついつい笑ってしまうのであった。
専門は国語と古文で、とくに漢字について詳しく、国文学の知識があるらしかった。たくさんいる先生の中でもリーダー格で、たしか進学相談の責任者だった。そのためか、9つある学級の中で私たちのクラスはいの一番の1組を拝領した。のちに3年1組センコーズと仲間内で呼ぶようになる面々との出会いがそこにあった。
恋の話を少ししよう。
中学校の頃に好きになった彼女が同じ高校に入学してきた、と前に書いたが、その彼女とは、3年間を通じてついに同じクラスになることはなかった。入学後もその恋心を持ち続けたが、シャイな性格はあいかわらずで告白などできようはずもなく、瞬く間に時間が過ぎた。
時折校内で見かけるときにはドギマギしたが、何か行動に出るわけでもなく思いを募らせるだけだった。このあたり、後年結構大胆な行動をとるようになったのとは大違いで、初心(うぶ)そのものだ。
この点、ほかの同級生は大人びていた。ジャズやロックといった洋楽を聞き、うわさによれば酒もたばこも経験済みだという。さすがにSEXの話は聞かなかったが、あるいは私のような遅れている奴にそうした話は伝えられなかっただけかもしれない。
このころの私といえば、無論、酒やたばこなど口にしたこともない。洋楽などにはまるで興味がなく、強いて言えばフォークソングが好きで、ラジオから流れるそれを好んで聞いていた。楽器メーカーのヤマハが後押しするコッキーポップという番組があり、お気に入りだった。
この点、「先進派」の面々からみれば、素人臭いものばかりを聞いている、うざったいおぼっちゃんだったろう。やや小太りの体形で髪は七三分け。ニキビ面で、しかもいつもカメラをぶら下げているという風体は、まさに今で言うオタクである。後年、わが奥様から聞いた話からも、このころの私は男性としての魅力はゼロに等しかった。
ひと様に恋をして受け入れられるということ自体が不可能であることは明らかだったが、それを自覚するでもなく、ただひたすらに自分だけで作り上げた恋愛モードのラビリンスの中にいた。そこから抜け出せなくなり、もがき苦しむ姿は我ながらなさけなかった。
高校2年の秋のこと、受験の準備をそろそろ始めなければいけない段階になり、ようやくこの恋を終わらせよう、という気になった。もやもやとした気分では次のステップに向かえない、と自分に言い聞かせようとした。かといって直接話すことなどできようはずもなく、手紙を書いた。
中学時代からの同窓生だから住所は知っている。震える思いで彼女への気持ちを書き、ポストへ投函したが、そこには自分の気持ちに答えてくれるなら、来る彼女の誕生日に平和公園に来てほしい、と書いてあった。
彼女の誕生日は、10月15日だった。手紙を投函したその日からこの日までの長い長い時間が過ぎていき、ついにはその日を迎えた。
指定した時間は放課後の3時か4時ころだったと思う。早めにその場所に行き、5分待ち、10分待つ頃からもうあきらめムードが漂っていた。結局1時間ほど待ったが、彼女が現れることはついになかった。
奇しくもその日は、広島東洋カープが、球団創設以来の初優勝を飾った日だった。公園を後にして、八丁堀の繁華街を通ったときには、町中がお祭り騒ぎだったが、傷心の私にはそんな光景も目に入らず、ひたすらに肩を落として自宅へと帰っていった。
この時期、長い間の悩みに結論が出た、ということはむしろよかったのかもしれない。ようやく次の難関である大学受験へ目が行くようになり、このころから真剣に進路について考えるようになっていった。
しかし時すでに遅しである。
この学校はいわゆる進学校であった。このため、大学受験に備えるためにはできるだけ環境を変えないほうがいい、ということで2年次のクラスがそのまま3年次に持ち越されたほどだ。
2年に上がってすぐのころから、来たる受験に備えよ的な指導などもあったが、秋といえばそろそろ追い込みに入る時期であり、本格的受験勉強を始めるには遅すぎる。
しかも写真や恋にうつつを抜かしていたこともあり、このころの私の成績はといえばまるでぱっとしないものだった。理科系を志望していたくせに、国語や社会などの文科系のほうの成績がむしろよく、数学や物理化学の成績は低迷していた。
慌てて中学時代に通っていた塾の英語の先生、山川先生に電話をかけて数学の塾を紹介してもらい、通うにようになったが、前からこの塾に通っていた他校の学生のレベルに追いつくことができず、これも焼け石に水だった。
やがて3年生になると、受験までの時間は早回しとなり、あれよあれよという間に卒業が近くなっていった。無論この間、体育祭や文化祭、修学旅行といった大イベントはあり、あいかわらずカメラをぶらさげてそれらの活動に参加してはいたが、こと勉強に関してはどうしても集中できなかった。
親に頼み込んでお金を出しもらい、通信教育も受け始めたが、意思の弱さが露呈し、埋めて返すべき答案用紙は空白のままうず高く積み上げられていった。
このころ、妙に熱っぽく、体がだるい、ということが続いた。あいかわらず学校までは歩いていく、という生活を続けていたが学校から帰ったあとも疲れがとれず、勉強もせずに寝込んでしまう、ということがままあった。
のちに分かったことだが、このころ私はどうも軽い結核にかかっていたらしい。のちに20代になって会社の健康診断を受けた際に撮影されたレントゲン写真には、肺にその名残らしい影が映っていると言われた。
就職後は体調もよく、その前の大学時代にも特段体に問題はなかった。調子が悪かったのはその高校時代の一時期だけであり、今思えばそのころ最悪の条件で受験シーズンを迎えていた、ということになる。
失恋をし体調もぱっとしない、という最悪のコンディションの中で受験への準備が始まった。それよりも、まずはともかく、進学する先を決めなければならない。
そこで、私が選んだ受験校には二つのタイプがあった。ひとつはもともとの目標である、海洋関係の学科がある大学で、もうひとつはカメラに関係し、精密機械工学の科目がある大学だった。
この時期この段階で一つの分野を選ぶことができず、分散してしまったという点、すでにもうかなりの混乱が見て取れる。しかも受験予定の学校は数校ではなく、6つも選んでいた。
海洋系が3つ、精密機械工学が3つであり、いずれもそのころの私の成績ではかろうじて受かるかもしれない、と目される大学だった。ただ、このうちのひとつ、東京の国立大学だけは受験倍率が30倍を超えており、受験する前から自分でもほぼ絶望的と分かっていた。
受かるはずもない大学を選ぶこと自体、計画性のなさがもう明らかなのであるが、もしかしたら…という一縷の望みに託したい気持ちがどこかあった。
受験予定の大学のうち、地方の国立大学以外は東京でまとめて受験することが可能だったので、これらの大学の受験日が近づくと、東京に宿を取って試験に望むことになった。
ただ、ホテルに泊まると高くつくため、父の東京のつてに頼み込んで下宿屋を見つけてもらい、短期間だけ滞在させてもらうことにした。
山手線のどこかの駅近くだったと思うが、薄暗くて陰気な下宿で、そこにはもう長い間受験のために下宿している同年代の若者、数人がいた。結局それら先住民とはほとんど接触をもたず、ほぼ引きこもり状態で受験を迎えた。
当然、この間も勉強もしなければならなかっただろうが、なぜかやる気にならない。今更じたばたしても同じさ、と開き直り、広島から持ってきていた小説を読みふける始末だ。
そんないい加減な受験体制で志望校に受かるわけはない。
結局、国立校であった2大学は予想通り落ち、かすかに希望をつないでいた精密機械工学系の3つもダメだった。
唯一合格通知が来たのが、一番行く気のなかった南海大学だった。
選んだ6校の中では一番レベルが低く、「万が一」ほかの志望校に全部落ちたら、というときのための「滑り止め」だった。しかしその万分の一の確率のくじが当たるとは思っていなかった。
このとき、失敗したな、と思った。もしこの大学を選んでいなければ、今年の受験は全滅であり、だとすれば、一年間浪人させてもらえるかもしれない、という期待があったからである。
ところが受かってしまったために、両親にしてみれば、そこへ行かないなら何のために受験したのよ、ということになる。
とはいえ、私立校だったため二人にとっては大きな負担にもなることから、まさか進学はないよな、と高をくくっていた。ところが、のちに聞いた話では、両親は私に黙ってくだんのセンコー先生にアドバイスをもらいに行っていた。
高校二年の失恋後、私は次第に気難しくなり、自分自身の世界に閉じこもるようになっていた。両親ともほとんど話さず、この受験にあたってもそれらの志望校を選んだ詳しい理由も伝えていなかった。
そのほとんどに落ち、困った両親は、最後の砦となったその大学に息子を通わせるかどうかの判断が得たかったようだ。気難しくなっている本人には確認もせず、担当教員に相談に行ったのはそのためだ。もっともその前に、私からも浪人させてくれ、と頼んではいた。しかし、あまりいい顔はされず、結論は先送りになっていた。
このとき、両親からの相談を受けたセンコーの答えは浪人はさせず、進学させなさい、だったようだ。だが、どういう論理でそう決めたのかについては、何も伝えられず、学校から帰った私に対して父はただ、進学しろ、と迫った。
一方、浪人をしてよりランクの高い志望校への入学を模索していた私は反発した。無論、センコー先生のアドバイスがあったことなどはまるで知らされていない。が、なぜか強気に進学を宣言する両親をみて、これはあきらめるしかないな、と次第に思うようになっていった。
このころの私は疲れ切っていた。失恋問題に加えて受験の失敗、そしてまだこのころ尾をひいていた体の不調…
結局はもうどうとでもなれ、という気分で、いやいやながら進学することに決めた。
その進学先は広島でもなく東京でもない。これまで一度も行ったことのない、縁もゆかりもない土地、静岡であった。
────────────────────────────────────────
本稿の内容はすべて事実に基づいたノン・フィクションです。ただし、登場する人物名は仮名とさせていただいています。また地名や組織名についても、一部は実在しない名称、または実在する別称に改変してあります。個々のプライバシーへの配慮からであり、また個人情報の保護のためでもあります。ご了承ください。