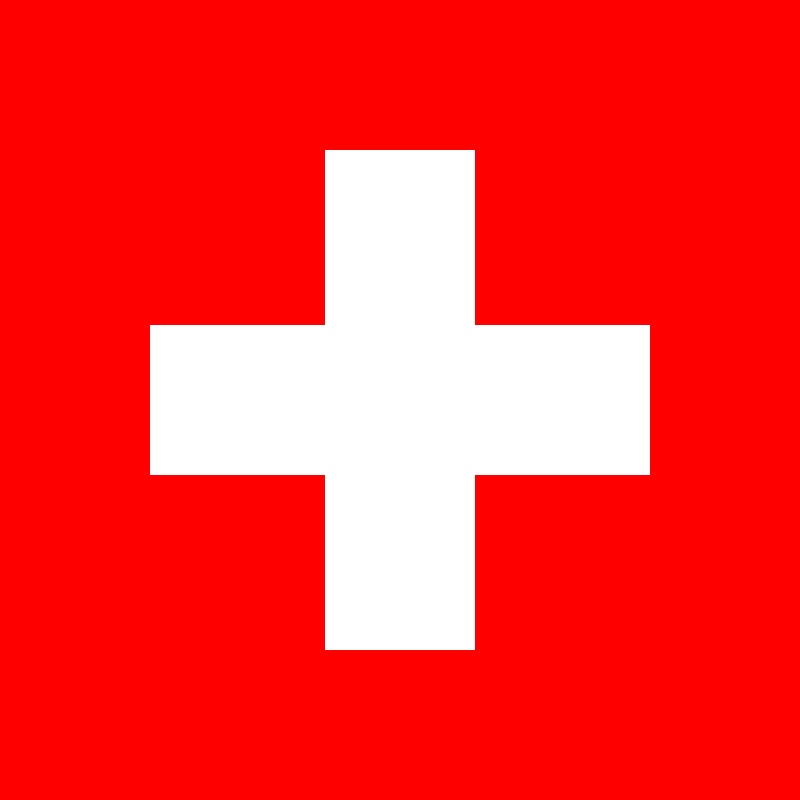9月も半ばになろうとしています。台風の襲来はまだまだ続きそうですが、少しずつ秋めいてきて、やがては月見の季節がやってきます。
月見は、主に旧暦8月15日から16日の夜に行われ、これは十五夜(じゅうごや)と呼ばれますが、旧暦9月13日から14日の夜にも行われ、こちらを十三夜(じゅうさんや)と呼びます。そして、こうした秋の夜に昇る月は「中秋の名月」と呼ばれます。
2020年の今年、旧暦8月15日は10月1日(木)、旧暦9月13日は10月29日(木)です。ただし、こうした十五夜や十三夜の月は、完全な満月ではありません。実際に満月になるのは、今年なら9月3日(土)や10月2日(金)、11月1日(日)などです。
十五夜や十三夜の夜の月齢は満月のそれ(13.8から15.8)とは限りません。例えば今年の10月1日の月齢は13.7、10月29日の月齢も12.3であって、満月の一歩手前です。
にもかかわらず、このように「名月の日」を決めて月を鑑賞する風習は、7~10世紀の中国の唐代の頃に始まりました。10~13世紀の宋代に記された「東京夢華録(とうけいむかろく)」という随筆には月夜の夜、人々が身分に関わらず街を挙げて夜通し騒ぐ様子が記録されているそうです。
日本にこの風習が入ってきたのは、平安初期の貞観年間の頃です。延喜19年(919年)には宇多法皇が十三夜の月見を催したという記録があり、このころの月見は詩歌や管絃を楽しみつつ酒を酌む、という貴族社会の遊びでした。
庶民とは縁のないものであり、現在のような願掛けや供え物といった宗教的な要素もありません。一般の人々は、満月のころになるとただ月を眺めつつその美しさを愛で楽しむだけでした。
室町時代に入ってからも、こうした派手な名月の鑑賞は上流社会で続いていました。しかし、応仁の乱以後の戦国期に入ると、権力を失った中央政権だけでなく地方の有力者たちもそれどころではない、ということで遊宴の内容は簡素になっていき、室町後期では名月の日には月を拝み、お供えをする程度になりました。
月を信仰の対象としてみるようになったのはこのころからで、御所に仕える女官達によって書き継がれていた当番制日記「御湯殿上日記」には、このころの天皇、後陽成天皇がナスに開けた穴から月を見て幸運を祈る「名月の祝」という祝い事の様子が記録されています。
時代がさらに下がり、江戸時代ころまでには月見はかなり世俗化しました。江戸初期の記録によれば、十五夜の日には飲み食いしながら夜遊びをするといったことが一般化しました。ただ、このころもまだ「月見団子」は登場していません。家庭にある普通の食べものを食べ、たとえば芋煮会といったようなものをしながら月見をしていたようです。
団子がお供えに使われるようになったのは江戸中期以降になります。十五夜の日に文机で祭壇をこしらえ、月見団子をお供えするといった、現在でも行われているような風習が定着したのは江戸後期のことです。ただ、地方によってお供え物は異なり、江戸では球形の月見団子が、京阪ではサトイモの形をした団子を供えていました。
一方、こうしてお供え物を準備しても、雲などで月が隠れて見えないこともあります。江戸の風流人たちは、こうした夜を「無月(むげつ)」と呼び、また中秋の晩に雨が降ることを「雨月(うげつ)」と呼んで、月が見えないながらもなんとなくほの明るい風情を楽しんだといいます。
さらに、江戸で月が見えても、地方によっては天候次第では月を見られない場合もあります。このため、ところによっては「月待ち」という風習があって、月夜になるまで待ってからお月見をしました。
一般には、15日の前の日の14日と当日を「待宵(まつよい)」、そのあとの16~17日を「十六夜(いざよい)」と呼び、名月の前後の月が月見の対象です。
これらの月が見えない場合、その翌日の十七夜の夜まで待って出た月は立待月(たちまちづき)と呼び、以後、居待月(いまちづき)、寝待月(ねまちづき)、更待月(ふけまちづき)と続きます。さらに二十三夜、二十六夜と月が出るまで待ち続ける地方もあるようです。
このように、日本人は月を鑑賞し、それを待ち続けるほどに崇めてきました。西洋でも月を鑑賞することに神秘的な意味を見い出す国は多く、月は人間を狂気に引き込むと考える民族もあるようです。
英語で“lunar”は「月の」という形容詞になりますが、 “lunatic”(ルナティック)といえば、気が狂っていることを表します。また狼男はまあるい満月の日に狼に変身し、魔女たちはそうした夜に黒ミサを開くとされます。満月には不思議な力があるとも、満月の夜には犯罪が増えるとも言われています。
このように満月を特別なものと考える国が多い一方で、同じ月でも新月のほうを崇める国々もあります。トルコ、パキスタン、モルディブ、マレーシアなどのイスラム圏の国がそれで、国旗には新月が描かれています。形は三日月のようにみえますが、これは月齢27~28日の月であり、ほぼ新月を表しています。
オスマン帝国の首都、コンスタンティノープルにおいては古くから新月がシンボルとして用いられていました。歴代の皇帝は国教であるイスラム教共通の意匠としてこれを広めようとし、その流れを汲む現在のトルコ共和国の国旗はいまでもかつてのオスマン帝国と同様新月があしらわれています。
とはいえ、新月を国旗に採用しているイスラム国家はそれほど多くはありません。これはオスマン帝国崩壊後、そこから独立した諸国の多くが、新月を意匠として採用しなかったためです。
トルコ共和国の国旗(基本的にはオスマン帝国当時のものと同じ)
赤十字と赤新月
現在でもイスラム教徒が多い国では新月を入れた国旗を使っています。ただ、イスラム圏では偶像崇拝の禁止が定められているため、月の崇拝は禁じられています。また、キリスト教信徒のイエス崇拝に繋がるという理由から十字も忌避されています。
こうした理由から、一般には「赤十字社」のシンボルは「赤十字」であるのに対し、こうした国ではそのシンボルに「赤新月」が用いられ、またその名称も「赤新月社」としているところが多くなっています。
赤十字といえば万国共通のものと思っている人も多いことでしょう。しかしその活動を日本やヨーロッパの多くの国が「赤十字運動」というのに対し、イスラム圏では「赤新月運動」と呼びます。いずれも戦争や天災時における傷病者救護活動を中心とした人道支援運動を行っていますが、シンボルと呼称だけは異なっています。
赤新月、もしくは赤十字を名乗るこうした組織は、世界各国に存在し、それらは国際的な協力関係を持っています。今日、赤十字・赤新月運動は、赤十字国際委員会 (ICRC)、国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)、各国の赤十字(赤新月)社の3組織で構成されています。
ただし、各組織は財政・政策の面で独立しており、ICRCは紛争、IFRCは自然災害、赤十字・赤新月社は主に国内で活動を展開し、それぞれの基本的な任務は異なります。
とはいえ、国を超えての活動は共同して行われ、国の内外を問わず、戦争や大規模な事故や災害の際の人道的支援は敵味方区別なく中立な立場で行われます。こうした活動は、1863年に制定された「ジュネーヴ条約」とこれに基づく各国の国内法によって行われ、特殊な法人格と権限を与えられています。
現在、世界に赤十字社があるのは152か国で、また34か国に赤新月社が設立され、合計186ヵ国が活動を行っています。なお、十字でも新月でもない“ダビデの赤盾”を用いるイスラエルのマーゲン・ダビド公社を含めると、全部で187か国で赤十字活動が行われていることになります。その主要任務は次の通りです。
紛争や災害時における、傷病者への救護活動
戦争捕虜に対する人道的救援(捕虜名簿作成、捕虜待遇の監視、中立国経由による慰問品配布や捕虜家族との通信の仲介など)
赤十字の基本原則や国際人道法の普及・促進
平時における災害対策、医療保健、青少年の育成等の業務
大半の国がそのシンボルには白地に赤い十字を模した赤十字(Red Cross)を採用しているのは上述のとおりです。
このマークは、赤十字社の設立者の一人であるアンリ・デュナンの母国スイスの国旗の赤地に白い十字の色を反転したものといわれています。ジュネーヴ条約にも「スイスに敬意を表するため、スイス連邦の国旗の配色を転倒して作成した白地に赤十字の紋章」との一文があります。
スイスの国旗 創設者のひとりアンリ・デュナンの母国
1863年に赤十字規約が制定された時から各国で使用されてきたものですが、当初は団体名は各国まちまちであり、こうした旗はおろか「赤十字社」という名称も使われてはいませんでした。
しかし団体の規模が大きくなるにつれて統一した名称が必要となっていったことを受け、1867年からオランダ救護社が通称として使っていた「赤十字社」を各国救護社の正式名称とすることが提案され、次々と各国がそれに倣っていきました。
ただし、中華人民共和国では「紅十字会」、また朝鮮民主主義人民共和国では「赤十字会」などと呼んでいます。
また、シンボルマークは赤十字ですが、上述のとおりイスラム諸国では、「十字はキリスト教を意味し、十字軍を連想する」として嫌われたため、白地に赤色の三日月を識別マークとし、「赤新月社」と呼ぶようになりました。
オスマン帝国もまた1865年にジュネーヴ条約に加盟しましたが、「ヨーロッパの瀕死の病人」といわれるほど国力の低下していたこの時代でもまだ多くの軍隊を抱えており、十字のマークは使えませんでした。兵士の大半がイスラム教徒であり、キリスト教の印である十字架の印を用いるのはタブーとされたからです。
そこで、1876年に新たに赤い三日月を模した赤新月のマークを制定し、以後オスマン帝国の救護部隊には赤十字に代わって赤新月を使用させる旨をスイス政府に通告しました。また、国際委員会には赤新月マークの使用を条件として加入することとしました。
第一次世界大戦後、いくつかのイスラム教国の新独立国が誕生すると、それらの国々は同じように赤新月を自国の団体のマークと定めました。ただ、インドネシアのようにイスラム教徒が多い国であるにも関わらず「赤十字社」を採用する国もありました。
一方では、パキスタン、マレーシア、バングラデシュなどのように、設立当初は「赤十字社」であったものの、国内の宗教事情の変化からのちに「赤新月社」に変更した国もあります。
さらには赤十字や赤新月以外のシンボルの使用を求めた国があります。イランの「赤獅子太陽(Red Lion with Sun)」などがそれです。最終的に認められましたが、国際委員会は現在に至るまで基本的にはこうした異なるマークの採用には否定的なスタンスを貫いています。
イスラム教国の赤新月マーク
第二次世界大戦後にユダヤ教を国教とするイスラエルが独立し、マーゲン・国の国旗ダビド公社(=ダビデの赤盾社)が設立された際、同国は「ダビデの赤盾(Red Star of David)」を使用したいと申請しましたが、このときも赤十字社のマークとして認定することは拒否されました。
このように赤十字国際委員会が、赤十字や赤新月以外の旗の採用を嫌うのは、余りにも多くの標章が乱立することで、混乱が生じることを懸念しているためです。しかし、国際委員会としては国際赤十字活動には多くの国が参加することを望んでおり、既に赤十字運動に参加していた国々も同じでした。
そこで、2005年の赤十字・赤新月国際会議総会において、赤十字・赤新月に代わる共通の標章採用が提案されました。賛成多数により採択されたそれは「赤水晶(Red Crystal)」とというものでした。赤の菱形を象ったマークで、宗教的に中立であり第三の標章としてふさわしいものと評価されたものでした。
この「赤水晶」の標章の意味や法的効力は従来の赤十字・赤新月と完全に同一とされています。つまり、このマークを用いれば国際赤十字への加盟が出来ることになります。こうしてイスラエルは「赤盾社」の名称のままで赤十字国際委員会に参加を正式に認められることになりました。
ただ、当初イスラエルが提唱した「ダビデの赤盾」は今でも認められていません。「表示標章」として紛争地帯を除くイスラエル国内のみで用いることを許されていますが、ジュネーヴ条約で定めた「保護標章」とはみなされていません。このため他国で交戦するような場合には用いることはできません。
このほか、国内にキリスト教とイスラム教徒が混在するような国もあり、こうした場合にも標章をどうするかが問題になります。
例えばエリトリアなどのように、宗教勢力のバランスから赤十字・赤新月の両方の標章を併用したいと主張している国があります。国際委員会としては、こうしたケースでも「赤水晶」を用いることによって国際赤十字へ参加できるようになるとアナウンスしており、その加盟を期待しています。
このようにたかが標章といえばそれまでですが、できるだけ多くの国に国際的な人道支援活動に参加してもらうためには、その国の国情に応じたシンボルを用意してあげる必要があるわけです。それぞれの国の国民が崇拝する宗教の違いはこうした国際規格を統一する際、いつも問題になります。
新標章の赤水晶(上)と、通常の赤十字(下)
赤十字社の設立
ところで、この赤十字社が創設されたきっかけは何かといえば、それは創始者の一人であるスイス・ジュネーヴ出身のアンリ・デュナンが1859年に北イタリアでの紛争に遭遇したことでした。
デュナンはこのころ、アルジェリアで現地の人々の生活を助けるための農場と製粉会社の事業を始めていましたが、そのために必要な水利権の許可が統治国のフランスから下りていませんでした。このため、このころイタリアでオーストリア帝国と戦っていたナポレオン3世に請願に行き、この戦闘に遭遇したのでした。
この戦争はソルフェリーノの戦いといいます。イタリアの統一を目指すサルデーニャ王国とフランスの連合軍が、これを阻止しようとしたオーストリア帝国と争ったものですが、この戦争では両軍合わせて20万を超える軍隊が衝突し、4万人近くの死傷者が出るほどの激戦となっていました。
デュナンは戦場に放置された死傷者とその救援活動をしている地元の女性たちの姿をみていたたまれなくなり、彼女たちに交じって自らも救援活動に参加するようになりました。
一週間ほどの短い滞在でしたがその悲惨さに大きな衝撃を受けた彼は、帰国した1862年、「ソルフェリーノの思い出」を出版。その中で「各国に戦争となった際に戦いの犠牲者たちを救援する組織を設けること」「戦闘による負傷者やその負傷者の救援にあたる者を戦闘に加わるいずれの側からも保護する法を定めること」の二つを提案しました。
デュナンのこの提案は大きな反響を呼び、翌年2月にはジュネーヴにおいて、デュナン、アンリ・デュフール、ギュスターブ・モアニエ、ルイ・アッピア、テオドール・モノアールの5人によって「国際負傷軍人救護常置委員会」(五人委員会。現・赤十字国際委員会)が発足します。
この5人はそれぞれ赤十字の設立に大きな役割を果たしましたが、とくにデュナンは優れた行動力を持ち、各国において赤十字の必要性を説き、支持を獲得する中心人物となっていきました。
残りの4人のうち、デュフールは元軍人で、1847年の分離同盟戦争(民主化推進派と保守派の間の紛争)においてスイスの分裂を防いだことで高い評価を得た人物です。この時に捕虜や負傷者に対し人道的な対応を取ったことで賞賛を浴び、その名声と各国への人脈から五人委員会の委員長となり、草創期の赤十字運動において指導的な役割を果たしました。
また、モアニエは弁護士であり、赤十字運動の理論化と組織化に力を尽くして、1910年に亡くなるまでこの運動の中核を担い続け、赤十字の育ての親ともいわれています。
アッピアは戦傷外科の権威であり、自らも医師として積極的に救護に出向くとともに、医学的な方面から助言を行いました。モノアールも外科医であり、指導層だけでなく一般市民への広報を重視していました。
五人委員会が設立された翌月の1863年3月には、委員会自身ではなく各国がそれぞれ民間救護団体を設立するという方針が確立され、ジュネーヴでこの問題に関する会議を開催することが決定されました。
これを受け各委員は各国に精力的な呼びかけを行い、10月には予定通り16カ国が参加する会議が開かれました。このとき参加した国々は以下の通りです。
スイス、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、ロシア、オーストリア、プロイセン、バーデン、バイエルン、ハノーファー、ヘッセン・カッセル、ザクセン、ヴュルテンベルク
このうち、プロイセン以下の7ヵ国は現在ドイツに属しています。従って現在の地図でいえばこのとき赤十字の設立に関わった国は10ヵ国ということになります。
この会合では、参加各国に救護団体を設立することなどが決められ、赤十字標章等を定めた赤十字規約が採択されました。またオランダ代表からこの団体はいかなる戦闘においても「中立を貫く」べきということが議題に提出され、採択されたことで中立原則も確立されました。
この会議が終わるとすぐに、具体的な救護団体設立の動きが本格化し、同年12月にはヴュルテンベルク王国(現、ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州)において世界初の赤十字社が設立されました。
翌1864年2月には現存する最古の赤十字社であるベルギー赤十字社が設立。その後も続々と多くの国がこの精神に賛同して救護団体を設立しました。同年8月にはスイスなど16カ国が参加した外交会議で「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(最初のジュネーヴ条約)が審議され、陸戦に適用されるこの条約には12カ国が調印して発効しました。
以後、ハーグ陸戦条約(ハーグ法)などの数々の国際人道法が設立されましたが、このジュネーヴ条約はその嚆矢とされており、その後欧州諸国は続々とこの条約を批准していきました。
1865年にはオスマン帝国が条約を批准、1868年には同国に救護団体が設立されるなどキリスト教圏以外にもこの運動は拡大していきました。現在、世界各国で繰り広げられている赤十字活動はすべてこの1863年のジュネーヴ条約に基づいています。
戦時国際法として傷病者及び捕虜の待遇改善を求めるこの条約は赤十字条約とも呼ばれ、これによって戦時下においても多くの人々の命が救われるようになったのです。
(この稿続く)