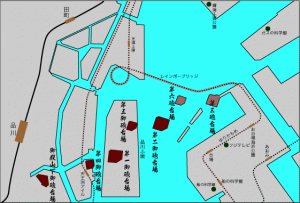1854年(安政元年)12月、わずか1年3ヶ月という短い期間で完成した五つの台場には、80ポンドの大型カノン砲を含む20~30門の大砲が配備され、翌年4月上旬、将軍徳川家定も出席し、台場完成を祝う試射会が開かれました。
実はこれに先立つ2月、ペリーが日本へ二度目に来航してきたときには、まだ完全には台場は完成していませんでした。が、ペリーは未完成ながらもその偉容に驚き、これより奥の江戸湾に侵入することなく、横浜まで引き返しています。
台場の配置は、江戸湾内の澪筋や水深の浅い場所の位置を正確に計算に入れて決められていたといい、大きな船は喫水が深いため、澪筋を通ってしか江戸湾の奥に進むことができませんでした。
従って、水深の浅い洲の上に台場を築いて、その間の水路を防御するという台場の配置は、蒸気船などの大型の艦船に対して、一定の効果を持っていたと思われます。
しかし幕末維新の動乱の中にあって将軍の居城である江戸城や江戸の街を守るため造られた台場は、結局一度も実戦に用いられることなく、その後の明治という時代を迎えます。
明治維新後、台場の所有権は陸軍省・内務省・民間さらに海軍省と、二転三転しました。その後は、第2台場に品川灯台が設置されたほか、第5台場には水上警察署の出張所が置かれるなど、東京湾内の安全を守るために使われました。また、第4台場は造船所として利用され、基礎工事のみが終了していた第7台場は牡蠣の養殖場として使われました。
第3台場だけが、第二次世界大戦時に高射砲が設置されるなど軍事目的に使われましたが、本来の目的の「海防」のために用いられることはとうとうありませんでした。
1923年(大正12年)の関東大震災では、各台場も石垣が崩れたり、内部の建物が倒壊したりするなどの被害を受けました。この内、第3台場と第6台場は、大正13年に国の史跡名勝天然記念物に仮指定(大正15年本指定)され、これを受けて東京市による補修工事が行われています。
第二次大戦後は、第5台場に一時的に戦災孤児収容施設が置かれたこともあったそうですが、東京港修築計画に伴う大規模な埋め立て工事によってその多くは潰され、船の通行にも支障があるという理由から撤去されました。
こうして昭和1962年(昭和37年)までには、第3・第6以外の台場は東京湾からその姿を消しました。
現在、残った二つの台場の内、第3台場は「第三台場史跡公園」という名前になっていて、お台場海浜公園と陸続きになり、歩いて立ち入ることができます。一方、第6台場のほうは立ち入りが禁止されていて、草木の生い茂る緑の小島として、東京湾内の野鳥のオアシスとなっています。
レインボーブリッジを渡ったことのある方も多いと思いますが、ここからは二つの台場を見下ろすことができます。また、日の出桟橋を発着する水上バスでお台場海浜公園に向かえば、海上から六号台場を間近に眺めることができるようです。
反射炉
さて、昨日から台場のお話が延々と続いてしまいましたが、その台場を築いた立役者、江川英龍のその後について書いていきましょう。
ペリー来航を契機に江戸湾海防の実務責任者となり、お台場建造を命じられ、これを見事に完成させた英龍ですが、幕府は江戸内湾での台場築造と平行して、ここに設置する大砲
の鋳造を英龍に命じました。
これに対して、英龍は大砲の鋳造にあたっては、「反射炉」と呼ばれる特殊な鋳造炉が必要であり、この建設を許可して欲しい旨を幕府に申請し、幕府もこの建造を許可します。
英龍は、早速建造の準備に取りかかり、当初その建造予定地は伊豆の下田港に近い賀茂郡本郷村(現下田市高場(たこうま))という場所に決定していました。この場所が選ばれたのは、現場が下田港に近く、資材や原料鉄の搬入のしやすさと、生産した大砲の搬出・回送の便を考えてのことだったと思われます。
1853年(嘉永6年)、お台場の建設が始まったのと同じ年の12月には、この下田で基礎工事も始められましたが、翌1854年(安政元年)の4月、下田に入港していたペリー艦隊の水兵が、反射炉建設地内に侵入するという事件が起こりました。
この年の2月13日、ペリーは予想よりもかなり早く再来日して横浜港に入港しました。お台場はこのころまだ未完成部分もありましたが、ペリー艦隊が品川沖まで侵入してきたとき、この砲台の偉容をまのあたりにし、目をみはったといいます。そして、品川より奥の江戸湾に侵入するのをあきらめ、神奈川沖まで引き返し横浜港に入港しました。
英龍らが短い時間に血の滲むような努力で完成させた台場は、こうして一応その成果をあげたのです。
横浜に入港したペリーらは、その後幕府と協議をはじめ、ひと月以上も粘った末、翌月の3月31日についに日米和親条約を締結することに成功。その中で下田も「開港場」として開放することを幕府に約束させることもできたため、横浜を出港後、アメリカへ帰国する直前に艦隊は下田に寄港していたのです。
反射炉の建設は、ペリーらも目にしたお台場に設置するための大砲を建造することを目的としていました。幕府にとっては国家機密であり、これをアメリカに知られることは、その後の外交上において好ましからぬ事態を招くことは明らかでした。このため、今後同様の事態が起こることを防ぐため、急遽反射炉建設地を移転することになりました。
移転先は、韮山代官所にも近い田方郡中村(現伊豆の国市中)と決定されました。内陸にあり、資材の搬入や製造された銃器の搬出には不利でしたが、代官所による監視もしやすく、外国人が入り込むなどの不慮の事故も防ぐことができました。
「反射炉」とは、銑鉄(鉄鉱石から直接製造した鉄で、不純物を多く含む)を溶解して優良な鉄を生産するための炉です。銑鉄を溶解するためには千数百度の高温が必要ですが、反射炉の場合、天井部分が浅いドーム形となっており、そこに熱を反射集中させることでその位置に高温を実現できる構造となっています
反射炉は、18~19世紀にかけてヨーロッパで発達し、その構造やそれを用いた鉄製砲の鋳造技術などの知識は、長崎の高島秋帆が輸入した蘭書などを通じて、日本にも伝わっていました。英龍も、それらの蘭書を研究し、反射炉についての理解を深めていたものと考えられます。
ヨーロッパで反射炉が発展した背景には、ナポレオンの存在がありました。19世紀初頭、ヨーロッパを席巻したナポレオンは、優れた戦術家として知られていますが、彼の得意とした戦術の特徴は、砲兵を重視し、大量の野戦砲を迅速に運用するというものでした。
これは、それまでの陸戦の常識を一変させる画期的なものであり、以後各国の陸軍は競って砲兵の充実を図ることとなります。ところが大砲を鋳造するにあたって、その材料となる錫と銅はこの当時いずれも高価な金属であったため、これによって造られる「青銅砲」自体も高価なものにならざるを得ませんでした。
より安価に大量の大砲を製造するためには、相対的に価格の低い材料が必要とされましたが、調査の結果、「鉄」がその材料として適当と考えられ、こうして鉄を原料に用いた大砲の製造が始められました。
しかし鉄は、錫や銅に比べてその融点(溶け出す温度)が高く、この問題を解決するためには特殊な炉が必要とされました。そしてその研究の結果、開発されたのが反射炉でした。
こうしたヨーロッパの事情は日本でも同様でした。英龍は自らの海防政策を完成させるためには、大量の大砲を製造する必要性を感じており、そのためには青銅砲に代わって鉄製の大砲を大量に生産できる反射炉の建設が不可欠であると判断したのです。
こうして計画がスタートした反射炉は、オランダのヒュゲニン(Huguenin)という人が著わした鉄製砲の鋳造マニュアルに掲載されていたものが参考にされ、伊豆の韮山で建設されることになったそれは、溶解炉を二つ備えるものを2基、直角に配置した形となっていました。
つまり、四つの溶解炉を同時に稼働させることが可能な設計であり、現存する韮山の反射炉は当初の計画通りに建造され、その後多くの大砲がこの反射炉によって鋳造されています。
その建設のためには、耐火煉瓦の開発なども必要であり、その煉瓦を焼く窯の調達や、焼いたあとの煉瓦の積み上げ方法などをめぐっても多くの思考錯誤もありましたが、そうした苦労もありながらも反射炉の建造は順調に進むかに見えました。
そうした最中、その竣工をみることなく、その設計者であり、計画の最高責任者であった江川英龍当人が江戸で亡くなってしまいます。1855年(安政2年)1月のことでした。
その前の年の暮れごろから英龍は何等かの病を得ていたようで、それをおして江戸や伊豆を往復していたころから、その病気が悪化したのではないかと思われます。
この前年、駿河湾沖で座礁したプチャーチン提督座乗のディアナ号を巡っては、幕府が出資してその代替船を建造することになり、その建造場所も同じ伊豆の戸田と決まり、後年「ヘダ号」と呼ばれる日本初の洋式帆船が建造が始まっていましたが、英龍はその建造責任者も兼ねていました。
これについては、当ブログの「ヘダ号」の項に詳しく書いてありますので、こちらものぞいてみてください。
かたやほぼ完成したとはいえ、まだ未完成の部分も多々あるお台場の建造責任者でもあり、そこに据える大砲を鋳造する反射炉の建設をも進めていた英龍の日々は、韮山や戸田、江戸と各地を転々とする中で、分刻みのスケジュールで進んでいたと考えられます。
詳しい死因は伝えられていませんが、その死の直前まで激務が続いていたといいますから、今で言うところの過労死であったかもしれません。多くの蘭方医が倒れた英龍の治療に携わったといいますが、そうした努力の甲斐もなく、その波乱に満ちた54年間の生涯を閉じることとなりました。
54才という年齢は、この当時の人の寿命からするとごく普通の年齢でしたが、その足跡を考えるとあまりにも早すぎ、惜しまれる死でした。ちなみに、ヘダ号は英龍の死から3ヶ月後の4月に完成し、日本初の西洋帆船の航行に成功しています。
英龍の死後、その遺体は韮山の江川邸のすぐ近くの「本立寺」に埋葬されています。本立寺は江川家が500年前に菩提寺として建立したもので、ここには英龍だけでなく、江川家ゆかりの者の墓石が100本以上も林立しています。
英龍の死を知った老中首座阿部正弘は、その就任当初こそ英龍には見向きもしませんでしたが、難工事といわれたお台場の建設を彼に一任した後は、その建設が彼なくしては進まないことを知るようになり、後年は彼の技術力だけでなく、人柄を高く評価するようになっていたといいます。
そして、なくてはならないその有能な幕臣を失った嘆きを、次のような歌に自らの気持ちを託して英龍の霊前に贈っています。
「空蝉は限りこそあれ真心にたてし勲は世々に朽ちせし」
「この世に生きている人の寿命には限りがあるものであるが、真心をもってことを成し遂げてくれた君の勲功は、その死後も朽ちることはないだろう」、というような意味でしょうか。
反射炉その後
老中首座の阿部正弘は、英龍だけでなく、その後勝海舟や大久保忠寛、永井尚志らの西洋事情通を登用して海防の強化に努めるとともに、高島秋帆を復活させて講武所の運営にあたらせるなど、洋式軍隊の整備を進め、長崎海軍伝習所、洋学所なども創設しました。
講武所はのちの日本陸軍の素地となり、長崎海軍伝習所は日本海軍、洋学所は東京大学の前身となっており、このほかにも大船建造の禁の緩和など幕末にあって、多くの幕政改革(安政の改革)にも取り組むなど、彼が手がけた事業の多くがその後明治政府に受け継がれました。
彼によって近代日本の基礎が造られたといっても過言ではなく、英龍を台場や反射炉、ヘダ号の建設責任者に任命したのも阿部正弘です。これ以外にも山ほどの事業を企画していましたが、1857年(安政4年)6月、老中在任のまま江戸で急死。
阿部正弘は将軍継嗣問題では一橋慶喜を推していたといい、生きていればその後の幕末の動乱において、慶喜の懐刀としてその能力を最大限に発揮したことでしょう。享年は39才。こちらも早すぎる死でした。
一方、英龍の死後、世襲代官江川家の跡を継いだのは、英龍の三男の江川英敏(ひでとし)でした。このとき英敏はわずか16才であり、単独では反射炉の完成はおぼつかないと周囲は考えたのか、英龍の代から交流があり、また蘭学の導入に積極的であった佐賀藩にその応援が依頼されました。
佐賀藩は快くこれを受け、杉谷雍助ら11名の技師を韮山に派遣し、英敏の要請に応えています。その結果、阿部正弘が亡くなったのと同じ年の(安政4年)11月、すべての炉が稼働可能な状態となり、反射炉は着工から3年半の歳月をかけて、ようやく完成の日をみました。
完成した反射炉では、幕末直前の1864年(元治元年)に使用が中止されるまで、数多くの鉄製砲が鋳造されました。
それらの中には、英龍が完成させたお台場に設置された6~80ポンドの大小のカノン砲(日本語では「加農砲」と表記)も含まれています。カノン砲は、低い弾道で目標物を直接狙うもので、お台場を通過する船舶を砲撃するのには最適な砲でした。カノン砲はお台場の固定砲以外にも移動式の野戦砲などの多くの種類が造られました。
このほかにも、攻城戦などの主として目標間に遮蔽物がある場合に用い、強力な搾穿威力を持つモルチール砲(臼砲)、カノン砲とモルチール砲との中間的な大砲で多目的に使用できるホーイッスル砲(忽砲)、小型船舶搭載用のボートホーイッスル砲などもこの韮山の反射炉で造られました。
反射炉を無事完成させた英龍の三男、英敏は反射炉の完成後の5年後にわずか23才で亡くなり、その跡を継いだのが英龍の五男の英武で、その後幕府が瓦解したことからこの人が、最後の韮山代官となりました。
明治維新後、反射炉は陸軍省に移管されましたが、その後はより強度の高い鉄を鋳造できる転炉などが導入されたことから、その後は使われることもなくなり、長い間放置されていました。
次第に破損の進む反射炉の保存運動が本格化したのは、英龍の没後50年にあたる1905年(明治38年)からのことです。
反射炉の保存運動は、韮山県令の女婿であった山田三良(さぶろう)という東大法学部の教授と、最後の韮山代官江川英武の息子で同じく東大法学部教授だった「江川英文」氏らが中心になっておこし、陸軍省の後援もあって無事、その保存修理事業を実現させました。
江川英文氏は、その後財団法人江川文庫を設立し、現在も残る江川邸の保存に努めるとともに、江川家代々の資料を研究者に公開する活動をしていましたが、1966年(昭和41年)に逝去。江川文庫は現在、英文氏のひ孫の江川洋氏が代表を務められており、その方のお父様?とお見受けする方に私たちがニアミスしたことは、この項の初めに書いたとおりです。
この江川文庫には、韮山代官役所の公文書と江川家の私文書などからなる古文書類と、多くの典籍、書画・工芸類・洋書・古写真・銃砲鋳造関連資料などが保管されており、このうち代官役所文書のうち、整理された3000点余りが昭和40年代に公開されはじめ、その後も整理が続いて現在では6000点程の古文書が公開されているそうです。
現在も非公開の資料の公開をめざして、静岡県が主体となり文化庁の後援を得て、整理・調査が続けられているそうで、最終的には目録点数だけで数万点に及びそうだということです。
反射炉の保存修理は明治42年1月に終了し、周囲に鉄柵をめぐらせ、煙突には地震対策として鉄帯をはめて補強された反射炉が完成しています。そして、1922年(大正11年)には史跡名勝天然記念物法によって史跡に指定され、最近、世界遺産への登録をめざして運動が行われ始めました。
その後は、1930年(昭和5年)の北伊豆地震によって北側炉の煙突上部が崩壊するなどの被害を受けたこともありましたが、昭和、平成と計三回の修理を経て、現在もその姿を間近に見ることができます。
幕末期には、佐賀藩や萩藩、水戸藩などでも反射炉が建造されましたが、当時のほぼ原形を保っているのは韮山の反射炉だけです。私も郷里の山口萩の反射炉を見に行ったことがありますが、原型をとどめているのは煙突部分だけであり、韮山の反射炉のようにきれいには保存されていません。
ヨーロッパでは製鉄技術の発展とともに高性能の高炉が開発されて反射炉に取って代わったため、反射炉の遺構は残っていないそうで、日本でもその後転炉などの最新式の鉄溶融炉が導入されたことから、現存する反射炉は全国でも数カ所になってしまいました。
調練所と韮山塾その後
韮山で「反射炉」を計画し、その完成を見ずして亡くなった江川英龍は、これ以外にも韮山で近代的装備による農兵軍の組織を企図しており、その一環として軍隊では食糧の補給がもっとも重要なテーマのひとつであると考えました。
そして軍用の携帯食料として「パン」の効用に着目し、日本で初めてパン(堅パン)を焼いたことは昨日も書きましたが、この兵糧パンは後年幕府軍が薩摩や長州と長期戦を戦ううえで大いに役立ったといいます。このため後年英龍は、日本のパン業界からは「パン祖」とも呼ばれるようになりました。
こうした数々の英龍の偉業をたたえ、英龍が亡くなった1855年(安政2年)の5月、その後を継いで韮山代官に就任した江川英敏に対して、幕府は芝の新銭座(しんせんざ)に八千数百坪の土地を下賜し、その後ここには大小砲専門の演習場と付属の建物が設置されました。
芝新銭座のこの調練場は「大小砲習練場」と呼ばれ、その後、幕府の徒組(かちぐみ)が入門して西洋砲術を学んだのをはじめとして、数多くの幕臣が砲術の伝授を受けており、諸藩士の入門者と合わせると、その人数は三千人以上にのぼりました。
他藩の入門者の中には、井上薫、黒田清隆、大山巌など、明治維新で名をなした長州や薩摩などの西国の人材がとくに多く含まれています。
英龍亡き後、入門者の指導に当たったのは、韮山塾で英龍から直接兵学を伝授された、壬生藩士の「友平栄(さかえ)」や川越藩士の「岩倉鉄太郎」と、韮山代官所の手代として高島秋帆から共に砲術を学んだ岩嶋源八郎・長澤鋼吉などでした。
調練場には理論を学ぶための学塾も併設されており、そこでは後に幕府の歩兵奉行となる大鳥圭介らが招かれ、語学を講義していました。また、築地に設けられた軍艦操練所との交流も盛んで、榎本武揚や福地源一郎(桜痴源一郎、後の東京日日新聞主筆)、福沢諭吉らもしばしば訪れたと伝えられています。
のちに福沢諭吉がこの調練所の建物を譲り受け、「慶応義塾」を創設したことは先のこのブログでも述べました。
後年、福沢諭吉が記したという「福翁自伝」には英龍の記述があり、「江川太郎左衛門も幕府の旗本だから、……(中略)、これもなかなか評判が高い。あるとき兄などの話に、江川太郎左衛門という人は近世の英雄で、寒中袷一枚着ているというような話をしているのを、私が側から一寸と聞いて……」などと記しており、この当時の英龍の高名ぶりを披露しています。
韮山で英龍が創設した「韮山塾」は、その後これを母体として、1886年(明治19年)、町村立「伊豆学校」として再発足。前述の英龍の五男、江川英武氏が韮山の地元有力者に請われて初代校長に就任しました。
江川家は、1868年(慶応4年)に戊辰戦争が勃発した際には、早々に明治政府側に恭順の意を示したため旧領を安堵され、1869年(明治2年)には最後の韮山代官だった、江川英武が「韮山県」の知事となりました。
その後、江川英武は明治4年(1871年)、兵部省の命を受け、岩倉使節団と共に留学生として渡米し、約8年の留学の後、1879年(明治12年)に帰国。内務省・大蔵省に出仕しました。
江川英武が伊豆学校の校長に請われて伊豆に戻ったのは33才の若さのときであり、明治政府を辞した理由はよくわかりません。が、薩摩や長州の人材ばかりが登用される明治政府の中にあって、旧幕臣の出身である英武の居場所はかなり狭かったためかもしれません。
この学校では、英語教育と柔道教育(富田常次郎氏を講師として招聘)に力を入れましたが、経営難から生徒が減少し、英武は数年後に校長職を辞して東京に戻りました。しかし、学校そのものは継続され、現在、「静岡県立韮山高等学校」として、現存する江川邸のすぐ西側で多くの学徒を排出し続けています。
ちなみに、富田常次郎という人は、もともとは沼津の西浦という場所の出身で、幼少時に天城で給仕をしていたところを、ちょうどこのころ天城山に出張に来ていた海軍省管財課に勤務の「嘉納治郎作」の目にとまり、嘉納治郎作の息子で、後年柔道家として有名になる「嘉納治五郎」の書生として引き取られました。
常次郎は、嘉納治五郎が1882年(明治15年)に講道館を設立する折には、その一番弟子として尽力し、講道館四天王の一人として称せられるようになります。四天王とは常次郎をはじめとして、西郷四郎、横山作次郎、山下義韶の4人で、この中の西郷四郎が「姿三四郎」のモデルといわれています。
しかしながら、韮山塾の精神を後世に伝えていこうとした英武の努力にもかかわらず、数年後には伊豆学校の生徒数は激減します。高額な教員への給料や学校運営の出資金の不足が、定員減の原因だったようです。
資金不足の原因は、英武を招聘した地元有力者たちのその後の協力が思ったほどのものではなかったためのようで、かつての江川家の家臣であった岡田直臣という人物がこの頃の「君澤田方郡」の郡長でしたが、こうした有力者による伊豆学校への協力も薄く、このため次第に英武の情熱も冷めていったようです。
伊豆学校を辞し、東京へ移った最後の韮山代官、江川英武は、その後又、第1回衆議院議員総選挙に静岡県第7区(駿東郡など)から無所属で出馬しましたが落選。続く第2回衆議院議員総選挙にも同選挙区から立候補しましたが、このときも最下位得票で落選しています。昭和8年(1933年)、神奈川県三浦郡葉山町において死去。享年81才でした。
衆議院選挙に落選後の晩年の多くは東京で過ごし、亡くなるまでの四十年以上は伊豆での学校経営の失敗を悔やんでいたのか、あるいは選挙落選の反動なのか、あたかも徳川幕府瓦解後の徳川慶喜の晩年と同じように趣味に没頭する生活をして過ごしていたそうです。
しかし、英武が校長として育てた伊豆学校は、この当時としては最高の質を持つ名門校だったようで、ここを卒業した生徒たちの多くがその後政界や財界で活躍していきました。幕末にあってその後の時代を支える英才を数多く輩出した韮山塾を彷彿させるものがあり、その伝統は現在の県立韮山高等学校に受け継がれているといいます。
その韮山高校の校訓は、「忍」だそうです。江川英龍が29才のときに亡くなった母の「久子」が亡くなる直前、「早まる気持をおさえ、冷静な気持を常に持つように」とこの文字を英龍に遺言したといい、以後英龍は「忍」の文字を書いた紙を死ぬまで懐中に携帯していたといいます。
その英龍の精神は、今も韮山高校に受け継がれており、同校ではその創立者はその当時の県令「柏木忠俊」氏であるとしながらも、これとは別に江川英龍、坦庵公を「学祖」として仰いでいるということです。
この韮山高校のすぐ裏手には、かつて北条早雲が築造した「韮山城」の跡があり、この山頂に登ると、そこからは西北方面に田方平野が一望でき、その彼方には堂々とした富士山を眺めることができます。
江川英龍の時代にはもうすでにこの韮山城は廃城になっており、徳川幕府による太平の世でもあって砦などの構造物もなく、このためこの場所は江川家の人間にとっては「庭」のような存在だったものと思われます。
おそらくは英龍も江戸から伊豆韮山へ帰ってきたときには、何度となく散歩がてらにこの山に登り、我々と同じように富士山を眺めていたに違いありません。
その眼下には、英龍が設立した韮山塾の跡を引き継いだ韮山高校のグラウンドがほんとうに間近に見え、時折、校舎内からは、風に運ばれて授業を行う先生の声や生徒たちのざわめく声までが聞こえてきます。
そしてその生徒たちは、英龍が残した「忍」の字を継承する子供たちです。いつか彼らの中から英龍の意思を継ぎ、時代を率いていってくれるような逸材が出てくれることを祈りつつ、この項を終えたいと思います。
伊豆の国市周辺では最近、「江川酒」というお酒が製造されたそうです。いつか入手し、かつての英龍の栄華をしのびつつ晩酌をしてみたいと思います。その「味」がどんなものかについては、またこのブログでも紹介することにしましょう。