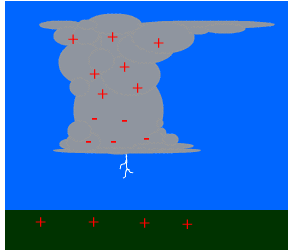先日の富士山の世界遺産登録の日は朝からスカッ晴れであり、その後も日中は陽射しに恵まれる日が続いていましたが、今日は一転、朝から雨模様でこの天気は終日続くようです。
一日雨というのは久々であり、梅雨らしいといえば梅雨らしい静かな一日になりそうな気配なのですが、しかしこんな日なのに、なぜか今日は「雷記念日」なのだそうです。
そのいわれは、930年(延長8年)に平安京の清涼殿に落雷があり、たくさんのお公家さんが亡くなったことに由来するようです。旧暦の6月26日ですから、現在ではほぼひと月遅れの7月の終わりごろのころのことだったようです。
この時落雷の直撃を受けて亡くなった一人に、大納言の藤原清貴がいます。このころ右大臣にまで上り詰めていた菅原道真の太宰府への左遷に関わった一人とされており、このため、この落雷は道真のたたりであると信じられるようになりました。
この道真失脚の政変は、昌泰4年(901年)に起こったことから「昌泰の変」といわれています。
醍醐天皇の治世下で昇進を続た道真の主張する中央集権的な財政に対して、朝廷への権力の集中を嫌う藤原氏などの有力貴族が反撥したために起こったものでした。
道真の進める政治改革には、現在の家格に応じたそれなりの生活の維持を望む中下級貴族の多くが不安を感じていたといい、このため道真の排除の動きに同調するものも多く、醍醐天皇も道真によって朝廷が牛耳られていることを快く思っていなかったようです。
こうして、道真は簒奪(本来君主の地位の継承資格が無い者が、君主の地位を奪取すること)を謀ったと虚偽の告訴をされ、罪を得て大宰権帥に左遷されることになりますが、左遷先の大宰府で、失意のなかわずか二年後に亡くなっています。
道真が京の都を去る時に詠んだ「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」はあまりにも有名です。その梅が、京の都から一晩にして道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという「飛梅伝説」もまた有名なお話であり、前にこのブログでも取り上げました。
ところが、その道真の死後、京には相次いで異変が起こるようになります。
まず道真の政敵であり、その左遷の首謀者であった藤原時平が延喜9年(909年)に39歳の若さで病死します。さらにこれから14年後、同じく左遷に賛成した醍醐天皇の皇子で時平の甥にあたる東宮の保明親王が延喜23年(923年)に薨去(こうきょ・皇族以上の崩御のこと)。
次いでその息子で皇太孫となった慶頼王もまた延長3年(925年)に亡くなります。慶頼王もまた時平の外孫に当たる人であり、これで時平を含めて醍醐天皇ゆかりの人物三人が次々と亡くなったことになります。
京の巷では、これだけでも道真の祟りではないかと噂がたちはじめていたといいますが、そんな中、930年(延長8年)の6月26日に、醍醐天皇がいる清涼殿である朝議が行われることになりました。この朝議での主な議題は、この年に生じていた平安京周辺の干害に対して、雨乞いの実施をやるかどうか、その是非について議論することだったそうです。
ところが、会議が始まってまもなくの午後1時頃より愛宕山上空から黒雲が垂れ込めて平安京を覆いつくして雷雨が降り注ぎはじめ、さらにはそれからおおよそ1時間半後に遠くから雷鳴が轟き始めました。雷鳴は徐々に清涼殿のほうに近づいてきて、近くで稲光が見えたと思った瞬間、突如、清涼殿の南西の第一柱に落雷が直撃。
この落雷に周辺にいた公卿・官人らが巻き込まれます。公卿では大納言民部卿の藤原清貫が衣服に引火した上に胸を焼かれて即死。右中弁内蔵頭の平希世も顔を焼かれて瀕死状態となりました。清貫は陽明門から、希世は修明門から車で秘かに外に運び出されましたが、希世も程なく死亡しました。
落雷は清涼殿だけでは終わらず、引き続いて隣の紫宸殿(ししんでん)にも走り、右兵衛佐美努忠包が髪を、同じく紀蔭連が腹を、安曇宗仁が膝を焼かれて死亡、更に警備の近衛も2名死亡。この一連の落雷によって全部で7人も死亡するという大惨事になりました。
このとき清涼殿にいたものの、危うく難を逃れた他の公卿たちも大混乱に陥り、この場に居合わせた醍醐天皇もまた、急遽清涼殿から常寧殿(じょうねいでん)という別の棟に避難しました。しかし、目の前で起こった惨状は彼にとってかなりのショックだったようで、この事件を境に体調を崩し、それから3ヶ月後に崩御してしまいます。
天皇の居所に落雷したということも衝撃的でしたが、死亡した藤原清貫は、かつての昌泰の変の際、菅原道真の動向監視を藤原時平に命じられていたこともあり、清貫は道真の怨霊に殺されたという噂が瞬く間に京中に広まりました。
こうして、この清涼殿落雷の事件以降、菅原道真の怨霊は雷神と結びつけられるようになります。道真の怨霊が雷を操ったのだということとなり、道真が雷神になったという伝説が全国的に流布するようになっていったのです。
このため、朝廷は京都の北野には北野天満宮を建立し、ここに火雷天神を祭って道真の祟りを鎮めようとしました。そして、以降百年ほどの間、大災害が起きるたびに道真の祟りとして恐れ、北野天満宮にはその度ごとに祈りが捧げられるようになりました。
やがては北野天満宮の末社が全国に作られるようになり、こうして「天神様」として信仰する天神信仰が全国に広まることになっていきます。各地に祀られた祟り封じの「天神様」は、そもそもは災害を封じるための神様だったものが、やがて災害の記憶が風化するに従い、道真自身をも祀る神社になっていったものが多いようです。
道真は生前優れた学者・詩人であったことから、後に天神は学問の神として信仰されるようになり、その多くが現在のように受験生にとって無くてはならないものになっていったわけです。
ちなみに、清涼殿の大参事を道真の祟りだと恐れた朝廷は、これ以降、道真に贈位を行い、また同じく流罪にされていた道真の子供たちの罪を解いて京に呼び返しています。
ところが、落雷のあった930年よりも7年前の923年(延喜23年)には既に朝廷は道真の罪を赦しています。この年までに藤原時平や保明親王が相次いで亡くなったことから、このとき既に彼らの死は道真の祟りだと考え初めていたのでしょう。既に道真は亡くなっていましたが、朝廷は生前の官位であった右大臣に復し、正二位を贈っています。
清涼殿の落雷以降に道真が復権したというふうに考えている人が多いと思いますが、実際にはこの事件よりも前から道真は赦されていたのです。
しかし、この落雷事件により改めてこれは重大事件だと朝廷も認識したのでしょう。改めて道真の霊を鎮めるための対策を本格的にやらなければならない、と考えたでしょうが、と同時に、どうせならこの事件をうまく利用しようと考えたのかもしれません。
おそらくは、この落雷事件を契機として北野八幡宮などの建立を行い、これを「災害対策」として知らしめることで人心を集めたかったのではないかと思います。この事件を契機として、こうした大災害はすべて道真の怨霊のせいにし、これを鎮めるための末社を全国に建立していくことで各地に朝廷の権威を流布したかったものと思われます。
各地での神社の建設は公共事業による景気対策の面もあり、かつこの当時はこうした神社にお参りして、荒ぶる神様の霊を鎮めることこそが「災害対策」であったわけです。
こうして道真の死はうまく利用され、怨霊として人々に恐れられるようになりましたが、一方で荒神様として崇めたてられるようにもなります。その後の災害対策にも大いに貢献したということで、朝廷は清涼殿の災害から63年後の正暦4年(993年)にさらに道真に正一位左大臣の位を贈り、また同年太政大臣の位まで贈っています。
こうした名誉回復の背景には、「災害対策の功労者」として道真を認めたということもあるでしょうが、道真を讒言した時平が早逝した上にその子孫が振るわず、道真にも好意的だった時平の弟・忠平の子孫が藤原氏の嫡流となったことも関係していたといわれています。
さて、日本ではこのように雷といえば神様であり、その神様が変じて菅原道真もまた雷神の象徴ということになってきたという経緯がありますが、諸外国でも古来より、雷は神と結びつけて考えられることが多かったようです。
ギリシャ神話ではゼウスがやはり雷神様であり、ローマ神話でもユピテルこと、「ジュピター」こそが雷神です。インドでもバラモン教のインドラは天空の雷神であり最高神です。
欧米ではカシが特に落雷を受けやすい樹木とされたのでゼウス、ユピテル、北欧神話のトールの宿る木として崇拝されたそうで、欧州の農民は住居の近くにカシを植えて避雷針がわりとしたとか。また、犬、馬、はさみ、鏡なども雷を呼びやすいと信じていたので雷雨が近づくとこれらを隠す風習があったといいます。
雷雨の際に動物が往々紛れ出ることから雷鳥や雷獣の観念が生まれ、アメリカ・インディアンの間では、その羽ばたきで雷鳴や稲妻を起こす巨大な鳥が存在すると考えられましたが、この鳥こそがあの「サンダー・バード」です。
アメリカインディアンの造るトーテムポールの先端にこのサンダー・バードの彫刻がされているのを見たことのある人もいるでしょう。姿は大きな鷲で、羽の色は雷のようであり、雷の精霊で自由自在に雷を落とすことができ、獲物も雷で仕留めるといわれていますが、アメリカでは、これを実際に「目撃した」とされる人が過去に何人もいます。
日本でいうところの「ツチノコ」あるいは河童のような存在というわけですが、この話は長くなりそうなので、また次の機会にしましょう。
話はまた日本に戻りますが、日本神話において雷は「最高神」という扱いは受けてはいませんが、雷鳴を「神鳴り」とも書くことからわかるように、道真の一件よりももっと古くから信仰されてきていました。
日本書記などではすでに葦原中国(日本)を平定した神さまとして、タケミカヅチ(建雷命、建御雷、武甕槌)が登場しており、これは雷神の代表という扱いでした。
平安以降、各地にある天満宮こそが雷神様の祭りどころという認識が定着していきましたが、これよりも前から日本各地に「雷電神社」と呼ばれるものがあり、このほかにも「高いかづち神社」などがありました。
これらの神社では、火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)・大雷大神(おおいかづちのおおかみ)・別雷大神(わけいかづちのおおかみ)などを祭神としていましたが、平安時代以降は人々に禍をもたらす神と考えられるようになり、天神の眷属(けんぞく)神として低い地位を占めるようになっていきます。
雷が起きると、落雷よけに「くわばら、くわばら」と呪文を唱える風習が今も残っていますが、これは、菅原道真の土地の地名であった「桑原」にだけ雷(かみなり)が落ちなかったという話に由来します。
平安時代に藤原一族によって流刑された道真が恨みをはらすため雷神となり宮中に何度も雷を落とし、これによって藤原一族は大打撃を受けることになったわけですが、このとき唯一、桑原だけが落雷がなかったので後に人々は雷よけに「桑原、桑原」ととなえるようになったといわれています。
「神鳴り(かみなり)」は言うまでもなく、その昔雷は神が鳴らすものと信じられていたためこう呼ばれるようになったわけですが、さらに古語や方言などでは、いかづち、ごろつき、かんなり、らいさまなどの呼び名もあるようです。
一方、雷は、「いなずま(いなづま)」とも言われます。その語源は稲が開花し結実する旧暦(太陰暦)の夏から秋のはじめにかけて雨に伴い雷がよく発生し、その落雷によって大気中の窒素が田畑に固着されるため、稲が良く育つようになります。これは本当の話のようです。
しかし、昔の人は、落雷した稲穂は雷に感光することで実るというふうに誤解していたため、雷を稲と関連付けて稲の「つま(=配偶者)」として、「稲妻」と呼ぶようになり、ときには言い方を変えて「稲光」(いなびかり)などと呼ぶようになったといわれています。
雷は田に水を与えて天に帰る神であったため、今でも農村では雷が落ちると青竹を立て注連縄(しめなわ)を張って祭る地方があるそうです。
また、どこの方言だか知りませんが、雷のことを「かんだち」と呼ぶところもあるようで、これは「神立ち」すなわち神様が現れるという意味で使われたのでしょう。
……とここまで書いてきたのですが、この後に続く「雷の歴史」なんてものがあるわけでもなく、これ以上話の広がりはなさそうなので、ここからは、雷とは、そもそもどういう現象なのかということについても説明していこうと思います。
語源や由来だけ書いて、その原理を知らせないというのはこのブログではあってはならない……なんて妙な義務感をもっているわけではありません。ただ単に自分の理解としても整理しておきたかっただけです。
ただ、これを説明しようと思って調べたのですが、この雷という物理現象をわかりやすく説明するのはなかなか骨が折れそうです。
が、あえて難しいことろは省いて、できるだけ簡単に説明してみましょう。
まず、雷の定義ですが、雷というのは、一口で言うと、「電位差が発生した雲または大地などの間に発生する光と音を伴う大規模な放電現象」ということになります。
雷を発生させる雲を雷雲と呼び、その時に雲は「帯電状態」つまり電気を帯びた状態となっています。なぜ雲の中で電気が生じるかは後で説明するとして、こうして雲の中で生じた電気が放電現象を起こしたものが「雷」です。
雲の中だけで起こる放電現象の種類にはいろいろありますが、これらはまとめて「雲放電」と呼ばれ、雲と地面との間の放電を「対地放電」つまり、これが「落雷」ということになります。
一方、気象用語としては雷のことは総じて「雷電」といいます。「雷」とだけ単独に言わないのには理由があります。
雷には光がつきもので、雷の発生に伴う光は俗に「稲妻」と呼ばれますが、これが、「雷電」のうちの「電」にあたるものです。一方、雷に際しては大きな音響がおこります。これも俗には「雷鳴」といわれますが、これは「雷電」という用語の「雷(らい)」にあたるものです。
従って、「雷電」とは、光と音を伴う放電現象のことであり、このふたつを合わせた用語ということになります。通常我々は雷(かみなり)と単に言うことが多いのですが、雷を物理的に表現するには「雷電」のほうが正しいのです。
ただ、現実的には遠方で発生した雷は光は見えるものの、風向きの影響などで音が聞こえない事もあります。雷電のうち、雷がないので、ただの「電」じゃないかということになってしまいますが、これはその通りです。音がないので、気象状況としては「雷電」は発生していない状態ということになります。
このため気象庁などでは雷と認められるものを「雷とは雷電(雷鳴および電光)がある状態。電光のみは含まない」とわざわざ定義しているくらいです。
さて、ではどうやって雲の中で電気が発生するのでしょうか。
とくに夏などで、日照により地表が著しく温められ、これに伴い大気も暖められることなどにより上昇気流が発生します。高い湿度を含んだ上昇気流は、低い位置から高い位置へ運ばれる際に次第にその湿度が飽和状態に近づき、一定の水蒸気量を超えると水滴になります。
この時点はまだ雨とならず、「雲粒」という状態であり、これが集まって雲となり、気流の規模が大きいほど高空にかけて発達しますが、これが我々が夏空でよく目にする積乱雲、つまり入道雲です。
この水滴はさらに高空にいくほど低温になるため、氷の粒子である氷晶になります。この氷晶はさらに成長してやがて霰(あられ)にまでなり、さらに上昇気流にあおられながら互いに激しくぶつかり合って摩擦されたり砕けたりします。
このとき、霰とあられが擦れあうことで静電気が発生し、霰にはこの静電気が蓄積されます。しかし、こうして高所でできた霰は氷晶よりも重たいため、次第に入道雲の下のほうに溜るようになります。一方、軽い氷晶は霰よりも上空に残されたり、逆に持ち上げられたりしますが、このとき、霰にはマイナスの電気、氷晶にはプラスの電気が蓄えられます。
つまり、入道雲の上層にはプラスの電荷が蓄積され、下層にはマイナスの電荷が蓄積されるという状態になります。
霰はマイナス、氷晶はプラスに帯電する原因は、長らく研究者の間で議論されてきた経緯があり、これを簡単に説明するのは冗長になるのでやめておきます。諸説があり、これらを全体的観点からまとめたものは、「着氷電荷分離理論」という難しそうな題名が付いています。
が、結論だけ言うと、霰や氷晶がプラスになるかマイナスになるかについては、雲の中の「雲水量」つまり「湿度」が関係しており、湿度が「低い」状態で氷晶と霰が衝突すると、霰より低温の氷晶がプラスに、高温の霰のほうマイナスに帯電するのだそうです。
さて、上層に溜まった氷晶と下層の霰がそれぞれプラスとマイナスになり、この間の電位差がかなり大きくなると、霰や氷晶の間にある「空気」はもはや絶縁の状態を越え、ある一定の限界値を超えると霰や氷晶の中の電子が空気中に放出されるようになります。
この限界値は約300万ボルトというすさまじく高い値です。放出された電子はさらに空気中にある気体原子と衝突してこれを電離させます。
電離というのは、物理学の分野では「荷電」ともいい、空気の成分である酸素や水素の分子や原子が、この霰や氷晶から放出されたエネルギーを受けて、自らも電子を放出するようになる状態です。「イオン化」ともいい、インテリアオブジェの「プラズマボール」で見ることのできるプラズマもこの電離(イオン化)現象のひとつです。
要は空気などの気体を構成する分子が部分的あるいは完全に電離し、陽イオンと電子に別れて自由に運動している状態であり、ともかくエネルギー量がむちゃんこ大きい状態といえます。
さて、電離によって雲のなかには大量の陽イオンと電子が次々と作られていきます。生じた陽イオンは電子とも衝突して新たな電子を叩き出し、こうしてできた2次電子が重なりあっていくうちには団子状態となり、ついには、「雪崩(なだれ)」のような状態にまでなり、連続した放電現象が生じます。
このときこの「電子雪崩」は、雲の上層ではなく、雲の下層へ向って飛び交います。これがいわゆる「稲妻」です。ただ、この段階では電子雪崩は雲の中だけで起こっている状態です。飛行機に乗っているととき、ときどき雷雲を見る機会がありますが、このとき雲の中だけでピカッと光っているような稲光はこの状態の雷です。
一方、積乱雲の下層に溜まった霰によってマイナス電荷が蓄積されると、ここから遠く離れた地表では、今度はプラスの電荷が誘起されます。これを「静電誘導」といいます。この両者の間でも、電位差がある一定を超えると放電が起きますが、これがいわゆる「落雷」です。
落雷は大気中を走る強い光の束として観測されます。1回の放電量は数万~数十万アンペアもあり、電圧は1~10億ボルト、地上の電力に換算すると平均で約900GW(=100W電球90億個分相当)に及ぶというすさまじいものです。
エネルギーに換算するとおよそ900MJであり、もし、無駄なくこの電力量をすべてためる事ができるなら、家庭用省電力エアコン(消費電力1kW)を24時間連続で使い続けた場合、10日強使用できるといいます。
ただ、この落雷が発生する瞬間は、時間にすると1/1000秒程度でしかありません。この間に、発生する音が「雷鳴」です。雷鳴は、雷が地面に落下したときの衝撃音だと思っている人が多いと思いますが、これは間違っています。
放電の際にはすさまじい「熱」も発生するため、この熱量によって雷周辺の空気が「ぐわっ」と急速に膨張し、音速を超えることによって「衝撃波」が生じることによって音が発生します。よくジェット戦闘機が空を飛ぶときにものすごい音がしますが、この飛行機が音速を出す性能があったとしたら、その音はかなり雷鳴に近いでしょう。
ちなみに、この衝撃波が発生する際に、雷が周囲の与える熱量もものごいもので、1マイクロ秒という瞬間に周囲の大気の温度は局所的に2~3万℃に上昇するといいます。
ただ、この衝撃波、つまり雷鳴は音速で伝わるため、音が伝わってくる時間の分だけ、稲妻より遅れて到達します。雷の発生した場所が遠いほど、稲妻から雷鳴までの時間が長くなりますが、この時間を計れば雷が発生したところまでのおおよその距離もわかります。
これまでに経験的にかなりのデータが蓄積されてきたことから、この距離は割と簡単な計算式で求めることができます。
発現地点までの距離(自分を中心とした半径)をP 、稲妻が光ってから雷鳴が聞こえる瞬間までの秒数を Sとすると、その計算式は次のように表されます。
P=0.34×S(単位キロメートル)
従って、ピカッと光って雷鳴が聞こえるまで10秒だったとすると、雷はあなたを中心とする周囲3.4kmのかなたで生じたことになります。
雷鳴が聞こえるほどの雷までの距離は遠くてもせいぜい10~15kmくらいだそうですが、雷雲外へも放電があるような大きな雷の場合などでは、雷雲から30km以上離れていても雷鳴が聞こえることがあるといいます。
雷は、栃木県や群馬県、埼玉県、茨城県といった北関東で多く、これらの地方は「雷の銀座通り」等と呼ばれるほどです。ただこれらの地方の雷は夏に多く発生します。これに対して、北陸地方や新潟県、山形県庄内地方、秋田県などの日本海沿岸では、冬季に目立って多く発生します。
こうした「冬季雷」は、これらの地方では「雪起こし」、「ブリ起こし」、「雪雷」などと愛称で呼ばれることも多いそうで、「雪起こし」が観測されたときが冬の始まりであると言い習わされています。
夏期の雷が積乱雲から地面に向かって放電するのに対し、この冬季雷は、地面から積乱雲に向かって、上向きに放電されます。北関東地方の夏季の雷よりも少ないとはいえ、数百倍のエネルギーを持つものが確認されているほか、一日中発雷することも多く、雪やあられを伴うこともあり、危険なものです。
また、はっきりとした落雷が無くても瞬間的な停電などの被害が出ることもあるそうです。ただし、海岸線から35km以上の内陸部では少ないようです。
幸い、ここ伊豆を含めた太平洋岸ではあまり雷は多くないようです。我が家でも昨年来から一年過ごした中でも雷を見たり聞いたりしたのは数回ぐらいだったと思います。
が、いざ一度落雷が起こると先の清涼殿での出来事のように大参事になりかねません。この落雷のメカニズムや予測についてもこのあと引き続き書こうかと思いましたが、今日はもうすでにかなりの分量を書いてきたので、もうやめにしたいと思います。
ちなみに俳句においては「春雷」は春の季語、「雷」「遠雷」「軽雷」は夏の季語、だそうです。「稲妻」は秋の季語なのだそうで、これは、秋に稲を刈る関係からでしょうか。冬の季語は「寒雷」ということです。
今日の雨はこれから遠雷や軽雷をもたらすほどひどいものにはならないようです。が、九州や近畿地方ではかなりの降雨になるようで、雨だけでなく雷の発生も考えられます。十分に注意してほしいものです。
みなさんの地方でも雷が発生しないとも限りません。もし発生したら、前述の計算式で距離を計算して対策をとってみてください。たとえ落ちなくても、より雷を身近なものとして感じることができるでしょうから。