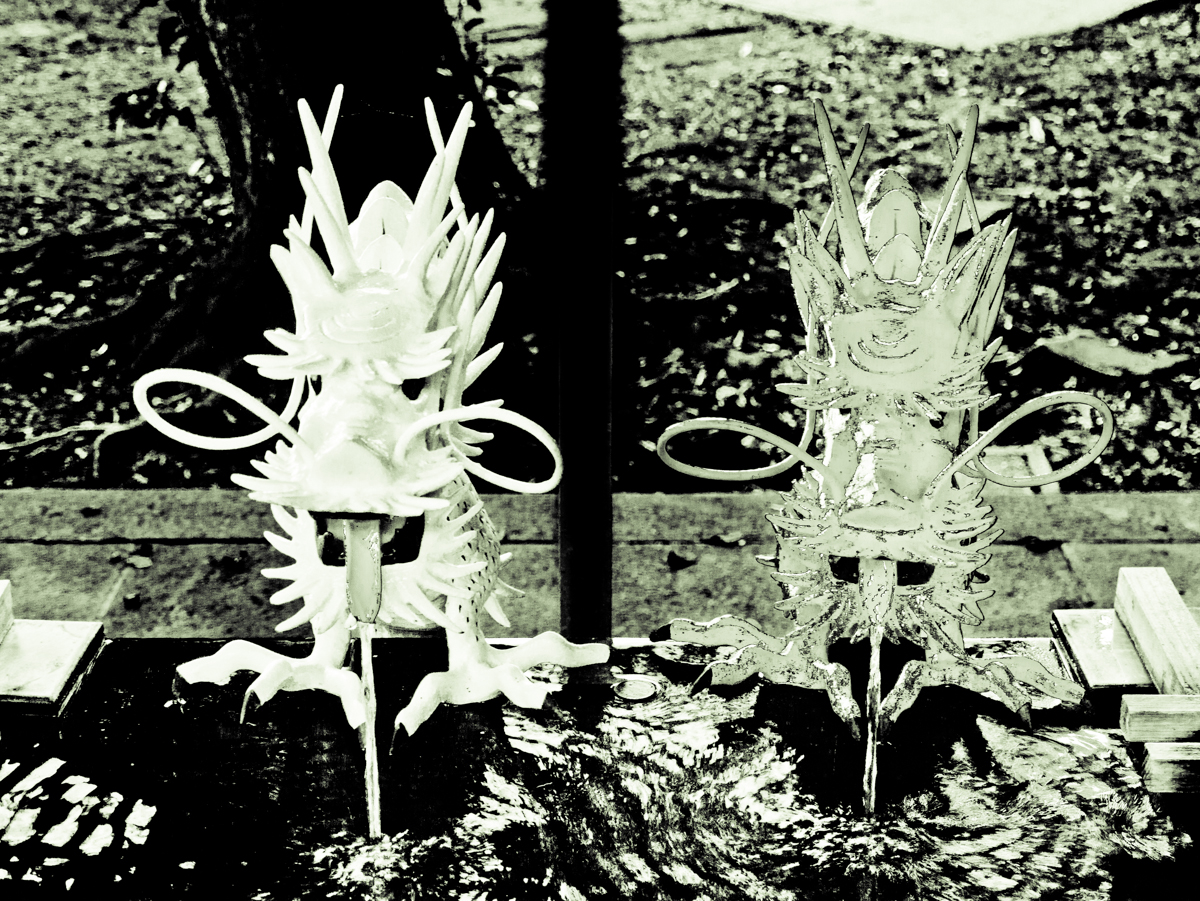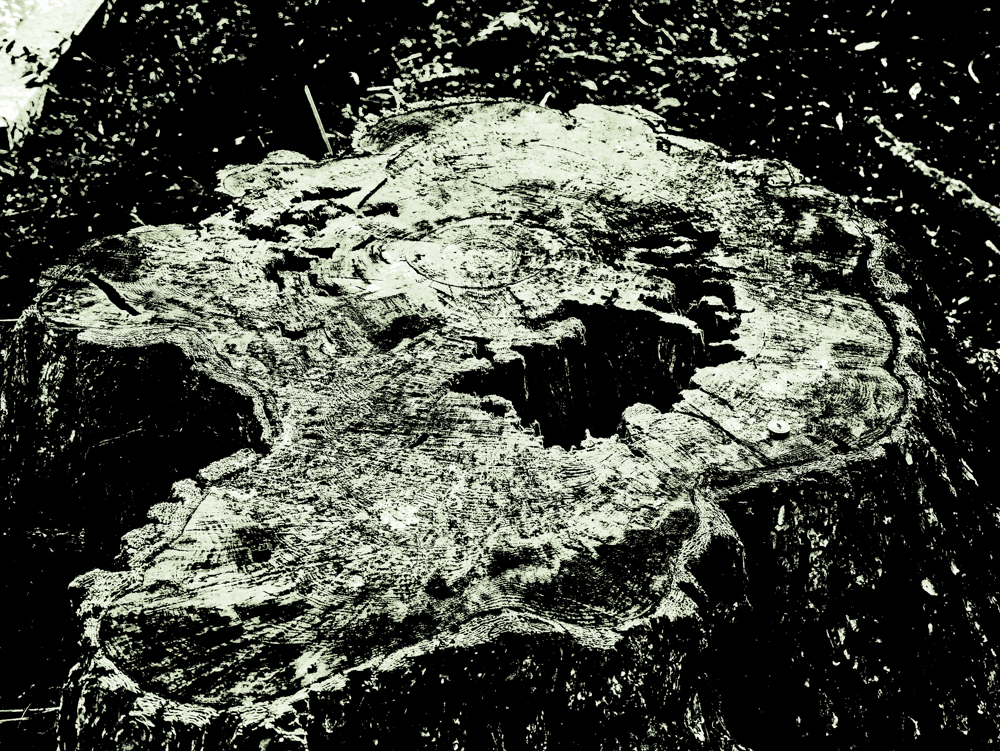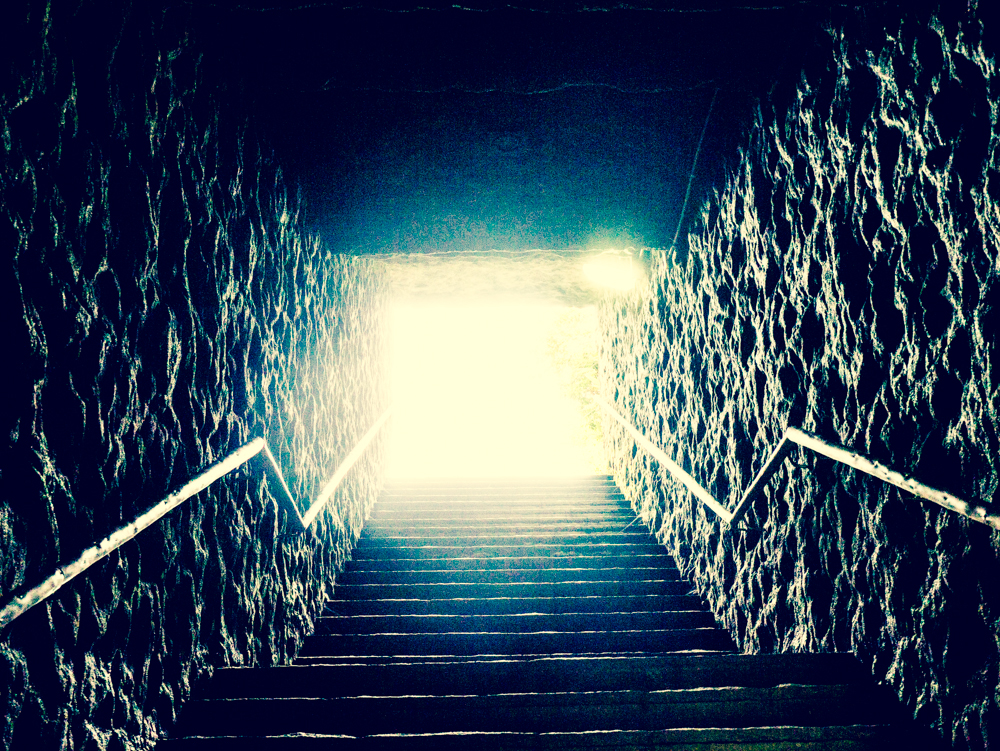 昨今のニュースネタでのトップは、やはりSTAP細胞なるものの真偽を巡っての一若手研究者と理化学研究所との攻防劇でしょう。
昨今のニュースネタでのトップは、やはりSTAP細胞なるものの真偽を巡っての一若手研究者と理化学研究所との攻防劇でしょう。
イギリスの科学雑誌、ネイチャーに投稿されたこの研究者の論文には、たくさんの共同研究者の名前が掲載されていたようですが、その中にはこの女性研究者の恩師の名前もあり、理化学研究所のナンバー2でもあるこの人の記者会見も数日前にあったばかりです。
私もかつて、アメリカの学会などに恩師とともに論文を提出したりしていたことがあるのでなんとなくわかるのですが、こういう論文を出すときにはこうした先輩研究者は、弟子である主執筆者が書いたその論文の中身について、それほど細かい部分まではチェックしません。
その理由は、そうした先輩研究者が後輩に名前を貸す、といったら過言かもしれませんが、自分が育てた研究者に敬意を払ってのことでもあり、自分がその論文に名を連ねるというのは、ある程度はその研究者を認めた、ということを表明する意味もあるためでしょう。
手塩をかけて育てた弟子が、世に出ていくときに、その手助けをしてやろう、という親心のようなもので、そういう面もあってやはりチェックは甘くなりがちです。
だからといって弟子のほうにも甘えがあってもいいということにはならず、認めてもらった以上は、御師の業績を汚さないように一生懸命良いものを出すべきなのでしょうが、この女性研究者にはそうした配慮がどこか足りなかったのではないか、と思えます。
こうした師弟関係において共同研究をする場合には、阿吽とまではいかずとも、それなりに「空気を読む」ということが大事なわけですが、しかしその空気についても明文化されるはずもなく、お互いが「なんとなく」察している、といった雰囲気の中で分かり合っているものであることが多いように思います。
なので、いってみれば不文律のローカルルールのようなものが、くだんの研究所内の研究者たちの間にもあって、そうしたあいまいさが今回の事件の根幹にあり、それが問題を難しくしているような気がしてなりません。
こうしたローカルルールというのは、一般家庭の中にもあって、例えば家族間の会話ひとつにしても、他の家庭では決して使われないような言葉を知らず知らずのうちに使っていたりします。
例えば、ウチの嫁のタエさんがよく「パイする」と口にするのですが、これはどうやら、「捨ててしまう」という意味のようで、彼女が育った家庭では、彼女のお母さんが普通にこれを使っていたとのことで、私と結婚して一緒に暮らすようになっても、彼女にとっては自然に口から出るようです。
無論、広島弁にはないことばで、他県にもない非常に限定的な言葉なのですが、長い間使っているうちには、自分でも標準語だと思い込むようになっていくものなのでしょう。
このほか、私が育った家では、「じらを言う」というのがあり、これは駄々をこねる、というほどの意味なのですが、同じ広島育ちのタエさんにこれを言ったところ、さっぱり通じず、何それ?と言われてしまいました。
エッ!?これって広島弁じゃないの? とそこで初めて気がついたわけですが、私は彼女と結婚するまで50年以上もの間、これを多くの広島の人がごく普通に使う言葉だと思っていました。
ところが、これは山口にしかない言葉のようで、山口で生まれ育った母親がやはり自分の家庭で普通に使っていたものを私が聞き覚えたもののようです。考えてみれば、こうした言葉は学校で友達同士使うことはほとんどなく、家に帰ったあと、何等かのわがままを言ったりやったりしたときぐらいしか、母親が口にしなかったことなどを思い出しました。
ローカルな家庭でしか使われない言語が、そこに暮らす住人にとっては標準語になっていく、という典型であり、こうした例はタエさんや私の家庭ばかりではなく、ほかの家でもよくあることではないか、と思います。
すなわちこれは、いわゆる「方言」というヤツであり、ある一定の地域でのみ通用する口頭言語のことです。
文字言語がほぼ共通している地域内で、文法は同じであっても単語や発音・アクセント・イントネーションが異なる地方の言語をさし、地域人口の集中程度により同一方言が形成されます。
しかし、この地域に隣接地域から人の出入りが多く、異なる地域の言語が交錯し始めると、次第にその他地域も含んで、その方言全体が変容していくとともに、その方言を話す地域も拡大していきます。
ただし、その地域間が山や川といった自然条件、あるいはある規律によって定められた境界などによって分断されると、それぞれ離れた地域間ではほとんど会話が通じないことになってしまいます。
それにしても、そもそもいつから「方言」と言うようになったか、について調べてみたところ、日本においては、820年頃成立の「東大寺諷誦文稿」に既にこの方言という言葉が出てくるようです。
「此当国方言、毛人方言、飛騨方言、東国方言」といった記述があるそうで、これが国内文献で初めて用いられた「方言」だということです。そんなに古い時代から、既に方言という概念が存在していたことになり、古代日本においても地方毎に違う言葉が話されていたことが想像されます。
しかし、言語は変化しやすいものなので、地域ごと、話者の集団ごとに必然的に多様化していく傾向があり、日本においても発音や語彙、文法に至るまで微妙な相違が生じるようになりました。とはいえ、その違いが全く別の言語と認められるほどには異ならず、同じ言語の変種と認められる程度のものが方言と呼ばれます。
ただし、同一国家内にあっても、社会階層や民族の違いなどによって、同じ言語といえどもでもまったく異なる話し言葉になり、ひいてはそれぞれの言語がひとつの国を形成することもあるようです。
例えば、旧ユーゴスラビアのセルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ地方などでは、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語といった言語が話されてきましたが、これらの言語は、異なる民族が使ってきた言語です。
それぞれ、表記体系・文法・規範的な語彙に違いがあってもお互いに非常に近く、第二次対戦後の旧ユーゴスラビアにおいては「セルボクロアチア語」という1つの言語だとされていました。
しかしユーゴスラビア紛争を経て国家が分裂した現在、それぞれの国家・民族でセルボクロアチア語はセルビア語・クロアチア語・ボスニア語という相異なった3つの言語であると再び主張されるようになっています。こうなると、もう「方言」というよりもむしろ、違う「言語」、というべきなのでしょう。
しかしそれでは、方言と言語は、何が違うのでしょうか。何を基準にして方言といい、どこからが言語になるのかについては非常にあいまいな気がします。
一般には、方言同士が時を経てそれぞれ異なる方向に変化していくと、やがては意思の疎通ができなくなるほど別モノになっていき、そうした過程のある段階で各々の方言は別言語だとみなされるようになっていくようです。
理論上は、同じ「語族」に属する言語でも、その方言がさらに変化して別言語に枝分かれたものはもう全く別の言語のようになってしまうことも多く、一般的な感覚ではしばしば「お互いに意思の疎通が可能」であることが方言か別言語かの基準とされるようです。
しかし、言語学的にみると、「同語族の共通言語」と、この同語族内で話される「共通言語の中の方言」を区別する明確な基準はないそうで、こうした学問の世界でも言語と方言の違いは曖昧で、ジャッジがしづらいもののようです。
中には、同じ語族とされている中においても、隣接する地域同士ではそれぞれ意思疎通ができるのに、数地域隔たると全く意思疎通ができなくなる、といった特殊ケースもあるそうです。
また、国境の有無や、友好国同士か敵対国同士かというような政治的・歴史的な条件や、そもそもそうした言葉を表記する文法や文字のようなものがあるのかないのか、文法や文字がないようなものを果たして言語と呼べるのかどうか、といった議論もあり、こと「言語」といった場合の例外はいくらでもありそうです。
このため、「世界にいくつの言語が存在するか」という質問に対しては、明確な答を出せる研究者はいないといわれています。
ただ、「言語」と「方言」に境界線を引くための指標としてしばしば引用されるのは、「言語とは、陸軍と海軍を持つ方言のことである」ということです。これは、自分たちが話す言葉がはたして「方言」であるか、それとも独立した「言語」であるかについては、その言葉を使う共同体が独立国家として軍隊を持つか否かで決まるという意味です。
独立国家であるならば、当然のことながら他国との争いがあった場合に、自国を守る軍隊を持っている必要があり、そうした政治的・軍事的な要因に支配されている国家が使っている言葉が言語である、というわけです。
しかし、上の旧ユーゴラビアの例のように、実際にはひとつの独立国家であっても、多民族で構成されている国では異なる言語が存在するのは当たり前であり、こうした、軍事的なものが言語を規定するのだ、という主張は必ずしも正当性を持つものではありません。
また軍隊を持っているある一つの国の言語が、ほかには存在しないか、といえばそんなことはなく、英語やスペイン語は、それぞれ独立した多数の別々の国々で話されています。
英語はイギリスで用いられるものとアメリカ合衆国のものとで細部が異なり、前者はBritish English、後者はAmerican Englishと呼ばれるほか、インド英語は、Inglish、シンガポール英語はSinglishといわれます。
しかし、英語は万国共通の公用語だとよく言われますが、同じ英語を話す別国人同士が会話するときに、まったくといっていいほど通じないことも多いようです。
例えばイギリス北部訛を持つイギリス人とアメリカ南部訛を持つアメリカ人の会話は成り立たず、ほとんど異星人と話しているような状態になってしまいます。が、それでも英語を共通語として意思疎通を図る国々は多いものです。
このほか、インドネシアを例にあげると、この国の言語はインドネシア語が標準語とされています。ところが、インドネシア語というのは、マレーシアの公用語であるマレー語の方言を基盤に整備されたものです。
このためインドネシア語、マレー語というと別の言葉のように思われているかもしれませんが、この両者の共通性は元々非常に高く、正書法(言語を文字で正しく記述する際のルールの)もほぼ同一で、この二国語での会話もある程度可能だといいます。しかし、一般的には両言語は別言語として扱われています。
また、インドの公用語であるヒンディー語とパキスタンの公用語であるウルドゥー語は、両国が同一のムガル帝国のころは同じ言語(ヒンドゥースターニー語)でしたが、インドとパキスタンの分裂により別の言語とされました。
その後はイスラム教徒の多いパキスタンがこれにペルシア語やアラビア語の単語や文字を取り入れるとともに、仏教徒の多いインドでは逆にヒンディー語からイスラムの影響を排し、サンスクリット語を代わりに取り入れ、インド化をおこなうなどしました。
こうして、インドとパキスタンそれぞれで話される言語は現在は全く違う言語になってしまいましたが、それでも現在でも、それぞれの言語を使いながらも両者の意思疎通はある程度可能だといいます。
国が違っていても、言葉が通じる例は、ドイツとオランダの間にもあります。ドイツ語は北部方言と、標準語とされる南部方言があり、これはお互いに通じないほど違うそうですが、どちらもドイツ語を構成する方言とされています。
他方、このドイツ語北部方言はオランダ語ときわめて近い関係にあります。しかし、オランダ側では、このドイツ北部方言をとくにオランダ語の方言とみなしていません。にもかかわらず、このドイツ語北部方言を話すドイツ人と、オランダ語の標準語を話すオランダ人との会話は普通に成立するそうです。
それぞれ別言語とされ、別国人なのに会話ができ、その一方でドイツ国内ではドイツ語北部方言を話す人とドイツ語南部方言を話す人とは会話が困難である、という我々からみるとさっぱり理解できない、奇妙なことになっています。
とはいえ、似たようなことは、中国と日本の間においても言え、日本人が使う漢字はもともと中国から入ってきたということは誰でも知っています。が、二国人間でそれぞれの母国語を使った会話はまったく通じません。
しかし、漢字を使った筆談ならばある程度の意思疎通はでき、漢詩の作り方などを学校でも教えていた明治時代には、日本人も文字を使えば、普通に中国人と会話ができたそうです。
一方、現在の中国国内の言語系体は、とくに発音においてヨーロッパ各国間の公用語ほどの違いがあるそうで、さらに表意文字である漢字にもかなりのバリエーションが存在するため、意思疎通が困難な場合も多いといいます。
ただ、同系の標準語が定められていて、これを共通語・補助語的に使うことで、意思疎通を図ることが可能です。
さて、我が日本国内を見てみると、やはり地方訛は存在します。とくに沖縄県や鹿児島県奄美群島の言語は、地理的、歴史的要因から本土の日本語とは差異が著しく、日本語というよりも「琉球語」として、日本語とは別言語とされることも多いようです。
しかし、口頭では互いに全く通じ合わないほどの違いがあるものの、独立言語として見た場合、日本語と系統が同じ唯一の言語と見なされるため、琉球語を話す人達は、日本と琉球を合わせて「日琉語族」と呼ばれています。
また、琉球語を日本語の一方言とする立場からは、これは「琉球方言」または「南島方言」と呼ばれていますが、逆に沖縄の人の中には、日本語は琉球方言と本土方言の2つに大きく分類できる、と言っている人もいるようです。
しかし、沖縄の人は普段使いではこの琉球語をしゃべる一方で、本土の人が来たときには、標準語(に近いことば)でしゃべってくれるため、中国のように意志疎通ができない、といったことはありません。
これは、一個の政府のもとに統一された日本では明治時代以降、中央集権国家を目指したため、沖縄においても学校教育や軍の中で標準語化が押し進められたためです。
1888年に設立された国語伝習所の趣旨には「国語は、国体を鞏固にするものなり、何となれば、国語は、邦語と共に存亡し、邦語と共に盛蓑するものなればなり」とまで書かれ、また富国強兵を進めようとした明治政府は、全国で軍部での標準語化の推進を強く推し進めました。
軍隊では、異なる地方の者同士が集まる場であり、戦場においてはこの方言の差異のために命令が取り違えられた場合には、死活問題にも発展する恐れがあったためで、このことから、方言を話すことを禁じる政策がとられました。
国会答弁などで、政治家がよく、国会答弁などで、「●●であります」と言ったりしますが、これはこの当時の軍隊の標準語化のなごりで、山口弁の丁寧表現の「~であります」からきています。
日本陸軍の創設者ともいわれる長州人の山縣有朋が導入したとものともいわれ、明治初期に軍隊用語の丁寧表現に導入された結果、やがては共通語としても使われるようになっていきました。
現在普通に使われる、~であります、は、どちらかといえば平坦なトーンですが、山口弁のありますは、ありますの「あ」の部分を強く発音されることもあり、このあたりが標準語とちょっと違います。
現在でも山口県のほぼ県全域で盛んに使われますが、県北部や西部の豊関方言、南部の宇部の方面ではあまり使われず、もっぱら山口市などの中央部のことばです。
明治期、山縣有朋に代表されるような長州閥の多くは陸軍や警察の創設に深く関わったため、軍や警察などでこうした格式ばった表現が取りいれられたようになった結果ですが、このほかの国家統制組織においても、方言は徹底的に弾圧されました。
このため、方言を話す者が劣等感を持たされたり、または差別されるようになり、それまで当たり前であった方言の使用がはばかられる事になっていきました。ただし、だからといって明治時代に、方言追放を徹底できたとは言い難く、軍・政府の重鎮であった、米内光政などは、終生南部訛りが抜けなかったそうです。
がこれは、米内は長州閥の多かった陸軍の所属ではなく、薩摩や旧幕府方の藩出身者の多い海軍の人であり、彼自身も幕末に新政府と敵対した盛岡藩の出身であり、陸軍のみならず海軍までこうした長州言葉が蔓延することをあまり良く思っていなかったためでしょう。
とまれ、こうした軍部での方言の矯正を主として言葉の統一が求められるようになると、東京方言を基に標準語を確立し普及させようとする動きが起りました。
同時に、方言を排除しようとする動きが強まり、標準語こそが正しい日本語であり、方言は矯正されなければならない「悪い言葉」「恥ずかしい言葉」とみなされるようになっていきました。
昭和40年代頃まで、方言撲滅を目的の一つとする標準語教育が各地の学校で行われ、なかには地域・家庭ぐるみで自発的に方言追放活動を推進するところもありました。
都会出身者の方言蔑視と地方出身者の方言コンプレックスが強固に形成され、方言にまつわるトラブルが殺人・傷害・自殺事件に発展することもあり、とりわけ集団就職などで国民の国内移動が活発化した高度経済成長期にはそういうことが多かったようです。
その後はさらに、テレビ・ラジオなどの普及もあって、こうしてほぼ全国的に標準語が浸透しました。
ただ、方言が全く無くなってしまったわけではなく、地方へ行けばやはりその地方の言葉が話され続けており、公的な場ではこれを標準語に戻す、といった形で標準語との共存が図られています。
現代の方言分布は、江戸時代の藩の領域に沿っているところが多く、特に津軽藩や仙台藩、薩摩藩など東北や九州は、東京や京都などの中央部から遠かったために、お国訛りがぬけきらず、この地方の人々の標準語はどうしても聞き取りづらいものになっているようです。
江戸時代の藩制では、藩の間の移動は制限され、藩が小さな国家のように機能していたため、どうしてもその国特有の訛が発生しました。江戸時代には方言を集めた書物も存在していたそうで、「物類称呼」(1775)という本などにも、東西方言の違いが記載されているそうです。
江戸時代の前半までは、江戸はまだ発展途上にあり、このため京阪神のほうがまだまだ賑やかで、京都方言が中央語の地位を占めていました。しかし、その後江戸の発展とともに江戸言葉の地位が次第に高まっていき、また江戸時代には上方の言葉が江戸に流入したため、江戸・東京方言は周辺の関東方言に比べてやや西日本的な方言になったといいます。
例えば、それまで江戸弁では「行くべ」と言っていたものが、「行こう」となったのもこのころで、やがて上方方言に対して江戸方言のほうがより優位な状態が固まっていき、明治時代になってからは、さらに東京方言を基に標準語を確立することになり、以後も標準語教育の過程で東京弁が標準語として定着していきました。
さらにテレビや映画などのマスメディアによる共通語の浸透、交通網の発達による都市圏の拡大、高等教育の一般化、全国的な核家族化や地域コミュニティの衰退による方言伝承の機会の減少などから、伝統的な方言は急速に失われるところとなり、各地の方言は衰退や変容を余儀なくされるようになりました。
各地のアクセントは多くの地域で保持されてはいるものの、特徴ある語彙などが世代を下るたびに失われていっており、このため、積極的に方言を守るための動きなどもあり、各地に方言の保存会が作られているほか、各種テレビ番組などでも地方の方言を持ち上げる演出が多くなってきているようです。
自分達の方言を見直そうという機運が各地で高まっており、例えば、その昔「おいでませ山口へ」というフレーズが全国的にも有名になったことがありました。
これ以降、方言を観光面で積極的な活用しようとする動きや、そもそも地元住民向けだったかなりローカルな商品やネーミングなどを、全国区に登場させるような風潮が生まれ、方言を用いた弁論大会、方言自体の商業利用の機会が増えました。
もとは地元ラジオ番組の一コーナーだった「今すぐ使える新潟弁」などは、CDとして全国発売されてヒットしたようで、このほか、東京出身のEAST END×YURIが出して1994年にヒットした「DA.YO.NE」に対して、大阪弁や北海道弁のほか、広島、博多、名古屋などの各方言バージョンが作られてヒットする、といったこともありました。
このほか、「大きな古時計」の秋田弁盤などもカバーされて発売されるなどのブームが続き、2000年代前半に入ってからは、とくに首都圏の若者の間で方言がブームとなり、方言を取り上げるバラエティー番組や仲間内で隠語的に使えるように方言を紹介する本が話題を集めています。
また近年、日常の口語に近い文面を多用する電子メールやチャットなどの出現によって、これまで書き言葉とされることの少なかった方言が、パソコンや携帯電話で頻繁に入力されるようになり、これに対応して、ワープロソフトの一太郎などで有名なジャストシステムは、各地方方言の日本語入力システムを発売しています。
このように、伝統的な方言の衰退は進んではいるものの、一概に標準語の中に埋没しているわけではなく、語彙については共通語化が著しいものの、文法やアクセントの特徴は若年層を中心に保たれているといった現状があります。
とくに、沖縄では、1980年代後半以降、標準語に対する独自性が、沖縄県のサブカルチャー愛好家の若者たちの間で見直され、戦後の沖縄県独自の習慣や風物ともども再発見されるようになった結果、「ウチナーヤマトグチ」と呼ばれる、新しい日本語の方言がよく使われるようになっています。
沖縄県民が「方言」として認識する土着の琉球語とは異なり、語彙・文法は、標準語とほとんど変わらず、このため、本土の人間がウチナーヤマトグチを聞いても理解は可能です。琉球語とは異なり、県外の人も俗に「沖縄弁」と呼ぶときは、この言葉を指すようです。
これは第二次世界大戦後、標準語(ヤマトグチ)を使ったメディアの普及や、学校における標準語普及運動により、旧来の話者は次第に高齢者に限られ、土地の方言が分からない、もしくは聞けても話せない若者が増えたためであり、普及した新方言は元の方言の影響を強く受けつつも、伝統的な方言と標準語のどちらでもない新しい方言に化していきました。
1990年代には、ウチナーヤマトグチを使った劇団、お笑い、音楽などが沖縄県で流行し、2000年代には、沖縄県の食文化、ライフスタイルなどへの興味を中心とした新しい「沖縄ブーム」や、NHK連続テレビ小説「ちゅらさん」のヒットなどもあって、この言葉のスローで優しい印象が全国で認識されるようになっています。
このように、沖縄で伝統的な方言でも共通語でもない言葉が流行するのと同調するかのように、「なまら」のように特定地域だけに広まる若者言葉も生まれており、これらは「新方言」と呼ばれています。これは、北海道の若い人の言葉で、たいそう、非常にという意味で、道内だけで使われている方言です。
このほかにも方言だと気付かれずに公的な場でも使われるようになっているものが増えており、これらの中から地方にとどまらず全国区として取り上げられ標準語になったものもあり、若い人を中心にこうした言葉を使う人が増えています。
例えば、「ごみステーション」というのはもともと、北海道や富山県東部において「ゴミ捨て場」の意味で呼ばれていたものです。これが、他地域ではカラスや猫などからの被害を防ぐために金網などで囲われたボックスケージをごみステーションというようになり、現在では全国的な用語になりました。
また、マクドナルドを指す、「マクド」は関西地方での略語として使われていたのが全国区になったもので、このほか、「モータープール」も主として大阪で駐車場を意味していた言葉が、全国でも使われるようになったものです。
ただ、全国区になりきらずに地方だけの新方言にとどまっているものも多く、「しれ/せれ」「食べれ」「やめれ」「掃除せれ」などは東北・越後・関東北部および九州北部にとどまっている例です。
地方によってはその新方言を、その地方の標準方言と信じ切っているケースも多いようで、熊本の若者が標準の熊本弁だと思っている「死にかぶる」というのは、難儀な目に遭うという意味の新方言です。
このほか、中国地方のテンパール(住宅用ブレーカ)、千葉県のパンザマスト(防災行政無線で児童の帰宅を促す放送)はそれぞれ商品名などから来ており、北海道のサビオ、富山県でのキズバン、熊本県および周辺地域でのリバテープ、佐賀県・長崎県などでのカットバンはいずれも「絆創膏」を表す新方言として使用されています。
笑ってしまうものも多く、福井県で、テレビ放送終了後のいわゆる「砂嵐」画面を表現する言葉は「じゃみじゃみ」というそうで、仙台弁でジャスといえばジャージーの意味で、これは甲州弁になるとジャッシーというそうです。
一方では、こうした新方言を使う側もこれを共通語ではないことを意識して使っている場合もあり、若年層では方言コンプレックスも薄れつつあってこうした新方言を頻繁に使うようになり、これらが逆に東京の言葉に影響を与え、いわゆる「若者言葉」にもなったものも多数あるようです。
改まった場面では使われることはなく、くだけた場面でしか使われませんが、こうした新方言の登場により、方言自体は失われるというよりもむしろ安定期に入った、と見る向きもあるようで、これからの日本語はこうした新方言や若者言葉によって席巻されていくのかもしれません。
ウチのタエさんがよく口にする「パイする」もやがては、この伊豆地方で流行り、全国区に登場するやもしれませんが、そのためにはこのブログを読む人が更に増えなくてはなりません。
今日このブログを読んだあなたも今日からゴミにすることを、パイする、と呼んでみていただく、というのはいかがなものでしょうか。