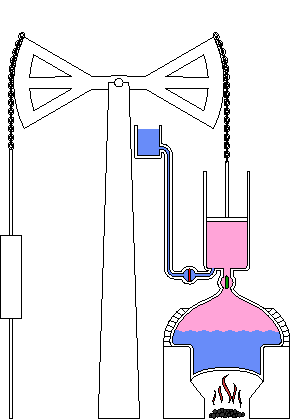先週の2月12日、大阪~札幌間で運営されている、JRの寝台特急列車、トワイライトエクスプレスの最終列車の切符が発売されました。
先週の2月12日、大阪~札幌間で運営されている、JRの寝台特急列車、トワイライトエクスプレスの最終列車の切符が発売されました。
しかし、午前10時の発売開始と同時にわずか数秒で上下とも完売したそうで、改めてこうした惜しまれつつも消えゆく昔ながらの鉄道車両に対しての根強い人気があることがわかります。
JR西日本は、昨年の5月にはすでに、この列車運転終了・廃止を予定していることをほのめかしており、いよいよそれが実現することになったわけですが、この廃止の理由としては、車両の老朽化などに加え、北海道新幹線開業時に青函トンネルの電圧が変更されることなどもあったようです。
この廃止とともに、並行在来線はJRから切り離され、第三セクター鉄道へ移管されることになっているそうで、その最終列車は3月12日運行される予定だといいます。約26年の歴史に幕を閉じることになり、多くの鉄道ファンに惜しまれての引退となるわけです
ただ、「トワイライトエクスプレス」の名称は、2017年春から営業運転を開始する豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」に受け継がれるといい、一昨年の10月に営業を開始して好評なJR九州の「ななつ星in九州」もそうですが、こうしたJRの在来線利用は今後はますます高級化の方向へシフトしていくのでしょう。
一方では、在来線といっても、こうした電気機関車で牽引される車両ではなく、レトロな蒸気機関車のような在来車両は、こうした高級化の波にはなかなか乗りにくいでしょう。昔ながらの古い蒸気機関車の運行は日本各地で行われていますが、商業利用のため再利用するとしてもあまりにも古すぎ、メインテナンスも大変なためです。
しかし、近年ではこうした古い蒸気機関車の産業遺産としての価値が見直されており、地元活性化のための観光資源としての活用が望めるため、そのニーズも高まっています。
こうした古い機関車などを昔と同様に現役で動かしながら保存することを「動態保存」といいますが、1976年(昭和51年)の大井川鉄道での保存運転より始まり、現在では全国でおよそ25台もの動態保存が行われているようです。
無論、常時運行は少なく、多くは休日や夏休みなどの人出が多い時に限っての限定運行のようです。とはいえ、実際に走らせることによって不具合もわかるわけであり、故障の原因となるパーツを交換することで、いつまでも現役を保って行こうとする試みでもあります。
ただ、最近はこうしたレトロな機関車の人気が出過ぎ、逆にこうした古いものが足りなくなるほどだといい、JR東日本などでは、日本各地の静態保存されている国鉄制式蒸気機関車の調査に2009年(平成21年)から乗り出しました。
これまでに3台のこうした蒸気機関車を復活させたといいますが、こうしたものが増えるということは逆に維持保守の手間が増え、さらに蒸気機関車を運転する事が可能な乗務員の更新育成など、課題も多くなってくるわけです。
さらには、燃料となる石炭も良質なものは枯渇状態にあってなかなか入手しずらいといい、このため大井川鉄道などでは、CO2排出抑制の観点からも含め、代替燃料による試験運転を実施するなど、燃料や環境に対する問題への取り組みも始まっているそうです。
古いものを維持していくというのはなかなか大変なことではあります。
この蒸気機関車というものですが、1802年に、イギリスのリチャード・トレビシックがマ高圧蒸機関を台車に載せたものを作ったものが世界初の蒸気機関車とされているようです。
その昔、私が小学生のころの社会科の教科書には、ジョージ・スチーブンソンが発明者と書いてありました。が、これは間違いであり、スチーブンソンが開発した蒸気機関車がかなり実用的であまりにも有名になったため、トレビシックの功績が忘れ去られていただけのことです。
スチーブンソンの蒸気機関車は、世界初の旅客鉄道ともされる実用機関車で、とくに最高時速46.6kmを誇った「ロケット号」は世界中で賞賛されました。
一方、歴史の陰に隠れたかのように忘れさられていたこのトレビシックという人は、鉱山技師の経験を活かし、最初に蒸気機関を用いた「蒸気自動車」の製作を始め、1801年には既に蒸気自動車を試作していました。
この年、人間が乗り込める蒸気自動車を公開し、これをパフィング・デヴィル号と名付け、同年のクリスマス・イヴに数名を乗り込ませて走らせることに成功しています。
その後も試験を続けましたが、3日後に道路にあった溝を通り過ぎた後で蒸気自動車が故障してしまいました。その原因はこの試作車の運転手が蒸気機関の火を消さずに自動車を放置したためでした。試験の途中、近くのパブで飲食している間にこの試験機の事を忘れ、このため内部の水が沸騰し、機関が過熱して壊れたのだといいます。
しかし、トレビシックはこれを重大な失敗とは考えず、運転手の過失によるものだと、サバサバとしていたといいます。こうした発明家には往々にして楽観的な人が多いものですが、この人もそうだったのでしょう。
こうしてトレビシックは、翌年の1802年には、自分で開発した高圧蒸気機関の特許を取得すべく、そのアイデアを証明するためで据置型機関を製作。仕事量を測定したところ、この蒸気機関は145psiという前例のないボイラー圧力を供し、毎分40回のピストン運動で動作したといいます。
これに気をよくした彼はさらに、この蒸気機関を載せた蒸気自動車を線路上を走行する「蒸気機関車」に改良しました。ただ、実際にこれを走らせて動かすことに成功したかどうかははっきりせず、ロンドンのサイエンス・ミュージアムにはその図面とトレビシックが友人に宛てた手紙が残っているだけだそうです。
この図面では、ボイラーから得られた動力を車輪に伝える装置などが石炭をくべる火室の扉の上にむき出しになっているなど、この車両の走行中に燃料をくべるのは非常に危険だったと見られ、記録には残っていないものの、実験は失敗に終わったのでは、という憶測もあるようです。
が、翌年の1803年には、こんどはよほど自信があったのか、「ロンドン蒸気車」と呼ばれるものをロンドンで公開しています。このことから、本来はこれが蒸気機関車の始祖とされるべきでしょうが、一応、その前年にも試作車があったと推定されることから、こちらが、人類史上初めて具現化された蒸気機関車とされるようになったようです。
このロンドン蒸気車は、ロンドンのホルボーンからパディントンまでを往復してみせ、報道関係などの注目を集めたといいます。が、しかし馬車に比べて乗り心地が悪く、燃料費が高くついたため、実用化はされませんでした。
その後、10年の年月が流れ、この間、トレビシックも含めて複数の技術者の手によって蒸気機関車が製作されました。が、どの機関車も実用的であるとは言い難い物でした。
しかし、1814年、上述のジョージ・スチーブンソンが石炭輸送のための蒸気機関車を設計。プロイセンの軍人の名をとって「ブリュヘ号」名付け、同年7月に初走行に成功しました。
時速6.4kmで坂を上り30トンの石炭を運ぶことができたといい、世界初の輪縁付きの車輪を採用しており、輪縁付き車輪と線路の接触部分の摩擦によって走行するという後年のスタンダードを完成させました。
産業界は、この「ブリュヘ号」を見て馬の代わり以上に活用できると称賛し、結局この蒸気機関車は16台も製作しされました。全16台のうち、存在が特定されたものの多くは、実際に炭鉱鉄道で使われていたそうです。
このように、蒸気機関車の登場は、1800年代初頭です。が、上でも述べたとおり、トレシビックがこれに先立ち「蒸気自動車」を完成させています。
しかし、これに用いられた高圧蒸気機関を考えたのは必ずしもトレビシックが最初というわけではなく、スコットランドの技術者・発明家、ウィリアム・マードックは既に1784年から同様の蒸気機関を開発し、蒸気自動車の試作を試みていました。
1794年にはトレビシックに請われてその実験を見せており、これは1797年から1798年にかけてマードックはトレビシックの近所に住んでいた、という縁があったためのようです。従って、トレシビックの人類史上初の蒸気自動車の発明、という称号はむしろこのマードックに与えられるべきかもしません。
ただ、実際にはこのマードックもまた、はじめて蒸気自動車を発明した人物とはみなされていません。蒸気自動車が発明されたのは1769年とされ、その発明者とされるのはフランスの軍事技術者、ニコラ=ジョゼフ・キュニョーです。
キュニョーは蒸気機関のピストンの直線運動を連続的な回転運動に変換する仕組みを世界で初めてつくり、これを用いて、前輪駆動の三輪自動車を製作しました。その動機はというと、このころフランス軍を統率していた宰相ショワズールの命により、野戦時の大砲牽引をおこなっている馬と荷車に代わるものを開発するよう依頼されたことでした。
5トンの大砲を牽引するための重量運搬具を大砲を後部に積載したい、というのがその依頼内容であり、このため、車としての機能はすべて前方に置かれる設計となり、直接前輪を駆動させるためボイラーを含む蒸気エンジン部のすべての重量が前部にかかる構造となりました。
このため、操舵時は前輪と共にエンジン全体が首を振る構造となりました。当然、舵取りが難しく、しかもこの試作車は全長7メートルを超える大型トラックでした。5トンの荷を積載し大人4人が時速9kmほどで走行できたそうですが、15分ごとにボイラーへ給水する必要があり実際の移動速度は時速3.5km程となりました。
しかし、一応稼働が確認されたことから、試作車として2年で2台が製作されており、この2台が世界最初の自動車と認定されています。
「キュニョーの砲車」と呼ばれ、その2号車は現存する最古の自動車として保管展示されており見学が可能で、これは1770年の試運転中に事故で壊れ翌1771年に補修されたものと伝えられています。
このように、蒸気自動車が発明されたのは、蒸気機関車や蒸気船よりも古いとされているわけですが、それではそもそも蒸気機関というものはいったいいつ発明されたのか、というところはどうしても気になってきます。
人類の歴史は火の扱いとともに始まったとされているわけで、その歴史はかなり古いのではないかと容易に想像できます。
案の定、文字として記録され残っているものとしては、紀元一世紀というかなり古い時代であり、古代アレクサンドリアの工学者・数学者であったヘロンが考案したさまざまな仕掛けの中に、「ヘロンの蒸気機関」と呼ばれるものが存在するようです。
ヘロンは、紀元10年~70年頃に生きていた人とされ、これは日本ではいつごろかといえば、実在していたかどうかも疑問視される垂仁天皇(すいにんてんのう)の時代であり、古墳時代です。
アレキサンドリアは、現在もカイロに次ぐエジプト第2の都市ですが、古代エジプト最後の王朝であるプトレマイオス朝の首都として発展し、一時は人口100万人を超えたともいわれ、そのため「世界の結び目」とも呼ばれた町です。
各地から詩人や学者たちが集まる学園都市でもあり、文学・歴史・地理学・数学・天文学・医学など世界中のあらゆる分野の書物を集め、70万冊の蔵書を誇りながらも歴史の闇に忽然と消えたアレクサンドリア図書館があったとされます。
ヘロンのほかにも「幾何学原論」で知られる数学者のエウクレイデスや、地球の大きさを正確にはかったアレクサンドリア図書館長エラトステネスのほか、かの有名な、アルキメデス、クラウディオス・プトレマイオスなどが活躍していました。
従って、蒸気機関があったとしても何ら不思議ではありません。記録に残っているものとしては、これこそが人類史上に蒸気機関が登場した最初のものであるとされています。
これは概念的には「蒸気タービン」に含まれるものです。ただ、ヘロンが創ったものは、蒸気で羽根車を回すというあまりにも原始的なものでした。記録に残っているものとしては、何のことはない、円筒の中に水を入れ、これを外部から加熱して、空けた穴から蒸気を噴出させ、その推力で円筒を回転させる、という簡単なものでした。
蒸気によって得られる圧力をまず往復運動に変換し、ついで回転運動の力学的エネルギーとして取り出す、といったより複雑な原動機、すなわち現代では「レシプロ式」と呼ばれるようなものでは無論ありません。
人類がこのレシプロ式にたどり着くにはさらに1600年以上もの月日が流れました。ただ、いきなりレシプロにたどり着いたわけではなく、まずは「真空エンジン」というものが考案されました。
フランス生まれでのちに宗教的理由からイギリスに亡命した物理学者であるドニ・パパンは、1695年に、蒸気を使った最初の「エンジン」を試作しました。それまでも蒸気圧はうまく利用すれば動力として使えそう、ということはわかっていましたが、多くの科学者は技術的な理由でその開発に頓挫していました。
パパンもまた、上述のような蒸気タービン式の発想しか当初持っていませんでしたが、試行錯誤の上発想を転換し、蒸気が液化することによって気圧が減少するという現象を利用することを思いつきます。
蒸気は気体であり大きな体積を持ちますが、これを冷やして液体にすることで小さな体積になります。このとき大きな圧力変化が生まれるわけですが、これを真空の容器内で行えば、大きな動力を得ることができる、と考えたわけです。が、しかしパパンはその実験には成功したものの実用化はなされず貧窮のうちに死亡したと伝えられています。
しかし、そのわずか3年後の1698年、イギリスの陸軍大尉で発明家のトーマス・セイヴァリが、ドニ・パパンと同様の原理の真空エンジンの開発に成功し、これを「鉱夫の友」と呼びました。
なんじゃそれは、と批判を浴びそうなネーミングですが、セイヴァリはこれをこのころ始まりかけていた産業革命における要ともいえる鉱山開発にこの装置が使えると踏んだのでしょう。
のちには、「セイヴァリ機関」と呼ばれるこのエンジンの試作品は、国王の前での実験にも成功し、これによりセイヴァリは特許を取得しました。ただ、このシステムは負圧によって直接に揚水するもので、ピストンやシリンダなどは持たず、レシプロエンジンからは程遠いものでした。
しかし、ヘロンの時代から1600年以上という気の遠くなるほどの年月を経て、人類はようやく「エンジン」というものを手に入れたわけであり、それを考えるとパパンやセイヴァリの功績は非常に大といえるでしょう。
なお、セイヴァリが取得した特許は「火力によって揚水する装置」という実に広範かつアバウトなものでした。このため、後続の技術者は何をやってもこの特許に抵触するということとなり、セイヴァリに対しての多額の特許料の支払いを余儀なくされたと伝えられています。
しかし、これから14年のちのセイヴァリの特許が切れたあとに、イギリスの発明家・企業家であるトーマス・ニューコメンは、1712年に、鉱山の排水用として同じ真空エンジンを使った蒸気機関の製作に成功しました。これが蒸気機関が実用化された第一号とされるもので、これはパパンやセイヴァリの蒸気機関をさらに発展させたものでした。
蒸気に冷水を吹き込んで冷やし、蒸気が水に戻るときに生じる負圧(真空減圧)でピストンを吸引する方式であり、この真空減圧方式エンジンは商用化されました。発明の動機としては、ニューコメンが住んでいた村の鉱山のわき水を汲み出す、自動の「つるべ井戸」を作りたかった、というものでした。
蒸気を造っては冷やす、といった工程を絶え間なく続ければ、常に地底から水をくみ上げることができる、というわけで、確かに実用的な装置でした。しかし、後年のレシプロエンジンのようにまだに往復運動を回転運動に変える、ということろにまでは至っておらず、また、運転速度は、毎分12サイクル程度であったといいます。
しかし、ニューコメンはこれで商売的に大成功し、折からの産業革命の波にも乗って、1733年に特許が切れるまで、あちこちの炭鉱などで100機以上のこの「ニューコメン機関」が製作され、主として鉱山底に貯まる水の排水などに使われました。
18世紀に入り、イギリスには石炭が豊富に存在したことから、これを燃やすことで良質な鋼鉄が造られるようになり、19世紀に入ってからは、さらに工業機械や鉄道のためにさらなる鉄が必要となっていきました。
イギリスで作られた工業機械は、海外へ輸出され、ドイツなどの工業化をも進めることになりましたが、このためには石炭はいくらあっても足らず、その量産は経済成長のために必須であり、その生産増のためには、炭坑に溜まる地下水の処理が非常に重要だったわけです。
ただ、こうしてうまく排水が行われるようになっても、せっかく掘り出した石炭のうち実に1/3程度がこの揚水ポンプのために消費され、計算上、全体としての熱効率はわずか1%にも達しなかったといい、非常に効率の悪いエンジンでした。
その後も多くの技術者がこの熱効率の改良に取り組みましたが、なかなか良いアイデアは生み出されず、その後30年余りが経ちました。
そこへ現れたのが、スコットランドの数学者・エンジニアであるジェームズ・ワットでした。彼は、1769年に新方式の蒸気機関を開発しましたが、これはニューコメンの蒸気機関の効率の悪さに目をつけて改良したもので、復水器で蒸気を冷やすという機構を取り入れており、これによりシリンダーが高温に保たれることとなり効率が増しました。
さらに負圧だけでなく正圧の利用、往復運動から回転運動への変換、ピストの速度を調整する調速機なども導入し、動作の安定などの改良をも行いました。これが、すなわち今日までエンジンの主流となっている「レシプロエンジン」です。
レシプロエンジンとは、英語ではreciprocating engineと書き、これは日本語では往復動機関あるいはピストンエンジンとも呼びます。
往復だけでなく回転運動をも産みだすエンジンですが、おおまかな動作としては往復運動が主であるためにこう呼ばれます。なお、レシプロエンジン=内燃機関だと思っている人もいるようですが、これは間違いです。
内燃機関、外燃機関というのは、後述するように、エンジンを回すための燃焼機関が駆動機関の中にあるかないか、だけの区別でこう呼ばれるだけであり、蒸気機関のように外部に燃焼器があるエンジンでも、これらを動力として回転運動を得るものはすべてレシプロエンジンです。
また、同様に現在のガソリンエンジンのように、シリンダーの中で燃料を燃やして回転運動を得るものも同様にレシプロエンジンです。
さて、こうして用途の広がったワットの蒸気機関は、水力に頼らない工場の立地や交通機関への応用など、産業革命・工業化社会の原動力になるとともに、燃料である石炭を時代の主役に押し上げていきました。
それまでの炭鉱では馬が動力として利用されていました。しかし、ウマの餌代があるときから高騰したため、炭鉱経営者が馬に代わる動力として安価に入手出来る石炭をなんとか有効利用できないかと考えており、ちょうどそこに登場したのがワットの発明でした。
このため、このワットの新蒸気機関は多くの炭鉱主から引っ張りだことなりました。ワットは科学者でしたが、商才もあった人で、こうした「据置型」の蒸気機関はまだまだ高価であったころから、これを「設備リース」的な手法で売り出すことで顧客に安価にエンジンを提供できるとアピールし、これがまたその普及を推し進めました。
それまで存在しなかった「馬力」という単位・尺度もワットの考案でした。個々のエンジンの性能価値を算定するため、標準的な荷役馬の力も参考に、一定時間の仕事率を指標として作り出された重要な概念であり、その後、蒸気機関に限らずさまざまな動力の尺度に広く用いられることになりました。
こうして、今日の前段で語ってきたような、蒸気自動車が生まれ、また蒸気機関車が生まれ、更には蒸気船が生まれて産業革命は世界中に広がっていったわけです。ちなみに、蒸気船の実用化は、1807年のアメリカ人発明家、ロバート・フルトンが、ハドソン川で運行した蒸気船がはじめてのものだといわれます。
が、彼はこれに先立つ4年前の1803年に既に、船長31m、船幅2.4mで左右舷側に3.5mの直径の外輪を備える蒸気船をフランスのセーヌ川で試走させて成功させており、この船は時速2.9マイルで流れをさかのぼる能力を示したといいますから、これが世界初といえるかもしれません。
その後、蒸気船もまた、外輪船からプロペラ船へと発展し、欧米のみならず、日本人もその技術を受けてその技術力を大いに発展させるに至っており、19世紀後半までは世界は蒸気機関によって成り立っていた、といっても過言ではないでしょう。
しかし、19世紀から20世紀にはいる頃からは、電気動力のほか、石油を使った「内燃機関」が発達をしはじめました。いわゆる「ガソリンエンジン」であり、正式には「内燃レシプロエンジン」と呼ばれるべきものです。上でも述べましたが、これは燃料を直接エンジン内部に注入し、ここで爆発炎上させて動力を得るため、「内燃機関」と呼ばれるわけです。
これに対して、蒸気機関は、ピストンやシリンダーなどのエンジンの中枢部は石炭などの燃焼させるボイラー、復水器などとは切り離されています。直線運動しか生み出せないものはそのままだと、上述の真空エンジンと同じですが、回転運動まで得られるものは「外燃レシプロエンジン」であるわけです。
内燃機関はこうした付帯設備をすべてひとつのパッケージの中にしまい込んだ形式であり、このためコンパクトにできるのが最大のメリットです。一方の、蒸気機関のような外燃機関では付帯設備が大きいため、対重量比での出力はどうしても低くなり、エネルギー効率が悪くなります。
しかも、起動・停止に手間がかかることなどが災いして、地位の低下を余儀なくされていった結果、とくに大型化にシビアな制限のある小型の移動機関、自動車については早期に内燃機関に移行し、蒸気自動車は姿を消していきました。
自動車ほど小型軽量化にシビアではない機関車は、20世紀中盤まで蒸気機関車が主役の座にあり続けましたが、それもその後減少を続け、冒頭でも述べたとおり、日本でも動態保存されているものが細々と残っているだけです。
ただ、蒸気機関の中でも最も原始的な蒸気タービンだけは今も生き残っています。大きさや起動・停止の手間などが問題にならない大型のシステムについては、それまでの蒸気式のレシプロエンジンからより原始的な蒸気タービンへの移行する、といったことが逆に行われており、とくにこれは「発電」の世界で顕著です。
蒸気タービンは、上でで述べたとおり、アレキサンドリアのヘロンの時代からある原始的な蒸気機関ですが、現代の蒸気タービンには、外部の熱源(ボイラー)により高温高圧となった蒸気がノズルから噴射されるというハイテクなものです。
この噴射蒸気は、圧力や温度が低下すると同時に速度がさらに増加しますが、これをさらに電子制御などで効率よく噴射させるようにし、この蒸気をタービンブレードに当てて軸を回転させ、発電機やポンプを駆動するものです。このタービンブレードそのものも空力学的、流体工学的な研究が進んでかなり効率の良い出力が得られるようになっています。
大規模な発電プラントではおもに蒸気タービンが用いられ、規模の小さいプラントや移動用施設ではディーゼルエンジンやガスタービンが使用されるという形で特性に応じた住み分けが生じており、さらに蒸気タービンの持つ外燃機関特有の熱源の多様性は、現在でも蒸気機関の最大のメリットとして有効です。
ご存知のとおり、原子力発電にも使われており、近年、家庭で捨てられる生ゴミやプラスチックゴミなどの廃棄物を利用した固形燃料である、RDF(ごみ固形燃料、Refuse Derived Fuel、RDF)などの開発が進み、こうした燃料を燃やして得られるエネルギーは蒸気タービンによって生み出されることが多いようです。
一方、船舶の分野でも、ほんの少し前までは(といっても19世紀のおわりころまでですが)、大型船舶用として、蒸気を使ったレシプロエンジンが結構使われていました。従来の蒸気レシプロエンジンは、石炭を使用でき、石油系資源に依存しないとう多様性があったためであり、内燃式のガソリンエンジンともある程度競合ができ、共存ができたためです。
さらに、20世紀に入ってからは旧来の蒸気タービンの改良・開発も進み、とくに民間の船舶に比べ高速・高出力を求められる軍艦においては、蒸気タービンの性能そのものが飛躍的に向上して効率がかなり良くなったことから、大型船舶では蒸気タービン、と言われた時代がありました。
が、その後、とくに戦後は内燃機関エンジンのほうも更に技術開発が進み、小型船舶から大型船舶までにも使われるようになっていきました。また石油ショックを契機に、ディーゼルエンジンの燃費効率が高くなったことから、民間船舶などではとくに蒸気タービンからディーゼルへの転換が進みました。
大型船舶用の蒸気タービンの能力もまた、この発達著しい内燃機関に劣るものではありませんでしたが、内燃機関を用いる船舶と統一性を図るために軽油しか用いられないことも多くなり、このため、本来いろいろな燃料が使える、という燃料面での多様性のメリットが失われるようになりました。
かつ軽油は蒸気タービン用としては揮発性の高さから爆発燃焼事故を招くなどの問題がありました。結果、次第に用いられなくなり、現在では蒸気タービンによる船舶は世界的にみてもかなりマイナーな存在となっています。
ただし原子力推進の軍艦や砕氷船においては、発電所と同じく蒸気タービンが唯一の選択肢として用いられています。その理由は複雑な仕組みを持つ蒸気レシプロよりも単純で故障も少なく安全であり、かつ出力が大きいことにほかなりません。
ただし、蒸気機関の原子力へ向けての利用については、日本に限って言えば先の東電事故をきっかけに非常に先細り傾向にあり、かつ、原子力船はひとつもない、ということはみなさんもご存知でしょう。
さて、今日の総括です。結論としては、大型の発電プラントやRDFのようなエネルギー利用の面においてのみ、蒸気機関は生き残っているというのが現状であり、これらのプラントも風力発電や太陽光発電などの自然エネルギー利用のプラントへとシフトして行っています。
全体的な印象としては既に蒸気機関の時代は終わりなのかな~、といった感じはやはり否めません。が、先達たちが残した産業遺産ということで、SLやその他多くの蒸気発電の遺物は残していってほしいと思います。
あるいは、遠い将来、月面開発や火星の開拓、といったことが実現するような時代には、こうしたレトロながらもシンプルで、大出力が得られる蒸気機関のようなものが大活躍する時代もくるかもしれません。が、それが実現するまで我々は生きていないでしょう。
以上、今日は蒸気機関という、非常にスタンダードな話題に挑んできたわけですが、私自身、意外に知らないことも多く、勉強になりました。みなさんはいかがだったでしょうか。