ヒガンバナが咲く季節になりました。
学名はリコリス・ラジアータといい、リコリスはギリシャ神話の女神・海の精の名、ラジアータは「放射状」という意味です。花が咲いたとき放射状に大きく広がっている様子は、クモの巣に見えなくもなく、英語では、レッドスパイダーリリーといいます。
秋の彼岸のころ、茎の先に強く反り返った鮮やかな花弁を広げるこの花は、葉は一切なく、花が終わって晩秋になってからようやく葉を伸ばし、年を越して他の植物が青々と茂る夏前にその葉が枯れるという、かなりの変わり者です。
彼岸花(ヒガンバナ)の名の由来は、秋の彼岸頃、突然に花茎を伸ばして鮮やかな紅色の花が開花することに由来しますが、これを食べた後は死(彼岸)が待っているからだともいいます。
たしかにこの花は毒を持っています。球根は鱗茎と呼ばれる鱗のような葉が重なり合ったもので、ここにアルカロイドという物質を含んでいて、口にすると流涎(よだれ)や吐き気、腹痛を伴う下痢を起こします。ひどい場合には中枢神経の麻痺を起こし、最悪の場合は死に至ることもあるそうです。
そのためか、葬式花、墓花、死人花(しびとばな)、地獄花、幽霊花、火事花、蛇花(へびのはな)、剃刀花(かみそりばな)、狐花(きつねばな)、捨て子花、灯籠花、天蓋花(仏像や住職が座っている上に翳される笠状の仏具)などなど、各地で不吉な名で呼ばれています。
一方、別名の曼珠沙華(マンジュシャゲ)は梵語(サンスクリット語)で「赤い花」「葉に先立って赤花を咲かせる」といった意味です。釈迦が法華経の悟りを得た際、これを祝して天から降ってきた花(四華)のひとつが曼珠沙華であり、天上の花です。
同じ花なのに片や死の世界の花を意味し、他方では天国に咲く花とされているという不思議な植物でもあります。
日本には有史以前に中国大陸から持ち込まれたようです。稲作が日本に伝えられたとき、土と共に球根が混入してきて広まったと考えられていますが、土に穴を掘る小動物(モグラ、ネズミ等)を避けるために有毒な球根をあえて持ち込み、畦や土手に植えたのだとする説もあります。
球根は有毒ではありますが、適切に用いれば薬になり、また水にさらしてアルカロイド毒を除けば救荒食(きゅうこうしょく)にもなります。これは、飢饉や災害、戦争に備えて備蓄、利用される代用食物のことで、栃(とち)や椎(しい)・楢(なら)などの木の実や蘇鉄(そてつ)の実などもそれです。
熊本城を作った加藤清正は籠城戦に耐えられるように、畳の芯や土壁の繋ぎに芋茎(里芋の茎)を埋め込んで救荒食としました。また壁にはかんぴょうを塗り込み、堀にはレンコンを植えていたといいます。
このほか、城内のあちこちにアカマツを植えさせました。アカマツの幹から剥ぎ取った樹皮は、コルク化した外樹皮を除いて軟らかくなるまで煮ると食べることができます。またこれを餅や米に混ぜ込むことで嵩増しができます。マンジュシャゲも同様に毒抜きをすれば、救荒食になります。
日本では北海道から南西諸島まで全国で見られます。土手、堤防、あぜ、道端、墓地、線路際など人手の入っているところに自生しますが、もともとは人の手によって植えられたものがほとんどです。害獣から作物を守るために田畑の縁に沿って植えられることも多く、それらが列をなす景観は秋の風物詩です。
山間部の森林内でも見られる場合がありますが、これはそうした場所がその昔人里であった可能性を示すものです。仏教に由来する花であることから、かつては墓地、あるいは寺院の周りに好んで植えられたようで、それらが荒廃した後も生き残っているものと想像されます。
ヒガンバナの名所として国内最大級のもののひとつに、埼玉県日高市にある巾着田があります。500万本のヒガンバナが咲き誇り、最盛期には最寄り駅である西武池袋線高麗駅に多数の臨時列車が停車し、彼岸花のヘッドマークをあしらった列車が運行されたりします。
また神奈川県伊勢原市にある日向薬師付近でも100万本のヒガンバナが咲きます。埼玉県秩父郡横瀬町にある寺坂棚田の畦にも100万本のヒガンバナが咲くそうです。
愛知県半田市の矢勝川の堤防にも多数のヒガンバナが咲きます。一説には200万本ともいわれ、その近くには童話「ごんぎつね」の作者、新美南吉を偲んで建てられた新美南吉記念館があります。
この地は南吉の出身地です。「ごんぎつね」は、それら旧知多郡半田町や岩滑(やなべ)地区の矢勝川、隣の阿久比町にある権現山を舞台に書かれたといわれています。「城」や「お殿様」、「お歯黒」という言葉が出てくることから、その設定は江戸時代から明治頃と考えられています。
「ごんぎつね」は筆者である南吉が幼いころに老翁から聞いた話という体裁をとっています。小学校の教本として使われており、どんな話か知っている人も多いでしょうが、一応紹介しておきます。
ひとりぼっちの小狐「ごん」は村へ出てきては悪戯ばかりして村人を困らせていました。ある日ごんは、村の兵十(ひょうじゅう)が川で魚を捕っているのを見つけ、いつものようにいたずら心から彼が捕った魚やウナギを逃がしてしまいます。
それから十日ほど後、兵十の母親の葬列を見たごんは、あのとき逃がしたウナギは、実は兵十が病気の母親のために用意していたものだったと悟り、後悔します。
母を失い、自分と同じようにひとりぼっちになった兵十に同情したごんは、ウナギを逃がした償いにと、イワシ売りの籠からイワシを盗んで兵十の家に投げ込みます。しかしその翌日、イワシ屋に泥棒と間違われて兵十が殴られていた事を知り、ごんは反省します。
ごんは自分の力だけで償いをすべきだと思い直し、その後自分で採ってきた栗やマツタケを兵十の家に届け始めます。しかし兵十はその意味が判らず、知り合いの加助の言葉を信じて神様のおかげだと思い込むようになります。それをこっそりと聞いていたごんは、割に合わないなと、ぼやきながらも届け物を続けます。
その翌日もごんは、栗を持って兵十の家に忍び込みます。兵十は物置でなわをなっていましたが、ふと目を上げると家に入っていく子狐を目にし、あのウナギを盗んだ狐だと気付きます。またいたずらに来たのかと納屋にあった火縄銃を取りに行き、火薬を込め、家の戸口から出ようとしていたごんを撃ってしまいます。
兵十が土間に倒れているごんに駆け寄ったとき、そばに栗が固めて置いてあったのが目に留まり、はじめてこれまでも栗や松茸を持ってきていたのがごんだったことを知ります。
「ごん、おまえだったのか。いつも、栗をくれたのは」と語りかける兵十に、ごんは目を閉じたままうなずきます。兵十は火縄銃をばたりと取り落とし、その筒口から青い煙が出ているところで物語は終わります。
出生地である半田を舞台に新美南吉がこの物語を執筆したのは、わずか17歳の時(1930(昭和5)年)でした。彼が幼少のころに祖父から聞かされた口伝を基に創作されたとされていますが、南吉は4歳で母を亡くしており、この名作が生まれたのはその経験が深く影響したといわれています。
本名は新美正八。雑誌「赤い鳥」出身の日本の児童文学作家と知られ、代表作であるごんぎつねも最初はこの雑誌に掲載されました。結核により29歳の若さで亡くなったため、作品数は多くありませんが、童話の他に童謡、詩、短歌、俳句や戯曲も残しています。
1913(大正2)年7月30日、畳屋を営む父・渡邊多蔵、母・りゑ(旧姓・新美)の次男として生まれました。前年に生まれ、すぐに死亡した兄「正八」の名をそのままつけられましたが、母は出産後から病気がちになり、29歳の若さで他界しました。父の多蔵は再婚相手を探しはじめ、のちに酒井志んという女性と再婚しました。
その後、南吉の母の実家、新美家ではりゑの弟・鎌次郎が亡くなり、跡継ぎがなくなってしまいます。そこで南吉が養子に出されることになりましたが、当時の法律では跡取りの長男を養子に出すことを禁じていました。
そこで多蔵は既に亡くなっていたりゑの父、六三郎の後見として自らの名前を新美家に入れ、自分の孫として南吉を養子に出すことにしました。六三郎には志もという老妻がおり、南吉は血のつながらないこの祖母の息子として新美家で暮らすようになりました。
しかし、寂しさに耐えられず、5か月足らずで渡邊家に戻った南吉は、今度は多蔵の再婚相手、志んと暮らすようになります。多蔵と志んの間には異母弟の益吉が生まれていましたが、志んは南吉を実子と同じように扱い、南吉も益吉をよくかわいがっていたといいます。
やがて南吉は半田第二尋常小学校(現・半田市立岩滑小学校)に入学します。おとなしく体は少し弱かったものの成績優秀で「知多郡長賞」「第一等賞」を授与されたこともありました。卒業式では卒業生代表として答辞を読みましたが、この答辞は教師の手を入れず、南吉一人で書き上げたものだったといいます。
小学校卒業後に入学した中学は、県立半田中学校(現・愛知県立半田高等学校)でした。ここのころから南吉は児童文学に取り組むようになり、校友会誌に「椋の實(むくどりのみ)の思出」「喧嘩に負けて」などの作品を出品しています。その後も様々な雑誌に作品を投稿し始めました。
半田中学校卒業直前、「赤い鳥童謡集(北原白秋編)」を読んで感銘を受けます。卒業後の希望は大学に行き、児童文学者の大西巨口(きょこう・主に名古屋で活躍した)や菊池寛のように新聞記者で生計を立てることでした。その中で作品を書き、いずれは記者を辞めて文筆業だけで食べていこうと考えていました。
進学先は早稲田大学に進学を考えていましたが、息子を進学させるつもりのない父の多蔵に反対されました。経済的な理由からだったと思われます。仕方なく岡崎の師範学校を受験しますが、結果は不合格。体格検査で基準に達していなかったためといわれています。
そこで、小学校時代の恩師の伊藤仲治をたずねたところ、母校の半田第二尋常小学校を紹介され、代用教員として採用されることになりました。
またちょうどこのころ、「赤い鳥」5月号に南吉の童謡「窓」が採用され、掲載されます。主催者の北原白秋を尊敬する南吉は喜び、教員生活の傍ら創作、投稿を続けるようになりました。その結果、さらに8月号には童話「正坊とクロ」が赤い鳥に掲載されました。
その後代用教員を退職。上京して東京高等師範学校を受験しますが今度も不合格。しかし創作意欲は衰えず、童謡同人誌「チチノキ」に入会。ここで白秋の愛弟子の巽聖歌(たつみせいか)や与田凖一と知り合いました。巽は童謡「たきび」の作詞者として知られる童話作家で、依田は昭和期の日本の児童文学界において指導的役割を担った人物です。
巽と仲良くなった南吉は、このころ彼の紹介で北原白秋の家を訪ねています。白秋との対面を果たし感激した南吉ですが、さらに巽から卒業生の半数が教職に就いているという東京外国語学校の受験を勧められます。教師になれるなら夢だった新聞記者にもなれるだろうと受験を決めます。
こうして1932(昭和5)年3月、東京外国語学校英語部文科を受験した南吉は、志願者113人中合格者11人という狭き門をくぐりぬけ見事合格を果たしました。寮のある中野区上高田には巽の他、与田凖一、藪田義雄(白秋の伝記などを書いた)も転居し、南吉は友人に囲まれて充実した学生生活を送るようになります。
入学前には「赤い鳥」に「ごんぎつね」が掲載されるという喜び事もありました。このころから南吉は白秋指導のもと童話を創作するようになり、巽と依田も新美南吉を世に送り出すことに尽力しました。「赤い鳥」にはそうした後押しを受けた南吉の作品の数々が掲載されるようになっていきます。
1934(昭和7)年、南吉は第一回宮沢賢治友の会に出席しました。賢治はその前年に亡くなっていましたが、彼は早くから賢治の作品を読み高く評価していました。この会は賢治没後に開かれた作品鑑賞会です。
ところが、それに出席の直後、南吉は喀血します。結核でした。すぐに実家に帰り1か月あまり療養したところ小康を得、4月に学校に戻りました。その後も比較的症状は軽かったことから学業は続け、1936(昭和9)年3月、東京外国語学校を卒業します。
東京で就職活動を始めた南吉ですが、この年は不景気だったこともあり、外大で教員免許を取らなかったことも災いして就職は困難を極めました。いろいろ探し回った結果、東京土産品協会という小さな会社に採用が決まり、英文カタログを作成する仕事を任されます。しかし激務の上月給は40円と安いものでした。
さらに、このころ病が進行し、二度目の喀血で倒れ1か月寝たきりの生活になります。幸いなことにすぐに近くには巽が住んでおり、夫妻の献身的な看病で多少元気になりました。しかし仕事はあきらめ、帰郷して療養に専念することにしました。
ただ、実家も裕福ではなく療養中でもあって金はどんどん出ていきます。家計のためにと半田にもほど近い知多半島の南部にあった河和第一尋常高等小学校に務めますが、代用教員であったためにすぐに職を失います。
しかしその直後新しい職をみつけました。杉治商会という飼料生産会社で、その生産高は全国の45%を占めて第一位で、全国に支店、工業を持つ大企業でした。
入社後、そこの鴉根山畜禽研究所というところに配属された南吉は、寄宿舎に住み込み、鶏の雛を世話をする仕事でを与えられました。ところが、この会社は大会社にもかかわらずその研究所の職場環境は劣悪で、20円という薄給の上、休みは月2回しかとれませんでした。結核を囲い体調も悪かった南吉はわずか4カ月でここを辞めています。
その後、半田中の恩師で安城高等女学校の校長になっていた佐治克己の働きかけで安城高等女学校への採用が決まります。1年生の学級担任となり英語や国語、農業を教えるほか図書係や農芸・園芸部長も務めました。給料は70円と厚遇でしたが、安城は半田の隣町でありながら通勤に1時間半もかかるため、翌年町内に下宿を見つけて移り住みました。
このころは体調もよく、3年生の修学旅行の引率として関西へ行ったり、同僚と富士登山を果たしたり、熱海や大島へも行くなど充実した年でした。ところが翌年、交際していた幼馴染の中山ちゑが青森県の知人宅で体調を崩して急死。その葬儀で南吉は男泣きに泣き、その後1か月は腑抜けのような状態だったといいます。
一方この年は彼の作品が次々雑誌に載りました。翌年はじめからは良寛の伝記を書き始め、10月に「良寛物語 手毬と鉢の子」が出版されます。これはヒットし、2万部も出版された結果、南吉は1300円もの印税を受け取りました。現在では3~400万円ほどの大金です。
このころ、女学校の教え子の兄の依頼で早稲田大学新聞に「童話に於ける物語性の喪失」を寄稿しています。これは長年童話を綴ってきた南吉の児童文学論の集大成ともいえるような内容でしたが、その執筆後から体調が悪化。さらには腎臓病を患って10日あまりも学校を欠勤することになりました。
その後も体調不良が続いたため、11月中旬には岩滑の実家に戻りますが、翌月には血尿が出て、このときついに南吉は死を覚悟しました。翌年1月、病院で診察を受け腎臓炎と診断された南吉は日記にそのころの死を見つめた思いを綴っています。
しかしあいかわらず創作意欲は活発で、3月末から5月末までの2か月の間に代表作の「ごんごろ鐘」「おぢいさんのランプ」「花の木村と盗人たち」「手袋を買いに」など、のちに代表作とされる童話を次々書き上げていきます。そしてこの年の10月はじめての童話集「おぢいさんのランプ」を刊行。
南吉はこの本で得られた印税で女学校職員全員に鶏飯をふるまい、職員室にラジオを寄付したりしました。しかしこのころから体調はさらに悪化し、喉が痛み声も出にくくなります。この年の11月、敬愛していた北原白秋が死去。明けた1943年の初めからは女学校を休むようになり、長期欠勤した結果、2月に安城女学校を退職しました。
退職後は咽頭結核のためほとんど寝たきりになります。既に死を覚悟していた南吉は、巽聖歌に原稿と病状を手紙にして送るとともに、このころ遺言状も書いています。南吉の病気を知らなかった巽は手紙の内容に驚いて岩滑を訪れ、離れで寝ている南吉と対面。南吉に頼まれて原稿の整理などをしています。
3月20日、恩師伊藤仲治の妻が見舞いにきましたが、南吉はほとんど声が出ない様子で、「私は池に向かって小石を投げた。水の波紋が大きく広がったのを見てから死にたかったのに、それを見届けずに死ぬのがとても残念だ」と語りました。3月22日午前8時15分、死去。29歳8か月の生涯でした。
新美南吉
生涯独身の南吉でしたが、その生涯に4人の女性との交際経験がありました。ただ、いずれも実を結ばずに終わっています。
そのうちの一人である木本咸子(みなこ)は、新美南吉の初恋相手です。18歳の頃、半田第二尋常小学校に代用教員として勤務中に交際を始めましたが、4年後に別れています。また2度目の恋人、山田梅子は24歳の頃、河和第一尋常高等小学校に代用教員として勤務中に交際を始めた相手ですが、ここを退職後疎遠になり、こちらとも翌年別れています。
上でもふれた中山ちゑは南吉の幼馴染です。子どもの頃から親しく遊んでいた彼女とは26歳の頃に再開して愛を深めあうようになり、結婚まで考えていましたが、翌年に急死したためその望みは叶いませんでした。その反動なのか、ちゑの死後の翌年、教え子の岩月みやという女性に結婚を申し込んでいますが、齢が離れすぎているという理由で断られています。
新美南吉は、地方で教師を務め若くして亡くなった童話作家という共通点から宮沢賢治とよく比較されます。
宮沢賢治は独特の宗教観・宇宙観を持ち、擬人化した動物なども登場させてシニカルで幻想的な物語を展開するのに対し、南吉の作品の主題はあくまでも人間であり、人の視線の先にある素朴でほのぼのとしたエピソードをさらに味わい深く脚色したり膨らませるといった作風で、「北の賢治、南の南吉」と呼ばれて好対照をなしています。
作品の多くは、故郷の岩滑新田(やなべしんでん)を舞台にしたものが多く、このため新美南吉は現在、半田市の名誉市民にもなっています。出身地の半田には、新美南吉記念館のほか、彼の実家や作品ゆかりの場所を巡るウォーキングコースも作られています。
新美南吉をはじめ多くの童話作家の登竜門となった「赤い鳥」は、1918(大正7)年7月1日創刊で1936(昭和11)年8月に廃刊になるまでに196冊が刊行されました。
創設者の鈴木 三重吉曰く、「低級で愚かな政府」が主導する唱歌や説話に対し、子供の純性を育むための話や歌を世に広めるための一大運動と宣言、発刊された「赤い鳥」への反響は大きく、それに賛同した支持者や投稿者によってこの文化運動はやがて「赤い鳥運動」とも呼ばれるようになっていきます。
創刊号には芥川龍之介、有島武郎、泉鏡花、北原白秋、高浜虚子、徳田秋声といったこの時代を代表する文人らの筆が寄せられるとともに、表紙絵は黒田清輝、藤島武二に師事した洋画家、清水良雄が描きました。
その後も菊池寛、西條八十、谷崎潤一郎、三木露風といった一流作家が作品を寄稿し、中でも新美南吉が憧れた北原白秋は「赤い鳥」において自作の童謡の発表を行いながら、寄せられる投稿作品の選者の役も担うなどの重要な役割を果たました。
創設者の鈴木三重吉という人は、広島県広島市出身の小説家で、広島県広島尋常中学校を出ており、これは現在の県立広島国泰寺高等学校で、私の母校です。
1882(明治15)年9月29日、広島市猿楽町(現エディオン本店がある地)に、父悦二、母ふさの三男として生まれましたが、母は三重吉が9歳の時に亡くなっています。三重吉が15歳の時「少年倶楽部」に投稿した「亡母を慕ふ」にその母のことが書かれています。
1901(明治34)年、京都の第三高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文学科に入学。ここで夏目漱石の講義を受けるようになります。ところが神経衰弱を煩い、静養のため大学を休学して広島に過ごしているときに完成させたのが「千鳥」という作品でした。
師である夏目漱石にその原稿を送ったところ賞賛され、漱石の友人であった正岡子規の弟子、高浜虚子にもそれが送られ、雑誌「ホトトギス」5月号に掲載されました。以降、大学に復学して漱石門下の一員としてその中心的な活動を行うようになります。
1908(明治41)年、東京帝国大学文学科を卒業。成田中学校の教頭として赴任して英語を教えるようになりますが、3年後に退職して上京、新宿の海城中学校の講師となりました。これは海軍兵学校へのエリート人材供給のための予備校として創立された学校で、古い歴史を持つ伝統校として現在でも都下有数の有名校とされています。
同年5月、三高時代に知り合ったふぢと結婚。2年後の1913(大正)2年からは掛け持ちで中央大学の講師となります。翌年より、「三重吉全作集(全13巻まで刊行)」の刊行を始めるなど数々の作品を執筆して小説家としての評価を上げましたが、片や自身の小説家としての行き詰まりを自覚し、中央公論へ「八の馬鹿」を発表以降、小説の筆を折りました。
1916(大正)5年、三重吉34歳のころ、三重吉宅には河上房太郎という青年が事務の手伝いに来るようになっていましたが、その縁で妹の河上らくも手伝いに来るようになり、このらくとの間に、長女すずが生まれました。三重吉には既に妻がいましたから、らくとのことはつまり「お手付き」ということになります。
こうして生まれた娘のために童話集「湖水の女」を創作したことをきっかけに、三重吉は児童文学作品を手掛けるようになりますが、その矢先に妻ふぢが亡くなります。ふぢは第三高校時代に付き合っていた京都の青物屋の娘でしたが、その結婚はわずか4年でした。
翌年から「世界童話集」の刊行を開始。このとき清水良雄が装丁・挿絵を担当し、児童文芸誌「赤い鳥」へ続く親交が始まります。続いて「赤い鳥」を創刊。海城中学は辞職、中央大学を休職して本格的に児童文学誌「赤い鳥」に力を入れ始めました。
「赤い鳥」では文壇の著名作家に執筆を依頼。芥川龍之介の「蜘蛛の糸」や有島武郎の「一房の葡萄」といった名作が生まれるとともに、北原白秋らの童謡、小山内薫、久保田万太郎らの児童劇など大正児童文学の名作の数々が本誌から誕生しました。当時、軍拡化で教訓色が強まっていた児童読み物は、こうして質の高い文芸としてその地位を高めていきました。
39歳の時、三重吉は小泉はま(濱)と再婚。その後もますます児童の情操教育の手本としての赤い鳥の内容の充実に努めますが、その延長で46歳の時には「騎道少年団」を設立しています。これは乗馬による少年の精神教育を主旨とする団体です。
さらに53歳の時、「綴方読本」を刊行。こちらは赤い鳥の「綴方投稿欄」の中で、選と選評というかたちで子供たちに行っていた文章作法の指導を集大成したものでした。
しかし、それが刊行される直前から喘息のため病床に臥すようになり1936(昭和11)年末には病状が悪化。東京帝国大学附属病院真鍋内科へ入院しますが、同年6月27日・午前6時30分、肺がんのため死去。53歳でした。
鈴木三重吉
三重吉の死去と共に、「赤い鳥」は同年8月号で終刊しましたが、同年10月、「赤い鳥 鈴木三重吉追悼号」が刊行されています。「赤い鳥」は18年間もの間刊行を続け、最盛期には発行部数3万部を超えたと言われます。学校や地方の村の青年会などで買われたものが回し読みされたものも多く、現在ならもっと売れていたでしょう。大ベストセラーです。
この間、排出された童話作家は、新美南吉以外にも巽聖歌や坪田譲治がおり、表紙を飾った童画家、清水良雄も高い評価を得ました。ほかに童謡差曲家として成田為三、草川信らがおり、1918年11月号に西條八十の童謡詩として掲載された「かなりや」には、のちに成田為三によって曲がつけられ、1919年の5月号に楽譜の付いた童謡がはじめて掲載されました。
唄を忘れた 金糸雀(カナリヤ)は
後(うしろ)の山に 棄てましょか
いえ いえ それはなりませぬ
唄を忘れた 金糸雀は
背戸(せど)の小薮(こやぶ)に 埋(い)けましょか
いえ いえ それはなりませぬ
唄を忘れた 金糸雀は
柳の鞭(むち)で ぶちましょか
いえ いえ それはかわいそう
唄を忘れた 金糸雀は
象牙(ぞうげ)の船に 銀の櫂(かい)
月夜の海に 浮(うか)べれば
忘れた唄を おもいだす
この歌にはそれまでの唱歌にありがちだった単純な有節形式を壊す試みがなされており、これによって芸術的な香気が高まり、詩的また音楽的にも従来と異なった響きを持っていたことから、大評判となりました。
当初、鈴木三重吉も童謡担当の北原白秋も、「わらべ歌」「子供の歌」という程度に考えられていた童謡に旋律を付けることは考えていませんでした。しかし歌と楽譜の同時掲載という形式が大きな反響を呼んだことから、元々文学運動として始まった赤い鳥運動は、音楽運動としての様相をも見せるようにもなりました。
以後、毎号、芸術味豊かな作品(=文学童謡)を掲載するようになります。この後、多くの童謡雑誌も出版されたことで、子供の情操教育のために作った芸術的な歌としての童謡普及運動、あるいはこれを含んだ児童文学運動はこの時代の一大潮流となっていきました。
さらに「赤い鳥」が刺激となって次々と子供向けの雑誌が出版されるようにもなり、三重吉の13回忌にあたる1948年(昭和23年)からは、「鈴木三重吉賞」が創設され、現在も全国の子供の優秀な作文や詩にこの賞が贈られています。
三重吉の遺骨は、鈴木家の菩提寺である、広島市・長遠寺(じょうおんじ)の鈴木家の墓に納められ、そのすぐ右隣には、三重吉の13回忌墓碑が建立されています。墓碑の「三重吉永眠の地 三重吉と濱の墓」の文字は、彼自身が生前に書き残したものです。
街中にある寺のためヒガンバナは多く咲いていないかもしれませんが、境内に「被爆ソテツ」があります。現地は爆心地に近く、三重吉の墓とともに戦禍を免れたようです。世界遺産、原爆ドームからもほど近い場所にあります。ぜひ訪れてみてください。


















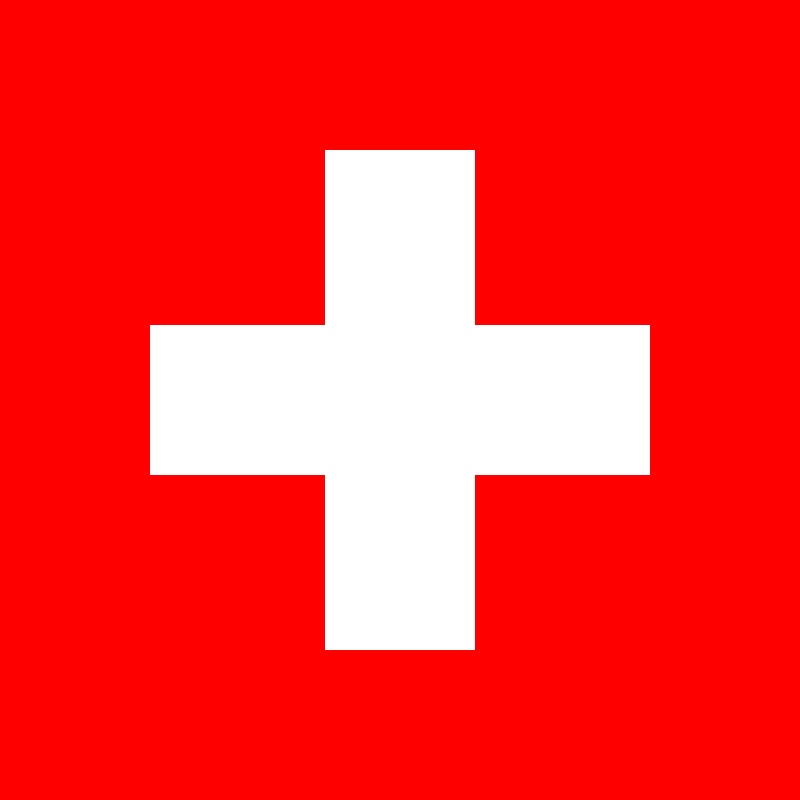












_-_panoramio.jpg)





