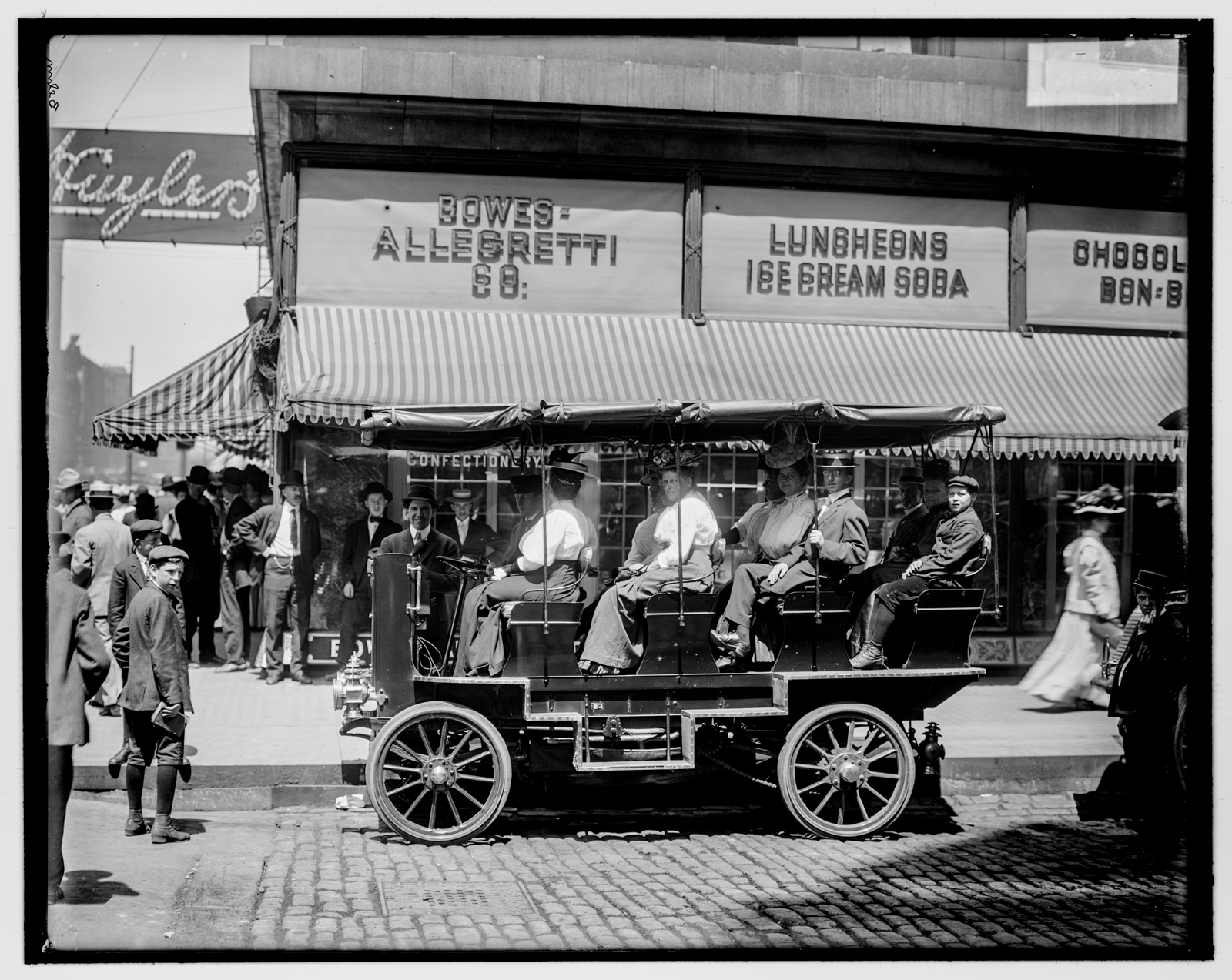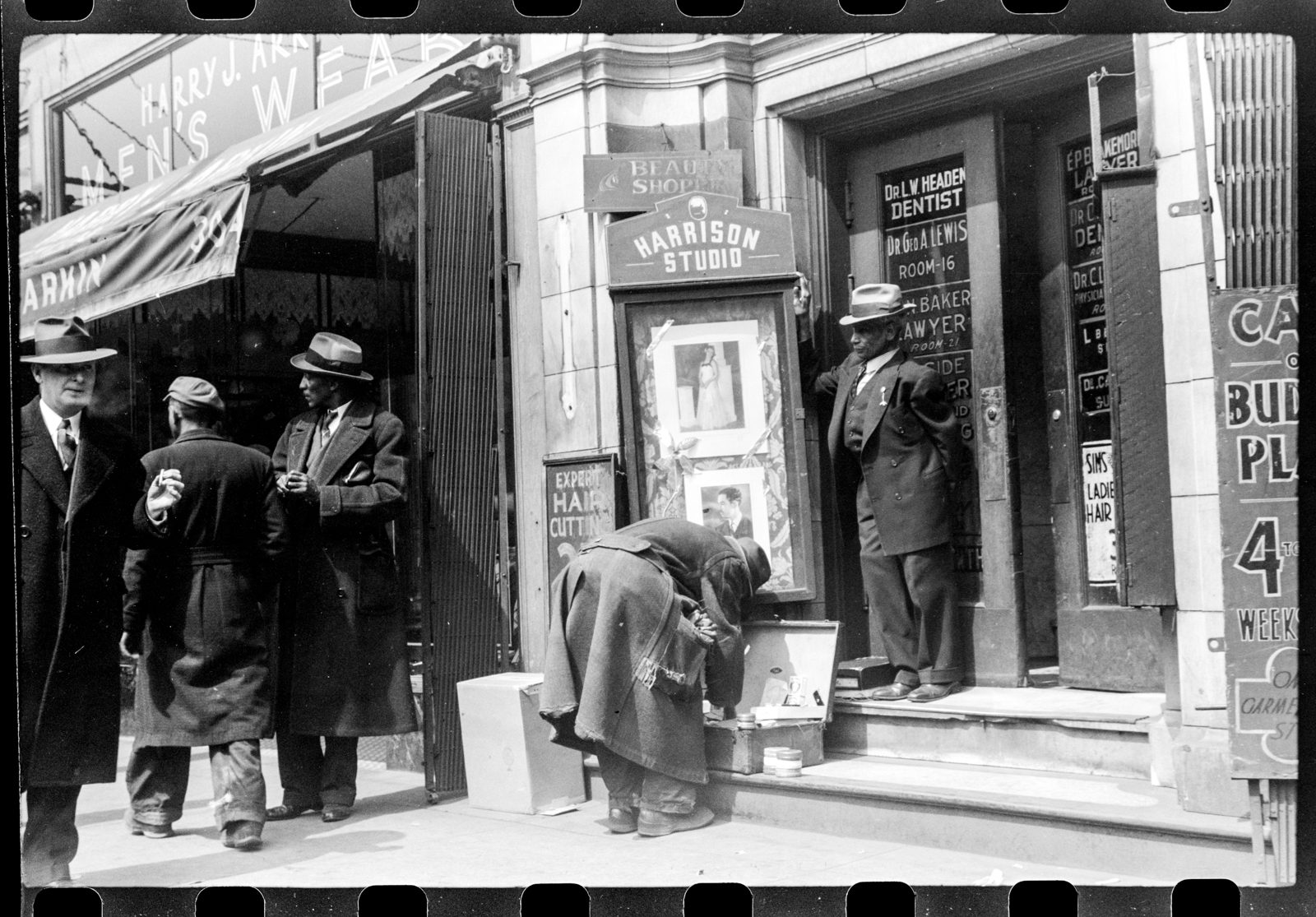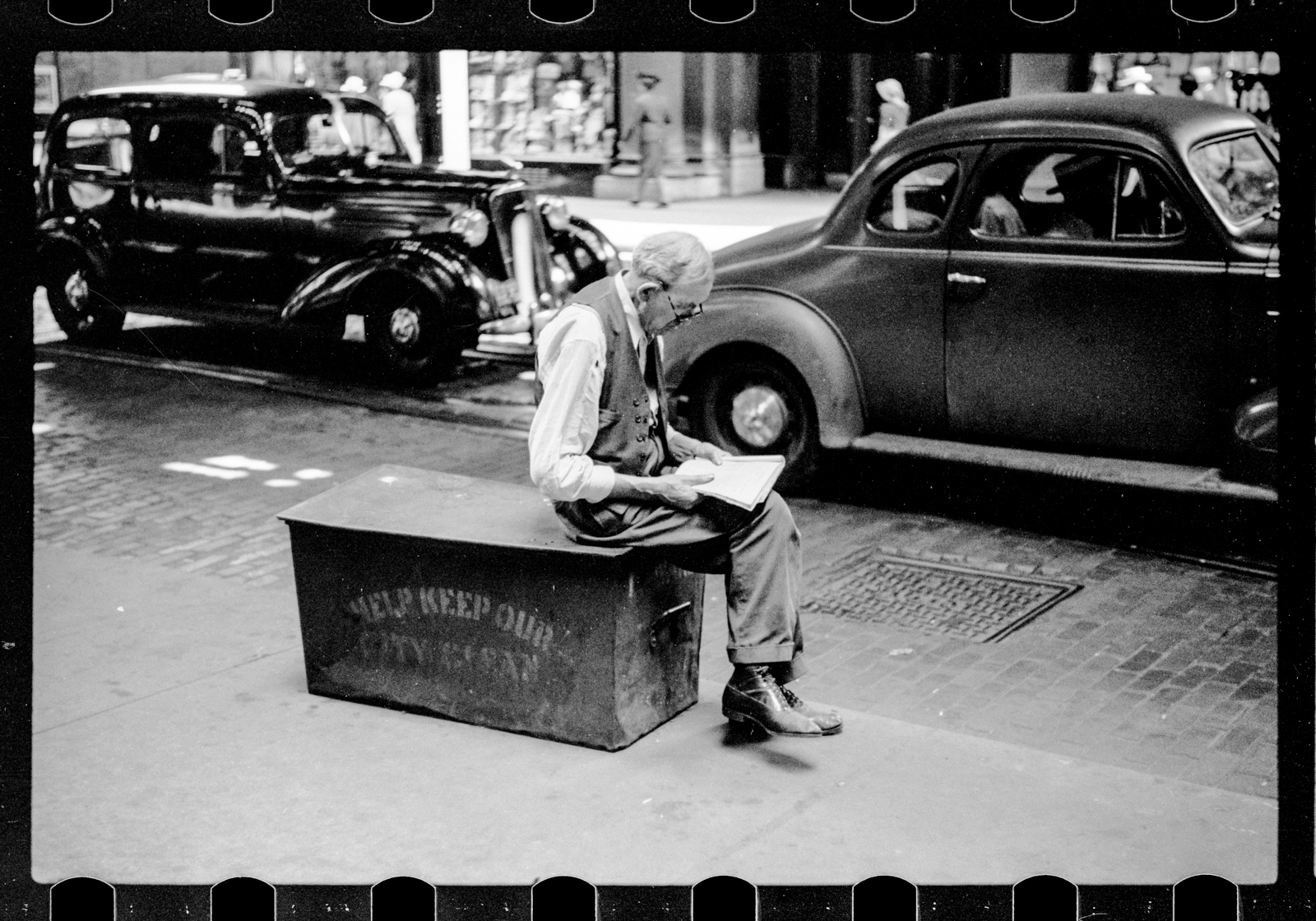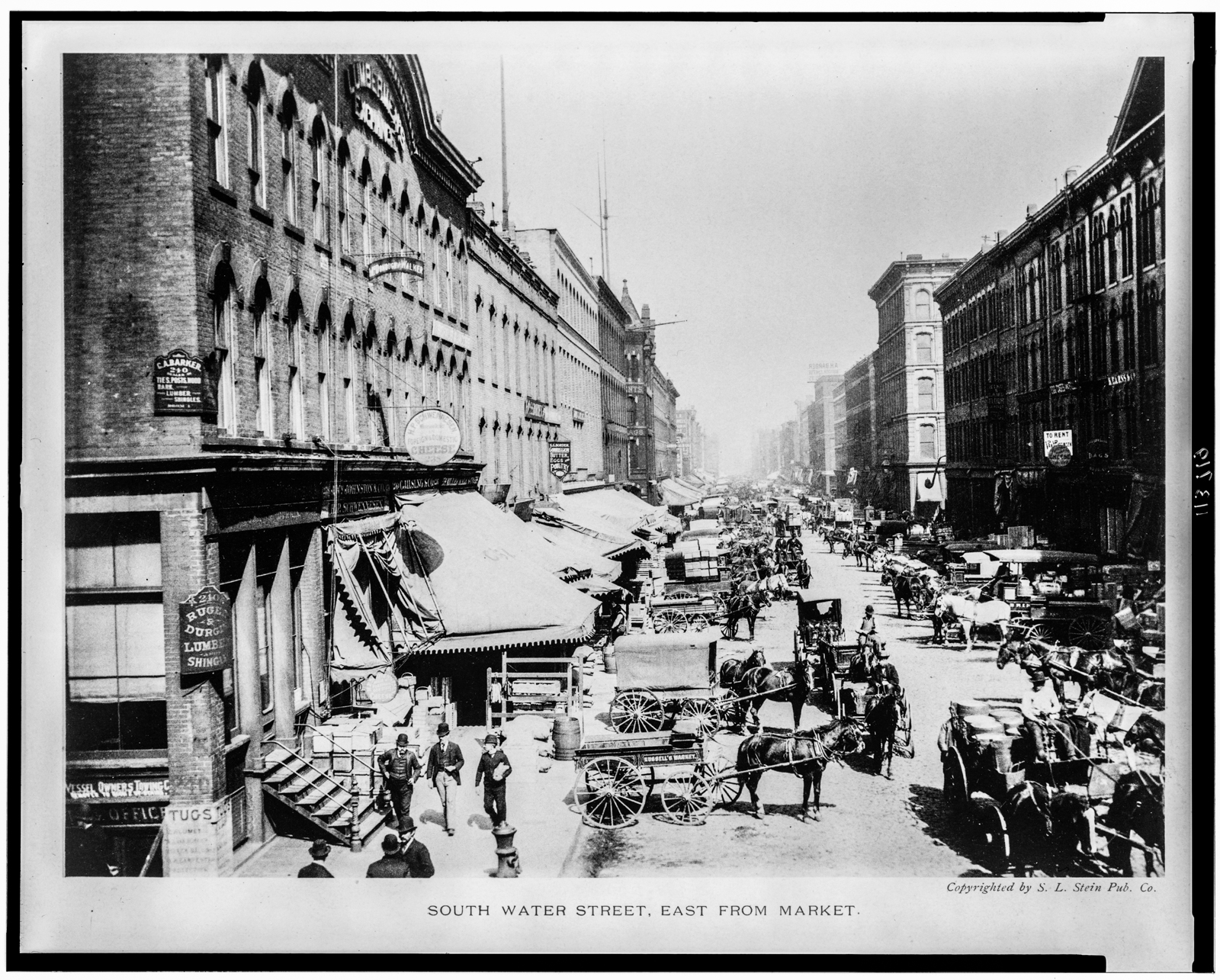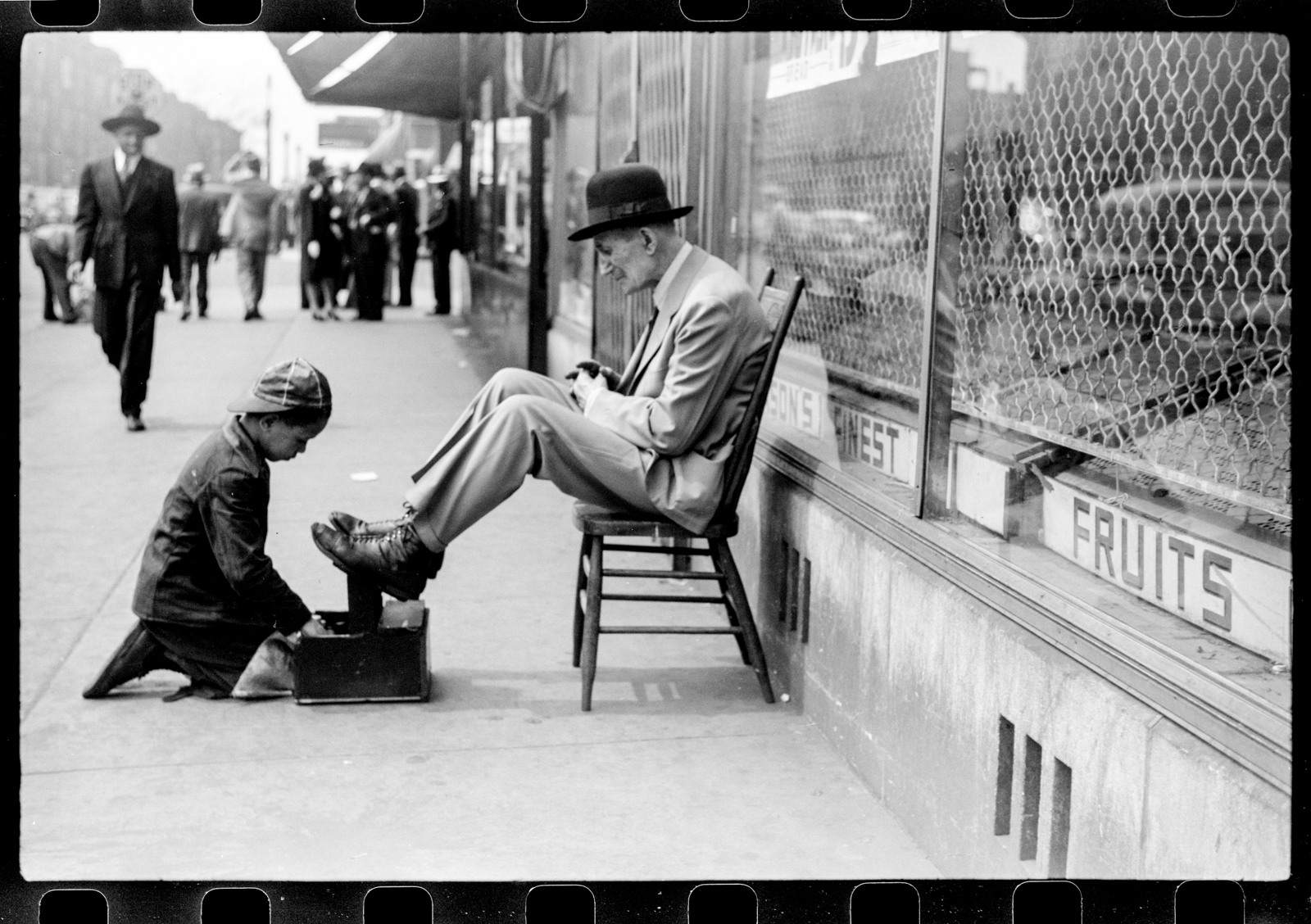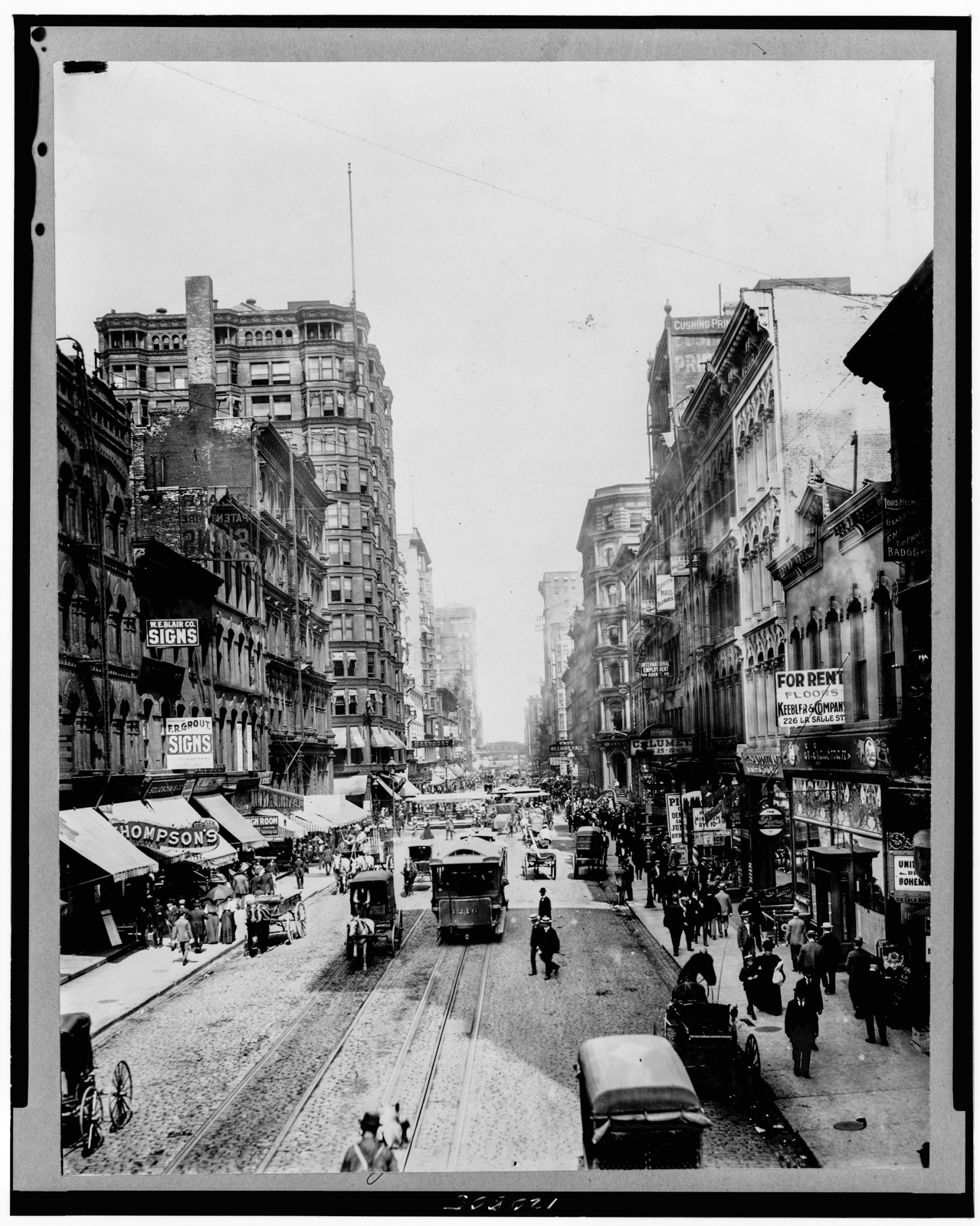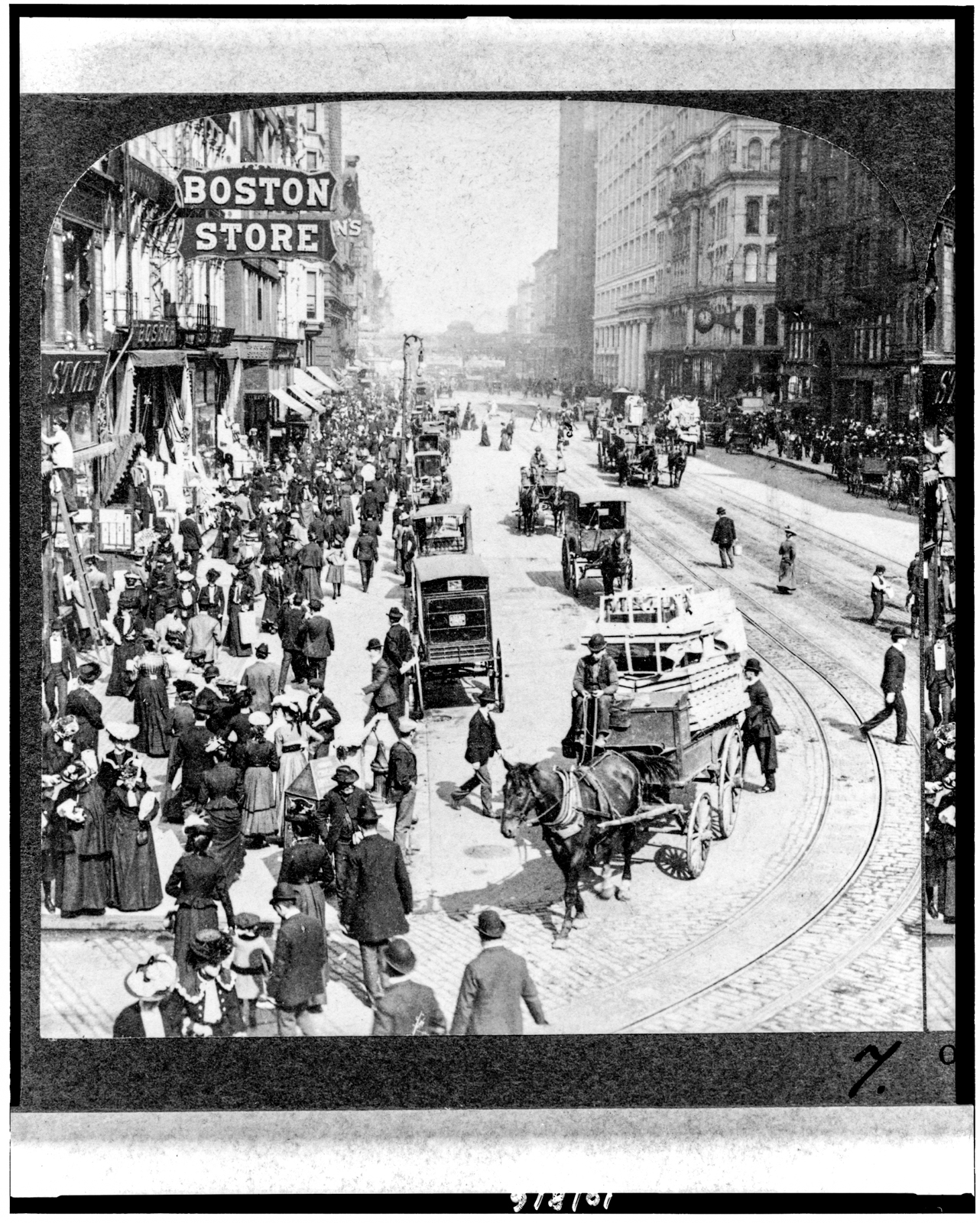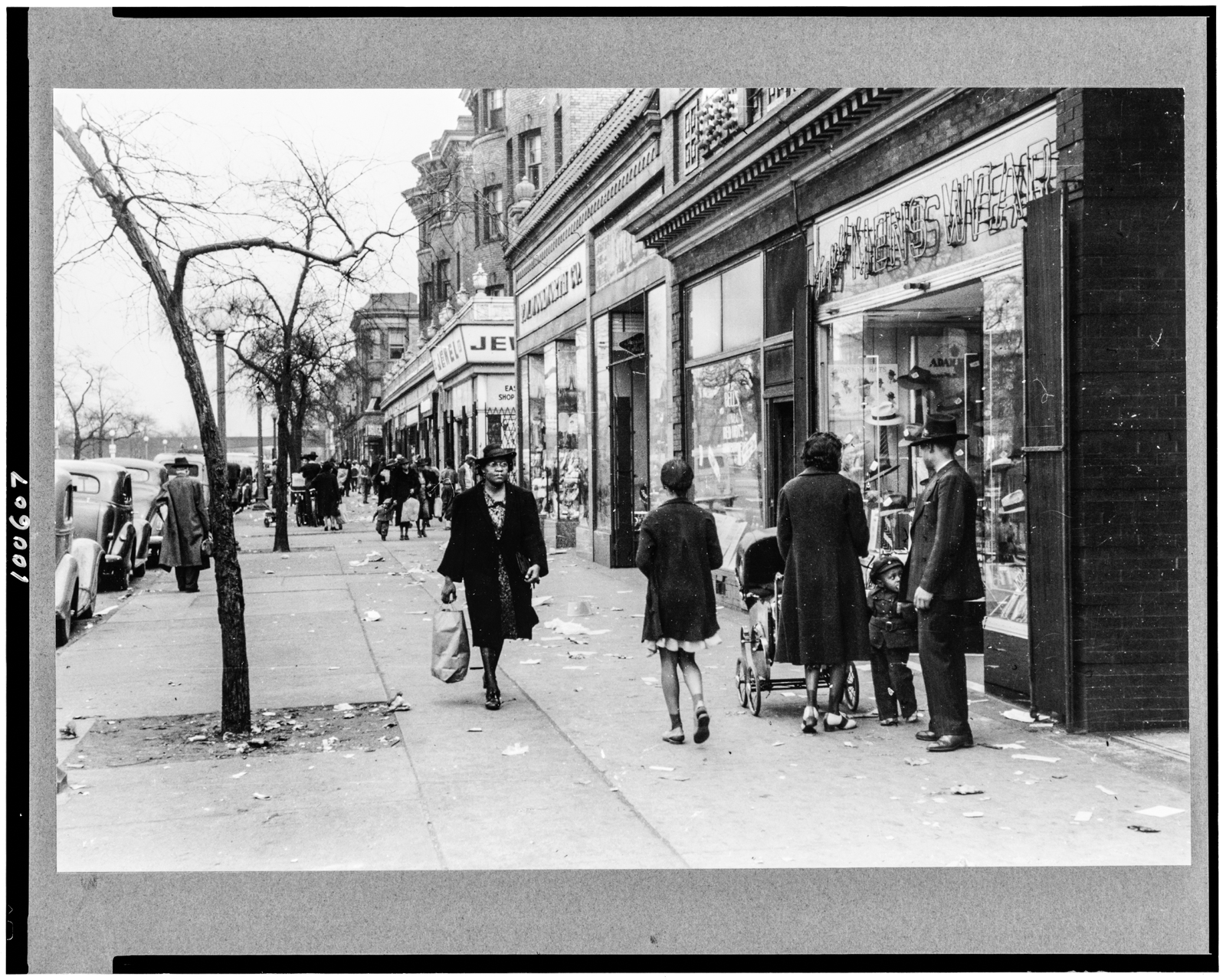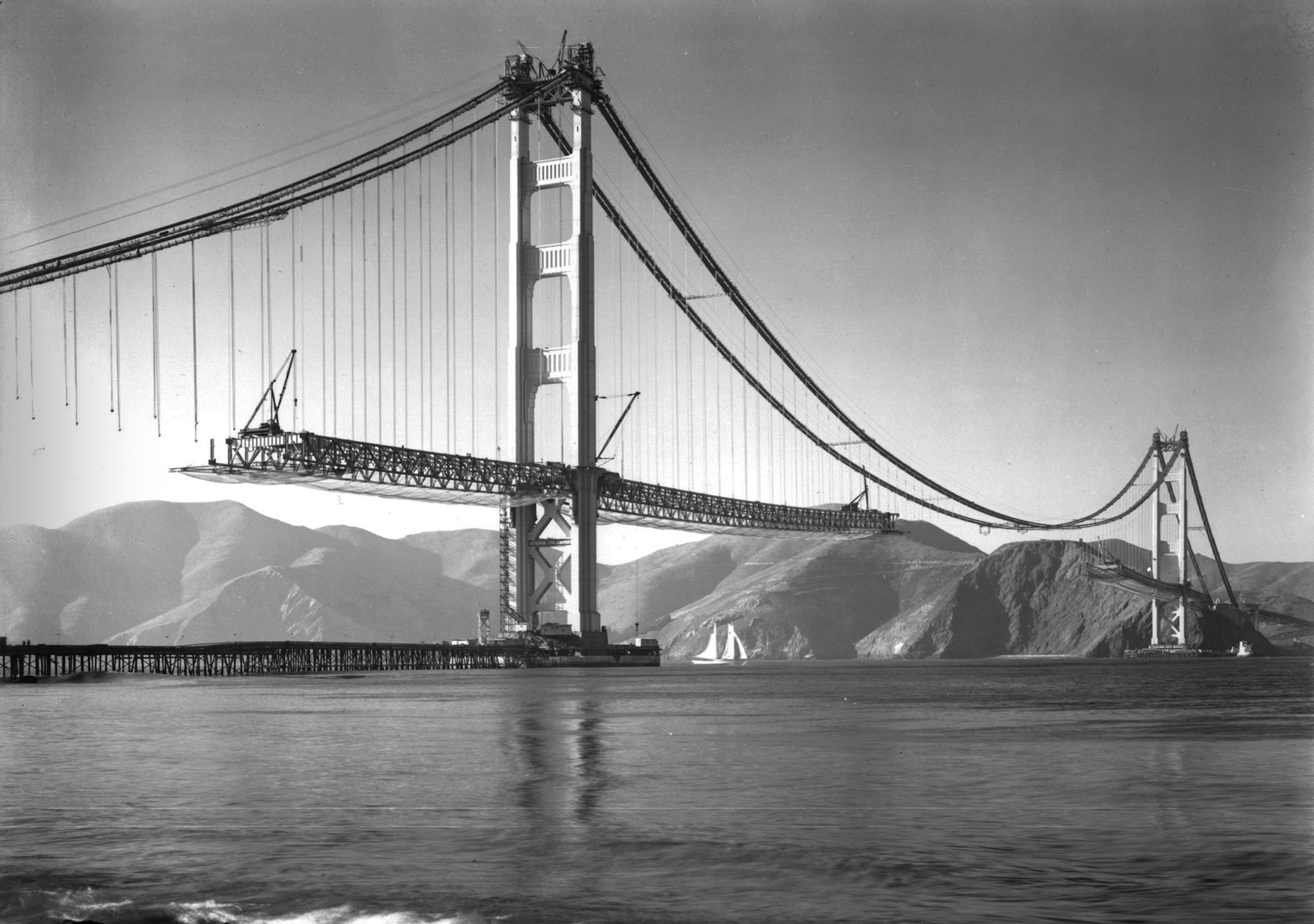好きな役者さんの一人だっただけに、大変残念なことですが、今生でのお役目を立派に終えられたことをご本人も満足されていることでしょう。私的にも公的にも高い評価を得るに値する方だっただけに、こういう人は前世においても社会的に認められる人物だったに違いありません。
が、必ずしも役者だったとは限らず、その引き締まった容貌からは武士だった前世もお持ちかもしれません。実際、そのご先祖は鎌倉時代の執権北条家の人だったということをご本人も生前から公表されていたようです。
北条家とは、改めて説明する必要もないかもしれませんが、源頼朝を助けて鎌倉幕府開闢をなしとげた、北条時政を中興の祖とする一族で、ここ伊豆が発祥の地です。時政の死後も5代に渡って源家を補佐する執権の座につきましたが、この北条家には分家が多く、その一門には、「名越北条家」というのがありました。
名越流北条氏は、鎌倉幕府2代執権・北条義時の次男・北条朝時を祖とする一族で、祖父は北条時政になります。時政は鎌倉幕府に仕えている間、鎌倉の名越(なごえ)という場所に邸を構えていましたが、孫の朝時は、この名越の家を継承しており、このことにより、名越北条と称するようになり、代々北陸や九州の国々の守護を務めました。
この名越という地は、神奈川県鎌倉市大町にある旧地名で、位置的にはJR横須賀線の鎌倉駅の南東部にあたります。
海岸からはやや奥まった場所にあり、かつての三浦半島方面への旧道である三浦往還(現在の県道311号)沿いにあり、名越という呼称は、このあたりの坂及び切通しが難所であったことから、「難越」(なこし)と呼ばれたことに由来すると言われています。
その名越北条氏の始祖とされる朝時の孫にあたるのが、北条篤時(とくとき)でやはりこの鎌倉名越に居を構えていました。さらに篤時の孫にあたる名越時如(ときゆき)の代あたりから名越の姓を名乗るようになったようで、その子孫は山口の大内氏に仕えるようになり、さらには九州北部に住みつくようになりました。
江戸時代の初めのころではなかったかと思われますが、太平の世になったこともあってか、このころの名越の主は武士の身分に見切りをつけ、代々冠してきた北条の名も捨てて「小松屋」の屋号で両替商を営むようになりました。
この商売は大きく当たったようで、この地を当地していた筑前福岡藩の黒田家の藩主から名字帯刀を許されて小田姓を名乗るようになりましたが、この小田家の子孫が、高倉健さんということになります。
このため健さんの本名も小田剛一といい、この江戸時代に両替商をしていたという小田家の本家は、北九州市から20kmほど西方にある福岡県中間市にあったようです。
明治時代から昭和時代にかけて、この地で産出される石炭がこの街を栄えさせ、明治大正時代に中間は炭鉱の町として全盛を誇りました。健さんは、1931年(昭和6年)にこの地生まれましたが、父はこの家に代々伝わる商売を継がず、その道を捨てて旧海軍の軍人になったようです。
退役後は、炭鉱夫の取りまとめ役などをしていたといい、またお母さんは学校の教員だったということでもあり、割と厳格な家庭であったのではないかと推測されます。
太平洋戦争が既に始まっていた1943年(昭和18年)に福岡県立東筑中学校に入学。しかし、途中、学徒動員にかりだされるなど勉強をやっているような状況ではなかったようです。戦後すぐに福岡県立東筑高等学校の商業科へ進みましたが、これは先祖が両替商などの商売をやっていたことと無関係ではないでしょう。
しかし健さん自身は世界を渡り歩く貿易商を目指していたようで、高校卒業後は明治大学商学部商学科へ進学。しかし、卒業後は戦後間もなくのことであり、大学卒業後も思ったような就職先がなく一旦帰郷し、このころ採石業をやっていたお父さんの仕事を手伝うことになりました。
23歳だったこのころのある日、「このままではダメになる」と思い、集金で持っていたお金を持ち出して家出同然の再上京。持ち出したお金も使い果たした頃に、大学の恩師から「新芸プロ」のマネージャー見習いの紹介をうけます。
喫茶店で面接テストを受けましたが、たまたまその場に居合わせていた東映の東京撮影所の所長で映画プロデューサー、マキノ光雄氏にスカウトされ、東映ニューフェイス第2期生として東映へ入社することになりました。
翌年、1月に24歳でいきなり主演映画でデビュー。「電光空手打ち」というタイトルでしたが、これは、空手道に青春をかける青年の役で、舞台はこの青年の出身地である沖縄から始まり、他派との抗争に巻き込まれながらも夢を追いかけて上京してここで成長する、という青春ものだったようです。
この映画はヒットしたようで、1週間後には続編が公開されたそうです。その後は、アクション・喜劇・刑事・ギャング・青春もの・戦争・文芸作品・ミステリなど、幅広く現代劇映画に出演しました。
さらにその後1963年に出演した「人生劇場 飛車角」もヒットし、それ以降、仁侠映画を中心に活躍。1964年から始まる「日本侠客伝シリーズ」、1965年から始まる「網走番外地」シリーズ、「昭和残侠伝シリーズ」などの主演でスターとしての地位を不動のものとしました。
以後の活躍は、連日のようにテレビや新聞で報道しているので、これ以上の説明は必要ないでしょう。
今年の8月26日に亡くなった米倉斉加年のお別れの会が10月13日に開かれた際に、故人に宛てて弔電を発したのが公の場での最後の活動だったそうで、去る11月10日午前3時49分、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で亡くなりました。
……と、ここまで書いてきて色々調べていたら、この11月10日という日には高倉健さんだけでなく、いろんな有名人、しかも俳優さんが同日亡くなっている、という意外な一致をみつけました。
例えば、2009年のこの日には、森繁久彌さんが亡くなっており、一昨年の2012年には女優の森光子さんが亡くなっています。これだけでも驚きなのですが、1974年には小笠原章二郎という俳優さんも亡くなっています。
私も含め、若い世代の人は誰も知らないと思いますが、この人は、日本映画黎明期の大正時代デビューした人で、当初の芸名は「楠英二郎」だったようですが、昭和時代に入り「小笠原章二郎」に改名。戦前は二枚目俳優として知られた人で、戦後は端役まで数多くの作品に出演し、テレビ放送が始まるとテレビドラマにも出演していたそうです。
晩年の1970年代まで活動しましたが、1954年の「和蘭囃子」という新東宝の映画では、顔を白塗りにした殿様をコミカルに演じたそうで、この演技が、後世の志村けんのコント「志村けんのバカ殿様」に繋がる「バカ殿」の原型になったといわれているようです。
さらに、です。1965年には、歌舞伎役者で、十一代目 市川團十郎さんが11月10日に亡くなっています。
この人は、一昨年の2013年(平成25年)2月3日に亡くなった、十二代目市川團十郎のお父さん、つまりニュースキャスターでタレントの小林麻央と結婚し、2010年に西麻布の飲食店で暴行を受け顔面を負傷した、十一代目市川海老蔵のおじいさんにあたります。
この十一代目 市川團十郎さんは、歌舞伎の世界に入る前の20代後半には、東宝劇団でも活動した人で、東宝との契約終了後の1939年(昭和14年)、市川宗家の十代目市川團十郎に望まれ、市川宗家の養子となり、翌年に九代目市川海老蔵を襲名しました。
この海老蔵時代、「花の海老様」として空前のブームを巻き起こすようになり、品格ある風姿、華のある芸風、高低問わずよく響く美声などを売り物として戦後歌舞伎を代表する花形役者の一人となっていきました。
1962年(昭和37年)、53歳のとき、十一代目團十郎を襲名。これは59年ぶりの大名跡復活だったということで、このときお披露目として興行された「勧進帳」は「一億円の襲名」と言われたそうです。
しかし、團十郎襲名からわずか3年半経った1965年(昭和40年)11月10日、胃癌で死去。56歳の若さでした。
その長男で十二代目 市川 團十郎さんのことはご記憶の方も多いでしょう。父が早世した後は自らの努力で芸を磨いた人で、スケールの大きい骨太な芸格が魅力で、重厚な存在感がありながらも、独特な愛嬌がありました。
市川宗家お家芸の歌舞伎十八番はもとより、荒事、世話物、義太夫狂言、新歌舞伎と多彩な役々を演じ分ける器用な人でしたが、2004年に長男が十一代目の市川海老蔵襲名した前後ごろから白血病を発症。
その後は壮絶な闘病生活を送り、妹から骨髄移植を受けたことでその後しばらくは舞台にも立てるほど回復されましたが、一昨年の2013年2月に肺炎のため死去。66歳でした。
その子である、十一代目市川海老蔵さんは、そうした父親の姿だけでなく、亡くなった祖父の十一代目 市川團十郎さんからも強い影響を受けたと語っています。少年時代の一時期、厳しい稽古に反発を繰り返していた折に、立ち直ったきっかけとなったのが、生前の祖父・十一代目團十郎のフィルムを見たことだったそうです。
海老蔵さんはこのときフィルムに映る祖父の勇姿と芸の美しさに感銘を受けたといい、その祖父のDNAを受け継ぎ、以後は古典の大役に挑み、初役を多くつとめ、高い評価を得るようになりました。そしてその姿に「海老さま」と人気のあった十一代目市川團十郎に重ね合わすファンも多いといいます。
さて、このように、11月10日という日は、有名な役者さんがたくさん亡くなっているわけですが、さらに調べてみると、実は、皇室ともゆかりの多い日ということもわかりました。1915年にはこの日に、大正天皇の即位礼が京都御所の紫宸殿で挙行され、1928年にも同じ日に昭和天皇の即位礼が同じく紫宸殿で挙行されています。
皇室典範・登極令制定後、初めてとなったこの大正天皇即位の礼は、1915年(大正4年)11月10日に京都御所紫宸殿で行われましたが、一般には公開されず、皇室関係者以外では貴族院議員などの国のトップだけを集めて行われました。
一方の昭和天皇の即位の礼当日の参列者は勲一等以上の者665名、外国使節92名他、2,000名以上もの参列者がありました。
1928年(昭和3年)11月6日、昭和天皇は即位の礼を執り行う為、宮城を出発し、京都御所へ向かいましたが、京都へ向かうこの天皇の行列は2名の陸軍大尉を先頭に神鏡を奉安した御羽車、昭和天皇の乗る6頭立て馬車、皇后の乗る4頭立て馬車、皇族代表の内大臣牧野伸顕の乗る馬車、内閣総理大臣田中義一の馬車と続く壮麗なものでした。
全長600メートルにも及んだというこの行列は、1分間に進む速度が86メートルと決められていたそうで、一行が京都に到着したあと続いて11月10日に行われた式典では内閣総理大臣・田中義一が万歳三唱して昭和の時代が幕を開けました。
ところが、11月10日に行われた皇室の行事は、これだけにとどまりませんでした。さらには、1940年の11月10日、皇居外苑で「紀元二千六百年式典」が実施されており、このときは日本各地で皇室2600年を祝う記念行事が盛大に行われました。
西暦1940年(昭和15年)が神武天皇の即位から2600年に当たるとされたことから、これを記念して行われた行事であり、日本政府はこれに遡る5年前の1935年(昭和10年)から既に「紀元二千六百年祝典準備委員会」を発足させ、初代天皇とされている神武天皇が祀ってある橿原神宮や陵墓の整備などの記念行事を計画・推進してきていました。
1937年には官民一体の「恩賜財団紀元二千六百年奉祝会」を創設。時代はそろそろアメリカとの関係があやしくなろうとしている時期でもあり、国民の意識を「神国日本」に向け、その国体観念を徹底させようという動きが強められていた時節柄でした。
「紀元二千六百年式典」は極めて神道色の強いものであり、敬神思想の普及のために「神祇院」なる組織まで設置され、奈良の橿原神宮の整備には全国の修学旅行生を含め121万人が勤労奉仕しました。
また外地の神社である北京神社、南洋神社(パラオ)、建国神廟(満州国)などの海外神社もこの年に建立され、神道の海外進出が促進されましたが、日本政府は、こうした活動により日本が長い歴史を持つ偉大な国であることを内外に示しそうとしました。
しかし、その一方で日本政府には、このころ既に始まっていた日中戦争の長期化とそれに伴う物資統制による銃後の国民生活の窮乏や疲弊感を、こうした様々な祭りや行事への参加で晴らそうとしていたわけです。
こうした中で迎えた1940年の「紀元二千六百年」は、年初めの橿原神宮の初詣ラジオ中継に始まり、全国11万もの神社において大祭が行われ、展覧会、体育大会など様々な記念行事が外地を含む全国各地で催されました。そして、11月10日、宮城前広場において内閣主催の「紀元二千六百年式典」が盛大に開催されました。
宮城外苑寝殿造の会場で挙行された内閣主催のこの「紀元二千六百年式典」の式次第では開会の辞を近衛文麿首相が読み、君が代奉唱、近衛首相による寿詞を首相が引き続いて奏上、天皇から勅語が下賜されたのち、軍楽隊・東京音楽学校による紀元二千六百年頌歌斉唱、万歳三唱されましたが、この模様は日本放送協会によりラジオで実況中継されました。
が、天皇の勅語の箇所だけはカットされたそうで、これは、ラジオの聴取者がどのような姿勢・体勢で放送を聴いているかがわからないため、不敬とされる状況が生じるのを避けるための措置であったといいます。天皇の肉声が正式なプログラムとして初めてラジオで流れるのは、その後1945年のポツダム宣言受諾を伝える玉音放送でした。
11月14日まで関連行事が繰り広げられて国民の祝賀ムードは最高潮に達し、式典に合わせて作曲された「皇紀2600年奉祝曲」は日本各地で演奏されました。
この曲は一曲だけではなく、紀元2600年を祝うために作曲された数々の曲の集合体であり、日本国内で作曲されたものもありますが、なんと欧米各国の作曲家に委嘱して作られました。アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、ハンガリーなどに依頼されましたが、アメリカはこのころ悪化していた対日関係を理由にこれを断りました。
結果、アメリカを除く5ヶ国から曲が提供されましたが、その後イギリスもアメリカと同様に敵性国家になったため、結局イギリスから提供された作品は演奏されませんでした。奉祝曲演奏会は、1940年12月7日・8日に東京の歌舞伎座において行われ、日本の著名な指揮者により演奏がなされました。
この演奏会は続いて12月14日と15日に一般向けの演奏会が行われたほか、大阪歌舞伎座でも一般向け演奏会が開かれ、その合間を縫ってラジオでも演奏の模様が全国放送されました。
各国の作曲家への返礼として、このときスタジオ録音されたSPレコード、印刷された楽譜、また、織物などが各作曲者に送られたそうですが、この翌年には太平洋戦争に突入したため、これらの贈り物を積んだ船は撃沈され、結局は届かなかったというエピソードも残っています。
ただ、友好国であったドイツの作曲家であったリヒャルト・シュトラウスには、その後作曲料の代わりに、この当時彼がコレクションとして収集していた「鐘」が代わりに送られ、これをシュトラウスは大いに喜んだそうです。
こうして、1940年11月10日の「紀元二千六百年式典」は無事に終わりましたが、この当時既に始まっていた日中戦争による物資不足を反映して、参加者への接待も簡素化され、行事終了後には、大政翼賛会のポスター「祝ひ終つた さあ働かう!」のポスターがあちこちに貼られるようになりました。
この標語の如く、その後戦時下の国民生活は引締めムードが強くなり、翌年の太平洋戦争への突入と共にますます厳しさを増していくことになっていきました。
終戦後、この11月10日に何等かの皇室の重要行事が行われたという話はないようですが、上で述べたような数々の式典が行われてきたことなどをみると、いまだもって皇室と非常に縁が深い日という印象があります。
そしてこの日に亡くなった森重久弥さんは、その皇室から、紺綬褒章(1964年)、紫綬褒章(1975年)、勲二等瑞宝章(1987年)、文化勲章(1991年)などなどの賞を受けており、2009年には従三位を受け、さらにはその没後に国民栄誉賞(2009年)まで受けています。
森光子さんもまた、1984年(昭和59年)11月、紫綬褒章を授与されており、1992年(平成4年)には、勲三等瑞宝章を授与されたほか、森重久弥さんと同様に文化勲章を受け、国民栄誉賞は生前に受賞しています。また従三位は死後に遺贈されています。
高倉健さんはといえば、この人も1998年に紫綬褒章を受けており、2006年には文化功労者とされ、2013年には文化勲章を受章しました。おそらくは、その死後にも何等かの栄誉が遺贈されるのではないでしょうか。
このように、皇室においてもハレといわれるような日に亡くなったということを考えると、どうしても神前に召されたのでは、と思ってしまうのは私だけではないでしょう。戦前の皇室は神格化された存在であり、現在も数々の問題をはらんでいますが、日本で一番古いファミリーであり、神に最も近い存在とも言われます。
まさか人身御供というわけでもないでしょうが、人身御供は、実は「神隠し」を起源とするものである、という説もあるようです。
神隠しとは、人間がある日忽然と消えうせる現象で、神域である山や森で、人が行方不明になったり、街や里からなんの前触れも無く失踪することを、神の仕業としてとらえた概念です。古来用いられてきた用語ですが、現代でも唐突な失踪のことをこの名称で呼ぶことがあり、天狗隠しともいいます。
なぜ、人身御供の起源といわれているかといえば、かつては神隠しとは神が人を食うために行われていた行為だと人々が考えていたためです。民俗学者の柳田國男によれば、日本では山で狼が子供を食ったという話が多く伝わっているということで、このオオカミがその後「山神」に転じ、これが子供をさらっていくと考えるようになったのだといいます。
そしてこのことが神隠しの起源となり、その後小児が失踪することをそう呼ぶようになっただけでなく、やがては荒ぶる神を抑えるために、こちらから人身御供を差し出す、というふうに変化していきました。
古代社会では人命は災害や飢饉によって簡単に失われる物でした。このため、気紛れな自然に対する畏怖のため、人身を捧げる風習が発生したと考えられ、自然が飢えて生贄を求め猛威を振るっているという考えから、大規模な災害が起こる前に、適当な人身御供を捧げて祈願することで、災害の発生を未然に防止したわけです。
特に日本では、あちこちの河川が度々洪水を起こしてきましたが、これは河川のありようを司る水神(龍の形で表される)が生贄を求めるのだと考えられ、このため河川の護岸工事などにおいては、人身御供の形で生贄が出されました。
人柱とも言われ、建造物やその近傍にこれと定めた人間を生かしたままで土中に埋めたり水中に沈めたりする風習を言いますが、事実であったかどうかは別として、人柱の伝説は日本各地に残されています。
また、城郭建築の時に、人柱が埋められたという伝説が伝わる城は甚だ多く、実際に城郭の遺跡を発掘したところその基礎から人骨が出てくるケースは結構あるようです。また、かつてのタコ部屋労働のように、不当労働や賃金の未払いから「どうせなら殺してしまえ」という理由で人柱にされてしまった例もあるといいます。
が、生きたままの人間を犠牲にする、というのは非常に世間体が悪いわけです。このため、一般にはこれを「神隠し」と称して神にさらわれたのだとし、そしてその神隠しにあった人たちは、岩や山、海や川などの神の宿る場所に行ったと人々に思い込ませました。
自然に存在する「依り代」のもとに行ったのだとされたわけですが、この依り代とは、憑代とも書き、神霊が依り憑く(よりつく)対象物のことです。神体などを指すほか、神域を指すこともあり、その場所と現世との端境でもあるという意味で、そこに「社(やしろ)」、すなわち神社を造って祀るようになりました。
そして、その神域とその外の境を「結界」と呼びました。鎮守の森や森林や山や海や川や岩や木などは、禁足地である場所も多く、現世の端境の向こうにある世界とし、そこに結界の象徴として社や境内を作ったわけです。
そして、その結界には、白い紙や布を吊るしたり張ったりしてそこが神域であることを示しましたが、この慣わしはその後家庭にも持ち込まれるようになり、現在でも神棚を白い紙や布を吊るしたり覆ったりするのはそのためです。
人身御供もその結界のかなたへ行き、表向きこれは神隠しとされました。災害を防ぐという大きな見返りを得るために、理不尽にもかかわらずその犠牲になるわけですが、いわば神という権力者に対して通常の方法ではやってもらえないようなことを依頼するための生贄だったわけです。
が、今回亡くなった高倉健さんをはじめ、これらの優れた役者さんたちは、けっして人身御供や生贄としてあの世に召されたわけではありません。それどころか、我々の世界においてはその演技を通じて多くのことを我々に教えてくれる貴重な存在であり、むしろ神によってその才能を望まれてあちらの世界に帰ったと考えるべきでしょう。
そして、今度はきっと神に奉仕するような存在になるに違いなく、あるいはより神様に近い存在になっていくのかもしれません。
古代日本において、祭祀を司る巫女自身の上に神が舞い降りるという神がかりの儀式のために行われたものが「舞」であり、これがもととなり、それが様式化して祈祷や奉納の舞となりました。そして、そこからは歌舞伎などが生まれ、やがてはそれが現在の芸能になっていきました。
その芸能を一生の生業にした健さんたちもまた、その俳優・女優業を通して知らず知らずにその活動を神に奉納していたのかもしれず、その生涯を終える日として、日本では最も神に近いとされる天皇家にゆえんのある日を選んだと考えることもできるかもしれません。
ですから、いっそのこと、11月10日を「芸能の日」とかいった記念日にでもしたらどうか、などと私などは思うのですが、そんな突拍子もないことを考えつつ、秋の日は更けていきます。
今年もあと一ヶ月あまり。その最後に毎年発表される墓銘録の中に、高倉健さんの名前も刻まれることを考えると少々寂しいかんじがします。
ご冥福をお祈りしたいと思います。