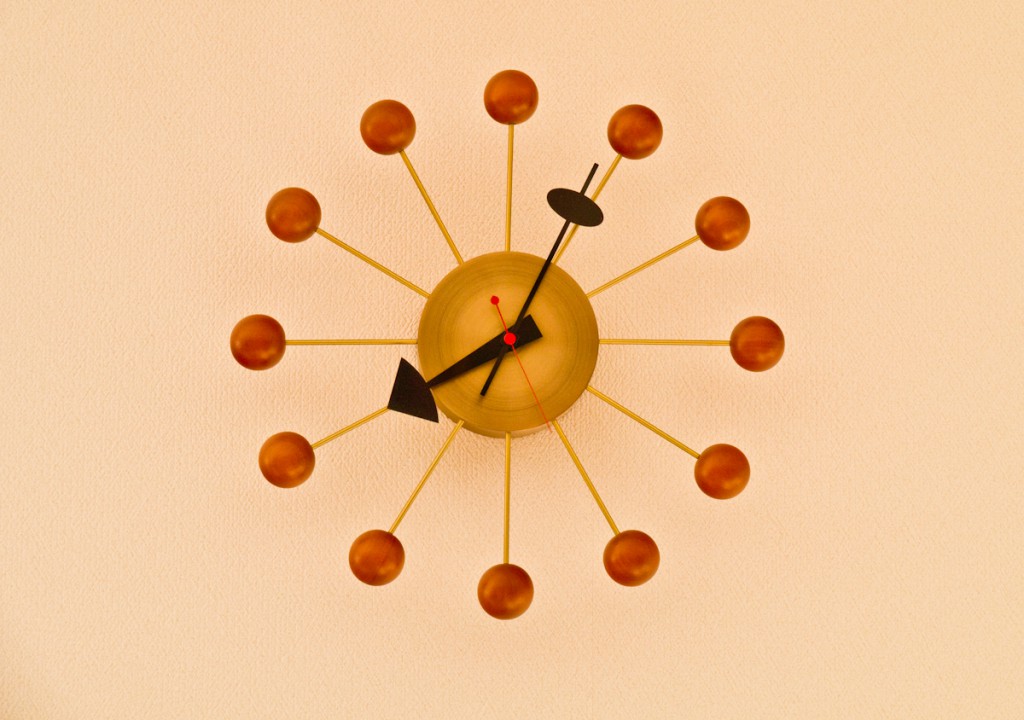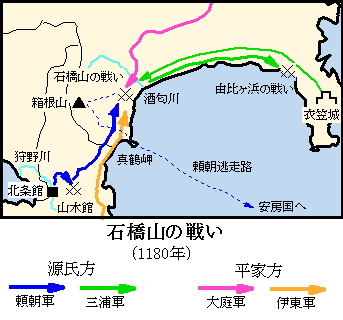台風一過と思いきや、また新たな台風が来ているそうで、週末から来週にかけてのお天気もいまひとつのようです。
先日の伊豆大島での土石流災害は、ここからはわずか30kmほど東へ離れたところで起こった出来事であり、とても他人ごとには思えません。
聞けばこの別荘地でも十年ほど前に小規模ですが崖の崩落があったとのことで、さらにその昔には、麓の熊坂一帯では狩野川台風による大被害があったこともあり、改めてこの伊豆地方というのはこうした水災害や土砂災害に弱い地域であるという印象を受けます。
安穏と住んでいるだけではなく、改めて災害への備えを怠らないように日ごろからの準備をしたいと思う次第です。
それにしても大島で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしたいと思います。いまだ行方知らずの方もいらっしゃるようですが、なんとか奇跡が起こってほしいものです。
ところで、富士山が初冠雪したようです。冒頭の写真は今朝の8時半ごろに撮ったものです。昨年が9月12日ですから、5週間も遅い初冠雪ということになります。
遅かっただけに、去年は頂上付近がほんのり白くなっただけでしたが、今年はもういきなり6合目付近まで真っ白となり、宝永火山の火口部分も半分くらいが雪をかぶっています。
これからは毎日こうして白く雪をまとった富士山を見れると思うとなんだかうれしくなってきました。お天気はいまひとつですが、窓から白富士が見えるなら、まっいいか。そんな気にもなります。富士山をながめながら寝そべれるようにそろそろコタツでも出そうかしら……
が、コタツなどに入っていてはせっかくの秋なのにもったいことこの上ありません。せっかくなら、旅行にでも行きたいところですが、先立つものもないし、今新しい仕事を始めようとしていて忙しいので、近場でがまんしようかと思っています。
昨年のいまごろ出かけた南伊豆の細野高原が気になっていて、そろそろここのススキの原が見ごろになっているはずです。が、今年は夏が暑かったために、ススキの穂も開くのが少し遅れているようなので、今度の台風が過ぎてからでも遅くないかもしれません。再来週の天気を期待しましょう。
ところで、旅といえば、NHKのBS放送で火野正平さんが、日本中を自転車で旅してまわっている番組があるのをご存知の方も多いでしょう。
私も昨年くらいからこの番組に気付き、毎週土日にある総集編を録画して欠かさず見ています。今回の秋の旅は、北海道から東北を下って静岡まで来るらしく、現在は福島から茨城あたりを通過しておられるはずです。
その火野さんが先日、青森の大間におられ、ここでは青函トンネルの工事に携わった方からのお便りからそこに行かれたのでした。そのとき、大間港をバックにトークをされていたのですが、その背後に一艘のイカ釣り漁船が停泊しており、その船腹に「特牛港」と書いてあるのにふと気が付きました。
特牛というのは、普通の人はまず読めないと思いますが、これは「こっとい」と読み、山口県の北西部にある豊北町というところにある小さな港町です。
あぁ~山口からこんなところまでイカ釣りにやってきたんだーとちょっと驚いたのですが、おそらくは山口のイカ釣りの漁師さんもまた日本海側をイカを求めて北から南まで日常茶飯事のように行き交いされているんだろうな、と想像されました。
それにしてもこの船はイカにも小さく、せいぜい100トンあるかないかの大きさであり、こんな小さな船で山口県から青森まで来るとはびっくりです。
さらに調べてみると、このイカ釣りについては、資源保護のために「イカ釣り漁船」を名乗るためには、農林水産大臣の許可を得る必要があり、かつこうした船はだいたいが社団法人のイカ釣り漁業組合という組織に所属し、この協会によってイカを捕獲できるテリトリーが決まるようです。
同協会のホームページを覗いてみたところ、協会への所属船は、大きく二つのグループに分かれるようです。
一つのグループは、総トン数30トン以上185トン未満のいか釣り漁船であり、火野正平さんの後ろに見えたのは、どうもこのクラスの船のようです。
これらの漁船は、主に日本近海に回遊するスルメイカ、アカイカ、ヤリイカを漁獲するほか、日本海のロシア排他的経済水域でスルメイカや北太平洋に広く分布するアカイカを漁獲していることです。
現在の大臣許可隻数は121隻だそうで、私がテレビでみかけた特牛港所属のイカ釣り船もその一隻であり、おそらくは山口から青森まで出かけ、ここからロシア近海まで出漁してイカを捕獲しに行くのか、あるいは帰ってきたばかりだったのでしょう。
この協会に所属するもう一つのグループは、総トン数、185トン以上の大型のいか釣り漁船です。これらの漁船は、遠く南米太平洋側にまで出漁し、ここに分布するアメリカオオアカイカやニュージーランド周辺のニュージーランドスルメイカを主に漁獲して日本に帰ってくるのだとか。
さすがにここまで遠くなると小さな船では難しく、大型船にならざる得ないことから、現在の大臣許可隻数はたった12隻ということでした。
このいか釣り漁業の方法ですが、自動いか釣り機によりイカ針を海中に投入し、引き上げる時にイカを漁獲するというものです。イカ針そのものが「疑似餌」の役割をしているため、エサはいりません。昼間にも漁業は行われますが、夜間に大量の漁灯を点灯させると、この光にイカが集まってきやすいので、より漁獲が容易になります。
近年は自動いか釣り機の導入、船内冷凍設備の向上によって、釣り上げられたイカは一尾ずつ急速凍結し、鮨、刺身原料としての高い高品質を保てるようになっており、この急速冷蔵法は、一尾凍結法(IQF:Individual Quick Frozen)と呼ばれています。
凍結方法としては、このほかにも加工原料向けのブロック凍結法というのもあり、こちらはどちらかといえば品質の悪い、あるいは小型のイカを対象としています。
ちなみに、いか釣り漁業はいか釣り用の特殊なイカ針を使用するため、イカ以外の魚を混獲することが全く無いそうで、乱獲の恐れのない、環境や資源にやさしい漁法といえるようです。ただ、漁灯で集魚したイカのうち、漁獲できるのは僅か10%程度だそうで、これはこれであまり効率的な漁法とはいえません。
が、歩留まりがあるのはある程度やむをえず、むしろあまり獲れすぎて資源を枯渇させないほうが良いのでしょう。近年捕獲数が激減しているマグロの二の舞にならないよう、しっかりと資源管理をしていってほしいものです。
ちなみにこのイカの漁獲高が一番多いのは、やはり青森県の八戸漁港だそうで、次いで、宮城県の石巻漁港、北海道の羅臼漁港となり、第4位が鳥取県の境漁港です。山口近海ではやはり少ないようで、特牛からイカ釣りに来ていた船はやはり漁場としてイカの豊富な北方をめざしてきたのでしょう。
このイカというのは、生物学的には、「軟体動物」に分類され、その仲間にはウミウシ、クリオネ、ナメクジ、タコなどがいますが、イカも含めていずれもが、もともとは貝殻を持っており、それぞれの進化の過程で貝殻を喪失したものです。
現在も貝殻を持つ軟体動物としては、二枚貝として我々もよく知る、アコヤガイ、ホタテガイ、カキ、アサリ、ハマグリ、シジミなどがあり、また、アワビ、サザエ、タニシ、カワニナ、ホラガイといった巻貝類は、軟体動物の中ではもっとも種数が多いものです。
カタツムリやナメクジは、これらの巻貝のうち腹足の筋肉が発達したもので、ナメクジは進化の際に、その背中側に巻いた貝殻を捨ててしまいました。ほかにもアメフラシ、ウミウシなどがこの親戚であり、こちらも貝殻は持っていません。
イカやタコは、こうした貝殻を捨ててしまったものの中では、とくに活発な動物であり、その活動のために足が多数に分かれて触手になりました。眼が発達しているのが特徴で、今はもう絶滅しかかっていますが、オウムガイなどもそうであり、既にいなくなってしまった種としては、アンモナイトがその代表選手です。
ただ、イカは貝殻を捨ててしまいましたが、コウイカなどは軟甲と呼ばれる石灰質で船形の殻を体内に抱えており、これは貝殻の名残です。また、ヤリイカやスルメイカもその体内にはイカの骨と呼ばれる筋があるのを、イカをさばいたことがある人ならご存知でしょう。
日本ではまず目にすることはありませんが、トグロコウイカという種類は、その体内にオウムガイのように巻貝状で内部に規則正しく隔壁があり、浮力調整のためか、これらの隔壁によって細かい部屋に分けられ、それぞれにガスが詰まっているそうです。
イカは本来の心臓の他に、2つの鰓に心臓の機能があり、この「鰓心臓」は鰓に血液を急送する働きを担っています。これらの心臓から贈り出される血は、人間のように赤くなく、青色です。銅タンパク質であるヘモシアニンという物質を含んでいるためですが、捕獲後我々が食べるために捌くと黒っぽいのはこの物質が空気中の酸素と反応するためです。
ちなみに、ほとんどの脊椎動物では、血液中に含まれるのは鉄由来のタンパク質であるヘモグロビンであるために赤色をしています。同じ水中を泳ぐ多くの魚たち同じくその血液が赤いのは我々と同じといえます。
イカが他の貝類と違って水中で活発なのは、そのぶよぶよの体によって浮力を得ているからです。ただ、ぶよぶよだけだと流れに持っていかれるため、その体内には比重の重い液体を体液として含むことで浮力調整をしており、これによりほぼ海水と同じ比重になっています。
昨年、ダイオウイカを世界で初めて日本の科学者が動画撮影して話題になりましたが、このダイオウイカなどの一部の深海イカは、浮力を得るために、塩化アンモニウムを体内に保有しています。
普通のイカもこの塩化アンモニウムを持っているものが多く、そのため独特の「えぐみ」もありますが、普通はそのえぐみがおいしさの秘訣です。が、ダイオウイカの場合は、この塩化アンモニウムの量がハンパではなく、このためもし食べようとしても臭くて食えたものではないそうです。
また、イカが水中で活発でいられるもうひとつの理由はその大きな目です。体の大きさに対しての眼球の割合が大きいことから、その行動の多くは視覚による情報に頼っていると考えられており、この目があるからこそ、エサを見つけることも天敵から逃げることもできるわけです。
さらに、イカやタコの眼球は外見上は我々人間のような脊椎動物の眼球とよく似ていますが、この目は非常によく見える目だそうです。
一見我々の目とよく似ているようですが、実はまったく異なる発生過程を経て生まれた器官であり、我々の目では視神経が目の全面を覆っていますが、イカの場合は網膜の背面側を通っており、このため、視神経が視認の邪魔になりません。
このため人よりも数倍優れた視力があると言われ、またまんまるいため、正面360度にわたって文字通り「盲点」がありません。
イカは、全世界の浅い海から深海まで、あらゆる海に分布しますが、軟体動物でありながら、なぜか淡水域にはいません。原因はよくわかりませんが、その活動を活発化させるための体液を保つ成分が淡水域では得られにくいからでしょう。
我々はイカを食べる側なのであまり気にしたことがありませんが、イカは何を食っているかというと、やはり小魚、甲殻類や主食としているそうで、プランクトンを食っていると思っている人もいるようですが、これは間違いです。
ただ無論、喰われる側でもあり、その天敵はカツオやマグロなどの大型魚類や、カモメやアホウドリといった鳥類、アザラシ・ハクジラ類のイルカやマッコウクジラなどの海生哺乳類などなどであり、イカの渡る世間は鬼ばかりです。
しかし、やられているばかりでは種が絶滅してしまいますので、身を守る術は持っています。これらの敵から逃げるときは頭と胴の間から海水を吸い込み漏斗から一気に吹きだすことで高速移動することは有名であり、またさらに体内の墨袋(墨汁嚢)から墨を吐き出して敵の目をくらませることができます。
ちなみにタコの墨は外敵の視界をさえぎることを目的としているため、一気に広がるのに対して、イカの墨はいったん紡錘形にまとまってから大きく広がるそうです。紡錘形にまとまるのは自分の体と似た形のものを出し、敵がそちらに気を取られているうちに逃げるためと考えられているそうで、賢いですよね~。
イカは日本人にとっては食い物にほかなりませんが、ユダヤ教を信じるイスラム教徒は、鱗がない海生動物は食べることは禁じられています。これを「カシュルート」といい、「清くない動物」の意味です。
理由はよくわかりませんが、川・湖に住む生き物で、ヒレと鱗のあるものは食べてもよいのですが、エビやカニなどの甲殻類のほか、貝類・タコ・イカなどはヒレや鱗がないので食べられないことになります。また、ウナギには実は細かい鱗がありますが、これは非常に目立たちにくいのでウナギも食べてはいけないそうです。
なので、イスラム系の人にウナギをご馳走するときには、一応本当は鱗があることを説明したほうがよさそうです。ちなみに、鳥の中で食べてはいけないものがあり、これは、鷲・クマタカ・鳶・ハヤブサ・鷹などの猛禽類のほか、カラス、ダチョウ、フクロウ、カモメ、ハクチョウなどだそうです。日本人もこれらは、あまりというか、まず食べませんよね。
イカやタコはその他の欧米諸国でも同様に不吉な生き物とされて食されることは少ないようです。デビルフィッシュッなどと呼んで嫌うようですがが、同じヨーロッパでもギリシアなど正教徒が多い東地中海地方ではイカ料理がよく食べられますし、スペインでもおなじみのイカスミ料理が楽しめます。
が、日本人のように刺身などの生食で食べる習慣は、彼らにはないようです。日本の場合、刺身のほかにも、焼き・揚げ・煮物・塩辛・干物など実に多彩な食べ方があるのは、その周辺海域で食べることのできるイカがたくさん獲れることにほかなりません。
イカ焼きは、お祭り・海の家の屋台の定番となっている他、イカソーメン・イカめしなどは、収穫量の多い地域の特産品となっているほか、ある種日本の風物詩でもあります。
日本は世界第一のイカ消費国であり、その消費量は世界の年間漁獲量のほぼ2分の1(2004年現在・約68万トン)とも言われているそうです。とくにスルメイカは、ほかの魚介類を含めたなかでも、日本で最も多く消費される魚介類です。
栄養も豊富で、ビタミンE・タウリンが多い他、亜鉛・DHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)も豊富であり、タウリンは、胆汁酸の分泌を促成し、肝臓の働きを促す作用があります。DHAは。健康増進効果があるとされ、EPAと同様にサプリメントや食品添加物として利用されていることはご存知の方も多いでしょう。
このほか、イカは消化しにくく、胃もたれの原因と思われがちですが、消化率は魚類と大差ないといいます。が、私はその昔、山県沖の飛島という島へ、ヤリイカの産卵調査に行ったとき、宿で毎日のように出されているヤリイカばかりを食っていたら下痢をした経験があります。もっとも、食い意地が張って食べ過ぎたのかもしれませんが……
このイカは、食材として役立っているだけでなく、最近は医学や工業といった分野でも着目されている生物です。
例えば、その神経細胞は、「巨大軸索」と呼ばれ、普通の生物に比べて極端に太く扱いやすい神経があり、これを利用して医学の分野では神経細胞や神経線維の仕組みや薬理作用の解明が進みました。
こうした実験で用いられるのはヤリイカが多いそうで、ただ、海で採れるもの以外を陸上で飼育するのは極めて難しいと言われていました。このため、大量に生きたヤリイカを飼育する方法が模索され、これに成功したのが、松本元さんという脳科学者です。
残念ながら、2003年に亡くなりましたが、神経細胞が巨大で観察しやすいこのヤリイカの人工飼育法の開発し、これを神経細胞の研究に生かし、さらには脳型コンピュータの開発を手掛けたことで有名です。
この業績は、オーストリアの動物行動学者で、近代動物行動学を確立した人物のひとりとして知られ、1973年にノーベル医学生理学賞を受賞した、コンラッド・ローレンツも絶賛したといいます。
コンラッド・ローレンツは、その研究上の必要性からいろんな生物の飼育を手掛けていたそうですが、イカについては「人工飼育が不可能な唯一の動物」と呼び、その飼育は極めて困難であるとしていました、
このため松本元がその飼育に成功したという話を聞いたとき驚き、そのの水槽で生きたヤリイカを見るために、わざわざ来日したそうで、実際にその目でみるまで、そのことが信じられなかったといいます。
来日後も、すぐに死ぬだろうからと信じず、イカが水槽内で生きている様を一週間もの間見届けてから、ようやく信じたといい、そのときこの松本博士が作った水槽を評して、「全ての水産生物の未来を変える」と断言したといいます。
こうして、巨大神経細胞が豊富に得られるようになった松本博士のグループは、その後次々と研究成果を挙げ、脳・神経科学の分野では世界的な業績を生み出しました。
所属していた電総研の地下にはヤリイカの水槽がいくつも設けられ、見学者に「色がきれいだろう」と紹介したりしていたそうですが、一方ではこのイカを使ってイカ焼きパーティーを行うといった茶目っ気のある人でもあったそうです。
ちなみに、イカの飼育は魚類などよりはるかに難しいため、一般人が趣味でアクアリウムとして飼うことはできにくいようです。水族館といえども難しいようです。ただ、滑川市の博物館「ほたるいかミュージアム」や魚津水族館で捕獲個体が展示されることもあるそうです。なので生きたイカを見たいひとは、富山県へ行きましょう。
その後、脳型コンピュータの開発を行うため理化学研究所に移り、脳科学総合研究センターのディレクターとして研究を行うなど活躍されましたが62歳でこの世を去っています。ノーベル賞こそ受賞はしませんでしたが、日本政府はその功績を称え、彼に正四位勲三等瑞宝章を贈っています。
このほか、イカの肝臓には、放射性物質が蓄積されやすいこともわかっており、このことからイカを使って海洋の放射性物質による汚染の状況を知ることもできるようになりました。水産庁の中央水産研究所では、蓄積量を継続的に調査しているといい、おそらくは福島原発沖の放射能の測定にもイカが使われていると思われます。
このほか、イカがあげた大きな功績としては、その内臓から「液晶」が作られたことです。
イカの肝臓から抽出したコレステロールを特殊な方法で化学反応させると、コレステリック液晶というものが作られ、これは通電することによって黒く変色します。
現在は、この化学反応の過程は解明されており、日本で用いられている液晶はほとんど化学的に合成されているため生きたイカは必要ありませんが、イカがなければこの組成も解明されなかったかもしれません。
このほか、イカは、古くはその墨がインクや絵の具に使われました。「セピア」というのは実はイカスミのことです。古代ギリシャ語では、コウイカのことをこう呼んでおり、地中海沿岸地方では古代よりイカが食材にされるとともに、このイカの墨がインクとして広く使用されていました。
イカ墨には悪臭があって色あせしやすいためにインクとしてはその後一旦使用されなくなりました、近世にはイカ墨をアルカリで溶かしたあと塩酸で沈殿させ、それを乾かして茶色の顔料として使うようになりました。
これが西洋全般に広まるようになり、これとともに”sepia”という単語も広まり、イカ墨やその顔料、そしてその色をも意味するようになったのです。
19世紀末には、セピアのインクが新聞や雑誌の印刷に使われることが流行り、この色は大人気になりましたが、その名残でこうした黒っぽい茶色がかったモノクロ写真を、現在でも「セピア調の写真」といいます。
「いか」の語源については、「いかめしい」形に由来するとの説などがあるそうですが、はっきりとしたことはわかっていないそうです。が、漢字としての「烏賊」の由来は、海に飛び込んでイカを食べようとしたカラスをイカの方が巻きついて食べてしまったとの故事に由来するとの説があるようです。本当だとすると、かなり馬鹿でかいイカですが。
大相撲の隠語で、「イカを決める」というのがありますが、これは勝負事や賭け事に勝ったまま勝ち逃げすることを意味するそうです。イカがスミを吐いて姿をくらますことに由来するようで、このほかにも大相撲では「しかをきめる」という隠語があり、これは、しらばっくれたり知らないふりをすることだそうです。
今日のブログもかなり長くなってきたので、そろそろしかをきめて、終わりにしたいと思いますが、逆に読者の方々からは「そうはいかの金玉」という声が聞こえてきそうです。
が、もうそろそろ終わりにしましょう。
南伊豆の細野高原は、このお天気ではこの週末は無理そうで、今度行くのは再来週になりそうです。南伊豆には下田もあり、もしかしたらおいしいイカも食べれるかも。みなさんもイカがでしょうか。