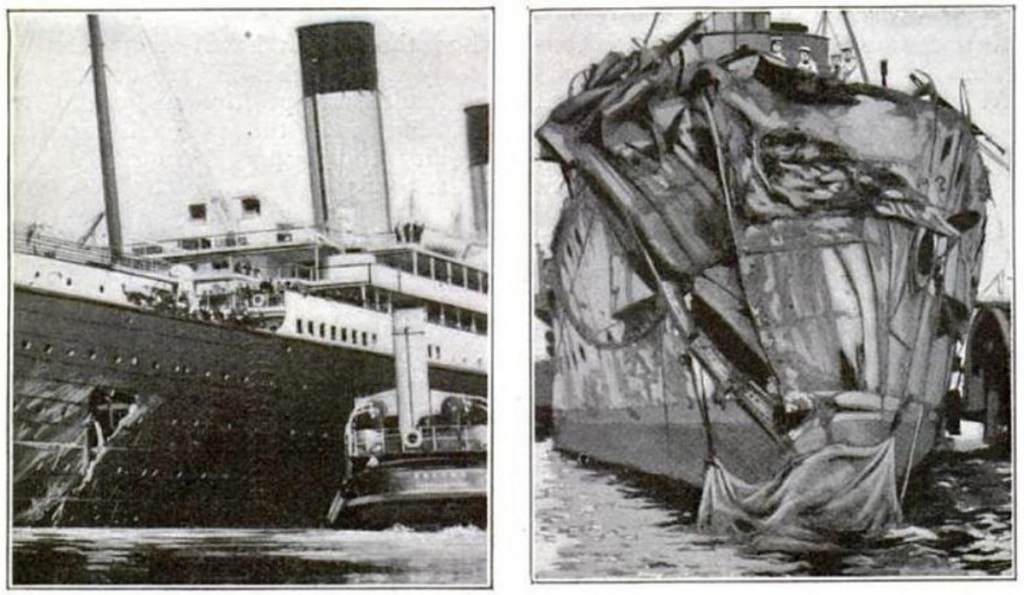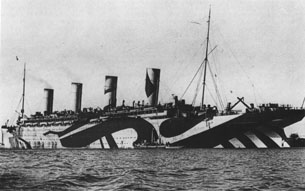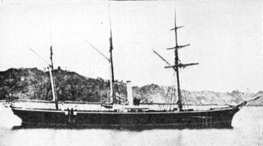今日で、9月も終わりです。
だというのに、未だ富士山の初冠雪はありません。それだけ今年の残暑は厳しかったということなのでしょうか。
さて、今日9月30日というのは、その数字から、「く(9)」る「み(3)」は「まるい(0)」という語呂合せができるということで、「くるみの日」になっており、これはくるみの名産地、長野県のくるみ愛好家達が制定したそうです。
クルミの原産地はヨーロッパ南西部からアジア西部とされ、北半球の温帯地域に広く分布しますが、日本に自生している胡桃の大半はオニグルミといい、長野県東御市がクルミの生産量日本一です。
ご存知の方も多いと思いますが、その殻はゴツゴツとして非常に硬く、中にあるナッツは非常に取り出しにくいのが特徴です。
このため、かなり昔から様々な形状のくるみ割り器が考案されてきましたが、1735年にドイツのテューリンゲン州ゾンネベルクというところで、「クルミ噛み器」が考案されました。
しかし、現在知られているような兵隊さんのような形に変化し、「くるみ割り人形」と呼ばれるようになったのはその後100年以上も経った1870年代頃のことのようで、ドイツ、ザクセン州のエルツ山地地方のザイフェンという小さな村の木材加工の工房の主が、これを考案しました。
最初のモデルは軽騎兵(兵隊)、消防士、山林監視官であったそうですが、その後、王様、警官なども造られ、その他にも、夜警、キノコ採り、サンタクロースといったものもあるそうです。
そもそもこういうモデルが生まれた背景には、一般庶民達の支配者階級に対する反発心や、ささやかな抵抗によるうっぷん晴らしという側面もあったのではないかという説もあるといいます。
このためか、最初のころは、堅い木の実の殻を口(歯)で砕く苦々しい顔をした男性を形どったものがほとんどだったそうですが、時代と共に、昔のようないかめしい怖い表情のものは少なくなり、現在は優しい表情のデザインのものが多くなっているそうです。
この「くるみ割り人形」は、ロシアの大作曲家、ピョートル・チャイコフスキーの作曲したバレエ音楽としても有名です。
これに「白鳥の湖」、「眠れる森の美女」を加えてチャイコフスキー作の三大バレエともいわれ、初演から100年以上もの間、愛されてきましたがいまだに数多くの改訂版が作られているといいます。
その筋立てはもともと、ドイツ人のE.T.A.ホフマン(エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン)という人の童話に基づいており、これをもとにクラシック・バレエの基礎を築いたことでも知られる、フランス人バレエダンサーのマリウス・プティパが台本を手掛けて創作されました。
その初演は1892年(明治25年)、ロシアのサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で行われました。このときの観客の反応はまずまずであったものの、主題が弱いと考えられたためか大成功とまでは言えず、現在のようなポピュラーな作品となるまでにはやや時間を要したそうです。
全曲の演奏時間の約1時間25分は昔からほとんどかわらず、これは2幕に分かれていますが、バレエの演技を抜きにして録音されたり、演奏会だけのために組曲にしたり、抜粋して演奏されるといったことも多いようです。
その内容はというと、ドイツのある裕福な家庭に生まれた少女クララが、クリスマスにプレゼントされたくるみ割り人形が、彼女の夢の世界に現われ、彼女をはつかねずみの大群から守るために奮戦し、勝利した人形は、凛々しい王子になって二人はお菓子の国で楽しく暮らす……というもの。
この物語の原作者のホフマンは、1776年生まれで、1822年に56歳で没した人です。この人ももともとは作曲家で、音楽評論家として知られていたようですが、その後画家や文学作家としても活躍し、多彩な分野で才能を発揮しました。が、とくに後期ロマン派を代表する幻想文学の奇才として知られているということです。
このホフマン原作のクルミ割り人形のストーリーを知らない方も多いと思いますので、ここで紹介しておきましょう。
物語は、医務参事官である、シュタールバウム家のあるクリスマスの情景からはじまります。
この家には上からルイーゼ、フリッツ、マリーの3人の子供がいました。一番下の娘マリーが7歳の時のクリスマスの日のこと、彼女はたくさんのクリスマスプレゼントのなかから不恰好なくるみ割り人形をみつけ、何を思ったのかこれがすっかり気に入ります。
ところが、これを使って兄のフリッツが大きな胡桃を無理に割ろうとして故障させてしまいます。人形を気の毒に思ったマリーは、その夜、戸棚に飾ってある他の人形のベッドを借りて、このくるみ割り人形を休ませようとします。
するとあたりの様子がもやもやと俄かに変化し、地面から7つの首をもつネズミの王様が軍勢をともなって現われました。そうしたところ、マリーが寝かせたばかりのくるみ割り人形が、むっくりと起き出したではありませんか。しかも人形は立って動き出し、戸棚にあったほかの人形たちを率いて、このネズミの軍を相手に戦争を始めました。
しかし、ねずみ軍団の力は強く、次第に人形たちが劣勢になっていきました。これをみていたマリーは、人形たちの窮地をなんとか救おうとしたのですが、その際中にふっと気を失ってしまいます。
気がつくと彼女は右腕に包帯を巻かれてベッドに寝かされていました。マリーが彼女の母親たちから聞かされた話によれば、マリーは夜中まで人形遊びをしているうちにガラス戸棚に腕を突っ込んで怪我をしてしまい、その拍子に気を失ったのだといいます。
マリーには、叔父が一人おり、彼女の名付け親となってくれたのもこの人でした。ドロッセルマイヤーおじさんといい、彼女は彼のことが大好きでいつも何かと相談に乗ってもらっていました。
なので、このときもおじさんにこの「夢」の中のことを話したところ、おじさんは、ニコニコしながら、彼女に似たような話がある、と言って「ピルリパート姫」というおとぎ話を彼女に話して聞かせ始めました。無論、これはおじさんの即興による物語でした。
この物語は、あるお姫様とねずみの戦いの話でした。姫はネズミの呪いを受けて醜くされてしまうのですが、王室のお抱えの時計師ドロッセルマイヤーとその甥の活躍によってもとの美しさを取り戻すことに成功します。しかしその身代わりに、時計師の甥は醜い姿に変えられてしまうことになったのでした。
この話を聞いたマリーは、それからのこと、彼女のくるみ割りこそがドロッセルマイヤーの甥なのだと妄想しはじめます。そして、それ以降、夜な夜なマリーのもとには、ねずみの王様が現われるようになり、くるみ割り人形の安全と引き換えにマリーのお菓子を要求するようになります。
マリーは仕方なく戸棚の敷居に菓子を置いておくようになりましたが、翌朝になるとネズミによって食い荒らされているのでした。しかもネズミの行為はだんだんとエスカレートし、はさらにマリーの絵本や洋服まで要求するようになります。
マリーはすっかり困ってしまい、くるみ割り人形のドッセルマイヤーに相談したところ、彼は一振りの剣を与えてほしいと答えました。翌朝、マリーは兄フリッツに頼んで兵隊人形のためのおもちゃの剣を一振りもらうことにし、これをそっとくるみ割り人形に持たせました。
こうしてその夜、剣を貰ったくるみ割り人形は、みごとにネズミの王様に打ち勝つことができました。そしてその姿をマリーのもとに現わすと、助けてもらったお礼にマリーを美しい人形の国へ招待したいと申し出ますが、その夜の「夢」はそこで終わってしまいました。
翌朝、自分のベッドで目覚めたマリーは、その夜の夢のような人形の国の情景が忘れられず、家族にそのことを話してまわりますがが、誰からも取り合ってもらえません。
ちょうどその日のこと、ドロッセルマイヤーおじさんが一人の青年を伴ってマリーの家を訪ねてきました。叔父さんによれば彼の隣にいるこの男性こそが、彼の甥だということでした。
叔父さんが「ピルリパート姫」の中でねずみの魔法によって醜くされてしまったと語ったこの甥は、醜いどころかとても感じの良い美青年でした。
叔父さんは、マリーの両親に用事があるからと一人奥の部屋に入っていきました。すると、マリーと二人きりになった途端にその青年がマリーのところに近寄ってきて、耳元でささやくようにこう言いました。
「僕があのとき君に救われたくるみ割り人形だよ。」
そして、彼女がくれた剣のおかげでねずみを退治できたことで、もとの姿に戻れたのだと話しました。彼は今や人形の国の王様となり、マリーを王妃として迎えに来たのでした……。
……と、このくるみわり人形の原作は、現実と夢物語が交錯する、複雑な構成になっています。もともと、作者ホフマンが友人の子供のために即興で作ったものであったそうで、自分の娘を幼くして亡くしていたホフマンはこの子供たちのひとり……これがマリーという名前でしたが……をとくに可愛がっていたということです。
この話はマリーのためのクリスマスプレゼントとして作られたものであったそうで、作中でも不気味な雰囲気を漂わせている、話好きで手先の器用な「ドロッセルマイヤーおじさん」は実はホフマン自身だったともいわれています。
ホフマンの自画像が残っているので見るとわかるのですが、かなりのブ男であり、不気味な小説ばかり書くこの当時彼のことを評して「お化けのホフマン」などと揶揄するひともいたということです。
こうして、この童話はその後、バレエの「くるみ割り人形」の原題にもなりましたが、バレエ版の中では、主人公の少女の名前が違うことをはじめ(マリーではなくクララ)、ホフマンの作品とはかなりその雰囲気には隔たりがあるようです。
このホフマンという人は、ドイツのケーニヒスベルクの法律家の家に生まれ、もともとは自らも法律を学んでおり、のちには裁判官にもなっています。
その傍らで芸術を愛好し詩作や作曲、絵画制作を行なっていったわけですが、1806年にナポレオンの進軍によって官職を失うとバンベルクで劇場監督の職に就くようになり、舞台を手がける傍らで音楽雑誌に小説、音楽評論の寄稿を開始しました。
1814年には判事に復職し、裁判官と作家との二重生活を送り始めましたが、病に倒れるまで旺盛な作家活動を続けました。
このとき彼が書き遺した小説には、上述のような童話風のもののほか、「自動人形」や「ドッペルゲンガー」といった「不気味」の代表ともいえるようなモチーフを用いたものも多く、現実と幻想とが入り混じる特異な文学世界が作り出されました。
自動人形というのは、オートマタ(Automata)とも呼ばれ、主に18世紀から19世紀にかけてヨーロッパで作られた機械人形のことをさします。
ギリシャ語の「automatos」から来たもので、もともとは「自らの意志で動くもの」という意味合いを持ち、必ずしも機械を指す言葉ではありません。
が、その後18世紀から19世紀にかけてのドイツやスイスの時計技術の革新と、ルネサンス以降のフランスで流行したディレッタンティズム(道楽化・道楽主義)の複合によって、オートマタとはこの「自動機械」のことを指すようになりました。
この自動機械の動力は基本的にはぜんまいばねでした。人形状の形をしていましたが、娯楽のためだけではなく宗教的な儀式などに用いられることもあり、人形や仮面のなかには部分的に可動するものもあります。これは、宗教上の事件を伝承する際、これを操作することにより、よりドラマチックに見せる効果などがあったのではないかといわれています。
つまり、機械的な仕掛けにより自動で動くという演出を付加することで、人形(ひとがた)信仰においてあたかも人形に魂が入っているかのように見せることができるわけです。
人形を作り、それが動く、動かすというテーマはユダヤ教のゴーレム(自分で動く泥人形)やギリシア神話のタロース(クレタ島を守っていた自動人形)の例にもみられ、古代の人々にとっては根源的なテーマでもあり、また創造主としての神への挑戦といった面もあったようです。
こうした自動人形は、単に人形の稼動部分を人間が直接動かすという段階を経た後、古代ギリシアにおいてより洗練されるようになり、その技術はその後のアルキメデスの螺旋、や同時期に発明されたといわれる歯車、サイフォン、水力、滑車などが発明されるきっかけにもなりました。
伊豆にも、伊東市の伊豆高原に、「野坂オートマタ美術館」というオートマタ専門の美術館があり、ここに18世紀から20世紀にかけてのオートマタが60体以上展示されているそうです。私もまだ中に入ったことはないのですが、実際にオートマタがどういう動きをするか説明つきでの実演が行われているといいますから、ご興味のある方は行ってみてください。
一方、「ドッペルゲンガー」というのはドイツ語で、自分とそっくりの姿をした分身のことを指し、または同じ人物が同時に複数の場所に姿を現す現象そのものを指す用語です。
自分がもうひとりの自分を見る現象であって、「自己像幻視」や「復体」とも訳されますが、ドイツ語の Doppelgängerを忠実に訳すと、「二重の歩く者」と言う意味だそうです。
自分の姿を第三者が違うところで見る、または、自分が異なった自分自身を見る現象であり、ドッペルゲンガー現象の特徴としては、ドッペルゲンガーとして現れる人物は周囲の人間と会話をせず、必ずその元の本人に関係のある場所だけに出現するのだそうです。
同じ人物が同時に複数の場所に姿を現す現象としては、このほかにも「バイロケーション」というのがあります。が、バイロケーションのほうは自分の意思でひき起こされる現象であり、「ドッペルゲンガー」のほうは本人の意思とは無関係におきるという点が違います。
“Bilocation”とは、意思によって一身二ヶ所存在を実現することであり、複所在、同時両所存在、バイロケーション現象ともいわれます。
また、遠隔透視(リモートビューイング)の際に意識が体を離れ、透視対象の傍にあるように感じられるという現象もバイロケーションといわれますが、ドッペルゲンガーと決定的に違うのは、バイロケーションの場合は本人の意思によって分身が図られるため、その分身と本人がじかに接触できる場合もあり、またはかなりの接近が起きうる点です。
その際、本人の間近でお互いに同じような行動をすることが多く、また、場合によっては、ドッペルゲンガーと違い、会話さえも可能であるといいます。ただ、ドッペルゲンガーもバイロケーションも、相手の身体は触ることができず皮膚が突き抜けてしまうといったことなどが特徴として挙げられます。
かつては、「自分のドッペルゲンガーを見ると、しばらくして死ぬ」などと語られることもあって恐れられた現象であり、これは今でも多くの国で信じられています。
超常現象といわれるもののひとつであるわけなのですが、あまりにも頻繁に起こってきたことから、近年では医学的な説明を試みようとした例もあるようです。が、これまでに発生したものの多くは科学によっては説明不能でした。
有名な人に起こったドッペルゲンガー現象の実例としては、アメリカ合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーンや、日本の芥川龍之介、帝政ロシアのエカテリーナ2世などがあり、この中の芥川龍之介の例は本人が自身のドッペルゲンガーを見たというものです。
またこれらより古い時代でも、古代の哲学者ピュタゴラスは、ある時の同じ日の同じ時刻にイタリア半島のメタポンティオンとクロトンの両所で大勢の人々に目撃されていたといいます。
さらに、19世紀のフランス人でエミリー・サジェという女性が経験した現象は、ドッペルゲンガーとしては最も有名で、この事例では同時に40人以上もの人々によってドッペルゲンガーが目撃されたといわれます。
江戸時代の日本でもドッペルゲンガー現象の記録は割とたくさん残っているようです。日本ではこれは、影の病い、影のわずらいと言われ、「離魂病」と称されていました。近年になってこれらの事例を集めて研究した人がおり、その著述「日本古文献の精神病学的考察」には、離魂病のある事例として次のようなことが記述されています。
北勇治という人が外から帰って来て、居間の戸を開くと、机に向かっている人がいました。自分の留守の間に誰だろう?と見ると、髪の結いよう、衣類、帯に至るまで、自分が常に着ているものと同じではありませんか。
自分の後姿を鏡を使わずに見た事はなかったのですが、その姿は自分と寸分違いないと思われたので、顔をよく見ようと近づいていったところ、その人物は向こうを向いたまま障子の細く開いた所から縁先に出て行ってしまいました。
あわてて後を追ったのですが、外に出るともうその姿は見えません。おかしなこともあるものだと、家族にその話をすると、彼の母親はものもいわず、顔をひそめたといいます。
その後、勇治は病気となり、その年の内に死んでしまいました。実は勇治の祖父・父もともに、この「影の病」により亡くなっており、あまりにも忌しいことであったので、母や家来はその事を言えずにいたのでした。結果として、この家では3代ともこの影の病にて病没してしまったということです。
日本の文芸評論家で、日本文化や日本美術、中国美術の評論を多く書いた吉村貞司という人は、こうしたドッペルゲンガー現象は、古代の日本神話の中にもその名残が見られると主張しています。
その例として、「味耜高彦根命(アヂスキタカヒコネ)」をあげ、これは天若日子(アメノワカヒコ)という別の神様のドッペルゲンガーと見ていい、と彼は主張しています。
アヂスキタカヒコネというのは、農業の神、雷の神、不動産業の神として信仰されている古代の神様で、「古事記」にも登場してきます。
一方、アメノワカヒコは大国主の娘の下照姫命と結婚した神様でしたが、葦原中国(天上の高天原に対する地上の国のこと)を得ようと企んでいたため、寝所で寝ていたところを矢で射ぬかれて死んでしまいました。
その夫はアメノワカヒコの夫人はシタテルヒメという女神でしたが、アメノワカヒコが死んでしまったので悲しみ、葬儀を行いました。その葬儀に訪れたのが彼女の父のアマツクニタマでした。
アマツクニタマが葬儀に訪れると、そこにはアヂスキタカヒコネも既に来ていましたが、その姿をみるとアメノワカヒコとそっくりであったため、アマツクニタマは、彼が生きていたものと勘違いしてアヂスキタカヒコネに抱きついてきました。
これに驚いたアヂスキタカヒコネは、穢わしい死人と一緒にするなと怒り、剣を抜いてアマツクニタマを蹴り飛ばしてしまった、というのがこの古事記の中の記述です。
このように、ドッペルゲンガーと近似する記述は古代から見られ、現在でもドッペルゲンガーと関連するものを見つけてきては比較研究する学者もいるといいます。
最近のテレビ番組でも新たな実例が紹介されることがあり、フジテレビ系列の「奇跡体験アンビリーバボー」でも海外のドッペルゲンガーの最近の事例を紹介したことがあります。これは母と娘が同時にドッペルゲンガーを経験した例でした。ただ、上述のように死んでしまうということもなく、この二人は現象があった後も問題なく生きていたそうです。
一方、医学においては、自分の姿を見る現象(症状)は「オートスコピー(autoscopy)」と呼んでおり、これは脳の側頭葉と頭頂葉の境界領域に脳腫瘍ができた患者が引き起こす症状であり、彼らの多くが自己像幻視を見るといいます。
この脳の領域は、ボディーイメージを司ると考えられており、機能が損なわれると、自己の肉体の認識上の感覚を失い、あたかも肉体とは別の「もう一人の自分」が存在するかのように錯覚することがあるのだそうです。
その昔放映された、テレビ番組「特命リサーチ200X」ではこのオートスコピーに関する特集が組まれました。
このときには、カナダ・マギル大学の医師がおこなった実験が紹介され、正常な人でもボディーイメージを司る脳の領域に刺激を与えると、肉体とは別の「もう一人の自分」が存在するように感じられることが確認されている、といった内容が放送されたそうです。
またドイツ・アーヘン大学の医者も、自己像幻視は脳腫瘍に限らず、偏頭痛が発生する原因となる脳内血流の変動によって、脳の一部の機能が低下することでも引き起こされうるとしているそうです。
前述のリンカーンや芥川龍之介も偏頭痛を患っていたそうで、このドイツ人医師は彼らがドッペルゲンガー現象として本人を目撃したとされる事例の多くはこの解釈でもってある程度説明しうる、という見解を示したそうです。つまり、芥川龍之介は脳腫瘍をかこっていたということになります。
しかし、ドッペルゲンガーには、上述の医学上の仮説や解釈で説明のつくものとつかないものがあり、「第三者によって目撃されるドッペルゲンガー」、たとえば数十名によって繰り返し目撃された上述のエミリー・サジェなどの事例は、脳機能障害では説明できないケースのひとつです。
エミリー・サジェは、1800年代のフランス人で、幽体離脱またはドッペルゲンガー現象を起こしたといわれる人物です。1845年、当時32歳のサジェは、ラトビアのリヴォニアにある名門校に教師として赴任しましたが、まもなく生徒たちが「サジェ先生が2人いるように見える」と言い出しました。
教師たちは生徒の空想として取り合わなかったものの、10人以上の生徒がそう言い出したため、集団幻覚か、それとも本当にサジェが2人いるのかと判断しかねる事態になっていきました。
生徒たちの証言によれば、あるときサジェが黒板に字を書いていると分身が現れ、黒板に書く仕草をしていたといい、また別の日にはある生徒がサジェと並んで鏡の前に立つと、鏡にはサジェが2人映っており、この生徒は恐怖のあまり卒倒しました。
後には生徒たち以外の目撃者も現れるようになり、給仕の少女が、食事中のサジェのそばで分身が食事の仕草をしている光景を目の当たりにし、悲鳴を上げたといいます。
この分身はやがてサジェのそばのみならず、サジェから離れた場所でも目撃されるようになっていきます。あるときには、42人もの生徒が同時に分身を目撃する事件も発生しました。
ある日生徒たちのいる教室にサジェがおり、すぐ窓の外の花壇にもサジェがいるという現象も起きました。このときは勇気のある生徒が、どちらが本物のサジェか確かめようとしました。そして室内にいるほうのサジェに触れたところ、柔らかい布のようでまるで手ごたえがなかったといいます。
このとき、花壇にいるサジェはぼんやりとした様子だったといい、しばらくすると室内のサジェは消えてしまい、花壇のサジェは普段通り動き始めたため、花壇のほうがサジェ本人だとわかったといいます。
このような分身の事件は、1年以上にもわたって続いたといい、生徒たちの噂話に困惑した学校の理事たちは、サジェを問いただしましたが、サジェ自身にはまったく分身の自覚がありません。学校側同様に本人もこの現象に悩むばかりで一向に事態は改善しませんでした。
多くの生徒はこの分身の現象をむしろ面白がっていたものの、彼らの父兄は決してそうではなく、このような奇妙な教師のいない別の学校へ転校させる親が続出しました。サジェは教師としては優秀な人物でしたが、学校側としてはこの事態を看過できず、やむなくサジェを解雇することにしました。
その後もサジェの赴任先では同じことが起き、20回近くも職場を転々としたそうですが、そのあげく、とうとう赴任先がなくなったサジェは、義妹のもとへ身を寄せました。そこでも分身は現れ、子供たちが「おばさんが2人いる」と面白がっていたといいます。
前述の芥川龍之介は、その自らの短編「二つの手紙」にドッペルゲンガーのことを書いています。
大学教師の佐々木信一郎を名乗る男が、自身と妻のドッペルゲンガーを三度も目撃してしまい、その苦悩を語る警察署長宛ての二通の手紙が紹介される、という形式の短編です。
芥川龍之介自身がドッペルゲンガーを経験していたらしいとされる記録もあり、芥川はある座談会の場で、ドッペルゲンガーの経験があるかと問われると、「あります。私の二重人格は一度は帝劇に、一度は銀座に現れました」と答えたといいます。
錯覚か人違いではないか?との問いに対しては、「そういってもらえれば一番解決がつき易いですがね、なかなかそう言い切れない事があるのです」と述べたといいます。
このように、ドッペルゲンガー現象は、古くから事例は多く、ホフマンや芥川龍之介のようにこれを小説に取り込む試みはかなり多くみられるようです。
ちょっと前の、といっても40年以上も前ですが、「ウルトラQ」という特撮番組の第25話にも「悪魔ッ子リリー」という話があり、これは肉体を離れ、精神体が悪事をするという内容でした。
最近では、杉浦日向子の漫画作品「百物語」にも「死の予兆」を反映させて、なりすました人物を殺害して、周囲の人に知られずにすりかわるというキャラクターが出てきます。
このほか、近年の日本のサイエンス・フィクションやファンタジー小説などにもよく登場し、そこでは、不埒な目的のために、特定の人や生き物になりすます「シェイプシフター“shapeshifter”」なるものもあり、これもドッペルゲンガーの派生と考えることができるでしょう。
この変化妖怪については日本だけでなく、世界中、古今東西広くに分布しており、その正体とされるものは、幽霊であったり、悪魔であったりと地域によっていろいろです。近年では、遺伝子組み換えによって生まれたバイオモンスター、なんてのもあります。
このように、ドッペルゲンガーは、日本においては江戸時代以前では離魂病として恐れられてきましたが、現代では小説やゲームなどの創作物においてはもその存在が脈々と継承されているわけです。
こうした、ドッペルゲンガーは、体外離脱または幽体離脱の一種ではないかという人も多いようです。
芸人さんの「ザ・タッチ」などがネタとして有名になって幽体離脱ですが、これは自分の肉体から抜け出す感覚の体験のことです。
私自身は経験はありませんが、国籍・文化圏にかかわらずこのような感覚はよく見られるようです。根拠はよくわかりませんが、10人に1人程度は生涯に一度は経験はしているのではないかとする人もいるようです。
体外離脱の典型は、自分が肉体の外に「浮かんで」いる、あるいは自分の物理的な肉体を外から見るといったもののようです。ただし、「体外に引っぱり出される」感覚とともに体外離脱体験をする人もいれば、突然体外に出ている状態を体験をする人もおり、その形態はさまざまです。
また、これもよく言われることのようですが、幽体離脱をしているときには、かなり具体的なイメージを持つことができ、かつ明確な自我もあって、鮮明な五感等もあることが多いといいます。あまりにも五感が鮮明なため、体外離脱している事に気づかず、そのまま日常を過ごしてしまったという例もあるといいます。
ただ、体外離脱を体験する時間はさほど長くなく、分単位であることが多いといいますが、体験者の中には、主観的な感覚としては、実際の経過時間よりもはるかに長い時間を過ごしているように思われることを指摘する人もいます。
体外離脱が起こるのは、主に、何かしら危険に遭遇した時、臨死体験をしている最中、あるいは向精神性の薬物を使っている場合などに多いようですが、人によっては、平常時、ごく普通の睡眠中や明晰夢の最中にも起こるようです。
また、こういうときには、いわゆる「金縛り」が起きている場合が多いといいます。
一方では、自らの意思で体外離脱体験をコントロールできるとする人も多く、一部には訓練によって体外離脱体験を起こそうとする試みもなされています。この場合瞑想に近い方法がとられているようです。とくにヨーガの行者などは修行中に体外離脱を起こすことはよく知られています。
こうした体外離脱体験なども含んだ霊界との交わりを体系的にとりまとめようとした人達も昔から多く、近代ヨーロッパでは神智学、人智学といった「学問」が形成されており、その一方では「近代西洋儀式魔術」や「神秘学」に代表されるようなオカルティックなものもあり、さまざまです。
スピリチュアリズムを主張する人達の間では、こうした現象を異次元世界、霊界とコンタクトする為にあるスイッチと考えている人もおり、これを本格的に研究した人としてとくに有名なのがロバート・モンローという人です。
もうこの項もかなり長くなっているので、今日はこれ以上述べませんが、彼が設立したのがロバート・モンロー研究所であり、体外離脱能力者でもあったロバート・モンローは、ヘミシンクと呼ばれる音響技術を開発して、たびたびあちらの世界の人々と交信しています。
ヘミシンクとは左右耳から波長がわずかに異なる音を聞くと右脳と左脳の脳波が同調することであり、ヘッドフォンから聞こえてくる音と瞑想の誘導を使うことでバイロケーション型の体外離脱が達成されるしくみだといいます。
原理はバイノーラルビートという確固たる音響技術に基づいているそうで、この音響技術を使用し、適切な訓練をするとバイロケーション型の体外離脱を体験できるといいます。
これらのことについては、日本では坂本政道さんという人が第一人者といわれています。
東大理学部の物理学科を卒業後、カナダで電子工学の修士をとり、ソニーで半導体素子の開発にあたったほどの俊英ですが、その後アメリカの半導体素子メーカーに引き抜かれて半導体レーザーの研究をしている最中に、「変性意識状態」ということに興味を持つようになります。
やがて、モンロー研究所のヘミシンク技術というものがあることを知り、この技術を使って自らも体外離脱経験をするようになり、それらの体験をつづった「死後体験」と呼ばれる本などを多数出版するようになりました。
この人の話をし始めるとまた長くなりそうなのでやめますが、ウチのタエさんがファン?で、私よりも彼の多数の著書を読んでいるとだけ、今日は書いておきましょう。
さて、今日はクルミの話題に端を発して、なぜか幽体離脱の話にまで飛んできてしまいました。
ここまでの話を信じるか信じないかはご自由ですが、いつもいうように、この世は不思議なことで満ち溢れており、科学的に説明できないからといってすべて否定できるような、この世はそんな単純なものではありません。
救急救命医として大勢の生死の狭間にある患者を診てきた矢作直樹というお医者さんは、臨死体験で幽体離脱した患者の体験を聞いた結果、「見た」出来事と実際の出来事と一致するという事実があることから、幽体離脱は「脳内現象」とは言えないだろうといっています。
そして、「人には、見える部分と見えない部分がある」とも語り、この見える部分というのは、実際にわれわれが見たり触れたりすることができる肉体であり、一方では目には見えないが恐らく肉体よりも大きな何らかの存在があるのだろうとも語っています。
そして、それこそが霊体ともいえるものだろうとし、物質的神経の仕組みを解明しても根本的因果関係を説明しているとは言えず、その背後にある霊的エネルギー体によってそれらの説明ができる、といった意味のことをおっしゃっています。
私自身も元は技術者であり、こういった優れた科学者すらも認める世界があることに疑いの余地はなく、ドッペルゲンガー現象も幽体離脱も実際にある現象だと思います。
また、ヘミシンクについても大変興味があります。なので機会あれば、またこのブログの中でもそのことついて詳しく書いてみましょう。
あなたも幽体離脱してみませんか?