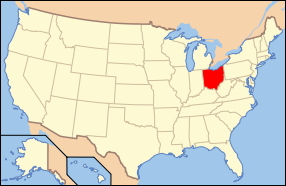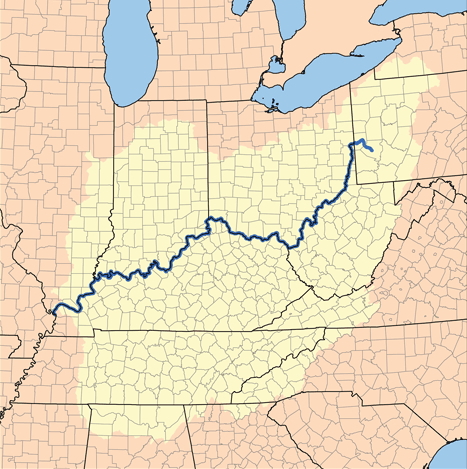結果は……というと、だいたい予想通りのところであり、この結果を受けた株価もあまり変動しなかったようですが、選挙前には「結果は折りこみ済みだから」というコメントをする経済アナリストが多かったそうです。
投票率が低いであろうことも予想通りでしたが、それにしてもこれほど低いとは予想しませんでした。その理由はといえば、おそらく誰もが、「だいたい予想がつくような結果になるような選挙に行ってもな~」という気分になったからでしょう。
選挙権があることは大事であり、国政に参加するということは義務だ、棄権するなどもってのほかだ、と有識者たちは声を揃えて言います。が、独走を続ける自民党を止めることのできるような元気な野党もなく、興味がわかないものはわかないのであって、選挙が始まる前から興ざめしている人も多かったのではないでしょうか。
私もそうした気持ちがないわけではなかったのですが、やはり義務は義務ということできちんと役割を果たそうと思い、行きました。投票に。が、できれば、さぼりたいという気持ちに弾みをつけるために、散歩に行く「ついで」、という理由で自分を納得させ、行ってきました。渋り渋り。しかも夕方近くになってから……。
で、どこに票を入れたかですが、これについてはお察しいただければと思います。が、こんな時期に自己防衛の目的のためだけに、国民の迷惑を省みずに選挙に打って出た自民党でないことだけは確かです。
とはいえ、これでようやく、落ち着いて年末年始の支度に入れる、という方も多いかと思います。私も同じで、選挙があるというので何かとそわそわしていた気分が落ち着き、滞っている諸事をこれから動かそうかな、という気になっています。
その最たるものは、やはり年賀状であったりするわけですが、いったいいつから年賀状を書いているかな~と記憶を辿ってみると、小学校の低学年のころからもうクラスメートと年賀状のやり取りをしていたような気がします。
学校の「図画」の時間に彫刻刀の使い方を教える、という名目で手彫りの年賀状を作ったのが最初のことだろうと推察できますが、何を彫ったか、どんな出来だったのかはもうほとんど記憶にありません。
その後、年賀状を出す相手が増えるにつけ、版画年賀状はかなり面倒だということに気付き、それからは市販のスタンプなどを使った年賀状になりました。さらにのちには、「プリントゴッコ」なるものも出て、こちらのほうがよりオリジナリティーが高いものができる、ということで、しばらく長い間はこれを使って年賀状を作っていました。
ご存知の方も多いと思いますが、これは、熱を与えると孔が空く特殊な用紙に、カーボンを含む特殊インクで描きたい図柄を書き、これにフラッシュランプをあてて加熱し、図柄の部分だけを溶かして印刷原稿を造るというものです。
これに白い年賀状を重ね、「ガリ版」の要領で印刷するわけですが、違う色柄の原稿を何枚も造れば、カラフルなデザインもできます。1970年代後半に発売された当初は、少ない枚数でも安価に自由なデザインのものができるというので、年賀状だけでなく、暑中見舞い、その他慶弔のハガキの作成などにも使われ、急激に普及していきました。
このプリントゴッコは1987年(昭和62年)に年間最多の72万台もの売上げを記録し、累計売上台数は日本を含めた全世界で1050万台にものぼったそうで、まさに世界的な「ごっこ」となりました。
しかし、その後一般家庭でもパソコンの普及が進み、と同時にインクジェットプリンターの高画質化、低価格化が進んだため、これに伴いパソコン上で動作する年賀状作成ソフトが普及していき、これに伴いプリントゴッコを使う人は減っていきました。
プリントごっこは、印刷所に頼むよりもずっと安価でデザイン性の高いものができるということで、人気を博したわけですが、しかしパソコンで作った年賀状のようにフルカラーでしかも画数の多い漢字を小さくきれいに印刷することはできず、またプリンターで印刷した紙のように速く乾かすことができません。
このため、プリントゴッコで印刷が終わった大量の年賀状を乾かす場所が必要であり、日本のように狭小住宅が多い国では、どこの家庭でもこれを乾かす場所を確保するのが大変であり、私もここへ引っ越してくる前は手狭なマンションであったため、そのスペースを空けるのが一苦労でした。
こうしたこともあり、その後さらにパソコンとインクジェットプリンターが急速に普及するとともに売り上げが減少し、販売元の理想科学工業は2008年(平成20年)6月末ついにプリントゴッコの本体の販売を終了しました。
その後も消耗品の販売は続けていたようですが、2年前の2012年(平成24年)12月でプリントゴッコの関連商品の全ての販売を終了し、これで完全にこの世の中から消えました。
しかし、40年以上にもわたる長い期間に国民の多くが使ってきたこのシステムには私も大変お世話になりました。将来文化遺産にしてもいいのでは、思うほどであり、それが無理ならば、せめて機械遺産にでもしてよ、と文科省にお願いしたいところです。
とはいえ、かく言う私も、十年ほど前から、年賀状はこのパソコンとインクジェットプリンターの組み合わせで作ることが多くなっています。最近はこれをデザインするソフトの性能もアップしており、かなりオリジナリティの高いものができるため、重宝しています。
しかし、かなり便利になったとはいえ、毎年夫婦合わせて200枚もの年賀状を刷るのは結構大変であり、またインク代もバカになりません。年賀状自体の購入価格も10000円を超えるわけであり、また今年からは消費税が上がっていて、これに400円を加えなくてはいけません。
400円くらい……とは思うのですが、400円あればかけそばの一杯も食えるわけですし、120円のマックバーガーなら3個も食べることができ、しかもおつりが来ます(腐った肉が入っているかもしれない商品にはあまり食指が動きませんが……)。
とはいえ、なかなかやめられないのがこの年賀状というものであり、なぜやめられないかといえば、それは年賀状をくれる相手というのは、長年のお付き合いのある人ばかりだからです。
長い間、しかも遠方にいて普段会うこともできないので、せめて年賀状の上だけでも、御挨拶したい、という日本人らしい細やかな気配りの気持ちから出ていることが多いでしょう。
この年賀状をやりとりするという風習が始まった時期ははっきりとはしないようですが、奈良時代ごろには既に、新年の年始回りという年始のあいさつをする行事がありました。
その後平安時代になると、貴族や公家にもその風習が広まりましたが、あいさつが行えないような遠方などの人への年始回りに代わるものとして文書による年始あいさつが行われるようになっていき、これが年賀状の起源のようです。が、無論この時代には、「ハガキ」などはなく、「書状」であり、年賀の本文は立派な包装紙に包まれていました。
さらにその後の武家社会においても文書による年始あいさつが一般化するようになり、江戸時代に入ってからは、非武家社会においても口頭の代用として簡易書簡を用いることが一般的になりました。そして、公的郵便手段である飛脚や使用人を使った私的手段により年始あいさつの文書が運ばれるようになっていきました。
が、江戸時代の年賀状も簡易的になったとはいえ、まだ「書状」であり、本文を和紙でくるんだものが一般的でした。明治維新後の1871年(明治4年)、郵便制度が確立したのちも、しばらくは、年賀状は書状で送ることがほとんどで、しかもその数は決して多くはなかったといいます。
しかし、1873年(明治6年)にできたばかりの逓信省が郵便はがきを発行するようになると、これによって年始のあいさつを簡潔に、しかも安価で書き送れるということで葉書で年賀状を送る習慣が急速に広まっていきました。そして、1887年(明治9年)頃には、国民の間で年賀状を出すことが年末年始の行事の1つとして定着しました。
かくして年賀状の枚数は毎年増え続けましたが、その後当分の間、これらの年賀はがきは「私製はがき」に普通の切手を貼ったものでした。その後もこうした私製ハガキの取扱量も増えていきましたが、現在の官製の年賀はがきの走りとなったのは、1935年(昭和10年)に私製ハガキの貼付用として発売された「年賀切手」でした。
この年賀切手はその後の時勢の悪化により1938年にいったん発行が中止されましたが、終戦後の1948年に復活し、この年から年賀切手の図柄が干支にちなんだ郷土玩具のものになりました。
そして、1949年(昭和24年)「、お年玉付郵便はがき」が官製の年賀はがきとして初めて発行され、大きな話題を呼び大ヒットしました。これを機に年賀状の取扱量は急激に伸びていき、こうして年賀はがきを年末に出すという「仕事」は毎年の国民の行事になっていきました。
しかし、それにしても、毎年のように苦労して大枚の数を書いて出すこの年賀状の相手の中には、もう何十年もお会いしておらず、実質、社会的なお付き合いは消散しているような方もいます。
が、それでもやめられないのは、そうしたかつてお世話になった人達の最近の動向や暮らしぶりを、年賀状を通じて知ることができるというメリットがあるからでしょう。
また、お付き合いはないけれども、完全に縁を切ってしまうのは忍び難い、というのは誰でも思う気持ちです。さらに、元気ならばいいのですが、病気になったりした人の様子などは年賀状でそれとなく知れたりもします。また年賀状の前に来る、喪中欠礼のハガキによって、その人のご家族の状況がわかり、相手の様子を推し計ることもできます。
時にはご本人が亡くなることもあり、私の家にも先日、高校時代の同級生の裳を告げるものもあり、大変驚きました。まだ若いのに……と夫婦でその早すぎる死を悼んだものですが、年賀状のやりとりを続けているということはこうした生死の情報をももたらしてくれるわけです。
しかし、昨今は、インターネットの普及によって、年賀状を出さない人が増えているそうで、デジタルネイティブ世代も次々と成人化していくこともあり、それにつれて年賀ハガキの需要は今後も減少し、発行枚数も減っていくと見積もられているようです。
日本の郵便行政における年賀ハガキの発行は戦後すぐの1949年からだそうで、その当時の発行枚数は1億8000万枚。以後枚数を漸増させながら、1964年には10億枚、1973年には20億枚に届きました。発行枚数のピークは2003年の44億5936万枚もありましたが、それ以降は多少の起伏を見せながらも枚数は少しずつ減少。
今年を含めた直近5年間は連続で前年比マイナス10%超を記録していて、現在発売中のハガキも前年比のマイナス10%を超えそうな勢いだということです。
その年に郵政省で扱った年賀状の総数を総人口で割った、「一人当たりが出す年賀状の数」も、ピーク時の2003年の平均枚数は約35枚だったものが、昨年の2013年では約25枚。10年で約10枚分減ったことになります。
無論この「総人口」には乳幼児や年賀状を出さない人も含まれているわけであり、年賀状を出す人の一人あたりの実態平均購入枚数は、もう少し上乗せされるはずです。が、それにしても、年賀状離れは加速していることは否めない事実のようです。
この傾向は年賀状を出す風習のない日本以外の海外諸国でも同じだそうです。海外では、年末年始に、「クリスマスカード」や、「グリーティングカード」と呼ばれるカードをクリスマスや新年などの年中行事に合わせて、友人や恋人など親しい人との間で交わします。意匠を凝らしたカラフルなカードで、通常、2つ折にして封筒に入れて郵送されます。
これが、近年はインターネットの発達によりやはり減ってきているということで、電子メールを利用したグリーティングカードに取って代わられる傾向が世界中で広まっているそうで、日本の年賀状もまたしかりです。年賀状をやめて、年末年始にグリーティングカードと称してメールを送る人は若い人を中心に急激に増えているようです。
デジタル媒体により作成され、電子メールにより取り交わされるため、紙を使用しないので、地球環境に優しいのが最大の特徴です。また、イラストや写真、アニメーションの追加や、一度にたくさんの人に送ることができるなど、年賀状にはない機能を備えており、その利用は広がっているといわれます。
スマホなどの携帯電話向けサービスも拡充されてきており、また、近年の電子グリーティングカードでは、ギフト券を兼ねているものもあり、挨拶状だけではなく、贈答品としての側面も見られるようになっているとのことです。
年賀状がこうした電子媒体に取って代わられる時代は早晩来るように思いますが、現在の「お年玉付き年賀はがき」もまた、「お年玉付き電子年賀はがき」のようなものになっていくのかもしれません。
しかし、「手書き」にこだわる人や、毛筆で年賀状を書く人、また自作・市販のゴム判だけでなく版画やイモ判の味は捨てられない、という人も多く、手作りの年賀状の味も捨てがたいものがあります。
こうした人に対して、今年からもう紙の年賀状はやめて電子メールにしますから、と宣言するのも忍び難く、まただいいち、こうした人に限ってパソコンやスマホが使えなかったりします。
かくして今年もまた、紙を使った年賀状を出すことになるわけでしょうが、その一苦労の時間を作りだすのがこの年末という時期には難しいもの。いっそのこと、年が明けてからにしようか、などと思っているところです。
年賀状を年末に出さなければならない、というのは、正月の三が日くらいまでにはそれを相手に届けたい、というところから来ているのでしょうが、その昔は年賀状といえば、年が改まってから書いていたようです。
ところが、明治時代以降、年賀状を出すことが国民の間に年末年始の行事の1つとして定着すると、その結果、年末年始にかけて郵便局には多くの人々が出した年賀状が集中し、郵便取扱量が何十倍にもなってしまいました。
この当時、郵便事業に携わる人の数は限られていたため、膨大な年賀状のために郵便物全体の処理が遅れ、それが年賀状以外の郵便物にも影響し通常より到着が遅れることがしばしば発生していました。しかも年末は商売上の締めの時期にも当たり、郵便の遅延が経済的障害ともなりかねない状況となっていきました。
その対策として1890年(明治23年)に年始の集配数を減らす対策が講じられましたが、それでも、さらに増え続ける年賀状にその対応だけではとても追いついていけませんでした。
また当時、郵便物は受付局と配達局で2つの消印が押されていました。このため年賀状を出す側の心理としては、受付局か配達局のどちらかで「1月1日」の消印を押してもらおうとする気持ちが強くなります。
片方だけならまだいいのですが、間違ってもその両方が、「12月31日」になるのは避けたいものであり、これだと「年賀」の意味が失われてしまうからです。
このため、多くの人が1月1日のスタンプが押されるタイミングを図って年賀状を出すようになり、この当時の配達日数は、3~5日であったことから、12月26から28日あたりと1月1日当日に年賀状を出す人が集中するようになりました。
そこで1899年(明治32年)、その対策として指定された郵便局での年賀郵便の特別取扱が始まりました。年末の一定時期、具体的には12月20から30日の間に指定された郵便局に持ち込めば、「1月1日」の消印で元日以降に配達するという仕組みであり、翌1900年には、このシステムは全国の主要都市の郵便局に拡大されました。
さらに1905年(明治38年)には、全国どこの郵便局でもこの年末の特別扱いが実施されるようになり、以後、年賀状といえば年末に投函するもの、ということがこの社会のルールになりました。
「年賀」とは本来、正月に口上するものであり、このため年賀状も元日に書いて投函するものだったはずですが、この特別取扱をきっかけに年末に投函し元日に配達するようになったわけであり、いわば1月1日に年賀状をどうしても届けたいと考える国民の大多数の意見に郵政省(当時の逓信省)の役人が答えたシステムというわけです。
しかし、考えてみれば、今の時代、別に1月1日に年賀状が届かなければならない、と考える理由はなく、上述のように、長年会っていない人の動向を知るためだけのものになっているのであれば、別に1月7日に届こうが、15日に届こうがいいわけです。
正月三が日に年賀状が届かない、といって文句を言ってくるひとはまず皆無のはずであり、むしろ、遅れて届いた年賀状のほうが着目され、あれっ?何かあったのかな、と文面を読んでくれる確率が高いように思います。
極論すれば、1月中に届けばいいのではないか、と私などは思うわけで、なので、今年からは昔ながらのように、年賀状は正月に書くようにする、というのもよいかもしれません。年が明ければ明けたで、いろいろ忙しいのでしょうが……
さて、かくして2014年の12月は一日、一日と減っていきます。みなさんはもう年賀状はお書きになったでしょうか?
まだ?それならば、来年に回しましょう。