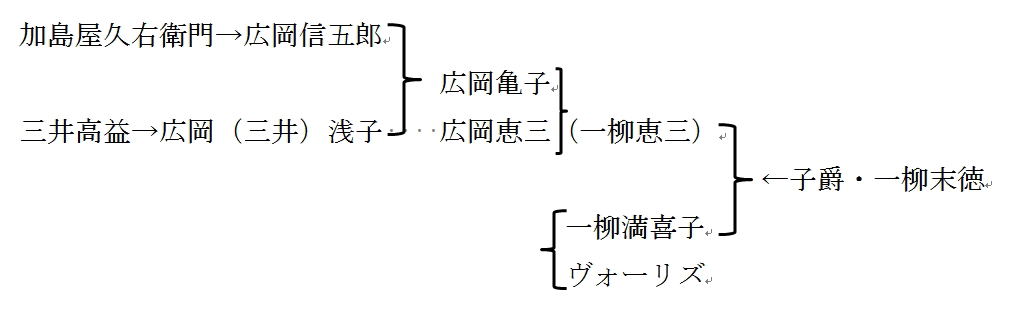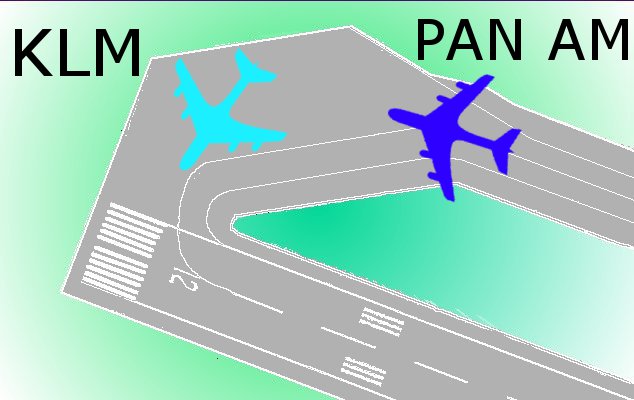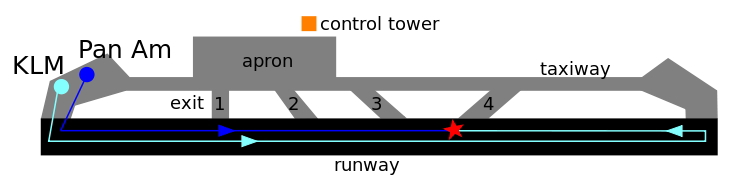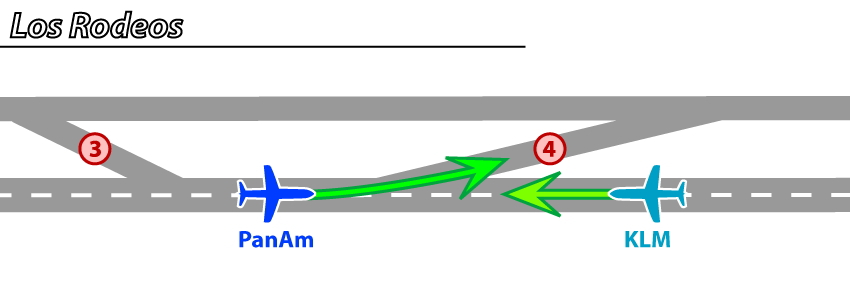今見ている歴史年表には、1776年9月7日、アメリカの潜水艇「タートル」がイギリスの戦列艦「イーグル」を攻撃した、とあります。
世界初の潜水艦と呼ばれるものは、これよりも156年前の1620年にイギリス海軍が開発したもので、櫂(かい)による人力推進という原始的なものだったうえに、実戦投入はされませんでした。
従って、戦争に用いられる戦闘艦、という意味では、事実上、このタートル(Turtle)なる潜水艦が、世界で初めての潜水艦と言ってよいでしょう。開発したのは、コネチカット州出身の、デヴィッド・ブッシュネルという人で、アメリカ独立戦争ごろに活躍した発明家です。
イェール大学在学中、火薬が水中でも爆発することを証明し、また、世界初の時限爆弾を作ったことでも知られています。1776年夏、その爆弾を使い、ニューヨーク港を封鎖していたイギリスの艦船の船体に穴を開けて爆弾を仕掛けようと考えましたが、その実行のために開発したのがこの潜水艦です。
現在2ドル札の裏面に使われている「アメリカ独立宣言「など歴史的場面を描いたことで有名な画家、ジョン・トランブルが、ジョージ・ワシントンにこのブッシュネルを推薦したと伝えられています。ワシントンは、このころまだ北軍の将軍でしたが、ご存知のとおり、のちの初代大統領です。
トランブルは、このころ、ブッシュネルの住むコネチカット州の知事を務めており、若き発明家としての彼の名声を聞き知っていたのでしょう。ワシントンは半信半疑ながらも、トランブルが勧めるまま、その「機械」の開発に資金と支援を提供しました。
ブッシュネルは提供された資金をもとに、全長2.4m、全高1.8m、全幅0.9mで、2枚の木製外殻にタールを塗り、鋼鉄製の帯で補強した潜水艇を完成させ、カメを思わせるその形状からこれを「タートル」と名付けました。
そして、この潜水艇を使って、イギリス軍の艦船に悟られないように近づき、船の船体に穴を開け、そこに59kgの火薬を詰めた樽を埋め込み、時限信管で爆発させることを想定しました。実戦に投入する前の試験は、兄弟エズラ・ブッシュネルがコネチカット川の水中で行ったとされます。
現代の潜水艦と基本原理は同じで、船底のタンクに水を引き込むことで潜水し、手動ポンプを回して排水することで浮上します。また、史上初めてスクリューで推進する方式を採用した船でもありました。さらに、91kgの鉛を装備しており、それを放つことで瞬間的に浮力を増すことができました。
ただ、哀しいかな、まだこの潜水艦もまた、動力は人力であり、しかも1人乗りでした。しかし、艇内の空気で約30分潜水でき、荒れていなければ1時間に5kmほど進むことができたといいます。
上部に6つの小さく分厚いガラス窓があり、そこからしか自然光が入ってきません。このため、ブッシュネルは艇内をもっと明るくしたいと考え、はじめロウソクを使おうと考えました。しかし、ロウソクに火が灯ると限られた酸素の消費が早まることがわかりました。
そこで、同じく発明家で科学者として名声を博していた、ベンジャミン・フランクリンに助けを求めました。ご存知のとおり、凧を用いた実験で、雷が電気であることを明らかにした人物です。
この実験はその後避雷針の発明に結びつきましたが、フランクリンはこのほかにも、フランクリンストーブとして知られる燃焼効率の良いストーブなども開発しており、この時代のいわばエネルギー工学のエキスパートでした。
ブッシュネルからの相談を受けると、早速対処方法を考えましたが、その結果として、羅針盤と測深計を生物発光の燐光で照らすアイデアを思いつきました。その光は夜間の照明としては十分でした。しかし、予想していたよりもかなり薄暗かったといい、これは、船体が海水で冷やされるため、発光生物の代謝が低く抑えられたからです。
とまれ、タートルは一応の完成を見たことから、実戦に投入されることになりました。このころのアメリカは、イギリスからの独立戦争の真っただ中であり、イギリス軍はニューヨーク占領のために大陸軍をロングアイランドの戦いで破り、マンハッタン島に後退した総司令官ワシントン率いる大陸軍を追ってイースト川を渡ろうとしていました。
イースト川に浮かぶイギリス海軍艦隊は多数におよび、大陸軍に激しい艦砲射撃を浴びせかけ、上陸点を守っていた経験の足りないアメリカ側民兵はこれにおののき、逃亡しました。キップス湾と呼ばれる湾の海側から抵抗もなく上陸に成功し、この作戦はイギリス軍の決定的な成功に終わりました。
このため、この戦いは後世で「キップス湾の戦い」と呼ばれています。この戦いのさなかの1776年9月7日夜、キップス湾での戦闘を支援するため、タートル潜水艇はマンハッタンの真南にあるガバナーズ島に係留されていたハウ将軍の旗艦イーグルを攻撃しました。
この新鋭艦の操縦者に選ばれたのは、一兵卒でしたが、大陸軍の中でも勇猛果敢な人物として知られていた、エズラ・リーという男でした。しかし、この作戦は、失敗でした。リーは、目標とするイーグルの船腹にまで到達することには成功しましたが、その胴体に穴をあけることができませんでした。
一説によれば、銅版で船体が覆われていたためにリーが船体に穴を開けられなかったのではないかとされています。が、薄い銅版にドリルで穴を開けられなかったはずはなく、おそらくは、リーがタートル号の操縦に不慣れであり、揺れる波中で、船体の1カ所に集中してドリルを回し続けられなかったのではないか、ということが言われています。
このイーグルが停泊していたガバナーズ島近辺というのは、ハドソン川とイースト川が合流する位置にあり、流れが強く複雑です。このため、タートル号がこの場所に係留された船を攻撃できるとしたら、上げ潮と川の流れが釣り合った短時間だけだったと考えられます。おそらくはその持ち時間の中で穴をあけられなかったのでしょう。
また、イーグルを攻撃するためには、タートル号は潮流を横切る形で同船に近づく必要があり、人力が推進装置であるこの船を操船するエズラ・リーは、イーグルに接近したころにはかなり疲れきっていたと考えられます。
さらに悪い事に、リーの乗るタートル号は、その退却時にイギリス側に発見されてしまいます。このためイギリス軍の兵士がボートで追いかけてきましたが、彼は咄嗟の判断で、火薬を詰めた樽を放ちました。これを見た、イギリス側は何かの計略ではないかとひるみ、その隙にリーはなんとか逃れることができたといいます。
しかし、この失敗にもめげず、リーは翌年の1777年、ふたたびタートル号に乗り、出撃しました。このときは、ナイアンティック湾に係留していたイギリスのフリゲート艦 HMS ケルベロスを浮遊機雷で攻撃しようとしました。今回の試みはある程度成功し、その爆発によって、同艦には数名の船員の死傷者がでました。
が、やはり船体に損傷を与えることはできませんでした。ただ、潜水艦として相手に攻撃を加えて成功した最初の例であり、その後世界中で運用されるようになるこの乗り物の歴史においては特筆すべきことでしょう。
その後、タートル号は、リー以外の搭乗員によって運用され、何度か出撃したようですが、最後は、ニュージャージー州フォートリーでイギリス側に発見され、沈められたと伝えられています。
ちなみにその後のリーは、独立戦争の緒戦のいくつかで戦いましたが、最後はニュージャージー州で戦われた、トレントンの戦いにおいて銃弾に倒れ、出身地のコネチカットにある、ダック墓地に埋葬されています。
数年後、この水没したタートルは、大陸軍によって回収されました。この事実はブッシュネルが、第3代アメリカ合衆国大統領トーマス・ジェファーソンへ宛てた手紙の中に記されているそうです。また、ブッシュネルはそれを解体し、おおまかな図面を残しました。
この図面を用い、1976年のアメリカ建国200周年においては、200周年記念事業として、このタートル号のレプリカが製作されました。コネチカット州知事、エラ・グラッソらによって進水式が行われ、コネチカット川で潜水試験も行われたそうです。
この複製品は現在、「コネチカットリバー博物館」に納められており、このほかにも地元の高校生が実動する複製を作ったものがあるそうです。
このタートル号が実戦投入されてから、以後およそ240年、潜水艦は目覚ましい発展を遂げました。耐圧構造の船体を持ち、潜航可能な軍艦は、現在でも潜水艦と呼ばれていますが、同様の構造の船でも、民間の海底探査船や水中遊覧用船などは潜水艇、潜水船などと呼ばれ、深海探査や救助用として別のかたちの発展を遂げました。
一方の軍用の潜水艦においては、その後同じアメリカでの南北戦争では、南軍が人力推進型の「ハンリー潜水艦」というものを開発しました。この船は、1864年に、サウスカロライナ州チャールストン港外で、同港を封鎖中の北軍木造蒸気帆船「フーサトニック」を外装水雷により撃沈しており、これは史上初となる潜水艇による敵艦撃沈記録でした。
また、同じ年、世界で初めて動力を使用した潜水艦が開発されました。フランス海軍の「プロンジュール」であり、これは12.5バールに加圧された圧縮空気をタンクに貯蔵し、これを利用するレシプロ式の空気エンジンで推進しました。80馬力を発揮し、4ノットの速度で5海里 (約9 km)航行できました。
最大潜行深度は10m、武装は衝角と電気発火式の外装水雷であり、さらに12人の乗員が脱出できるように、8×1mのサイズの小さな救命艇が装備されるという本格的なものでした。実戦には投入されませんでしたが、1867年のパリ万国博覧会にプロンジュールの模型が展示され、それを見たジュール・ヴェルヌが書いたのが有名なSF「海底二万里」です。
次いで、1867年には、スペインの技術者、ナルシス・ムントリオルがスペイン海軍の援助を受けて、潜水艦「イクティネオII」を非大気依存推進させることに世界で初めて成功しました。
非大気依存推進とは、ディーゼル機関などの内燃機関の作動に必要な大気中の酸素を取り込むために、浮上もしくはシュノーケル航走をせずに潜水艦を潜航させることを可能にする技術の総称です。ただし、いわゆる原子力潜水艦などの核動力を含まず、蓄電池や化学反応などによって内燃機関を補助・補完する技術を指します。
「イクティネオII」では、2基のエンジンを搭載していました。水上航行用の1基目は従来通りに石炭を使用しましたが、水中航行用の2基目は燃焼ではなく亜鉛53%・二酸化マンガン16%・塩素酸カリウム31%を混合させた化学燃料棒を化学反応させる事で、エンジンを回しました。これにより必要熱とともに、副産物として酸素も発生できました。
このエンジンの仕組みを調べてみましたが、よくわかりません。おそらくは化学反応で発生した熱で水を熱して気化させ、蒸気エンジンとしたものだと思われます。なお、酸素が発生することから、これにより乗組員の生命維持機能を持たせることもでき、20人もの搭乗員を乗せて、8時間以上も潜航航行できたといいます。
しかし、化学反応によって得られる程度の熱では、十分な推力は得られなかったとみえ、このため水中での推進力は、昔ながらの人力が併用されていました。それゆえ、水中での最大速力はわずか、2ノット(時速3.7km)でした。
とはいえ、いまから150年ほども前のこの時代に、世界に先駆けて非大気依存推進させることに成功したということは偉業といえます。1867年といえば、日本ではこの年、ようやく大政奉還が実現した年です。このため、実用的な潜水艦を発明したのはアメリカですが、本格的な潜水艦を世界に先駆けて発明したのはスペイン、とはよく言われることです。
その後、1888年には、フランス海軍が世界最初の電気推進の潜水艦「ジムノート(Gymnote)」を開発し、非大気依存推進の潜水艦の開発はさらに加速しました。
さらに、1900年になって、近代潜水艦の父と呼ばれた、スコットランド出身でのちにアメリカに帰化した造船技師、ジョン・フィリップ・ホランドによって設計された潜水艦「ホーランド号(水中排水量74t)」は、最初の近代的潜水艦として評価の高いものでした。
主機のガソリンエンジンと電動機の直結方式(ハイブリット)であり、内燃機関によって推進する近代潜水艦の元祖として知られます。また、「ホランド級潜水」として、アメリカのみならず、カナダ、イギリス、イタリア、オーストリア=ハンガリー帝国、オランダ、ノルウェー、ロシア帝国、そして日本までもがその模倣船を造りました。
ちなみに、この当時の大日本帝国海軍にとっては、初めての潜水艦がこのホランド級でした。アメリカで製造されたバラバラの部品を日本に輸送して完成させるという、いわゆるノックダウン方式で組み立てられ、「第一型潜水艦」とよばれ、都合5隻が建造されました。
純国産とされるものは、その2年後の1906年に起工されたもので、六隻目なので、「第六型潜水艦」と呼ばれました。アメリカから製造権を購入して建造されたもので、ホランドの設計に基づき、川崎造船所で2隻が建造されました。
コピーながら日本で初めての潜水艦建造でしたが、船体はホランド型よりも小型となっています。日露戦争には間に合いませんでしたが、第一次世界大戦後まで、主に練習艦として運用が継続されており、優秀な艦でした。
ちなみに、その後大日本帝国海軍は潜水艦を艦隊決戦における敵艦隊攻撃用に投入することを意図し、大型の「大海型潜水艦」と「巡洋潜水艦」の二系列を中心に建造しました。巡洋潜水艦は水上機を搭載したのが特徴で、航続力と索敵力に優れた偵察型でした。対して海大型は、水上速力と雷撃力に優れた攻撃型でした。
しかし太平洋戦争では、開戦前に想定されていた艦隊決戦は起こらず、目立った活躍はありませんでした。インド洋での通商破壊や、南方への輸送任務などに投入されましたが、米海軍艦艇の優秀な対潜兵器の前に多くが撃沈されていきました。
その日本と同盟国であったドイツは、第一次大戦期から開発していたUボートで世界の海を席巻し、これは名作とうたわれました。
第一次大戦では約300隻が建造され、商船約5,300隻を撃沈する戦果を上げました。また、第二次大戦では、1,131隻が建造され、終戦までに商船約3,000隻、空母2隻、戦艦2隻を撃沈する戦果をあげました。しかし、その引き換えに849隻のUボートが失われました。
これに対し、連合国側のアメリカ海軍もドイツ同様、潜水艦を対日通商破壊に投入しました。高性能なレーダーやソナーなどにより、電子兵装の劣る日本艦船を次々と撃沈していきましたが、その活躍により日本商船隊は壊滅し、対日戦勝利に大きく貢献しました。
そのアメリカ海軍は、戦後10年を経て1955年に、世界初の原子力潜水艦、「ノーチラス」(排水量3,180t)を完成させました。原子炉と蒸気タービンを採用した、史上初の潜水艦であり、水中速力20ノットを誇り、潜航可能時間はなんと3ヶ月と驚異的なものでした。
この原子力主機登場により、その後、潜水艦の水中速力と水中航続力は大きく増大するとともに、戦闘能力も飛躍的な向上を遂げました。原子力潜水艦が大型水上艦艇を撃沈した例は、1982年のフォークランド紛争時に、イギリス海軍の「コンカラー」がアルゼンチン海軍の巡洋艦「ヘネラル・ベルグラーノ」を雷撃によって撃沈した事例が最初です。
「コンカラー」は「ヘネラル・ベルグラーノ」を24時間以上つけ回しましたが、全く気付かれなかったといい、この戦いにより、それまで水上艦に対し圧倒的に不利と思われていた原潜の有効性が証明されました。
世界初の原子力潜水艦ノーチラスの就航はまた、潜水艦の種類の分化にも寄与しました。とくに核を搭載する潜水艦は、米ソ冷戦時代に著しく進化し、弾道ミサイル潜水艦や巡航ミサイル潜水艦は、時代の花形となりました。
これらのほとんどは、原子力潜水艦です。長期間、敵国領海深くに潜み、いざとなれば核を放って相手の息を止める、というこの潜水艦建造技術は、アメリカのお家芸ともいえるものであり、ソ連がその技術を追いかけました。が、現在では米露以外でも、イギリス、フランス、中国、インドがそれぞれ建造に成功し、実戦配備しています。
そのほか、原子力潜水艦を保有しない国では攻撃型潜水艦、沿岸型潜水艦などが造られるようになりました。
沿岸型潜水艦というのは、哨戒型潜水艦とも呼ばれるものです。小型で航続力に乏しく、自国周辺海域での哨戒任務に使用されます。第二次大戦時までは、中型・小型の沿岸型潜水艦が多数建造されました。
しかし対潜兵器の進化した現代では、大洋の真っただ中である、「公海」で作戦行動するのは浅航行を必要としない原子力潜水艦が主力となり、これらの沿岸型潜水艦はなりをひそめました。
ただ、冷戦終結後にはソ連海軍を引き継いだロシア海軍の潜水艦部隊は財政状況が悪化し著しく不活発となったため、米海軍における原潜についても、従来の敵潜水艦や敵水上艦艇への攻撃及び味方機動空母の護衛のような任務は大幅に軽減されるようになりました。
しかしながら、冷戦終結と入れ替わり世界では地域紛争が頻発するようになり、アメリカの攻撃型原潜には別な任務が求められるようになりました。巡航ミサイルを装備するようになり、これを艦首の垂直発射システムから水中発射し、敵の重要目標へ対地攻撃します。
また、敵対国の沿岸に隠密に侵入して、偵察や情報収集活動を行ったり特殊部隊の投入や回収を行うことが可能な艦内構造に変化し、さらに敵潜水艦の発見追尾などの任務も担うようになりました。現在では索敵が原子力潜水艦の一番の任務であるといえます。
このため、仮に通常動力型の潜水艦が外洋で作戦行動をしても、こうした原子力潜水艦に容易に位置を察知され「無力化」されてしまいます。それゆえ、基本的に通常潜水艦は自国近海での哨戒任務にしか使用できず、このため、その多くは「沿岸哨戒型潜水艦」と呼ばれることも多くなっています。
しかし、沿岸といっても、自国の海岸線から200海里(370.4km)の範囲内である、排他的経済水域などのやや広い範囲で活動する潜水艦は、「攻撃型潜水艦」と呼ばれます。魚雷や機雷などを主兵装とし、領海に侵入してきた敵の水上艦艇や潜水艦などの攻撃を任務とする潜水艦です。略称は、米英海軍および海上自衛隊ではSSと呼ばれます。
一方、原子力推進式のものも攻撃型潜水艦といえますが、この場合は核動力 (Nuclear) を表すNを付けてSSNになります。しかし、一般的に原子力推進のものは「攻撃型原子力潜水艦」と呼び、それ以外の推進力を持つ潜水艦は、単に「攻撃型潜水艦」と呼ぶようです。
かつての非原子力型の攻撃型潜水艦は、水上艦艇に比べ最高速力や防御力、電子装備、水中航続距離などの基本的能力が劣り、巡洋艦や駆逐艦とまともに戦闘するためには少々非力でした。このため、主に待ち伏せ攻撃、港湾での情報収集、特殊部隊投入、物資輸送、通商破壊などの対貨客船任務、などの任務に投入されました。
しかし第二次大戦以降、魚雷やソナー、各種電子機器、通信装置の性能が向上し、さらに原子力潜水艦で培われた技術を流用することでその攻撃性は画期的に向上し、現在では強力な戦闘力を持つ最強の軍艦として、かつての戦艦に匹敵する地位を獲得しました。
また、攻撃型潜水艦は敵水上艦船だけでなく敵潜水艦も攻撃目標とするようになりました。隠密性の高い潜水艦を探知し攻撃するのは、やはり同じ潜水艦のほうが有利だからであり、このため敵の戦略ミサイル潜水艦を攻撃する任務や、自国の艦隊を敵の攻撃型潜水艦から護衛する任務を与えられるようにもなりました。
このため、上述のとおり、日本が保有している潜水艦は、「沿岸哨戒型潜水艦」ともいえるわけですが、外洋に出て敵を威嚇または攻撃できる十分な能力持っていることから、「攻撃型潜水艦」といっていいでしょう。自民党はこの呼び方を嫌がるでしょうが。
日本では、海上自衛隊自衛艦隊に所属する、「潜水艦隊」を保有しており、潜水艦隊の司令部は神奈川県横須賀市に置かれています。ここをヘッドとして、呉基地の第1潜水隊群、横須賀基地の第2潜水隊群が主力です。このほか、潜水艦教育訓練隊、第1潜水訓練練習隊、横須賀潜水艦教育訓練分遣隊があります。
潜水艦隊には、現在、16隻の作戦用潜水艦、2隻の訓練用潜水艦の計18隻の潜水艦があります。呉市にある第1潜水隊群が10隻、横須賀市の第2潜水隊群が8隻を保有しています。
第1と第2潜水隊群は、もともと並列で運用されていました。が、それでは有事に指揮系統がバラバラになりかねないとの危惧があり、昭和55年の法律改定により、潜水艦群の作戦運用は、横須賀の本部で一元化され、「潜水艦隊」として統一されることになりました。
これら一連の潜水艦群の中でも最新型のものは、「そうりゅう型潜水艦」です。海上自衛隊初の非大気依存推進(AIP)潜水艦であり、13中期防の4年度目にあたる平成16年度(2004年度)予算より取得を開始した潜水艦(SS)であることから、16SSとも呼ばれています。
最近、ニュースでオーストラリア海軍への技術供与が可能かどうか、が話題になっているのはこの艦です。
オーストラリアは、世界一のウラン埋蔵量を持っており、世界有数のウラン輸出国ですが、国内に原子力発電所はひとつもありません。放射性廃棄物の処分に有効な手立てがないことなどを理由に、国民の多くが原発に対してノーといっているためです。
また、火力発電の燃料でもある石炭も世界有数の埋蔵量を誇ることから、エネルギー安全保障の観点から原子力政策を打ち出すことが困難な状況です。そうしたこともあって、原子力潜水艦についても根強い反対意見があり、オーストリア海軍は、コリンズ級という潜水艦を6隻ほど持っていますが、すべて通常動力型潜水艦です。
ただ、このコリンズ級潜水艦は、ほとんどが1996~2003年に建造されたもので、少々老朽化しており、加えて、最近中国海軍のアジアにおける活動の活発化を鑑みて、コリンズ級潜水艦の代替として4,000トンクラスの大型潜水艦の導入を計画するようになりました。
ドイツの216型潜水艦の他にスペイン、フランスの潜水艦の調査が行われていましたが、2011年に日本が武器輸出三原則政策を緩和したため、そうりゅう型も検討対象に加えられた、というわけです。
ただ、オーストラリアのアボット政権は、公約で次期潜水艦を国内で建造すると表明しており、そうりゅう型の完成型を輸入することは、この公約に反することになります。このため、オーストラリア内で反発が強まる恐れがあり、また、日本政府にも、機密性の高い潜水艦を他国に輸出することに慎重論があります。
しかし、アボット首相は国内での潜水艦の建造が国内経済へ与える効果については懐疑的であるともいわれ、あくまで軍事的な観点から判断するとしています。なお、日本の潜水艦は、インドも高い関心を持っており、その他の国からも高い評価を得ていることから、HⅡロケットと同様に、潜水艦技術を輸出する時代が来るかもしれません。
原子力潜水艦より劣るのでは、というのが一般的な見方ですが、原子力潜水艦の欠点は、電動機推進時(エンジンは停止)のディーゼル・エレクトリック方式の潜水艦に比べ、静粛性が劣ることです。原子力機関では、高速回転する蒸気タービンの軸出力で低回転のスクリューを回すため、ギヤで減速装置を回しますが、これが大きな騒音発生源となります。
これは沿岸に潜んで敵を待ち伏せる、という目的のためにはネックとなります。オーストラリア海軍もまた日本と同じように、公海にまで出て他国潜水艦を探査したり、攻撃を加えるような必要性はあまりないため、従来型の通常動力潜水艦で十分、というわけです。
こうしたことを受け、昨年の2014年10月には、オーストラリアのジョンストン国防相が、江渡聡徳防衛大臣との会談で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に要請しました。まだ、実際に技術供与が行われるかは五分五分のようですが、中国の海洋進出が進む西太平洋の現在の状況をみると、可能性はあるのではないでしょうか。
この「そうりゅう」の能力ですが、高速力を発揮する際には、従来通りのディーゼル・エレクトリック方式が用いられますが、哨戒や索敵、あるいは情報収集といった静粛行動の際には、「スターリングAIPシステム」という特殊なエンジンを駆動します。
いわゆる「スターリングエンジン」というヤツで、非常に複雑なシステムです。が、熱効率が高く排ガスを出さず、かつ静粛性が高いのが特徴です。ただ、出力が低いので低速(4~5ノット=7.4~9.3km/h)です。が、航続性能は著しく高く、詳細データは公表されていませんが、このエンジンで電気を作り、3週間程度の水中行動ができるといわれています。
また、最高潜航深度は5~600mとも700mを超えるとも言われており、いずれにせよ潜航能力に関しては間違いなく、世界トップクラスのようです。アメリカもこの深度を潜れる原潜を数隻持っていますが、試験段階のようで、量産型原潜の潜航深度は4~500m程度にすぎません。
また、自衛隊に実戦配備されている89式長魚雷という「深深度魚雷」は、静粛性を重視し、長距離航走を可能としています。速度は55ノット(約100㎞/h)と劣るものの、射程は約40㎞と通常魚雷の約4倍、特筆すべきは最大潜航深度900mでも発射できることです。
もっとも、魚雷を射出するためにはその深度まで潜らなければなりませんが、実際そこまで潜航できるかどうかは、日本だけでなく、各国とも最高位の軍事機密です。
一方、アメリカでは、Mk50魚雷と呼ばれる深深度魚雷が最高深度を持っているようですが、それでも580メートルにすぎず、かつ高価です。加えてアメリカは近年、深深度に潜行する潜水艦よりも、浅深度における潜水艦を主要な脅威とみなすようになり、こうした高価・複雑な深深度向け魚雷の採用には積極的ではありません。
敵を攻撃するためには、ミサイルのほうが有利と考えているのもその理由のようです。ミサイル発射の時は安全深度まで浮上しなければならず、さもなければ射出時に不具合が起きたり、射出できても水圧により圧壊の可能性があるそうです。
従って、アメリカの原潜の多くは、潜航深度4~500mといわれており、原潜本体においても、近年ではこれより深く潜れるものは税金の無駄遣いとして敬遠されているようです。こうしたことから、アメリカが潜水艦に求める性能は、浅い海を長く潜れて広い範囲を行動でき、かつ高い攻撃能力を持つこと、ということになります。
これに対して、日本の攻撃型原潜に求められるのは、深い海をそこそこの時間潜航できて、かつできるだけ敵に悟られないように相手を追い詰めて仕留める、という点であり、このため「深さ」という点においてこだわりがあるようです。従って、この点については、そうりゅう型は世界のトップクラス、といえそうです。
さらには、情報処理システムも最高レベルのものが導入されています。これこそトップシークレットのようなので、詳しくはわかりませんが(私に詳細な知識がないこともありますが)、武器管制システムおよび魚雷発射指揮システムは、二重の光ファイバーによるLANによって構築されています。
そして、これらのネットワーク化システムによって生成された情報を意思決定に反映するためのインタフェースも充実しています。例えば、センサー情報や航海情報などの情報表示装置なども迅速性、広域性が確保されているといいます。
さらに、他の艦とのネットワーク構築も進んでおり、そうりゅう型の7番艦で最新鋭の「じんりゅう」からは新たなXバンド衛星通信装置が装備されたようです。
Xバンド通信は8GHz以上の高周波数帯域を使う通信のことで、携帯電話通信や地上デジタル放送などよりもはるかに高い周波数で通信するため、従来の衛星通信と比較して、気象などの影響を受けにくい、高速・安定通信が可能である、といった特徴があります。
ただ、聞きかじった範囲では、潜水艦の耳ともいえるソナーシステムについては、基本的にはアメリカ海軍の開発した技術を模倣している、といった状況のようです。世界最高レベルではあるものの、能力的に以前のものからさほど進歩していないようであり、将来へ向けての新技術への挑戦が必要、といったことが取沙汰されているようです。
とはいえ、かつての造船大国日本として培った最高の技術が蓄積された潜水艦であり、それをオーストラリアのような他国に売っていいかどうか、という議論はまだまだ続きそうです。
なお、最新鋭艦のじんりゅうの建造費は545億8千万円だそうです。先日公表された新国立競技場の建設費用が、1550億円ですから、これ一隻でその費用の3分の1が賄うことができます。
国威高揚のための国際大会も、国を守るための装備もどちらも大事です。が、1000兆円を超える借金でいまや国民1人あたりの負担額は830万円にもなっており、はたしてそんなムダ遣いばかりしていていいのか、と少々複雑です。
今の日本にとって、本当に必要なものに対する精査が必要になってきている時代のように思えます。