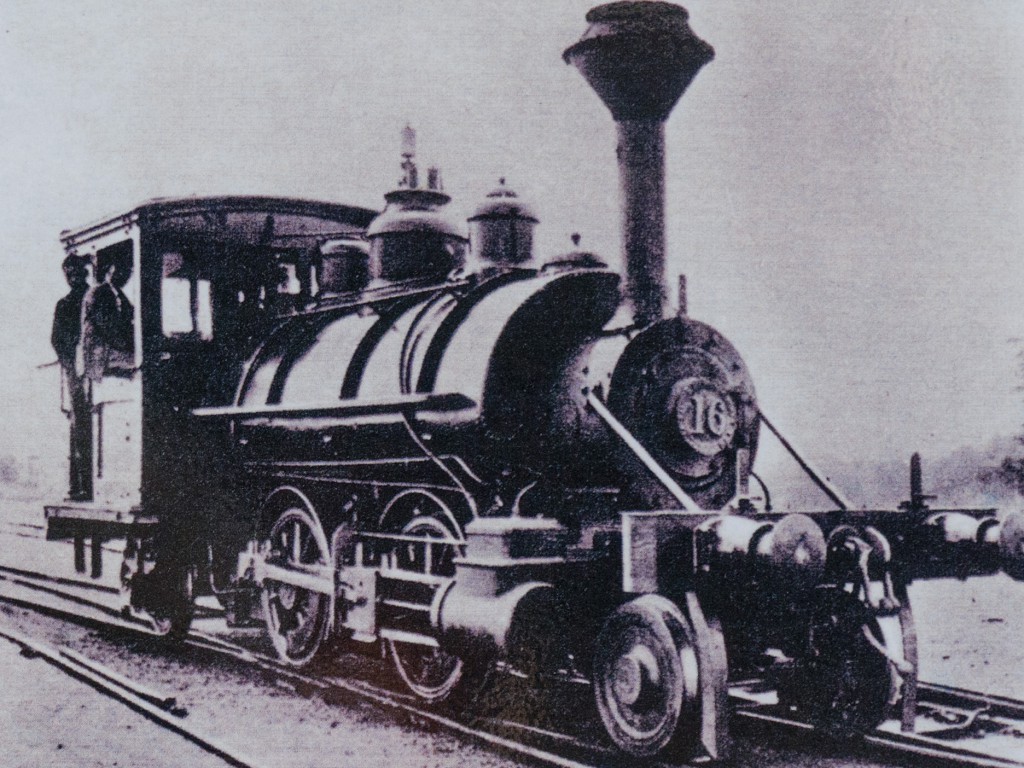最近、遠出をして帰る際、うちで料理するのは面倒なので、ふもとにある大仁の「回転寿司」などで外食をして帰ることも多くなりました。
メニューが豊富で安く、サラダなども一緒に注文すれば栄養価も満点で、何よりもおなかがすいているときなどには、入ってすぐに食べれるところが気に入っています。
伊豆へ来るまではあまりこういうお店へ行くこともなかったのですが、数か月前に久々にこういうお店に入りやみつきになってしまいましたが、また最近はずいぶんとシステムが近代化されているのには少々驚きました。
最近のこういうお店には目の前にメニューが表示されるタッチパネルが取り付けられていて、なかなか回ってこない寿司をここからダイレクトに注文できるのですね。
以前の回転寿司だと、目の前で握ってくれる職人さんがいて、この方に声をかけるか、注文伝票に記入して店員さんに渡すかすると、しばらくして「特注品」が出てくるというシステムのお店が多かったように思いますが、最近はこういうふうに合理化されているのかぁと妙に感心してしまいました。
寿司の皿の下にICチップが組み込まれているお店もあって、あまり長い間「回転」し続けているお皿があると、このICチップがそれを探知して、お店側に教えるのだとか。できるだけ新鮮なモノをお客さんにという発想からなのでしょうが、加えてお店側も今表に出ているネタの新しさを常に把握しておけるというわけで、すごいと思います。
寿司一皿を100円程度で提供しているお店も多く、こういう低価格を実現するためには各店とも人件費を減らすためにはいろんな試みを行っているようです。我々がよく行くようになったお店も、レジ係以外にはダイレクトオーダーの寿司を届けるウェイターさんが数人いるだけで、寿司職人さんの姿は見えません。
寿司を握る人は、店の裏の厨房にいて、この人たちも必ずしも本職の方ではなく、素人を採用してこれに実地教育をしたり、場合によってはアルバイト店員さんが「機械」で握っている場合もあるようです。
ワサビやおしぼり、水などもすべてセルフサービスで、寿司に欠かせないお茶でさえ、粉末状の「抹茶」らしきものがカウンターに置かれていて、これを湯呑に入れて薄めるだけ。このお茶、まずいのかなと思ったら、案外といけるのにはびっくりしました。
この回転寿司を一番最初に発明したのは誰だろう、と調べてみたところ、大阪で「立ち喰い寿司」のお店を経営していた「白石義明」という人のようです。低コストで効率的に立ち食い寿司を客に提供することを模索していたところ、ビール製造のベルトコンベアを応用することを思いつき、多数の客の注文を効率的にこなす「コンベヤ旋廻食事台」を考案しました。
そして、1958年、大阪府布施市(現・東大阪市)の近鉄布施駅北口に日本で最初の回転寿司店である「元禄寿司」を開設しました。この「コンベヤ旋廻食事台」は、1962年12月6日に「コンベヤ附調理食台」として白石義明の名義で実用新案登録(登録第579776号)されましたが、現在ではこの権利は切れ、各社が自由にこれを使うようになりました。
その新案登録が切れる前の1968年、宮城県の企業の「平禄寿司(現・ジー・テイスト)」が東日本ではじめて禄寿司の営業権契約を獲得し、仙台市に元禄寿司のフランチャイズ店を開店していますが、元禄寿司によると、これが「東日本で初めての回転寿司店」だったそうです。
私は全く覚えていないのですが、1970年に開催された日本万国博覧会にも元禄寿司が回転寿司を出展されていて、このときにはその斬新さが表彰されるほど評判だったそうで、これにより元禄寿司の知名度は一気に高まりました。
従来の寿司店の高級化傾向に対して、安くてお手軽、明朗会計というこのシステムは大いに世間に受けるようになり、元禄寿司は北関東を中心にフランチャイズ事業者を募り、郊外への出店を拡大していきました。その後1970年代以降、元禄寿司のフランチャイズは全国的に広まり最盛期には200店を超えたといいます。
しかし、1978年に「コンベヤ附調理食台」の権利が切れたため、現在のような大手の回転寿司屋の新規参入が相次いで競争が激化。また、もともと元禄寿司をネームバリューとしてフランチャイズ展開していた企業も、自前の店名ブランドを掲げて独立していくようになります。
ところが、元禄産業さんはさらに頭がよかった。実用新案の権利が切れるのを見越して、回転寿司のお店の名称として使われそうな「まわる」「廻る」「回転」などを商標登録していたのです。このため、後発の他店はその後しばらく「回転寿司」の名称を利用できないこととなり、この状態は1997年まで続きました。
現在はこの商標権も切れ、「回転寿司」という用語は普通に使われていますが、ひと昔前までは元禄寿司さんの専売特許だったのです。
ところで、この寿司皿を回転させているコンベアなのですが、造っているメーカーのほぼ100%が石川県にあるのだそうです。
金沢市の石野製作所というところがシェア約60%、同じ石川県の白山市の日本クレセントという会社が約40%だそうで、そもそもは、元禄寿司の創業者の白石氏がどちらかの会社に特注したものだったでしょう。そしてその後もその機能はどんどん進化しています。
1974年には石野製作所がコンベアの上に給湯器がつけた「自動給茶機能付きコンベア」を開発しました。グルグル回るコンベアのすぐ横に黒くへこんだゴム製の「ボタン」のようなものがあり、これに湯呑を押し付けるとお湯が給湯されるという、今ではどこの回転寿司屋さんでもみられるアレです。
このほか、注文した品が通常の寿司搬送とは別のコンベアで搬送される「特急(新幹線)レーン・スタッフレスコンベア」やこれと同じく湯呑が搬送される「湯呑搬送コンベア」、なども開発されました。
「鮮度管理システム」も開発され、これは前述のように皿の下にICチップが組み込まれていて、一定の時間を経過した皿が、コンベアから自動的に取り出されるシステムで、こうしたシステムを両社がしのぎをけずって今も開発し続けているそうです。
この両社が開発したのかどうかわかりませんが、使用済みの皿を効率的に回収できるように、カウンター内部に皿回収溝が流れている店もあります。
客席ごとに皿の投入口が設置され、皿を投入すると数が自動計算され価格が表示されるようになっており、とくに子供連れのお客さんなどに進んで投入してもらうために、投入した皿の数で自動的にキャラクター商品などの景品が当たる機能を付加したお店などもあるようです。
回転寿司のお店には、カウンター席が主流の対面型店舗と、これにボックス席を合わせた混合型店舗がありますが、そのどちらも皿を載せたコンベアは「時計回り」に回転するものが多いそうです。これはカウンター席で箸を持った右利きの人が取りやすいようにとの配慮によるものです。
ボックス席ではややとりにくい、ということになりますが、これは一緒に座っている人が他の人のためにとってあげる、ということで解決できます。また前後二列で左右両方から流れてくるコンベアを設置しているお店もあるそうで、こうした回転寿司店では内回り外回りの両方からとることができます。
コンベアのベルト長の日本最長は147mだそうで、日本最短は5mとのこと。最長は分かる気がしますが、最短の5mのシステムを導入するお店ってどんなお店なんでしょうか。必要ないように思いますが……
この回転寿司のシェアですが、日本国内では、埼玉県が本社の「かっぱ寿司」(カッパ・クリエイト)が全国392店を展開していて最大手になるようです(2012年7月現在)。これに次いで「スシロー」(あきんどスシロー・大阪)が334店、「無添くら寿司」(くらコーポレーション・大阪)が303店となっており、いずれも100円均一のお店が上位を競っています。
我々がよく行くのが、はま寿司(東京)で、こちらが168店で、上位三店に次いで4位に入っています。はま寿司も100円均一店ですが、平日は90円を売りにしており、この10%差のためか平日もいつもお客さんでいっぱいで、売上に大きく貢献しているようです。
この他の回転寿司チェーンは、価格設定が高めな店と100円均一店の両業態がしのぎを削っていますが、同じ会社であっても、高級路線と100円均一の店を両方を持っているところもあるみたいです。ちなみに、回転寿司発祥の「元禄寿司」は現在直営11店舗であり、健在ではあるものの、当初の勢いは無くなってしまっています。
いつの世にも企業の盛衰は激しいものです。
近年は高級ネタを売りにした回転寿司屋も出てきており、立地としては漁港や海沿いの都市・県庁所在地の一等地等に店舗を構え、近海で取れる魚や高級魚を売りにしたお店が多いようです。我々が先日行った、沼津港周辺にもこうした高級回転寿司店が軒を連ねていました。
それでは、海外にも回転寿司はあるのでしょうか。ウィキペディアによると、海外での回転寿司は1990年代末に、イギリスのロンドンで回転寿司に人気が集まったのが初めてのようです。
人気に拍車をかけたのは「Yo! Sushi」というチェーン店で、1997年にソーホーで開業し、その後、イギリス国内に次々と開店、1999年にパディントン駅構内のプラットホーム上に回転寿司屋を出店したことで注目を浴びました。
開業後大きな人気を呼び、創業者のサイモン・ウッドロフという人は、この成功によってイギリスの外食産業で大きな地位を獲得したそうです。この「Yo! Sushi」寿司の質についてはイギリスの新聞紙「週刊サンデータイムス」が「ロンドンで最高」と評価したこともあったそうです。
このロンドンのチェーン店では日本と同様に、商品の価格を皿の色で区別するシステムを採用しており、コンベアに並ぶのは寿司だけでなく、刺身、天ぷらや焼きうどん、カツカレー、日本酒まであるそうです。
どら焼きやケーキ、果物などのデザートなどの日本の回転寿司でおなじみの商品のほか、紅茶やパンなどもあり、あげくの果ては「唐辛子入り鶏ラーメン」「鶏の唐揚げ」「餃子」まであるそうで、ここまでくると回転寿司ではなく、まるで「回転居酒屋」です。
このチェーン店、現在、ロンドン市内のハーヴェイ・ニコルズやセルフリッジなどの高級デパート内、さらにヒースロー国際空港内など20ヶ所以上の店舗を展開しているそうで、さらにフランスや中東のドバイにも進出しており、2006年にも新店舗を開くと発表されています。
イギリス以外の国ではオーストラリアで「スシトレイン」という回転寿司屋がチェーン展開しているそうです。
アジアでは、台湾で、現地企業の争鮮(SUSHI EXPRESS)が、台湾および中国本土において回転寿司チェーンを展開しているほか、最近は韓国でも回転寿司店が増えてきているとのこと。
こうした海外の回転寿司チェーンは向こうの資本によるものがほとんどですが、日本のチェーンも、「元気寿司」などが同名でハワイやアジアに数十店舗を展開しているほか、「マリンポリス」という会社がアメリカ本土に「SUSHI LAND」の店名で十店舗以上を出店しているそうです。
寿司はローカロリーで、さっぱりしているため外国人でも受け入れやすいらしく、他の国でもこれからもまだまだ回転寿司の進出は続いていきそうです。
また、外国人だけでなく日本人にも人気の理由はなんといってもその「ネタ」の多さです。回転寿司では、本来寿司として使われない寿司種も多く、巻物では、キュウリなどを使った「かっぱ」のほか、べったら、しば漬、田舎漬、山ごぼう、梅しそ、納豆、穴キュウ(穴子+きゅうり)、カツ、エビフライなどがあります。
牛や豚のカルビ肉、チャーシュ、ローストビーフ、ハンバーグ、ベーコン、チキン照焼、えび天、いか天、ししゃも天などの、およそ寿司ネタとは考えられないようなものもあり、このほか、「太巻」ともなると、その中身には、ありとあらゆるものが詰め込まれています。
その他の副食として、味噌汁類やお吸い物類、あら汁などを提供する店も多く、酒のつまみとして、唐揚げ、フライなどのほか、煮物、お新香が出る店もあります。そば、うどん、ラーメンなどは、その昔は考えられませんでしたが、家族連れで出かける人も多いのでしょう、こうしたメニューがある店も増えています。
ゼリーやプリン、ケーキ、ジュース、果物といったデザートの種類も増えているのは子供だけでなく、女性客を狙ったものでしょう。
元々ファミリーレストランなどの外食産業の原価率は平均して30%程度なのだそうですが、一般的な回転寿司店でのそれは50%程度とかなり高めです。利益が出ないような高級魚が含まれている反面、高利潤を得るため代用魚が用いられることがあり、「えんがわ」「サーモン」などは、「ヒラメ」や「サケ」のことではない場合が多いそうです。
また、「チャネルキャットフィッシュ」というアメリカナマズの一種をマダイ・ヒラメ・スズキ・アイナメなどと称して並べている場合や、観賞魚として有名な「ティラピア」やマンボウを鯛とする場合もありました。
このほか、アフリカのナイル川の汽水域に生息する「ナイルパーチ」をスズキ、ロコガイをアワビとして代用していることなどもあり、これらは2003年にJAS法が改訂されて以来、こうした日本名を使用しないこととすると定められましたが、現在どの程度これが守られているかは定かではありません。
大手の寿司チェーンでは公正取引委員会の抜き打ち検査などもあるようですから、まさかこういうまがい物は使っていないとは思いますが、中小の回転寿司店ではグレーゾーンの商品を出しているところもあるのではないかと疑ってしまいます。
2005年の週刊誌記事によると、公正取引委員会は「回転寿司の場合“こんな安い値段で本物ができるはずがない”という認識を多くの消費者が持っている」として、排除命令などは出せないと回答したそうで、すると我々がいつも回転寿司で食べているものも、もしかしたら……なのかもしれません。
それでもおなか一杯になればいいや、と私などもついつい思ってしまいますが、やはりお寿司は本来の日本産のものを多少お金がかかっても食べたいもの。ましてや伊豆に住んでいるのですから、今度からは少しきちんとした寿司屋で食べるようにあらためようかな、とも思ったりもします。
もっとも懐が許せば……のお話です。不況のさなか、まだまだ100円回転寿司の進撃は続いていくことでしょう。悪いことだとは思いませんが、くれぐれも海外産のニセ寿司の食べ過ぎには注意しましょう。