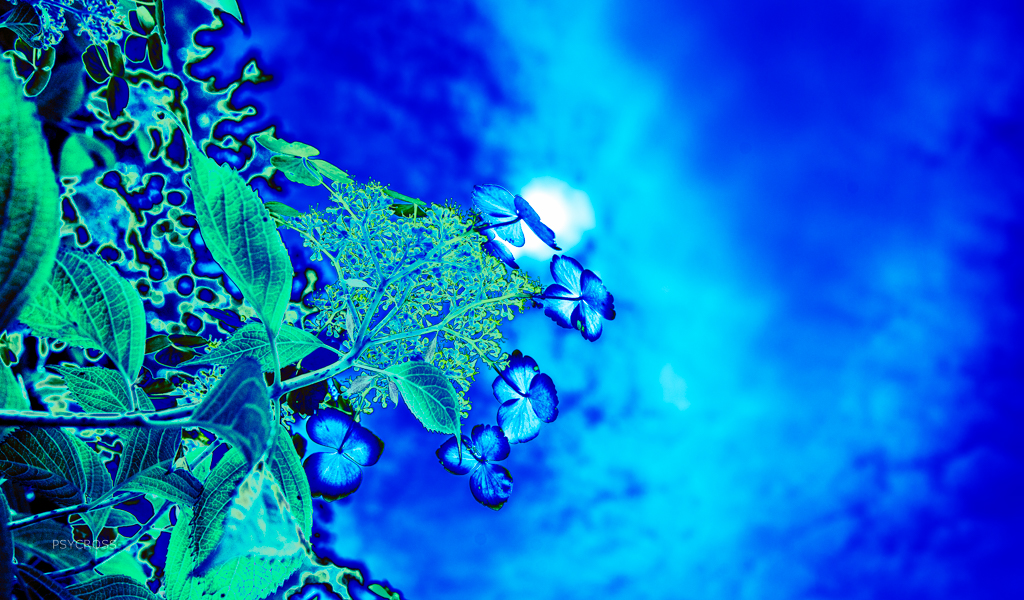夢の中のその場所は、雑然としている。
町の中心部のようだ。
なのに道行く人もまばらで閑散としている。
しかし、まるで活気がないか、というかとそうでもない。
すりガラスの向こう、時おりよぎる影。煙突から出ている煙が見えるほか、何かを煮ているような匂いがする。遠くから子供が泣いているような声も聞こえる。あちこちに生活の気配があるのだ。
すべてが計算されたものではないことは確かである。時間をかけて、自然にこののどかな環境はつくられてきたに違いない。
通りの向こう、交差点の左側にやや高い白っぽい建物が見える。病院のようだ。その上のほうの階に、明るい病室がある。広い部屋で、どうやら新生児室らしい。よく晴れていて、三方ある窓からは眩しいばかりの日差しが部屋に注ぎ込んでいる。
春の日の朝。桃の節句から何日か経ったころの光景─。
何人もの赤ん坊がいる。が、みんな静かに眠っている。その中、ひとりの若い女性が胸元に抱えこんだものを覗き込んでいる。微笑を浮かべて満足そうな顔。
小さなからだ。未熟児らしい。こんな貧相な子が、まともな人生を送れるのだろうか。
実際、その人生は波乱に満ちたものになるのだが、この人はそれをまだ知らない。齢はおよそ25か6。出産用の白い浴衣を着たその人こそが私の母だ。
時とところが変わって、また別の光景がみえる。
木造の官舎が軒を連ねている。さきほどの町から南へ数キロ先の山合の村にそれはある。退院した彼女は生まれたばかりの私を連れてその一角にある我が家に戻った。けっして広い家ではない。6畳間と4畳半の部屋がひとつずつ、小さな台所に風呂、トイレは共用だ。谷間にあるため、明るくもない。そこにこの夫婦が住むようになってもう3年になる。
私には姉がいる。5歳年上だが、このとき同じ長屋には住んでいない。母の実家に預けられており、のちに合流することになる。
父はいわゆるダム屋だ。といっても土木技術者ではなく、電気が専門である。満州で生まれ育ち、専門学校でその知識を得た。それがその後の彼の人生においてどれだけ役に立ったことか。本人が一番自覚しているだろう。
満州は言うまでもなく現在の中国である。広大なその大地の自然は島と山で構成される日本とはおよそ異なる。「大陸」というにふさわしく、どこまでも続く平坦で単調な環境はけっして人には優しくない。しかし、そこで生まれ育った、というのが彼にとってはその後の人生におけるひとつのステータスとなった。
と書くと、まるで満州生まれを自慢していたかのように聞こえるが、少し違うようだ。むしろそこに生まれたことに対して引け目のような気持ちを持っていたのではないか。
かつて清が領有していたこの地域を日本は侵略に近い形で手に入れた。しかし欧米に敗れてそれを失った。父の卑屈はそこに原因があるように思う。祖国が今は存在しない、というのは、何か自分の存在が否定されているように感じるものなのかもしれない。
国を失ったユダヤ人と同じだ。しかしユダヤ人はその後自分の国をもらった。そのため、今度はそこに住んでいたパレスチナの人々が居場所を失った。一度生まれ故郷を失った、という点で、両者と父は似ている。
自分の生まれた故郷に帰りたくても帰れない人々のことを難民という。同じく根無し草のように漂っているという感覚が父のその人生においても常にあったに違いない。
そのあたりの気分は人の生き方を窮屈にさせるものらしい。小学校しか出ていない、とよく自嘲気味に話していた。といっても、高等小学校と呼ばれるもので、今でいえば中学校だ。この当時は高等小学校を出ればもう働きに出るというのがあたりまえであり、商家であった父の実家ならなおさらのことである。
ともあれ、そうした出自のせいというべきか、彼の性格というべきなのか、その後の父の人生は実に控えめなものであった。出る釘は打たれる、と言わんばかりにおとなしく出しゃばらずに、ひたすらに自分の砦だけを守って生きていく、という生き方だった。
高等小学校卒業後の15~6歳のころ、満州電業という、日本の電力会社のような組織に入社した。会社組織ながら教育機関があり、そこで学ばせてもらってから職に就いた。いわゆる電気技師の卵だ。
数年現場でキャリアを積んだが、その前後で日中戦争が勃発。やがて太平洋戦争へと発展した。20歳になるかならないかの彼は、徴兵され満州北方へ送られる。
それまで一サラリーマンだった彼にとっての軍隊は厳しい世界だったに違いない。しごきの洗礼は当然あっただろうが、そこでの生活を、ときに面白おかしく話した。
「フケ飯」というものがある、とある日教えてくれた。これは、上官の白飯に自分のフケを入れ込む、というものだ。白いフケは、白飯の中ではほとんど見わけがつかない。しかしフケには下し作用があり、これを食した上司はたいてい、腹をこわす。
初年兵だった父を含めて下流の兵士たちは横暴な上司に反感を持っている。いつか仕返しをしてやりたいと日頃からうっぷんを溜めているが、さすがに刃傷沙汰はまずい。それなら、ばれない程度にお灸をすえてやろう、という仕返しのひとつがこれであり、当時の軍隊ではかなり横行していたらしい。
普段、下っ端の兵士は白飯など食えない。粟や稗、麦飯などが主食だ。兵隊は冷や飯、上官は据え膳、という世界であり、軍隊というものは階級社会の典型である。だが、強い者が弱いものをいじめる場合、たいていそこには大きな落とし穴がある。恨み嫉みの積み重ねがその穴を穿ち、仁徳のない人間はそこに落とされる。
安心して口にできるはずの食べ物に実は毒が盛られていた、といった類の話はクレオパトラの時代からある。かくして父の所属していた部隊でもそれが起きた。尻をかかえて厠に駆け込む上司を陰でみていた仕掛け人たちは、大笑いして溜飲を下げたという。
イジメに対する意趣返しのようなもので、ほほえましくもある。いたずら、というには少々度がすぎているが、日本人同士ならまだ許しあえる部分があるだろう。しかし、敵国人同士殺しあう戦争ともなるとそうもいかない。やがて父も悪夢のような争いに巻き込まれることになる。
初年兵としての父は、結局戦闘には参加しなかった。しかしこのころ、すでに本土は各地で空襲を受け、満州各地の拠点も連合国から攻撃を受けるようになっていた。そこへ新たに参入してきたのがソ連である。
満州北方各地から乱入してきたソ連軍は、父が所属していた部隊が展開する地域にも進出してきた。
ある日の朝、ついにソ連軍が父の起居する駐屯地を急襲した。のちの彼の手記によれば、部隊はそうした危険を感じ、列車に乗って移動しようとしていたようだ。このころすでに満州北部には十分な武器や物資は届かない。敵を迎え撃つ武器も少なく細長く伸びた無防備な車両の帯は、敵の恰好の餌食となった。
父はその列車の後方に乗っていたが、ソ連軍が襲ってきたとき、まず機銃の掃射を受けた。その車両には数人が乗っており、はっと気が付くと、すぐ隣に座っていた同僚が血しぶきをあげていた。銃撃によって眉間を撃ち抜かれ即死していたそうだ。
このままでは死ぬ、と咄嗟に判断した父は、すぐに列車を飛び下り脱出した。転がり落ちるようにして荒野を走り抜けた先で振り返ると、さっきまで乗っていた列車が側の砲撃を受けて粉みじんとなり、噴煙をあげていた。
命からがら脱出に成功した父だが次なる試練が待ち受けていた。やがて押し寄せてきたソ連軍に追いつかれ、捕虜となり、そのままシベリアへ送られた。いわゆるシベリア抑留で、彼はその酷寒の地で3年を過ごすことになる。
つらい3年だったに違いない。そのころのことを多くは語らなかったが、零下の日々が続く中での同僚の死や生活の厳しさを時に口にした。私が小学生の頃、時折当時のことを語ったが、息子に語って聞かせるというよりも、独り言のようにしか聞こえなかった。
そんな厳しい時期を経て、やがて春がやってくる。待ちに待った帰国だ。しかし舞鶴港に入った船から陸を見た彼は、「祖国」である満州とは全く違った光景を目にする。自然だけでない。道行く人々の風体や建物の形も彼が育った環境とは異なる。大陸育ちの彼にとっては異国そのものだ。
父の父─私の祖父は、もともと金沢の人である。若いころに満州で一旗揚げようと思い立って出国。彼の地でガラス屋を営んで成功した。父はその家の次男として生まれたが、幼いころ兄は亡くなり、そのあと生まれた彼が事実上の長男となった。
祖父の最初の妻、私の祖母は彼が10歳前後のころに亡くなった。が、その前に父のほかにもう一人男児を設けた。祖父にはこの弟のほか、その後再婚した相手との間にできた妹が一人おり、父の出征前の家族構成は三人兄妹と夫婦二人というものだ。
終戦の混乱が続く中、祖父一家は戦地に行ったままの長男の消息を知る由もない。自分たちにも危険が迫りつつあり、追われるようにして満州の地を後にする。苦労はしたようだが無事に満州を脱出。日本に着いてからは、郷里の金沢で親戚の家に寄宿するようになった。
一方の父は、シベリアで命を縮めたものの、なんとか五体満足で舞鶴まで帰還してきた。しかし行くべきところはない。本来帰るべき故郷はすでになく、初めて足を踏み入れることになる第二の故郷、金沢へと向かっていった。
舞鶴から金沢までは、その当時も北陸本線が通っている。しかし、戦後すぐの動乱期には鉄道のダイヤも乱れていたに違いない。帰国したばかりで十分な持ち合わせを持っていなかったであろう父は、もしかしたら徒歩で金沢まで向かったかもしれない。
地図で調べてみると舞鶴~金沢間はおよそ200kmもある。一日40km歩くとして5日はかかる工程だが、はたしてシベリアで体力を落とした父がそうした行為に出たかどうか。
復員兵にはいくばくかの手当が出た、という話も聞いたことがある。復員者用の無料乗車証となにがしかの現金を持って汽車に乗り、金沢へ向かったと考えるのが自然だろう。
とまれ、祖国を追われ、シベリア帰りの父は、ようやく先祖が代々住まう金沢にやってきた。奇跡的に空襲を免れ、今も江戸の面影を残す北陸屈指の都会だ。そこに江戸時代の末頃から「越中屋」の名で呉服商をしていた家がある。
明治の中ごろまではかなり裕福な商家だったようだ。戸籍に残っている住所から調べてみると往時は、かなり賑わった場所に店を開いていた。香林坊にも近く、現在もにぎわう町の中心部だ。曾祖父は市議会議員も務めており、調べたところかなり高額の税金を払っている。当時の金沢市への税金支払い額ランクでは上から2番目だ。
しかし、明治の末までには落ちぶれた。理由はよくわからないが、古い形に固執しすぎたに違いない。人絹などの新しい素材で作られた安価な衣服が流通していく中、昔ながらの木綿や絹などの品質にこだわったのだろう。それでは価格面で勝負にならない。
そのあげく大きな借金を抱えた。大きな屋敷は売り払われ、一家も奉公人も離散した。本家筋に近い親戚たちだけが、遠くへ行くでもなく、なんとなく、もとあった屋敷の界隈に安普請の家を借りて住まうようになった。
そのひとつの家に父も迎えられたが、親戚とはいえ、会ったこともない人々ばかり。一応表向きは歓迎されたものの、どことなくよそよそしい。
どの親戚の家に父が住むことになったのかははっきりしない。が、そんな没落一族の居住環境がかんばしくないものであったであろうことは容易に想像できる。狭いだけでなく、当然、何かと居心地は悪い。
居候でもあり、まだ若かった彼がぶらぶらしていいはずもない。職を求めて町に出るが、そこで復興したばかりの政府が新設した役所の存在を知る。
建設省だ。彼にとってラッキーだったのは、ちょうどそこで彼が学んできた電気関係の技術者の募集があったことである。応募して採用され、最初の赴任先となったのが、山口のダム現場だった。
佐波川ダムという。サバと読む。山口は読みにくい地名が多い。防府(ほうふ)という町があるが、ボウフと読む人がいる。ほかに岐波(きわ)、厚狭(あさ)、埴生(はぶ)… 誰も読めないのが兄弟(おとどい)という山で、このほか特牛という地名もある。これはなぜかコットイと読む。
佐波川ダムは、今の山口市内の南東、徳地町の山合にある。現在周辺は水域公園になっていて、キャンプ場や様々なレジャー施設がある。しかし、父が赴任してきたころは当然、何もない山中だ。
そこに何年か勤めたころに、地元の人の紹介でお見合いをした。その相手が、母である。若いころの写真をみると、わりと整った顔をしている。が、けっして美人ではない。利発そうだが、燗が強そうにも見える。
一見そうは見えないが、なかなかのスポーツマンで、国体に陸上の選手として出場したことがある。といっても、田舎の町のこと。ほかに大したランナーがいなかっただけで、全国区的にはさほど秀でていたわけではない。
とはいえ、運動神経がよかったのは確かで、その後私が入学した小学校ではママさんバレーチームの主将を務め、広島大会で優勝したこともある。
対する父は、というと、スポーツにはまるで縁がない。またたいした趣味もない。残っている写真からは風采があがらない、ひょろっとした小男という印象を受ける。ただいかにも人がよさそうな面立ちである。また、ちょいとした愛嬌がある。想像するにそれなりに女性受けはよかったのではなかろうか。
はるか60年以上前のことである。二人を実際に並べて見ることはできないが、気の強そうな女と軟派な男との組み合わせは、意外にお似合いだったかもしれない。
年齢差は7つあった。父が大正15年、母が昭和7年生まれで、大きく離れているわけではないが、多少の年代的ギャップはあっただろう。
生まれも育ちも当然違う。方や大陸生まれのボンボン、もう一方は田舎育ちの百姓娘ということで、話のかみ合いどころがどこにあるのか、想像もできない。
が、見合いの結果は上々だったようで、二人はその後、式をあげた。母の実家のあった、山口市郊外の仁保(にお)という場所でだ。写真が残っているが、昔ながらの文鎮高島田結いの母と紋付き袴の父、すぐ近くに住む叔父夫婦やその他の親戚が写っている。
私には姉がいる、と先に書いた。母が21歳の時の子である。父は28歳だったはずで、この結婚後にすぐ、身ごもったらしい。
佐波川ダムでの仕事はその後4~5年続いたようだが、やがてダムも完成に近づき、次の任地は愛媛の大洲と決まったころに、母は次の子を宿した。私である。
身重の体で、まだ小さかった姉を連れて大洲へ行くのはなかなかしんどかろう、という話になったのだろう。ちょうど幼稚園に入る年ごろになっていた姉は、そのまま山口の母の実家に預けていくことになった。
この姉について、少し書いておこう。
山口に残された姉は、そこで幼稚園に通うことになった。市の中心部にある亀山公園内に今もあり、「山口天使幼稚園」という。
そのすぐ側にある、「サビエル記念聖堂」とも関係があるので、まずそのことについて触れる。
江戸時代に入るよりも半世紀ほど前、スペイン人のフランシスコ・ザビエルは山口を訪れて布教を行おうとした。この地を治めていた大内義隆はザビエルの宣教を許可し、信仰の自由を認め、当時すでに廃寺となっていた大道寺という寺をザビエル一行の住居兼教会として与えた。これは、日本最初の常設教会堂といわれている。
この寺は山口駅から4kmほど北に行ったところにある現在の自衛隊駐屯地の近くにあったようだが、今はなく、記念公園になっている。ザビエルはこの大道寺で一日に二度の説教を行い、約2ヵ月間の宣教で獲得した信徒数は約500人にものぼったという。
こののち、ザビエルは豊後国(現大分県)でも布教を行っており、これは現在までも続く長崎をはじめとする九州各地での熱心なカトリック信者の活動につながっている。
しかし、その後徳川幕府の時代にはキリスト教が禁教となったことから、九州や中国地方でのその活動の系譜は途絶えた。山口においても大道寺をはじめ関連する伝道場所が閉じられた。が、維新後に許され、亀山公園内にザビエルの日本での布教を記念して建設されたのが、初代ザビエル記念聖堂である。
ザビエルの来日400年を記念として1952年(昭和27年)に建てられた。その厳かな雰囲気に惹かれ、私は子供のころここをよく訪れたものだ。時に入り口のドアが空いていると、こっそりとその中を覗き込んだりしていたが、その天井には、法衣を着たザビエルがちょんまげ姿で脇差を指した侍相手に布教をする姿が描かれていた。
残念ながら1991年(平成3年)に失火により全焼したが、サビエル記念聖堂の所有者であるイエズス会より多くの資金援助を受けるとともに、種々の教会関係機関、山口信徒、山口市民や全国から寄せられた募金により1998年(平成10年)に再建されている。
その運営は現在でもイエズス会が行っているが、姉が通うようになった山口天使幼稚園はその隣にあって、同じカトリック系の学園法人が運営している。おそらくイエズス会が保有する土地を融通してもらったのだろう。1957年に「サビエル児童会館」という児童福祉施設として建てられたが、ちょうど姉が入園したころに幼稚園に昇格した。
園内にはマリア像が置かれているなど、ある程度宗教色の強い幼稚園である。といっても、おおかたは普通の幼稚園と変わらない。園児に教義を押し付けるようなところはなく、姉はこの幼児園で伸び伸びと時を過ごした。
ちなみに姉の誕生日は12月25日のクリスマスで、イエス・キリストと同じだ。だが、いまだもって宗教などにはまるで興味はない。教会のミサなどには一度も行ったことがないだろう。
キリスト教どころか仏教などにもまるでご縁はなく、たまに神社にお参りに行くくらいだ。子供のころから現在に至るまで趣味もたいしてない。ただ、運動神経はよく、若いころはいわゆる体育会系だった。元国体選手の母のDNAを受け継いだからだろう。高校時代には新体操部のキャプテンを務めていた。
想像するに周囲の男子も騒いでいただろう。弟の自分から見てもなかなかチャーミングだった。しかし、だからといって異性と浮名をあげる、といったこともなく、割と真面目に高校生活を送った。卒業後は、大手の保険会社に入社し、まともな会社員となった。
その会社に勤めて4~5年後、同僚の男性と結婚し、男一人、女二人の子を設けた。40台まではその夫の転勤であちこちを転々としたが、その後広島に落ち着き、幸せそうな日々を送っていた。少なくとも弟の私の目からはそう見えた。
ところが50台になって、突然離婚を宣言。息子や娘たちはさかんに諫めたが聞かず、同年齢の男性と同棲するようになった。ちなみにこの男性と彼女は小・中学校の同窓生であり、そうしたことが縁で付き合うようになったらしい。
父もこの不倫のことは知っていたらしく、姉が離婚を両親に告げたときのその怒りようはすごかったらしい。後で母に聞いたところ、許さん、認めぬの一点張りだったようだ。
その後離婚届も出さないまま時が流れたが、この間父との和解はなく、二人の関係は急激に冷え込み、その冷戦は父が死ぬまで続いた。
もっとも父と姉の折り合いの悪いのはこの時が初めてではない。私はどちらかといえば子供のころから父にかわいがられていたほうだったが、姉のほうはというとしょっちゅう父に叱られていた。
その原因はよくわからないが、相性が悪かった、としか言いようがない。男女の差という以外にもまるで共通項がなく、食べ物やテレビの番組に関しても二人が同じものを好きだったという記憶がないし、そもそも互いにあまり話したがらなかったように思う。
姉が小さかったころはそうでもなかったのかもしれないが、小学校高学年になるころからそうした傾向が特に強まった。年頃の娘と父親というものは、そもそもそういうものだろうが、何かひとつくらいは話の合うネタがあってもよさそうなものだ。
父がそもそも無趣味であったこともある。またあまり社交的なタイプでもなかった。休日に同僚や誰かとゴルフに行ったりするようなこともなく、うちにいて、朝から晩まで家に引きこもっているような内向的なタイプだ。あえて趣味といえば庭いじり以外では読書だった。
一方の姉はといえば、家にいることはほとんどないという印象で、実際、学校から帰るとすぐに友達と外へ遊びに行っていたし、お泊りで友人宅にお世話になることもよくあった。社交的なタイプといえ、これはおそらく母に似たのだろう。内攻的な性格である父とは正反対だ。
その点、私とはウマが合った。私も内攻的なタイプと言え、子供のころから外に出るよりはうちの中で本を読むのが好きだった。小学校では図書館の虫だったが、中学生になるころからはとくに歴史本をよく読むようになった。
父も本が好きで、とくにノンフィクションが好きだった。よく戦争モノを読んでいたが、私の歴史好きはそこから来ている。父の蔵書のうち、最初に借りて読んだのは吉村昭で、それは「海の史劇」という日露戦争を題材にした小説だったが、これを面白いと思った。
やがて自分自身でそうしたものを探すようになり、その流れで戦国時代や幕末を舞台にした、いわゆる時代小説のジャンルにはまった。
私が歴史ものを読むようになってからは、逆に父がその影響を受けたようだ。戦争モノ以外にもそちらにも目がいくようになり、私が読む本にもお金を出してくれるようになった。中学生のころ、小遣いとして月に千円ももらっていただろうか、その数倍の額を手渡されて、よく近所の本屋に通ったものである。
私が買ってきた本を父もまた読み、お互いに書評で盛り上がる、ということも多く、その後私が長じてからも、あの本は面白かった、あれがいい、といった話をよくしたものだ。
ところが、姉はというと、こちらもまた趣味というものがほとんどない。その点が父との共通点といえば共通点なのだが、いかんせん趣味のない者同士の間では分かち合うものは何もない。姉はといえば、私や父のように小説の類などはあまり興味はなく、買ってくるのは漫画のほうが多かった。
父はそれを低俗な読み物、と決めつけていたようで、彼女の居室に少女漫画の本がうずたかく積み上げられていくのをいつも苦々しく見ていた。「マンガばかり読んで!」というのが父が姉を説教し始めたときに出る最初のことばだ。しかし、その怒りの矛先は実はマンガばかりではない。
彼女の長電話がそれだ。この当時は当然携帯電話などなく、どこの家庭にもダイヤル式の黒電話が一台だけ、というのが普通だった。
その電話を独り占めにしていたのが姉であり、母や私が聞いていようがいまいがおかまいなしに長話を続ける。なるべく父のいない頃を見計らって電話をしていたが、父が帰宅し、たまたま玄関口で姉が長話をしているのをみつかると、ひと嵐がくる。
父を観察していると、姉の電話を見かけたときからすでにもう不機嫌で、電話を切ったあと、姉が素知らぬ顔で居間に入ってくるのをみるとますます顔が険しくなる。
その後食事をする間にだんだんと機嫌は持ち直してくるのだが、ビールなどのアルコールが入り、何かの拍子にその怒りがぶり返してくると、いつもの「マンガばかり読んで!」が始まるのであった。
たいていは姉が自室にひっこんでこの嵐は静まるのだが、ほかに学校の成績のことなどが絡まると、治まるどころかさらに雨風が強くなる。よせばいいのに、そこに母も加わって、三つ巴の親子喧嘩になっていくのであった。
この父娘の対立を傍観しつつ、気分的に私はいつも父の肩を持っていた。男同士ということもあっただろうが、姉と話すくらいなら、という気分がいつもあった。父と姉があまり相性がよくなかったのと同じく、彼女とは折り合いが悪く、よく姉弟喧嘩をした。
何が原因かは問題ではない。何かを勝手に使っただの、父母に告げ口をしただの、つまらないことで言い争いになるのだが、要は相手の存在が気に入らないのだ。その背景には父が私の肩を持つことへの姉のジェラシーがあったかもしれない。
ときに大ゲンカとなるが、5つ年上の姉とは、体力的にも言葉の上でもとても勝負にならない。このため、いつもフラストレーションを溜めていたが、ときには陰湿であることは承知の上で巧妙な仕返しもよくやった。
そのひとつとしてよく覚えているのが、チャンネル争いの結末である。私が小学生の高学年のころ、すでに我が家にはカラーテレビがあった。父はこうした電気製品の購入には積極的であり、その理由は所属先が電気を扱っており、業者とのコネにはことかかなかったためだ。
しかし、当の本人はあまりテレビを見ることは少なく、夜帰ってきてから食事が終わり風呂に入ったあとは、自室に閉じこもって読書にいそしむ。残る私と姉、母がテレビを見ているのだが、8時台のバラエティーが終わると、争いが始まる。
私はどちらかといえば男の子らしく、科学ものやチャンバラが好きなのだが、女性陣はといえばやはりドラマである。このときも二人がタッグを組んでお気に入りの番組をせしめた。
どんな番組だったか忘れたが、このときはどうしてもある番組が見たく、学校から帰るとそれを見るのを楽しみにしていた。ところが、いつものように二人にテレビを占領されたことから、大ゲンカになった。しかし、二対一では勝負にならず、とうとう居間を締め出された。どうにも憤りの収まらない私は、大胆な行動に出る。
二人が続いてのドラマ番組をみるまで、トイレや皿洗いに立ったときのことである。おもむろに、私は押入れからカッターナイフを取り出した。
そして二人に見られないようにコンセントからテレビへと延びる線の半分に切れ込みを入れた。電源はプラスかマイナスかどちらかをカットすれば絶たれる。両方に刃を当てれば、ショートしてしまう可能性があるが、気を付けて片方だけを断線すれば、大事には至らない。
学校の技術家庭の時間に知った知識を応用した犯行だったが、二人はそんなことは露とも知らない。茶の間に帰っていざお気に入りのドラマを見ようとするが、いくらスイッチを入れても映らない。やがてテレビが壊れた、と大騒ぎになった。
それを陰で見てほくそ笑む私。その日、父は残業で帰りが遅かったが、帰ってきてそうそう騒ぎ立てる二人に促されてテレビのチェックに入った。
チャンネルやらスイッチを次々にチェックしていったが、最後に私のいたずらに気が付き、つぶやいた。「あーこりゃ、電源がはいらないはずだわ」。
それをふすまの陰で聞いていた私は、すぐに怒られると覚悟した。が、1分経っても2分たっても何も起こらない。やがて母から「風呂にはいりなさいよー」の声が聞こえたが、不思議なことに結局その夜は、その後何のお咎めもなかった。あとでそっと断線したテレビのコードをみると、きれいにビニールテープで補修がしてあった。
翌朝も何事もないように学校へ行き、その後、この話が蒸し返されることは二度となかった。しかし、なぜ父は怒らなかったのだろう、という疑問が残った。
のちのち考えて私が出した答えはこうだ。まず、このとき私が取った行動は許されるものではなかったが、二人して一人を占め出すのはよくない、と父は思ったのだろう。また、そもそも父は、マンガばかりではなくドラマ三昧の姉を苦々しく思っていたようだ。そしてそれに加担する母にも批判的な気持ちを持っていたに違いない。
あるいは息子がとったその行動を、子供ながらに頭脳的でなかなかやるな、と思ってくれたのかもしれない。その後、父が亡くなるまで、あのとき何故私を叱らなかったのかその理由を聞くことはなかった。しかしその後、いつもそういう形で何も言わず、私のやることにエールを送っていてくれたような気がする。
さて、余談が過ぎた。姉のことはまた書くことにしよう。
こうして山口に姉一人を残して父と母は新しい赴任地である愛媛県の大洲へと移っていった。
大洲市は、「伊予の小京都」と呼ばれ、肱川の流域にある大洲城を中心に発展した旧城下町である。
伊予の地を南北につなぐ大洲街道と東西に結ぶ宇和島街道の結節点にある。また東には四国山脈を抜けて土佐国(現在の高知県)に出る街道もあり、さらに、すぐ西には大洲の外港とも言える八幡浜(現・八幡浜市)があった。地理的には四国の中にあって一番西方に位置するが、交通の要衝と言える場所であり、軍事的にも古くから要所であった。
最初にここに城を造ったのは、伊予宇都宮氏である。豊前宇都宮市の流れを汲む豪族であり、もともとは豊前(現大分県)を拠点にしていたが、14世紀ころから海を隔ててすぐのこの地に入り、先住民を鎮撫してここを所領とするようになった。
14世紀末、伊予宇都宮氏初代の豊房は、肱川と久米川の合流点にあたるこの地に城を創った。当時地蔵ヶ岳と呼ばれていたこの高台から名を取り、城は「地蔵ヶ岳城」と呼ばれていた。その後、江戸時代初期になってからは、藤堂高虎が徳川からここを下賜され、大洲藩と呼ばれるようになってから大洲城の名が定着した。
高虎はさらにこれを大規模に修築し、近世城郭としての体裁を整えた。こうして、伊予大洲藩の政治と経済の中心地として大洲の城下町は繁栄していった。
現在でも江戸時代の当時の風景が余さず残っている。なまこ壁の家や腰板張りの土蔵群などが並ぶ場所は、「おはなはん通り」と呼ばれ、1966年から翌年に放送されたNHK連続テレビ小説「おはなはん」のロケ地にもなっている。
冒頭で描写した私が生まれた病院は、そこからもほど近い。市役所の近くにあったようだが、今は既になく、消防署になっている。街の中心部だけに、ビルが立ち並んでいるが、半世紀以上も前のこのころは、ひなびた商店街があるだけだった。
父が建設省に入って二番目の仕事として関わったのは、市内を流れる肘川の上流にある鹿野川ダムという多目的ダムの建設だった。肱川は、その総延長が約100キロメートルにわたり、数百本もの支流を持つ愛媛県内最大の河川である。
その下流に大洲市街が位置するが、上流では川幅の狭い区間が多数存在するため、過去に市民は再三水害に悩まされてきた。建設省は1953年(昭和28年)10月、肱川の治水・利水を目的とした「肱川総合開発事業」の一環として鹿野川ダムの建設に着手した。
河口から約35キロメートル上流にさかのぼった場所がその建設地として選ばれた。ダムに堰き止めた水で洪水調節するとともに。ダム式水力発電所を併設し、最大1万400キロワットの電力を発生させて、大洲市内へ供給する。
工事は1956年(昭和31年)6月に始まったが、地質不良により基礎掘削量の増加を余儀なくされ、さらに1958年(昭和33年)12月に、試験的に湛水した際には、湖畔の3地区で地すべりの発生が確認された。このため、土壌改良や数々の地滑り防止策がとられたが、これが功を奏し、ダムは1959年(昭和34年)3月に無事完成した。
父と母はダムの建設が始まった当初から、ダムが完成してその管理権が愛媛県に移譲されるまでここにいたようだ。移管されたのは1960年であるから、ほぼ足掛け4年ここで暮らしたことになる。
その間、私が生まれ、狭い長屋はがぜん賑やかになった。母は今回の出産では産後の肥立ちが悪かった。母乳があまり出なかったようで、生まれて何カ月も経たないうちに私に与えられる乳はミルクに切り替えられた。
のちに母によく聞かされた話では、私は温かいミルクが嫌いで、与えられるといつも吐き出していたという。冷たいミルクを与えると、ゴクゴクと喜んで飲んでいたというから、よほど変わっている。
無論、自分ではそんなことはまるで覚えていない。ミルクだけでなく、その前後の記憶についてもまるでないが、これは誰しもが同じだろう。羊水の中のことや生まれてすぐのことを覚えている、という人がにいるようだが、そうしたケースは稀である。私もまた生まれたころのことは無論のこと、2歳になってからのことすら記憶にない。
余談になる。私は、幼いころばかりではなく、大人になってからも記憶がほとんどない、といったことがある。その時私は何をしていたのだろう。何を考えていたのだろう。どこへ行っていたのだろう、どうしても思い出せない時間があるのだが、そうした経験は誰にでもあるのではなかろうか。
また、もしかしたら、あれは夢だったのかもしれない、ということもある。現実には違いないのだが、その移り行く状況の中に身を置いていること自体、実態のないことのように思える。これまで歩んできた長い人生の間において、そうした時間は確かに存在する。とくに、大きな失意や大きな喜びの中にあったとき、そうしたことが多かったように思う。
ここに書きたいと思っていることは、まさにそうしたことである。忘れてしまっている話や夢のように思えたことを書き出していくのは面白いに違いない。少なくとも、明瞭に記憶に残っていることを書き留めるだけの話よりは人に読んでもらえそうだ。
また、記憶の欠落を埋め、自分史を完成させる、といったことには意味がある。なぜなら、自分がなぜこの世に生まれてきたのか、という疑問の解消につながっていく可能性があるからだ。
とはいえ、ここでは、まがりなりにも自伝らしきものを書こうとしている。夢物語ばかりでは人様に納得して読んではもらえないだろう。そこで、やはり現実にあった具体的な話を骨格に置いて書いていこう、ということになる。
そしてそれを書き出す場合、一番手がかりとなるのはやはり記憶しかない。それは古いものから順番に積みあがっていくものらしい。
しかし、時代が遡ればさかのぼるほど下のほうにあるから引っ張り出しにくい。また、前後がわからなくなっているものも多い。さらに言語能力が発達する前の記憶ほど、情報量は少ないから、これは丹念に掘り起こさなければ物語にならない。
この点、前世の記憶と同じである。断片的な情報はあるものの、顕在意識の中で思い出そうとするともうろうとしたものしか出てこない。本来なら、今生だけではなく、こうした過去生に遡っての自分史が書ければもっと面白いだろうなと思う。ただ、断片的なものであるからリニアにはつながりにくい。
さらに、それぞれが独立した人生だから、繋げたとしても物語にはならない。何千年前、もしかしたら何万年も前から続く自分の人生をすべて思い出したとして、それをつづるのには、おそらく何十年、あるいはもっと時間がかかるだろう。
残念ながら、本稿に使える時間はそれほど長くはない。なので、限られた時間の中で限られた情報しか導き出せないだろう。それならば、ここでは自分が今生で最も重要だったと考える経験を中心に書いていきたい。神経を研ぎ澄まし、できるだけ多くの記憶呼び覚ました上で、さらに欠落している部分があるなら、それを夢の話や想像で補っていくことにする。
人の齢は短い。たかだか80年、長く生きても100年だ。長い転生の歴史を思えばほんの短い午睡の中の夢のようなものだ。ゆえに、この稿でこれから書いていくことも、また夢の途中の話である。
────────────────────────────────────────
本稿の内容はすべて事実に基づいたノン・フィクションです。ただし、登場する人物名は仮名とさせていただいています。また地名や組織名についても、一部は実在しない名称、または実在する別称に改変してあります。個々のプライバシーへの配慮からであり、また個人情報の保護のためでもあります。ご了承ください。