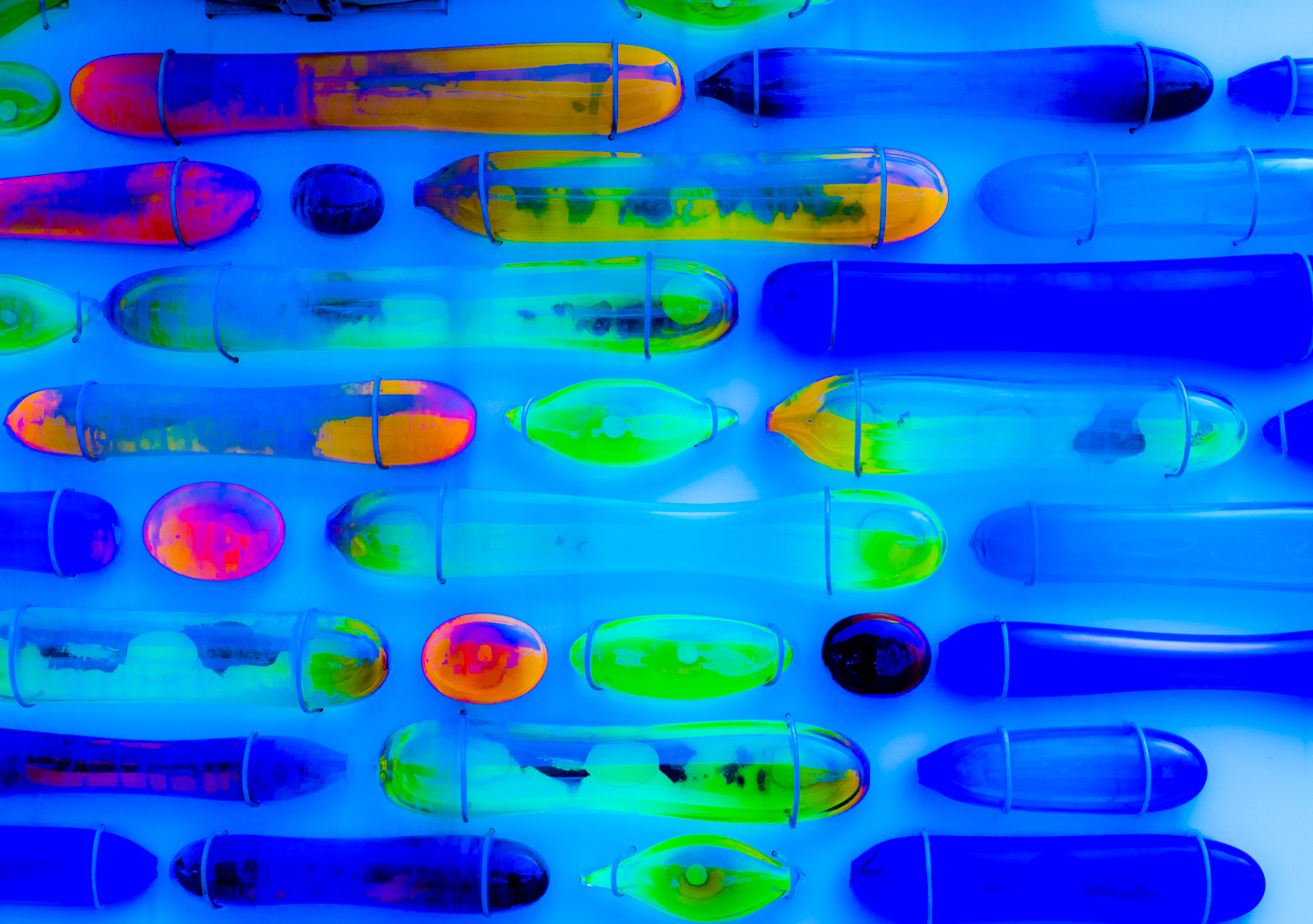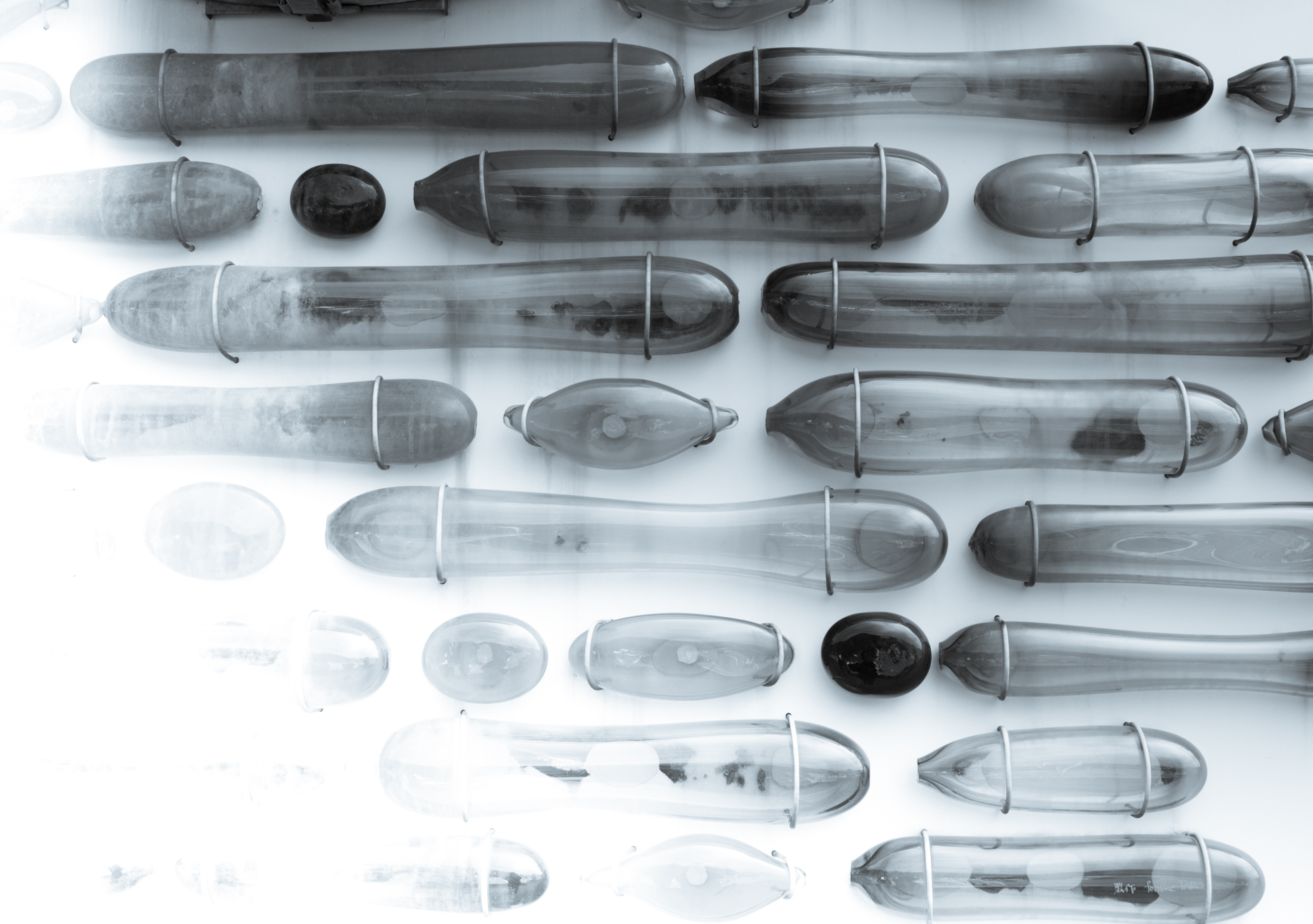今年もあとひと月となりました。
そろそろ、一年を振り返ってみてもいいころかな、と今年あったことなどを思い返したりしているところです。
私的には可もなく不可もなくというところですが、それほど悪い年ではありませんでした。健康に恵まれ良い一年だったと思います。
一方、社会的な一年をみると地震や水害などの災害が多く、相変わらずのコロナ禍も続いていて、あまりいい年ではなかったな、という印象です。この疫病による我々の生活への影響は来年もまだまだ続きそうです。
しかし、そうした中で催された東京オリンピックでは日本人選手が大活躍しました。日本はアメリカ、中国に次いで28個もの金メダルを獲得し、1964年の東京オリンピックの16を大きく上回りました。全体でも58個で、当時のほぼ倍の数を獲得しています。
さらに先月、二刀流で活躍したエンジェルスの大谷選手がMVPを獲得するという朗報も入ってきて、スポーツ界ではとかく明るい話題が多かったように思います。
そのほかでは今年はいろんな意味で節目でした。例えば、東日本大震災発生からちょうど今年で10年が経ち、同じく福島第一原子力発電所事故からも10年です。アメリカ同時多発テロ事件からも20年で、ソビエト連邦の崩壊から30周年でした。
「宇宙」に目を向けると、ユーリー・ガガーリンによる世界初の有人宇宙飛行から60周年、アメリカがスペースシャトルを退役させてからちょうど10年です。そのアメリカでは今年9月、宇宙開発会社、米スペースX社による民間人初の宇宙滞在飛行が成功しました。
国内ではさらに先の10月4日、内閣総理大臣指名選挙が行われ、岸田文雄氏さんが総理大臣に指名されました。100代目ということで、こちらも何か時代の一区切りを感じます。
ちなみに初代総理は、明治18年選出された伊藤博文で、日本は平均1.4年に一度新総理を選んでいます。アメリカ大統領の5.0年に一人に一度に比べて格段に多くなっています。
このように何か「時代の節目」を感じる年というのはあるもので、過去においても、誰がみてもそうだったといえる年があります。
そのひとつが1989年だったではないでしょうか。
この年、ベルリンの壁が崩壊したことを節目に、その後1992年までの間に、東欧の脱共産化、東西ドイツの統一、ソ連崩壊、冷戦の終結と、文字通り世界地図が塗り替わりました。とくに東側陣営の盟主であり超大国でもあったソ連の消滅は全世界に衝撃を与えました。
これによって、社会主義の実現を信じていた西側諸国内の社会主義政党や政治学者はイデオロギー論争に敗北し、冷戦時代にソ連共産党から受けていた資金提供は途絶えました。
各国の共産主義者は大打撃を受け、イタリア共産党は解党して左翼民主党に鞍替えを余儀なくされました。日本共産党は「大国主義、覇権主義の歴史的巨悪の党の終焉を歓迎する」とあたかもこれを歓迎するような強気な声明を出しました。しかし、世界的な脱社会主義への動きを「歴史の逆行」とする党員もいて、少なからず政策転換を迫られました。
ソビエト連邦の崩壊によって公文書が情報公開されたため、名誉議長だった野坂参三氏がかつてソ連のスパイであったことが発覚し、満100歳を超えていながらその職から除名されるという事件も起きています。
こうしたソ連崩壊をみた西側諸国は、これを「=共産主義の絶滅」と錯覚してしまいました。中国やキューバなど、未だソ連以外にも社会主義の強国が存在していたにも拘わらず、にです。
その存在を重視しなかった結果、力をつけた中国はその後、唯一アメリカに抗しうる国と言われるまでに勢力を伸ばしました。ソ連に代わって共産主義の旗頭になったこの国が、これほどまでの経済・軍事大国になるとは誰が予想していたでしょう。
そのアメリカでは昨年、「保護主義と分裂抗争の世界」を生み出したドナルド・トランプが大統領選に敗れました。今年はそれに代わって登場したバイデン大統領によって次々と新しい政策が実行に移され、これによって新たな世界秩序が生まれつつあります。
このように昨年から今年にかけての時期は、1989年に次ぐ大変化の時期と考える要素がたくさんあります。加えて、新型コロナウイルスが流行り始めたのは昨年、今年はそれが大流行しました。今後はこの2年間がセットで歴史の節目とみなされるようになっていくことは間違いないでしょう。
無論、これまでにもこれ以上の歴史的大変革と呼ばれた時期はたくさんあります。人類の創生にまで遡れば、二足歩行を行うようになった時代がそれであり、さらに火や鉄を手にした時期にも大きな変化が起きました。
その後、古代文明への移行、ヨーロッパやアジアを中心にした現代的諸地域世界の成立、そして二度の世界大戦、というふうに我々の歴史は、大きな変化があった時代を境に大きく分けることができます。
しかし、考えてみれば人類の歴史はわずか数千年にすぎません。地球誕生は46億年前といわれており、そうした気が遠くなるような時間に比べればほんの一瞬といえます。
その現生人類が、いまやそれよりはるかに長い歴史を持つ地球に大きな影響を与えようとしています。地球温暖化などの気候変動、生物の大量絶滅による多様性の喪失、人工物質の増大、化石燃料の燃焼や核実験などは、地球環境は大きく変えようとしています。
その始まりは、おおむね二次大戦が終わった1945年頃ではなかったか、といわれています。歴史区分としては「現代」とされる時期ですが、最近ではこれに代わって、「人新世」という時代区分にすべきではないかという議論があります。
これは「じんしんせい」とも「ひとしんせい」とも読むようで、ほかに新人世(しんじんせい)や人類新世という呼び方案があります。オゾンホールの研究でノーベル化学賞を受賞したパウル・クルッツェンらが2000年に提唱したもので、国際地質科学連合でも適当な時代区分かどうかについて研究を始めています。
1945年と書きましたが、これについては様々な意見があり、人類が地球環境へ影響を与え始めたのは、はるかに昔の12,000年前の農耕革命を始まりとするもの、あるいは大戦が終わって世界秩序が落ち着いてきた1960年代以降とすべきだとするものなど幅があります。
しかし、第二次世界大戦直後に、社会経済や地球環境が劇的に変化したと考える研究者が最も多く、彼らはその変化が始まった初期のころのことを別途、グレート・アクセラレーション(大加速)と呼んでいます。その開始時期についても、1945年、1950年代など諸説がありますが、いずれにせよ、この時期を境に急激な変化が起こったとされます。
その社会経済的変化の指標としては、人口、国内総生産(実質GDP)、対外直接投資(FDI)、都市人口、一次エネルギーの使用、化学肥料の使用、巨大ダム、水利用、製紙、交通、遠隔通信、海外旅行などがあげられています。
また自然環境の指標は、二酸化炭素、亜酸化窒素、メタン、成層圏オゾン、地球の表面温度、海洋酸性化、海洋における漁獲量、エビ養殖、海洋の富栄養化や無酸素化につながる沿岸窒素の増加、熱帯雨林と森林地域の喪失、土地利用の増大、陸上生物種の推定絶滅率などです。
こうしたグレート・アクセラレーションの考え方が出てくる前までは、地球環境問題というとき、まず最初に「地球温暖化」が取り上げられていました。しかし、温暖化だけではそうした変化は説明できないという声が高く、上のような多くの指標をもとに地球環境の変化を分析した結果、その分岐点が1945年ころだった、と結論づけられました。
その変化の方向性が良い方向性かといえば逆です。我々が棲む環境は多くの要素によってどんどんと悪化しつつあり、影響を与えた人類そのものがその波に飲み込まれようとしてます。
一方、もうひとつの巨視的な地球環境の変化の捉え方として、「プラネタリー・バウンダリー」という考え方があります。
この考え方ではまず、地球全体をひとつのシステムとして考えます。それを維持するためには常に一定条件のもとにシステムが正常に働き続けける必要がありますが、ある限界を超えるとシステムは予想がつかない振る舞いをするようになりやがて崩壊に向かい始めます。
この限界点を「引き返し不能点(ティッピング・ポイント)」といい、この仮説では、環境に負荷を与える化学物質、重金属や有機化学物質による生物圏の汚染、土地利用の変化、淡水利用、生物多様性の喪失、窒素とリンの循環といった「人類が作り出した脅威」がその限界点を創り出しているとされます。
さらに、これらのダメージによって成層圏オゾン層の破壊、海洋酸性化、などが加速されており、その結果、2009年時点では既に、気候変動、生物多様性の損失、生物地球化学的循環の3つの環境指標は限界を超えている、とする研究もあります。
そう明言するのは、プラネタリー・バウンダリーの提唱者で、スウェーデンの環境学者ヨハン・ロックストロームと化学者のウィル・ステフェンをはじめとする約20名の地球システムの研究者たちであって、いずれも一流の研究者達です。
このように、現在の地球環境が既にその限界値を超えているならば、今後はさらに危機的な状況に陥る可能性もあり、悲観的な見方をすれば、その結果やがて人類は滅亡してしまうでしょう。
それを防ぐためには、現在ある資源を保持しつつ安定してこの世界で暮らし続けていくための手立てを打っていかなくてはなりませんが、そのために設定された目標が、最近よく耳にする“SDGs”です。「持続可能な開発目標」とされ17の世界的目標が示されています。
2015年9月25日の国連総会で採択されたもので、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」として、向こう15年間の間に実現することが目標とされています。
SDGsの詳細については既に多くのメディアで紹介されているためここで詳しくは述べませんが、これらの目標と達成基準を実施するために、全ての国に対応が求められています。達成基準は各国政府が定め、地球規模レベルでの目標達成を目指しつつ、経済、社会、環境などの各分野で並行して持続可能な開発を行うという取り決めです。
日本でも、政府が2016年から全国務大臣を構成員とする「持続可能な開発目標 (SDGs) 推進本部」を設置してその取り組みを開始しています。ただ、先進国である日本の義務としては、自国の利益だけでなく、環境が脆弱な国々や紛争下にある国々への援助などの特別な配慮が求められており、世界的な視点をもってこれに取り組んでいかなくてはなりません。
しかし、何やら総花的なこうした目標が果たして達成できるかどうかについて、研究者たちの間でも疑問視する向きがあるようです。仮にこうした試みの一部がうまくいったとしても、他がすべて失敗に終わったら、地球環境は今よりもさらに悪化し、その結果人類は、その長い歴史を閉じるかもしれません。
そしてその「絶滅シナリオ」が開始される際にトリガーになりうるのは、何か大きなイベントである可能性が高く、それには自然現象によるものと、人類自身の活動の結果によるものの二つがあると考えられます。
自然現象としては上でもあげた温暖化や気候変動以外では隕石衝突や火山の爆発といったものなどが考えられますが、一般にはこれらが一度に発生して人類が滅亡に追い込まれる事態が起きる確率は極めて低いと考えられています。
一方、人為的なものはそれ以上にリスクが高いとされています。例えば核によるホロコースト生物兵器戦争、パンデミック、人口過多などがあります。こうしたインパクトによって百年以内に人類が滅亡する、といったストーリーは昔からよく描かれてきました。
とくに核戦争・生物戦は、人類を滅亡に追いやる可能性が高いとする説がまことしやかに流布されています。冷戦期を超える軍備拡張競争が起こって大量破壊兵器の際限なき増加が続き、それらが第三次世界大戦の勃発で一度に使われる、といった話を何かの映画で見た人も多いことでしょう。
一方、ウイルスやプリオン、抗生物質耐性を持つ細菌などが大発生し、全人類に感染して死滅させるといった、いわゆる「パンデミック」も人類を破滅させる可能性が高いとされます。
そうしたものを作る技術的な障壁は発展途上国であっても既にかなり低くなっているといわれており、テロなどでばらまかれた病原体が人類を絶滅させる可能性はありそうです。
現在進行している極度の人口増加が人類の破滅をもたらすという説もあります。地球の歴史上、人類ほど数を増やし、また広範囲に広がった大型脊椎動物は他にありません。1800年に10億人だった世界人口は1930年に20億人に達し、現在では約79億人です。
将来的には120億人を超えるという推計もあり、将来的にも発展途上国で出生率が高い状態が続くと考えられています。人口爆発とも呼ばれる人口の増加により、人類は必然的により多くの資源を消費し、より広大な土地を利用するようになるでしょう。
それでも食糧生産が需要を満たせず、偶発的な飢餓発生などが起きれば消費が多すぎるため再生可能な資源も枯渇します。結果、耐えられる限界を超えて増殖した人類は、やがて劇的に減少していくと考えられています。
もし現在の発展途上国が先進国の水準に到達したならば、現在の先進国のような少子化が世界的に発生し、その後は永続的に人口が減少していくという説もあります。仮に世界の出生率がドイツもしくは日本の水準にまで落ちるとすれば、2400年の時点で人類は滅亡するといった学説も出されています。
科学の発展もまたそのトリガーになる可能性があります。規制なく野放図に科学の発展を続けていくと、人間の制御できない新技術が生まれてしまい、結果として人間を滅ぼすことになる恐れがあるという説などがそれです。
0.1 – 100 nmサイズの機械装置のことをナノマシンといいます。将来的にはこれを使った癌治療が実現するなど、医療の世界だけでなくその他の分野でも革新が起こると考えられています。自己増殖能力を持つものも出てくるとされていてグレイグー(Grey goo)と呼ばれています。これが際限なく増殖したとすると、地球の生態系を崩壊させる危険性があります。
また科学者が、世界が存在できているバランスを「たまたま」崩してしまう、ということもあるかもしれません。地球上でマイクロブラックホールを発生させたり、素粒子物理学研究上で偽の真空を創出したりしている段階で間違いが起こる可能性があります。
実際、欧州原子核研究機構の大型ハドロン衝突型加速器が稼働して、素粒子を光速に近い速度で衝突させたときに、マイクロブラックホールが生成される可能性が指摘されています。そうでなくても、現在我々が生きているこの大気中ではこの実験を上回る高エネルギー衝突現象が日常的に発生しています。
さらには人類を超える生物が登場するのではないかという危惧もあります。現在はホモ・サピエンスが霊長類の頂点に君臨していますが、過去には別の種族もあり、これらは全て競争に敗れ絶滅しました。
将来これと同様のことが起こり、我々以上に進化した新人類によって我々が駆逐されるかもしれません。我々の進化は現在も続いており、その中から理論上は新たな生物種が誕生する可能性は十分にあります。
一方、未来の人類はその進化の過程でその遺伝子に異常を来すかもしれず、そのために完全に2つの種に分裂してしまう可能性も指摘されています。まったく違う遺伝子に分化した両者が共存できればいいのですが、他方を撲滅しようと全面戦争になる可能性もあるわけで、その中で人類が滅亡していくというシナリオもありえます。
遺伝子工学などの発展により人為的に「ポストヒューマン」が生まれる可能性もあるでしょう。現在の我々よりも肉体的にも知能的にも優れた「新人類」です。これを「進化」と呼ぶかどうかは別として、地球の歴史上前例がないこうした新人類の登場によって、古い人類が滅ぼされる危険性もあるのです。
逆に人類は退化するのではないかとする説もあります。人間は既に進化の極致に達しており、今後は適者生存の原理が通用しなくなるという説です。既に人類は誕生して進化してきたのとは逆の方向性に向かいつつあり、やがて退化しすぎて滅亡に至るといわれます。
以上のように「人類の滅亡」ついてはいろんな可能性があります。無論、我々の経験したことがないような大事件であり、従って、参考とするデータは何もなく、このためそれがどのくらいの確率で現実となる可能性があるかについての予測は甚だ困難です。
ただ、すべてを仮設で埋め尽くして推論した例もあり、ハーバード大学の哲学者、ジョン・レスリーが2007年に打ち立てた理論では、500年後に人類が滅亡している可能性は30パーセントだそうです。また、2006年にイギリスの経済学者ニコラス・スターが発表した計算結果では、100年以内に人類が滅亡する確率は10パーセントでした。
いずれも100パーセントではありません。ということは、どうやら科学者たちはこの世からきれいに人類が消滅するとは考えていないようです。
人類のすべてが滅亡しないとされる根拠のひとつとしては、例えば世界規模の核戦争などが起こったとしても、人口密度の少ない僻地では人類が生き残るのではないか、とされるためです。例えばチベットの高地、南太平洋の隔絶された島々といった特殊環境では、人類が生き残る可能性があります。
また大都市の地下鉄の線路や構内、政府要人が退避するための核シェルター、長期間の孤立に耐えうる計画と物資を有している南極基地などで人類が生き残る可能性もあるわけです。
核爆弾だけでなく、人類の数を激減させる方法は他にもいくつも存在しますが、いずれにおいても少数の人類は生き残り、いずれは回復して最小存続可能個体数を上回る可能性が高いという説が有力です。
また、地球上のどこかに自立して外海と隔絶された集落を建設することで、人類存続可能性を高めることができる可能性もあります。実際に、いまからこれを実行しておくべきだと提唱する研究者もいて、ある学説では100人ほどの生存者がいれば、破滅的災害の後に人類が存続できる可能性は高いとされています。
それを宇宙空間に求めるべきだとする学者もいます。天才宇宙科学者といわれた故スティーヴン・ホーキング博士も、かつて太陽系内の星に広く移民することで、将来の地球規模の災害や熱核戦争による人類滅亡リスクを下げることができると語っていました。
遠い将来、こうしたコロニーを作成するため、火星をテラフォーミングして、恒久的に自給自足が可能な環境がそこに構築されているかもしれません。地球を脱出して宇宙植民としてそこで暮らす我々は、他の星に住まう宇宙人からは火星人と呼ばれているでしょう。
月もまたその可能性のある場所です。近年の研究で、月に貴重な鉱物資源だけでなく、およそ60億トンもの水が存在していると分かっています。
水は水素と酸素に分解できます。水素はロケットの燃料になるため、月から新たな居住地を目指して旅立つこともできます。また酸素が人類が生きるために役立つことは言うまでもありません。月資源開発を進めれば、多くの地球人がそこに住める可能性があるのです。
さて、時代の区分に始まり、人類の将来のことなど考えているうちに、今日も話が長くなってしまいました。
今年も押し迫ってきました。今年最後の満月は、12月19日だそうで、これは地球から最も遠い満月だそうです。ということは最も小さい満月ということになります。
年の瀬を迎えつつある今、人類滅亡の可能性などは忘れて、遠く離れたその小さな月に住まう夢でも見ながら今夜の一杯を頂くことにしましょう。