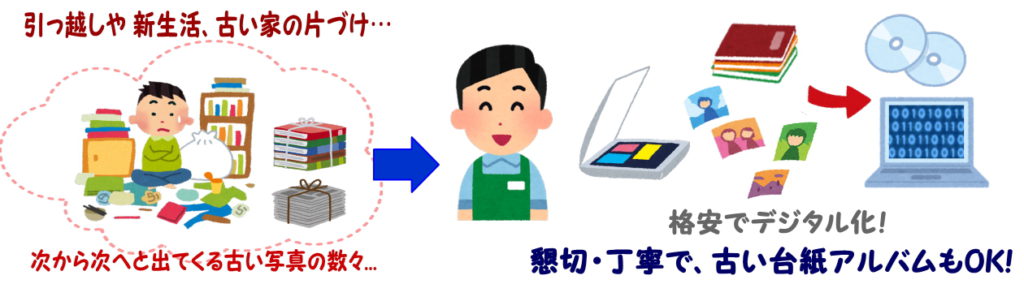今から56年ほど前のちょうどいまごろ、日本で初めての南極観測隊が、南極の東北沿岸に到着、のちに「昭和基地」となる場所に設営を始めました。
正確には、1957年1月29日、東京大学の教授で地球科学が専門の永田武を隊長とする53名の第一次南極隊が、観測船「宗谷」で南極の東北沿岸、大陸から約4キロメートル離れた「東オングル島」付近に上陸。ここを、「昭和基地」と命名し、この年の冬からの越冬に備え、基地の建設を開始しました。
この「昭和基地」という名称は、29日のその日に宗谷から無線によって日本に打診され、1月31日には政府でこれを正式名称とすることが決定され、その翌日の2月1日から本格的に建設が始まりました。
現在に至るまでこの基地は拡張を続けながら存続しつづけており、昨年の11月には、第54次南極観測隊が日本を出発し、12月20日に南極大陸の昭和基地に到着しました。
第54次南極観測隊は、今年3月下旬に帰国するまで約3ヶ月にわたって南極に滞在し、従来からの観測を踏襲し、昭和基地とその周辺の大陸沿岸部での気象観測や電離層観測のほか、海洋物理・化学観測、測地観測など多くの研究観測を行なう予定です。
白瀬中尉による南極探検
この昭和基地の歴史は、ほぼそのまま日本の南極観測の歴史でもあります。
が、これに先立つほぼ半世紀ほど前の1910年にも、日本の陸軍軍人で南極探検家の白瀬矗が開南丸で東京から出航し南極探検をおこなっています。
白瀬隊は、日本が明治時代として近代国家になって初めて南極に派遣された「探検隊」で、白瀬自身は、「陸軍中尉」の肩書を持つ軍人ではありましたが、隊員28名は、朝日新聞上で「身体強健にして係累なきもの」を資格として募集された者たちであり、300人もの応募者の中から決定された民間人でした。
この探検は、1910年(明治43年)に、白瀬らの有志が「南極探検に関する請願書を帝国議会へ提出して派遣を請願したものですが、衆議院は満場一致で可決したものの、政府はその成功を危ぶみ3万円の援助を決定するも補助金を支出しませんでした。
このように政府の対応は冷淡でしたが、白瀬隊の雄図に国民は熱狂し、渡航に必要とされた費用14万円(色々な価値換算基準があるが、一説では現在の3800倍として約5億円)は国民の義援金によってまかなうことができました。
しかし、船の調達も難航し、そのための予算も2万5千円程度(同約1億円)にすぎなかったため、積載量が僅かに204トンという木造の帆走サケ漁船にわずか18馬力の蒸気機関を取り付けるなどの改造したものが探検船として使われることになり、この船は、東郷平八郎によって「開南丸」と命名されました。
極地での輸送力は、雪上車のようなものがある時代であるわけではなく、29頭の犬だけであり、探検隊の装備も、極寒に耐えるために毛皮中心であるなど、現在のものとは比較にならいないほど貧相なものだったということです。
1910年7月には、大隈重信伯爵を会長とする南極探検後援会が発足。こうして、日本初の南極探検船は、翌年の2月26日に南極大陸西南部(注:南極大陸の「北」は南アメリカ大陸南部方向。南はオーストラリア方向)にある、ロス海へと到達し船を進めましたが、すでに南極では夏が終わろうとしていたため途中から引き返し、越冬のためオーストラリアのシドニーへ寄港します。
11月中旬にシドニーを出航し、翌年の1911年1月16日、ついに大陸最南部付近のエドワード7世半島を経由して南極到達に成功します。このとき、「開南丸」はクジラ湾のロス棚氷でロアール・アムンセンを中心とする南極探検隊の南極点到達からの帰還を待つ「フラム号」と遭遇しています。
開南丸から7名から成る「突進隊」をロス棚氷へと上陸させましたが、貧弱な装備のために探検隊の前進は困難を極め、28日に帰路の食料を考え、南極点まで行くことは断念。そして、南緯80度5分・西経165度37分の地点一帯を「大和雪原(やまとゆきはら・やまとせつげん)」と命名して、隊員全員で万歳三唱したといいます。
同地には「南極探検同情者芳名簿」を埋め、日章旗を掲げて「日本の領土として占領する」と先占による領有を宣言しました。その後、第二次世界大戦の敗戦時に、日本はこの地の領有主張を放棄してしまっていますが、この地点は棚氷であり、領有可能な陸地ではないことが後に判明しています。
この突進隊の探検が続いている間、開南丸はエドワード7世半島付近を探索しており、この結果新たに発見された湾に、「大隈湾」や「開南湾」という名前を命名しています。
白瀬隊が名付けたこの「開南湾」や「大隈湾」などの地名は、現在でも南極条約のもとに公式なものとして採用されており、「大和雪原」も公式に認められているようですが、なぜか各国が出版している地図からはこの名称は消えているそうです。
これは、白瀬隊の探検の後、アメリカなどの探検隊がこれらの場所に別の英語名を名付けたとき、日本政府が何の抗議もしなかったためのようです。結局のところ、アメリカの譲歩により元の日本名が正式名として認められたようですが、国際的な舞台ではいつも強い主張ができない日本の悪い面が出た一例といえるでしょう。
白瀬隊はその後、アレクサンドラ王妃山脈付近を探索した後、開南丸に乗って日本へ向けて出航しようとしましたが、いざ南極を離れようとすると海は大荒れとなり、連れてきた樺太犬21頭を置き去りにせざるを得なくなりました。
無論、その多くはかわいそうに死んでしまいましたが、このうちの6頭は「生還」という記録があるようです。これは別の国の探検隊がその後の探検の際に救出したのだと思われますが、この項を書くにあたっては、これに関する詳しい記事は見つけることができなかったのでよくわかりません。
が、いずれにせよ大多数の犬を失ったことで、隊員たちの落胆は相当なものだったようで、しかも参加していた樺太出身のアイヌの隊員2名は、犬を大事にするアイヌの掟を破ったとして、帰郷後に北海道で民族裁判にかけられ、有罪を宣告されたと伝えられています。
一行を乗せた開南丸は、ウェリントン経由で、無事日本に帰国していますが、そもそもこの遠征隊には内紛が絶えませんでした。シドニーに滞在して、南極を目指す準備をしていたころから、仲間同士でのいさかいがたびたび起こっており、隊員による白瀬中尉の毒殺未遂事件が起きたとさえいわれているようです。
帰国に際し、ウェリントンに戻るころには、白瀬隊の内紛は修復出来ないほど悪化しており、白瀬と彼に同調するもの数人は、開南丸ではなく汽船で日本に帰ってきたといいます。とはいえ、その他の白瀬隊の多くは、開南丸に乗って、1912年6月20日に無事に芝浦に帰還しました。
昭和基地の建設
その後、日本人による南極探検、もしくは南極観測は40年以上も行われませんでしたが、前述のとおり、第二次世界大戦後の1956年、長い空白を破って第1次南極地域観測隊が南極観測船の宗谷で南極へ向かい、昭和基地を開設しました。
日本が、南極観測を行うようになったきっかけは、1950年代、アメリカの地球物理学者で南極の電離層の研究をしていたロイド・バークナー(Lloyd Berkner)によって提案された、南半球の高緯度地域の高層気象データの蓄積を勧めるための「国際極年」でした。
国際学術連合(ICSU)は、これを極地以外の総合的な地球全体の物理学観測の計画にまで拡張し、これに答えるかたちで70を超える国立またはそれに相当する機関が協力し、「国際地球観測年委員会」が組織され、実行に移されました。
この「国際地球観測年」が提案された1951年(昭和26年)、日本はまだGHQの統制下にあり、独立を回復していなかったため、日本はこれに参加することで国際的地位を認めてもらおうと考え、参加を表明します。
当初、日本独自の技術で赤道観測を行う予定でしたが、日本が観測をしようとしていた土地(これがどこだったのか何を調べてもよくわかりませんが)の予定地の領有権を持っていたアメリカは、ここで自国で観測を行うという理由で、日本側に丁重とはいえこれを拒否する回答を送ってきました。
どこだかわかりませんが、おそらくは軍事的な要衝地か何かだったのでしょう。
このため、やむなく日本は、国際地球観測年で国威を発揚する場所を「南極」に変更することに決め、ちょうど1955年2月に組織された12か国による共同南極観測に参加させてもらうことにし、これに加わった結果として計画されたのが、この第1次南極地域観測でした。
本来は二ヶ年、2次の観測隊を送るだけで終了する予定でしたが、準備期間が短かすぎ、1955年に開始する予定だった観測は、観測船に予定されていた「宗谷」も旧船を急ぎ改造したものであり、このため十分な装備を整えることができずに断念しました。
さらにこの観測では当初、観測隊出発まで基地の場所さえは決まっておらず、その決定は隊長に一任される予定であったといい、今で考えると考えられないようなずさんな計画でした。
こうして、ともかくも一年をかけて準備をし直し、翌1956年末に出発した南極観測船「宗谷」に乗船した、前述の永田武隊長が率いる第1次南極観測隊53名は、翌年の1957年1月29日に東オングル島に到着。ここを「昭和基地」と命名します。
2月1日から建設が始まり、隊長の永田以下の大部分の隊員が宗谷に乗って離岸する15日までには、「観測棟」が4つ完成しました(うち1つは発電棟)。
南極に残ることになったのは、西堀栄三郎副隊長兼越冬隊長以下であり、この11名が日本人としては初めて南極で6月以降の「越冬」をすることになりました。
樺太犬
ちなみに、日本の夏は、あちら南極では対極の真冬となり、最も寒い8月では、平均気温が-19.4度、最高平均気温でも-15.8度であり、最低平均気温にいたっては-23.3度、過去における最低気温の記録は-42.2度という極寒の世界です。
日照時間は、6月にはゼロとなりますが、7月には4.8時間、8月でも64.1時間であり、このような寒いよ~、暗いよ~、怖いよ~?という場所は、世界でも最も過酷な生活環境といえます。
案の定、この1次隊は、観測器具が凍りつくなどの極度の困難が続いて観測どころではなかったといい、このときに輸送などで活躍し、隊員の大きな励ましにもなったのが犬橇などの荷益のために一緒に連れて行った樺太犬だったといいます。
このとき、11名を残して離岸し、無事日本へ向けて帰港したはずだった「宗谷」も、その後分厚い氷に完全に閉じ込められ、当時の最新鋭艦だった旧ソ連の「オビ」号に救出されています。
第一次隊が南極で越冬後、その翌年の1958年には、1次隊でも隊長であった永田武が再び第2次観測隊を率い、第一次越冬隊員の帰還と、第二次越冬隊員の派遣を実現すべく、前回と同じく「宗谷」によって昭和基地をめざしました。
しかし、このときは、深い岩氷に挟まれたため、宗谷は昭和基地近くの沿岸への接岸を一旦断念。遠く離れた場所に接岸し、ここから第二次越冬予定隊員たちが陸路(氷上)で昭和基地をめざしました。
しかし、宗谷の接岸がなければ一冬を越せるだけの十分な物資の補給もままならないため、天候の悪化もあいまって、第一次越冬隊と第二次越冬隊の全隊員が、いったん、飛行機とヘリコプターで昭和基地から脱出しました。
このとき、第一次越冬隊員と一緒に昭和基地入りした犬のうち15頭はその後の越冬活動のためとして残されてしまいます。越冬隊員らは犬たちの救出のため、昭和基地への帰還を希望しましたが、天候はその後も回復せず、永田は越冬不成立を宣言。結局犬たちは、置き去りにされることに決まりました。
このあたりの逸話を映画化したのが、1983年(昭和58年)夏に公開された「南極物語」であり、南極大陸に残された兄弟犬タロとジロと越冬隊員が1年後に再会する実話を元にドラマチックに描いたフィクションとして描かれ、大ヒットしました。
この映画は、フジテレビが企画製作、学習研究社が半分の製作費を出資して共同製作したもので、日本ヘラルド映画と東宝が配給。北極ロケを中心に少人数での南極ロケも実施し、撮影期間3年余をかけ描いた大作映画でした。
フジサンケイグループの大々的な宣伝が効を奏し、少年、青年、成人、家庭向けの計4部門の文部省特選作品となり、映画館のない地域でもPTAや教育委員会がホール上映を行い、当時の日本映画の興行成績新記録となる空前の大ヒット作品となりました。
その後何度もテレビ放送され、一昨年にもキムタクこと、木村拓哉さんが主演で「南極大陸」としてリメイクされたのを見た方も多いでしょう。
ちなみに、この1958年公開の南極物語のキャッチコピーは、「どうして見捨てたのですか なぜ犬たちを連れて帰ってくれなかったのですか」だそうで、物語の哀感を訴えたいという気持ちはわかるものの、キャッチコピーとしてはちょっと……というかんじですね。時代を感じさせます。
さて、このように1次、2次と多くのトラブルを伴った日本の南極観測隊ですが、当初2次で終了する予定であったものが、2次観測がこうして悪天候により不成立になってしまったため、3次まで延長され、1年後に第3次越冬隊がふたたび昭和基地に到着します。
このときタロジロが発見されて話題になったわけですが、このときに派遣された宗谷には、第三次観測隊のための大幅な改装が施され、大型ヘリコプターによる航空輸送力の強化に力が注がれており、気象状況の悪化により宗谷が基地に接近できない場合でも人や物資の充分な輸送が可能となりました。
3次観測隊が派遣された1959年1月から3月までの間には、観測隊を運んだ宗谷内には、はじめて「宗谷船内郵便局昭和基地分室」も置かれたそうです。
当初、二次だけで終わる予定であった南極観測は、3次観測隊が送られた結果、結局その後も観測は続けられることが決まり、1960年には、第4次観測も実現、越冬が実施されました。
福島ケルン
ところが、この年の10月、この第4次越冬隊員の一人の福島紳氏(当時30才)が遭難し、日本の観測隊における初めての死亡者となりました。その経緯は次のとおりです。
第4次越冬隊の犬係の吉田栄夫は、オーロラ観測係の福島の協力を得て、ロープで係留していた樺太犬にエサを与え、その後二人は、海岸にある橇を固定するため、昭和基地を離れました。
このとき、天候が悪化し、ブリザードが正面から吹き付けるような状態となり、視界はゼロに等しく、結局二人は橇に到着することができず、方向を誤ったと判断した福島は、橇の点検をあきらめて、昭和基地へ戻ろうとしますが、方向を見失ってしまいます。
吉田は、なんとか昭和基地近くの岩まで到達しますが、このとき福島とはぐれたことに気付き、必死で昭和基地にたどり着くと、すぐに仲間とともに福島の捜索に向かおうとしました。
ところがこのとき、不運にももうひとつの遭難が起きており、その遭難救出のために他の隊員が出払っていたため、昭和基地には村石幸彦という隊員一人しかいませんでした。
福島が遭難する3日前、ベルギー隊の6名がセスナ機で昭和基地近くまでやってきたのち、天候が悪化し、ブリザードのためにセスナ機を飛ばせず、ベルギー隊は昭和基地からやや離れた場所にテントを張って宿営していました。
このベルギー隊のうち二名は、激しいブリザードが吹き荒れる中、昭和基地へ助けを求めるためにテントを出ますが、途中で遭難してしまいます。テントに残ったベルギー隊から無線による救援要請を受けた第4次越冬隊は、捜索隊3班を編成し、行方不明になった二人の捜索へ出ました。
ベルギー隊の遭難は福島らの遭難とほぼ同時に起きており、吉田が昭和基地になんとか辿り着いたとき、村石隊員以外全員の隊員がベルギー隊の捜索のために出払っていたのです。
ベルギー隊を捜索中の越冬隊員たちは、福島が遭難したことを知ると、ベルギー隊を支援しつつも福島の捜索も開始。一方、福島の捜索に出た吉田と村石の二人は、再び激しいブリザードのため再び方向を失い、ふたりは二次遭難を避けるために雪原に穴を掘ってビバークして夜をすごしました。
ところが、遭難していたベルギー隊の二人は、その夜自力で昭和基地へ到着していました。翌日、午後三時にはブリザードがおさまったため、吉田と村石も基地へ帰還。第四次越冬隊は、ベルギー隊のセスナ機で、上空から福島を探しましたが、発見できず、日本の南極地域観測統合推進本部は、1960年10月17日に福島新の死亡を決定しました。
福島隊員の遺体は、この8年後の1968年に、基地より約4 km離れた西オングル島で発見されています。
遭難地点には、このときの越冬隊によってケルンが建てられ、このケルンは「福島ケルン」と呼ばれ、1972年に締結された、「環境保護に関する南極条約議定書」では、「南極の史跡遺産」に指定されたそうで、日本としても、「南極史跡記念物」に指定され、今も大事に守られているそうです。
日本の南極観測の長い歴史において、死亡したのはこの福島隊員ひとりであり、その死は悼まれましたが、以後、死亡事故が起こっていないのは、このときのことを教訓として万全の安全体制がとられているからであり、このほかにも連れて行った犬たちが不慮の事故で死ぬといった痛ましい事故は起こっていないようです。
その後、当初2次で終了するはずだった南極観測隊は、結局5次まで延長され、さらに再延長を求める声が高まりました、「宗谷」の老朽化により、1961年出発、1962年帰還の第6次観測隊からは日本の南極観測は中断。この第6次観測では越冬も行われず、その後昭和基地は再び閉鎖されてしまいました。
しかし、その4年後、1965年に最新鋭の南極観測船「ふじ」が竣工し、同時に第7次観測隊が編成され、この年から越冬が再開。その後、1983年(昭和58年)の第25次観測隊および越冬隊の編成時に、観測船はさらに初代の「しらせ」に変わりました
この「しらせ」のネーミングは、言うまでもなく、日本人として初めて南極大陸の探検を行った白瀬中尉にちなんでいます。
1973年(昭和48年)9月日には、昭和基地は国立極地研究所の観測施設となり、以後、国立極地研究所が独立行政法人となった現在まで毎年観測隊が編成され、観測が続けられています。
その後、砕氷艦「しらせ」の老朽化により、観測活動の継続に支障が懸念されましたが、2006年に舞鶴で後継艦の二代目「しらせ」が建造され(2009年(平成21年)5月完成)、同年の第51次南極観測隊および越冬隊からその運用が開始されています。
現在の昭和基地
昭和基地は現在、天体・気象・地球科学・生物学などの天文学、地球物理を総合的に観測するための施設として、大小60以上の棟から成る一大基地になっています。
この中には3階建ての管理棟が含まれるほか、居住棟、発電棟、汚水処理棟、環境科学棟、観測棟、情報処理棟、衛星受信棟、焼却炉棟、電離層棟、地学棟などなどの最新鋭の患側装置を備えた観測棟が連なり、このほかにも、ラジオゾンデを打ち上げる放球棟があります。
荒天時は使用しない特殊な棟を除き、各棟は渡り廊下で接続されており、れは、他国の南極基地で3 m離れた別棟のトイレに向かった隊員が悪天候で遭難死する事故があり、このような事故を防ぐためだといいます。
多くの建物は木造プレハブ構造で、大手住宅メーカーのミサワホームが製造したものが使用されているということで、およそ生活する上においては日本で居住しているのと変わらないほどの設備がそろっており、大型受信アンテナ、燃料タンク、ヘリポート、太陽電池パネルが装備されているほか、貯水用(貯氷用)のダムまであるそうです。
医務室、管理棟、厨房、食堂、通信室、公衆電話室、図書室、娯楽室などの中枢施設は、このうちの管理棟内にあり、医務室には手術が行える設備がありますが、実際は非常時用で手術例はほとんどないといい、重要な手術は「しらせ」などの観測船の船内で行われるようです。
南極観測隊の発足の当時に資材の運搬用に導入された樺太犬など犬ぞり用の犬は、その後環境保護に関する南極条約議定書により生きた動物や植物等の南極への持ち込みが禁止されたため、現在はいないそうです。
かわりに、全天候型の雪上車が導入され、現在南極観測隊で使用されている「SM100S」シリーズは、車両重量は11トン、稼動時マイナス60℃、未稼動時マイナス90℃の耐寒性能を持ち、3800mの高地で使用可能といい、最大牽引は約21トンと世界的にも特筆される性能を持っているそうです。
現在、南極地域観測隊員は約60名で、そのうち約40名が越冬します。翌年度の隊が来た観測船で前年の越冬隊が帰国するため、基地には常に人がいることになり、越冬交代式は近年通常2月1日に行われるそうです。隊員の多くは国家公務員の男性ですが、専門技能を持った民間企業の社員や、「みなし隊員」として民間企業出向の女性も派遣されています。
ちなみに、昭和基地を含め、南極大陸には現在永住している人はいないそうです。しかし多くの国が恒常的な基地を大陸上に設置しており、多くの研究者が科学的研究関連の業務に従事しています。
その数は、周辺諸島を加えると冬には約1000人、夏には約5000人程が常駐しているとのことで、多くの基地には1年を通じて滞在し越冬する研究者もいるということです。ロシアのベリングスハウゼン基地には、2004年に正教会系の至聖三者聖堂が置かれ、年度交替で1-2人の聖職者が常駐しているといいます。
これらの多くの「南極の住人」は、「南極光」とも呼ばれるオーロラを常に目にしていることでしょう。太陽風のプラズマが地球の大気を通過することで発生する光学現象であり、このほかにも、太陽光の異常屈折がもたらすグリーンフラッシュといわれる現象や、細氷(ダイヤモンドダスト)といった、極寒の地ならではの現象もみることができるといいます。
ダイヤモンドダストは、晴天か晴天に近い時に発生するため、「天気雨」の一種と考えられているそうで、これに伴って「サンピラー(sun pillar)」という現象がおこることもあるとか。
これは大気光学現象の一種であり、日出または日没時に太陽から地平線に対して垂直方向へ炎のような形の光芒が見られる現象だそうで、実物はもっとすごいのでしょうが、写真で見ただけでもすごい現象のようです。
最近は、こうした研究者のみならず、一般人も南極に行くことのできるツアーもあるようで、それなりの旅行料金は取られるのでしょうが、こうした誰でもみることができるわけではない現象を見ることができるのなら、ちょっと行ってみたい気はします。
とはいえ、おそらく一生、南極など行く機会はないでしょうが、それでも生きているうちに月や火星に行くことができる確率よりははるかに高い確率でそのチャンスはめぐってくる可能性は残されています。私が大金持ちになる確率のほうが高いでしょうが……
さて、今日は、まだまだ、寒い中、何を思ったかこれより寒い南極についての話題を書いてきましたが、いかがだったでしょうか。
暑いときには逆に暑いものを食べるとバテないといいますが、寒いときには寒いなりに温かいものを食べたほうがよさそうです。
先日から私の風邪をもらってしまい、寝込んでしまったタエさんのため、今日は(も)鍋にすることにしましょう。鍋ときどきカレー、ところによりおでん……です。ちなみに昨夜の我が家はカレーでした。みなさんの今夜の御献立はなんでしょうか。