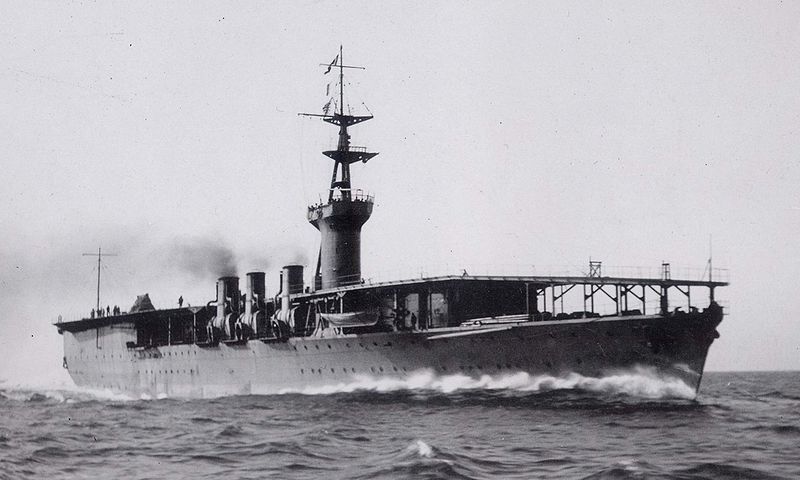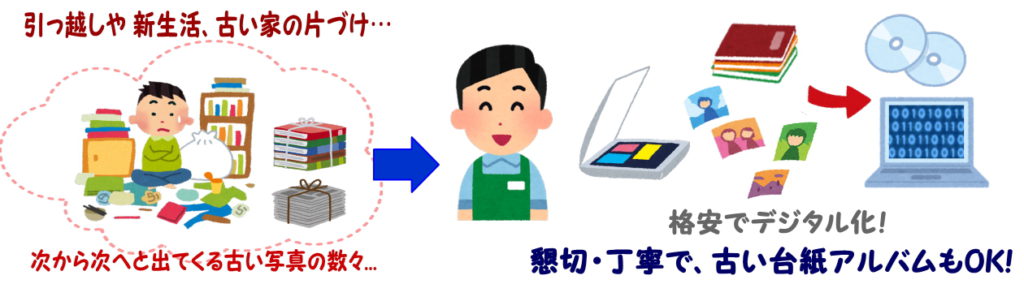さて、今年も残るところわずか3日になりました。来年の干支(えと)は巳ということで、ヘビの年なので、これにちなんで、お金持ちになれるよう期待したいところです。
このヘビ年だのウマ年だのというのは、誰もが知っている十二支にちなんでおり、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12匹の動物は、誰もが子供のころから慣れ親しんできたものでしょう。
それぞれ音訓2通りの読み方があり、このうちの訓読みのほうの「ね、うし、とら……」のほうは誰もが諳んじて言えると思いますが、音読みのほうはどうでしょうか。
これは、子年から順番に、「し(子)、ちゅう(丑)、いん(寅)、ぼう(卯)、しん(辰)、し(巳)、ご(午)、び(羊)、しん(猿)、ゆう(酉)、じゅつ(戌)、がい(亥)」だそうで、こちらはさすがに全部読める人はあまりいないのではないでしょうか。無論、私もそうでした。
この十二支のことを「地支」というのに対して、「天支」というのがあり、これを「十干(じっかん)といいますが、こちらは、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素の順列です。
天干(てんかん)とも言うそうで、十二支も十干も古代中国で考えられ、日本に伝えられました。現在の日本では、干支(えと)というと十二支だけを指すように思われていますが、本来中国では、この十干と十二支を合わせた暦のことを、「干支」と呼んでいました。
この十干については、再度後述します。
そもそも十二支も十干も古代中国で考案された日付を記録するためのしくみです。「殷(いん・紀元前17世紀頃~紀元前1046年)」の時代にはまだ紙が発明されておらず、亀の甲を紙代わりに使い、ここに文書記録を残したものを「甲骨文」といいますが、この殷の時代の甲骨文の中に、既に十二支や十干の用語が出てくるそうです。
日本にこれが伝わった時期については不明ですが、7~10世紀の律令制の時代には既に陰陽師などがこの暦を使っており、その後の戦国時代ころまでには、日付だけでなく、年・月・時刻・方位の記述にも利用されるようになりました。
中国からは天文学も日本にもたらされ、この中では、「十二辰」という概念ももたらされましたが、これは天球を天の赤道帯に沿って東から西に十二等分したものをさしており、その呼称として「十二支」が当てられました。
中国の天文学ではまた、木星が約12年で天球を西から東に一周することから、天球を「十二次」と呼ばれる分割方法によって分割し、周期運動する木星の位置を記録していました。
しかし、これは十二辰で定めた天球分割の順番に対しては逆方向であったため、紀元前4世紀ごろ、十二辰の方向に合わせるべく木星とは逆回りに天球を巡る「太歳(たいさい)」という架空の星を考え出しました。
そしてこの毎年の「太歳」の天球における位置が、どの十二辰にあるかを示す紀年法が使われるようになり、その年の十二辰に該当する十二支の名で、その年を「○○年」呼ぶようになりました。これが現在まで使われている「干支(えと)」との起源です。
また、太陽の周りを一年かけて回る地球の1年をこの十二辰の数「12」で割り、これを「月建」と呼んだことから、これが現在の○月という呼び方に発展しました。さらに、時刻も十二辰で割り、「十二時辰」とされ、さらに十二辰は方位の表示にも用いられるようになりました。
「正午」とは、昼の12時を指しますが、この「午」から数えて六つめの「子」を使って「正子」と書き、これは夜の12時のことをさします。
また、赤道に直角に南北を結ぶ「経線」のことを「子午線(しごせん)」と呼びますが、これもこの十二辰の用法の発展です。現在使われることはありませんが、「卯酉線」というのもあり、これは「緯度線」と同じものです。ただし、中国天文学の「卯酉線」は、局所的には一致するものの、現在の緯線と厳密には異なるそうです。
さて、この中国天文学における十二辰の呼称である「十二支」の各文字として、何故動物名が使われることになったかですが、そもそもこれは動物ではなく草木の成長における各相を象徴したものではないかといわれており、中国の漢の時代の歴史書「漢書」にそのことが書かれているそうです。
草木の成長のそれぞれの過程に名前が割り当てられていたわけで、中国ではこれを古くは「十二生肖(せいしょう)」と呼んでいたそうです。
その後「十二生肖」にはそれぞれに動物を割り当てるようになりましたが、もともとの古代中国における十二生肖は、植物の生長過程を現したものですから、動物とは関係なく、単に順序を表す記号であったようです。
これがなぜ動物と組み合わせられたかについては、諸説あるようですが、どちらも十二であることから、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説が有力です。
ただ、現代のイラク付近にあった「バビロニア」の天文学が中国に伝来し、この中の「十二宮」に割り当てられていた動物が中国でも馴染の動物に化けたのではないか、といった説もあるようです。
その後、日本に伝来した十二支ですが、日本ではこの中国天文学を多少アレンジし、同様に伝わった先ほどの「十干」と組み合わせ、「甲子」「丙午」のようにして暦で使うようになりました。
木(もく、き)・火(か、ひ)・土(と、つち)・金(こん、か)・水(すい、みず)の五つの要素のことを「五行」といいますが、これそれぞれに「陰」と「陽」が割り当てられており、5×2=10 となったものが十干(天干)を構成します。
古代殷の時代には、10個の太陽が存在してそれが毎日交代で上り、10日で一巡りすると考えられており、十干はそれぞれの太陽につけられた名前と言われています。この太陽が10日で一巡りすることを「旬」と呼び、現在我々が使っている上旬、中旬、下旬と言う呼び名もこれに由来します。
日本に伝来してからは、陽を兄、陰を弟と呼ぶようになり、この「兄弟」は日本でのもともとの読みが「えと」であったため、いつのまにやら中国から伝わった十二支と十干を組み合わせた暦であった「干支」という用語も日本では「えと」と読むようになったといわれています。
現在の日本人にはあまりなじみのない十干ですが、それぞれ意味があって、それは以下のようになります。
甲(こう・きのえ):木の兄。草木の芽生え、鱗芽のかいわれの象意
乙(おつ・きのと):木の弟。陽気のまだ伸びない、かがまっているところ
丙(へい・ひのえ):火の兄。陽気の発揚
丁(てい・ひのと):火の弟。陽気の充溢
戊(ぼ・つちのえ):土の兄。“茂”に通じ、陽気による分化繁栄
己(き・つちの):土の弟。紀に通じ、分散を防ぐ統制作用
庚(こう・かのえ):金の兄。結実、形成、陰化の段階
辛(しん・かのと):金の弟。陰による統制の強化
壬(じん・みずのえ):水の兄。“妊”に通じ、陽気を下に姙む(はらむ)の意
癸(き・みずのと):水の弟。“揆”に同じく生命のない残物を清算して地ならしを行い、新たな生長を行う待機の状態
この十干「干」と十二支の「支」を組み合わせたものが「干支(かんし)」ですが、10通りの要素と12通りの要素を掛け合わせるといろんな形の暦ができます。
「還暦」という言葉がありますが、これは、12年サイクルである「十二支」が「十干」の半分である5回分回って一巡した年、つまり、12×5=60ということで、60才のことを還暦というのです。
また、十干を表す甲・乙・丙……という順列を頭にし、十二支を表す子・丑・寅……という順列と組み合わせると、60通りの組み合わせをつくることができます。本来は120の組み合わせができるはずですが、120周年サイクルは長すぎると考えたためか、60どまりになっています。この60の中に同じ組み合わせはありません。
そして、例えば甲と子を組み合わせた年を「甲子(きのえね)」の年と呼ぶ慣わすようになり、これがすなわち「干支(えと)」です。60通りあることから、六十干支とも呼ばれますが、一般的には「干支」で通っています。
60通りしかありませんから、60年経つと、また最初の「甲子」に戻りますが、昔の人の寿命はだいたいそれぐらいだったことと、また寛政や天保といった年号がありますから、「天保○○年庚申」などと書くと、ああこの年か、とその年を特定できるわけです。
ちなみに、今年2012年は、「壬辰(みずのえたつ)」で六十干支の順番でいくと29番目になります。また、来年2013年は、「癸巳(みずのとみ)」です。
なお、話がさらにややこしくなるので、適当にやめますが、十干には、「五行」である木・火・土・金・水、毎の兄弟(陰陽)の十通りの組み合わせにはそれぞれ意味(性質)が割り当てられていて、なおかつ、十二支のそれぞれにも五行に基づいた意味(性質)が割り当てられています。
例えば来年の十干である「癸」は「陰の水」であり、十二支である「巳」は、「陰の火」となりますが、この年年に異なる組み合わせで、その年がどんな年かが定められています。
それによると、今年の「壬辰」は、「土剋水」といい、これは「土は水を濁す。また、土は水を吸い取り、常にあふれようとする水を堤防や土塁等でせき止める。」という意味です。
また、来年の「癸巳(みずのとみ)」は、「水剋水」であり、これは「水は火を消し止める。」という意味を持ちます。
これをどう解釈するかは、みなさんのご想像におまかせしますが、私はこの「土で水が汚れるけれどもその土が逆に水を堰き止めてくれる」というのを、「いろいろと問題の多い年ではあったが、なんとか踏みとどまることができた」と解釈してみました。
ちなみに、東日本大震災や原発事故のあった昨年の干支は、辛卯(かのとう)であり、その性質は「金剋木」であり、この意味は「金属製の斧や鋸は木を傷つけ、切り倒す。」でした。まさに天災や人災が我が国の資産や人々を傷つけ、「切り倒した」年であったわけです。
だとすると、来年の干支である「癸巳」の「水は火を消し止める。」は、長かった我が国の災いもようやく「消し止められる」という意味になるかもしれません。期待しましょう。
さて、このように、十干と十二支を組み合わせた暦のことを、古くは「えと」と呼んでいましたが、今日では十干のほうはすっかり廃れてしまい、こうした古い暦は使われなくなり、「干支(えと)」と言えば十二支だけの代名詞になってしまいました。
「十干」は忘れられつつあり、せいぜい酒類の品質表示として「甲乙丙丁」などのグレードを表す言葉として使われているぐらいで、他のグレードもほとんどが「ABC」になってしまっています。
そして、動物イメージを付与されることによって具体的で身近なイメージを獲得した十二支のみが、現代の文化の中にかろうじて生き残っています。
近年ブームとなっている風水は、この十二支だけを用いたもので、東西南北の四方位が十二支の子・卯・午・酉に配当されるのに加えて、北東・南東・南西・北西はそれぞれ「うしとら」「たつみ」「ひつじさる」「いぬい」などと呼ばれ、これに該当する八卦には、また別途、「艮」「巽」「坤」「乾」などの新しい仕組みの文字があてられ、それぞれに意味を持たせています。
ちなみに、北東は「艮(ごん)」と呼び、これは「鬼門」とされ、同じく「坤(こん)」と呼ばれ、「裏鬼門」される南西方向とともに忌み嫌われています。
これは、北東方向が「うしとら」であるため、ウシのような角をはやし、トラの皮のふんどしをしめた「鬼(オニ)」がいるというイメージが定着したものといわれます。が、南西方向は未申(ひつじさる)ですが、猿の形をした羊なのか、羊の形をした猿なのかよくわかりませんが、あまり迫力はありませんね。
この十二支は、城郭建築における建物のネーミングにも使われており、曲輪(くるわ)の四隅に置かれた「櫓(ろ)」は防御の拠点ですが、「辰巳櫓(たつみろ)」などのように、方角の名称をあてて櫓の名称とする習わしがあります。
また江戸には、「辰巳芸者(たつみげいしゃ)」と呼ばれる芸者さんたちがいましたが、この芸者さん達は、江戸城の南方にあたる、深川仲町に住んでおり、この方向が辰巳の方向であったことから、この界隈にあった遊郭を「辰巳の里」と呼んだことにちなんでいます。
この遊郭は幕府公認の遊里ではなかったために、辰巳芸者は男性名を名乗り、男が着る羽織を身につけたため、「羽織芸者」とも呼ばれましたが、「鉄火で伝法」、「気風(きっぷ)がよくて粋」ということで、江戸っ子の間では人気の芸者衆だったようです。
さらに、十二支は、航海用語にも取り入れられており、船舶航行時に使われた「おもかじ」「とりかじ」という言葉は、「卯面梶」「酉梶」から来ているとする説もあります。
このように、十二支は日本の文化にすっかり溶け込んでいますが、その「輸入元」である中国で使われている十二支とは少し違っています。
中国では十二支のことを依然「十二生肖」と呼んでいるようですが、このほか「十二属相(じゅうにぞくしょう)」とも呼ばれています。日本の十二支に相当するのが、「鼠・牛・虎・兎・龍・蛇・馬・羊・猿・鶏・犬・豚」であり、その内訳を見ると「豚」だけが日本のイノシシと違っています。
このように豚に変わって猪を十二支に加えているのは、近隣諸国の中では日本だけだそうです。これはおそらく日本ではあまり動物の肉を食べるという習慣がなく、もし動物を必要とするとしてもその都度狩猟によって捕獲していた「狩猟文化」の国であったため、豚や牛などの家畜を飼うという風習がなかったためと考えられます。
「猪」は、本来はブタを意味する漢字だそうで、本来は豚を意味していたものが、日本人にとっては狩猟をおこなうことで目にしやすいイノシシの意味になり、十二支にもこちらが加えられるようになったようです。
中国以外の国では、ベトナムやタイ王国にも十二支にあたるものがあるそうですが、これらの国でも割り当てられる動物に若干の違いがあり、ベトナムでは丑は水牛、卯は猫、未は山羊だそうで、亥はやはり中国と同じ豚です。
タイでは未が山羊、亥は豚ですが、その他は日本と同にということです。さらにモンゴルでは寅の代わりに豹(ひょう)を用いるそうで、インドでは酉は「ガルーダ」と呼ばれる神話に出てくる神鳥であり、アラビアでは辰がワニに、ブルガリアでは寅が猫にそれぞれ置き換わるということです。
意外にもロシアでも十二支は親しまれているそうですが、日本や中国のように暦として定着するほどのものではなさそうです。が、大きな町などへ行くと、露店などで十二支の置物などを普通に売っているとのことで、おそらくは中国からの輸入文化として定着したものでしょう。
さて、日本でこうしたおなじみの十二支ですが、ほかにも多々いる動物の中からこの12種類が選ばれた経緯については、いろいろ語り継がれてきた伝説があります。
そのひとつは、次のようなものです。
あるとき、お釈迦様は動物たちから新年の挨拶を受けることになりました。ちょうど、十二支の干支を決めようと思っていたお釈迦様は、これは良い機会だと思い、新年の挨拶に来た順番に十二支の動物を割り当てることにしました。
お釈迦様の招集により、その指定された会場へ指定日にぞくぞくと動物が集まってきました。
牛は足が遅いので早めに行ったのですが、一番乗りしたのは牛の背中に乗っていて、到着する直前にここから飛び降りて会場へ駆けつけた鼠でした。このため、牛は二番目になってしまいました。
鶏も会場へ向かおうとしましたが、行こうとしたら猿と犬が喧嘩をしていたので、この仲の悪い二人を「仲」をとりもつことにしたために、猿と犬の間に入って会場に到着することにしました。
一番乗りした鼠ですが、会場へ行く途中、猫に挨拶に行く日を尋ねられ、このとき嘘をつき、実際よりも一日遅い日を教えました。このため猫は十二支に入ることができず、これを根に持った猫は、それ以後、鼠を追いかけまわすようになりました。
鼠の嘘を信じて一日遅れて挨拶に行った猫は、お釈迦様から「今まで寝ていたのか。顔を洗って出直して来い。」と言われ、それからよく顔を洗うようになりました。
こうして、十二番目に猪が会場に入り、めでたく十二支が決まりましたが、13番目に会場に入ったのは鼬(イタチ)でした。十二支に入れず、くやしがるやら悲しむやらのイタチをかわいそうに思ったお釈迦様は、それから毎月の最初の日を「ついたち」と呼ぶように、と他の動物たちに言い渡しました……
こうしたお話は代表的なものであり、地方によってはまたいろいろ違ったバリエーションがあるようです。13番目の動物はカエルやシカであったという話もあるそうで、自分なりにまたストーリーを考えてみるのもまた面白いかもしれません。
さて、昨日は一日雨模様でしたが、今日は朝から陽射しに恵まれるようになりました。年末年始のお買いものにもいかなければなりませんが、お釈迦様に叱られた「猫」が破った障子も張り替えなくてはなりません。
それが終われば残すところはあと二日。確かに「いろいろと問題の多い年ではあったが、なんとか踏みとどまることができた」年だったようにも思います。来年は干支どおり、「水で火を消し止める」ことができるような一年になるでしょうか。期待したいところです。