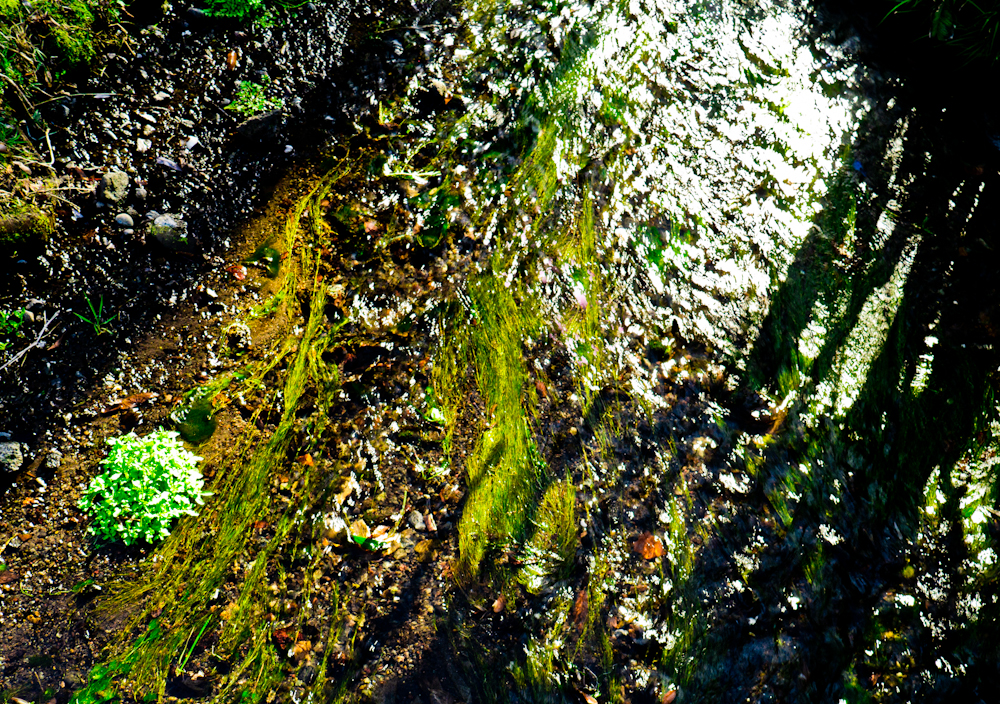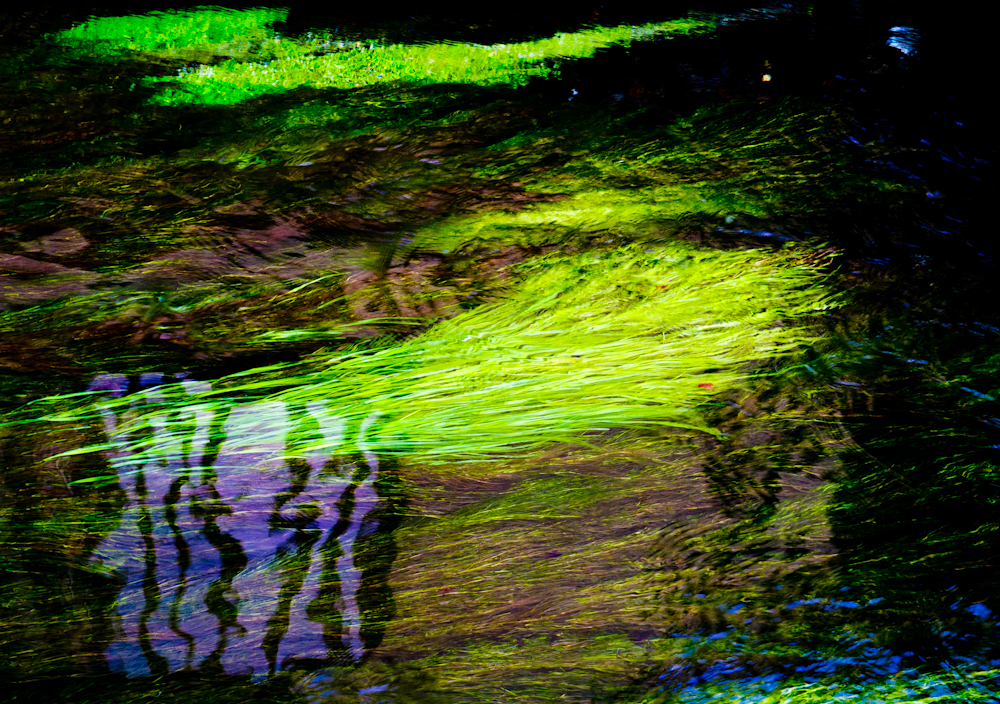昨日のお昼、テレビを見ていたら、先日山口の周南市で殺人事件を引き起こした男性が警察に拘束された際、これとほぼ同時刻にこの男が飼っていたレトリーバーが死亡した、という報道がされており、ちょっとびっくりしました。
犬のほうは、男が行方不明になってから保護され、動物愛護団体がケアをしていたそうですが、その死因は心臓発作ということで、怪我をしていたとかエサが足りなかったとかの理由ではないそうです。
飼い主がいなくなったことで、ストレスが溜まっていたためではないか、とまことしやかに動物学者さんがコメントを加えておられましたが、死亡時刻が男の拘束時間と一致したという点についてはとくに言及はなく、この報道もその理由についてはうやむやに終わってしまいました。
飼い主と遠く離れていてもその無念の気持ちが伝わってのではないか、とこの報道番組のゲストさんがコメントされていましたが、だとすると、これはいわゆる「テレパシー」にほかなりません。
テレパシーとは、一般には人間同士で、ある人の心の内容が、言語・表情・身振りなどによらずに、直接に他の人の心に伝達されることを指すようですが、人間と犬などの動物の間でもこうした超常的な情報交換システムのようなものがあるのかどうか、調べてみました。が、科学的に証明されたというような情報は得られませんでした。
しかし、人間は物質文明の発達によって本来持っていた霊的感覚が鈍り、次第に五感に限られた世界のみで生きるようになりましたが、人間以外の動物たちには依然そうした超常能力は残っているのではないか、と考える人達もいるようです。
また、動物の中でもいわゆる「ペット」として、人間の愛情によって縁が生じた動物たちには、人間と似たような精神的資質が発達し、人間との間にコミュニケーションを図るために独特のテレパシーの進化が促進されているのではないか、と考える人もいるようです。
その真偽はよくわかりませんし、何も実証されているわけではありませんが、動物のテレパシーの能力は人間よりもはるかに発達しているのではないかという人もいて、これを裏付けるような事例についてもたくさん報告されているようです、
例えば、こういう逸話があります。
イギリスの動物保護協会に勤めている女性の愛犬で、ウェールズ産のテリアだそうですが、この犬にはそうした能力があるのではないか、といわれているそうです。
この犬は、この女性も飼い始めた時からかなり賢い犬だと思っていたそうです。日々の散歩はメイドに任せ、彼女が一緒に連れ出していましたが、これとは別に、毎朝彼女が勤めに出かける前に近くの丘へひとりで遊びに行かせるなど、放し飼いにしていたといいます。
しかし、ひとりで遊びに出かけるときも、その帰りの時間は実に正確で、必ず30分ほどで帰ってきて、出かける準備をする彼女の部屋のドアを足で叩いていたそうです。
ところが、いつもよりその帰りが遅い日がありました。女性はもうすぐ出かけなければいけないというのに、車にでもひかれたのかと心配になりましたが、何を思ったのか、とっさに心でこの犬に呼びかけてみることにしました。
姿勢を正して静かにし、この飼い犬のイメージを心に描きながら、「すぐに帰っておいで」というメッセージを繰り返してみたところ、すると、驚いたことに2~3分後にこの飼い犬はいつものようにドアを叩く音とともに帰ってきたそうです。
これ一回だけだったら偶然ということも考えられます。しかし、その後も同じことが何度もあり、その都度、犬はまるで彼女の心の声が聞こえたかのように帰ってくることが繰り返されたことから、彼女もどうやらこれは偶然ではない、と思いはじめるようになりました。
そう思えるもう一つの理由は、彼女が心の呼びかけをせず、この犬が普通に散歩して帰ってくるときには、音もなく静かに家の中に入ってきたそうですが、彼女が呼びかけたときには、ハアハアと息が切らしており、あきらかに猛スピードで帰ってきているらしいことでした。
このほかにも、この犬には彼女のテレパシーが伝わっているのではないかと思わせる出来事がありました。
彼女が仕事から帰ってくる時間はいつもだいたい決まっているのですが、この犬はそのことをわかっているようで、習慣的にいつも彼女が帰ってくる30分ほど前までには玄関にしゃがんみ込んで、彼女の帰りを待っているのが常でした。
ところがある日、女史がいつもより早目に帰宅したことがありました。帰宅した彼女はこの飼い犬の姿が家の中に見えないので、どこへ行ったかを家の者に聞いたところ、その家人の答えはメイドが散歩に連れて出たというものでした。
それから10分ほど経ったあとのことです。この時刻が彼女がいつも帰宅する時間でしたが、このとき道路の向こうのほうから、この犬が猛然とダッシュしながら自分に近づいてくる姿が見え、その後にはこれを必死で追いかけようとするメイドの姿が見えたのです。
メイドによれば、犬と一緒に家からはかなり離れた池のそばを散歩していたところ、彼は急に立ち止まり、くるりと向きを変えて猛スピードで家の方へ走り出したということで、あわてて呼び止めようとしましたが、振り向きもしなかったというのです。
いつもなら、もう帰ろうと言っても帰りがたがらないのに、このときはどうしたことかと思ったとメイドは不思議がっていました。
これをどう解釈するかについては人によってさまざまでしょうが、女性が帰る時間になったので、この犬も「体内時計」でそのことをふと思い出し、帰ってきたのではないか、と考えることもできるでしょう。
しかし、見方を変えれば、いつも女性が帰宅した時に門前にいる犬が出迎えてくれないことを不審に思い、その念が、テレパシーとなって飛んでいき、これをこの犬がキャッチしたのではないかと考えることもできます。
この例は、賢い犬の中には、飼い主のテレパシーが通じるものもいるということを思わせる一例にすぎませんが、次の例は、単にテレパシーの域を出ず、犬にこれ以上の能力があるかもしれないと思わせるものです。
同じイギリスに、A・E・ディーンという女性がいますが、この女性は心霊写真を撮る能力がある「霊媒」としてイギリス国内でも有名な人です。コナン・ドイルの死後、この心霊写真を撮ったことで有名で、ある実験会で、ドイルと霊界通信をし、彼の指示によって撮影した写真を現像してみると、確かにドイルの顔が写っていました。
この写真は英国中で評判となり、念のためにドイルの奥さんにこれを確認してみてもらったところ、メッセージを送ってきたドイル本人であることが確認されたそうです。
このディーン女史は、一匹のセントバーナード犬を飼っていましたが、この犬にもかねてから霊視能力があるのではないかといわれていたそうです。この犬は、客人が来ると、必ず女史と一緒に出てきて、うしろ脚で立ち、前脚を客人の肩に置くのが習慣だったそうです。
これがこの犬の挨拶であり信愛の情を示すしぐさなのですが、大きな犬ですから、大人でもこの挨拶によって後ろに倒れそうになってしまうほどでした。
ある日のこと、このディーン女史の友人がその旦那さんと共にといっしょに訪ねてきたそうです。
ところが、この夫婦はどうやら“見えざる客”と一緒に女史を訪れたらしく、この犬はこの我々には見えない客を同じ生身の人間と間違えたようです。
そしていつものようにうしろ脚で立ち、前脚を持ち上げる仕草をするのですが、その脚が空を切って、どすんと床に落ちるたびに、おかしいなといった表情をしながら、それを何度も繰り返したといいます。
このことから、この犬にはそこに誰かが立っている姿が見えたのではないか、と女史は考えたというのですが、いかんせん、普通の人間には見えない存在ですから、なかなか信じがたいことではあります。
しかし、同じように犬や猫といったペットには人間には見えないものが見える、という話はよく聞きます。
かくいう我が家のテンちゃんも、この家に来てからはほとんどありませんが、以前東京で借りていたマンションでは、何もないはずの部屋の中空を見つめている、というのを何度か目撃しました。
何が見えるの?と聞いても身じろぎもせずにそちらを向いているのですが、無論、私たちには見ることができません。多少霊感のある私にもこのときは何も感じなかったので、「ヘン」なものではなかったのでしょう。
多分に敵対的な霊であったりする場合、猫などではときにこれに感応して毛を逆立たせたり、尻尾を大きく膨らませて一目散に逃げたり、といったことも聞いたことがありますし、そうしたものなら私も鳥肌立てていたことでしょう。
おそらく、ペットを飼ったことがある人は、似たように、時々誰もいない壁や空間をじっと見つめていたり、見えないものをしきりに目で追っていたりする彼等の姿を見かけたことが一度や二度はあるのではないでしょうか。
ま、こうしたことを信じる信じないはお任せしますが、こうしてみると、山口の動物愛護団体で亡くなったというこのワンちゃんも、おそらく見えない主人の姿を闇夜で霊視し、彼の心の叫びをテレパシーで聞いていたのかもしれません。
その死との因果関係もよくわかりませんが、打ちのめされた人間の弱い心がその死を縮めたのかもしれません。あるいは、その死によって、容疑者の男のこころを慰めてやろうとしたのかも。
このように可愛がっていたペットが、その死後も飼い主の側を離れない、という話もよく聞きます。
イギリスのある海軍将校は、スキッパーキ種というスピッツタイプの犬を飼っていました。とても偏屈な犬だったそうで、どの犬とも仲良くならず、散歩途中で違う犬とすれ違う時には、うなり声をあげてその犬を追っ払うのが常だったそうです。
しかし、飼い主の将校にはとてもなついていました。14歳ほどの年齢で他界しましたが、その後何かの機会にある霊能者がこの将校を霊視したところ、その死後もこの飼い主の側にいつもついている姿が見えたそうです。
その後、この将校はしばらく犬を飼うことはしていなかったそうですが、もともと犬好きなので散歩などで出歩くたびに見かける近所の犬をみて亡くした愛犬を思い出していたようです。
そうした近所の犬の中に一匹にメスのテリアがいて、この犬も将校には良くなついていたそうです。将校がスキッパーキを伴って散歩していないときなどには、通りで見かけるとすぐそばに寄りそってくるほどだったそうです。
ところが、愛犬を亡くした後のある日、一人で町を散歩に出かけた際、このテリアを見かけたので、いつものように近づいていって頭を撫でてやろうとしたところ、なぜかその日だけは彼を恐がるように避け、通路のわきへ寄ろうとしたそうです。
遠巻きに将校を見つめるだけで、なぜかいつものように近くに寄ってこないため、初めのうちはなぜだろうと不審に思っていましたが、そのうち、かつて霊能者に見てもらったときのことを思い出しました。
将校が亡くなった犬の霊と一緒に歩いているのをみて、これを見たテリア恐がったというわけです。ウーという声こそは聞こえませんでしたが、おそらくは歯をむいてテリアを睨みつけ、彼女を威嚇していたのに違いありません。
このほかにも、飼っていた犬や猫が、飼い主の守護霊になることもあるという話をときどき聞きます。
ただ、死んでから守護霊になるだけではなく、生きているうちから、飼い主のことを守ってくれていることも少なくないそうです。
だとすれば、この山口のワンちゃんもその守るべき飼い主の存在が近くにいなくなったことに気付き、それならばということで、死して守護霊になる道を選んだのかもしれません……
もっともこうした動物と人間の間に存在する超常能力といったものは、相手が物言えぬ動物であるだけに科学的には立証できにくいのもではあります。霊が見えたの?と聞いて答えてくれたとしても、ニャンとかワンではイエスなのかノーなのかさっぱりわからないわけですから。
しかし、人間と人間の間のテレパシーならば立証できるかもしれないということで、過去にそうした実験が実際に行われています。
例えば、神経科学の専門家の間にはよく知られているという専門誌「Neuroscience Letters」に、2003年、こうした実験の報告論文のひとつが掲載されました。
この科学誌は、かなりまじめな医学専門誌だそうで、この論文によれば、この実験を行ったドイツの科学者たちは、脳波測定とfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を駆使して実験を行い、その結果として、「二人の隔離された人間の間で脳活動が同期発生する」という可能性を示したというのです。
「脳活動が同期発生する」というといかにも専門的でわかりにくいのですが、ようするに「テレパシー現象を確認できた」ということのようです。
この実験では、23歳から57歳までの一般市民男女38人が被験者として採用され、その内訳はこのうちの、10組、20人は、夫婦・友人・親類など、互いに感情的に「関係がある(つながりがある)」と感じる人たちでした。
一方残る人達の中からは7組14人を「関係がない」と感じる他人同士としてペアを組ませ、これとさらに残る4人をランダム選択しました。
そして、この「互いに関係がある」と感じる10組の中うちの7組と、「関係がない」という7組のそれぞれを「対象群」として比較実験を行い、また「関係がある」と感じる残り3組と、4人の個人被験者を対照群とした比較実験が進められました。ただし、「関係がある」と感じる10組の中にも双生児は含まれていなかったそうです。
このように被験者をグループ分けしたのは、意味付けが異なるそれぞれのグループでの実験結果を比較することによって、実験結果が人為的に造られたものではないことを立証することが目的でした。
実験の内容としては、対象群それぞれのペアの2人に1人ずつ、隣り合う部屋に入ってもらい、この部屋は外部から音も光も遮断され、電磁気的にも隔離された密室となっていました。
そして、片方の被験者に部屋のビデオスクリーンを通じて、一定の視覚刺激パターンを見せました。このパターン提示は1秒間で、これは3.5秒から4.5秒間隔で、72回提示するといいうものでした。
またこれと同時に、隣室にいるもうひとりの被験者は、静かに待機しているだけで視覚刺激は与えられません。
両方の被験者の頭部には6箇所に設置した電極から、脳波を記録が記録されます。どちらの場合でも、被験者たちは、お互いが隣室で何をしているのかは、まったく知らないとう状況下で実験は進められました。
こうして科学者たちは、この実験で得られた被験者の脳波の測定記録を小さな時間単位(137ミリ秒)ごとに分割し、それぞれの単位内で、視覚刺激を受けなかった方の被験者の脳波に起こる「揺らぎ」の発生頻度を分析してみました。
すると、驚くべきことに、視覚刺激を受けた被験者の視覚性の脳波の電位が最大となったのと同じ時間に、視覚刺激を受けなかったもう一人の被験者の脳波にも、通常時の電位変化とは明らかに違う変化が頻繁に起こっていることがわかりました。
複数以上のペアにおいて、視覚刺激を与えられた被験者と、「受信者」にあたる刺激を与えられなかった被験者のそれぞれの脳の中で、ほぼ同時に大きな電位変化が生じるのが確認されたのです。
さらに面白いことに、この脳波の「揺らぎ」現象は、被験者ペアの「親密さ」とは、関係なく発生していたということです。つまり、いわゆる「赤の他人」同士でも、脳波の伝達が起こったということが確認されたのです。
ドイツ人科学者たちはこの実験の結論として、「この現象は方法上の欠陥で生じたとは考えにくいものであり、しかもその性質を理解するのが困難な現象である。(中略)この現象を説明できる生物物理学的メカニズムは現在のところ知られていない」とだけ述べ、この現象がテレパシーと呼べるかどうかまでには言及しませんでした。
同様の実験は、この翌年にもアメリカ人科学者たちによって行われました。米国カリフォルニアの「ノエティックサイエンス研究所」というところで行われたもので、結果は2004年に論文発表されています。
この実験では、11組の成人カップルと、2組の母娘のカップルが被験者として採用されました。
実験の内容としては、各カップルに「互いにつながりを持っているという感覚(feeling of connectedness)」を持ち続けるように要請し、これに集中できるように、指輪や時計などの個人的な品をカップル内で交換させ、実験中ずっと握っているように指示するというものでした。
そして、カップルには相談して、どちらが「思い」を送る側で、どちらが「思い」を受ける側になるか決めてもらい、その後、お互いから電磁気的に隔離された個室に一人ずつ入りました。
次に、送り手が受け手に「思い」を送るスタート合図として、送り手に対して、別室で待機している受け手のビデオ画像がライブ放映されました。ライブ画像は1回あたり15秒でこの画像は実験時間中、17~25回、ランダムな間隔で提示されました。
しかし、送り手は、受け手の画像がモニタに映ったら、受け手の個人的な品を手に握り、その人のことを思いますが、受け手の側は、いつ自分のライブ画像が別室で放映されているのかは全く知らないという条件下におかれました。
受け手はその状態で、個室において送り手のことを思い続けている、というだけの状態に置いたのです。
こうしてて各カップルの頭部に電極が設置され、脳波が同時に測定されました。
その結果としては、前年のドイツ人科学者たちの実験結果と似たような結果となりました。
ビデオ画像の放映が開始されると、それを見た人物(送り手)の脳波には、これを見たことによる「誘発電位」の揺れが生じましたが、この時受け手側の脳波にも、やや遅れてではありますが、明らかに脳が活動したことを示す揺れが生じたのです。
また、ビデオを見た送り手の視覚性誘発電位が強く出ている場合には、受け手の脳波にあらわれる揺れも、やはり強い傾向があったといい、これらのことからこの実験を行ったアメリカ人科学者たちは、「何らかの、未知の情報的あるいはエネルギー的交換が、隔離された人々の間で存在する」という事実を肯定せざるを得ませんでした。
これらの科学的に立証された「脳波の伝達」を果たしてテレパシーと呼んでいいのかどうかは、いまだに結論は出ていないようです。
が、このようにかつては超常現象と呼ばれていたものに科学的なメスを入れるという行為は2000年以降頻繁になっているようであり、それらは宇宙における「暗黒物質」の解明努力がなされるようになったことと無関係ではないでしょう。
「幽霊粒子」と呼ばれている「ヒッグス粒子」が確認されたという報道は耳に新しいところであり、現代の科学技術をもってすれば、もしかしたらこれまで「幽霊」と呼ばれていたものの正体も明らかになっていくのかもしれません。
「テレパシー」もしかりです。もしかして、その存在が本当に確認され、人間同士だけではなく、動物と人間の間のテレパシーも解明されたら、遠い将来にはもしかしたら本当に犬猫の言葉を翻訳する機械も実現するかもしれません。
ただ、それをウチのテンちゃんにも装着しようものなら、毎日のように「遊べ~」、「遊べー」の声が聞こえてくるかも。あるいは「腹減った」、「今はその気分じゃないのよ」なんてのもありかもしれません……
……うっとうしくて仕方がありません。なので、声には聞こえない、今のテレパシーのままだけのほうが、お互いにとっては幸せ、なのかもしれません。
皆さんはどうお思いでしょうか。