年が明けました。2016年です。
あけましておめでとうございます。
今年も頑張って、できるだけこのブログを続けていきたいと思います。変わらぬご愛顧をお願いいたします。
さて、みなさんはもう初夢をご覧になったでしょうか。
私はふだんあまり夢をみないほうなのですが、なぜかほぼ毎年、正月1日から2日にかけての明け方に夢を見ます。
今年もまた妙な夢を見ました。グループであるコンペに参加している夢なのですが、最終的に選ばれた私のグループの案が評議委員全員に否決されてしまいます。
しかし諦めきれない私はその案の良さを説明しようとするのですが、なぜか言葉が出ず、グループ長のある女性が私に代わってそれを説明する……というなにやら非常にもどかしい夢でした。
その女性が誰なのか、なんのコンペなのかもよくわかりません。わけのわからない夢を見るというのはよくあることではあるのですが、それにしてもどういう意味があるんだろうな~と考え込んでしまいました。
自分の作品を否定されるというのはあまりいい夢ではないのは確かです。ただ、夢の解釈というのはその内容というよりも、そのときの自分の気持ちに本当の意味があるのだといいます。
なぜか言葉が出ない、というのは本当はこうしたいのだけれどもできない、うまくいかない、といった感情を表しているのかもしれず、なかなか業績の上がらない昨今の自分を表しているのかも、と考えたりもしています。
フロイトによれば夢の素材は記憶から引き出されているといいます。どの記憶が選ばれるかといえば、その選択方法は意識的なものではなく、無意識的なものだそうです。しかし、無意識とはいえ、ある統合性に基づいて引き出されるといい、一見すると乱雑でとりちらかってみえるような夢の内容においても何か統一された意味があるようです。
結果として、夢を見ている本人は夢の中で起こったさまざまな出来事を一つの物語として連結させようと常に努力するそうで、それによって何等かの目的を達するのだといいます。そうすることにはさまざまな狙いがあるようですが、一般的にはそうした夢を見ることは潜在的な願望を充足させるものだといいます。
つまり夢を見る、ということは無意識による自己表現であると考えることができるようで、私が見た夢も、日ごろからああしたい、こうしたい、と思っていながらも、潜在意識の中に隠れ、表に出てこなかったものを夢に見たのかもしれません。
毎年のように見るこの初夢が、この説のように日ごろ意識の中に埋もれているものが現れてきただけのものなのか、あるいは何やらその一年を占うような予兆的な意味を持っているのか、については、年によっても違うような気がします。なので、今年も一年を通してこの夢の持つ意味を検証していきたいと思います。
ところで、初夢というのは、私のように2日の明け方にみるものを指すのでしょうか。あるいは大晦日から元旦にかけてみる夢が初夢なのでは、と少々疑問に思ったりもします。同様の疑問を持つ方も多いことでしょう。
いつ見る夢のことを初夢というのか、については昔の人も同じ疑問を持っていたようで、はたして江戸時代にも「大晦日から元日」「元日から2日」「2日から3日」と、主に3つの議論があったようです。
しかし、「大晦日から元日」にかけては夜は眠らず騒ぎとおす、というのは今も昔同じです。このため、「元日から2日」のほうが現実的だ、という意見が多かったようです。また、この時代には正月2日目に書初めや初商いなどの新年の行事が行われることが多く、このため江戸時代後期までには「2日から3日」に見る夢が初夢、という説が強くなりました。
とくに、「商業の町」でもあった大阪や江戸では、「2日から3日」が主流となり、この日に見る初夢が「正夢」として全国的に広まりました。しかし、明治の改暦後は、2日に初商いをする習慣が薄れていきました。
日本の官公庁や多くの企業では、いわゆる「三が日」を正月休みとして祝日扱いするようになったためであり、1月4日から平日となり、初商いはこの日にすることが多くなったためです。このため、初夢を見る日も、「元日から2日」に戻り、現在でも、2日の明け方に見る夢とすることが多くなっているようです。
ただ、初夢の起源をみると、そもそも初夢とは節分と立春にあたる2月3日から4日ごろに見る夢ということになるようです。鎌倉時代には、暦上の新年とは無関係に節分から立春の夜に見る夢を初夢としていたそうで、この時代は、立春を新年の始まりと考えていました。
したがって、今年の正月に初夢を見損なった、という人は、来月の節分まで待って、リベンジを果たせばよいのではないかと思います。
「一富士二鷹三茄子」の初夢は良い夢だといいます。江戸時代初期にはすでに言われていたことで、その起源にはいろいろありますが、徳川家縁の地である駿河国での高いものの順という説が有力です。すなわち、富士山、愛鷹山、初物のナスの値段です。
また、富士山、鷹狩り、初物のナスを徳川家康が好んだことにちなむ、という説もあり、いずれにせよ、この故事は、現在の静岡県に由来する、ということになります。
ほかにも、富士は日本一の山、鷹は賢くて強い鳥、なすは事を「成す」、あるいは富士は「無事」、鷹は「高い」、なすは事を「成す」という掛け言葉から来ているという説もあるようです。
実は4番目以降もあり、これは例えば四扇、五煙草、六座頭(しおうぎ、ごたばこ、ろくざとう)といったものです。一富士二鷹三茄子と四扇五煙草六座頭はそれぞれ対応しており、富士と扇は末広がりで子孫や商売などの繁栄を、鷹と煙草の煙は上昇するので運気上昇を、茄子と座頭は毛がないので「怪我ない」であり、家内安全を願うものです。
7番目はないのかな、と思ったらさすがにこちらはないようです。いずれにせよ、今年私が見た初夢の内容はこの1番から6番の中に含まれておらず、残念ながら縁起のいい夢ではなかったと判断されます。
このように自分が見た夢の吉凶を占うことを夢占い、あるいは夢判断とよく言います。この場合の夢は見た者の将来に対する希望・願望を指すか、これから起き得る危機を知らせる信号といわれます。
バビロニアにおいては夢の解釈技法が発達し、夢解釈のテキストまで作られていたそうで、
古代の北欧でもやはり人々は夢解釈に習熟しており、ある種の夢に関しては、その解釈について一般的な意見が一致していたといいます。たとえば、白熊の夢は東方から嵐がやってくる予告だ、といった共通の認識がありました。
ユダヤ法典には、エルサレムに12人の職業的夢解釈家がいたことが書かれているそうで、このほか、ネイティブアメリカンの部族の中には、夢を霊的なお告げと捉え、朝起きると家族で見た夢の解釈をし合うという習慣があるといいます。
ところが、古代ギリシャにおいて夢は神託であり、夢の意味するものを解釈しようとしてはいけない、「解釈を必要としない」ものだとされていたそうです。夢の送り手はゼウスだとかアポロだと考えられていたといい、従って恐ろしい夢をみればそのまま恐ろしいことが起こり、楽しい夢をみれば、楽しいことが起こる、と解釈されていたようです。
このように、夢は神や悪魔といった超自然的存在からのお告げである、という考え方は世界中に見られます。「旧約聖書」でも、神のお告げとしての夢は豊富に登場します。
一方、夢は睡眠中に肉体から抜け出した魂が実際に経験したことがらが夢としてあらわれるのだ、という人もいます。
肉体から抜け出した魂が感じる感覚が、最高潮に達して無我夢中の状態になることをエクスタシーといいます。
恍惚、忘我ともいい、快感が最高潮に達して無我夢中の状態になることをさします。エクスタシーは、さまざまな歴史的経緯を経て、現代では世俗的な意味でも、宗教的意味でも、あるいは哲学的・芸術的な意味でも用いられています。
最近では性的な意味で扱われることも多く、「オーガズム」を謳った性感マッサージのような少々いかがわしい世俗的なサービスの世界でも「エクスタシー」という言葉は使われます。
しかし、エクスタシーの本来の語源は、ギリシア語のekstasis、エクスタシスであり、その意味は「外に立つこと」であって、つまり、魂がみずからの肉体の外に出て宙をさまよう、といった意味が込められています。
プラトンは「何かを純粋に見ようとするなら、肉体から離れて、魂そのものによって、ものそのものを見なければならない」と言っており、各種の宗教はこうした考え方を拡大解し、後世では宗教的体験における神秘的な心境をさすようになりました。
またさらに時代が下ると、幽体離脱後に感じるエクスタシーには、予言、幻想、などをともなうことも多いとされるようになりました。魂が肉体から離れたこうしたエクスタシー状態において、神仏などの霊的存在と直接接触したり交流する、とされている例は世界各地に見られます。
肉体から離れた霊魂を脱魂とか遊離魂などと呼ぶことは行われており、すなわち、夢というのは、「睡眠中に霊魂が身体を離脱して経験したことがらだ」とする解釈があります。また「病気や身体衰弱というのは霊魂の離脱が原因だ」とする解釈もあるようです。
古代の日本では、魂は体から簡単に離れてしまうことがあると考えられていました。古代の鎮魂祭についての注釈書には、鎮魂とは浮遊した霊を身体の中府に収めて鎮めることだ、という記述があるそうで、日本の宮廷儀礼ではこうした「鎮魂祭」が重視されていたそうです。
また病から死への移行という側面に関しては、日本の古代から中世にかけては、天皇の病気は空中に浮遊する邪霊や怨霊が天皇の体内に侵入した結果生ずると考えられていました。
こうした邪霊や怨霊を巧みに取り除くことができれば天皇は死をまぬがれ、再び生の世界、つまりこの世へ復帰できますが、除去に失敗すると、天皇の肉体は亡骸(むくろ)になってしまう、と考えられていました。
そうした邪霊や怨霊がやがて変性したものが「物の怪(もののけ)」です。人間に憑いて苦しめたり、病気にさせたり、死に至らせたりするといわれる怨霊、死霊、生霊など霊のことで、妖怪、変化(へんげ)などを指すこともあります。
平安時代の貴族たちが栄華を誇った反面、繊細な性格を持ち合わせていたため、時代の敗者たちの怨みや復讐に対する恐れ、将来への危惧などから、この物の怪に一層の恐れを抱くようになりました。
閉鎖的な宮廷社会を送っていた当時の貴族たちの精神も、物の怪への恐れを助長することとなりました。こうしたことで物の怪自体が怨霊と考えられ、やがて疫病に加えて個人の死、病気、苦痛などのすべてが物の怪によるものと見なされ、その病気自体も物の怪と呼ばれるようになりました。
さらにその後、「もの」に対する恐怖の観念によって、病原体ともいえる生霊や死霊自体が「物の怪」と呼ばれるに至ります。物の怪に取りつかれることは死を意味しますから、人々は、これをできるだけ排除しようとしました。
たとえば「源氏物語」に御修法(みしほ)の場面というのがあります。六条御息所と葵上は光源氏の愛を奪い合いますが、結局葵上が正妻になります。やがて六条御息所は亡くなりますが、死んだ後もその執念の思いが物の怪となって紫上に祟ります。
それが原因になって紫上もやがてこの世を去るわけですが、物語が進行するにつれ、光源氏の他の愛人との愛憎も加わって、こうした三角関係がトグロを巻くように渦巻き状をなしていきます。
こうしたドロドロした人間関係が源氏物語全編の主要なテーマであるわけですが、この御修法の場面というのは、その愛憎劇の中でついに物の怪になってしまった六条御息所を祈祷によって治めようとする場面です。
その加持祈祷においてはまず、不動明王を中心とする五大明王の像、もしくは、絵像を並べ、護摩を焚き、そして陀羅尼(仏教において用いられる呪文の一種)を唱えます。これを「五壇の御修法」といいます。
病気になったり、死病に取り憑かれたり、 あるいは流行病が発生したり、この地上に異常な事件が起こったりするような時、この時代にはその原因は誰かの物の怪である、 という病理診断が下され、こうした祈祷が行われるわけです。
こうした祈祷では、護摩を焚く際に、芥子(けし)の実をくべて匂いを立てます。芥子にはもののけ祓いの特効薬としての効果があるとされており、当時からもののけを排除するために頻繁に使われていました。現在でも麻薬に分類されているとおりです。
古代から行われていた鎮魂祭の手法は、この時代にはもう物の怪には効果がないと考えられるようになっており、それに代わって密教による悪霊祓いの手法が登場し、こうした護摩焚きをする御修法が流行するようになっていたわけです。
しかし、このように悪魔祓いまでするのは、何か非常に重い病気の場合などであり、体を離れて浮遊した、とされる魂がもののけに化け、人に災いを与えるときだけです。
このほか、魂が人の体を離れる場合というのは、体外離脱が起こった場合があります。体外離脱が起こるのは、主に、何かしら危険に遭遇した時、臨死体験をしている最中だといわれ、一説によれば臨死体験中に体外離脱も体験する確率は約40%もあるといいます。
また、向精神性の薬物を使っている時にも体外離脱が起こるといわれ、人によっては、いわゆる「金縛り」が起きている時に経験することもあるといいます。
しかし、平常時、ごく普通の睡眠中や明晰夢の最中、自らの意思で体外離脱体験をコントロールできる人もおり、ヨーガの行者などは修行中に体外離脱を起こすことができます。
この体外離脱という体験は「夢」や明晰夢をみるときの感覚と似ているそうで、体外離脱後には通常の夢とは比較にならないほど強いリアリティーを伴う世界が現れると報告する人も多いようです。
しかし、そうした臨死体験をした人や修行を積んだ人でなくても、我々は通常の生活でも単に眠りについたあと、その魂は体を離れることもあるそうです。肉体を離れた魂は、あの世でいろいろな体験して元の体に帰ります。そして、その体験の記憶が夢として残る、といわれています。
「オーラの泉」で一躍有名になった江原啓之さんは、夢は、主に「肉の夢」「魂の夢」「霊の夢」の3つに分けられると言っています。
「肉の夢」は「睡眠中に肉体に何らかの刺激を受けているときに見る夢」のことを指し、例えば暑苦しさ、騒音、ふとんの重みなどによって睡眠中でも「肉体の意識」の比率がどうしても高くなり、肉体が感じている不快さをそのまま反映する夢です。
また、「魂の夢」は「自分自身の心にあるストレスや思いぐせによって見る夢」であり、日々の現実の中で悩みや恐れ、気にかかることがあると、睡眠中も意識がそちらに向き、心の状態を如実に表す夢です。
江原さんは「肉体はしっかり休めていても、魂に静寂がないと、たましいはのびのびと里帰りできず、自分の心をのぞき見るような魂の夢を見るのだ」といいます。現実に追われる現代人が見ている夢には、そういう魂の夢が多いそうです。
そして、最後の「霊の夢」こそが、霊体があの世に里帰りをしている間に見る夢です。睡眠中に私たちは肉体をこの世に残し、幽体と霊体はスピリチュアルワールドの中の幽界へ里帰りします。そして、この夢を見るときというのは、あちらの世界で守護霊やその他のいろいろな霊と接触し、この世に必要な教えを受けて戻ってくるといいます。
こうした霊の夢をみるときには、「宇宙」との一体感、全知全能感、強い至福感などを伴い、この体験は時に人の世界観を一変させるほどの強烈な夢となることもある、といいます。白黒ではなく、カラフルな夢の場合はこの霊の夢であることが多いそうで、非常に極彩色なリアルな夢を見た、と思ったらこの霊の夢、と考えていいでしょう。
医学的にも「変性意識状態」というのがあるといわれており、これも「宇宙」との一体感、全知全能感、強い至福感などを伴い、時に人の世界観を一変させるほどの強烈なものと言われています。
精神や肉体が極限まで追い込まれた状態になったとき、こうした状態に置かれるといい、上の「霊の夢」と似ています。瞑想によっても得られ、また催眠等による、非常にリラックスした状態でもこうした体験をできるようです。また、いわゆる「ヤク」をやる人もこの状態に置かれることがあるとされます。
医学的には、「日常的な意識状態以外の意識状態」のことを指し、通常の覚醒時のベータ波意識とは異なる、一時的な意識状態が確認できるということで、近年、社会学分野におけるひとつの研究対象として真面目に研究されているようです。
さらにこの変性意識状態のひとつに、「トランス状態」というのがあります。その状態にもよりますが、「入神状態」と呼ばれるものであり、一般的には、脱魂状態、もしくは恍惚状態とも呼ばれているものです。
1960年代に「トランスパーソナル心理学」という学問分野が心理学の新しい潮流として研究されはじめました。これは、人間がこの世に存在する究極的な目的とは、自己を越えた何ものかに統合されることに違いなく、その方法を追及する、といった哲学的な内容です。行動主義心理学、精神分析、人間性心理学に続く第四の心理学といわれます。
心理学における「自己超越」の概念をさらに発展させたとされています。人間には、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、尊敬・評価の欲求、自己実現の欲求の5つの欲求があるとされますが、自己超越とはこれを超えるものです。
この説を唱えたA.H.マズローという心理学者によれば、「真、善、美の融合、他人への献身、叡智、正直、自然、利己的個人的動機の超克、“高次”の願望のため、“低次”の願望を断念する、増大する友情と親切、目標(安静、静謐、平和)と手段(金銭、権力、地位)とのやすやすたる区別、敵意、残忍、破壊性の減少」、などがその状態です。
つまりは、自己超越を自覚するためには、敵意や憎悪を捨て、利己的に金銭や地位を追い求めることをせず、他者への献身や平和などに尽力できるほどの高い意識を持つことでそれが達成できる、ということでしょう。
トランスパーソナル心理学では、そのためのさまざまな精神統合の手法が開発されました。そして、その中でも自己超越をもたらす上でかなり有効である、とされる手法のひとつがトランス状態です。人間を自己超越に導くうえで最も肯定的な効果をもたらす、として長年研究されてきました。
医学的にもその効果が徐々に認められつつあり、とくに精神疾患に対する有効な療法としても有効とされており、一時的にトランス状態を患者に与える方法を活用する医療関係者が増えているそうです。
で、どういった状態なのよ、ということなのですが、トランス状態の見かけの程度というのは、全身の痙攣を伴う激烈なものから、あくびを繰り返すだけの軽度のものもあり、さらには他者からの観察では通常の状態と全く変わらないものまで、さまざまなヴァリエーションがあるそうです。
一方、内面的には、催眠によって表層的意識が消失し、心の内部の自律的な思考や感情が現れる状態だそうです。何か非常に嬉しいことがあったとき、恍惚状態になる、とよくいいますが、そういう感覚なのかもしれません。こうした嬉しい状態を意図的に創りだし、心を癒そうとするのがトランス状態だ、と聞かされれば、なるほど神経にはよさそうです。
ただ、これに似た状態には、ヒステリーやカタレプシーにより意識を喪失した場合などもあります。カタレプシーというのは、受動的にとらされた姿勢を保ち続け、自分の意思で変えようとしない状態であり、緊張病症候群と呼ばれ、ヒステリーと同様に一種の病気です。
このほか、宗教的修行によって、外界との接触を絶ち、法悦状態になったものなどもトランス状態ということもあるそうで、こうした状態というのは特殊な宗教活動によって得られる場合も多いようです。
たとえば東北地方のイタコ、ゴミソ、カミサン、オナカマ,ワカと呼ばれる呪術者や,各地の行者、祈禱師、卜師などがそれで、彼らは数珠を持って呪文などを唱えたり、ある種の楽器を使って徐々にトランス状態に入っていきます。
また、沖縄(琉球)におけるユタ、台湾・中国南部・東南アジア・インドを中心とした南方文化圏における「シャーマン」のように特殊なものを火に注いでその煙を吸う例もあるようです。文化人類学などによる宗教研究ではしばしばこの“シャーマン”という言葉・概念によって、こうしたトランス状態に入る呪術者を分類・説明しています。
こうしたシャーマンのトランスには、霊魂が身体から離れて異界に移動し神や霊と接触する上述のエクスタシー(ecstasy、脱魂)型と、反対に神や霊などの超自然的存在がシャーマンを訪れる possession(ポゼッション、憑依)型の2種類があると言われています。本論からすれば、いうまでもなく前者が「夢の伝道者」ということになります。
ただ、こうした宗教家はふだんから人目を忍んで生きているようなので一般的な人が接触する、というのはなかなか難しいでしょう。しかし、彼らのお世話にならなくても通常の催眠でこうしたトランス状態を体験できます。ただし、その道の専門家の門をたたき、正しい治療を受けなくてはなりません。
「催眠療法」と呼ばれているもので、これは催眠を用いた一種の心理療法ですが、一連の暗示操作によって覚醒レベルを下げて被暗示性を高めた状態、すなわち、トランス状態に導き治療を行うものです。
きちんとした治療家によってもたらされた「正しいトランス状態」においては、通常の感覚は失われ、例えば目の前でストロボを発光させても反応しなくなるといいます。からだの一部に針を刺してもそれを感じないそうで、また脳ではアルファ波が優勢になることが知られています。
トランス状態のもたらすこのような緊張緩和効果は、精神的に不安定な人の治療に役立つばかりでなく、健常者においても向上心の芽生えや、生きる活力を与えるほどの力があるといいます。また、怪我をした人のリハビリテーションにおけるメンタル面での効果もあるといい、このほか教育、スポーツなどの幅広い領域への応用が期待されているようです。
欧米では、「催眠療法家」という人々がいるそうで、彼らは協会を結成し、「催眠療法士」を認定する仕組みが一般的になっているそうです。日本でも、大分大学内教育福祉科学部内にある、日本催眠医学心理学会認定の「催眠技能士」等があります。
そのほか、「ヒプノセラピスト」として資格認定を行う民間機関がいくつかあるといい、こうした催眠療法家にお願いするのも一つの手です。
さらに、こうした医療関係者の手を借りずに、座禅などによる瞑想法によって深い瞑想状態を作り出すことができれば、同じようなトランス状態を醸し出すことが可能だともいいます。これならお金もかからず、誰にも迷惑かけることはありません。ただ、座禅によりトランス状態に達するためには、かなりの年月の修行が必要だといいます……
ま、方法はいろいろあるにせよ、今年の年頭に初夢を見るのを失敗した、という人は、ここはひとつ、自分でこのトランス状態を作り出すことによって初夢を見てはいかがでしょうか。
今年はこうした体験も含め、良い夢をたくさんみましょう。そして、あちらの世界とこちらを頻繁に行き来して、さらに高い極みにある自分を探し出す、あるいは自分を取り戻してみる、というのを目標にしてはいかがでしょうか。



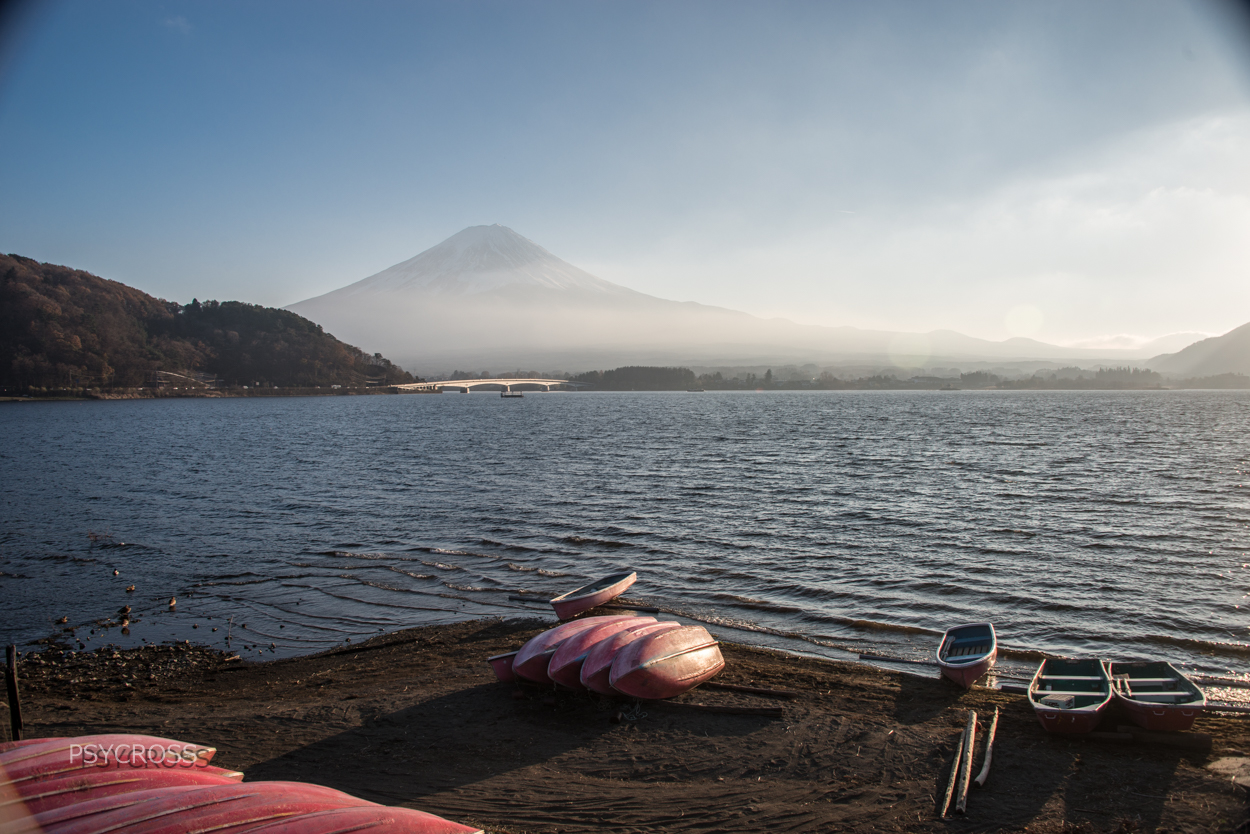





























 1988年度の世界幻想文学大賞を受賞したほどの名作で、その後、いわゆる「ループもの」と呼ばれる主としてSF小説でポピュラーになった分野の先駆けともなりました。この本は日本でもベストセラーになり、また海外では数々の映画やドラマの原作にもなりました。
1988年度の世界幻想文学大賞を受賞したほどの名作で、その後、いわゆる「ループもの」と呼ばれる主としてSF小説でポピュラーになった分野の先駆けともなりました。この本は日本でもベストセラーになり、また海外では数々の映画やドラマの原作にもなりました。







