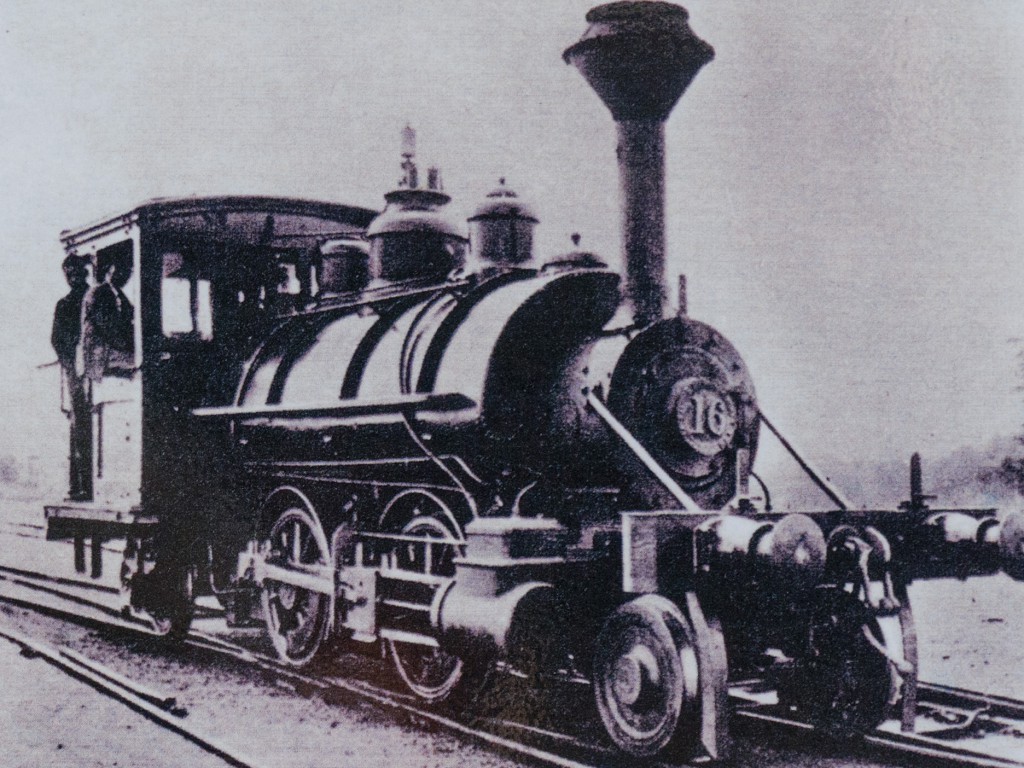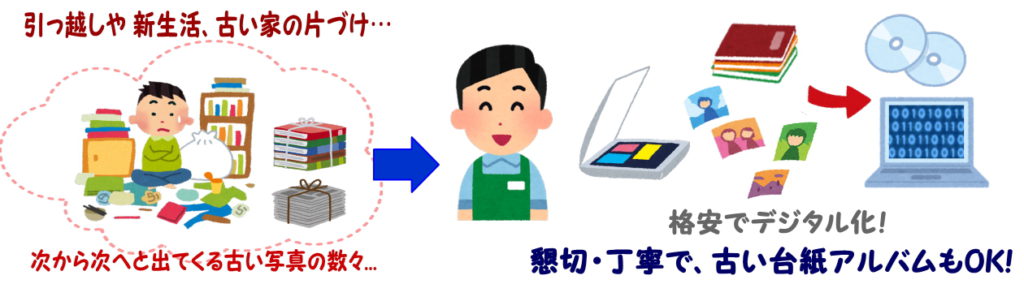毎月25日は、天神様の縁日だそうです。今日は24日ですが、明日がその日です。
天神様とは本来、国津神(地上の神様)に対する天津神(天上の神様)のことであり、特定の神の名ではありません。しかし、平安時代に藤原時平の陰謀によって大臣の地位を追われ、大宰府へ左遷された菅原道真公のことを雷神信仰と結びつけ、以後「天神様」として畏怖・祈願の対象とするようになりました。
道真が亡くなったあと、天変地異が引き続いて起こったことから、道真公は火雷天神と呼ばれようになり、その神霊に対する信仰は「天神信仰」と呼ばれ、学問に造詣の深かった道真を祀り、「学問の神様」とした神社が各地に造られるようになりました。
この、菅原の道真が亡くなった日が、旧暦の2月25日だったことから、毎月この日が天神様の縁日になりました。縁日というと、「祭り」というイメージをお持ちの方が多いと思いますが、とくに天神様に限らず大きな神社やお寺では縁日になると屋台の出店が並び、大勢の人が集まってにぎやかな雰囲気になります。
しかしそれにしてもそもそも「縁日」とはなんだろう、と調べてみたところ、縁日とは神社や寺の創建やその寺社に祭られる神仏の降誕などの特別な日に行われる祭典、供養の日のようです。
元々は「会日(えにち)」と言ったようですが、それが訛って「縁日(えんにち)」になったようです。そもそも「縁日」は、寺社に祀られた神仏と人間の間の「縁」が結ばれた日と言う意味で使われるようになったものです。
この日は、祀られた神様や仏様にとっても特別な日なので、この日参拝した人には、特別なご利益があると考えられ、この「特別なご利益」を授かろうと、この日に参拝する人が増え、多くの人が集まるところに目をつけた寺社が商売人に屋台の出店を許し、そのテナント料を徴収するようになりました。
なので、天神様の縁日に行くと、とくに学問の神様ということですから、受験生や何等かの資格を取ろうとしている人にとっては合格の可能性が高くなるに違いありません。
ところで、この縁日に出回る「屋台」なのですが、これはいったいどういう人たちが運営しているのだろう、とかなり前から気になっていました。
調べてみたところ、近年のこうした屋台は第二次世界大戦後、闇市の屋台が広がっていったのと同時に日本中に広まっていったようです。正月の寺社や縁日など大きな行事の場所にはたこ焼き、焼きそば、綿菓子、磯辺焼、おもちゃなどを売るいろんな屋台が出店しますが、こうした祭りの縁日等大きなイベントに出店する屋台はたいがいが「的屋(てきや)」と呼ばれる人たちによって営まれている場合が多いとのことです。
現代の屋台の形式そのものは第二次大戦後の闇市の名残りのようですが、この的屋そのものはかなり古い歴史があるようです。「的屋」とは、思いもかけずに儲かることや、一山、当てようと目論んだことが大当たりすることを指し、「的矢」になぞらえて使われるようになった言葉だそうです。
祭りや市や縁日などが催される、境内や参道、門前町において屋台や露店で出店して食品や玩具などを売る小売商や、射的やくじ引などを提供する街商、大道芸をやって客寄せをし商品を売ったり、芸そのものを生業にする大道商人らのことを総称して「的屋」といいます。
的屋の人たちは、祭りや市、縁日などが催される、境内、参道や門前町のことを「庭場」と呼んでいるそうで、的屋の人たちの中には、この庭場において御利益品や縁起物を売る商売人もいます。
商売人といっても、こうした商売はいわゆる「寺社普請」と呼ばれる相互扶助の一環でもあり、古くは町鳶、町大工といった町人たちが行った冠婚葬祭の互助活動と同じです。
この商売によって彼らが手にするお金も「現金」を手にする感覚ではなく、「ご祝儀」をいただく、という感覚のようで、お寺や神社からの依頼によって御利益品や縁起物を売る行為自体が、神仏の託宣を請けている、という意味を持つのだそうです。
的屋は「露天商や行商人」の一種であり、日本の「伝統文化」を地域と共有している存在でもあります。このため、的屋の人たちは価格に見合った品質の商品を提供するというよりも、祭りの非日常(ハレ)を演出し、それを附加価値として商売にしているという自負があります。
「ハレ」の反対は「ケ」であり、「ハレとケ」は、日本人の伝統的な世界観のひとつです。ハレ(晴れ、霽れ)は儀礼や祭、年中行事などの「非日常」、ケ(褻)はふだんの生活である「日常」を表していますが、「ケ」のほうは「穢れ(けがれ)」のケだという説もありますす。
もともとハレとは、折り目・節目を指す概念であり、その語源は「晴れ」であり、「晴れの舞台」、「晴れ着」などの「ハレ」はこれをさします。これ対し普段着は江戸時代までは「ケ着」といったそうですが明治以降から言葉として使用されなくなりました。
また、現代では単に天気が良いことを「晴れ」といいますが、江戸時代までさかのぼると、長雨が続いた後に天気が回復し、晴れ間がさしたような節目に当たる日についてのみ「晴れ」と日記などに記す風習がありました。
ハレの日はめでたい日ということで、餅、赤飯、白米、尾頭つきの魚、酒などが飲食されますが、江戸時代よりも前は当然これらは高級食材であり日常的に飲食されたものではありませんでした。また、このための器もハレの日用であり、日常的には用いられませんでした。
つまり的屋の人たちが売りに出しているものも「ハレ」を演出する商品というわけで、このためハレの日に屋台で売り出すものは、多少高くても「縁起物」だという感覚が彼らにはあります。それを買う側の我々も高いなーと思いつつも、「まっ、お祭りだし」とたとえ高くてもなんとなくそれを買うこと自体が縁起が良いこと、と感じている、というわけです。
この的屋と呼ばれる人たちの起源ですが、これは思ったよりかなり古くからある商売のようです。そもそも日本では、古くからいろいろな生業において「組」と言う徒弟制度や雇用関係があり、的屋ももともとは、親分子分の関係を基盤にしてできた企業や互助団体であったりします。
零細資本の小売商や、ちょっとやばい人たちに雇われている下働きの人々の団体というイメージもありますが、これに該当しない地域に密着した形や、個人経営や兼業の的屋も多くあるといいます。
地勢的な違いや、歴史的な成り立ちの違いに人と資本の要素が複雑に絡み合って発生し成り立ってきた商売のようで、単に「的屋」としてひとくくりにすることにこそ無理があるとも言われます。が、一般的に的屋の源流とされているものは、だいたい以下の五つだそうです。
猿楽師(奇術・手品・曲芸・軽業・祈祷・占いなどを大道芸として行いながら、旅回りをしていた人たち。太刀まわりや一人相撲など日本古来の芸も含む)
香具師(芸や見世物を用いて客寄せをし、薬や香の製造販売・歯の医療行為をする人たち。野士・野師・弥四と書いて「やし」と呼ぶ場合も。
的屋(「まとや」。これも、「矢師(やし)」と呼ばれ、「ハジキ」ともいわれる。弓矢を使った射的場を営む人たちのことで、射的だけでなく、くじ引きなどの景品交換式遊技を生業にする人たちのことも的屋という。ヤクザの持つハジキ(拳銃)はこれが語源。)
蓮の葉商い(時節や年中行事に必要な縁起物の木の実や葉、野菜や魚、地域によっては獣肉などの季節物や消え物(きえもの)を市や縁日で販売する人たち。)
鳶職・植木職(鳶職や植木職が町場の相互関係の中で、「町火消し」などの特別な義務と権限を持つようになり、「熊手や朝顔」などの縁起物や、「注連縄(しめなわ)やお飾り」などの販売権を持つようになった人たち。現在でもその権利は不文律といわれる。)
ちなみに、上述のうちの的屋では、客が弓矢を楽しむ横で矢を回収することは危険な行為であるということで、関東の的屋の間では危ない場所を矢場(やば)と言うようになり、これが変じて危ない事を「矢場い・やばい」と表現するようになりました。
こうした古来からの営みを行う人たちを総称して「的屋」と呼ぶようになったのがいつのころのことからなのかは、定かではないようですが、平安時代のころには既に上記のような商売は成立していたようであり、この五つの中に「的屋(まとや)」があることから、いつのころからか、これらの商売を総称して「的屋(てきや)」と呼ぶようになったのでしょう。
しかし、その商売の形態が確立したのは明治時代以前の江戸時代のころのようで、こうした人たちはお寺や神社などからの依頼、つまり「託宣」としてこれらの商売を行うようになりました。
この商売の形態を「寺社普請」といいます。江戸時代より古い時代には、人々の暮らしの中心に寺や神社がありました。その定期的な修繕や新設、基盤の拡張をする場合、そのためには多額の費用がかかりますが、これを地域の人々から直接寄付によって募集するのには無理があります。
そこで「祭り」と称して縁日や市を開催し、そこに的屋を招いて、非日常(ハレ)を演出してもらう、つまり的屋に上述のような商売をしてもらうことで儲けてもらうことにしたわけです。
そして、それによって儲けたお金の一部を神社仏閣が場所代として的屋から貰い受け、これによって寺社の修繕や新設を行いました。家を造ったり修繕することを「普請」といいますが、「寺社普請」とは、本来このように的屋に頼んで境内で商売を行ってもらうことをさしたのです。
この方法は、単に地域の人たちから直接寄付を募るよりも効果的で、庶民も「お祭り」と称して夜店や出店の「非日常」を楽しむことができることから、日本全国で大いに流行るようになりました。いわゆる日本の「祭り文化」が生まれ、これが人々の生活を豊かにすると同時に技術を持った商売人としての的屋の人たちもその生活がなりたっていきました。
ちなみに宝くじの起源である「富くじ」も、寺社普請のために設けられた、非日常を演出する資金収集の手段だったといいます。
こうした「ハレ」の場で持たれた「有縁」が「会日」となり、やがて「縁日」という呼称に変化していき、庶民の生活習慣に深く根ざすようになるにつれ、これがもとで各地域での経済が活性化され、定期的な「市」が持たれるようになります。そして的屋を中心とする露天商はますます発展していきました。
神事や、お祓い、縁起といった価値観は、商売する的屋側としても商品に高い付加価値をつけることができる手法として高く評価され、江戸時代の「祭りブーム」と相まって的屋はますます栄えるようになっていきます。その勢いは昭和初期まで続き、第二次世界大戦前の東京都内では、年間に600を超える縁日が催されるまでになり、忌日をのぞき、日に2・3ヶ所で縁日が行われていたといいます。
しかしその後の戦争による疲弊により縁日はあまり開かれなくなりました。お祭り自体は復活するものも多かったにかかわらず、縁日は職業人としての的屋がいなければ成り立たないものであり、これらの的屋の多くが、戦後の貧困によって廃業や転職を余儀なくされたためです。
縁日などという商売はもう古い、というよう戦後世間の風潮もあり、的屋に成る人も少なく、その総数は減少の一途をたどりました。
ただ、かつての的屋(てきや)のひとつであった的屋(まとや)は、現在も温泉場や宿場町に残る射的場として残っているところも多く、こうした「景品交換式遊技場」は、スマートボール(ピンボール)やパチンコの源流ともいわれます。前述したとおり、宝くじの源流は的屋がやっていた「富くじ」屋です。
戦前ほど多くの的屋がいなくなってしまった現代ですが、全くいなくなったかといえばそうではなく、その生き残った後継者たちはいろいろな形態で全国各地で商売をしています。
例えば、「転び(ころび)」というのがあり、これは地面引いた茣蓙(ござ)などの上に直に商品を転ばして売っていたためにこう呼ばれています。新案品と呼ばれる目新しい商品を売る事が多く、その身軽さから、近年では庭場にとらわれず、小学校の下校時にあわせて、子供向けに売り場を開く事もあります。
私も子供のころに下校しようすると学校の入口にたくさんの色をつけた「ひよこ」を売っている行商人さんがいましたが、これがそうです。最近では消えるカラーインクセットやカラー砂絵セット(色別に着色した硅砂と木工用ボンド)、カラー油土の型枠セットなどを販売する的屋さんがいるようです。
また、縁日に良く出ているのが、「小店(こみせ)」といわれるもの。これは売り台が小さく、ほとんど間口がない店で、飴などの「小間物」を扱っており、もともとは市や縁日で前述の「蓮の葉商い」などをやっていた人たちの名残です。
伝統的な的屋で地域密着型の商売なので、地元の人々が既得権をもって商売している例が多く、外から来た的屋さんよりその地域においてはいろいろな条件面で優先されていことが多いそうです。
さらに、縁日などでは、「三寸(さんずん)」と呼ばれ、小店よりももう少し大きいお店があります。売り台の高さが、一尺三寸(約40cm)になっているからといわれ、その昔、渡世人として各地方を渡り歩く的屋家業の人が顔役に世話になる時、「軒先三寸借り受けまして……」と口上をしたからといわれています。
この三寸を運営しているのは、縁日や市や祭りが催される場所を求めて全国を渡り歩き、床店(とこみせ)と呼ばれる組み立て式の移動店舗で商売をする、いわゆる露天商です。個人や個人経営の人たちが集まった「組」もありますが、「神農商業協同組合」の組合員も多いといいます。
「神農商業協同組合」とは、旅回りの的屋の世話や、庭場の場所決めの割り振りや場所代の取り決めや徴収をするための仕組みを組織化したもので、相互扶助を目的とした露天商の連絡親睦団体として全国にいろんな名前の組織が存在するようです。
江戸時代、的屋は「神農」とも呼ばれることがあり、的屋のことを「稼業人」、博徒のことを「渡世人」と呼んで区別していました。「無宿渡世・渡世人」とは、本来は生業を持たない、流浪する博徒を指し蔑まれましたが、的屋については商売を持っているため、渡世人ほど嫌われることはありませんでした。
生業とする縄張りも、的屋では「庭場」といいますが、博徒では「島」と表現するなどの違いがあります。また的屋たちは、個々が持っている信仰は別として、その商売の神様として「神農」という神様を信じ、これを祀っていましたが、これに対して博徒は職業神として「天照大神」を祀っていました。
こうした共通で奉ずる神様を持った的屋たちは、組織として「組」を形成し互助活動を行うようになり、こうした組が各地にある「神農商業協同組合」の前身です。
大工、鳶、土方(つちかた)などの建設業団体や河岸、沖仲仕、舟方(ふなかた)などの港湾労働団体、籠屋、渡し、馬方(うまかた)などの運輸荷役団体と同じであり、そういう意味では、現代の各業界の代表会社で組織する「社団法人」に似ているかもしれません。
しかし、互助活動に対しての「謝礼」を授受する風習があり、こうした表向きは謝礼とされる金銭の授受の中には、いわゆる「民事介入」、すなわち民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為である「ミンボー」にあたるケースも多いのではないかと指摘されています。
的屋の人たちすべてがそういう人たちではありませんが、その一部がやくざと同一視されているのはこれが理由です。現在の暴力団といわれる組織の中でも老舗といわれる組の中には、元をたどればこれらの神農を信奉する的屋業を営んでいたものがあることも事実のようです。
各地の神農会を運営していた世話主のことを「庭主」といいますが、本来、行商人や旅人の場所の確保や世話をする世話人が、集まって組織となり、神農会と呼ばれる庭主の組合がつくりました。が、戦後の貧乏期には円滑な運営をなしえない状態になる者も多く、これらが転じて各地の暴力団の傘下組織となったものも少なくないといいます。
一部には肝心な世話することを怠って何もしない「庭主」や、競合する出店を脅迫し排除したり、挨拶に来るよう呼びつけたり、行商人などから「所場代」名目で金品をたかるものも存在するそうで、こうした行為は博徒と変わりありません。
これらの中には、県などの公認を受けた協同組合として活動している組織もありますが、実際にはヤクザ組織の親分が協同組合理事長を兼任している場合もあり、こうしたケースの場合は協同組合というより親分の私物の組合といった趣きが強いのも事実です。極端な場合には、理事長そのものが替え玉という場合もあるようです。
だからといって、今縁日などで出店をされている方々がすべて暴力団がらみとみるのは早計で、その多くは、その寺社や近くの商店街の了承を得て正規に運営されているものがほとんどです。
こうした縁日で買ったり、飲み食いして支払われたお金の一部はその寺社への寄付金の一部にもなるわけであり、そう考えると、おみくじやお賽銭と同じということになります。
無論、暴力団のような非情な組織の存在を許してはいけません。暴力団組織の排除の機運を高める一方で、こうした「ハレ」の場を演出する場が戦前のようにもっと多くなるよう、
正直な的屋さんがもっと増えるよう、行政なども積極的に関与して、そのしくみを変えていかなくてはなりません。
日本経済の再生は、案外とこうした縁日や市といった日本の伝統的な行事に関わる組織や人々の見直しから始めるべきなのかもしれません