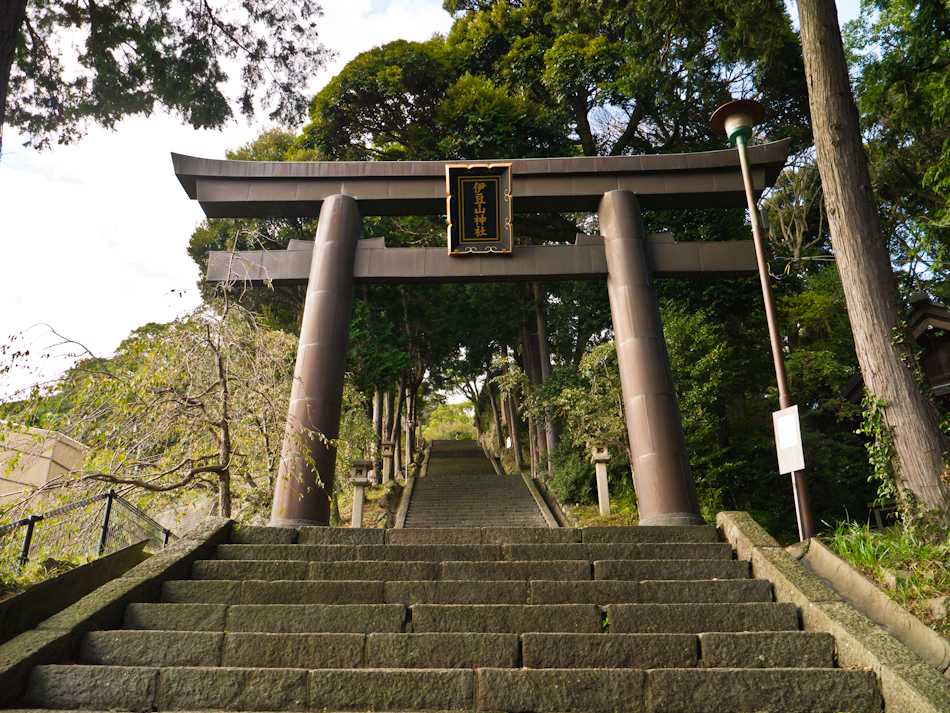先週末、広島に在住の姉夫婦から「カキ」が大量に送られてきました。
先週末、広島に在住の姉夫婦から「カキ」が大量に送られてきました。
言うまでもなく、広島は全国でも有数のカキの名産地で、そのシェアは約50%をも占めます。これに次ぐのが、宮城県の約23%ですが、ご存知のように東北の津波の関係でここ数年少しく減産しているようです。
広島県は大規模業者が多いのに対し、宮城県は個人での生産が多く、牡蠣生産に携わる漁業関係者数は全国で一番多いそうで、こうした個人漁業者の被害は相当なものだったようです。が、ニュースなどでも伝えられている通り、この冬からはかなり持ち直してきて、今シーズンようやく出荷にこぎつけた生産者さんも多いとのことです。
カキは、いろんな書き方があります。牡蛎、牡蠣、硴などがそれで、日本では古くから、沿岸地域で食用のマガキやイワガキが採取されてきたほか、薬品や化粧品、建材(貝殻)としても利用されてきました。
が、食用にされない中型から小型の種も多く、どの種類も岩や他の貝の殻など硬質の基盤に着生するのが普通です。
英名では”oyster”です。こちらのほうは、日本語の「カキ」よりも広義に使われ、岩に着生する二枚貝のうち、形がやや不定形で表面が滑らかでないもの一般を指し、真珠の養殖に使われるアコヤガイ類やかなり縁遠い種類などもoysterと呼ばれることがあるようです。
このカキですが、一般に我々が知るカキというのは、かなりゴツゴツとした貝殻を持っていますが、この形というのは、波の当たり具合などの環境によっても形が変化します。このため、カキが定着する岩などの基盤に従って成長するため殻の形が一定せず、外見による分類が難しく、野外では属さえも判別できないこともあるそうです。
従って、学術上未だに分類が混乱しているものも少なからずあり、外見に惑わされない分子系統などを使った分類がなされつつあるそうですが、まだまだ完全なる生物学的な仕分けは終わっていないそうです。なので、生物学に興味のある方、その完成にチャレンジしてみてはどうでしょうか。
しかし、我々が食するカキは、たいていはこうした天然物ではなく、養殖です。その一般的な方法は、カキの幼生が浮遊し始める夏の初めに海中に吊るした「ホタテ」の貝殻に幼生を付着させるというものです。
後は餌が豊富な場所に放っておくだけで大きくなり、総じて天然物に比べて中身も大きくて味も良いものができあがります。
天然物のほうは、養殖ものと違って一旦岩などに付着すると、一生ほとんど動かないため、筋肉が退化し内臓がほとんどを占めています。日本テレビの科学番組「所さんの目がテン!」でハマグリの内臓を寄せ集めてカキフライもどきを作ったところ、20人中18人が騙されたという結果が出たそうです。
干潮時には水が無い場所に住む場合が多く、グリコーゲンを多く蓄えています。これにより、他の貝と違って水が無い所でも1週間は生きていられるといいます。グリコーゲンというのは、動物の体の中で、糖類などの成分を一時的に栄養として貯蔵しておくために形を変えたもので、動物デンプンとも呼ばれる栄養素です。
が、養殖のものはこうした内臓部分よりも筋肉のほうが大きく、プリッとしたふくらみの中に入った内臓とこの筋肉の取り合わせが、あの独特の食感を生み出します。
一番よく食べられるのが、マガキ(真牡蠣)で、日本でカキといえばこれを指します。本来は冬が旬ですが、最近では大型で夏でも生殖巣が発達しない「3倍体牡蠣」も開発され、市場に出ています。流通しているものの中には韓国からの輸入品も相当量あるようです。
このほか、イワガキ(岩牡蠣)が良く食べられますが、こちらはマガキと対照的に夏が旬であり、「夏ガキ」とも言われます。殻の色が茶色っぽく、マガキに比べて大きいものが流通します。天然物しかないと思っている人も多いようですが、こちらも養殖物が存在します。
このほか、有明海ではスミノエガキ(住之江牡蠣)というのがあるそうですが、他所へはほとんど出回らないようです。有明海ではこのほかにもシカメガキというのが産出されるそうで、これはほかにも熊本の八代海や福井県の久々子湖に分布します。
現在、アメリカの多くで食されているカキは、1946年頃に熊本県八代市の鏡町からアメリカに種ガキとして輸出されたものが広まったものだそうで、ワシントン州沿岸を中心に養殖されていて、その名も「クマモト」というそうです。
小振りながらクリーミーで濃い味が特徴です。昔フロリダの北部に住んでいたころ、オーランドやニューオリンズにも出かけましたが、ここで食べたのがこれだと思います。日本のマガキのような臭みがなく、レモン汁をかければ生でいくらでも食べれる、といったかんじで、大変おいしかったのを覚えています。
一方、欧州では、ヨーロッパヒラガキというヨーロッパ原産種があります。別名、ヨーロッパガキ、フランスガキともいい、その外観は輪郭が丸く平たいかんじで、ブロン、フラットとも呼ばれる高級食材です。
かつてのヨーロッパ、特にフランスでカキと言えばこのカキのことを指しましたが、1970年代以降、寄生虫などにより激減。このため需要をまかなうために日本産のマガキを輸入して養殖するようになり、それ以来フランスなどで流通するカキの相当部分は日本由来のマガキになりました。
日本ではかつて、宮城県気仙沼市の舞根(もうね)などでこのヨーロッパガキが僅かに養殖されていて、国内のフランス料理店に卸されていたようですが、こちらも先の大津波でカキ養殖施設が壊滅状態に陥りました。
この災害時には、フランスのカキ養殖業者達がかつて日本に助けてもらった恩返しとして、養殖施設の復旧に協力したそうですが、オリジナルのヨーロッパガキの生産が復旧したのかどうか心配です。
カキは、グリコーゲンのほか、必須アミノ酸をすべて含むタンパク質やカルシウム、亜鉛などのミネラル類をはじめ、さまざまな栄養素が多量に含まれるため、「海のミルク」とも呼ばれることはみなさんもよくご存知でしょう。
世界中で食され、長い歴史の中で人類が親しんできた貝の一つです。一般的に肉や魚介の生食を嫌う欧米食文化圏において、カキは例外的に生食文化が発達した食材であり、古代ローマ時代から珍重され、養殖も行われていました。
フランスでは、生ガキはオードブルとなっているほか、生ガキをメニューの中心に据える「オイスターバー」と呼ばれるレストランも多数存在します。ナポレオン、バルザック、ビスマルクといった歴史上の人物がカキの愛好家であったことはよく知られています。
日本では縄文時代ごろから食用されており、多くの貝塚からカキ殻が発見されています。その昔は日本ではカキよりもハマグリのほうがたくさん獲れたようですが、ハマグリは養殖ができないため現在は逆になってしまいました。
古来からの和名は「おかきのかい」あるいは「かき」であり、密集している貝を掻き取ることが語源と考えられているようです。
養殖の技術は、室町時代ごろに開発されたようで、大坂では明治時代まで広島から来る「牡蠣船」が土佐堀、堂島、道頓堀などで船上での行商を行い、晩秋の風物詩となっていたそうです。
かつては広島や東北などの産地から消費地まで輸送するのに時間がかかったため、日本ではカキの生食は産地以外では一般化せず、もっぱら酢締めや加熱調理で食されました。日本人では武田信玄や頼山陽などがカキの愛好家であったことが知られています。
ただし、現在我々は生ガキを普通に食しますが、昔の人は生でこれを食べることはしなかったようで、日本人がカキを生で食べるようになったのは、欧米の食文化が流入した明治時代以降のことです。
しかし、カキの食べ方は生食以外にも様々です。カキフライのような揚げものや、鍋物の具にして食べるほか、網焼きにしたりしてもおいしくいただけます。
網焼きや生食では身だけでなく汁もともに吸うのがツウです。
我々がスーパーなどで目にするものはき身のものが多いでしょうが、殻つきのカキでは、身が浸されている殻の中の海水を含む汁にも多くの栄養素やうまみがたっぷりと含まれていますから、殻つきが手にはいったら、その汁を余すことなく飲み干しましょう。
このほか、カキの貝殻は粉砕して薬にも使われます。これは牡蠣(ボレイ)といい、焼成し、「ボレイ」または「ボレイ末」とし漢方薬局などで売られています。「日本薬局方」にも記載されているれっきとした生薬であり、薬理作用として、血糖低下、免疫増強作用などの作用があるようです。
薬用以外にも天然炭酸カルシウムとして使われ、あるいは1000℃程度に焼成すると「牡蠣灰」というものができ、これは、消しゴムの添加剤などの工業用や食品添加物、砂糖精製用助剤などに利用されています。
このほか、カキは水中の懸濁態物質やプランクトンを取り込むため、カキを収穫することで、水中の栄養塩の回収につながります。特にカキは濾過量が他の2枚貝に比べて極めて多く、1時間に約10リットルの海水を濾過するといいます。 アサリは1時間に1リットルの海水を濾過するそうですから、その10倍です、
アメリカの首都ワシントンD.C.の東にあるチェサピーク湾では、カキを使ってオイスターガーデニングと呼ばれる水質浄化活動も行われているそうで、カキの擬糞はゴカイなどの底生生物の餌となり、底生生物は魚類の餌ともなり、豊かな生態系を作ります。
我々は、広島から送られてきたこのカキを、一昨日は生ガキで、昨日の夜はカキフライにしておいしくいただきました。
ところが、3日目の今日ともなると、そろそろ「あたる」のが気になってくるところです。
送ってくれた姉によれば、昨年の正月に彼女はカキにあたってしまい、上も下も大変だった(ここのところ表現が難しい)とのことで、我々も注意したいところです。
古来より食べられてきたカキですが、その一方で「あたる」食品としてもよく知られています。現代の日本国内で流通している生食用のカキは、極力食中毒を回避するために、一応生産・流通段階で対策がとられています。
とくに生食用として販売されるカキには加工基準が設けられており、カキそのものを対象として規格基準が設けられていて、さらには、保存基準、表示基準も規定されています。
具体的には、加工基準としては、食品衛生法により、大腸菌群最確数が一定以下の海域で採取されたもの、それ以外の海域で採取されたものであって、大腸菌群最確数が一定以下の海水、または塩分濃度3%の人工塩水を用い、かつ、当該海水若しくは人工塩水を随時換え、又は殺菌しながら浄化したもののどちらかであること、などが規定されています。
また、規格基準としては、細菌数(大腸菌)の数や腸炎ビブリオ菌などの数の制限値も決められていて、これらに加え地方によってはさらに厳しい指導基準を条例などで設けている場合もあるようです。
とくに生食用カキではこうした加工基準を満たすために、紫外線殺菌された海水中や人工海水などを充分に循環させた環境下にて絶食状態として数日間飼育されることも多いようです。
しかし、生食用のカキにこうした処理を施す場合、貝表面や貝内部に取り込まれた細菌の大部分は貝内から排出されてほぼ無菌状態にはなりますが、これとは引き替えに、カキの身が痩せてしまったり風味が損なわれたりする場合もあり、加熱処理用のものよりも味が劣ることも多いようです。
また、こうした処理をして出荷されても、生カキを買う側の保存状態がよくなく、このため微量に残っていた細菌やウィルスが繁殖して中毒に至る例もあるようです。
なので、「生食用」と書いてあるから安心せず、こうしたカキを買ってきた場合は、浸かっている塩水を交換する、日にちが経ったら加熱して使うなどして、できるだけ安全策をとられることをお勧めします。
このカキの食中毒症状を引き起こす原因としては貝毒、細菌(腸炎ビブリオ、大腸菌)とウィルスが良く知られており、とくにウィルスとしてはノロウィルスがよく知られています。どの原因も生育環境(海水)に由来するものであり、二枚貝特有の摂餌行動などによって貝内部、特に消化器官(中腸腺など)に取り込まれ濃縮されるものです。
従って、殺菌処理をしているからといって100%安全とは限りません。
「貝毒」というのは、あまり聞き慣れないかもしれませんが、貝が捕食する海水中の有毒プランクトンを蓄積したものです。
これにあたるというのは稀なケースのようですが、その対策としては一応、出荷の段階では、生育海水中の植物プランクトンの種類および貝に含まれる毒が定期的に検査されています。
有毒プランクトンの発生し易い時期は3月から5月なので、とくにこの時期には重点的に検査を行うとともに、濾過海水中で一定期間飼育することで、毒の量を規制値以下に減毒できるそうです。
残るは、細菌とウィルスですが、そもそもこのふたつはいったい何が違うのでしょうか。
細菌というのは、よく「ばい菌」とも言いますが、自分で細胞を持っています。人間に病気を引き起こす細菌は、人間の体の中に入ると、人間の細胞に取り付きます。細菌は、この細胞に取り付き、細胞の栄養を吸い取って、代わりに毒を出して細胞を殺してしまいます。栄養を吸い取った細菌は、自分が分裂して、仲間を増やしていきます。
一方、ウィルスは細菌よりずっと小さく、自分で細胞を持っていません。ほかの細胞に入り込まなければ生きていけないのです。ウィルスが人間の体に入ると、細胞の中に入り込み、その細胞に、自分のコピーを作らせます。
細胞の中で自分のコピーが大量に作られると、やがて細胞は破裂して死んでしまいます。破裂したとき、細胞の中から大量のウィルスが飛び出し、ほかの細胞に入り込みます。こうしてウィルスが大量に増えていくのです。
細菌の場合は自分の細胞を持っているので、細菌をやっつける薬を造ることができます。抗生物質といって、細菌の細胞を攻撃することができる薬です。ところがウィルスには細胞がありませんから、ウィルスをやっつけることは困難です。ウィルスを攻撃しようとすると、ウィルスが入り込んでいる人間の細胞を壊してしまう恐れがあるからです
カキにつく大腸菌のような一般的な細菌は海水中に常時一定数存在するものであり、ごく少量であれば食中毒症状を引き起こすことはありません。しかし、気候や水質、保存方法などによっては細菌が大量に増殖することもあり、生食する際には注意が必要です。
現代の日本国内の生食用カキの場合は、上述のように流通段階では十分な対策が取られているのでまず心配はいりませんが、問題なのはやはり購入者が間違った方法で保存することで、残った少量の細菌を増殖させてしまうような環境に放置することはやはり危険です。
腸炎ビブリオ菌のほうは、20℃付近でおよそ10分間に1回と活発に分裂・増殖しますが、15℃以下では増殖は抑制されます。また、経口摂取によって感染症状を引き起こす際には生菌100万個程度が必要であるとされています。
このことから、腸炎ビブリオ菌対策としては20℃以上の環境に数時間置かないようにすることが、食中毒対策として重要です。とくに夏場が旬のイワガキなどを、家庭で調理する際には十分に注意すべきでしょう。
70度以上1分間の加熱でほぼ死滅するとされているので、加熱処理すればこちらのほうは大丈夫です。ちなみに、大腸菌のほうも75度以上1分間の加熱でほぼ死滅するとされています。
このほか、カキに赤痢菌がついているというレアケースもあるようですが、日本国内産についてはまず問題になることはないそうです。ただし、韓国では2001年にカキが原因で1,000人規模の罹患者を出したことがあるそうなので、スーパーで見かけてカキが韓国産であるかどうかは一応確認してから購入しましょう。
ただ、以前、韓国産のカキが日本国内において、国内産として産地偽装され流通されていることが発覚したこともあり、こうした場合の対処のしようはありません。が、一般にこうしたカキは安価であるはずなので、安すぎる生ガキを見たら注意しましょう。
一方、カキのウィルスと言えば、やはりノロウィルスです。2000年頃より急に増えてきており、こちらにかかった時の病状は細菌よりもはるかに過激です。
その感染力は85℃以上で1分間以上加熱されることにより破壊されると考えられていることから、ノロウィルスにかかりたくなかったら、中心部まで十分に加熱することがまず重要です。
2001~2003年の調査では、生食用カキの12.9%、加熱加工用カキの24.4%がノロウィルスで汚染されていたという統計もありますが、最近はかなり汚染防止対策が進んだことから少なくなっているようです。が、対策をとるに越したことはありません。
ところで、このウィルスというのはそもそも何者なのでしょうか。細菌との違いは上述の通りですが、改めてどういうものかと聞かれるてすぐ答えられる人は少ないのではないでしょうか。
そこで調べてみると、ウィルスというのは、「細胞を構成単位としないが、遺伝子を有し、他の生物の細胞を利用して増殖できる」という性質を持ち、一応、生物としての特徴を持っているものなのだそうです。
現在でも自然科学は生物・生命の定義を行うことができておらず、便宜的に、細胞を構成単位とし、代謝、増殖できるものを生物と呼んでおり、細胞をもたないウィルスは、非細胞性生物として位置づけられています。
生物であるようで生物でないので、生物というよりむしろ「生物学的存在」といわれることのほうが多いようで、とはいいながら、遺伝物質を持ち、生物の代謝系を利用して増殖するウィルスは生物と関連があることは明らかです。
感染することで宿主の恒常性に影響を及ぼし、病原体としてふるまうことも多く、ウィルスを対象として研究する分野はウィルス学と呼ばれる専門分野が確立されているほどです。
ウィルスが一般的な生物と大きく異なる点は、まず我々生物の体は細胞が構成されていますが、ウィルスは非細胞性で細胞質などは持たないことです。また、基本的にはタンパク質と核酸からなる粒子にすぎないというところも違います。
さらに大部分の生物は細胞内部にDNAとRNAの両方の核酸が存在しますが、ウィルス粒子内には基本的にどちらか片方だけしかありません。さらに他のほとんどの生物の細胞は2n乗で指数関数的に増殖していくのに対し、ウィルスは一段階づつしか増殖しません。またウィルス粒子が見かけ上消えてしまう暗黒期が存在する点も細胞と異なります。
このほか、ウィルスは単独では増殖できず、他の生物の細胞に寄生したときのみ増殖できるという特性があり、しかも自分自身でエネルギーを産生せず、宿主細胞の作るエネルギーを利用する非常にいやらしいヤツです。
その詳しい生物学的な説明は、専門家でもないのでこれ以上差し控えますが、ウィルスの増殖は以下のようなステップで行われます。
細胞表面への吸着 → 細胞内への侵入 → 脱殻(だっかく) → 部品の合成 → 部品の集合 → 感染細胞からの放出
感染細胞から放出されたらまた別の細胞を探して吸着・侵入・合成・集合・放出を繰り返して増えていきますが、その過程は一段階づつなので、細胞のように増殖し始めると止まらない、といった急激な変化はありません。
ただし、ウィルスによる感染は、宿主となった生物に細胞レベルや個体レベルでさまざまな影響を与えます。その多くの場合、ウィルスが病原体として作用し、宿主にダメージを与えるという非常にやっかいなものです。
しかも、ウィルスが感染して増殖すると、宿主細胞が本来自分自身のために産生・利用していたエネルギーや、アミノ酸などの栄養源がウィルスの粒子複製のために奪われ、いわば「ウィルスに乗っ取られた」状態になります。
これに対して宿主細胞はタンパク質や遺伝子の合成を全体的に抑制することで抵抗しようとしますが、一方でウィルスは自分の複製をより効率的に行うために、さまざまなウィルス遺伝子産物を利用して、宿主細胞の生理機能を制御しようとします。
またウィルスが自分自身のタンパク質を一時に大量合成することは細胞にとって生理的なストレスになり、また完成した粒子を放出するときには宿主の細胞膜や細胞壁を破壊する場合もあります。このような原因から、ウィルスが感染した細胞ではさまざまな生理的・形態的な変化が現れます。
その生理機能の変化によって、ウィルスが感染した細胞は色々な方向で変化していきますが、まず典型的なものとしてあげられるのは、ウィルス感染によって細胞が死んでしまうことです。
ウィルスが細胞内で大量に増殖すると、細胞本来の生理機能が破綻したり細胞膜や細胞壁の破壊が起きる結果として、多くの場合、宿主細胞は死を迎えます。これは生物にとっては致命的なことではありますが、一方では感染した細胞が自ら死ぬことで周囲の細胞にウィルスが広まることを防いでいると考えられています。
このほか、ウィルスがもたらす生物の生理的な機能の変化としては持続感染というのがあります。
これは、ウィルスによっては、短期間で大量のウィルスを作って直ちに宿主を殺すのではなく、むしろ宿主へのダメージが少なくなるよう少量のウィルスを長期間に亘って持続的に産生(持続感染)するものです。持続感染の中でも、特にウィルス複製が遅くて、ほとんど粒子の複製が起こっていない状態を潜伏感染と呼びます。
もうひとつが、細胞の不死化(細胞の老化)と「がん化」です。こうした生理変化をもたらすウイルスを腫瘍ウイルスあるいはがんウイルスと呼びます。
ウイルスが宿主細胞を不死化あるいはがん化させるメカニズムはまちまちです。が、ウィルスの種類によっては宿主のゲノムにウイルス遺伝子を組み込むものもあり、この場合にはがん抑制遺伝子が潰された結果、がん化する、つまり細胞は癌細胞に変化します。
ノロウィルスは、上記三つのうちの、一番最初の型のウィルスです。ヒトに経口感染して十二指腸から小腸上部で増殖します。このとき、毒素は分泌せずに十二指腸付近の小腸上皮細胞を脱落させ、伝染性の消化器感染症(感染性胃腸炎)を引き起こします。
死に至る重篤な例は稀ですが、苦痛が極めて大きく、稀に十二指腸潰瘍を併発することもあります。
我々の子供のころにはそんなものはなかったよな~と思ったら、それもそのはず、発見されたのは、1968年のことで、アメリカ合衆国オハイオ州ノーウォークの小学校において集団発生した急性胃腸炎患者の糞便から検出されたのが始めてだそうです。
この地名にちなみ、当初「ノーウォークウィルス (Norwalk virus)」と命名され、その後このウィルスによる胃腸炎・食中毒が世界各地で報告されようになりました。
その後、1977年になって、札幌で幼児に集団発生した胃腸炎からノーウォークウィルスとよく似た小型球形ウィルスが 病原体として発見され、これが「サッポロウィルス (Sapporo virus)」と名付けられました。
2002年にパリで行われた、第12回国際ウィルス学会では、それまで「ノーウォーク様ウィルス属」と呼ばれていたものを「ノロウィルス属 (Norovirus)」、「サッポロ様ウイルス属」と呼ばれたものを「サポウイルス属 (Sapovirus)」と区別して呼ばれるようになりました。
しかし、その後日本では後者よりも、前者のほうの発症率が高く、「ノロウィルス」がこの感染症の標準語のようになっていきました。
ところが、2011年に札幌で行われた、国際微生物学連合会議では、「ノロ(NORO)」姓の子供、つまり「野呂」などの子供たちがいじめやからかいを受けるおそれがある、という指摘があり、「ノロウイルス」名称について各国の専門家たちと深く議論を行いました。
その結果、「ノロウイルス」というのは属名であって、そのようなウイルス種名は存在しない、ゆえに正しい呼称(種名であるノーウォークウイルス)を使用すべきであるという声が多くあがりました。
こため、この会議ではノーウォークウイルスに起因する病気の発生に対して「ノロウイルス」という用語を使用しないよう、メディア、医療・保健の各機関、科学者団体に強く求める」という趣旨のプレスリリースを発表したのですが、それまでの慣行からか日本ではあいかわらずノロウィルスと呼ばれています。
日本ではかつて「お腹の風邪」と呼ばれていましたが、その症状は単なる風邪というよりかなり激烈であり、主な症状は突発的な激しい吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、悪寒、38℃程度の発熱で、嘔吐の数時間前から胃に膨満感やもたれを感じる場合もあります。
1年以内に感染していない人や、先天的に免疫ができない人、抵抗力が弱い老人や子供などはウィルス感染を起こしやすく、激しい感染性胃腸炎を引き起します。
通常1~2日で治癒するようで、後遺症が残ることもありませんが、免疫力の低下した老人や乳幼児では長引くことがあり、死亡した例も報告されています。お年寄りなどではとくに、吐瀉物を喉に詰まらせることによる窒息などが多いようです。
ただし、感染しても発症しないまま終わる場合もあり、これを「不顕性感染」といい、その症状は普通の風邪とも似ています。吐き気や下痢などはなく、普通の風邪と同様の症状しか現れないのです。
このため、一般にノロウィルスの症状は「嘔吐、下痢、腹痛を伴う風邪」というふうに表現されることも多いようですが、これら普通のように見える風邪が実はノロウイルスによる感染症によるものである可能性も低くはないそうです。
従って、これらの人でもウイルスによる感染は成立しており、こうした風邪引きさんの吐しゃ物やくしゃみ、鼻水に触ったりするのは厳禁ですし、とくに糞便中にはかなり大量のウイルス粒子が排出されているため、その処理には厳重な注意が必要です。
このノロウィルスの治療ですが、特別な治療法は確立されていないそうで、かかってしまったら、仕方がない、というかんじのようです。ただし、激烈な症状はせいぜい数日、この間、苦しいけれども我慢しさえすれば回復は早いようです。
ただし、感染から発病までの潜伏期間は12時間~72時間(平均1~2日)だそうで、症状が収まった後も便からのウイルスの排出は1~3週間程度だとすると、一カ月間をこのウィルスとお友達にならなければならなくるわけです。しかもこの間、自分が感染源になることを考えれば、極力これにはかかりたくないものです。
場合によっては、7週間を越えての排出も報告されており、しかも11~3月の発症が多く報告されてはいるものの、年間を通じて発症もありうるということです。
2007年に報告された厚生労働省食中毒統計による食中毒報告患者数は、71%がノロウイルス属感染症ということで、かなりの高率です。
血液型で感染率に差があるそうで、当初、O型は罹患しやすくB型は罹患しにくいことなども報告されていたようですが、最近はウイルス株の各遺伝子型によって様々な血液型でのノロ感染が増えつつあるそうなので、A型だから大丈夫といったことはないようです。
ただし、ヒト以外では発症しないとされており、ノロにかかったからといって、愛猫や愛犬と離れて暮らさなければならない、というような悲哀はないようです。とはいっても、感染したからといって、腹いせにイヌネコの上にゲロしたりしないようにしましょう。
厚生労働省や保健所では、カキなどに代表される二枚貝は、食す際には内部まで十分に加熱調理するように、また調理の際に使用した器具の十分な洗浄を呼びかけていますが、生ものを食べることが大好きな日本人は、冬場のカキを何かにつけ食べたがります。
最近、ノロウィルスが流行している原因としては、感染者の排泄物に含まれるウィルスを下水処理場では十分に除去できないことから、排水が流入する養殖海域で養殖される貝類にノロウィルスが付着することなどが指摘されています。
こうしたことから、日本では報道のせいもありますが、「ノロウィルスと言えばカキ」という印象が広まり、特に2006年から2007年にかけてノロウィルス感染報道があるごとにカキの売上が減少しました。
一方、韓国などでは、下水汚泥や糞尿の海洋投棄が行われている例があるそうで、水域全体がウィルスにより汚染されている場合があり、2012年6月にはアメリカ合衆国の食品医薬品局が韓国から輸出するカキ、二枚貝、ムール貝の衛生基準が不十分であるとして市場からの回収要請を出しているほどです。
従って、日本でのノロウィルスの蔓延には、韓国から入ってきているカキによる感染の拡大もあるのかもしれません。
とまれ、生で食べる場合には日本産であれ韓国産であれ、ノロにかかる可能性は否定できません。塩水でのすすぎを欠かさないなど、十分な対策に気を付けましょう。
カキは、英名に「R」のつかない月、すなわちMay, June, July, Augustの5、6、7、8月は産卵期であり食用には適さないとされています。まだ今の時期は、そのグリコーゲン含量がどんどん増えている時期であり、まだまだカキのおいしい時が続きます。
冷蔵庫に残ったカキを今日は何にして食べようか、今考え中です。みなさんの今晩のお献立はなんでしょうか?もしかしたらカキなべ?それともカキの釜飯でしょうか。
美味しいカキの食べ方があったら、ぜひご一報ください。