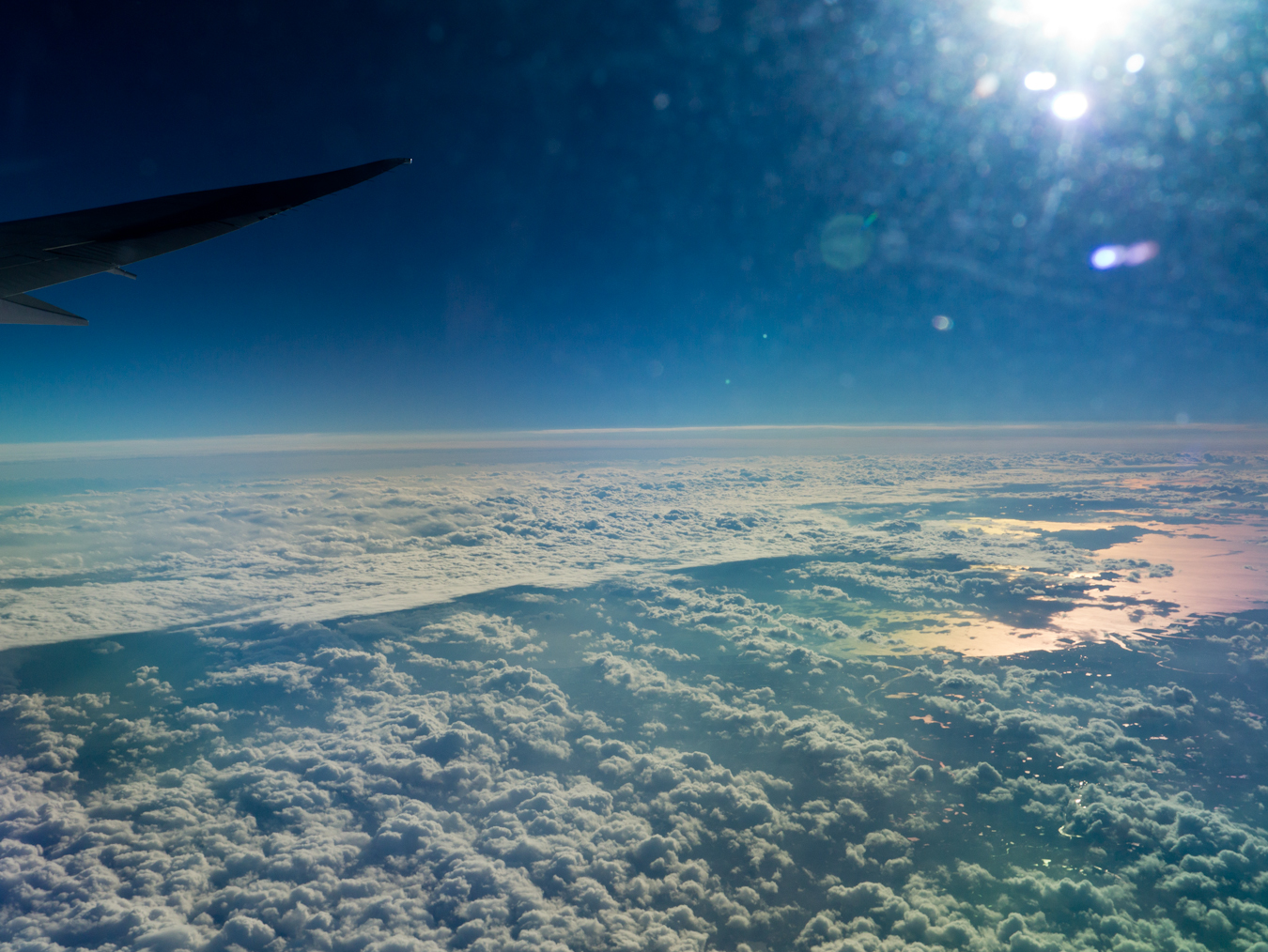姉の末っ子の姪が結婚をするというので、その式に出席するためでしたが、ひさびさの旅行らしい旅行だったので、二人して大興奮だったのは言うまでもありません。
その結婚式の様子や、この旅行での出来事の数々についてはまた詳しく書き記すとして、今回のこの旅ではまた、ひさびさに飛行機に乗りました。
往復とも広島空港発着の最新式の787であり、かねてよりバッテリーの発火問題などで色々トラブルのあった機体であったことなどは、このブログでもかつて書きました。
が、そんな心配などみじんもないほど安定した飛びっぷりで、帰りに羽田に降りる際には、気象条件が少々悪く、結構揺れたのですが、急激に変わる気流の変化を軽く受け流しながら降下し、綺麗な三点着陸を果たしました。
無論、操縦するパイロットさんの技量にもよるのでしょうが、やはり最新鋭の機体をコントロールする装置などのたまものなのではないか、と思ったりもしたものです。
ここしばらく、おそらく3年以上飛行機には乗っていなかったのですが、往復の機内でのサービスは、従前と変わらず行き届いたもので、スチュワーデスさんの対応にもまた、日本ならではの「お・も・て・な・し」の精神は健在で、細かいところにも注意が行き届く、気持ちが良いものでした。
……と書いてきたところで、最近はこの「スチュワーデス」というのはあまり一般的な用語ではないのだな、と気づきました。
かつての日本の航空会社では、船舶の男性司厨員に由来する「スチュワード」と女性スタッフの「スチュワーデス」を客室乗務員の名称として採用して用いるようになったもののようですが、最近ではこの呼び方はなりをひそめ、「CA(Cabin Attendant)」「キャビンアテンダント」と呼ぶことのほうが多いようです。
実はこれは正式な英語ではなく、TVドラマなどの影響で作られた和製英語である、というのは意外と知られていません。正しい英語としては「フライトアテンダント」(Flight Attendant)、もしくは「キャビンクルー」(Cabin Crew)が正解です。
なんでもかんでも横文字にしたがり、それをカタカナで使っているうちに標準語になってしまうというのは日本ではありがちなことですが、それにつけても、CAのことを正しい英語であると主張してやまない輩もいたりして、そういう人に限って英語は得意でないことが多かったりします。
そもそも何でも、アルファベットを並べて説明したがる日本の風潮を私はかねてから苦々しく思っていて、BGMとかCADなどの分かりやすいものはまぁ許せるとして、LTEとか、IPとかいった本来は難解なコンピュータ用語までをも、意味もわからずにしたり顔で使っている人をみると、なにやら妙に腹がたってきます。
意味がわからない用語をそのまま略して使うのではなく、きちんと日本語に直してから略すなり流行させるなりすればいいのに、と思うのですが、その手間暇を省いて広めておいて、みんな分かったような顔をする風潮はそろそろやめればいいのにと、思うのですが、みなさんはいかがでしょう。
ま、それはともかく、この女性客室乗務員のことをスチュワーデスと呼ぶのは、かつては普通のことであり、これに対して「スチュワード」のほうは、男性乗務員がほとんどいないこともあり、あまり一般的な用語としては広まりませんでした。
むしろ、スチュワードと同じ意味の「パーサー」などと呼ばれる機会のほうが多く、男性乗務員というと、こちらのほうが正しいと思っている人さえいるのではないでしょうか。
女性乗務員の呼称としては、スチュワーデス以外にも、「エアホステス」「エアガール」などというのもあったようですが、ホステスのほうは、水商売のマダムみたいに聞こえるし、エアガールというと妙に軽々しいかんじもするためか、やはり「スチュワーデス」と呼ばれることのほうが多かったようです。
ところが、このスチュワーデスという呼び方は、日本では1990年代以降急速にされなくなり、今ではほとんどお蔵入り状態です。
調べてみると、これは1980年代以降、アメリカにおける「ポリティカル・コレクトネス」という風潮が出てくるようになり、この社会現象が日本へも伝播し、浸透したためのようです。
ポリティカル・コレクトネス(political correctness)というのは、それまでごく普通に使われていた用語に、社会的な差別・偏見が含まれていることが「発見」された場合、これを修正、すなわちCorrectしようとする動きであり、修正というよりも、むしろそういう言葉を見つけ出して、なくしてしまおう、とする社会的な動きです。
ご存知、人種のるつぼと呼ばれるアメリカでは、職業や性別、年齢・婚姻状況といった基本的な人的違いはもとより、文化・人種・民族・宗教などなどの各分野において多様な性格を帯びる人々が暮らしており、これに加えて、近年福祉国家としての発展を続ける中、ハンディキャップなどに基づく差別・偏見などに関する数々の問題も浮上してきています。
ポリティカル・コレクトネスは、こうしたアメリカに生じた差別や偏見を防ぐ目的で、言葉の表現や概念を変えていこうと起こった運動であり、とくに1980年代に入ってから、「用語における差別・偏見を取り除くために政治的な観点から見て正しい用語を使おう」という動きが活発になり、広く認知されるようになっていきました。
「偏った用語を追放し、中立的な表現を使用しよう」というわけであり、言葉を是正することによって、国家内の差別是正全体をめざそうという動きでもあります。法制化されたわけではありませんが、社会的な風潮として、いまやアメリカ各地で浸透しています。
また、こうした運動はアメリカ国内だけにとどまらず、ヨーロッパにも飛び火し、ひいては西側諸国の一員である日本でも流行するようになった、というわけです。
無論、もともとはアルファベットを用いる英語などの言葉を母国語とする欧米各国で起こったことだったわけですが、上述のとおり、なんでもかんでも外来語をカタカナに書き換えて、あるいはその手間を惜しんで略語のまま使うことが大好きな日本人の間でも近年急速に広まっていきました。
この運動は(そもそも「運動」といえるかどうかもあやしいところですが)、社会的な差別・偏見が含まれていない公平な表現・用語を推奨しています。適切な表現が存在しない場合は、新語が造られることもあり、上述のスチュワーデスが、キャビンアテンダントなどという和製英語に置き換えられたのは、その好例といえます。
このとき、そもそもの「客室乗務員」を表す英語である、「Flight Attendant(フライトアテンダント)」という単語をなぜそのまま使わなかったのかよくわかりませんが、1990年代にはその業績も好調であった、日本航空がまず、1996年9月末日で「スチュワーデス」という呼称を廃止しました。
廃止した理由は、それまでの経緯から、スチュワーデス=女性という構図があまりにも定着してしまっており、女性特有の職業である、との世間からの印象を払しょくしたかっためでしょう。「偏った用語を追放し、中立的な表現を使用する」というポリティカル・コレクトネスがここでも適用されたわけです。
そして、「アテンダント」(AT)と呼ぶように改めたことから、この上に「キャビン」を冠して、いつしかキャビンアテンダントと呼ばれるようになっていったようです。
ちなみに、同時期にANA(全日本空輸)もまた、「スカイサービスアテンダント」呼ぶように改めたようですが、正式名称はそうであっても、やはり巷では「キャビンアテンダント」と呼ぶ人のほうが多くなってしまい、いつのまにやら社内外においてもCAのほうが通りがいい、ということになってしまっているようです。
とはいいながら、スチュワーデスと呼ばれた時代があまりにも長かったため、その後も日本ではこうした大手の航空会社自身が「スチュワーデス○○」などの言葉を女性の客室乗務員に対する用語として様々な形で使い続けており、マスコミなどでも多用されていて、スチュワーデス、という呼称がまったく消え去った、というわけではないようです。
略語で「スチュワーデス」さんのことを「スッチー」さんと呼ぶ人も多く、私自身もこの呼称の愛用者でもあります。
にもかかわらず、いまや「スチュワーデス」という用語は、キャビンアテンダントに駆逐されようとしており、この誰もが英語と信じて疑わない和製英語が、新聞や雑誌をはじめ、いたるところに氾濫しています。
こうしたポリティカル・コレクトネスの当初のアメリカにおける代表的なものとしてあげられるのが、英語の敬称において男性を指す「Mr.」や「Woman」などの性別に関するものです。
例えば英語では、Mr.が婚・既婚を問わないのに対し、女性の場合は未婚の場合は「Miss(ミス)」、既婚の場合は「Mrs.(ミセス)」と区別されますが、これを女性差別だとする観点から、未婚・既婚を問わない「Ms.(ミズ)」という表現に置き換えられるようになりました。
そもそもこの「Ms.」というのは、「mister」の女性形で、未婚・既婚を問わない語として17世紀頃に使用されていました。が、その後、女性を丁重に扱う場合には「Miss」「Mrs.」と区別したほうがいい、という風潮のほうが強くなっていたことから消え去っていたものが、奇しくもポリティカル・コレクトネスによって復活する、ということになったのです。
このように、言語において男性と女性の別を設けるのは女性蔑視にあたり、差別だとする風潮は、それまでは、伝統的に男性であることを示唆する)「~man」がつく「職業名」についても、女性差別的であり、ポリティカル・コレクトネスに反するものとされるようになり、manに代わって、「~person」などが使われるようになりました。
一例としては、「議長」を表す、chairmanが、chairpersonに、また、「警察官(policeman)」がpolice officerに、「消防官(fireman)が、fire fighterに、といった具合です。
この風潮は、日本にも及んでおり、例えばこれまでは、実業家のことを「ビジネスマン(businessman)」と呼んでいたものが、最近では「ビジネスパーソン(businessperson)」
と呼ばれることが多くなっているのに気が付いている人も多いでしょう。
同様に、重要人物のことをその昔は、「key man」と読んでいたものが、最近ではポリティカル・コレクトネスの影響を受けて、「キーパーソン(key person)」と呼ぶ機会が増えています。
最近の日本の例では、このほかにも「専業主婦」などの例のように、女性であることが当然と決め付けるような表現も問題となっているそうで、じゃぁなんて呼ぶのよ、ということなのですが、「お籠りバーさん」でもまずいし、「子守オヤジ」もいけないとすれば、「専業家庭人」とでも呼べというのでしょうか。
このほか、アメリカにおけるポリティカル・コレクトネスは、人種・民族用語においてもその修正を迫りました。
黒人を指す「Black(ブラック)」がアフリカ系アメリカ人を意味する「African American(アフリカン・アメリカン)」に置き換えられたことは多くの人がご存知でしょう。とはいえ、肌が黒いからアフリカ系だとは限らず、またアフリカ出身だから黒人だとも限らないわけです。
また、African Americanは、「アフリカ系アメリカ人」を指し、これはアメリカに奴隷として連れてこられて以降の歴史が長い人種を意味します。が、一方では、奴隷制度が存在しない近年の移民で、そもそも英語を母語とせず、アフリカ以外の国から移住してきた者も、「アフリカ系アメリカ人」と呼べるか、というとそうではありません。
例えば、フランスで生まれて育ち、言語もフランス語の黒人もいるわけであり、これらを含めて一括して、アフリカン・アメリカンと呼ぶのには無理があり、こうした人達の中にはこう呼ばれるのを嫌がる人も少なからずいるようです。
また、人種の壁をなくそうと、アメリカの先住民族をさす「Indian(インディアン)」と呼ぶのをやめようという動きもあります。
インディアンというのは、もともとインド人という意味ですが、コロンブスがアメリカ中部のカリブ諸島に到達した時に、ここをインド周辺の島々であると誤認し、先住民をインド人の意味である「インディオス」と呼んだために、以降アメリカ先住民の大半をインディアンと呼ぶようになったものです。
が、インド人であるにせよ、アメリカ先住民であるにせよ、インディアンという呼び方は人種差別を思い浮かばせる、ということで、最近では「Native American(ネイティブ・アメリカン)」という表現に置き換えられており、またカナダでは「First Nation(ファースト・ネーション)」と呼ばれています。
さらに、とくに北米などでは、多様な宗教に配慮をしようという動きもあり、例えばクリスマスはキリスト教の行事であるため、公的な場所・機関、大手企業では他の宗教のことも考慮して「メリー・クリスマス」と言わずに、最近では「ハッピー・ホリデーズ」と呼ぶようです。
ホリデーズとしたのは、日本ではクリスマスは休日ではありませんが、アメリカなどでは、クリスマスは休日であることが多いためです。このほか「クリスマスカード」も「グリーティングカード」に置き換えられており、これはSeason’s Greetingつまり、「季節のご挨拶」の意味であって、これなら宗教臭さは消え去ります。
2004年に、ブッシュアメリカ合衆国大統領が年末のあいさつをしたときにも、「メリー・クリスマス」ではなく、「ハッピー・ホリデーズ」と述べたそうで、このほかヨーロッパにおいても、イタリアなどでは小学校の年末の演劇会において、例年恒例であったキリスト生誕劇を止めて、「赤ずきん」などに演目を変えるところが増えているとか。
とはいえ、欧米ではこうした宗教におけるポリティカル・コレクトネスは、伝統や文化の否定にもつながる、ということで、反対意見もあり、論争となっているそうです。
また、フランス語やスペイン語では、男性名詞や女性名詞などのように、その言語における名詞や動詞、形容詞で男性形と女性形を分けており、言語において性別による差別の是正という点に関しては、あまりポリティカル・コレクトネスは進んでいないといいます。
アメリカなどでも、マンホールを意味する語を「manhole」から「personhole」と言い換えるのはさすがに行き過ぎとの批判も存在し、また日本においても、これは「言葉狩り」ではないかという人もいて、表現の規制につながる物であるとの批判があり、こうした表現の書き換えは、表層を変えるだけで何の本質的な意義がないとの批判も存在する声も多いようです。
たとえば、固有名詞として国民の間で広く定着している、「ウルトラマン」や「スーパーマン」、「スパイダーマン」を、ウルトラパーソンやスーパーパーソン、スパイダーパーソンと言いかえるか、といえば、誰もが嫌な顔をするでしょう。
アンパンマンに至っては、「アンパンパーソン」と言い換えたら、「わかんなーい」と多くの幼稚園児たちが大泣きするにちがいありません。大和ハウスのダイワマンをダイワパーソン、と言い換えたら、ファンからは大ブーイングがおこりそうです。
そもそも、この「ポリティカル・コレクトネス」という言葉は、アメリカ合衆国における政治の世界で、保守派などがその巻き返しにより、「人権政策」を掲げ、これに関する政策を選挙戦における目玉としようとしたところから出てきたようです。
「ポリティカル(political)」は、「政治の」、「政治に関する」の意であり、このことからもこれが政治用語だとわかります。わざわざ政治用語であることをわからせるために、その「まんま」の表現を冠したところを評して、「見てくれ」を狙った薄っぺらい政策であるとあからさまに批判する向きも当初からあったようです。
かくして、そんなことも露しらず、単に欧米で流行っているからという希薄な根拠の中において、日本においてもポリティカル・コレクトネスは浸透するようになり、発祥から20年以上経過した現在でもいまだその「発見」と「駆逐」は進行中です。
例えば、ちょっと前から「看護婦」は女性蔑視だということで、男性の看護士も含む「看護師」に改められ、「保健婦」は「保健師」、「助産婦」は「助産師」となりました
かつては、保母さんと言っていたものが、最近は男性も多いことから、「保育士」と呼ばれるようになり、こうした幼児教育施設や病院関連の福祉施設では世相を反映したポリティカル・コレクトネスが続々と進んでいます。
が、これらについてはこれまで女性の独断場と思われていた職場への男性の進出が相次いできているためか、あるいはその逆もあって、特に否定的な声はないようです。
ちなみに、この助産師に関しては、「師」といいながら、今でも、法律的には、資格付与対象は女性だけに限られています。が、将来的には、生まれてくる子供を取り上げる男性助産師も増えてくることになるかもしれません。
ところが、同じ福祉や医療の世界では、かつて「障害者」と呼んでいたのを、最近は「障がい者」とわざわざひらがなで書くことが奨励されています。ここまでくると少々やりすぎではないの、という気もしますが、これは「害」の字が周囲に害を与えるという印象を回避するためだということです。
こうした福祉用語以外にも、医学用語として「痴呆症」と呼んでいたものが最近は、「認知症」に、また、精神分裂病は「統合失調症」、らい病(癩病)は「ハンセン病」と呼ばれるようになっています。
痴呆というのは確かに多少悪意のある表現であると誰もが認めるところでしょうが、それでもバカやアホに比べれば格段に格調高い表現であり、また「癩」というのは、その症状から来ており、「鱗状の~」とか、「かさぶた状の」という意味であって、患部の状況を適切に表した非常にわかりやすい用語ではあります。
ところが、この病気に罹患したその外見を忌み嫌い隔離しようとした時代があったことからこれを反省し、この用語を使うのをやめよう、ということになったようですが、日本語の表現方法としてはかなり巧みな部類に入るものである、と言わざるを得ません。
精神分裂病もまたしかりです。精神がズタズタに引き裂かれるといえば、どういう状態かはすぐにわかるわけであり、実際に発症した方々の周囲では反論もあるでしょうが、なかなかうまい表現だと私は思います。
また、日本でも人種差別用語として多くのことばが改められてきています。かつての「土人」は、「先住民」に、トルコ風呂は「ソープランド」に改められ、肌色は、現在では「ぺールオレンジ」もしくは、「うすだいだい」と呼ばせるようです。
土人というのは、そもそも北海道におけるアイヌのことを指していたそうで、アイヌを先祖とする人々への蔑視だということで廃止されたもので、トルコ風呂もトルコの人達に配慮された結果廃止されました。
「肌色」については、従来からクレヨンやクレパスの色として慣れ親まれてきたものですが、これもネグロイドの肌は褐色で、白人の肌は白であることから、こうした言葉を使うことが人種差別につながる、ということのようです。
が、肌色の「肌」という言葉から、黒人や白人を連想する日本人がいったいどれだけいるというのでしょうか。
かつて、日本で「ちびくろサンボ」という大変抒情豊かな童話絵本がありましたがこれも「くろ」が黒人蔑視にあたるとして、出版社の自主規制により廃刊となり、いまやどこの本屋へ行ってもみられなくなってしまいました。これは必ずしもポリティカル・コレクトネスとはいえないかもしれませんが、その風潮の延長の上で起こったできごとです。
さらには、日本でも性別によるポリティカル・コレクトネスが進んでいます。
学校などで名前を呼ぶとき、その昔は男子に「~君」、女子に「~さん」を用いていたのを、最近では男女とも「~さん」と呼ぶことが奨励されているそうで、実際に教育の現場で実践している学校も多いそうです。
ところが、慶応義塾大学の関連教育期間では、男女とも「~君」で呼び合うそうで、これは「先生」は創設者福澤諭吉だけという考え方から、教授を含む教師陣も含めすべて平等に先生以外の呼び方、つまり君付けで呼び合う、という風習があったことからきているそうです。
もともとは先生同士がお互いを呼び合う際に用いていたようですが、次第に生徒を呼ぶときにも君づけで呼ぶようになっていったようです。こうした伝統はやがて慶応以外の他校にも及び、現在でも各地の教育現場で生徒を女性であっても~君と呼ぶ先生がいるのはこのためです。
が、これは男女を平等に扱う風習としては数少ない例外であって、実際には現在でも、~さん、~君で男女を使い分けることが一般的です。しかし最近は、とくに指導がなくても、男子生徒のことを「~さん」と杓子定規に呼ぶ先生が増えているそうで、私などは、こうした話を聞くと、なんだか学校現場も殺伐としてきたな、という印象を覚えます。
逆に一般的な職場では、男性だけを君と呼ばず、女性をも君付けで呼ぶところも多くなっているという話も聞きます。また従来は女性を呼ぶ際には、その昔は愛情をこめて「~ちゃん」と下の名前で呼んでいましたが、現在ではこれも差別的だということで、苗字だけで~君と呼ぶようにと、わざわざお達しまで出している会社も多いとか。
男女の別を何をそこまで無理してなくす必要があるのかと私は思うのですが、みなさんの職場や学校ではいかがでしょうか。
このほか先ほどの障害者の呼び方にも関連しますが、最近は「ブラインドタッチ」のことを、「タッチタイピング」と呼ばなければならないそうで、これは、無論「ブラインド」が「盲目」」を意味し、視覚障碍者を差別することにつながるから、ということのようです。
盲目といえば、生物名でも、それまでは「メクラウナギ」と呼んでいたものを最近では、「ヌタウナギ」と呼ぶそうで、このほかにも、イザリウオをカエルアンコウ(いざりとは足の不自由な人のこと)、オシザメをチヒロザメ、セムシウナギをヤバネウナギ、バカジャコをリュウキュウキビナゴへ、といった改名がみられます。
こうした、ポリティカル・コレクトネスについては、行き過ぎたものもあるようですが、必ずしもそのすべてが批判されるようなものではありません。
改名、変名がすべて改悪というわけではなく、認知症、統合失調症などは言葉を変えた事により当事者や家族の気持ちが多少なりとも楽になったという人も多いようで、とくに病気が傷害といった医療の分野などで差別されていた人達が、こうしたポリティカル・コレクトネスの普及によって救われた、という例が多いようです。
しかし、このように言葉を変える事による心理的影響は無視できず、行き過ぎは表現の自由を束縛するものであるとして、批判する人もまた多数います。
表現者が自ら斟酌して自らの表現に制限を課すことを「自主規制」と呼びますが、こうした面でのポリティカル・コレクトネスが進行しすぎ、日常慣例化すると、これはやがて「タブー」になっていきます。
とくに芸術の世界においては、不特定多数の大衆を対象とした表現をなすことが多いことから、文芸などにおいては著者や出版社が、音楽の世界においては作曲家や作詞家、レコード会社、放送局などが主体的に判断して言葉の置きかえや著作物の発表を取り止めることなども往々にしてあります。
日本のテレビやラジオなどの放送局では、身体的障害を表現する用語を「放送禁止用語」などとして「○○が不自由な人」と言い換えるのが一般的ですが、これを例えば、過去に出版された文学作品においても適用しようとすれば、それは文学ではなくなってしまう可能性があります。
行き過ぎたものは、「言葉狩り」にほかならず、今日では、このような文学作品には、末尾などに「差別用語とされる語も含むが、当時の状況を鑑みまた芸術作品であることに配慮して原文のままとした」などと記されることも多くなっています。
受け手の立場や考え方などにより、不適切とも適切ともなるひとつひとつの表現を直接の表現者ではない第三者が判断して規制することは非常に難しいことです。
例えば「漫画」では、「ユーモア」と「毒」が作品の味付けに不可欠といわれていますが、差別表現で問題を起こした作品の「ユーモア」や「毒」は許されないもので、ときにそのような作品に限って発行部数が大きい場合も多く、こうした場合にはその社会的影響は非常に大きなものになります。
したがって、言葉の表現者には、才能やセンスがあることも重要ですが、その表現には「人権感覚」が強く求められなくてはなりません。
しかし、人権感覚はその専門家を称する運動団体の関係者ですら、差別のカテゴリーが異なると「自信がない」と述懐するほど難しい問題であり、出版業界などでもこうした人権感覚を養うためには、何十年もの経験が必要だという人もいます。
いわんや研鑽しても、その能力を培うことができない人も多いそうで、各出版社ともそうした人を養成するために、社内啓発に努力していますが、なかなかそういう能力は簡単には身につかないようです。
ましてや、国民の多くが接するような学術用語や、医学用語、福祉用語といった、難しい分野の用語を、こうした感覚が希薄な役人たちが司り、「勝手に改変しようとしている」とまで言い切るのは少々行きすぎかもしれませんが、彼等の造った新用語が必ずしも意味があるものばかりとはいえません。
先述の障害者の「害」を変えるなどというのは、明らかに行き過ぎです。「障害」というのはれっきとした由緒正しい日本語であり、わざわざ変える必要はないと思います。
このように、なんでもかんでも、時代に合わないから、差別だからという主張のみでいつのまにやらどんどん変えていってしまっている最近の風潮には少々苦言を呈したいと思います。
従来からある言葉の意味をかみしめ、その文化的な意義も確かめながら本当に必要なものだけを変えていかなければ、こうした風潮は文化の退潮にもつながっていくのではないかと思います。
なので、スチュワーデスはそのままでよく、キャビンアテンダントなどという、わけのわからない用語に変更する必要はないのです。
いまあなたが使っている言葉が、本当に意味がある言葉なのか、また意味が分かって使っているのかどうか、今一度、考えてみてください。