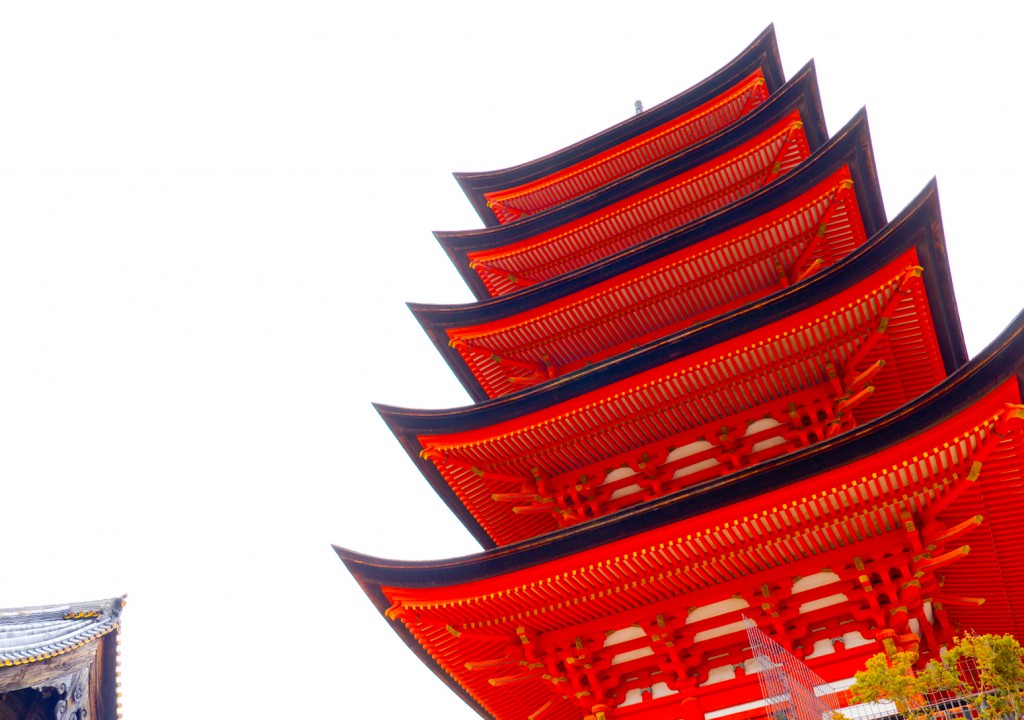クリスマスも終わり、大晦日へのカウントダウンが始まりました。
そろそろ今年一年を振り返るころかな、と今年起こった出来事などが記載されているWEBページを眺めていたのですが、いやはや今年も色々ありました。
それを全部ここで挙げることはできませんが、例えば気象に関していえば、今年はかなり異常でした。
夏には高知県四万十市でこれまでの国内最高気温を更新し41.0°Cを記録、また気象庁の927観測点のうち143箇所でもこれまでの最高気温を更新するなど、各地で記録的な猛暑となりました。
一方、オホーツク海高気圧の影響により東北地方では梅雨明けが遅れ、また関東地方では早期に梅雨が明けたものの7月後半には一時的に低温傾向(戻り梅雨)となるなど時期により気温の差が激しくなりました。
また、多雨や少雨といった地域の差が見られたり、局地的な豪雨が発生するなど地域による偏りも大きかったようです。気象庁では今夏の特徴として、東南アジア周辺の海面水温が高かったことによって明らかに「異常気象」であったとの見解を示しています。
さらには、8月には気象庁は、13年ぶりの黒潮大蛇行を発表しています。これが影響したのか、9月に入ると大気の状態が不安定となったことにより、竜巻による被害が北関東で続発したのは記憶に新しいところです。
そして、そのあとの短い秋とこの寒い冬。これから年末にかけて大寒波がきそうな気配であり、来年にかけてどのくらい雪が降るのか見当もつきません。来年はいったいどんな異常気象が起こるのでしょう。
今年始まった、綾瀬はるかさん主演の2013年NHK大河ドラマ「八重の桜」の視聴率も気になったので調べてみると、全50話の平均は14.6%と低調で、大河ドラマ第52作目でしたが、「平清盛」(2012年)の12・0%、「花の乱」(1994年)の14.1%、「竜馬がゆく」(1968年)14.5%に続く、過去4番目の低さでした。
ただし、関西地区は13.7%でしたが、ドラマの前半の舞台となった福島地区などでは23・2%と比較的高く、東北では健闘したようです。
初回21.4%でスタートし、第5話までは18%を超えていたようですが、第6話頃から一気に15%台に落ち、第10話には12.6%で初めて15%を割り込みました。その後も11%台から16%の間を行ったり来たりでしたが、裏番組で放送されたプロ野球・日本シリーズの影響もあり、第44話ではなんと10.0%と最低を記録。
とくに後半戦は、戊辰戦争も終わって、主な話題が同志社大学の創設という地味なテーマも祟って、どんどんと視聴率を下げたようです。
久々の幕末モノということで、期待もし、我々夫婦としても最後まで見守ってはいたものの、やはり後半戦は、あまり面白くなかった……かな。それにしても、綾瀬はるかさん、熱演お疲れ様でした。次回、また別の大河ドラマでの活躍を期待しましょう。
こうした話題以外にも、今年起こった事件の中には遠い過去の出来事のように忘れていたことなども多々ありました。
その後どうなったのかな、と気にはなっていたものの、メディアなどの報道がトーンダウンしていったため、結局どうなったのかが分からずじまいになっていたものも多くあります。
例えば、ボーイング787のバッテリー問題もそのひとつです。
2013年1月7日の現地時間午前10時半頃、成田国際空港からのフライトを終えボストン・ローガン国際空港で駐機中のJAL008便の機体内部の電池から発火しました。
また、2013年1月16日午前8時25分頃、山口宇部空港発東京国際空港行きANA692便も香川県上空10000メートルを飛行中に、操縦席の計器に「機体前方の電気室で煙が感知された」との不具合のメッセージが表示されるとともに異臭もしたため、運航乗務員が緊急着陸を決断、午前8時47分に高松空港に緊急着陸しました。
ANA692便は、緊急着陸後に誘導路で脱出シューターを利用し緊急脱出をしたため、5人のけが人がでましたが、日本の運輸安全委員会はこの緊急着陸を重大インシデントとして調査を行いました。
アメリカ連邦航空局 (FAA) は、ANA機の事故を受けて耐空性改善命令を発行してアメリカ国籍の同型機に対し運航の一時停止を命じ、世界各国の航空当局に対し同様の措置をとるように求めました。このため、世界各国で運航中の787すべてが一時運航停止となりました。
先のJAL008便の事案では乗客172人、乗員11人の計183人は既に全員降機しており、人的被害はありませんでした。
しかし、事故発生場所は787を製造販売するボーイング社のおひざ元のアメリカ国内、FAAの管轄空港内であり、このため国家運輸安全委員会 (NTSB) までもが乗りだし、事故調査にあたっています。当事者のボーイング社もまた、FAAと共同で包括調査するなど、原因究明に躍起になりました。
これら一連の事故により、787の機体を数多く保有するANAとJALは、所有するすべてのボーイング787の飛行を自主的に一時停止しました。FAAは、ANAの事故を受け、1月16日に耐空性改善命令 (Airworthiness Directives:AD) を発行。
この処置を受け、日本の国土交通省もボーイング787の運航停止を命じる耐空性改善通報を出すと発表し、この処置に世界各国の航空当局も追随したことから、この当時世界各国で運航中であった8社50機の機体すべてが再開見通しのたたない無期延期の運航停止となりました。
ボーイング社もこの措置を受け、各社に予定していた787型機の納入すべてを一時停止することを決定しました。なおFAAが大型旅客機の運航停止を指示したのは1979年に発生したアメリカン航空191便墜落事故によるDC-10以来のことです。

787運行停止の措置は、同機材で運航していた路線だけでなく、これ以外の路線にも影響を与えました。787を使用していた路線を他種の機材で補充しながら運航するために他路線でも欠航、時刻・機材の変更が多発したためです。
また、787を新規就航させる予定だった路線の開設の延期も発生し、経営計画の大幅な変更や修正を強いられたため、数社の航空会社がボーイングに対して補償の権利行使を実行しました。しかし、補償額は莫大に及ぶため、ボーイング社との折り合いはまだついていないようです。
その後、NTSBが詳細な調査をおこなった結果、ボストンJAL機出火の事故原因としては、8個の電池セルの中の6番目がショートして「熱暴走」を起こし、他の電池セルに波及したとする経過報告が2月に発表されました。
ところがなんとこのバッテリーは日本の電池メーカーである、ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)が製造し、フランスのタレス・グループを通じて供給されたリチウムイオン電池で、最先端技術によるものでした。
このため、この発表以後、多くのメディアでGSユアサが事故の原因であったかのような報道がなされましたが、実際は周辺制御装置の異常など、複合的な問題も考えられ、ショートの原因は必ずしもバッテリーとは言い切れませんでした。
そもそも、問題となっているリチウムイオン二次電池は、一般家庭で使用される乾電池などとは違い、それ単体では使用ができず、使用するには電圧等を制御する制御システムが必須なためです。こうした制御システムは、GSユアサではなく、別会社が供給していました。
また、ボーイングは運行再開前にGSユアサ製バッテリーの使用を継続する事を発表しており、こうしたことからもGSユアサのバッテリー自体に問題があった可能性は低いと考えられ、日本を代表するメーカーの事故への関与という汚名は返上されました。
その後ボーイング社は、熱対策を行った新バッテリーユニットの再開発にとりくみ、FAA に申請した結果、3月中旬には、FAAはこの新バッテリーユニットの認証計画と新バッテリーに改修されたボーイング787の試験飛行を承認しました。
しかし、NTSBが主張している「熱暴走」については依然不安を残したままで、787の提供者であるボーイング社のチーフ・プロジェクト・エンジニアであり、副社長でもあるマイク・シネット氏すらも、「熱暴走の定義は人により異なるが、われわれは熱や圧力、炎が機体を危険にさらす状態にあると考えている」と熱暴走の実在を否定していません。
ところが一方では、「ボストン・ローガン空港も高松空港もそのレベルではなく、バッテリーに過充電も見られなかった」とも述べ、今回の事故が「熱暴走」を起因とするものであることを暗に否定しています。
ボーイング側の説明は更に二転三転します。同じ席で顧客の航空会社向けには、機体への重大な影響があるものを「熱暴走」と説明していたのです。このように、ボーイングの開発担当者もまたこの「熱暴走」なるものの見解を巡って、それがどういう原因で生じるかを把握しきっていないのは明らかであり、この現象に相当振り回されている様子がうかがえます。
しかし結局ボーイング社は、懸案となっているバッテリーの1つのセルから2つのセルへ波及するとされる、一般的には「熱暴走」という現象の科学的な意味は「認識している」ものの、一般顧客向けへの説明としては、これは「熱暴走とは異なる」と釈明し、最終的には「熱暴走なし」の独自見解は変えませんでした。
しかし、無論こうしたあいまいな見解を誰しもが鵜呑みにするわけはなく、その後も本当の原因究明をめぐっての追及の声はしばらくの間やむことはなかったようです。
そんな中、ボーイング社はバッテリー発火対策として、三段階での対策を提示しました。すなわち、バッテリーのセル単位での発生防止、不具合が生じた際の拡散防止、機体への影響防止、の3つです。
とくに最初のセル単位での発生防止においては、ショートにつながる結露など、原因として考えられる 約80項目を4グループに分け、セルとバッテリーは設計や製造工程や製造時テストを見直し、セルは絶縁テープで囲み使用される絶縁体も耐熱性や絶縁性を改良し、隣り合うセルでショートが起きないよう、徹底した対策を施しました。
また、充電器も電圧を見直し、充電時の上限を低く設定してバッテリーへの負荷を減らし、下限を高めて過放電を防止するとともに、新たにバッテリーを収めるエンクロージャー(ケース)と排気システムを採用。出火要因を排除し、仮に出火した場合でも燃焼が続かない環境を維持できる構造にしました。
さらには、バッテリーから電解液が漏れたり熱や圧力が発生した場合はエンクロージャー内にとどめ、煙や異臭は機外に放出するそれぞれの対策も施しました。
ボーイング社によれば、新型バッテリーではこれまでに予想されたもののおよそ三倍の圧力に耐えられるようになったといい、この性能を確認するため、エンクロージャー自体の耐圧試験を6万時間以上をも行ったといいます。

こうした対策強化を受け、FAAはボーイング社が提示していた改修した新バッテリーシステムの認証計画と試験飛行を3月25日に承認。これを受けて、同日と4月5日にも、新バッテリーシステムに改修した新しい機体で試験飛行を行い、新バッテリーシステムのデータを収集し、設計通りに機能するかを検証しました。
FAAはこれら検証を受けてボーイング社が提案した運航再開に向けたシステムの改修を承認。同年4月26日に新バッテリーユニットへの改修を行った「新ボーイング787」の運航再開を許可するAD(耐空性改善命令)の更新発行を行いました。
ボーイングとしては、FAAからAD(耐空性改善命令)が発行されたことを受け、バッテリー改修のための技術者のチームを全世界に派遣し、バッテリー改修を787のすべてに施しました。また、各運航航空会社に問題箇所の指摘とその解決作業手順や整備などの変更を指示する改修指示書も発行しました。
787はヨーロッパの航空各社に納入予定であるため、このアメリカでの決定を受け、欧州航空安全機関(EASA)もまた4月23日に運航再開に向けたシステムの改修を承認しました。
とはいえ、国家運輸安全委員会、NTSBはこの決定に先立つ4月23・24日の二日間、同型機のリチウムイオン電池に関する公聴会を開催するなどしており、この運航再開承認後も同組織としてはバッテリー火災の原因究明の姿勢を崩していません。
この辺が、アメリカの偉いところだと思います。日本では運輸省にあたるFAAが承認したからといって追及の手を緩めず、学識経験者で組織されて強い権限を持つNTSBなどが引き続き目を光らせ、交通のような重要インフラの安全に関しては万全を期す、という考え方が徹底しており、日本もこうした点などをまだまだ見習うべきでしょう。
もっとも日本も最近はこうした委員会の発言力がかなり強くなってきてはいますが、福島第一原発の事故究明にあたっての事故調査・検証委員会や原子力規制委員会の対応については、他の学識経験者から厳しい意見があいつぐなど、原子力の安全を監視する番人としての立場は盤石ではないことを示しています。
一方の日本の国土交通省航空局の対応ですが、このNTSBの公聴会でも一応、新しいバッテリーシステムについては大きな異論が出なかったことを受け、この翌日には、正式に国土交通省として耐空性改善通報(Technical Circular Directive:TCD)を発行し、これによって「新バッテリーユニット」は正式に受け入れられ、787の運航再開は承認されました。
しかし、日本独自の対策として、新たに以下を運行各社に要請しました。
・各機体改修後の確認飛行(全機を対象に各一回実施)
・バッテリーに対する安全性の確認(飛行中のバッテリー電圧監視を全機対象に飛行開始後継続的に実施、使用したバッテリーのサンプリング検査を継続的に実施)
・運航乗務員の慣熟飛行を全運航乗務員を対象に実施
・同型機の安全、運航に関する情報開示をあわせて実施
これは、787の製造元でない日本としては最善の措置を取りたかったということでしょう。
そもそもこの事故が日本製のバッテリーから発生したものの、バッテリーにまつわる運営システムの改良はアメリカ側に委ねざるを得ず、手も足も出ないので、せめてこうした運行手順だけはしっかり守らせて、日本からは新たな責任問題を出させないよう国内の航空会社にくぎを刺したわけです。
しかし、こうした新たな運用規則が増えた国内航空各社はたまったものではありません。「運航乗務員の慣熟飛行」ってどうやって証明するんでしょうか。
ともかくもこうした国土交通所の指示を厳守することを条件に、早くも4月22日には再開待ちに待っていたANAが国内4(羽田、成田、岡山、松山)空港で、新バッテリーユニットへの改修を開始し、JALもまた羽田、成田2空港で改修を始めました。
しかし、一機当たりの改修には一週間前後もかかったため、日本国内の787の全改修が終了したのは、5月23日でした。また、日本以外の各国にあった50機の787の改修もまた、5月29日までには完了しました。
787の日本での最大の利用者であるANAには、同機種のパイロットが200名近く在籍していますが、1月に運航停止になって以降、その多くは自宅待機を余儀なくされ、定期的にシミュレーターで訓練を行うだけとなっていました。
この間、長いお休みによって実機による運航ができなかったことによる操縦技能の低下が懸念され、また休止期間が長引いたことで機長資格を失効するパイロットも複数出ることとなり、会社としては正式な商業運航再開までに別の機体を使って訓練飛行などを複数回行いました。無論乗客はいませんから、この飛行による費用はドブ捨てになります。
しかし、改修が終わったことから、まずは旅客定期便運航再開よりも前に貨物定期便を再開しようということになり、4月28日には、羽田発着で約2時間の貨物機の試験飛行が実施されました。
さらには5月16日には高松空港に緊急着陸したJA804Aが運輸安全委員会の調査なども経てバッテリー改修を行い、121日ぶりに羽田へ回航と確認飛行も実現。
同年5月23日に同社は商業運航再開を前倒しして、同年5月26日の臨時便より商業運航を再開しました。これをもって1月16日に耐空性改善命令が出て以降運休していた全787の飛行が再開されました。この間、実に4か月余りであり、ANAだけでも減便や路線の運休による減収はおよそ80億円にも達しました。
JALもまた、5月2日に羽田と成田の2空港で試験飛行を行ったのち、ボストン・ローガン国際空港で出火した機体は、バッテリーユニットを交換、確認飛行を実施した後5月19日に成田空港に回航され、約130日ぶりに日本へ帰着しました。6月1日からは羽田発シンガポール行きの035便を皮切りに順次商業運航を再開するとともに、現在もJALにおいては同型機は国際線専用で運航されています。
ただ、JALでは成田~デリー線の再開が7月12日となり、また成田~モスクワ線に関しても9月1日になるなど、完全に停止前の運航規模に復帰するまでは時間がかかりました。また、787の導入を機会に新設を延期していた成田~ヘルシンキ線の開設も7月1日からとなりました。
ボーイングは、ANAに納入する予定だった他の787の納入も、運航再開後に初めており、それまで遅れていた納入遅れを挽回しようと現在躍起になっていますが、いまのところ、予定されていた機体は納期が大幅に遅れたものの納入されるようです。

こうして、ようやく787の問題は解消されたかのように見えますが、新しい機体であるだけにまた別のトラブルが発生しないか心配です。誰しもがそうでしょう。
実際、上述のバッテリー問題解決後も、787のトラブルは続いているようです。
例えば今年の7月12日、エチオピア航空の機体でロンドン・ヒースロー国際空港に到着し全電源を落とした数時間後に火災が発生しました。
英国航空事故調査局(AAIB)(en)は、航空機用救命無線機(ELT)が出火原因となった可能性が高いとの報告書を公表し、FAAなど各国航空当局に対して耐空性が確認されるまでは問題のELTの電源を切る通達を出すよう勧告しています。
これを受けFAA、JCAB、EASAそれぞれの当局は当該ELTについて、点検又は取り下ろしのいずれかの措置を求める通告を発表しています。
また、記憶に新しいところでは、先月11月の23日、日本航空は国際線の一部路線において使用機材をボーイング787から別機種へ変更することを発表しました。これは、787と同じGEnx-2Bエンジンを搭載している他社のボーイング747-8型機が積乱雲が発生している空域を飛行した際に、一時的にエンジン推力が減少する事案が発生したためです。
実は、私事ですが、来年の1月に広島で姪の結婚式があり、これに我々夫婦も招待されていて、この際、飛行機で行こうと思っており、ANAを利用することになりそうです。
なので、その機材が787であるかどうかは一応チェックしておこうと思っているのですが、時間を押した旅行なので、予定によっては787を利用せざるを得ないかもしれません。
とはいえ、日本のメーカーも参画して開発したというこの最先端機に乗ってみたい気持ちもあり、そこのところは少々複雑です。
787については、以前もこのブログでそのスペックを紹介したことがあったのですが(1/22 「787」参照)、ここで、この世界最先端技術を使って開発されたといいう787についてもういちどおさらいしておきましょう。
ボーイング787は、別名ドリームライナー(Boeing 787 Dreamliner)といいます。アメリカ合衆国のボーイング社が開発・製造する次世代中型ジェット旅客機で、これまでの中堅機、ボーイング757・767・777などの後継となる飛行機です。
中型機としては航続距離が長く、今までは大型機でないと飛行できなかった距離もボーイング787シリーズを使うことにより直行が可能になり、これにより、需要があまり多くなく大型機では採算ベースに乗りにくい長距離航空路線の開設も可能となりました。
1995年に就航開始した777に次ぐ機種の開発を検討していたボーイングは、将来必要な旅客機は音速に近い速度(遷音速)で巡航できる高速機であると考え、2001年初めに250席前後の「ソニック・クルーザー」と呼ばれる俊足機を世に提案しました。
しかし、2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件後の航空業界の冷え込みの影響などから少しでも運航経費を抑えたいという航空会社各社の関心を得ることができず、2002年末にこのソニック・クルーザー開発を諦めて通常型の「7E7」の開発に着手しました。
この通常型7E7は、速度よりも効率を重視したボーイング767クラスの双発中型旅客機であり、2003年末には航空会社への販売が社内承認されました。
2004年4月、全日本空輸が50機発注したことによって開発がスタートし、呼称も787に改められました。その後、日本航空も発注したほか、ノースウエスト航空(現・デルタ航空)、コンチネンタル航空(現・ユナイテッド航空)など多数の大手航空会社が発注しています。
その最大の特徴は、特にターゲットとなる767より、航続距離や巡航速度は大幅に上回るとともに、燃費も向上している点です。炭素繊維を使用した炭素繊維強化プラスチック(カーボン)等の複合材料の使用比率が約50%であり、残り半分が複合材料に適さないエンジン等なので、実質機体は完全に複合材料化されたといえます。
この軽量化により、巡航速度はマッハ0.85となり、マッハ0.80の767、マッハ0.83程度のA330、A340より長距離路線での所要時間が短縮されることになりました。
航続距離は基本型の787-8(後述)での航続距離は最大で8,500海里(15,700km)、ロサンゼルスからロンドン、あるいはニューヨークから東京路線をカバーするのに十分であり、東京からヨハネスブルグへノンストップで飛ぶことも可能です。
従来機の767と比較すると燃費は20%向上しており、これは炭素繊維素材による空力改善と複合材の多用による軽量化・エンジンの燃費の改善、およびこれらの相乗効果によるものです。軽量化によって機内空間を増やすこともできるようになり、このため最大旅客数も若干増加させることができました。
実は、この787の製造ラインの3分の1以上を日本企業が担っています。日本企業の担当比率は合計で35%とアメリカ以外で最大かつ過去最大の割合であり(767は15%、777は20%を担当)、この35%という数字はボーイング社自身の担当割合と同じです。
ボーイング社外で製造された大型機体部品やエンジン等を最終組立工場に搬送するため、貨物型のボーイング747を改造した専用の輸送機が用いられており、日本では生産工場が名古屋近郊にある関係で中部国際空港に定期的に飛来しています。
日本企業の筆頭は、三菱重工業であり、同社は747計画時の2000年5月にボーイングとの包括提携を実現しており、機体製造における優位性を持っていました。
すでに1994年には787の重要部分の開発の日本担当が決定しており、三菱は海外企業として初めて主翼を担当しました。三菱が開発した炭素繊維複合材料は、この当時から開発が始まったF-2戦闘機のボーイング社との共同開発に際して初めて使用されたものです。
この時、アメリカ側も炭素系複合材の研究を行っていたものの、このF-2の協同開発から、ボーイング社が三菱側が開発した複合材の方が優秀であると評価したため、三菱が主翼の製造の権利を勝ち取ることになったものです。
三菱が主翼、川崎が前方胴体・主翼固定後縁・主脚格納庫、富士が中央翼・主脚格納庫の組立てと中央翼との結合を担当しており、エンジン開発でも、川崎重工とIHI、三菱(名誘)が参加しています。
機体重量比の半分以上に日本が得意分野とする炭素繊維複合材料が、1機あたり炭素繊維複合材料で35t以上、炭素繊維で23t以上をも採用されています。
こうした炭素繊維複合材料の製造は現在に日本の独断場であり、世界最大の炭素繊維メーカーである東レもまた、実質的にこの開発に加わることとなり、ボーイングと一次構造材料向けに2006年から2021年迄の16年間の長期供給契約に調印し、使用される炭素繊維材料の全量を供給していく予定です。
この787には、4種の派生機があります。
このうち、「787-3」は、航続距離約6500km、交通量が多い路線を的にした296座席(二列制)の短距離型であり、「787-8」は、座席数223座席(三列制)であり航続距離15700kmと787-3のほぼ倍です。787型機の基本型であり、最初に開発されたモデルでもあります。
このほか、胴体を延長させ、座席数259座席(三列制)の「787-9」というのがあり、「787-10」は、これをさらに胴体延長して、座席数290席に増やしたものです。これはエアバス社のA350-900に対抗するために計画されたモデルです
これら各派生機の受注状況は以下のようで、これからもわかるようにその主力は787-8と787-9となっています(2013年11月時点)。
787-3型機 : 0機
787-8型機 : 496機
787-9型機 : 396機
787-10型機 : 120機
787型機 全機種合計 1012機
各派生機とも、客室は従来より天井が20cm高くなっています。面積比で767の約1.2倍、777の約1.3倍にも及ぶとのことで、A350の1.65倍の大型の窓が採用され、窓側でなくとも外の景色を見ることができるといいます。
また窓にはシェードがなく、代わりにエレクトロクロミズムを使った電子カーテンを使用し、乗客各自が窓の透過光量を調節できるという斬新なものです。
さらに、客室内はLED光により、様々な電色が調整できるといい、トイレには、日本航空の主導で、TOTO株式会社、株式会社ジャムコ、ボーイング社との共同開発による、日本で一般に普及している温水洗浄便座がオプションとして採用され、ANAもこれを国際線用機に採用したそうです。
が、国内線には温泉洗浄便座は導入されていないようです。とまれ、飛行機や船が大好きな私としては、こうした数々の新しいシステムをこの目でみたくなりました。
先に述べたように、2013年の時点ではまだ、787の機体の信頼性が安定していないのも事実ですが、人はいつかはあの世にいくもの。生きているうちに、787に乗ってみるのも悪くはないな、と思い始めているところです。

ところで、ボーイングはこの787に飽き足らず、まだまだ新しい飛行機を開発しようとしているようです。
ボーイング・イエローストーン・プロジェクト(Boeing Yellowstone Project)というのがあり、これは、ボーイングが進めている、次世代旅客機の開発プロジェクトです。
現在までに、ボーイングY1・Y2・Y3と呼ばれる3機種の開発計画を発表しており、そのうちY2は787として実現しています。また、Y2(787)はそもそも757-300、767、777-200などの後継機となる200-300名程度を乗せる次世代中型旅客機を想定したものであり、エアバスではA350の開発でこれに対抗しています。
一方のボーイングY1は、ボーイング717、737NGシリーズ(737-600/700/800/900)、757-200などの後継機となる次世代小型旅客機で、100-200名程度を乗せる機体として開発中です。
ライバル会社のエアバスもまた、A320シリーズの後継機として同規模のエアバスNSRを開発中であり、このクラスではこれよりやや小ぶりですが(乗客数70~100程度)、日本のMRJも加わってさらに競争は激化しようとしています。
787の開発で得られた新しい技術、例えば、複合材料製のより軽量で丈夫な胴体や主翼、より大きなバイパス比で燃費や静粛性が向上した新世代のターボファンエンジン、進化したコックピット、より快適な客室技術、などが盛り込まれた新設計の旅客機を目指していると思われますが、MRJのライバル機としてどのような姿で登場してくるか楽しみです。
ただ、787の開発の遅延による影響や、新世代のエンジンを開発するメーカーの都合もあり、開発は未だ本格化しておらず、ボーイングは2008年に、Y1の環境負荷低減の技術が未熟であるため、当分の間は基礎技術研究に注力し、現行の737を改良したシリーズの生産を継続する方針を発表しています。
一方のボーイングY3は、ボーイング777-300、747(ジャンボ)の後継機となる次世代大型旅客機であり、300-600名以上を乗せる最大クラスの機体として開発中のものです。
別途ボーイングが開発中のボーイング747-8(3クラスで450~500名程度)と重複しますが、A380に匹敵する、より大型の機体(500~600名程度)を開発したいということのようです。
が、その全貌を表すのはまだまだかなり先のようです。その理由はいろいろあるようですが、こうした巨大な飛行機を作るのはもうやめにして、中型で航続距離が長く、燃費の良い飛行機のほうが効率的とする考え方が、世界の航空機メーカーに定尺しつつある、ということが理由としてあるようです。
いずれにせよ、これらの新たな飛行機開発においても、日本はボーイング社のようなアメリカの航空機製造メーカーの重要なパートナーとして引き続き、協力体制を築いていくことになりそうです。
MRJの開発によって日本はアメリカの水準に追いついたともいわれますが、アメリカの航空機産業のその裏には日本以上に進んでいるロケット開発を初めとする宇宙産業の技術があり、これに日本はまだまだ追いついていないためです。アメリカと共同で飛行機やロケットを開発していくことで、これらのノウハウを更に吸収する必要があります。
このイエローストーン・プロジェクトを初めとする、次世代のボーイングの飛行機開発にあたっては、既に2012年6月に、日本における航空機製造主要パートナーである三菱重工、川崎重工、富士重工、および東京大学生産技術研究所と製造技術に関する共同研究を開始しており、この研究結果は、上述の787開発にも応用されてきました。
ボーイングと日本のこれらの機関や企業は、産学連携の新たな枠組みであるコンソーシアムの設立に向けた協議を実施する覚書も締結しており、研究開発作業は東大生研の教授陣が主導し、主にその技術スタッフが実務を担当することなども決まっています。
まずはチタニウム、アルミニウム、複合材の切削加工に関する新たな技術開発に取り組み、コンソーシアム設立後は製造技術に関わるより多様な研究開発を実施することで、上記のY1、Y3の開発につなげていく予定だといいます。
しかし、日本も独自の旅客機開発を進めており、上で取り上げたMRJもそのひとつです。このMRJは、今年の10月より、愛知県豊山町の小牧南工場で飛行試験機初号機の最終組み立てが開始されており、来年早々にも日本の空を飛びそうです。
現時点で、世界中の航空会社から330機もの注文が来ており、国内でも日本国政府が政府専用機として10機程度の発注を検討しているそうです。MRJはボーイング737より小型で、滑走路が1,500m以上あれば離着陸できる見通しのため、政府などが災害時に運用できる空港の選択肢が多くなることが期待されています。
さらに、日本初の小型ジェット、ホンダジェット(Honda jet)も商用化実現が近づいています。
つい先だっての12月13日、ホンダとGEの折半出資子会社であるGE Honda エアロエンジンズは、Honda jetに搭載されるエンジン「HF120」が、米国連邦航空局による連邦航空規則のPart33が定める型式認定を取得し、量産に向けたステージに入ったと発表しています。
さらに先週の20日にはHonda JetがFAAの型式証明取得に先立ち必要になる型式検査承認(TIA)を取得したことを発表、これによりデリバリー開始予定は、来年こそは難しいものの、2015年1 ~3月期となることは確実となりました。
来年以降の数年は、日本の航空機産業にとっては劇的な進化を遂げる時期になるかもしれません。期待しましょう。