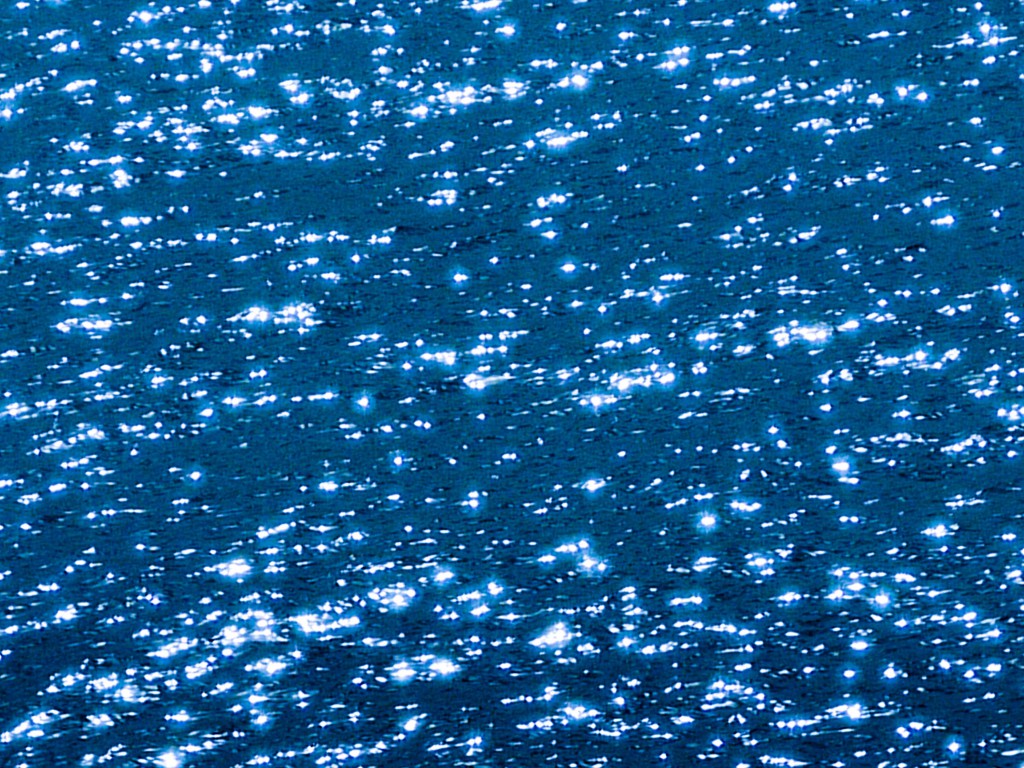今朝、東京など関東地方では雪が降っているようです。今回はこの雪は伊豆には降らないようで、ちょっと残念な気もしますが、2月もまだまだ先が長いことから、まだもう一回くらい降るのではないかと思います。期待しましょう。
今朝、東京など関東地方では雪が降っているようです。今回はこの雪は伊豆には降らないようで、ちょっと残念な気もしますが、2月もまだまだ先が長いことから、まだもう一回くらい降るのではないかと思います。期待しましょう。
ところで、雪といえば、41年前のちょうどいまごろには、雪の祭典、冬季オリンピックが札幌で行われていました。1972年2月3日から2月13日まで行われた札幌オリンピックで、日本およびアジアで初めて開催された冬季オリンピックでもありました。
この大会では、スキージャンプ70m級(現在のノーマルヒル)で、笠谷幸生が金メダル、金野昭次が銀、青地清二が銅と、日本人が冬季オリンピックでは初めて表彰台を独占しました。
札幌オリンピックでは結局これ以外に日本選手によるメダル獲得はなりませんでしたが、ジャンプ70m級の金銀銅メダル独占という快挙は、のちに日本のジャンプ陣が「日の丸飛行隊」と呼ばれるようになるきっかけにもなりました。
このスキージャンプは、北欧が発祥の地の「ノルディックスキー競技」のひとつとされています。ご存知のとおり、ジャンプ台と呼ばれる専用の急傾斜面を滑り降り、そのまま角度の付いた踏み切り台から空中に飛び出し、専用のスキー板と体を使ってバランスをとり、滑空します。
その飛距離と姿勢の美しさ、「美しく、遠くへ跳ぶ」ことを競う競技であり、このスキージャンプ競技に出場する選手は、「ジャンパー」と呼ばれ、他の競技ではなかなか味わうことのできない、観客を魅了する華麗な競技のひとつでもあります。
このノルディックスキー (Nordic ski) ですが、競技の名称かと思ったら、もともとは北欧で使っていた「スキー板」のことだそうで、これは、北欧のスカンジナビア地方で誕生・発展したスキー板であり、板とブーツの構造が、ビンディングでつま先だけが繋がれるものをさします。
現在はスキー板ではなく競技そのものを指す用語として定着していますが、滑降競技が主である、アルペンスキーと比較するとかかとが固定されない点で異なり、その競技形態は以下の3つの型に分類できます。
・クロスカントリースキー
長いストックと細長くて軽いスキー板で、雪原や整地されたなだらかなコースを滑る。冬季五輪正式種目。
・スキージャンプ
太く長いスキー板で、ジャンプ台から飛躍する。冬季五輪正式種目。
・テレマークスキー
アルペンスキーのように雪山やゲレンデを滑る。テレマークという名称は、特に技術や用具について、ノルディックの別名としても用いられる。世界選手権やワールドカップがあるが、冬季オリンピックの種目にはなっていない。
現在、「ノルディックスキー競技」、「ノルディック競技」などと呼ばれるのは、オリンピック正式競技に認められている、クロスカントリーとジャンプをまとめた競技の呼称であり、本来はノルディックスキーのひとつである、テレマークスキー競技はこの中には加えられていません。
もっとも、テレマークスキーの派生形がアルペンスキーと考えることもでき、かかとを固定するアルペンスキーとは少し形態が異なりますが、事実上、本来のノルディックスキー3競技すべてがオリンピック正式種目になっていると考えることもできます。
ジャンプ競技の歴史
このうちのジャンプ競技は、1840年ごろのノルウェーのテレマーク地方が発祥の地とされており、1840年といえば日本ではまだ江戸時代で天保年間のころのことです。
そもそもノルウェー地方の冬の間の遊びだったようですが、多くの人がスキーで遊んでいるうちに、自然発生的にその技術を競おうということになり、地元のお祭りなどで競われる競技になっていったようです。
その後、1860年代ころには、競技ルールもかなりまとまってきて、このころ行われていたジャンプ競技では、正式に「選手」と呼ばれるような人も出てきており、テレマーク地方出身のノルトハイム (Nordheim)という競技者などが有名だったそうです。
このころのジャンプ競技は、その発祥がテレマーク地方を中心に発達してきたこともあり、この競技において最も美しいとされ高得点に結びつく着地時の姿勢のことを、「テレマーク姿勢」と呼んでいました。
今日でもテレマークという呼称は、ジャンプ競技選手がジャンプを終えて滑降するときの美しい姿のことを、「美しいテレマーク姿勢です」などとアナウンサーが言っているのを聞いたことがあろうかと思います。
現在では、ジャンプ競技の着地時にこの姿勢が求められ、スキーを前後に開き、片足を前に出してひざを深く折り、腰を落としてショックを吸収しながら停止する姿勢のことをいいます。
競技が行われたとして記録に残されている最も古いジャンプ競技は、1877年(明治10年)にノルウェーで行われたジャンプ競技だそうですが、この大会の由来やどのくらいの選手が出場したとか、どのくらいの飛距離が出たとかの詳しい記録は残っていないようです。
が、その二年後の1879年(明治12年)に同じくノルウェーのテレマークで行われた競技では、この地方の靴屋で働いていた少年、「ジョルジャ・ヘンメスウッド」がクリスチャニアという場所の競技場となった丘で23m飛んだという記録が残っています。
このジャンプ競技における飛行姿勢については、最初から現在のように両手を両脇に揃えて飛ぶような形ではなく、初期のころにはほぼ「直立不動」の姿勢で飛んだようです。1920年代には、腰を曲げて前傾姿勢を取る「タムス型」と呼ばれる姿勢と、この直立不動状態で飛ぶ「ボンナ型」という2つの前傾姿勢が広まりました。
いずれの型においても、両腕は脇に揃えられておらず、バランスを取るため前後左右にグルグルと回すことが認められており、二つの型のうちとりわけタムス型のほうが、飛距離が伸びたことから、その後戦後直後まで多くのジャンパーがこの型を取り入れるようになりました。
現在のように両腕を揃えて飛ぶようになったのは、1950年代前半からのことで、その先駆けは、フィンランドの「アンティ・ヒバリーネン」という選手でした。このころから、手を動かさず体に付け、深い前傾姿勢を取るスタイルが定着し、このスタイルはその後長らく基本的なフォームとして1990年頃まで主流となりました。
その一方で1960年頃には、両手を前に出して万歳のような姿勢で飛ぶジャンパーもいたようで、アメリカのカリフォルニア種のスコーバレーで行われたスコーバレー冬季オリンピックでは、ドイツのヘルムート・レクナゲルがこの姿勢で優勝しています。しかしその後の五輪ではこの姿勢で勝つ選手はなかなか現れず、結局このスタイルは自然消滅しました。
その後、20世紀後半までは、気をつけの姿勢でスキーを揃え、横から見ると、胸から上とスキーが平行になるのが理想とされ、前述の札幌冬季オリンピックでの笠谷幸生以下の三選手がメダルを独占した際の姿勢もこの飛型でした。
また、1970年代までは、滑降は始める際のアプローチのときには、両腕を前に下げる「フォアハンド」のスタイルが主流であり、この姿勢が一番空気抵抗が少なく、速度が出ると思われていましたが、現在では最初のアプローチから中腰で両手を並行に後ろへ揃えるスタイルが主流になっています。
このアプローチスタイルは、「アッシェンバッハスタイル」と言われ1976年頃、東ドイツのアッシェンバッハ選手が、アプローチを滑走する際にこの姿勢をとり、好成績を残したことからほかの選手も真似をするようになりました。現在では「バックハンドスタイル」といわれるようになり、ジャンプ競技におけるスタンダード姿勢となっています。
ジャンプ姿勢はその後、20世紀終盤には、スウェーデンの「ヤン・ボークレブ」選手が始めた「V字飛行」が主流になりました。
このV字飛行は、それまでの板を揃えて飛ぶ飛型よりも前面に風を多く捉えて飛距離を稼ぐことができましたが、このころのジャンプ競技の採点基準では、姿勢の乱れとみなされ大幅な減点対象になっていました。
しかし、上位に入るには他を大きく引き離す飛距離が必要であったため他の選手も次第にこの姿勢を取り入れるようになり、その後競技規定のほうが変更され、V字飛行で飛んでも減点対象から除かれるようになりました。
このクラシックスタイルからV字飛行への転向には、日本やオーストリアが素早く対応しました。
V字時代最初のオリンピックとなったアルベールビルオリンピックでは、唯一V字をマスターしたトニ・ニエミネンを擁するフィンランドがオーストリアを下して優勝しました。その一方ではフィンランドなどの強豪国は転向に乗り遅れ、その後しばらく成績が低迷することになりました。
日本は、この大会で金1・銀2・銅4の合計7個のメダルをとり、冬季オリンピックでは当時史上最多数のメダルを獲得しましたが、このうちの金メダルは、ノルディック複合団体の三ヶ田礼一、河野孝典、荻原健司の三選手の活躍で得たものです。
前半のジャンプをV字飛行で飛んだ日の丸飛行隊は、2位以下に大差をつけ、翌日の後半・クロスカントリーでも危なげなく逃げ切って金メダルを獲得したのです。この金メダルの獲得は、1972年札幌冬季オリンピックの笠谷幸生以来のものであり、冬季五輪での日本2個目の金メダルとなりました。
現在のジャンプ競技
現在のジャンプ競技は、ジャンプ台の大きさや形状、助走距離の長さ、K点までの距離などによって、ノーマルヒル、ラージヒル、フライングヒルの三種目に分かれています。
ノーマルヒルは、一般にK点90mであり、かつては「70m級」と呼ばれていたもので、ラージヒルのK点はこれより長く120m。こちらはその昔「90m級」と呼ばれていました。もっとも飛距離の長いフライングヒルは、K点が180mを超えるもので、この飛距離を飛ぶジャンプ台は現在日本には存在しません。
ところでこのK点(ケイてん)って何だ?と疑問に思われる人も多いでしょう。このK点とは、そもそもはドイツ語で建築基準点を意味するKonstruktionspunkt(英: construction point)のことであり、スキーのジャンプ競技におけるジャンプ台の建築基準点を意味します。
テレビなどでジャンプ競技を見ていると、上述のノーマルヒル、ラージヒル、フライングヒルなどの各ジャンプ台の着地斜面の下部には、赤い線が引かれているのをご覧になった方も多いでしょう。
この赤線の位置がK点であり、ジャンプ台はだいたいこの位置を境にして着地滑走路の「傾斜曲率」が大きく変わります。そして、選手がジャンプ台から飛び降りるとき、この着地地点よりも先に飛び降りると、そこでは急に傾斜角度が変わって上向きになるため、着地時に危険が伴うことになります。
このため、本来は建築基準点を示すイニシャルであった「K」を、飛ぶと危険であるというドイツ語で「極限点」を意味するkritischer Punkt(英: critical point)の意味に置き換えて使うようになり、1972年に日本で開催された札幌オリンピックのころからこの極限点をK点と呼ぶようになりました。
ジャンプ競技は、その日の風の具合やジャンプ台の雪の状況によって、選手の飛ぶ飛距離がかなり異なってきます。競技が始められる中でもこうした条件は変わってくる可能性があり、かなりの飛距離を伸ばす選手が出てきた場合、ある「最大着地地点」を超えると選手の安全が脅かされる可能性があります。
そして当初は、大会運営者は競技者ができるだけこの「最大着地地点」つまり、K点を超えないよう、競技の前にテストジャンパーに試験的にジャンプを行わせ、スタート地点の高さや助走路の長さを調節して「K点」を決め、できるだけこれを超えないように競技してもらうのが一般的でした。
しかしその後、滑空中の姿勢を含む滑空技術・着地技術・競技服等が大幅に進歩したことなどから、ジャンプ場の完成時に固定されていたK点1を越えてもあまり危険がないことがわかるようになり、K点の設定にもそれほど気を使わなくてもよくなりました。
このため、いわゆる「K点越え」のジャンプが可能になり、当初のように建築基準点の指標の意味であった「極限点」としての「K点」は事実上意味をなさなくなりました。
このK点を超えるか超えないかが採点基準にも取り入れられるようになり、この採点法ではK点を飛距離の基準とし、K点に着地した飛躍に対してはより高得点が与えられます。逆に着地地点がK点に達しなかった場合は減点され、超えた場合は加算されます。
減加算される点数は、ジャンプ台の規模により異なり、例えばノーマルヒルでは2.0点/m、であり、ラージヒルでは1.8点/mです。
かつて「K点」ということばがなかったころ、各ジャンプ台の許容できる飛行距離を表すことばとしては、「ヒルサイズ」が使われていました。これは選手がこの距離を超える飛行をすると危険であるという飛距離であり、初期のころのK点と同じ意味でした。
天候条件などが変わりこの「ヒルサイズ」越えをする選手が増えてくると、競技の続行について審議される「指標」として使われていましたが、現在ではこのヒルサイズは、およそ選手が到達できない飛距離をさすようになり、現在ではジャンプ台の大きさは「ヒルサイズ=○○m、K点=○○m」というかたちで示されています。
長野オリンピックでジャンプ競技がおこなわれた白馬ジャンプ競技場のK点は、前述のとおり、ノーマルヒルで90メートル、ラージヒルで120メートルでした。
なお、それぞれのジャンプ競技場では「バッケンレコード(最長不倒記録)」といった形で、最高記録が認定されており、大会において選手たちがこうした記録を塗り替えるか否かもまた、このジャンプ競技の楽しみでもあります。
さて、ジャンプ競技には、ノーマルヒル、ラージヒル、フライングヒルの三種目があると書きましたが、冬季オリンピックにおける正式種目はこのうちのノーマルヒル、ラージヒルの二つだけです。
一方、スキージャンプのワールドカップでは、ノーマルヒル競技は行われておらず、より飛距離が長いためにダイナミックな競技を観戦客が楽しませることのできるラージヒルとフライングヒルだけが行われることが多く、オリンピック同様、個人戦だけではなく国対抗で団体戦も行われています。
ジャンプ競技の技術
こうしたこのジャンプ競技の醍醐味ですが、やはりなんといっても屋外競技のため、競技結果が天候や風の向きや強さなどの自然的条件に左右される、その不確実性というか意外性でしょうか。
実力十分で優勝間違いなし、と思われた選手でも天候の悪化によって待ち時間が長くなり、その間に体調や精神面での不調をきたしたりして、思ったより成果があげられないといったこともままあります。
気温に起因した、助走面の雪質にも左右され、こうした競技環境の変化は、外見上は派手でダイナミックな競技である反面、選手たちの精神状態をも大きく左右するかなりデリケートな競技です。
助走路上では、クラウチング (crouching)と呼ばれるしゃがみ込むような助走姿勢をとって風の抵抗を低減し、スピードを得ますが、このときの重心の位置、助走面の状況、スキーワックスの種類などはその後のジャンプの際のスピードに影響を与えます。
踏み切り地点(カンテという)上においては、立ち上がる反動力で飛び出す「テイクオフ」姿勢が重要となりますが、助走で得た速度に加え、踏み切りの方向、タイミング、飛び出し後の空中での風向風速などが飛距離に大きく影響します。
空中姿勢は、前述のとおり、スキー後方の内側の角が接触させ、スキーの前方が大きく開いたV字型をとり、スキーと身体との間に空気を包み込むようなスタイルが理想とされています。
着地後は、前述のテレマーク (Telemark) 姿勢が理想とされ、両手を水平に開き、しゃがんだ状態で、膝から下を前後に開いて、後ろの足はつま先立ちます。
着地後、転倒ラインを越えるまでの間に手をついたり、転んだりすると飛型点が減点されますが、いうまでもなく着地するまでの落下・滑空距離のほうが大事であり、このほか、空中での滑空時姿勢(飛型)や着地時の姿勢の美しさ(着地姿勢)をポイント化して競技が競われます。
飛行は通常は2回行い、合計点で競うことになっていますが、天候の悪化などにより、1本目のみで競技終了となる場合もあります。
ワールドカップでは、1本目を終えた時点で、飛型点・飛距離点を合計し、上位30人に絞り、残った者から得点の低い順に2本目を跳ぶため、1本目に最高得点した者が、最終ジャンパーとする方式を採用していますが、現在多くの大会でこの方式が用いられているということです。
他の競技でもそうですが、スキージャンプでは、それに使う用具がスキー板一枚とシンプルなのがまた魅力のひとつです。しかし、シンプルなだけに飛距離をいかにして稼ぐかについては、このスキー板の性能にも寄るところが大きいのも確かです。
ジャンプ競技では、ジャンプしたあとの飛行では揚力を得て落下を遅らせることが必要であり、このため幅が広く、長いスキーを使用しますが、一方では板が大きく長いにもかかわらず、非常に軽量に造ってあります。
またスキー板の裏面には7~9本以上の溝があり、直進方向に適し、スピードを得られる工夫がなされ、かかと部分は「ヒンジ」になっていて、靴がスキー板の角度の変化に追従できるようになっています。
毎年各メーカーは、規定の範囲で細かな工夫を重ねていますが、過去にはスキーの先端が通常の三角形でなく、四角くトップの角度を低くした、カモノハシの口のような板や、先端に穴をいくつも空けて空気抵抗を低くしようとした板などのユニークな板もあったそうです。
スキーの長さについては、度々規則が改定され、現在は、身長とBMI(体重と身長から算出される肥満指数)を元に長さを算出する形式が用いられており、現在では幅95mmから105mm、長さは身長の145パーセント以内に規制されているそうです。
なお、コスチュームも滑空時に揚力を得る滑降の材料であるため、かつては多くの選手が特殊素材のだぶだぶの全身スーツを着ていましたが、現在ではより身体に密着したスーツを用いることがルールで規定されているということです。
日本勢の活躍
2008年現在、日本には、ノーマルヒルとラージヒルの双方の正式競技場を有する場所は、冬季オリンピック会場だった、長野県白馬村(白馬ジャンプ競技場)と、北海道札幌市の「宮の森ジャンプ競技場(ノーマルヒル)」と「大倉山ジャンプ競技場(ラージヒル)」だけです。
札幌オリンピックにおいては、この宮の森ジャンプ競技場においての70m級ジャンプ競技(現ノーマルヒル)において、笠谷以下の三選手が金銀銅のメダルを独占しましたが、大倉山での90m級ジャンプ(現ラージヒル)では、笠谷幸生は、いずれも1回目に2位の好位置につけながら2回目に距離を伸ばすことができずメダル獲得を逃しました。
その後も、1992年アルベールビルオリンピックでは原田雅彦が4位、1994年リレハンメルオリンピックでは岡部孝信がまたしても4位とあと一歩メダルに届かず、過去日本人選手は、オリンピック、世界選手権において多くのメダルを獲得していますが、ラージヒルだけでは長い間金メダルを獲得できず、日本選手の鬼門とされていました。
しかし、1997年トロンヘイムの世界選手権で原田雅彦が金メダルを獲得し、その翌年の1998年長野オリンピックでは船木和喜が、ラージヒルで金メダルを獲得しており、ようやく長い間金メダリストのいなかった時代の雪辱を果たしました。
しかし、まだオリンピックにおける女性選手のメダル獲得はありません。それもそのはず、女子によるジャンプ競技は先の2010年バンクーバーオリンピックまで正式競技種目として認められていなかったためです。
ところが近年、オーストリア、ドイツ、ノルウェー、日本などで、ノーマルヒルを中心とした女子選手の増加に伴い、ヨーロッパなどで女子の国際大会が頻繁に開催されるようになりました。男子の競技のように飛距離は出ないものの、女性ならではの「しなやか」なジャンプにも人気が集まり、競技人口も増えたことから、女子スキージャンプはオリンピックでの採用の可能性が十分ありといわれるようになりました。
しかし、2006年11月の国際オリンピック委員会の理事会では、2010年バンクーバーオリンピックの競技種目としては見送ることが決定され、このことは関係者の批判を呼び、アメリカが中心となって見送り決定の撤回を求める運動が起きました。
この結果、2011年4月6日、国際オリンピック委員会は、2014年ソチ冬季五輪で女子スキージャンプを含む6種目の新たな採用を決定しましたが、IOCはその採用の理由として「以前より競技レベルが上がり国際的普及度も上がった」と述べています。
そのソチオリンピックも来年に迫り、日本でもジャンプ女子競技の採用が大きく報道され、
メダル有望種目として期待を高めています。
ただ、日本のジャンプ女子はまだ競技が始まって間もなく、本格的に大会が行なわれるようになったのは1990年代終盤に入ってからのことで、スキージャンプ・ワールドカップより1つ下の格付けであるコンチネンタルカップの女子ジャンプで、2005-06年シーズンに田中温子が総合8位に入ったのが最高でした。
ところが、2011年にこの女子コンチネンタルカップのオーストリア・ラムソーでの大会に出場した「高梨沙羅」選手は、この大会史上最年少で優勝し、大きな注目を浴びました。
この大会が開かれたのは、世界選手権の直前であり、ランキング上位の数人は出場していなかったといことですが、ジャンプ競技の世界大会で日本女子が優勝するというのはすごいことです。
高梨選手はその後も、2012年には、ドイツ、ヒンターツァルテンで行われたFISワールドカップ女子の第3戦で2位となり、初の表彰台に立ったほか、インスブルックユースオリンピック個人戦でも優勝。
国内でもNHK杯、全日本選手権(ノーマルヒル、ラージヒル)を連覇し、今季のワールドカップ女子ジャンプでもその第1戦、4戦、5戦、8戦で優勝しています。
高梨沙羅はまだなんと16歳の高校生であり、コンチネンタルカップで初優勝したときはまだ14歳の中学生だったといいますから唖然としてしまいます。
ほかにも2011年の世界ジュニア選手権で3位に入り、日本女子勢で初めて同大会の表彰台にも立った伊藤有希選手などもおり、伊藤選手もまだ18歳という年齢を考えると、高梨選手同様、来年のソチオリンピックまでにはまだまだ伸びしろがありそうです。
日本がこれまでに冬季五輪で獲得した金メダルはわずかに9個(うち5個は長野五輪)であり、女子選手の冬季五輪金メダリストとなると里谷多英と荒川静香の2人しかいません。
それだけに女子ジャンプにかかる期待は大きいようですが、かつての日の丸飛行隊を養成した男子ジャンプ陣がその後ろ盾になり、今後も競技の普及と選手の強化につなげていくことでしょう。もともとスキージャンプへの関心度が高い日本だけに、女子選手の強化で他国に立ち遅れるという心配も少ないはずです。
来年のソチ五輪に向け、日本の女子ジャンプ陣がどのような軌跡を描いていくのか注目したいところです。