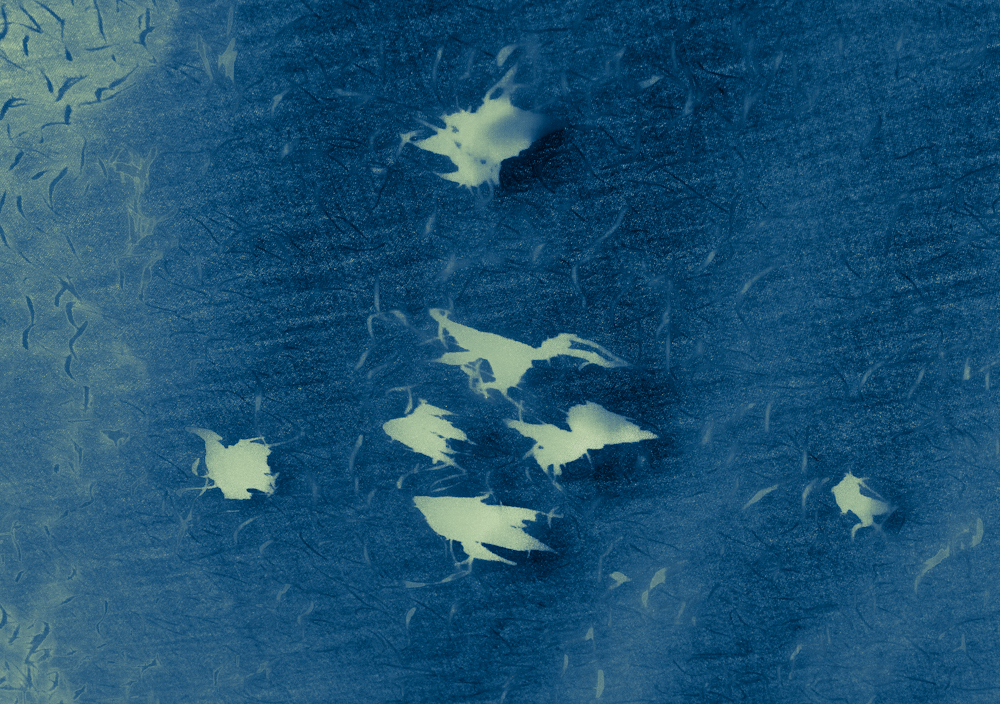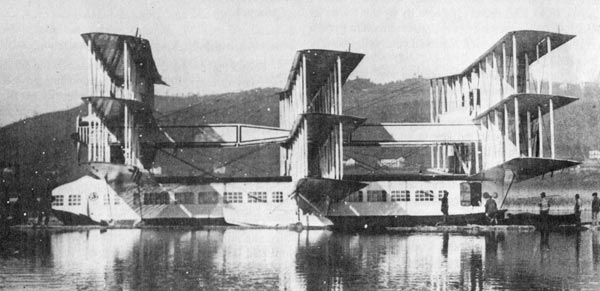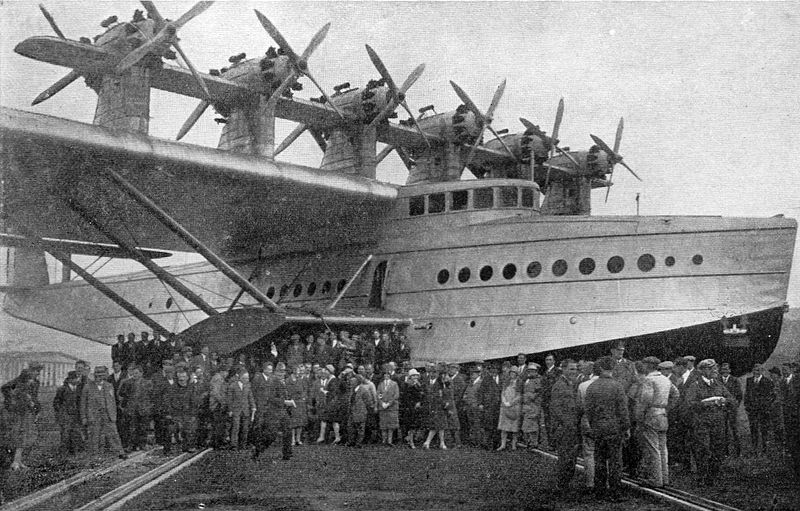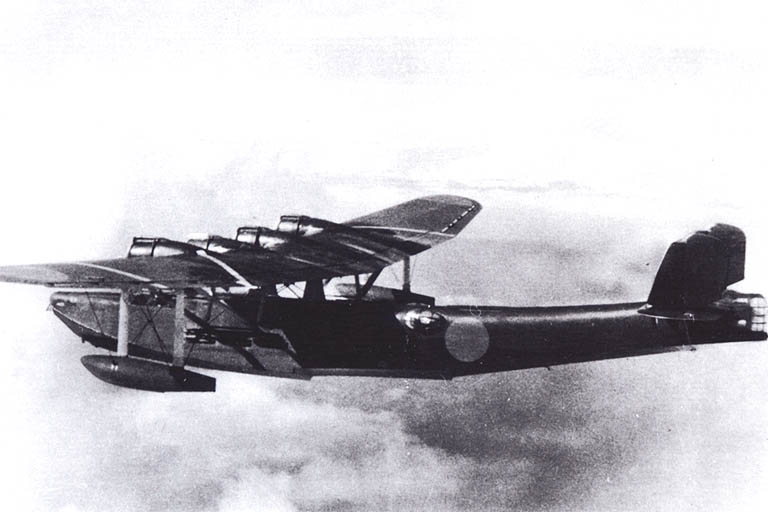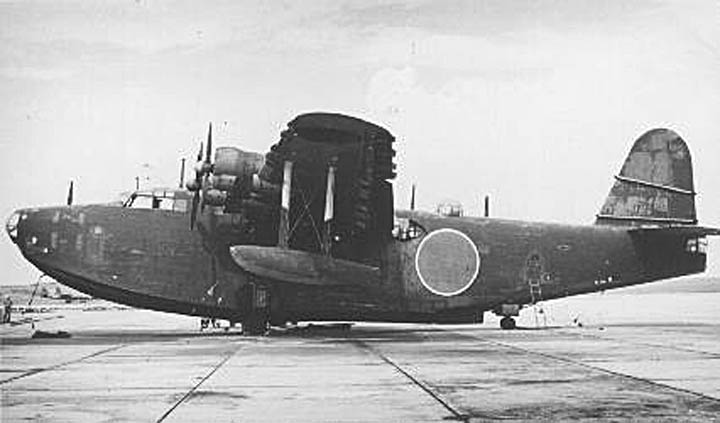今日は中秋の名月です。みなさん、お月見の準備はできたでしょうか。
さて、まったく月とは関係ありませんが、私以上の年配の方なら、おそらくは誰でも知っていると思いますが、その昔、「こんにちは赤ちゃん」という歌がはやりました。
東京オリンピックが開催された1964年の前年の、1963年にNHKの番組、「夢であいましょう」のテーマ曲として歌われた歌であり、同年11月に発売されたレコードは100万枚を超える大ヒットとなりました。
歌っていたのは、福岡出身の歌手、「梓みちよ」さんで、この「こんにちは赤ちゃん」は、この年の第5回日本レコード大賞受賞曲ともなり、翌年の1964年センバツ高校野球の開会式行進曲にもなったそうです。
私はこのころまだ小学校入学前であり、物心つくかどうかの年頃でしたが、大ヒットしたこの歌はよく覚えており、これを幼稚園かどこかで歌っていたような覚えもあります。
その後も梓みちよさんは、「二人でお酒を」という大ヒットを飛ばし(1974年3月)、この曲で5年ぶりに「NHK紅白歌合戦」にもカムバック出場するなどして人気を維持し続け、さらには1971年から1978年まで桂三枝さんの「新婚さんいらっしゃい」の名アシスタントとしてお茶の間の人気を集め続けました。
1943年生まれといいますから、今年でも御年70歳になっておられるはずです。が、現在でもコンスタントに歌謡番組に出演されているそうで、あいかわらず意欲的な芸能活動を行っておられるようです。聞くところによると、実業家としても活躍しているとのことで、最近、「梓プラチナローズジェル」という化粧剤をご自身で監修して発売されたとか。
ところで、この、梓みちよさんのもうひとつのヒット曲に「メランコリー」というのがあります。1976年の作品であり、これも翌1977年にかけてロングヒットました。
歌の歌詞はというと、
秋だというのに 恋もできない
メランコリー♪ メランコリー♪
というもので、私もその昔よく歌ったものですが、このサビの部分は良く覚えているのですが、その前のほうの歌詞のほうはほとんど覚えていません。
ただ、このあとに続く歌詞は、次のようなものでした。
それでも 乃木坂あたりでは 私は いい女なんだってね
腕から時計を はずすように 男とさよなら 出来るんだって
淋しい 淋しいもんだね
一転して軽いテンポに転調し、まるで自笑するような詩の内容もなかなかしゃれていて、とても30年以上も前の歌とは思えません。
しかし、この歌が流行っていたころは、まだ子供だったため、「メランコリー」という言葉もよくわからず、国語辞典を引いても、「〈憂鬱(ゆううつ)〉または〈悲哀〉にあたる感情」といったまたわけのわからない説明が書いてあって、じゃぁ憂鬱ってなんなのよ、と思ったりしたものです。
その後、長じるにつけ、どうやら暗い気分になったときの感情を指すものらしい、となんとなく理解したつもりになっていました。が、この「メランコリー」という言葉の深い意味については考えてみたこともありませんでした。
ところが、最近、ようやく暑い夏が終り、秋風が吹き始めるようになると、妙に物思いにふけることが多くなり、そんなときふと口について出たのがこの歌です。しかし、これを口づさみながら、あれ、まてよ、メランコリーっていったいなんだっけ、と思ったのです。
そういうわけで、改めてこの言葉を調べてみる気になったのですが、色々検索してみると、これはなかなか面白いそうな用語である、ということがわかりました。
英語では“melancholia”と書き、これはギリシア語の“melagcholia”に由来するのだそうで、もともとはキリスト教の教義に出てくる、「七つの大罪」のひとつ「憂鬱」のことを指すようです。
七つの大罪とはいうものの、もともとはもう一つ多くて八つあり、厳しさの順序によると「暴食」、「色欲」、「強欲」、「憂鬱」、「憤怒」、「怠惰」、「虚飾」、「傲慢」でした。
しかし、6世紀後半に八つから現在の七つに改正され、「虚飾」は「傲慢」に含まれるようになり、「怠惰」と「憂鬱」は一つの大罪となり、「嫉妬」が追加されました。従って、現在でいう七つの大罪とは、「傲慢 嫉妬 憤怒 怠惰 強欲 暴食 色欲」であり、実際には「憂鬱」という言葉は抜け落ちています。
ちなみに、この七つの大罪には、それぞれ対応する悪魔とその悪魔がかわいがっている動物があてがわれており、「傲慢」は、グリフォン(鷲の上半身とライオンの下半身をもつ伝説上の生物)、ライオン、孔雀であり、「嫉妬」には蛇や犬、「憤怒」はユニコーン、ドラゴン、狼、「強欲」は狐、針鼠、「暴食」豚、蝿、「色欲」蠍、山羊、だそうです。
で、メランコリーが含まれる「怠惰」には、熊と驢馬(ロバ)が割り当てられていて、これはこの二つに怠け者のイメージがある、ということからきているのだと思われます。が、怠け者という意味では、四六時中寝ているネコのほうがよっぽどふさわしいと思うのですが、猫はなんで割り当てられなかったのでしょう。
それはともかく、キリスト教上で、これらの七つの罪は、悪魔とその手下のこれらの動物が司っていたと考えられており、「罪」そのものというよりは、人間を罪に導く可能性があると見做されてきた欲望や感情のことを指し、人は死ぬと、この罪をあの世で清めなくてはならない、ということになっているそうです。
無論、キリスト教という一宗教の教義として教えられていることであり、あの世にいったらこれらの罪を償うために、何等かの制裁を加えられるなどということはあるわけはありません。
人は死ぬと、その生前に修業した魂のレベル毎に、それにふさわしい階層に行って、そこでまた新たな修業を積む、ということを繰り返すだけです。が、生前の行いが正しくない場合には低い階層に行くということなので、これをペナルティーと考えるべきかもしれません。
さて、このように、メランコリーとは、そもそもはキリスト教の教義の中での「罪」として登場してきた用語でしたが、その後これは、医学や哲学の世界においても研究されるようになりました。
ギリシアに発祥を持つ古代医学においては、「四体液説」というものがありました。古代ギリシアの医者だったヒポクラテスが提唱したものといわれており、この説では人間の身体の構成要素として四種類の体液があげられており、それは、血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁です。
四体液説ではこれらの体液のバランスによって健康状態などが決まっていると考えられ、この四つの液体を重要視しながら、古代の医学は築きあげられたといわれています。
なぜ四つなのかというと、この当時には、これとは別途、「四大元素説」というのがあり、これは地球上にあるすべてのものが、四つの元素、すなわち、空気・火・土・水の4つからなるとされる考え方で、四体液説もこれに準じて考え出されたものです。
この説においては、体液は人間の気質にも影響を与えると説明しており、例えば、血液が多い人は楽天的で、粘液が多い人は鈍重、黄胆汁が多い人は気むずかしい気質を持つとされ、さらに黒胆汁が多い人は憂鬱となっています。つまり、「メランコリー」の性癖を持つ人は、黒胆汁が多い人ということになります。
 左から、黄胆汁質(短気)、黒胆汁質(陰鬱)、粘液質(鈍重)、多血質(楽天的)各々の表情
左から、黄胆汁質(短気)、黒胆汁質(陰鬱)、粘液質(鈍重)、多血質(楽天的)各々の表情
それにしても、血液や粘液はなんとなくわかるのですが、「胆汁(たんじゅう)」っていったい何なのよ、ということなのですが、これは現代医学的には人の「肝臓」で生成される黄褐色でアルカリ性の液体のことをさします。
肝臓を形成する肝細胞で絶えず生成され、総肝管を通って「胆のう」に一時貯蔵・濃縮される物質であり、食事をとると、胆のうから十二指腸に排出され、その効果を発揮します。実際には、近代医学では、胆汁は3つに分類されることがわかっており、これは、「胆管胆汁(A胆汁)」「胆のう胆汁(B胆汁)」「肝胆汁(C胆汁)」の三つです。
それぞれ意味があり、その組み合わせと十二指腸の中にあるその他の物質との反応によって、いろいろな効果を出しますが、例えば食物中の脂肪を乳化して脂肪の消化吸収を促すとか、酸脂肪を乳化して消化酵素の働きを助け、消化をしやすくする、といった具合です。
こうした近代的な知識をこの当時の人が持っていたとは思えず、胆汁を黄胆汁と黒胆汁の二つに分類したのは、前述のとおり四大元素説とつじつまを合わせたかったからにほかなりません。が、もしかしたら人の解剖実験などから、胆汁にも何種類かある、ぐらいは理解していたのかもしれません。
とまれ、ヒポクラテスら古代の医学者は、「憂鬱」というものは、黒胆汁が作りだすものだと考え、これが多い人は、「黒胆汁質」という気質を持ち、憂鬱な気分になることの多い人、というふうに分類しました。
もちろん、胆嚢の働きと、憂鬱との間などに因果関係などあるはずもありません。が、現在においてもドイツや日本では「うつ病が起こりやすい性格」が研究される中で、こうした「循環器質」との関連の研究がなされることもあるということで、あながち無関係とばかりはいえないようです。
ただ、現在医学ではうつ病と、こうした特定の体液の多い少ないなどの個人差を関連付ける研究は少ないようで、うつ病は、体液などによって規定されるその人の性格(例えばA型人間とか)とは無関係で、特定の出来事との関連により起こる、と考える立場をとる学者の方が多いようです。
しかし、そうした現代に至るまでの医学の進歩の過程においては、憂鬱な精神状態というものが、胆汁などの体内分泌物と関連があるのではないか、という考え方が支持される時代が長く続き、その結果、こうした風潮は、「西洋思想」としてその中に「メランコリー」という概念を定着させるのに役立ちました。
このため、もともととは宗教、さらには医学的な発想から出てきた概念であったものが、やがて「哲学」の世界でもさかんに研究されるようになり、現在の我々が使っている「メランコリー」というものの意味は、ボードレール、キルケゴール、サルトルといった名だたる哲学者によって概念化されるようになっていきました。
すなわち、哲学用語としての、メランコリーな精神状態というのは、それを引き起こす要因となるのが、個人的な性格ないしは身体的特徴であり、さらにはこれを基調としてその延長にある「存在論」から導き出される、という考えです。
だんだんと難しくなってくるので、あまりこれ以上は突っ込みませんが、「存在論」というのは、哲学の一部門です。
分かりやすく言うと、存在論では、例えばあなたや私、つまり「存在者」の個別の性格や身体的特徴を議論するのではなく、あなたや私という人間が、存在する「意味」や根本的に、いったい「何者か」、なぜそこに存在しているのか、ということを考える学問ということになります。
なーんだそんなの簡単じゃん。精子と卵子がくっついて、誕生してくるに決まってんじゃん、と誰しも思うでしょうが、そうではなく、それでは精子や卵子はなぜ、存在しているのか、というのを議論するのが、「存在論」です。
これを真剣に考えているとだんだんと頭がおかしくなってしまいそうですし、哲学というとどうも理屈っぽいものというイメージが私にもあって、こうした話をするのは本来あまり好きではありません。
がしかし、この存在論というのは、現在でも多くの大学でも教えられている学問体系を生み出す礎となったものであり、現在の文化を形作るのに役立っているのだ、といわれればそうはいきません。
その考え方を初めて明確にして、体系化したのは、古代ギリシアの哲学者「アリストテレス」です。
彼は「存在論」という学問を体系化し、「論理学」をあらゆる学問成果を手に入れるための「道具」とした上で、「理論」、「実践」、「制作」に三分し、理論学を「自然学」と「形而上学」、実践学を「政治学」と「倫理学」、制作学を「詩学」に分類しました。
難しい話はもうやめますが、もうお分かりのとおり、文科系の大学に進んだ人は、これらの一つや二つの講義を、単位取得のためにとったご経験がおありでしょう。
「存在論」というのはそれほど現代の人文系の学問に影響を及ぼした思想であり、現在の人類の文化を形作った基礎として大変重要な思想なのです。そしてそうした学問体系を生み出したのがほかならぬ「メランコリー」というわけです。
とはいえ、「憂鬱」という人の状態を哲学的に追及する、ということはあまりにも難しく、こうした頭の良い哲学者たちならまだしも、一般の人には難しすぎて馴染みがたい、ということもあり、結局哲学はその「普及」にあまり貢献しませんでした。
メランコリーという言葉を世に浸透させていったのは、やはり医学であり、前述のヒポクラテス(紀元前5世紀から4世紀にかけて活躍)は、黒胆汁が過剰になることで憂鬱室が引き起こされると考え、精神および身体にある種の症状を起こす「病気」である、とその著書で記述しました。
「恐怖感と落胆が、長く続く場合」と具体的な憂鬱質の症状を示したのもヒポクラテスであり、この考え方は多くの医学者たちに支持されていきました。
その後、2世紀のギリシアの医学者ガレノスは、このヒポクラテスの医学的知識や学説を強く支持し、ヒポクラテスの説をもとに四体液説をさらに発展させました。彼は、憂鬱質は脾臓と精巣で作られる黒胆汁の過剰により引き起こされるとし、さらにこれらの四体液を人間の四つの気質や四大元素と結びつけて説明し始めました。
もともと、四大元素説から発生した四体液説ですが、それまではその関連はあまり研究されていなかったものが、ここで初めて体系化されます。ガレノスの説では憂鬱は、四大元素のうちの「土」の元素と結び付いているとされており、彼はここから、四体液説をさらに「季節」や「気象」「時間」といったアイテムと無理やり結びつけようとしました。
「土」は四季のうちの「秋」と最も関連深いとし、また人生のうちの成人期と、一日のうちの午後と結び付けました。その理由は明瞭で、秋や人生の晩年、そして午後には人々は憂い悩みます。この時期になると黒胆汁が増え、憂鬱質になりやすい、と考えたわけです。
ガレノスは人間のさまざまな改質を説明するものとして冷熱乾湿の4つの性質があると考え、これを季節と関連づけました。それを整理すると、以下のようになります。
血液:春 熱・湿・・・多血質:楽天的
黄胆汁:夏 熱・乾・・・黄胆汁質:短気
黒胆汁:秋 冷・乾・・・黒胆汁質:陰鬱
粘液:冬 冷・湿・・・粘液質:鈍重
こうして、この世を構成する「元素」と結びつけらえた四体液説は、やがてその後中世になると、宇宙にある天体の運行を予測することから生まれた「占星術」と結びつくようになります。
ご存知のとおり、占星術では、木星や火星、水星、土星といった元素名がついた惑星の運行が重視されており、これが四体液説と結びつくことになったというわけです。
ちなみに、占星術では、「土星」が憂鬱質と関連付けられており、土星を守護星とする、やぎ座や、みずがめ座の人達がこの気質を強く持っている、とされました。この星座の方、憂鬱に心当たりはありませんか?
ところで、現在日本語でよく使われている「メランコリー」は正しくは「メランコリア」であり、その語源からもこちらが正しい使い方のようです。
が、現在では「メランコリア」というのは、その分野の表現やその由来などについての「研究」を表す用語として別途使われるようになっており、英語でも精神医学的な研究テーマの中での用語はmelancolia、一般的な話し言葉などで憂鬱、などの精神状態を表現するときにはmelancholyと使い分けているようです。
どちらも正しい用法なのですが、ややこしいのでここでもメランコリーとしたまま、続けたいと思います。
さて、占星術と結び付けられるなど、少々拡大解釈されるようになった「メランコリー」ですが、その後時代が下っても、依然、基本的には医学用語としてそのまま継承されていきました。
そうした中、医学も次第に、神経医学、精神医学的なども含めて次第に裾野が広くなっていくようになり、メランコリーもまたそうした精神神経医学的な分野の中で研究されるようになりました。
西暦980年ころのペルシアでは、この国の医師で心理学者だったアル=マジュシという人が、その著書で「精神病」についても触れ、その中で、メランコリーは、「狼化妄想症」という精神の病であると述べています。
そこには、「その患者は雄鶏のようにふるまい犬のように鳴く。夜に墓場をさまよい、目は暗くなり、口は乾き、こうなるとその患者は回復することは難しくなり病気が子へと遺伝する」と書かれており、これではまるで狂人です。しかも、遺伝するとまで書いており、ひどい扱いようになっています。
同じくペルシアを代表する知識人で、哲学者・医者・科学者であったイブン・スィーナー(980~1037)という人も、メランコリーは、「気分障害」であると述べ、「患者は疑い深くなることがあり、ある種の恐怖症を悪化させることもある」としています。
こうしたペルシア人医師たちが書いた著書は、12世紀にラテン語に翻訳され、近世までヨーロッパでも広く読まれるようになり、西ヨーロッパでもメランコリーが研究されるように至ります。
中でも、こうしたメランコリーの治療について最も幅広く述べたのは、イギリスの学者ロバート・バートンという医者でした。1621年に書いた著書の中で彼は、音楽とダンスによる治療法が、精神病、特にメランコリーの治療にとって有効であるという内容の記述を残しています。
しかし、このように、精神医学上で研究されるようになったとはいえ、このころにはまだ、メランコリーは、四体液説に基づく、血液の病の一種と考えられていました。
ところが、このバートンの著書が出版された7年後の1628年になると、ウィリアム・ハーヴェイというイギリスの解剖学者が「血液循環説」を唱えました。
血液循環説というのは、「血液は心臓から出て、動脈経由で身体の各部を経て、静脈経由で再び心臓へ戻る」という、現在ではごく当たり前で、小学生でも知っていることです。しかし、この仕組みは長きにわたって人類に知られておらず、これがこの学者によってようやく明らかになったのです。
かつて古代ギリシアのガレノスが、四体液説という、現在とは全く異なる内容の生理学理論まとめあげ、これが浸透した影響で、これに先立つ1600年代初頭の段階でも、例えば血液は肝臓で作られ、人体各部まで移動し、そこで消費されると考えられていました。
ところが、ハーヴェイが提唱した循環説によって、こうした考え方は完全に否定されました。
ハーヴェイは、血管を流れる大量の血液が肝臓で作られるわけはないとし、「血液の系統は一つで、血液は循環している」との仮説を立てました。そしてこの仮説が正しければ、血管のある部分では血液はもっぱら一方向に流れるはずであると考え、腕を固く縛る実験でそれを確認しました。
腕や足を縛れば、当然血流は止まりますから、血液が循環しているということは誰にでも理解できます。同様に他の部位の一部を止めれば、血流は悪くなることが確認され、これによって血液が体中を循環していることが証明できるようになった、というわけです。
ところが、この発表は、血液肝臓発生説をとなえる四体液説信奉者の間で強い反発を生み、当時この理論は激しい論争の的となっていきました。
しかし、ハーヴェイは、その後もこれらの古い考え方に反論に対する冊子を発行しつづけました。その結果としてその後血液循環説は多くの人々によって様々に実験・検証されるようになり、その正しさは次第に受け入れられていき、またこの血液循環説が後に心臓や血圧、静脈と動脈の存在などの正しい理解へと繋がっていきました。
こうして、血液循環説が正しいと信じられるようになっていったことから、古代の医学説は次第に否定され、メランコリーを引き起こす憂鬱質を説明する四体液説ももはや医学分野では顧みられることはなくなっていきました。
しかし、あまりにも長い間信じられていた説であったため、前述の哲学はもとより、哲学から派生した分野ともいえる、文学や芸術など他の知的分野にはなお大きな影響を与え続けていきました。
一方、その後の14世紀にイタリアで始まり、やがて西欧各国に広まった「ルネッサンス」は、古代ギリシアのガレノスが提唱した占星術を広めるのに役立ち、これによって広く受け入れられるようになり、メランコリーは土星の影響下によって発生するという説が広く信じられるようになっていました。
前述のとおり、土星はやぎ座やみずがめ座の人の守護星ですが、星占いでは、この土星の運行と自分の守護星(例えば木星や火星)の運行との関連からその人の運命を占います。
従って、占星術上で、土星が自分の守護星に強い影響を与えるような位置関係になった場合には、あなたはやがて憂鬱な気分になりやすくなるだろう、といった占い結果を占星術師は告げるわけです。
こうした占星術は、コペルニクスが地動説を提唱するまでは、天動説を中心としてそのロジックが形成されていました。ところが、やがて天文学の発展によりこの天動説が覆され、地動説が主流になると、四体液説が血液循環説によって大打撃を受けたように、占星術界にも大きな震撼が走りました。
しかし、幸いなことに占星術はこのころまでに天文学とも深く結びつくようになっており、やがて占星術にも理解のあった天文学者、ヨハネス・ケプラーがこの問題に取り組み、地動説下においても非合理のない占星術を考え出し、従来の占星術の矛盾を取り除いて構成しなおしました。
このため、占星術は、再び息を吹き返しました。さらにケプラーは占星術を数学的なものに純化しようとする試みも含めて、様々な改革を試みており、こうして体系化された新占星術の概念はその後多くの占星術師に受け入れられるようになり、現代に到っています。
こうしてより「科学的」になった占星術は16世紀には、フランスが「先進国」でしたが、このあとの17世紀半ばにはそれはイギリスで主流になりました。
こうして、ヨーロッパ諸国では、フランスやイギリスを中心としてこの新占星術が流行するようになり、これに伴って占星術は「星座」のデザインにもみられるように、芸術としてのテーマとしてもよく選ばれるようになり、その影響はとくに絵画において色濃く出るようになりました。
そして、芸術家たちが腕をふるう上で恰好なテーマとなったのが、四体液説が滅びたあとも芸術テーマとして根強く生き残っていた「メランコリー」であり、占星術においても土星の影響下で人々がかかるとされていた、この「憂鬱」という症状は数多くの絵画作品で描かれるようになっていきます。
例えば、ドイツの画家で、アルブレヒト・デューラーという人が描いた寓意画に、その名もズバリ、「メランコリアI」と題されたものがあります。
1514年に制作されたこの版画で、メランコリアは霊感の訪れを待つ状態として描かれ、この寓意画には右上のほうに魔方陣や、角を切り落とした菱面体や、砂時計、太陽などとともに描かれており、これらはいずれもこの当時の占星術と関連したオブジェです。
ちなみに、魔方陣(注:「魔法」ではない)とは、正方形の方陣に数字を配置し、縦・横・斜めのいずれの列についても、その列の数字の合計が同じになるものです。
また、右上、右下、左上、左下のそれぞれ2×2の四マスも、中央の2×2の四マスも、いずれも和が34になっていることを下のマトリックスで確認してみてください。さらにこの魔方陣の中には、作者がこの絵を制作した、1514の数字も埋め込まれている点も驚きです。
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1
こうして、ルネサンス以後の中世ヨーロッパにおいては、憂鬱質(メランコリー)は「芸術・創造の能力の根源をなす気質」とまで位置づけされるようになります。
芸術家たるもの憂鬱であるべき、ともいえるような風潮まで現れ、やがては、「メランコリスト」を自称する芸術家らが肖像画、寓意画において盛んにメランコリーをテーマにした絵が描くようになり、作家や音楽家、学者までがその作品の中でメランコリーを扱うようになりました。
とくに、17世紀初頭のイギリスでは、メランコリーという状態をまるで宗教として崇拝するかのような文化的現象すら起こっており、ここでもやはり絵画にとどまらず、文学や音楽などのあらゆる芸術においてメランコリーな作品が主役でした。
これは、ヘンリー8世時代に始まったイングランド宗教改革によって、罪・破滅・救済といった問題への関心の高くなったのが原因ともいわれていますが、ケプラーによって息を吹き返した占星術とも無関係とはいえず、イギリス人は現在でもそうですが、幽霊や霊といったオカルト的なものは大好きで、占星術も根強い人気がありました。
このため、星の運行によってもたらされる「憂鬱」という状態に対してもオカルティックな対象として見るような兆候があり、多くの人がなぜ憂鬱になるか、ということに対して強い関心を寄せていました。
音楽においてもその影響がみられ、イギリスの作曲家、ジョン・ダウランドなどの曲などがもてはやされました。彼は1612年に国王付きのリュート奏者となった人ですが、自分自身を “semper dolens”(常に嘆いている)と標榜し、悲しみやメランコリーを題材とした通俗作品を得意としました。
こうした風潮は、ケプラーを生んだドイツにおいても同じであり、ドイツ文学においても、この時代の「憂鬱」を表すような文化的なムードを示す文学作品が多数造られ、例えばドイツの詩人、で劇作家、小説家のゲーテ(ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ)の「若きウェルテルの悩み」はその中でもとくに有名なものです。
その内容はというと、青年ウェルテルが婚約者のいる身である女性シャルロッテに恋をし、叶わぬ思いに絶望して自殺する、というストーリーですが、日本でも翻訳されて親しまれているので、一度読んだことのある人もいるのではないでしょうか。
このほか、この時代にはヨーロッパ各国で「メメント・モリ(memento mori)」というラテン語が流行り、これは「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」という意味の警句ですが、これもまたメランコリーの流行から派生したものです。
「死を記憶せよ」などと訳され、日本語直訳では「死を思え」、意訳では「死生観」とも訳すことができるもので、現在でもヨーロッパのお墓ではこのメメント・モリをモチーフにした意匠が施されるものを多く目にします。
髑髏や智天使、王冠、骨壷、墓掘り人のつるはしやシャベルといったものであり、お墓だけでなく、その他の芸術作品のモチーフとしてもヨーロッパではこのメメント・モリは広く使われる……といったことは、先日のブログでも書きました。
そもそもメメント・モリは、「自分が死すべきものである」ということを人々に思い起こさせるために使われる言葉や意匠ですが、これもまたメランコリーからきたものとわかると、この時代のヨーロッパ人のこれへの傾倒ぶりがよくわかります。
こうした、ヨーロッパ諸国においてかつて浸透した「メランコリー」は、その後開国した日本にも持ち込まれるようになり、明治時代以降、その言葉がごく普通に使われるようになりました。
ただし「憂鬱」という言葉は、中国の古典にもあり、日本へもそのまま輸入されようですから、明治期以降にメランコリーを翻訳したものではなさそうです。であるとすれば、中国でもその昔から憂鬱という心理状況が認識されていたのでしょうし、当然、日本人もその意味を古くから理解していたはずです。
従って、メランコリーという新しい言葉が入ってきても、その意味がわかると、憂鬱のことであると理解し、あまり混乱はなかったようです。また、メランコリーであるという状態に対して、ヨーロッパ人ほどのめり込むこともありませんでした。
その理由はやはり、ヨーロッパのように四体液説や占星術の流行といったメランコリーが浸透しやすいような時代背景がなかったためでしょう。
それにしても、日本語の「憂鬱」という漢字は、こうしてワープロで書いている分には問題ありませんが、筆数も多くかなり難しい部類に入る言葉なので、いざ手書きで書こうとするとなかなか書けません。
むしろ「今日、私ちょっとメランコリーなの」といった表現のほうが粋なかんじがし、冒頭の梓みちよさんの曲などで使われたのもそうした理由からでしょう。
さて、このようにヨーロッパでは、芸術のあらゆる分野に影響を与えたメランコリーですが、医学分野では研究の対象として消滅した感があります。
しかし、「心理学」としてはまだまだ研究し続けられており、かつてその第一人者として名を馳せたのが、精神分析学者のフロイト(ジークムント・フロイト)です。
彼は、その著書で「悲しみ」(悲哀、喪)と「憂鬱」(メランコリー)を明確に区別しており、愛する者や対象を失って起こる「悲哀」の場合は、時間をかけて悲哀(喪)の仕事を行うことで、再び別の対象へ愛を向けられるようになると書いています。
これに対しメランコリーは、「苦痛にみちた深い不機嫌さ・外界にたいする関心の放棄、愛する能力の喪失、あらゆる行動の制止と、自責や自嘲の形をとる自我感情の低下が起こる」ようになり、引いては妄想的に処罰を期待するほどになる、としています。
メランコリーの場合、愛するものを失った悲しみは悲哀と共通しますが、「愛するもの」が具体的なものではなく観念的なものである点が違います。
また、対象を失った愛は「自己愛」に退行し、失った対象と自我との同一化が進みます。
この過程で愛ははついに「憎しみ」に変わり、失った対象およびこれと同一化された自我に対して激しい憎悪が起こります。やがてこの感情がさらに高まり、自責や自嘲が起こる点が単なる「悲しみ」と異なるとしており、フロイトはここにこそ、自殺の原因がある、と言っています。
そしてフロイトのこうした研究成果を踏まえた現代の心理学では、憂鬱(メランコリー)の概念はうつ病(デプレッション)とほぼすべて置き換えられ、同一のものとみなされているそうです。
2008年3月、ローマ法王庁は新たな7つの大罪を発表しました。それは、遺伝子改造・人体実験・環境汚染・社会的不公正・貧困・過度な裕福さ・麻薬中毒です。
この中に、自殺は含まれていませんが、年間3万人もの自殺者を出している日本では、これに太古のギリシアと同じように「憂鬱」を加え、「八つの大罪」としても良いのではないでしょうか。
災害による後遺症と不況に悩まされる現代社会において、多くのストレスと憂鬱をかかえる多くの日本人にとって、その解消こそが明るい未来を作る鍵になっていくに違いありません。